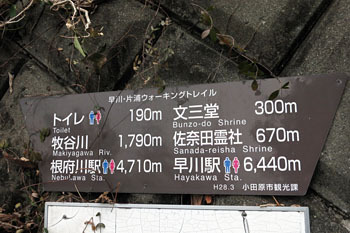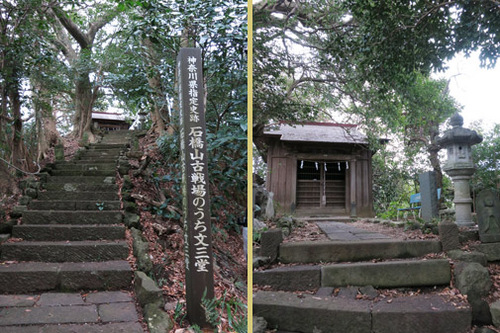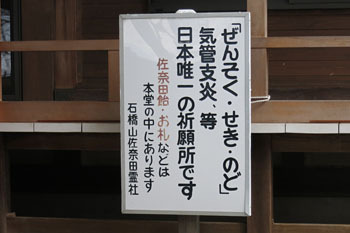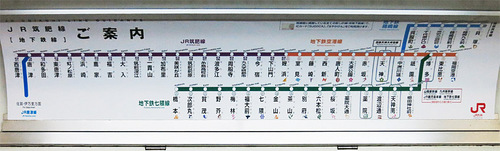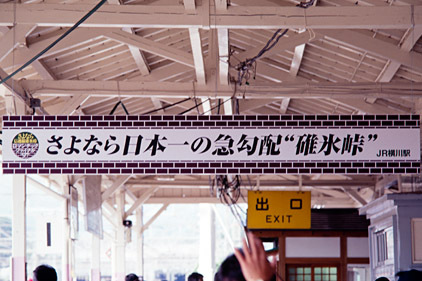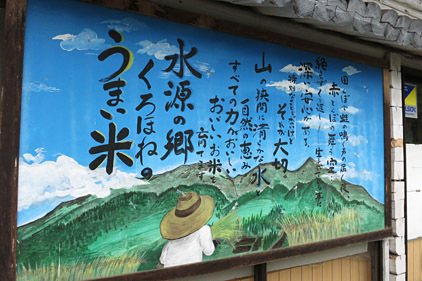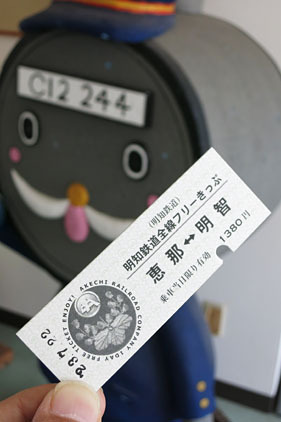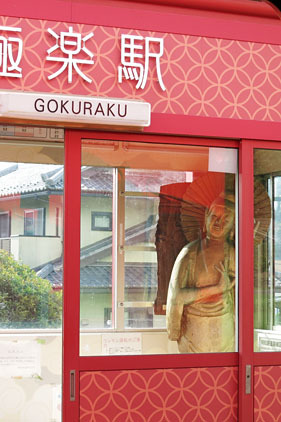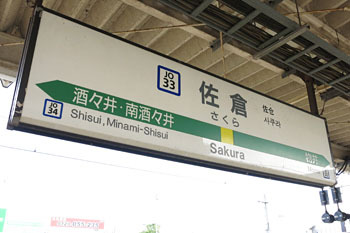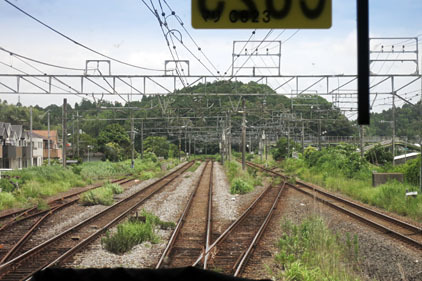東海道本線・・・E259系「マリンエクスプレス踊り子」撮影記 [鉄道写真撮影記]
首都圏と成田空港の間をむすぶJR東日本の空港アクセス特急「成田エクスプレス」(通称・N’EX)(゚ー゚*)ネックス。当列車のほぼ専属で使われているE259系には「成田エクスプレス」であることが一目でわかるよう、車体に“N’EX”の英文字と飛行機をイメージしたロゴマークが大胆にデザインされており、とくに前面へ施されたものは印象的でした (o´∀`o)カコイイ。
特急「成田エクスプレス」の運用を
先代の253系から引き継いで
2009年にデビューしたE259系。
オリジナルデザインでは
“N’EX”を強調しています。
(゚ー゚*)ネックス
▲10.3.22 総武本線 佐倉-物井
先代の253系から引き継いで
2009年にデビューしたE259系。
オリジナルデザインでは
“N’EX”を強調しています。
(゚ー゚*)ネックス
▲10.3.22 総武本線 佐倉-物井
ところが来月(2024年3月)に控えるダイヤ改正を機に当系がほかの特急列車(総武本線の特急「しおさい」)にも「成田エクスプレス」と共通で使用されることとなり、それを見越してか昨年の春ごろから車体デザイン(外装)を順次リニューアル(内装にも変化があるのかな?)(・o・*)ホホゥ。赤と白を基調とした全体的な塗分けはあまり変わらないものの、これまで黒地に“N’EX”のロゴがあしらわれていた前面は、メタリックシルバー(銀色)に“SERIES E259”という車両形式を強調したものに改められ、けっこう印象が変わったように感じます (・∀・)イメチェン。あくまでも個人的には見慣れていることもあるからか、どっちかというと“旧デザイン”のほうが好みだったな σ(゚・゚*)ンー…。
こちらがリニューアルされて
新デザインとなった最近のE259系。
( ̄  ̄*)ニーゴーキュー
先頭車の前面や側面に
メタリックなシルバーを採用し
“ご利用いただく様々な場面”や
“移り変わる沿線地域の風景”を映し込ませて
「時代の変化に対応し持続して進化を遂げる」ことを
表現しているのだそうです。
(´ε`)フーン
▲24.1.20 山手線 原宿
新デザインとなった最近のE259系。
( ̄  ̄*)ニーゴーキュー
先頭車の前面や側面に
メタリックなシルバーを採用し
“ご利用いただく様々な場面”や
“移り変わる沿線地域の風景”を映し込ませて
「時代の変化に対応し持続して進化を遂げる」ことを
表現しているのだそうです。
(´ε`)フーン
▲24.1.20 山手線 原宿
そしてそのデザイン変更はかなり早いペースで行われたようで (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…、私が新宿などでたまたま“N’EX”を見かけるたびに「新デザインが増えてきたなぁ・・・」なんて感じていたものでしたが σ(゚・゚*)ンー…、気が付けば全22編成(全22本)ある当系のうち、旧デザインはなんと “残り一本” だけとなってしまったらしい(2/17現在)Σ(゚∇゚;ノ)ノ エッ!?。わずか一年足らずでこの進捗状況とはちょっと驚きです ( ̄▽ ̄;)マジカ…。
リニューアルが開始された直後には
新デザインにも側面に施されていた
“N’EX”のロゴマークでしたが
(左の編成)
現在は消されているみたいです
(ちなみに右は旧デザイン編成)。
▲23.7.8 成田線 佐倉-酒々井
新デザインにも側面に施されていた
“N’EX”のロゴマークでしたが
(左の編成)
現在は消されているみたいです
(ちなみに右は旧デザイン編成)。
▲23.7.8 成田線 佐倉-酒々井
そんな旧デザイン(旧塗装)最後の一本となったE259系の当該編成(Ne022編成)を使用するという、おもに鉄道ファン向けのイベント性の高いツアー列車(団体臨時列車)が週末に企画されました (゚∀゚)オッ!。人気で即完売となったツアーに私は参加(乗車)できないけど(そもそも参加申し込みをするつもりがあったのかどうかはさておきw)、これは希少性の高まった旧デザインを確実に記録できる絶好のチャンスです (・∀・)イイネ。
早春の今は時期的に梅や早咲きの桜(河津桜など)の花がほころび始めて、できればそのような季節感もちょっと意識しつつ、ツアー列車として走る“N’EX”(?)の撮影に臨むこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
2月17日(土)
早春の今は時期的に梅や早咲きの桜(河津桜など)の花がほころび始めて、できればそのような季節感もちょっと意識しつつ、ツアー列車として走る“N’EX”(?)の撮影に臨むこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
2月17日(土)
旧デザインのE259系によるツアー列車が運転される当日の朝、私が東京から乗ったのは東海道線の熱海ゆき下り普通列車 (゚ー゚*)トカセソ。
「成田エクスプレス」のなかには東海道線(いわゆる横須賀線)に直通して大船(おおふな)を発着駅(起終点)としている列車も多く設定されているのですが(おもに横浜〜成田空港の利用客需要を見込んだもの)(*゚ェ゚)フムフム、私がもし通常の定期運行している“N’EX”を撮るとしたらおそらく、東海道線より手軽に撮りやすいと個人的に感じる総武線や成田線の沿線へ向かっていたでしょう(たとえば“モノサク”とか)σ(゚・゚*)ンー…。
しかし今回企画されたツアー列車(団体臨時列車)は、本来の「成田エクスプレス」の運行区間(新宿・大船〜成田空港)に倣ったものではなく、東海道線の大船と熱海のあいだにて運転が行われます(単純往復でなく少し変則的な行程)。
「成田エクスプレス」のなかには東海道線(いわゆる横須賀線)に直通して大船(おおふな)を発着駅(起終点)としている列車も多く設定されているのですが(おもに横浜〜成田空港の利用客需要を見込んだもの)(*゚ェ゚)フムフム、私がもし通常の定期運行している“N’EX”を撮るとしたらおそらく、東海道線より手軽に撮りやすいと個人的に感じる総武線や成田線の沿線へ向かっていたでしょう(たとえば“モノサク”とか)σ(゚・゚*)ンー…。
しかし今回企画されたツアー列車(団体臨時列車)は、本来の「成田エクスプレス」の運行区間(新宿・大船〜成田空港)に倣ったものではなく、東海道線の大船と熱海のあいだにて運転が行われます(単純往復でなく少し変則的な行程)。
東海道線の下り列車で
神奈川県を横断するように
西へと進むと
やがて車窓に広がるのは
相模湾の海景色。
(*’∀’*)ウミ♪
でも空は雲に覆われていて
きょうはあまり天気がよくない?
(-ω-;*)ドングモリ
▲東海道本線 早川-根府川(車窓から)
神奈川県を横断するように
西へと進むと
やがて車窓に広がるのは
相模湾の海景色。
(*’∀’*)ウミ♪
でも空は雲に覆われていて
きょうはあまり天気がよくない?
(-ω-;*)ドングモリ
▲東海道本線 早川-根府川(車窓から)
なぜ、“N’EX”とはあまり関係なさそうなこの区間(大船〜熱海)がE259系を使うツアー列車の行程になっているのかというと (゚ー゚?)オヨ?、実は当企画の主旨が最後の旧デザインを惜しむだけにとどまらず、かつてE259系を使用して東海道線で一時的に運行されていた、特急「マリンエクスプレス踊り子」のイメージを再現したものだからです (゚∀゚*)オオッ!(ちなみに当企画のツアー名は「最後の旧デザイン『マリンエクスプレス踊り子』号で巡る車両センター撮影会ツアー」)。
2012年から2020年まで不定期の臨時特急として東京と伊豆急下田をむすんでいた「マリンエクスプレス踊り子」は、「成田エクスプレス」専属のE259系がほかの特急列車に使われた唯一の例で(2024年2月現在)(・o・*)ホホゥ、もちろん当時の当系は旧デザインでしたから、今回の「マリンエクスプレス踊り子」としての復刻運転は“最後の一本”をウマく活用したマニアックな面白い企画ではありませんか (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
それならば “N’EX”というよりか「マリンエクスプレス踊り子」らしさが表せるような場所で撮影をしたいと思い (゚ー゚*)マリン、私が下車したのは駅のホームから相模湾の海が一望できることで知られる根府川(ねぶかわ)。
2012年から2020年まで不定期の臨時特急として東京と伊豆急下田をむすんでいた「マリンエクスプレス踊り子」は、「成田エクスプレス」専属のE259系がほかの特急列車に使われた唯一の例で(2024年2月現在)(・o・*)ホホゥ、もちろん当時の当系は旧デザインでしたから、今回の「マリンエクスプレス踊り子」としての復刻運転は“最後の一本”をウマく活用したマニアックな面白い企画ではありませんか (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
それならば “N’EX”というよりか「マリンエクスプレス踊り子」らしさが表せるような場所で撮影をしたいと思い (゚ー゚*)マリン、私が下車したのは駅のホームから相模湾の海が一望できることで知られる根府川(ねぶかわ)。
神奈川県小田原市に所在する
東海道本線の根府川。
( ̄  ̄*)ネブ
太平洋の相模湾に面した高台に
可愛らしい趣きのある
木造駅舎が建っています。
ホームから望める海景色は壮観な眺め。
晴れていればもっとよかったけどね・・・。
(・ε・`)チェ
▲東海道本線 根府川
東海道本線の根府川。
( ̄  ̄*)ネブ
太平洋の相模湾に面した高台に
可愛らしい趣きのある
木造駅舎が建っています。
ホームから望める海景色は壮観な眺め。
晴れていればもっとよかったけどね・・・。
(・ε・`)チェ
▲東海道本線 根府川
東京0701-(東海道1825E)-根府川0839
東海道線が相模湾の海岸沿いを走るこの根府川界隈(おもに早川〜真鶴)は、海を背景に列車が撮れる好撮影地が点在しており、私も当線の臨時列車などを撮りにちょくちょく訪れています ...(((o*・ω・)o。ちなみに個人的に馴染みがあるのは早川の駅から歩いて行くことが多い、当区間で屈指の“お立ち台”としてメジャーな石橋集落の玉川橋梁なのですが、今回は少し気分を変えて根府川のほうからアクセスする場所を選んでみました ( ̄  ̄*)ネブ。
それにしても、きょうの当地の空は一面が雲に覆われていて日が差す気配がなく、どうもスッキリとしない模様 (・ω・`)ウーン…。事前にチェックしてきた天気予報によると、昨日の時点では“晴れのち曇り”、それが今朝の出がけには“曇り時々晴れ”となり、現地に着いた今は“曇り”と下方修正されています (-ω-;*)ドングモリ。せっかく海景色が臨めるようなところへ来たのに、これではあまりいい絵にならなそうだけど、件のツアー列車はきょう一日限りの特別運転なのでほかの日に出直すワケには行かないのよね (・ε・`)チェ。
東海道線が相模湾の海岸沿いを走るこの根府川界隈(おもに早川〜真鶴)は、海を背景に列車が撮れる好撮影地が点在しており、私も当線の臨時列車などを撮りにちょくちょく訪れています ...(((o*・ω・)o。ちなみに個人的に馴染みがあるのは早川の駅から歩いて行くことが多い、当区間で屈指の“お立ち台”としてメジャーな石橋集落の玉川橋梁なのですが、今回は少し気分を変えて根府川のほうからアクセスする場所を選んでみました ( ̄  ̄*)ネブ。
それにしても、きょうの当地の空は一面が雲に覆われていて日が差す気配がなく、どうもスッキリとしない模様 (・ω・`)ウーン…。事前にチェックしてきた天気予報によると、昨日の時点では“晴れのち曇り”、それが今朝の出がけには“曇り時々晴れ”となり、現地に着いた今は“曇り”と下方修正されています (-ω-;*)ドングモリ。せっかく海景色が臨めるようなところへ来たのに、これではあまりいい絵にならなそうだけど、件のツアー列車はきょう一日限りの特別運転なのでほかの日に出直すワケには行かないのよね (・ε・`)チェ。
やってきたのはこんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
高台の視界がひらけた箇所からは
相模湾と東海道線の線路が一望。
E231系による
長い15両編成の普通列車が
キンキンというフランジ音を響かせて
海を背景にきれいな弧を描きます。
▲東海道本線 早川-根府川
(「゚ー゚)ドレドレ
高台の視界がひらけた箇所からは
相模湾と東海道線の線路が一望。
E231系による
長い15両編成の普通列車が
キンキンというフランジ音を響かせて
海を背景にきれいな弧を描きます。
▲東海道本線 早川-根府川
お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」を楽しみにしつつも、曇天という天候条件にモチベーションがいまいち上がらないなか (-ω-;*)ウゥム…、丘の上のミカン畑に設えられた細い農道を歩き進み、駅から30分ほどでとりあえず目的地としていた撮影ポイントに到着 (・ω・)トーチャコ。
高台の細道から見渡せるその景色は、右手の奥に相模湾の海が、そして眼下には集落のなかで大きく曲線を描く東海道線の線路が確認でき、なかなか壮観な眺めです (・∀・)イイネ。返すがえす晴れてくれたらよかったのになぁ (^^;)ゞポリポリ。
ちなみにこの場所は、ためしに撮ってみたE231系の普通列車のカットように、フレームの右のほうにできるだけ海を写し込ませるのが定番のアングルではないかと思われますが (^_[◎]oパチリ、きょうに限ってはこんなものが私の目に留まりました (=゚ω゚=*)ンン!?。
高台の細道から見渡せるその景色は、右手の奥に相模湾の海が、そして眼下には集落のなかで大きく曲線を描く東海道線の線路が確認でき、なかなか壮観な眺めです (・∀・)イイネ。返すがえす晴れてくれたらよかったのになぁ (^^;)ゞポリポリ。
ちなみにこの場所は、ためしに撮ってみたE231系の普通列車のカットように、フレームの右のほうにできるだけ海を写し込ませるのが定番のアングルではないかと思われますが (^_[◎]oパチリ、きょうに限ってはこんなものが私の目に留まりました (=゚ω゚=*)ンン!?。
それは斜面のほんの一角でピンク色の花を咲かせていた“おかめ桜” ( ̄  ̄*)オカメ。
早春という今の開花時期や濃いピンクの花色から、同じく早咲きの“河津桜”と似た印象のサクラですが σ(゚・゚*)ンー…、河津桜やソメイヨシノなどより木が小ぶりで(樹高は成長しても3メートル程度)繁殖力が強く、花を下に向かせて咲かせるのが特徴だそうです(うつむき加減で慎ましやかに咲くから“おかめ”なのかな?)。ちなみにこの根府川地区では植樹した本品種を名物として地域の活性化に取り組んでおり、“根府川おかめ桜まつり”が春の恒例行事として催されます ( ̄。 ̄)ヘー。
そんな“おかめさん”がいいところにいるじゃないですか (・∀・)イイネ。
早春という今の開花時期や濃いピンクの花色から、同じく早咲きの“河津桜”と似た印象のサクラですが σ(゚・゚*)ンー…、河津桜やソメイヨシノなどより木が小ぶりで(樹高は成長しても3メートル程度)繁殖力が強く、花を下に向かせて咲かせるのが特徴だそうです(うつむき加減で慎ましやかに咲くから“おかめ”なのかな?)。ちなみにこの根府川地区では植樹した本品種を名物として地域の活性化に取り組んでおり、“根府川おかめ桜まつり”が春の恒例行事として催されます ( ̄。 ̄)ヘー。
そんな“おかめさん”がいいところにいるじゃないですか (・∀・)イイネ。
鮮やかなピンク色の“おかめ桜”は
西湘(西湘南地域)に春を告げる彩り。
(゚- ゚)ハル
その向こうを伊豆へとむかう
E257系の特急「踊り子」が
カーブを切って走り抜けてゆきました。
きょうは河津桜を見に行く観光客で
車内が満席かな?
▲東海道本線 早川-根府川
西湘(西湘南地域)に春を告げる彩り。
(゚- ゚)ハル
その向こうを伊豆へとむかう
E257系の特急「踊り子」が
カーブを切って走り抜けてゆきました。
きょうは河津桜を見に行く観光客で
車内が満席かな?
▲東海道本線 早川-根府川
お!意外と悪くないかも (゚∀゚)オッ!
眼下のカーブに現れたE257系の特急「踊り子」に“おかめ桜”を添えて撮ってみると (^_[◎]oパチリ、アングルの片隅に写し込んだピンク色が曇天の風景でもきれいに映えていいアクセントになりました ъ(゚Д゚)ナイス。構図的に斜面の花を入れると背景に海が入れにくくなってしまい、仮にこれが晴天下の青い海だとしたらカットするのを惜しむところだけど (・∀・`)ウミ…、きょうの冴えない天気なら海を狭めることにあまり躊躇はありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。
そこでこの場所のこのアングルを“ひとつの候補”として頭に入れておき (*`・ェ・)σチェック、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」が通過するまでにはまだ時間に余裕があるので、もう少し周囲を散策しながら他の撮影ポイントも覗いてみようと思います ...(((o*・ω・)o。
眼下のカーブに現れたE257系の特急「踊り子」に“おかめ桜”を添えて撮ってみると (^_[◎]oパチリ、アングルの片隅に写し込んだピンク色が曇天の風景でもきれいに映えていいアクセントになりました ъ(゚Д゚)ナイス。構図的に斜面の花を入れると背景に海が入れにくくなってしまい、仮にこれが晴天下の青い海だとしたらカットするのを惜しむところだけど (・∀・`)ウミ…、きょうの冴えない天気なら海を狭めることにあまり躊躇はありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。
そこでこの場所のこのアングルを“ひとつの候補”として頭に入れておき (*`・ェ・)σチェック、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」が通過するまでにはまだ時間に余裕があるので、もう少し周囲を散策しながら他の撮影ポイントも覗いてみようと思います ...(((o*・ω・)o。
起伏に富んだこのあたりの農道は
丘の上から相模湾の眺望が楽しめる
ウォーキングコースとして
小田原市が設定されており
(早川・片浦ウォーキングトレイル)
散策に訪れる人も見かけます。
テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘
根府川から早川までコースを歩いたら
約11キロもあるのか。
ウォーキングコースのみどころが
「石橋山古戦場跡」。
平氏追討の命令を受けた源頼朝が
伊豆から鎌倉へ向かう途中にある石橋山で
3000におよぶ平家軍と300の頼朝軍が対戦。
10倍を超える敵の軍勢に頼朝軍は敗れました。
これが当地を戦場とした“石橋山の合戦”です。
(・o・*)ホホゥ
石橋山の合戦で
頼朝軍の先陣となって討ち死にした
義忠の佐奈田与一を祀っているのが
合戦場の一角に建立された「佐奈田霊社」。
ちなみに与一が戦いのさなか
喉に“たん”がからんで声が出せなくなり
味方の援護を受けられずに
討たれてしまったという伝えから
ここ佐奈田霊社は
咳やぜんそく、気管支炎の疾病治癒に
ご利益があるそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
そんな佐奈田霊社のすぐ近くで
私が次にやってきたのは
こんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
ここでも線路脇の斜面に
“おかめ桜”のピンクが見えますね。
(o ̄∇ ̄o)ピンク
丘の上から相模湾の眺望が楽しめる
ウォーキングコースとして
小田原市が設定されており
(早川・片浦ウォーキングトレイル)
散策に訪れる人も見かけます。
テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘
根府川から早川までコースを歩いたら
約11キロもあるのか。
ウォーキングコースのみどころが
「石橋山古戦場跡」。
平氏追討の命令を受けた源頼朝が
伊豆から鎌倉へ向かう途中にある石橋山で
3000におよぶ平家軍と300の頼朝軍が対戦。
10倍を超える敵の軍勢に頼朝軍は敗れました。
これが当地を戦場とした“石橋山の合戦”です。
(・o・*)ホホゥ
石橋山の合戦で
頼朝軍の先陣となって討ち死にした
義忠の佐奈田与一を祀っているのが
合戦場の一角に建立された「佐奈田霊社」。
ちなみに与一が戦いのさなか
喉に“たん”がからんで声が出せなくなり
味方の援護を受けられずに
討たれてしまったという伝えから
ここ佐奈田霊社は
咳やぜんそく、気管支炎の疾病治癒に
ご利益があるそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
そんな佐奈田霊社のすぐ近くで
私が次にやってきたのは
こんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
ここでも線路脇の斜面に
“おかめ桜”のピンクが見えますね。
(o ̄∇ ̄o)ピンク
ウォーキングコース(早川・片浦ウォーキングトレイル)にも設定されている、みかん畑の農道を早川のほうへと歩き進んで テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘、その道中にある史跡の「石橋山古戦場跡」や「佐奈田霊社」などへ立ち寄ったのち (*゚ェ゚)フムフム、二カ所目となる次の撮影ポイントへとやってきました (・ω・)トーチャコ。
先ほどE257系の「踊り子」などを撮影した最初の場所(以降、“踊り子アングル”と称すw)よりは高度が低いものの、やはりここも丘の上から俯瞰で線路を見下ろすことができ、その背景には海が広がります (「゚ー゚)ドレドレ。そして傍らの斜面(みかん畑)にはこちらでも“おかめ桜”がピンク色の花をたくさん咲かせていて、それを列車と絡めて撮ることができそう (・∀・)イイネ。
「マリンエクスプレス踊り子」はまだだけど、少し待ったところで下り線にはこの列車が現れました (=゚ω゚=*)ンン!?。
先ほどE257系の「踊り子」などを撮影した最初の場所(以降、“踊り子アングル”と称すw)よりは高度が低いものの、やはりここも丘の上から俯瞰で線路を見下ろすことができ、その背景には海が広がります (「゚ー゚)ドレドレ。そして傍らの斜面(みかん畑)にはこちらでも“おかめ桜”がピンク色の花をたくさん咲かせていて、それを列車と絡めて撮ることができそう (・∀・)イイネ。
「マリンエクスプレス踊り子」はまだだけど、少し待ったところで下り線にはこの列車が現れました (=゚ω゚=*)ンン!?。
なごみ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
車体に茶色・・・いや、独特な“漆色”を纏って重厚感を醸し出しているのは、“ハイグレード車両”のE655系「和(なごみ)」ではありませんか ( ̄∇ ̄*)ナゴミキャンベル。
全車(全席)がハイクラス(グリーン車)で編成された当系は、定期運用および増発的な臨時列車に使われることはなく、プレミアムツアーなどの団体専用列車として運行することが多く、また、時には天皇陛下が地方へ巡幸される際にお乗りになる“お召列車”にもなる車両で(その際は中間に貴賓車的な特別車両を組み込む)、わずか一本(一編成)しか存在しないレアなもの (*・`o´・*)ホ─。
ちなみにこの神出鬼没(?)な「なごみ」を私は狙って撮影するより、たまたま撮影ポイントなどで遭遇することがけっこう多いのですが(ホント、ちょくちょく逢うのよねw)(=゚ω゚)ノ゙ヤア、都内の品川から伊豆の河津へと向かう“河津桜観賞のツアー列車”として東海道線(から伊東線、伊豆急線へ直通)に設定された今回の運行は事前に情報を把握しており、このあとの「マリンエクスプレス踊り子」とあわせて撮影に臨んでみました (^_[◎]oパチリ。当列車のツアーが目的とする“河津桜”ではないけど、“おかめ桜”とのコラボでこのプレミアムトレインが撮れたのは嬉しい収穫 ъ(゚Д゚)ナイス。
ただしこの場所、“おかめ桜”はさっきの“踊り子アングル”より花が多くてピンクにボリュームを感じるし、構図の向かって右手にはご当地らしいみかん畑が、さらに左手には海も広く入れられるのですが、個人的に何となく画が雑然とした印象を受けます (゚ペ)ウーン…。私はやっぱり桜色をそっと添えたような“踊り子アングル”のほうが好みだったかなぁ・・・。
そんなワケで、いちばんのお目当てである「マリンエクスプレス踊り子」の撮影は、もう一度 “踊り子アングル”に戻ることとしました モドル…((((o* ̄-)o 。なお、“なごみアングル”から“踊り子アングル”への移動距離は大したこと無いけど、アップダウンが激しくてけっこうキツい歩きなのよね(急な坂を下って、上って、下って、また上るwww)ε〜ε〜ε〜(((;;´Д`)ヒィヒィ…。
車体に茶色・・・いや、独特な“漆色”を纏って重厚感を醸し出しているのは、“ハイグレード車両”のE655系「和(なごみ)」ではありませんか ( ̄∇ ̄*)ナゴミキャンベル。
全車(全席)がハイクラス(グリーン車)で編成された当系は、定期運用および増発的な臨時列車に使われることはなく、プレミアムツアーなどの団体専用列車として運行することが多く、また、時には天皇陛下が地方へ巡幸される際にお乗りになる“お召列車”にもなる車両で(その際は中間に貴賓車的な特別車両を組み込む)、わずか一本(一編成)しか存在しないレアなもの (*・`o´・*)ホ─。
ちなみにこの神出鬼没(?)な「なごみ」を私は狙って撮影するより、たまたま撮影ポイントなどで遭遇することがけっこう多いのですが(ホント、ちょくちょく逢うのよねw)(=゚ω゚)ノ゙ヤア、都内の品川から伊豆の河津へと向かう“河津桜観賞のツアー列車”として東海道線(から伊東線、伊豆急線へ直通)に設定された今回の運行は事前に情報を把握しており、このあとの「マリンエクスプレス踊り子」とあわせて撮影に臨んでみました (^_[◎]oパチリ。当列車のツアーが目的とする“河津桜”ではないけど、“おかめ桜”とのコラボでこのプレミアムトレインが撮れたのは嬉しい収穫 ъ(゚Д゚)ナイス。
ただしこの場所、“おかめ桜”はさっきの“踊り子アングル”より花が多くてピンクにボリュームを感じるし、構図の向かって右手にはご当地らしいみかん畑が、さらに左手には海も広く入れられるのですが、個人的に何となく画が雑然とした印象を受けます (゚ペ)ウーン…。私はやっぱり桜色をそっと添えたような“踊り子アングル”のほうが好みだったかなぁ・・・。
そんなワケで、いちばんのお目当てである「マリンエクスプレス踊り子」の撮影は、もう一度 “踊り子アングル”に戻ることとしました モドル…((((o* ̄-)o 。なお、“なごみアングル”から“踊り子アングル”への移動距離は大したこと無いけど、アップダウンが激しくてけっこうキツい歩きなのよね(急な坂を下って、上って、下って、また上るwww)ε〜ε〜ε〜(((;;´Д`)ヒィヒィ…。
一カ所目の撮影ポイントへ戻ると
そのタイミングで通過したのは
観光列車的な要素が高くて
特急「踊り子」の豪華版といえる
E261系の特急「サフィール踊り子」。
( ̄  ̄*)サフィール
その様子を丘の上のおかめ桜が眺めます。
▲東海道本線 早川-根府川
そのタイミングで通過したのは
観光列車的な要素が高くて
特急「踊り子」の豪華版といえる
E261系の特急「サフィール踊り子」。
( ̄  ̄*)サフィール
その様子を丘の上のおかめ桜が眺めます。
▲東海道本線 早川-根府川
ところで、本日運行するE259系の「マリンエクスプレス踊り子」は一般的な特急列車や臨時列車(いわゆる多客臨)ではなく、あくまでもそのイメージを再現(復刻)した企画のツアー列車(団体列車)であり (゚ー゚*)ダンリン、当列車に乗車できるのはツアーイベントの参加者のみなので、詳細な運転時刻は一般向けに公表されていません ( ̄b ̄)シークレット? 。
とりあえず私が事前に知っていたのは、ツアー告知の概要に記されていた大まかなものでしかなかったのですが(10時半ごろにイベント開始)、同好の士(鉄ちゃん)がSNSにあげてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、ちょうど私が“踊り子アングル”のほうへと戻ってきた頃(12時ごろ)に当該列車は始発駅に設定された大船を発車して、いま東海道線をこちらのほうへと下ってきているらしい ...(((o*・ω・)o。大船から根府川まで「踊り子」などの所要時間を参考にするとだいたい40〜50分くらいかな? σ(゚・゚*)ンー…。
私がいるこの場所はマイナーな撮影ポイントではないハズだけど、ほかに同業者は誰も現れずに一人だけで待つことしばし (・ω・)ポツン。やがて通過の目安としていた頃合いに、列車の接近を知らせる踏切の鳴動が丘の上からでも確認できました (゚∀゚)オッ!。
とりあえず私が事前に知っていたのは、ツアー告知の概要に記されていた大まかなものでしかなかったのですが(10時半ごろにイベント開始)、同好の士(鉄ちゃん)がSNSにあげてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、ちょうど私が“踊り子アングル”のほうへと戻ってきた頃(12時ごろ)に当該列車は始発駅に設定された大船を発車して、いま東海道線をこちらのほうへと下ってきているらしい ...(((o*・ω・)o。大船から根府川まで「踊り子」などの所要時間を参考にするとだいたい40〜50分くらいかな? σ(゚・゚*)ンー…。
私がいるこの場所はマイナーな撮影ポイントではないハズだけど、ほかに同業者は誰も現れずに一人だけで待つことしばし (・ω・)ポツン。やがて通過の目安としていた頃合いに、列車の接近を知らせる踏切の鳴動が丘の上からでも確認できました (゚∀゚)オッ!。
「マリンエクスプレス踊り子」の復刻運転で
海が望める西湘の鉄路を久しぶりに走る
N’EXカラーのE259系。
まもなく見納めとなるこの出で立ちに
おかめ桜がそっと惜別の花を添えます。
▲東海道本線 早川-根府川
海が望める西湘の鉄路を久しぶりに走る
N’EXカラーのE259系。
まもなく見納めとなるこの出で立ちに
おかめ桜がそっと惜別の花を添えます。
▲東海道本線 早川-根府川
マリンエクスプレスのN’EXが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
海辺の入り組んだ地形に敷かれたダイナミックな曲線で、しなやかな弧を描くように走りゆくE259系の「マリンエクスプレス踊り子」。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。他形式にあまり例がない気がするのですが、実は屋根の上まで赤く塗られているのが当系の特徴で (゚ー゚*)アカ、アングルに写し込んだ“おかめ桜”のピンク色とともに、きょうの冴えない曇天でも情景に色味を差してくれました (・∀・)イイネ。
高台からの俯瞰撮影という遠景ではぶっちゃけ、旧デザインでも新デザインでもパッと見はあまり変わらないように思えるけど (´・ω`・)エッ?、まずは(?)このいかにも東海道線らしい西湘(西湘南地域)の景色でふだんは入線しないE259系が撮れ、さらにそこへ花を咲かせた“おかめ桜”という早春の季節感を添えることもできて、満足のいく一枚が残せたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。個人的にはやっぱり二カ所目の“なごみアングル”よりこっちのほう好みなので、戻ってきてよかった (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
海辺の入り組んだ地形に敷かれたダイナミックな曲線で、しなやかな弧を描くように走りゆくE259系の「マリンエクスプレス踊り子」。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。他形式にあまり例がない気がするのですが、実は屋根の上まで赤く塗られているのが当系の特徴で (゚ー゚*)アカ、アングルに写し込んだ“おかめ桜”のピンク色とともに、きょうの冴えない曇天でも情景に色味を差してくれました (・∀・)イイネ。
高台からの俯瞰撮影という遠景ではぶっちゃけ、旧デザインでも新デザインでもパッと見はあまり変わらないように思えるけど (´・ω`・)エッ?、まずは(?)このいかにも東海道線らしい西湘(西湘南地域)の景色でふだんは入線しないE259系が撮れ、さらにそこへ花を咲かせた“おかめ桜”という早春の季節感を添えることもできて、満足のいく一枚が残せたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。個人的にはやっぱり二カ所目の“なごみアングル”よりこっちのほう好みなので、戻ってきてよかった (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
引き続き次にやってきたのは
こんなところ。
今度は線路際の撮影ポイントです。
このあたりは柵が低くて撮りやすい。
(・∀・)イイネ
(もちろん安全に撮影できる範囲を
しっかりと意識しています
\_(`・д・)ココ重要)
▲東海道本線 根府川-早川(後追い)
こんなところ。
今度は線路際の撮影ポイントです。
このあたりは柵が低くて撮りやすい。
(・∀・)イイネ
(もちろん安全に撮影できる範囲を
しっかりと意識しています
\_(`・д・)ココ重要)
▲東海道本線 根府川-早川(後追い)
さて、臨時特急として運行されていた本来の「マリンエクスプレス踊り子」は、東海道線から伊東線、伊豆急線へと直通する伊豆急下田ゆきでしたが、今回のツアーは下り列車の運転を東海道線の熱海までとしています ( ̄  ̄*)アタミ。私が下車した根府川は熱海の3駅手前(上り方)に位置しているため、熱海で折り返す上り運転のツアー列車(このあとは熱海から国府津へ向かう)は程なくしてここに戻ってくるハズ (・o・*)ホホゥ。
そこで私は丘の上の“踊り子アングル”から足早に坂を下り、これまで高台から見下ろしていたカーブする線路の脇へと移動してきました ...(((o*・ω・)o。そこからは列車の車両を主体としたものが撮れるため、今度はE259系の“旧デザイン”を記録するようなカットを狙ってみたいと思います (・∀・)イイネ。
さすがにこの場所はすでに何人かの同業者が先におられましたが (*・ω・)ノ゙チワッス、想定していたほど多くはなく(10人くらいだったかな?)、私も好みの立ち位置を難なくキープできました ε-(´∇`*)ホッ。
そこで私は丘の上の“踊り子アングル”から足早に坂を下り、これまで高台から見下ろしていたカーブする線路の脇へと移動してきました ...(((o*・ω・)o。そこからは列車の車両を主体としたものが撮れるため、今度はE259系の“旧デザイン”を記録するようなカットを狙ってみたいと思います (・∀・)イイネ。
さすがにこの場所はすでに何人かの同業者が先におられましたが (*・ω・)ノ゙チワッス、想定していたほど多くはなく(10人くらいだったかな?)、私も好みの立ち位置を難なくキープできました ε-(´∇`*)ホッ。
トンネルを抜けてきた
E257系の特急「踊り子」が
カーブを力走。
( ̄  ̄*)ニゴナナ
貫通型の当系(2100番台)特有の
縦書き・・・いや、斜め書き(?)な
愛称表示にシブさを覚えます。
(´w`*)シブイ
▲東海道本線 根府川-早川
E257系の特急「踊り子」が
カーブを力走。
( ̄  ̄*)ニゴナナ
貫通型の当系(2100番台)特有の
縦書き・・・いや、斜め書き(?)な
愛称表示にシブさを覚えます。
(´w`*)シブイ
▲東海道本線 根府川-早川
まずはE257系の特急「踊り子」で試し撮り (^_[◎]oパチリ。
ここは線路脇の道路から望遠レンズを装着したカメラで覗くと シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、カーブを切って向かってくる上り列車を正面がちに狙えて、なかなか迫力が感じられます (゚∀゚*)オオッ!。
なお、タイミングがいいのか悪いのか、カーブの内側となる下り線のほうでは保線員さんによる線路点検のような作業が行われており (σ゚д゚)σヨシッ!、これが若い頃の私だったら車両主体の写真に保線作業員といえども人が写り込むのを嫌って、撮影場所を移動していたかもしれませんが (´〜`)ウーン、ある程度の歳を重ねてこの趣味(撮り鉄)も長くなってきた最近では、むしろ保線作業などもまた鉄道情景のひとつだと割り切れるようになった気がします (-`ω´-*)ウム。なので、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」のときに保線員がいるとしても、もしくは作業が終わって撤収したとしても、どちらだって構いません ヾノ・∀・*)カメヘン、カメヘン。
そんな保線員(監視員)のかたが携帯しているトランシーバーが発する、『トーカイドー、ノボリ、セッキン(東海道上り接近)』という注意を促す鉄道無線の音声が私の耳にも聞こえました (°ω°*)セッキン!。
ここは線路脇の道路から望遠レンズを装着したカメラで覗くと シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、カーブを切って向かってくる上り列車を正面がちに狙えて、なかなか迫力が感じられます (゚∀゚*)オオッ!。
なお、タイミングがいいのか悪いのか、カーブの内側となる下り線のほうでは保線員さんによる線路点検のような作業が行われており (σ゚д゚)σヨシッ!、これが若い頃の私だったら車両主体の写真に保線作業員といえども人が写り込むのを嫌って、撮影場所を移動していたかもしれませんが (´〜`)ウーン、ある程度の歳を重ねてこの趣味(撮り鉄)も長くなってきた最近では、むしろ保線作業などもまた鉄道情景のひとつだと割り切れるようになった気がします (-`ω´-*)ウム。なので、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」のときに保線員がいるとしても、もしくは作業が終わって撤収したとしても、どちらだって構いません ヾノ・∀・*)カメヘン、カメヘン。
そんな保線員(監視員)のかたが携帯しているトランシーバーが発する、『トーカイドー、ノボリ、セッキン(東海道上り接近)』という注意を促す鉄道無線の音声が私の耳にも聞こえました (°ω°*)セッキン!。
今回は保線員さんとご一緒に(?)
にぎやかなお迎えで
“N’EX”、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
黒色が引き締める
凛々しいE259系のフロントマスク。
そこには“N’EX”のロゴマークとともに
「マリンエクスプレス踊り子」の
エンブレムも金色に輝いています。
(゚∀゚*)オオッ!
▲東海道本線 根府川-早川
にぎやかなお迎えで
“N’EX”、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
黒色が引き締める
凛々しいE259系のフロントマスク。
そこには“N’EX”のロゴマークとともに
「マリンエクスプレス踊り子」の
エンブレムも金色に輝いています。
(゚∀゚*)オオッ!
▲東海道本線 根府川-早川
正面からマリンエクスプレス踊り子が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
線路上にいる作業員さんへの合図とする警笛で、ミュージックホーンを鳴らしながらトンネルを抜けてきたE259系・Ne022編成 (o ̄∇ ̄o)ピポパポ♪。その見慣れた旧デザインの前面には「マリンエクスプレス踊り子」の運転時に施されていた金色のエンブレムが丁寧に再現されており、それを掲げた当系の表情はどこか誇らしげに見えます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
正直、デザインがリニューアルされるまでとくに意識したことはなかったけど、あらためて見るオリジナルカラー(旧デザイン)は赤、白、黒のバランスが絶妙で、さらに英文字をタテにした“N’EX”のロゴマークもしっくりとハマり、カッコいいデザインだったんだなぁ・・・(´ー`)シミジミ。これがもうまもなく見られなくなるのは、ちょっと惜しい気がしますね σ(・∀・`)ウーン…。
線路上にいる作業員さんへの合図とする警笛で、ミュージックホーンを鳴らしながらトンネルを抜けてきたE259系・Ne022編成 (o ̄∇ ̄o)ピポパポ♪。その見慣れた旧デザインの前面には「マリンエクスプレス踊り子」の運転時に施されていた金色のエンブレムが丁寧に再現されており、それを掲げた当系の表情はどこか誇らしげに見えます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
正直、デザインがリニューアルされるまでとくに意識したことはなかったけど、あらためて見るオリジナルカラー(旧デザイン)は赤、白、黒のバランスが絶妙で、さらに英文字をタテにした“N’EX”のロゴマークもしっくりとハマり、カッコいいデザインだったんだなぁ・・・(´ー`)シミジミ。これがもうまもなく見られなくなるのは、ちょっと惜しい気がしますね σ(・∀・`)ウーン…。
振り返って後ろ姿もパチリ。
(^_[◎]oパチリ
最後の一本となった旧デザインのE259系。
当編成がいつリニューアルするのか
詳しくはわからないけど
おそらく私にとっては
これが見納めになりそうです。
サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~
▲東海道本線 早川-根府川(後追い)
(^_[◎]oパチリ
最後の一本となった旧デザインのE259系。
当編成がいつリニューアルするのか
詳しくはわからないけど
おそらく私にとっては
これが見納めになりそうです。
サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~
▲東海道本線 早川-根府川(後追い)
高台からの遠景で眺めた往路の下り列車に対し、その折り返しとなる復路の上り列車では“N’EX”の旧デザインと「マリンエクスプレス踊り子」のエンブレムなどディテールがよくわかるように撮れて (^_[◎]oパチリ、個人的に納得のいく記録を残すことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、保線作業員さんのエキストラ出演(?)にも感謝です(いやいや、重要なお仕事の最中に失礼いたしました m(_ _)m)。
カーブを切って走り去る“N’EX”の後ろ姿を見送って、撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
カーブを切って走り去る“N’EX”の後ろ姿を見送って、撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
デザインのリニューアルがすすむ「成田エクスプレス」のE259系 (゚ー゚*)ネックス。
その”旧デザイン”で最後の一本となった編成を使用し、東海道線にて一日限りの復刻運転が行なわれた「マリンエクスプレス踊り子」は、あいにく日差しに恵まれない曇天での撮影ではあったものの (-ω-;*)ドングモリ、情景的な狙いの往路では沿線に咲いていた“おかめ桜”の艶やかな花色に早春という今の季節感を表すことができ (*’∀’*)オカメ♪、車両を主体とした復路では天候をあまり意識せずに旧デザインの特徴がよくわかるアングルで撮れて (^_[◎]oパチリ、何カ所か歩いて巡ったところでの撮影を楽しみながら満足のいく成果が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
それにしても、E259系という車両自体が引退するわけではないけれど、まさかオリジナルカラー(旧デザイン)がもう見られなくなるとは思いもせず (´・ω…:.;::..キエル…..、撮り鉄としてどんなものでも日頃の記録が大事なのだとあらためて考えさせられます (-`ω´-*)ウム。本番前の適当な試し撮りとしているような列車なども、いずれは貴重なカットとなるのかもしれませんね(ちなみに冒頭で紹介したモノサクでのE259系は、当時のお目当てだった総武本線113系の試し撮りでしたw)。
さて、せっかく根府川まで来たのなら、帰りに小田原へ寄ってキンメ・・・は、お高くて贅沢なので、アジフライでも食べていきますか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。
その”旧デザイン”で最後の一本となった編成を使用し、東海道線にて一日限りの復刻運転が行なわれた「マリンエクスプレス踊り子」は、あいにく日差しに恵まれない曇天での撮影ではあったものの (-ω-;*)ドングモリ、情景的な狙いの往路では沿線に咲いていた“おかめ桜”の艶やかな花色に早春という今の季節感を表すことができ (*’∀’*)オカメ♪、車両を主体とした復路では天候をあまり意識せずに旧デザインの特徴がよくわかるアングルで撮れて (^_[◎]oパチリ、何カ所か歩いて巡ったところでの撮影を楽しみながら満足のいく成果が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
それにしても、E259系という車両自体が引退するわけではないけれど、まさかオリジナルカラー(旧デザイン)がもう見られなくなるとは思いもせず (´・ω…:.;::..キエル…..、撮り鉄としてどんなものでも日頃の記録が大事なのだとあらためて考えさせられます (-`ω´-*)ウム。本番前の適当な試し撮りとしているような列車なども、いずれは貴重なカットとなるのかもしれませんね(ちなみに冒頭で紹介したモノサクでのE259系は、当時のお目当てだった総武本線113系の試し撮りでしたw)。
さて、せっかく根府川まで来たのなら、帰りに小田原へ寄ってキンメ・・・は、お高くて贅沢なので、アジフライでも食べていきますか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。
根府川1402-(東海道1882E)-小田原1409
小田原1513-(小田急1158急行)-新宿1643
小田原1513-(小田急1158急行)-新宿1643
まもなく消滅する(であろう)
“N’EXイメージ”の
E259系オリジナルカラー。
(゚ー゚*)ネックス
でもひょっとしたらいつの日かまた
イベント(有料撮影会)などで
復刻されるのかな?笑
(; ̄▽ ̄)アリソウ…
▲17.12.5 山手線(湘南新宿ライン) 新宿
“N’EXイメージ”の
E259系オリジナルカラー。
(゚ー゚*)ネックス
でもひょっとしたらいつの日かまた
イベント(有料撮影会)などで
復刻されるのかな?笑
(; ̄▽ ̄)アリソウ…
▲17.12.5 山手線(湘南新宿ライン) 新宿
なお更新日のきょうは
2/22で“猫の日”ですが
(=^・ω・^=) ニャア
拙ブログ的には本記事で取り上げた
最後の旧デザインである
E259系“Ne022編成”にちなんだものですw
2/22で“猫の日”ですが
(=^・ω・^=) ニャア
拙ブログ的には本記事で取り上げた
最後の旧デザインである
E259系“Ne022編成”にちなんだものですw
2024-02-22 22:22
身延線・・・373系 特急「ふじかわ」撮影記 [鉄道写真撮影記]
カラッカラに乾いた乾燥注意報が気になるものの(火の用心!)、年明けからずっと晴天続きの関東地方 (´▽`*)イイテンキ♪。
都内の仕事場へ向かうのに私が乗る高架線を走る通勤電車(中央線ね)の窓からは、西のほうに富士山のお姿がクッキリと遥拝できました (「゚ー゚)フジサン。やはり冠雪した冬富士はとくに美しく、それを見ると“撮り鉄”の私としては富士山を背景にした列車の写真が撮りたくなります ((o(゙ε゙)o))ウズウズ。
んじゃ、縁起物でもある富士山へ新年のごあいさつを兼ねて、週末はそちらの方にお出かけしてみましょうか (・∀・)イイネ。
1月6日(土)
都内の仕事場へ向かうのに私が乗る高架線を走る通勤電車(中央線ね)の窓からは、西のほうに富士山のお姿がクッキリと遥拝できました (「゚ー゚)フジサン。やはり冠雪した冬富士はとくに美しく、それを見ると“撮り鉄”の私としては富士山を背景にした列車の写真が撮りたくなります ((o(゙ε゙)o))ウズウズ。
んじゃ、縁起物でもある富士山へ新年のごあいさつを兼ねて、週末はそちらの方にお出かけしてみましょうか (・∀・)イイネ。
1月6日(土)
今シーズンは暖冬とはいえ、まだ夜明け前の5時半はやはり寒くて頬や耳、鼻が冷たい {{{(>_<+)}}}サブッ!。そんな暗い時間に東京から東海道線の沼津(ぬまづ)ゆき下り普通列車に乗って西進します ...(((o*・ω・)o。
都内から富士山のほうへ鉄道で向かう場合、“東海道本線(東海道新幹線)で静岡県”か“中央本線で山梨県”という二通りにざっくりと分けられますが、今旅の私は前者を選びました (* ̄  ̄)シゾーカ。
都内から富士山のほうへ鉄道で向かう場合、“東海道本線(東海道新幹線)で静岡県”か“中央本線で山梨県”という二通りにざっくりと分けられますが、今旅の私は前者を選びました (* ̄  ̄)シゾーカ。
東京を5時半に出た東海道線は今の時期
西湘の相模湾に沿って走るあたりでちょうど
日の出を迎えます。
(゚∀゚)オッ!
水平線上にはちょっと雲が湧いているけど
きょうもいいお天気になりそうですね。
富士山の見え具合はどうかな?
▲▲東海道本線 早川-根府川
▲東海道本線 根府川
(いずれも車窓から)
西湘の相模湾に沿って走るあたりでちょうど
日の出を迎えます。
(゚∀゚)オッ!
水平線上にはちょっと雲が湧いているけど
きょうもいいお天気になりそうですね。
富士山の見え具合はどうかな?
▲▲東海道本線 早川-根府川
▲東海道本線 根府川
(いずれも車窓から)
出かける前(昨夜)にテレビやネットでチェックしてきた天気予報によると、関東や東海地方はここ数日に続いてきょうも“晴れ”となっています ( ̄∇ ̄)ハレ。ただし、それで安心しきれないのが山をのぞむ撮影 (´・ω`・)エッ?。たとえその地域が青空の広がる晴天であっても、山のまわりにもくもくと湧きだした雲が山頂を隠してしまうのはよくあることで、実際に自分の目で山の状況を確認するまでは何とも言えません (-`ω´-*)ウム。
東海道線だとまず小田原の手前あたりで車窓から富士山が望めるハズですが、今の時間はまだ薄暗くてよくわからない (≡”≡*)クライ。小田原を過ぎると相模湾の海沿いを走るようになる当線からは箱根の山に隠されて富士山がしばらく見えず、ちょっとモヤモヤした気分で乗り進みます (´〜`)ウーン。
東海道線だとまず小田原の手前あたりで車窓から富士山が望めるハズですが、今の時間はまだ薄暗くてよくわからない (≡”≡*)クライ。小田原を過ぎると相模湾の海沿いを走るようになる当線からは箱根の山に隠されて富士山がしばらく見えず、ちょっとモヤモヤした気分で乗り進みます (´〜`)ウーン。
沼津で静岡ゆき普通列車に乗り継ぎ。
ボックスシートを備えた
セミクロスシート仕様の313系です。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
このあたりの区間(熱海〜浜松)は少し前まで
ロングシートの211系ばっかだったけど
最近はセミクロスの313系が増えている印象で
個人的に嬉しいことです
(編成も3両だったものから
5両になった列車が多くなったね)。
▲東海道本線 沼津
ボックスシートを備えた
セミクロスシート仕様の313系です。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
このあたりの区間(熱海〜浜松)は少し前まで
ロングシートの211系ばっかだったけど
最近はセミクロスの313系が増えている印象で
個人的に嬉しいことです
(編成も3両だったものから
5両になった列車が多くなったね)。
▲東海道本線 沼津
次に車窓から富士山がチェックできるのは、熱海の先にある長〜いトンネル(全長7,804mの丹那トンネル)を抜けたあとの三島付近 ( ̄  ̄*)ミシマ。そこを通過するころには日が昇ってじゅうぶんに明るくなっています。
はたして車窓に映し出されたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!
はたして車窓に映し出されたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!
雲ひとつない青空のもとで
優雅にそびえる富士の山。
(゚ー゚*)フジ
ちなみに三島や沼津あたりでも
すでに富士山はチラ見できましたが
建物が多い街なかより少しひらけた
この東田子の浦付近が
車窓からの富士山は撮りやすい。
(^_[◎]oパチリ
▲東海道本線 原-東田子の浦(車窓から)
優雅にそびえる富士の山。
(゚ー゚*)フジ
ちなみに三島や沼津あたりでも
すでに富士山はチラ見できましたが
建物が多い街なかより少しひらけた
この東田子の浦付近が
車窓からの富士山は撮りやすい。
(^_[◎]oパチリ
▲東海道本線 原-東田子の浦(車窓から)
ふじさん、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
神経質なまでに雲の湧きあがりを懸念していた私をあざ笑うかのように、きょうの富士山は頂までスッキリと美しい姿をみせていました (゚∀゚*)オオッ!。それを見てとりあえず(?)ホッと安堵します ε-(´∇`*)ホッ(のちに雲が湧くかもしれないけど)。
この好条件の富士山がきれいに撮れるような場所を目指して、私が富士で東海道線から乗り換えたのは身延線(みのぶせん)ノリカエ…((((o* ̄-)o。
神経質なまでに雲の湧きあがりを懸念していた私をあざ笑うかのように、きょうの富士山は頂までスッキリと美しい姿をみせていました (゚∀゚*)オオッ!。それを見てとりあえず(?)ホッと安堵します ε-(´∇`*)ホッ(のちに雲が湧くかもしれないけど)。
この好条件の富士山がきれいに撮れるような場所を目指して、私が富士で東海道線から乗り換えたのは身延線(みのぶせん)ノリカエ…((((o* ̄-)o。
身延線は東海道本線と接する静岡県富士市の富士を起点に、富士宮、内船(うつぶな)、身延、下部温泉(しもべおんせん)、甲斐岩間(かいいわま)、鰍沢口(かじかさわぐち)、市川大門(いちかわだいもん)、東花輪(ひがしはなわ)など、おもに富士川の左岸(東岸)地域に所在する各駅を経て静岡県から山梨県へと北上し、中央本線と接する山梨県甲府市の甲府へといたる88.4キロの路線 (・o・*)ホホゥ。
いわゆるローカル線を表す“地方交通線”に分類されるものの、全線が直流電化されて特急列車も定期運行しており、また静岡側の富士〜西富士宮、山梨側の鰍沢口〜甲府における市街地区間の輸送密度と運行本数をみると、地方交通線より重要度の高い“亜幹線”という印象が強いでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。ただし西富士宮〜鰍沢口のあいだは運行本数が極端に少なくて、景色的にものどかなローカル線の風情が漂います (´ー`)マターリ。ちなみに昨春(2023年)に私が撮影へ訪れた、桜がきれいな駅の塩之沢(しおのさわ)はその閑散区間にあり、身延線を旅するのはそのとき以来のこと。
いわゆるローカル線を表す“地方交通線”に分類されるものの、全線が直流電化されて特急列車も定期運行しており、また静岡側の富士〜西富士宮、山梨側の鰍沢口〜甲府における市街地区間の輸送密度と運行本数をみると、地方交通線より重要度の高い“亜幹線”という印象が強いでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。ただし西富士宮〜鰍沢口のあいだは運行本数が極端に少なくて、景色的にものどかなローカル線の風情が漂います (´ー`)マターリ。ちなみに昨春(2023年)に私が撮影へ訪れた、桜がきれいな駅の塩之沢(しおのさわ)はその閑散区間にあり、身延線を旅するのはそのとき以来のこと。
ボックスシートの窓側をキープして
車窓から富士山を眺めます。
(「゚ー゚)ドレドレ
場所(区間)によって
富士山が見える側は異なるけど
甲府方面へ進む下り列車なら
向かって右席のほうが見やすいかな。
(ただし列車によっては
ロングシートの場合もあります)
▲身延線 富士-柚木
車窓から富士山を眺めます。
(「゚ー゚)ドレドレ
場所(区間)によって
富士山が見える側は異なるけど
甲府方面へ進む下り列車なら
向かって右席のほうが見やすいかな。
(ただし列車によっては
ロングシートの場合もあります)
▲身延線 富士-柚木
そんな身延線は富士山麓の西側を南北方向に敷かれており、とくに路線前半の富士から沼久保(ぬまくぼ)のあたりにかけては天候条件がよいと車窓よりその雄大な山容がきれいに望めて、屈指の“富嶽鉄景”に挙げられます (・∀・)イイネ。
お伝えしたとおり雲ひとつない快晴に恵まれたきょうは絶好の“富士山日和” ъ(゚Д゚)ナイス。これは沿線での撮影にもおのずと期待が高まるというものです (*´v`*)ワクワク♪。
お伝えしたとおり雲ひとつない快晴に恵まれたきょうは絶好の“富士山日和” ъ(゚Д゚)ナイス。これは沿線での撮影にもおのずと期待が高まるというものです (*´v`*)ワクワク♪。
入山瀬(いりやませ)は
駅前の自動車教習所越しに富士山が。
(゚ー゚*)フジ
▲身延線 入山瀬(車窓から)
富士根はまさにその名の通り
ホームから富士山ビュー。
(゚ー゚*)フジ
このあたり(富士〜富士宮)では
ほぼ各駅から富士山が望めるので
それぞれ途中下車して見比べるのも
面白いかも知れませんね。
▲身延線 富士根(車窓から)
静岡県富士宮市の中心駅で
富士山本宮浅間大社の最寄駅である
富士宮。
(゚ー゚*)フジノミヤ
写真には写っていませんが
当駅のホームからも角度によっては
富士山を見ることができます。
▲身延線 富士宮(車窓から)
富士宮を発車した列車からは
朱の大鳥居と富士山という
ありがたみのある車窓景色が見られます。
(゚∀゚)オッ!
ちなみにこの大鳥居は
富士山世界遺産センターの横に建つ
富士山本宮浅間大社の一之鳥居(第一鳥居)。
▲身延線 富士宮-西富士宮(車窓から)
富士宮の次駅で
同市内に所在する西富士宮。
ここから先(下り方)の身延線は
列車の運行本数が減ります。
私が座った席の窓からはちょうど
その下り方面の時刻表が確認できました。
(*゚ェ゚)フムフム
▲身延線 西富士宮(車窓から)
駅前の自動車教習所越しに富士山が。
(゚ー゚*)フジ
▲身延線 入山瀬(車窓から)
富士根はまさにその名の通り
ホームから富士山ビュー。
(゚ー゚*)フジ
このあたり(富士〜富士宮)では
ほぼ各駅から富士山が望めるので
それぞれ途中下車して見比べるのも
面白いかも知れませんね。
▲身延線 富士根(車窓から)
静岡県富士宮市の中心駅で
富士山本宮浅間大社の最寄駅である
富士宮。
(゚ー゚*)フジノミヤ
写真には写っていませんが
当駅のホームからも角度によっては
富士山を見ることができます。
▲身延線 富士宮(車窓から)
富士宮を発車した列車からは
朱の大鳥居と富士山という
ありがたみのある車窓景色が見られます。
(゚∀゚)オッ!
ちなみにこの大鳥居は
富士山世界遺産センターの横に建つ
富士山本宮浅間大社の一之鳥居(第一鳥居)。
▲身延線 富士宮-西富士宮(車窓から)
富士宮の次駅で
同市内に所在する西富士宮。
ここから先(下り方)の身延線は
列車の運行本数が減ります。
私が座った席の窓からはちょうど
その下り方面の時刻表が確認できました。
(*゚ェ゚)フムフム
▲身延線 西富士宮(車窓から)
ずっと車窓に見えている(と言っても過言ではない)富士山を贅沢に眺めながら進むこと20分ほどで、列車は沿線最大の街である富士宮市の富士宮に停車 (゚ー゚*)フジノミヤ。そして富士宮の次駅で同市内に所在する西富士宮は身延線の運行上の境界駅となっており、富士〜西富士宮は普通列車が日中でもおおむね20〜30分間隔の頻度ですが、富士山西麓と南アルプス東麓に挟まれた富士川沿いの山あいを進むようになる当駅以北(甲府方)は運行本数がグッと減り、普通列車は二時間に一本という時間帯もあります ( ̄  ̄)スクナイ。
なお私がいま乗っている列車は、ここより先へと進む貴重な(?)甲府ゆき・・・ですが、それを活かせたのはわずか一駅だけ。西富士宮の次駅の沼久保で下車しました (・ω・)トーチャコ。
なお私がいま乗っている列車は、ここより先へと進む貴重な(?)甲府ゆき・・・ですが、それを活かせたのはわずか一駅だけ。西富士宮の次駅の沼久保で下車しました (・ω・)トーチャコ。
車内清算制のワンマン列車から
私が降りたのは
富士宮市内に所在する沼久保。
(゚ー゚*)ヌマクボ
駅舎はなく狭いホームが一面だけの
簡素な造りの無人駅ですが
その構内から望める富士山は
これまた見事な眺めです。
(・∀・)イイネ
▲身延線 沼久保
(開いている構内踏切より撮影)
私が降りたのは
富士宮市内に所在する沼久保。
(゚ー゚*)ヌマクボ
駅舎はなく狭いホームが一面だけの
簡素な造りの無人駅ですが
その構内から望める富士山は
これまた見事な眺めです。
(・∀・)イイネ
▲身延線 沼久保
(開いている構内踏切より撮影)
東京0540-(東海道323M)-沼津0804~0809-(2745M)-富士0827~0912-(身延3627G)-沼久保0941
富士宮、西富士宮に続く富士宮市内にありながら、駅のまわりに民家はまばらで林が目立ち、言いかたはあまりよくないけど“街はずれ”にあたるような雰囲気がただよう無人駅の沼久保 (゚ー゚*)ヌマクボ。
そんなのどかな環境のなか線路と並行した県道を富士宮のほうへ歩き進むと、列車の窓からよく見えていた富士山が道路からもきれいに望めて、なかなか気持ちのいいウォーキングです ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘。
富士宮、西富士宮に続く富士宮市内にありながら、駅のまわりに民家はまばらで林が目立ち、言いかたはあまりよくないけど“街はずれ”にあたるような雰囲気がただよう無人駅の沼久保 (゚ー゚*)ヌマクボ。
そんなのどかな環境のなか線路と並行した県道を富士宮のほうへ歩き進むと、列車の窓からよく見えていた富士山が道路からもきれいに望めて、なかなか気持ちのいいウォーキングです ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘。
ちなみに起点側の静岡(富士)から山梨(甲府)のほうへ向かって基本的には北上する形をとる身延線ですが、富士宮から沼久保を経て稲子(いなこ)にかけての区間は線路がクネクネと大きく蛇行しており 〜(( ̄ー ̄))〜クネクネ、いま私が歩いている線路沿いの道も上りの富士方向へと進んでいるのに、その方角は南でなく北を向いています (゚ー゚?)オヨ?。何だか方向感覚が惑わされそうなこの区間の途中にあるのが、私の目的地とする身延線の撮影ポイント。そこへは駅から歩くこと20分ほどで到達できました。
おお、絶景かな絶景かな(鉄ちゃん的に)w(゚o゚*)w オオー!。
ここは富士山を背景にして身延線の列車がスッキリと撮れる、当線きっての“お立ち台”的な有名撮影ポイントで、ウマくアングルを組み立てれば列車と富士山がバランスよく収まります (・∀・)イイネ。そして先述したようにここは南を背にして北のほうを向いているのに甲府方面へ進む下り列車が基本的に正面順光となる、いろいろな意味で妙(奇妙?絶妙?)な印象の面白い場所 (゚∀゚)アヒャ☆。
ここは富士山を背景にして身延線の列車がスッキリと撮れる、当線きっての“お立ち台”的な有名撮影ポイントで、ウマくアングルを組み立てれば列車と富士山がバランスよく収まります (・∀・)イイネ。そして先述したようにここは南を背にして北のほうを向いているのに甲府方面へ進む下り列車が基本的に正面順光となる、いろいろな意味で妙(奇妙?絶妙?)な印象の面白い場所 (゚∀゚)アヒャ☆。
当地でカメラを構えて最初に通過したのは、静岡ゆき上り特急列車の「ふじかわ4号」(゚ー゚*)フジカワ。
特急型車両の373系で運転される「ふじかわ」は東海道本線と身延線を直通して静岡と甲府のあいだを走る特急列車で、身延線内の普通列車をサポートする地域輸送とあわせて静岡と山梨の県都をむすぶ都市間輸送も担っており、一日に7往復もの運行本数が設定されています (・o・*)ホホゥ。
この場所で上り列車の「4号」は進行方向の後ろ側から撮る“後追い撮影”となるため、とりあえず適当な試し撮り的にシャッターを切ってみたところ【◎】]ω・)パチャ、パッと見で構図のバランスは悪くないように思えるものの、アングルの右下のほうにある家屋をカットしたら富士山の右肩に突き出した宝永山(ほうえいざん)までフレームから外れてしまいました (ノO`)アチャー。ちなみに宝永山は江戸時代の宝永4年(1707年)に発生した富士山の大噴火によってできた側火山で、私が前に静岡の人と富士山の話をしたとき「宝永山は静岡側から見る富士山の特徴だから、写真などを撮るときにできれば入れるべし ヽ(゚ω゚)ベシ」と聞いたことがあり、私はそれ以来この宝永山の存在を意識するようになっています ( ̄  ̄)ホーエーザン(なお山梨側からだと宝永山は確認しづらい)。う〜ん、ここはやっぱり「宝永山も入れるべし」か (-`ω´-*)ウム。
あと細かいとこだけど、富士山の向かって左の山裾にかかる木の枝もちょっと気になるかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。それらを修正したアングルで次に臨むのが本番となる下り列車の「ふじかわ3号」 (*`・ω・´)-3フンス!。
特急型車両の373系で運転される「ふじかわ」は東海道本線と身延線を直通して静岡と甲府のあいだを走る特急列車で、身延線内の普通列車をサポートする地域輸送とあわせて静岡と山梨の県都をむすぶ都市間輸送も担っており、一日に7往復もの運行本数が設定されています (・o・*)ホホゥ。
この場所で上り列車の「4号」は進行方向の後ろ側から撮る“後追い撮影”となるため、とりあえず適当な試し撮り的にシャッターを切ってみたところ【◎】]ω・)パチャ、パッと見で構図のバランスは悪くないように思えるものの、アングルの右下のほうにある家屋をカットしたら富士山の右肩に突き出した宝永山(ほうえいざん)までフレームから外れてしまいました (ノO`)アチャー。ちなみに宝永山は江戸時代の宝永4年(1707年)に発生した富士山の大噴火によってできた側火山で、私が前に静岡の人と富士山の話をしたとき「宝永山は静岡側から見る富士山の特徴だから、写真などを撮るときにできれば入れるべし ヽ(゚ω゚)ベシ」と聞いたことがあり、私はそれ以来この宝永山の存在を意識するようになっています ( ̄  ̄)ホーエーザン(なお山梨側からだと宝永山は確認しづらい)。う〜ん、ここはやっぱり「宝永山も入れるべし」か (-`ω´-*)ウム。
あと細かいとこだけど、富士山の向かって左の山裾にかかる木の枝もちょっと気になるかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。それらを修正したアングルで次に臨むのが本番となる下り列車の「ふじかわ3号」 (*`・ω・´)-3フンス!。
富士山バックで「ふじかわ」が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
四灯のヘッドライト(前灯)を輝かせて迫りくる373系の特急「ふじかわ」と、その後ろでどっしりと見守る雄大な富士山のお姿 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。定番の構図ではあるけれど素直な身延線らしい情景を好条件で撮る事ができました (^_[◎]oパチリ。
例年の今ごろの時期と比べたら頂の冠雪がやや少なめに感じますが、これは暖冬といわれる今冬らしさが表れた風情だと思いますし、このくらいの薄化粧もまた粋で美しいもの (*'∀'*)ステキ☆。そして右下に写り込んだ家屋の一角がウマくかわせなかったものの、今度はしっかりと宝永山まで入れてみました (・∀・)ホーエーザン。あらためて見るとちょこんと突き出た宝永山がなんだか可愛いじゃないですか(笑)
きょうの撮影でいちばんのターゲットだった「ふじかわ3号」を、とくに問題なく撮れてホッと一息 ε-(´∇`*)ホッ。
四灯のヘッドライト(前灯)を輝かせて迫りくる373系の特急「ふじかわ」と、その後ろでどっしりと見守る雄大な富士山のお姿 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。定番の構図ではあるけれど素直な身延線らしい情景を好条件で撮る事ができました (^_[◎]oパチリ。
例年の今ごろの時期と比べたら頂の冠雪がやや少なめに感じますが、これは暖冬といわれる今冬らしさが表れた風情だと思いますし、このくらいの薄化粧もまた粋で美しいもの (*'∀'*)ステキ☆。そして右下に写り込んだ家屋の一角がウマくかわせなかったものの、今度はしっかりと宝永山まで入れてみました (・∀・)ホーエーザン。あらためて見るとちょこんと突き出た宝永山がなんだか可愛いじゃないですか(笑)
きょうの撮影でいちばんのターゲットだった「ふじかわ3号」を、とくに問題なく撮れてホッと一息 ε-(´∇`*)ホッ。
撮影地から富士山がきれいに見えている好条件に恵まれたので、引き続き次の甲府ゆきの下り普通列車(3629G)も待ってみます ( ̄  ̄*)ドンコー。
こちらのアングルは先ほどの「ふじかわ3号」が姿を現した際に「ふじかわ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!」と、カメラのシャッター動作の確認もかねてためしに“早切り”したカットを参考にしたもので、構図のなかでこのあたりに列車を置いて存在を少し控えめとし、そのぶん富士山の雄大さを強調するのもアリだな・・・と思い、それを実践してみました (^_[◎]oパチリ。
特急列車らしい華麗な走りをイメージして車両を大きめにした「ふじかわ3号」のカットと、車窓から壮大な富士山が望める身延線らしい旅情感をイメージした普通列車のカット、ほぼ同じ立ち位置から印象の異なる二枚が撮れて満足のいく成果となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
これで富士山を背景にした身延線の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
こちらのアングルは先ほどの「ふじかわ3号」が姿を現した際に「ふじかわ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!」と、カメラのシャッター動作の確認もかねてためしに“早切り”したカットを参考にしたもので、構図のなかでこのあたりに列車を置いて存在を少し控えめとし、そのぶん富士山の雄大さを強調するのもアリだな・・・と思い、それを実践してみました (^_[◎]oパチリ。
特急列車らしい華麗な走りをイメージして車両を大きめにした「ふじかわ3号」のカットと、車窓から壮大な富士山が望める身延線らしい旅情感をイメージした普通列車のカット、ほぼ同じ立ち位置から印象の異なる二枚が撮れて満足のいく成果となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
これで富士山を背景にした身延線の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
こちらは撮影ポイントの近くにある
日蓮宗大法山 東漸寺さん。
山門に鎮座するお釈迦さまと
その両脇を固める仁王さまが立派で
思わず足を止めてしまいました。
(*・`o´・*)ホ─
ちなみにこの門前からも富士山が望めます。
(゚ー゚*)フジ
日蓮宗大法山 東漸寺さん。
山門に鎮座するお釈迦さまと
その両脇を固める仁王さまが立派で
思わず足を止めてしまいました。
(*・`o´・*)ホ─
ちなみにこの門前からも富士山が望めます。
(゚ー゚*)フジ
さて、今旅は身延線の撮影が私のいちばんの目的ではあるけれど、せっかく新年が明けてまもない今の時期に富士宮へ来たのならば、市内の中心部にある「富士山本宮浅間大社」をお参りしたいところ (・∀・)イイネ。
駄菓子菓子(だがしかし)、普通列車の運転が二時間に一本という当区間では、次の富士ゆき上り列車(3628M)まで一時間以上も沼久保で待たなくてはなりません ( ̄  ̄;)イチジカン…。まあ、富士山の見える駅でぼーっと過ごしていてもよいのですが 。゜(# ̄ ▽. ̄#) ボケー°。、ためしに今の私がいる撮影地から浅間大社まで歩いたらどれくらいかかるのか、スマホの地図アプリで調べてみたところ []o(・_・*)ドレドレ、“およそ3キロで徒歩43分”という予測。
駄菓子菓子(だがしかし)、普通列車の運転が二時間に一本という当区間では、次の富士ゆき上り列車(3628M)まで一時間以上も沼久保で待たなくてはなりません ( ̄  ̄;)イチジカン…。まあ、富士山の見える駅でぼーっと過ごしていてもよいのですが 。゜(# ̄ ▽. ̄#) ボケー°。、ためしに今の私がいる撮影地から浅間大社まで歩いたらどれくらいかかるのか、スマホの地図アプリで調べてみたところ []o(・_・*)ドレドレ、“およそ3キロで徒歩43分”という予測。
これは決して近くはないけど歩けなくもない距離で、とくに急いで行く理由はありませんが、20分かけて沼久保駅へ戻って一時間後の列車を待つより目的地に早く着けそうです σ(゚・゚*)ンー…。いいお天気のもと富士山を眺めながら歩くのは気持ちよさそうだし (・∀・)イイネ、だらけて過ごした正月休みの運動不足も少しは解消できそう (。A。)アヒャ☆。私は撮影地をあとにすると大社のほうへ向かって歩みを進めました ...(((o*・ω・)o。
浅間大社へ向かう道中には
高台から富士山と富士宮の街が
広く一望できるところがありました
(展望台などでなくただの道路脇)。
(゚ー゚*)フジ
歩いたからこそ見られたこの眺めは
嬉しいご褒美です。
(´▽`*)ワ~イ♪
んで、
そこから街なかを注視すると
(「゚ー゚)ドレドレ
先ほど身延線の車窓からも見えた
富士山本宮浅間大社の
大鳥居(一之鳥居)が確認できます。
あそこがウォーキングのゴールね。
(*`・ω・´)-3フンス!
いい陽気のおかげか
さほど苦労することなく
富士山本宮浅間大社には
おおむね時間どおりに歩き着けました。
(・ω・)トーチャコ
なおこちらの大鳥居は
車窓から見えた“一之鳥居”ではなく
参道を進んだところにある
“二之鳥居”(第二鳥居)です。
(゚ー゚*)フジ
初詣の参拝者で賑わい
私もお参りに訪れた
富士宮の「富士山本宮浅間大社」。
富士山を御祭神(浅間大神)として祀る
浅間神社の総本宮にして
駿河国の一之宮です。
本殿、幣殿、拝殿(写真下)、
楼門(同上)などは
関ヶ原の戦いに勝利した
徳川家康の寄進により建立されたもの。
(*・`o´・*)ホ─
高台から富士山と富士宮の街が
広く一望できるところがありました
(展望台などでなくただの道路脇)。
(゚ー゚*)フジ
歩いたからこそ見られたこの眺めは
嬉しいご褒美です。
(´▽`*)ワ~イ♪
んで、
そこから街なかを注視すると
(「゚ー゚)ドレドレ
先ほど身延線の車窓からも見えた
富士山本宮浅間大社の
大鳥居(一之鳥居)が確認できます。
あそこがウォーキングのゴールね。
(*`・ω・´)-3フンス!
いい陽気のおかげか
さほど苦労することなく
富士山本宮浅間大社には
おおむね時間どおりに歩き着けました。
(・ω・)トーチャコ
なおこちらの大鳥居は
車窓から見えた“一之鳥居”ではなく
参道を進んだところにある
“二之鳥居”(第二鳥居)です。
(゚ー゚*)フジ
初詣の参拝者で賑わい
私もお参りに訪れた
富士宮の「富士山本宮浅間大社」。
富士山を御祭神(浅間大神)として祀る
浅間神社の総本宮にして
駿河国の一之宮です。
本殿、幣殿、拝殿(写真下)、
楼門(同上)などは
関ヶ原の戦いに勝利した
徳川家康の寄進により建立されたもの。
(*・`o´・*)ホ─
正月明けの週末に、雪化粧した美しい冬富士とその麓を走る鉄道の情景を求めて旅した、身延線の富士宮界隈 ( ̄∇ ̄)ミノブセソ。
富士山が背景の舞台で躍動する373系の特急「ふじかわ」や313系の普通列車を、青空が澄みわたる好天のもとで気持ちよく撮影することができ (^_[◎]oパチリ、新年に嬉しい幸先のよいものとなりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、訪れた撮影ポイントは一か所のみで“撮り鉄”としての成果は少なめだったけど、列車の車窓から眺めた富士山は“乗り鉄”として楽しめ (゚ー゚*)フジ、さらに富士山をご神体とする「富士山本宮浅間大社」にもお参りができて (-人-〃)ムニャムニャ、“乗る、撮る、参る”という私なりの富士山詣を満喫できたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。
なお、私の初詣参拝は氏神様である地元の神社で元日に済ませたので、ここ本宮浅間大社では年明け早々に衝撃的な出来事が続いた今年一年が、もうこれ以上の災いなく平穏でありますように願いました。
さ、大社へのご挨拶を済ませたことだし、ご当地名物の“富士宮焼きそば”を参道の横丁(お宮横丁)で食べてから帰ろう (゚¬゚〃)ヤキソバ。
富士山が背景の舞台で躍動する373系の特急「ふじかわ」や313系の普通列車を、青空が澄みわたる好天のもとで気持ちよく撮影することができ (^_[◎]oパチリ、新年に嬉しい幸先のよいものとなりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、訪れた撮影ポイントは一か所のみで“撮り鉄”としての成果は少なめだったけど、列車の車窓から眺めた富士山は“乗り鉄”として楽しめ (゚ー゚*)フジ、さらに富士山をご神体とする「富士山本宮浅間大社」にもお参りができて (-人-〃)ムニャムニャ、“乗る、撮る、参る”という私なりの富士山詣を満喫できたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。
なお、私の初詣参拝は氏神様である地元の神社で元日に済ませたので、ここ本宮浅間大社では年明け早々に衝撃的な出来事が続いた今年一年が、もうこれ以上の災いなく平穏でありますように願いました。
さ、大社へのご挨拶を済ませたことだし、ご当地名物の“富士宮焼きそば”を参道の横丁(お宮横丁)で食べてから帰ろう (゚¬゚〃)ヤキソバ。
お参りのあとにいただく
富士宮の名物といえばもちろん
「富士宮やきそば」。
(゚¬゚〃)ジュルリ
コシが強めなご当地産の麺を使い
“肉かす”(豚あぶら)を具材に入れ
サバやイワシなどの“削り粉“を
ふりかけるのが特徴だそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
今や全国的に有名となった
ご当地グルメの代表格ですが
やはり本場で食べるのはひと味違う
・・・かな?
(゚д゚)ウマー!
ビジュアルに惹かれたデザートは
富士山をイメージした
“富士山ジェラート”。
(゚ー゚*)フジ
青はラムネ(カルピス?)っぽい味で
白は朝霧高原の牛乳を使った
濃厚なミルクでした。
冬でも気温が高めのきょうは
アイスが美味しい♪
富士山本宮浅間大社の最寄駅の
富士宮ですが
駅舎はとくに富士山や大社を
イメージしたものでなく
いたってシンプルな造りの橋上駅舎。
( ̄  ̄)フツー
▲身延線 富士宮
富士宮から乗る身延線
富士ゆき上り普通列車は
西富士宮を始発駅とする区間運用で
ロングシート仕様の313系でした。
( ̄  ̄)ロング…
▲身延線 富士宮
富士で東海道線に乗り継いで
東京のほうへ帰ります。
少しダイヤが乱れていたようで
3両編成の熱海ゆき普通列車は
けっこう混んでいました。
▲東海道本線 富士
富士宮の名物といえばもちろん
「富士宮やきそば」。
(゚¬゚〃)ジュルリ
コシが強めなご当地産の麺を使い
“肉かす”(豚あぶら)を具材に入れ
サバやイワシなどの“削り粉“を
ふりかけるのが特徴だそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
今や全国的に有名となった
ご当地グルメの代表格ですが
やはり本場で食べるのはひと味違う
・・・かな?
(゚д゚)ウマー!
ビジュアルに惹かれたデザートは
富士山をイメージした
“富士山ジェラート”。
(゚ー゚*)フジ
青はラムネ(カルピス?)っぽい味で
白は朝霧高原の牛乳を使った
濃厚なミルクでした。
冬でも気温が高めのきょうは
アイスが美味しい♪
富士山本宮浅間大社の最寄駅の
富士宮ですが
駅舎はとくに富士山や大社を
イメージしたものでなく
いたってシンプルな造りの橋上駅舎。
( ̄  ̄)フツー
▲身延線 富士宮
富士宮から乗る身延線
富士ゆき上り普通列車は
西富士宮を始発駅とする区間運用で
ロングシート仕様の313系でした。
( ̄  ̄)ロング…
▲身延線 富士宮
富士で東海道線に乗り継いで
東京のほうへ帰ります。
少しダイヤが乱れていたようで
3両編成の熱海ゆき普通列車は
けっこう混んでいました。
▲東海道本線 富士
富士宮1312-(身延3554M)-富士1330~1334-(東海道432M)-熱海1421~1433-(1886E)-小田原1455~1504-(湘南新宿ライン4832Y特別快速)-新宿1619
2024-01-22 22:22
筑肥線・・・103系1500番台 E12編成 撮影記 [鉄道写真撮影記]
早いもので師走となり、年末年始のお休み(休暇)を意識する頃 σ(゚・゚*)ンー…。
「え、お正月?おほほほ、もちろんハワイよ (´∇ノ`*)オホホホホ」
・・・な〜んてことはまずないけど、鉄道が好きな “鉄ちゃん” の私としては休み中に泊りがけで、“乗り鉄” や “撮り鉄”などを楽しむ “鉄旅”(鉄道の旅)にお出かけしたいと考えます ( ̄▽ ̄*)テツタビ。
駄菓子菓子(だがしかし)、帰省や旅行などで多くの人たちがいっせいに移動する年末年始は当然ながら、飛行機も新幹線も大混雑が必至でチケット(航空券・指定券)が取りにくいし、ホテルなどの宿泊施設はどこも“強気”な高価格の設定となっています ( ̄  ̄;)タカスギクン…。
相次ぐ値上げで物価高をひしひしと感じる昨今に加え、ただでさえ物入りが多い時期(忘年会や新年会のお誘いなどもw)、あくまでも“趣味”の範ちゅうである鉄旅の費用はなるべく抑えたいもの。そうすると年末年始のハイシーズン(繁忙期)に旅行へ出かけるのはキビシいか σ(・∀・`)ウーン…。
でもなぁ・・・私には今年(2023年)やり残したというか、できれば年内に行きたいところがあるんですよね。
んー、それならば何も年末年始の休みじゃなくていいんじゃない? (*゚o゚)ハッ!
紅葉の行楽シーズンがおおむね落ち着き、学生の冬休みが始まる前の狭間となる12月の上旬は例年、比較的旅行者が少ないとされる “閑散期” のひとつで、この時期の交通機関はすいているし、宿泊施設なども価格を安めに設定しています (。-∀-)ホゥ(最近はインバウンドの増加で必ずしもそうではないけど)。
ためしに運賃を変動制としている(日や便によって異なる)格安航空会社(LCC)のサイトを適当にチェックしてみたところ \_ヘヘ(- ̄*)ドレドレ、やはり12月の第二週目の平日(12/4〜8)ならば、私が行きたい地域への航空運賃が最安値で片道なんと4,000円台!(゚∀゚)オッ!。また、某ビジネスホテルチェーンのお部屋も年末年始に比べて半額に近いお値段で泊まれるじゃありませんか! (゚∀゚*)オオッ!!。
「社長、やすい、やすぅ〜い♡ 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。」
この安さを目の当たりにした勢いで往復の航空便と宿泊の予約したのが、今からひと月半前にあたる10月下旬のこと。そのころの私は仕事が多忙で休日出勤もあったため代休が何日か溜まっており、それをおトクな “閑散期” に振り替えて活用しちゃいましょう ъ(゚Д゚)ナイス。
前置きが長くなりましたが、そんなワケで今冬の私は年末年始でなく、12月上旬の平日である7日の木曜日から、“乗り鉄” や “撮り鉄”をおもな目的とした “鉄旅” に出かけることとしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。そのかわりに年末年始は遠出せず、のんびりと近場で過ごそう (。A。)アヒャ☆。
12月7日(木)
まだ夜明け前の早朝4時半に都内某所の自宅を出て (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…、JR中央線、地下鉄東西線、京成本線と路線を乗り継ぎ(これがウチから成田までの最安ルートw)、成田空港の第3ターミナル(LCC専用ターミナル)に着いたのは7時半 ( ̄  ̄*)ナリタ。
羽田空港に比べたらもちろん遠さは否めないけど、この成田までの手間や不便さが航空運賃の安さに反映されているのだと思えば納得でしょうか (-`ω´-*)ウム。
「え、お正月?おほほほ、もちろんハワイよ (´∇ノ`*)オホホホホ」
・・・な〜んてことはまずないけど、鉄道が好きな “鉄ちゃん” の私としては休み中に泊りがけで、“乗り鉄” や “撮り鉄”などを楽しむ “鉄旅”(鉄道の旅)にお出かけしたいと考えます ( ̄▽ ̄*)テツタビ。
駄菓子菓子(だがしかし)、帰省や旅行などで多くの人たちがいっせいに移動する年末年始は当然ながら、飛行機も新幹線も大混雑が必至でチケット(航空券・指定券)が取りにくいし、ホテルなどの宿泊施設はどこも“強気”な高価格の設定となっています ( ̄  ̄;)タカスギクン…。
相次ぐ値上げで物価高をひしひしと感じる昨今に加え、ただでさえ物入りが多い時期(忘年会や新年会のお誘いなどもw)、あくまでも“趣味”の範ちゅうである鉄旅の費用はなるべく抑えたいもの。そうすると年末年始のハイシーズン(繁忙期)に旅行へ出かけるのはキビシいか σ(・∀・`)ウーン…。
でもなぁ・・・私には今年(2023年)やり残したというか、できれば年内に行きたいところがあるんですよね。
んー、それならば何も年末年始の休みじゃなくていいんじゃない? (*゚o゚)ハッ!
紅葉の行楽シーズンがおおむね落ち着き、学生の冬休みが始まる前の狭間となる12月の上旬は例年、比較的旅行者が少ないとされる “閑散期” のひとつで、この時期の交通機関はすいているし、宿泊施設なども価格を安めに設定しています (。-∀-)ホゥ(最近はインバウンドの増加で必ずしもそうではないけど)。
ためしに運賃を変動制としている(日や便によって異なる)格安航空会社(LCC)のサイトを適当にチェックしてみたところ \_ヘヘ(- ̄*)ドレドレ、やはり12月の第二週目の平日(12/4〜8)ならば、私が行きたい地域への航空運賃が最安値で片道なんと4,000円台!(゚∀゚)オッ!。また、某ビジネスホテルチェーンのお部屋も年末年始に比べて半額に近いお値段で泊まれるじゃありませんか! (゚∀゚*)オオッ!!。
「社長、やすい、やすぅ〜い♡ 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。」
この安さを目の当たりにした勢いで往復の航空便と宿泊の予約したのが、今からひと月半前にあたる10月下旬のこと。そのころの私は仕事が多忙で休日出勤もあったため代休が何日か溜まっており、それをおトクな “閑散期” に振り替えて活用しちゃいましょう ъ(゚Д゚)ナイス。
前置きが長くなりましたが、そんなワケで今冬の私は年末年始でなく、12月上旬の平日である7日の木曜日から、“乗り鉄” や “撮り鉄”をおもな目的とした “鉄旅” に出かけることとしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。そのかわりに年末年始は遠出せず、のんびりと近場で過ごそう (。A。)アヒャ☆。
12月7日(木)
まだ夜明け前の早朝4時半に都内某所の自宅を出て (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…、JR中央線、地下鉄東西線、京成本線と路線を乗り継ぎ(これがウチから成田までの最安ルートw)、成田空港の第3ターミナル(LCC専用ターミナル)に着いたのは7時半 ( ̄  ̄*)ナリタ。
羽田空港に比べたらもちろん遠さは否めないけど、この成田までの手間や不便さが航空運賃の安さに反映されているのだと思えば納得でしょうか (-`ω´-*)ウム。
三鷹0440-(中央416H)-中野0452~0500-(東京メトロ東西線A513S)-西船橋0552…京成西船0604-(京成本線527)-空港第2ビル0701
福岡ゆきのジェットスター505便(GK505)は定刻の8時20分に成田空港を出発し、快晴の空を西のほうへ向かって飛び立ちました ⊂ニニニ(^ω^)ニニニ⊃ブーン。
そう、飛行機の行き先が示すとおり、今回の私がめぐる旅先は九州です (゚ー゚*)キューシュー。
なお本記事の冒頭にて、予約時の航空運賃の最安値が “4,000円台” と記していますが、その価格なのは早朝の6時に成田を出発するような、ふつうではちょっと利用しにくい便(GK501)であり、私が自宅からでも間に合う8時台の便は“最安”でなく片道5,580円でした。それでもこの運賃で福岡まで飛べちゃうならじゅうぶんに安くてありがたい 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。
列車での鉄旅だとほとんど眠らない私ですが飛行機では爆睡し、二時間半ほどのフライトはあっという間でした (・ω・)トーチャコ。
成田0820-(ジェットスターGK505)-福岡1040
そう、飛行機の行き先が示すとおり、今回の私がめぐる旅先は九州です (゚ー゚*)キューシュー。
なお本記事の冒頭にて、予約時の航空運賃の最安値が “4,000円台” と記していますが、その価格なのは早朝の6時に成田を出発するような、ふつうではちょっと利用しにくい便(GK501)であり、私が自宅からでも間に合う8時台の便は“最安”でなく片道5,580円でした。それでもこの運賃で福岡まで飛べちゃうならじゅうぶんに安くてありがたい 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。
列車での鉄旅だとほとんど眠らない私ですが飛行機では爆睡し、二時間半ほどのフライトはあっという間でした (・ω・)トーチャコ。
成田0820-(ジェットスターGK505)-福岡1040
福岡の空港と市内中心部をむすぶ
福岡市地下鉄の空港線。
(゚ー゚*)チカテツ
福岡空港駅の地下ホームに待機していたのは
1981年の当線開業時から使われている
ベテラン形式の1000系です。
▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 福岡空港
ちなみにこの1000系は
日本の地下鉄車両で初となる
ワンマン運転対応車であることが評価され
ローレル賞(1982年度)を受賞しています。
( ̄。 ̄)ヘー
なお先日には当系を置き換える
新形式車両の投入が発表されました。
福岡市地下鉄の空港線。
(゚ー゚*)チカテツ
福岡空港駅の地下ホームに待機していたのは
1981年の当線開業時から使われている
ベテラン形式の1000系です。
▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 福岡空港
ちなみにこの1000系は
日本の地下鉄車両で初となる
ワンマン運転対応車であることが評価され
ローレル賞(1982年度)を受賞しています。
( ̄。 ̄)ヘー
なお先日には当系を置き換える
新形式車両の投入が発表されました。
国内の都市にある空港のなかで最も便利なところに立地し、アクセス的にも優れているのではないかと個人的に思う福岡空港。
郊外の空港から街なかまで連絡バスで数十分や一時間もかかるようなところも多いなか、当空港はターミナルビルと直結した地下に位置する福岡空港駅より福岡市地下鉄の空港線に乗れば、JR九州の各線が発着する博多まで5分、繁華街の中州や天神までも10分程度の乗車時間で行くことができます (・∀・)イイネ。
そんな地下鉄空港線に私は数えきれないくらいお世話になっていますが、いつも鉄旅を目的に福岡を訪れる場合はすぐにJRへと乗り換えるため、福岡空港(駅)からわずか二駅だけ乗って博多で下車するパターンが多い ( ̄  ̄*)ハカタ。
しかし今回の私は博多で降りることなく、さらに中洲川端、天神も通り過ぎて、福岡空港から乗った筑前前原(ちくぜんまえばる)ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。
いったいどこへ向かっているのか・・・
郊外の空港から街なかまで連絡バスで数十分や一時間もかかるようなところも多いなか、当空港はターミナルビルと直結した地下に位置する福岡空港駅より福岡市地下鉄の空港線に乗れば、JR九州の各線が発着する博多まで5分、繁華街の中州や天神までも10分程度の乗車時間で行くことができます (・∀・)イイネ。
そんな地下鉄空港線に私は数えきれないくらいお世話になっていますが、いつも鉄旅を目的に福岡を訪れる場合はすぐにJRへと乗り換えるため、福岡空港(駅)からわずか二駅だけ乗って博多で下車するパターンが多い ( ̄  ̄*)ハカタ。
しかし今回の私は博多で降りることなく、さらに中洲川端、天神も通り過ぎて、福岡空港から乗った筑前前原(ちくぜんまえばる)ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。
いったいどこへ向かっているのか・・・
福岡市西区に所在する
高架駅の姪浜。
ここが地下鉄空港線の終点ですが
私が乗っている筑前前原ゆきは
当駅からさらに先へ進みます。
...(((o*・ω・)o
▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 姪浜
(車窓から)
高架駅の姪浜。
ここが地下鉄空港線の終点ですが
私が乗っている筑前前原ゆきは
当駅からさらに先へ進みます。
...(((o*・ω・)o
▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 姪浜
(車窓から)
あらためてご紹介すると福岡市地下鉄(福岡市交通局)空港線は先のとおり、福岡空港(駅)から博多、中洲川端、天神、唐人町(とうじんまち)、西新(にしじん)など福岡市中心部の各駅を経て、同市西区の姪浜(めいのはま)にいたる全長13.1キロの地下鉄路線(なお路線起点は姪浜)(゚ー゚*)チカテツ。
なお当線は姪浜を介して当駅を起点とするJRの筑肥線(ちくひせん)との相互直通運転が行なわれており、基本的に日中は糸島市の筑前前原まで、朝夕の通勤時間帯には佐賀県唐津市の西唐津(にしからつ)まで乗り入れています (・o・*)ホホゥ(ただし福岡市地下鉄の車両は筑前前原までの運用。また唐津〜西唐津の区間は正式には唐津線)。
実はその地下鉄が直通する先の筑肥線こそ、九州を訪れた私の今旅における最初の目的路線であり、そのため博多でも天神でも下車せずに乗り続けたのでした (´ω`)ナルヘソ。
福岡空港から福岡市内を西進し、およそ50分で筑前前原に着きます。
なお当線は姪浜を介して当駅を起点とするJRの筑肥線(ちくひせん)との相互直通運転が行なわれており、基本的に日中は糸島市の筑前前原まで、朝夕の通勤時間帯には佐賀県唐津市の西唐津(にしからつ)まで乗り入れています (・o・*)ホホゥ(ただし福岡市地下鉄の車両は筑前前原までの運用。また唐津〜西唐津の区間は正式には唐津線)。
実はその地下鉄が直通する先の筑肥線こそ、九州を訪れた私の今旅における最初の目的路線であり、そのため博多でも天神でも下車せずに乗り続けたのでした (´ω`)ナルヘソ。
福岡空港から福岡市内を西進し、およそ50分で筑前前原に着きます。
車内に掲げられていた路線図。
(クリックすると別ウインドウで
拡大表示されます)
真ん中に表記された路線が
福岡市地下鉄空港線(福岡空港〜姪浜)と
JR筑肥線(姪浜〜西唐津)で
両線は直通運転が行なわれています。
(*゚ェ゚)フムフム
筑前前原で唐津ゆきに乗り換え。
短い3両編成の電車が
ホームの中央で発車を待っています。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
▲23.12.7 筑肥線 筑前前原
(クリックすると別ウインドウで
拡大表示されます)
真ん中に表記された路線が
福岡市地下鉄空港線(福岡空港〜姪浜)と
JR筑肥線(姪浜〜西唐津)で
両線は直通運転が行なわれています。
(*゚ェ゚)フムフム
筑前前原で唐津ゆきに乗り換え。
短い3両編成の電車が
ホームの中央で発車を待っています。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
▲23.12.7 筑肥線 筑前前原
日中は地下鉄からの直通列車が終点となる筑前前原 (゚ー゚*)バル。
筑肥線は当駅を境にして運行体系が変わり、これまで乗ってきた地下鉄直通列車は6両編成がおよそ10分から15分間隔くらいで運行されていたのに対し、ここから乗り継ぐ唐津ゆき普通列車は3両編成が30分間隔となり、また線路も複線から単線となるため、一気にローカル線らしい趣きが漂うようになります (´ー`)ローカル。
そんな筑前前原と唐津(西唐津)のあいだの区間運用でおもに使われている電車が、昭和の国鉄時代に製造された、いわゆる“国鉄型車両”の103系です ( ̄  ̄)コクデン。
筑肥線は当駅を境にして運行体系が変わり、これまで乗ってきた地下鉄直通列車は6両編成がおよそ10分から15分間隔くらいで運行されていたのに対し、ここから乗り継ぐ唐津ゆき普通列車は3両編成が30分間隔となり、また線路も複線から単線となるため、一気にローカル線らしい趣きが漂うようになります (´ー`)ローカル。
そんな筑前前原と唐津(西唐津)のあいだの区間運用でおもに使われている電車が、昭和の国鉄時代に製造された、いわゆる“国鉄型車両”の103系です ( ̄  ̄)コクデン。
え?これがヒャクサン(103系)!? (=゚ω゚=*)ンン!?
鉄道に詳しいかたか、もしくは年齢がある程度は上のかた(昭和生まれ?)ならば、その形式を聞いてなんとなく姿が思い浮かぶかもしれませんが (゚・゚*)ンー…、103系は国鉄の通勤型電車である “国電” の代名詞的な存在の車両で、かつては首都圏の山手線や京浜東北線、関西圏の大阪環状線や奈良線など、それぞれ色分けされて多くの路線に使われていたもの (´ω`)ナツカシス。ちなみに今年の春には兵庫の和田岬線から引退した当系が大きな話題になりましたっけ (uдu*)ゥンゥン。
その103系のデザインといえばシンプルな顔立ちで、オデコ(前面上部)に備えられた丸いヘッドライト(前灯)が特徴のひとつとされているのですが、いま停まっている筑肥線の103系はそれとは異なって別の形式に見える印象です (゚ー゚?)オヨ?。
しかしこれもれっきとした103系のひとつ (ー`дー´)ヒャクサン。
鉄道に詳しいかたか、もしくは年齢がある程度は上のかた(昭和生まれ?)ならば、その形式を聞いてなんとなく姿が思い浮かぶかもしれませんが (゚・゚*)ンー…、103系は国鉄の通勤型電車である “国電” の代名詞的な存在の車両で、かつては首都圏の山手線や京浜東北線、関西圏の大阪環状線や奈良線など、それぞれ色分けされて多くの路線に使われていたもの (´ω`)ナツカシス。ちなみに今年の春には兵庫の和田岬線から引退した当系が大きな話題になりましたっけ (uдu*)ゥンゥン。
その103系のデザインといえばシンプルな顔立ちで、オデコ(前面上部)に備えられた丸いヘッドライト(前灯)が特徴のひとつとされているのですが、いま停まっている筑肥線の103系はそれとは異なって別の形式に見える印象です (゚ー゚?)オヨ?。
しかしこれもれっきとした103系のひとつ (ー`дー´)ヒャクサン。
先述の福岡市地下鉄空港線との直通運転開始(および姪浜〜唐津の電化)にあわせて1982年に新製された筑肥線用の103系は、1963年に製造が開始された同系の “最終形態” といえるもので ( ̄  ̄*)ラストロット、制御装置や台車などの走行機器類は従来の103系と同様にしたものの、車体のデザインは同時期に製造が進められていた105系や119系(前面)、201系(側面や車内)に似たようなものとなり ( ̄▽ ̄)クリソツ、また地下鉄線に直通する特殊用途であることから、103系のなかで “1500番台” に区分けされました ( ̄。 ̄)ヘー。
そんな筑肥線の103系1500番台は現在、地下鉄直通列車の運用を後輩にあたる303系や305系に委ねて自身は退き、短編成化されて筑前前原以西のローカル運用を担っています (´ー`)ローカル。1500番台はちょっと異色な印象の103系ではあるけれど、これもまた今や貴重な国鉄型車両の生き残りであり、国電好きの私が興味を惹かれる存在 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そこで九州へやってきた目的のひとつとして、きょうはこの103系1500番台を筑肥線の沿線で撮影したいと思います (・∀・)イイネ。
しかも、私が乗った唐津ゆき下り列車と途中の駅で交換した(行き違った)、筑前前原ゆき上り列車は・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
しかも、私が乗った唐津ゆき下り列車と途中の駅で交換した(行き違った)、筑前前原ゆき上り列車は・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
青いのキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
赤い顔でなく “爽やかな水色の103系” が、反対のホームに停まっているではありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。
これは筑肥線の「電化40周年」および「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して、当線で使われる103系1500番台のうちの一本(E12編成)にデビューした当時のカラーリングを再現した、いわゆる “復刻色” ってヤツです (*゚ー゚)リバイバル。現在の同系の標準色(現行色)はJR九州のコーポレートカラーである赤い色ですが、国鉄時代は筑肥線から望める玄界灘の海をイメージしたといわれる水色(青22号)に塗られていました ( ̄。 ̄)ヘー。
今旅で私が筑肥線へ撮影に行くならば、この復刻色の “青い1500番台” に運用が当たるといいな・・・と期待を持っていたところ(とくに運用は公表されていない)、運良く当該編成を引き当てることができたみたいです。これは沿線での撮影を前にテンションの上がる嬉しい展開 (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみに筑肥線の103系は現在の在籍数が5編成、それに対して日中の稼働は3運用のようなので、単純に考えれば復刻色の一本が運用に就く確率は60パーセントということになります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
それにしても私ってば我ながら思うに、復刻色や復刻運転などの “リバイバルもの” が好きだよなぁ(笑)。それだけ昔を懐かしむ歳になったということか (^^;)ゞポリポリ。
赤い顔でなく “爽やかな水色の103系” が、反対のホームに停まっているではありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。
これは筑肥線の「電化40周年」および「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して、当線で使われる103系1500番台のうちの一本(E12編成)にデビューした当時のカラーリングを再現した、いわゆる “復刻色” ってヤツです (*゚ー゚)リバイバル。現在の同系の標準色(現行色)はJR九州のコーポレートカラーである赤い色ですが、国鉄時代は筑肥線から望める玄界灘の海をイメージしたといわれる水色(青22号)に塗られていました ( ̄。 ̄)ヘー。
今旅で私が筑肥線へ撮影に行くならば、この復刻色の “青い1500番台” に運用が当たるといいな・・・と期待を持っていたところ(とくに運用は公表されていない)、運良く当該編成を引き当てることができたみたいです。これは沿線での撮影を前にテンションの上がる嬉しい展開 (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみに筑肥線の103系は現在の在籍数が5編成、それに対して日中の稼働は3運用のようなので、単純に考えれば復刻色の一本が運用に就く確率は60パーセントということになります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
それにしても私ってば我ながら思うに、復刻色や復刻運転などの “リバイバルもの” が好きだよなぁ(笑)。それだけ昔を懐かしむ歳になったということか (^^;)ゞポリポリ。
筑前(福岡県)と肥前(佐賀県)を結ぶことを線名の由来とする筑肥線は、福岡市地下鉄の空港線と接する姪浜から、今宿(いまじゅく)、周船寺(すせんじ)、筑前前原、筑前深江(ちくぜんふかえ)、福吉(ふくよし)、浜崎、虹ノ松原(にじのまつばら)などを経て、唐津にいたる42.6キロの直流電化区間、および唐津市の山本から伊万里(いまり)にいたる25.7キロの非電化区間からなる路線 (・o・*)ホホゥ。
もともと当線は博多から東唐津を経て伊万里へといたる一本の路線でしたが、博多と姪浜の区間は地下鉄空港線に引き替えられる形で1983年に廃止され、また同時期に電化開業と合わせて唐津市内の利便性を考慮した経路変更が行われ(虹ノ松原〜山本の廃止と虹ノ松原〜唐津の開通)、現在は二つの区間に分断された珍しい形態の路線となっています(なお唐津と山本のあいだは分断前の筑肥線とは別ルートに既存していた唐津線でむすばれている)( ´_ゝ`)フーン。
このようにいろいろと複雑な経緯で面白い歴史を持つ筑肥線ですが、今旅では電化区間で使われる103系を沿線で記録することが目的のため、あえて非電化区間のほうは話題から省かせていただきます(ちなみに私は筑肥線の旧線時代に乗ったことはないけど、「時刻表2万キロ」の筑肥線と唐津線の話は好きw)。
もともと当線は博多から東唐津を経て伊万里へといたる一本の路線でしたが、博多と姪浜の区間は地下鉄空港線に引き替えられる形で1983年に廃止され、また同時期に電化開業と合わせて唐津市内の利便性を考慮した経路変更が行われ(虹ノ松原〜山本の廃止と虹ノ松原〜唐津の開通)、現在は二つの区間に分断された珍しい形態の路線となっています(なお唐津と山本のあいだは分断前の筑肥線とは別ルートに既存していた唐津線でむすばれている)( ´_ゝ`)フーン。
このようにいろいろと複雑な経緯で面白い歴史を持つ筑肥線ですが、今旅では電化区間で使われる103系を沿線で記録することが目的のため、あえて非電化区間のほうは話題から省かせていただきます(ちなみに私は筑肥線の旧線時代に乗ったことはないけど、「時刻表2万キロ」の筑肥線と唐津線の話は好きw)。
車窓に玄界灘の海を映して走る
筑肥線の普通列車。
う〜ん、快晴の海景色が気持ちいい。
(´▽`*)イイテンキ♪
▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉
(車窓から)
車内がガラガラに空いていたので
窓枠を額縁に見立ててパチリ。
(^_[◎]oパチリ
このように窓枠が十字の車両も
今じゃ減ったよなぁ・・・。
▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉
(車窓から)
筑肥線の普通列車。
う〜ん、快晴の海景色が気持ちいい。
(´▽`*)イイテンキ♪
▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉
(車窓から)
車内がガラガラに空いていたので
窓枠を額縁に見立ててパチリ。
(^_[◎]oパチリ
このように窓枠が十字の車両も
今じゃ減ったよなぁ・・・。
▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉
(車窓から)
お顔は105系、車内は201系だけど、走行時に唸らすモーターや停車時に響かせるアイドリングの音は間違いなく103系のもの ヒャクサン( ̄- ̄ 3゛。そんな1500番台の車窓に広がる玄界灘の海景色を眺めながら西進を続け、やがて到着した下車駅は鹿家(しかか)(・ω・)トーチャコ。
福岡空港1107-(福岡市空港線473C)-筑前前原1153~1210-(筑肥345C)-鹿家1240
佐賀との県境近くに位置し、福岡県最西端の駅である糸島市の鹿家。駅名にもなっている地域名(二丈鹿家)の由来はわからないけど、“しかか” と書かれた駅名標の平仮名表記が何だかかわいい (・∀・)シカカ。
海辺に近い当駅はそこから直視で海は見えないものの、ほんのりと潮の匂いが漂います (´ω`)ウミ。周囲がそんな環境なら海景色で筑肥線の列車が撮れるのではないかと思い、事前に近隣の撮影ポイントをいくつか下調べしておきましたが \_ヘヘ(- ̄*)チェック、まずは先ほど途中駅で行き違った(交換した)復刻色の青い103系が次の西唐津ゆき下り列車として30分後にはやってくるので、とりあえず調べたなかでいちばん駅に近い撮影地へ向かうことにします ...(((o*・ω・)o。
佐賀との県境近くに位置し、福岡県最西端の駅である糸島市の鹿家。駅名にもなっている地域名(二丈鹿家)の由来はわからないけど、“しかか” と書かれた駅名標の平仮名表記が何だかかわいい (・∀・)シカカ。
海辺に近い当駅はそこから直視で海は見えないものの、ほんのりと潮の匂いが漂います (´ω`)ウミ。周囲がそんな環境なら海景色で筑肥線の列車が撮れるのではないかと思い、事前に近隣の撮影ポイントをいくつか下調べしておきましたが \_ヘヘ(- ̄*)チェック、まずは先ほど途中駅で行き違った(交換した)復刻色の青い103系が次の西唐津ゆき下り列車として30分後にはやってくるので、とりあえず調べたなかでいちばん駅に近い撮影地へ向かうことにします ...(((o*・ω・)o。
駅から姪浜方向へ歩いて10分ほど、坂を上がった小高い丘の道からは筑肥線の線路と海が確認できます (゚∀゚)オッ!。
海原が景色の一面にどーんと広がるようなダイナミックさはなく、昼過ぎという今の時間帯は日あたりの光線状態も微妙な感じだけど、後続の列車に間にあう駅近のお手軽な場所だと考えれば悪くないといったところか σ(゚・゚*)ンー…。
海の写し込みかたを模索しながらアングルを調整していると、まもなく青い電車が姿を現しました ε-(°ω°*)キタッ!。
海原が景色の一面にどーんと広がるようなダイナミックさはなく、昼過ぎという今の時間帯は日あたりの光線状態も微妙な感じだけど、後続の列車に間にあう駅近のお手軽な場所だと考えれば悪くないといったところか σ(゚・゚*)ンー…。
海の写し込みかたを模索しながらアングルを調整していると、まもなく青い電車が姿を現しました ε-(°ω°*)キタッ!。
青い1500番台が撮れました〜!ヽ(´▽`)ノワーイ♪
海岸に沿った筑肥線らしい線形の緩やかなカーブを走りゆく、国鉄復刻色の青い103系 (゚ー゚*)アオ。
正直なところ関東人の私にとって筑肥線は馴染みが浅く、復刻色を見ても懐かしいという印象は薄いのですが、現在のJR九州の車両ではあまり見ないような淡い青色(青22号)の車体色はどこか、穏やかな景色にしっくりとマッチする落ち着いた雰囲気を感じます (´ー`)マターリ。
アングル的に見ると、やはり車体の手前側面に日の光はほとんど当たらず(この場所は午前が順光)、また、背景の海の入れ方や、線路の手前にある雑草の処理などいろいろと迷ったあげく (´〜`)ウーン、列車の置き位置(シャッターを切る位置)がどうも決めきれず、真ん中の架線柱を挟んでその手前とあとの二枚切り パチャ【◎】]ω・´)パチャ。一枚目と二枚目のどちらも一長一短な感じがして、結局いまだにどちらが正解なのか(もしくはもっと最善の撮り方があったのか)よくわからないカットとなりました (^^;)ゞポリポリ。それでも海バックで復刻色を撮れたのは嬉しい収穫 (+`゚∀´)=b OK牧場!。
唐津方面へと走り去ってゆく復刻色を見送ったのち、このあとも引き続き鹿家の界隈にて別の撮影ポイントへ歩いて移動します ...(((o*・ω・)o。
海岸に沿った筑肥線らしい線形の緩やかなカーブを走りゆく、国鉄復刻色の青い103系 (゚ー゚*)アオ。
正直なところ関東人の私にとって筑肥線は馴染みが浅く、復刻色を見ても懐かしいという印象は薄いのですが、現在のJR九州の車両ではあまり見ないような淡い青色(青22号)の車体色はどこか、穏やかな景色にしっくりとマッチする落ち着いた雰囲気を感じます (´ー`)マターリ。
アングル的に見ると、やはり車体の手前側面に日の光はほとんど当たらず(この場所は午前が順光)、また、背景の海の入れ方や、線路の手前にある雑草の処理などいろいろと迷ったあげく (´〜`)ウーン、列車の置き位置(シャッターを切る位置)がどうも決めきれず、真ん中の架線柱を挟んでその手前とあとの二枚切り パチャ【◎】]ω・´)パチャ。一枚目と二枚目のどちらも一長一短な感じがして、結局いまだにどちらが正解なのか(もしくはもっと最善の撮り方があったのか)よくわからないカットとなりました (^^;)ゞポリポリ。それでも海バックで復刻色を撮れたのは嬉しい収穫 (+`゚∀´)=b OK牧場!。
唐津方面へと走り去ってゆく復刻色を見送ったのち、このあとも引き続き鹿家の界隈にて別の撮影ポイントへ歩いて移動します ...(((o*・ω・)o。
海沿いの国道を西の方へ。
歩道が備えられていない箇所も多いので
海に気を取られて注意がおろそかにならぬよう
クルマに気を付けなきゃ。
お、県境。
「佐賀県だ、ぴょ〜ん!」
(わかる人にはわかる県境越えのフレーズw)
ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩
鹿家から歩いて30分くらい。
次にやってきたのはこんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
海岸に沿って筑肥線の列車が走ります。
通過していったのは上りの筑前前原ゆき。
でも、真ん中には車道があって
ちょっと撮りにくそう?
σ(゚・゚*)ンー…
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
歩道が備えられていない箇所も多いので
海に気を取られて注意がおろそかにならぬよう
クルマに気を付けなきゃ。
お、県境。
「佐賀県だ、ぴょ〜ん!」
(わかる人にはわかる県境越えのフレーズw)
ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩
鹿家から歩いて30分くらい。
次にやってきたのはこんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
海岸に沿って筑肥線の列車が走ります。
通過していったのは上りの筑前前原ゆき。
でも、真ん中には車道があって
ちょっと撮りにくそう?
σ(゚・゚*)ンー…
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
鹿家駅近くの撮影地をあとにして、海岸に沿った国道を西の方へしばらく進むと、やがて県境をまたいで福岡県糸島市から佐賀県唐津市へと入ります |フクオカ|…((((o* ̄-)o|サガ|。ここでパッと景色などが変わるわけではないけど、歩いて越境するのは何となく特別な気分 ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩。
そんな県境近くに位置するのが次なる撮影ポイントで、このあたりは歩いてきた国道と並行して筑肥線の線路が海岸沿いに敷かれています (・o・*)ホホゥ。ただし、ためしに当地へ着いて撮ってみた上り列車の写真を見るとわかるとおり (^_[◎]oパチリ、たしかに列車と海をひとつのフレームに収めることはできるけど、線路と海のあいだには車道や歩道があって、たまたまクルマが通らなかったもののアングル的に落ち着かない感じ ( ̄  ̄;)ビミョー。
でも、ここで私がカメラのレンズを向けるのは、立ち位置の右手にあたる線路のほうでなく、左手に広がる海のほう (゚ー゚*)ウミ。そのアングルでもう一度シャッターを切ると・・・【◎】]ω・)パチャ
そんな県境近くに位置するのが次なる撮影ポイントで、このあたりは歩いてきた国道と並行して筑肥線の線路が海岸沿いに敷かれています (・o・*)ホホゥ。ただし、ためしに当地へ着いて撮ってみた上り列車の写真を見るとわかるとおり (^_[◎]oパチリ、たしかに列車と海をひとつのフレームに収めることはできるけど、線路と海のあいだには車道や歩道があって、たまたまクルマが通らなかったもののアングル的に落ち着かない感じ ( ̄  ̄;)ビミョー。
でも、ここで私がカメラのレンズを向けるのは、立ち位置の右手にあたる線路のほうでなく、左手に広がる海のほう (゚ー゚*)ウミ。そのアングルでもう一度シャッターを切ると・・・【◎】]ω・)パチャ
唐津湾の海辺を進む
現行色の103系1500番台。
その赤い顔が晴天の海景色に映えます。
ひとつ上の写真で撮った上り列車を
遠景で追ってみました。
(^_[◎]oパチリ
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
現行色の103系1500番台。
その赤い顔が晴天の海景色に映えます。
ひとつ上の写真で撮った上り列車を
遠景で追ってみました。
(^_[◎]oパチリ
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
浜が入り組んだ海岸の先には、さっき真横(国道の脇)を通過した上り列車の姿が海越しにふたたび確認できます (゚∀゚)オッ!。こちらのアングルは海を広く入れることができて、なかなか爽快じゃありませんか (・∀・)イイネ。
そう、この場所を撮影地に選んだ私の狙いは、海越しとなるこちらのアングルです (-`ω´-*)ウム。ここでも例の “青い復刻色”(E12編成)を待ってみましょう (゚ー゚*)アオ。
なお、当該編成は私がのんびりと歩いているあいだに西唐津から筑前前原のほうへ上っており、次にやってくるのはその折り返しとなる下り列車(西唐津ゆき)です。
そう、この場所を撮影地に選んだ私の狙いは、海越しとなるこちらのアングルです (-`ω´-*)ウム。ここでも例の “青い復刻色”(E12編成)を待ってみましょう (゚ー゚*)アオ。
なお、当該編成は私がのんびりと歩いているあいだに西唐津から筑前前原のほうへ上っており、次にやってくるのはその折り返しとなる下り列車(西唐津ゆき)です。
海越しに青いヤツが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
空と海に挟まれて、車体もブルーに染まっちゃったような復刻色の103系1500番台。壮大な情景にちんまりと収まった青い電車がカワイイじゃないですか (*’∀’*)カワユス♪。ちなみに背景に望める島のようなものは糸島半島で、それもまた絵のなかでいいアクセントとなっています。ああ、気持ちのいい眺めだなぁ (´ー`)マターリ。
本記事の冒頭で触れたとおり、私が事前に格安の航空券を手配して今旅を計画したのは、さかのぼることひと月半前の10月下旬。当然ながらその頃に旅行当日の天候がわかるはずなく、空模様はまさに天まかせの運次第ってところでしたが 八(゚- ゚)オネガイ、きょうはスッキリと晴れわたった絶好の “撮り鉄日和” で、さらに復刻色の運用にも当たり、私が望んでいた最高の条件に恵まれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。これはもうホントに、はるばる九州まで来た甲斐があったというものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
おっと、しみじみと喜びをかみしめている場合じゃなく (*`ロ´)ハッ!、海越しの遠景で下り列車を撮ったあとはすぐに、クルマの通行状況を注意深く確認しつつ道路を横断し コッチ…((((o* ̄-)o、続けて今度は線路脇にてカメラを構えます。
空と海に挟まれて、車体もブルーに染まっちゃったような復刻色の103系1500番台。壮大な情景にちんまりと収まった青い電車がカワイイじゃないですか (*’∀’*)カワユス♪。ちなみに背景に望める島のようなものは糸島半島で、それもまた絵のなかでいいアクセントとなっています。ああ、気持ちのいい眺めだなぁ (´ー`)マターリ。
本記事の冒頭で触れたとおり、私が事前に格安の航空券を手配して今旅を計画したのは、さかのぼることひと月半前の10月下旬。当然ながらその頃に旅行当日の天候がわかるはずなく、空模様はまさに天まかせの運次第ってところでしたが 八(゚- ゚)オネガイ、きょうはスッキリと晴れわたった絶好の “撮り鉄日和” で、さらに復刻色の運用にも当たり、私が望んでいた最高の条件に恵まれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。これはもうホントに、はるばる九州まで来た甲斐があったというものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
おっと、しみじみと喜びをかみしめている場合じゃなく (*`ロ´)ハッ!、海越しの遠景で下り列車を撮ったあとはすぐに、クルマの通行状況を注意深く確認しつつ道路を横断し コッチ…((((o* ̄-)o、続けて今度は線路脇にてカメラを構えます。
もういっちょ、青いヤツが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
一粒で二度おいしい(?)、この撮影ポイント (゚ー゚*)グリコ?。海越しの遠景で撮ったあとには、線路脇からの近景で列車を主体とした “編成写真” も抑えることができました【◎】]ω・´)パチッ!。
最初に鹿家の駅近くで撮ったものと、ここで海越しの遠景で撮ったもの、そのどちらのカットも風景のなかに列車を収めた情景的なアングルで、車両の細かいところまではわかりにくかったですが σ(゚・゚*)ンー…、あらためて編成写真を見てみると、国鉄色の復刻とともに前面の右上(オデコのあたり)には国鉄のエンブレムである“JNRマーク”(JNR=Japanese National Railwaysの略)もしっかりと再現されており、それが燦然と輝いています 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
また、この進行方向で編成の先頭に立つのは、国鉄時代の新製時には存在しなかった形式区分で、のちの短編成化により中間電動車(モハ)から先頭車へ改造されて誕生した制御電動車の “クモハ” ですが ( ̄  ̄*)クモハ、その床下にずらっと並んだ箱のような抵抗器(自然通風式)が国電好き(そのなかでもとくに地下鉄直通車好き)の私としては “萌えポイント” で、超マニアックだけどそこがよくわかるように撮れたのは嬉しい記録となりました ъ(゚Д゚)ナイス。う〜ん、たまらん(笑)(*゚∀゚)=3ハァハァ!
一粒で二度おいしい(?)、この撮影ポイント (゚ー゚*)グリコ?。海越しの遠景で撮ったあとには、線路脇からの近景で列車を主体とした “編成写真” も抑えることができました【◎】]ω・´)パチッ!。
最初に鹿家の駅近くで撮ったものと、ここで海越しの遠景で撮ったもの、そのどちらのカットも風景のなかに列車を収めた情景的なアングルで、車両の細かいところまではわかりにくかったですが σ(゚・゚*)ンー…、あらためて編成写真を見てみると、国鉄色の復刻とともに前面の右上(オデコのあたり)には国鉄のエンブレムである“JNRマーク”(JNR=Japanese National Railwaysの略)もしっかりと再現されており、それが燦然と輝いています 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
また、この進行方向で編成の先頭に立つのは、国鉄時代の新製時には存在しなかった形式区分で、のちの短編成化により中間電動車(モハ)から先頭車へ改造されて誕生した制御電動車の “クモハ” ですが ( ̄  ̄*)クモハ、その床下にずらっと並んだ箱のような抵抗器(自然通風式)が国電好き(そのなかでもとくに地下鉄直通車好き)の私としては “萌えポイント” で、超マニアックだけどそこがよくわかるように撮れたのは嬉しい記録となりました ъ(゚Д゚)ナイス。う〜ん、たまらん(笑)(*゚∀゚)=3ハァハァ!
次に上り列車としてやってきた
現行色の同系でも
床下の抵抗器を意識して撮ってみました。
(^_[◎]oパチリ
西日に光る赤とシルバーのカラーリングは
こうやってみると意外にカッコいい。
(・∀・)イイネ
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
現行色の同系でも
床下の抵抗器を意識して撮ってみました。
(^_[◎]oパチリ
西日に光る赤とシルバーのカラーリングは
こうやってみると意外にカッコいい。
(・∀・)イイネ
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
情景的な遠景、車両主体の近景、お目当ての復刻色をその両方のアングルで撮れたことにじゅうぶん満足ですが (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪、せっかく晴天の海景色という好条件なので、もうちょっと撮影を続けます。
次は浜辺に下りてみましょうか (o ̄∇ ̄o)ハマベミナミ。
次は浜辺に下りてみましょうか (o ̄∇ ̄o)ハマベミナミ。
“かき焼き”に“活車えび直売所”
このあたりの沿道には
何とも魅力的な看板が並んでますねw
(゚¬゚)ジュルリ
やってきたのはこんなところ。
夏には海水浴が楽しめそうな
きれいな砂浜です。
でも今は私の影だけがぽつん。
(・ω・)ポツン
だいぶ陽が傾きました。
このあたりの沿道には
何とも魅力的な看板が並んでますねw
(゚¬゚)ジュルリ
やってきたのはこんなところ。
夏には海水浴が楽しめそうな
きれいな砂浜です。
でも今は私の影だけがぽつん。
(・ω・)ポツン
だいぶ陽が傾きました。
今は〜 もう秋〜 だれも〜 いない海〜♪ θ( ̄0 ̄*)
暦の上ではもう冬なのですが、思わずそんな歌を口ずさみたくなるような、季節はずれの海岸(物語w)にやってきました (゚- ゚)ビーチ。
この場に不似合いな感じのごっつい望遠レンズを装着してカメラを構えていると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、端から見れば沖のほうにイルカでも現れるのかと思われそうですが ヾ(゚ω゚)イルカ?、私がファインダー越しに見つめる先に現れるのはもちろん “電車” です(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
暦の上ではもう冬なのですが、思わずそんな歌を口ずさみたくなるような、季節はずれの海岸(物語w)にやってきました (゚- ゚)ビーチ。
この場に不似合いな感じのごっつい望遠レンズを装着してカメラを構えていると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、端から見れば沖のほうにイルカでも現れるのかと思われそうですが ヾ(゚ω゚)イルカ?、私がファインダー越しに見つめる先に現れるのはもちろん “電車” です(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
唐津湾の一画で弧を描くように砂浜が伸びる浜崎海岸。
その波打ちぎわから東の方を向くと、私が鹿家からてくてく歩いてきた海沿いの国道とそれに並行した筑肥線の列車が望めて (「゚ー゚)ドレドレ、ここもまた海辺の鉄道情景を面白く撮れます (・o・*)ホホゥ。
まずは唐津のほうへ赤い現行色が下って行ったあと (゚ー゚*)アカ、今度は筑前前原のほうに上る青い復刻色の番 (゚ー゚*)アオ。
その波打ちぎわから東の方を向くと、私が鹿家からてくてく歩いてきた海沿いの国道とそれに並行した筑肥線の列車が望めて (「゚ー゚)ドレドレ、ここもまた海辺の鉄道情景を面白く撮れます (・o・*)ホホゥ。
まずは唐津のほうへ赤い現行色が下って行ったあと (゚ー゚*)アカ、今度は筑前前原のほうに上る青い復刻色の番 (゚ー゚*)アオ。
浜辺でも復刻色が撮れました〜 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
最初に現行色を撮ったアングルも私好みだけど、せっかくの貴重な復刻色ならばもうちょっと列車の存在感を強調したくて、前カットより手前の位置を走るところでシャッターを切ってみました (^_[◎]oパチリ 。西日が沿岸にキリッと浮き立たせたブルーの電車がいい雰囲気。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。運まかせと言える白波の形も悪くないタイミングで、浜辺の情景を素敵に演出してくれたと思います (・∀・)イイネ。
最初に現行色を撮ったアングルも私好みだけど、せっかくの貴重な復刻色ならばもうちょっと列車の存在感を強調したくて、前カットより手前の位置を走るところでシャッターを切ってみました (^_[◎]oパチリ 。西日が沿岸にキリッと浮き立たせたブルーの電車がいい雰囲気。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。運まかせと言える白波の形も悪くないタイミングで、浜辺の情景を素敵に演出してくれたと思います (・∀・)イイネ。
壮大な景色にちんまりと写る列車は
まるで鉄道模型のよう。
それを追ってもう一枚パチリ。
(^_[◎]oパチリ
打ち寄せる白波の表情が
画に動きを与えてくれました。
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
まるで鉄道模型のよう。
それを追ってもう一枚パチリ。
(^_[◎]oパチリ
打ち寄せる白波の表情が
画に動きを与えてくれました。
▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎
(後追い)
海岸線を走り去ってゆく青い電車を海越しに見送り、おもに復刻色の103系1500番台を狙った筑肥線の撮影はこれにて終了です (´w`*)ドツカレサン。
なお、来るときは鹿家で下車しましたが、そこからところどころで撮影をしつつ西へ向かって線路沿いを歩き進み、この海岸はもう次駅の浜崎のほうが近い位置となっていました σ(゚・゚*)ンー…。ならば帰りはそちらの駅を利用しましょう コッチ…((((o* ̄-)o。
なお、来るときは鹿家で下車しましたが、そこからところどころで撮影をしつつ西へ向かって線路沿いを歩き進み、この海岸はもう次駅の浜崎のほうが近い位置となっていました σ(゚・゚*)ンー…。ならば帰りはそちらの駅を利用しましょう コッチ…((((o* ̄-)o。
佐賀県唐津市東部の
浜玉町(旧・浜玉町)に所在する
筑肥線の浜崎。
(゚ー゚*)アユ
新しくてモダンな駅舎は
昨年(2022年)に改築されたばかりのものです。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
ちなみに海岸から駅までは
歩いて15分くらい(約1.2キロ)でした。
▲23.12.7 筑肥線 浜崎
新装駅舎のきれいなコンコースでは
「筑肥線の電化40周年」と
「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して
筑肥線の歴史を写真や資料などで紹介する
展示が行われていました。
(・o・*)ホホゥ
103系に復刻色が施されたのも
この記念企画の一環なんですよね。
その浜崎駅の近くから
西に向かって長く続いているのが
防風・防潮林として唐津湾沿いに植林された
“虹の松原”と呼ばれる松林。
全長約4.5キロにわたって続く松は、
約100万本と言われており
これはなかなか見ごたえがあります。
(*・`o´・*)ホ─
浜崎から東唐津へかけて
虹の松原に線路が沿っている筑肥線。
日が落ちた時間でもう薄暗いけど
オマケ程度にここでも
103系が撮れるかな?・・・と
ためしに列車を一本待ってみたら
やってきたのはおもに朝夕に設定され
西唐津と福岡空港の間をダイレクトにむすぶ
地下鉄直通運用の303系でした。
( ̄  ̄*)サンマルサン
▲23.12.7 筑肥線 虹ノ松原-浜崎
玄界灘の海の幸が豊富なご当地は
先ほどロードサイドで目にした
牡蛎や車海老なども魅力的ですが
唐津の名物といえばやっぱり
近隣の呼子(よぶこ)などで水揚げされる
天然のイカ(アオリイカなど)。
(゚¬゚*)イカニカン
・・・ということで
きょうの夕食はちょっと贅沢に
海鮮料理屋さんでイカ三昧!
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
いか刺しに、いか天、
いかワタ、いかしゅうまい・・・と
イカづくしを満喫です。
くコ:彡 イカ
新鮮で甘味が感じられる
アオリイカのお造りが絶品!
ふわふわのいかしゅうまいも美味しい♪
旬のご当地名物を味わえるって幸せだなぁ。
イカ(゚д゚)ウマー!
浜玉町(旧・浜玉町)に所在する
筑肥線の浜崎。
(゚ー゚*)アユ
新しくてモダンな駅舎は
昨年(2022年)に改築されたばかりのものです。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
ちなみに海岸から駅までは
歩いて15分くらい(約1.2キロ)でした。
▲23.12.7 筑肥線 浜崎
新装駅舎のきれいなコンコースでは
「筑肥線の電化40周年」と
「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して
筑肥線の歴史を写真や資料などで紹介する
展示が行われていました。
(・o・*)ホホゥ
103系に復刻色が施されたのも
この記念企画の一環なんですよね。
その浜崎駅の近くから
西に向かって長く続いているのが
防風・防潮林として唐津湾沿いに植林された
“虹の松原”と呼ばれる松林。
全長約4.5キロにわたって続く松は、
約100万本と言われており
これはなかなか見ごたえがあります。
(*・`o´・*)ホ─
浜崎から東唐津へかけて
虹の松原に線路が沿っている筑肥線。
日が落ちた時間でもう薄暗いけど
オマケ程度にここでも
103系が撮れるかな?・・・と
ためしに列車を一本待ってみたら
やってきたのはおもに朝夕に設定され
西唐津と福岡空港の間をダイレクトにむすぶ
地下鉄直通運用の303系でした。
( ̄  ̄*)サンマルサン
▲23.12.7 筑肥線 虹ノ松原-浜崎
玄界灘の海の幸が豊富なご当地は
先ほどロードサイドで目にした
牡蛎や車海老なども魅力的ですが
唐津の名物といえばやっぱり
近隣の呼子(よぶこ)などで水揚げされる
天然のイカ(アオリイカなど)。
(゚¬゚*)イカニカン
・・・ということで
きょうの夕食はちょっと贅沢に
海鮮料理屋さんでイカ三昧!
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
いか刺しに、いか天、
いかワタ、いかしゅうまい・・・と
イカづくしを満喫です。
くコ:彡 イカ
新鮮で甘味が感じられる
アオリイカのお造りが絶品!
ふわふわのいかしゅうまいも美味しい♪
旬のご当地名物を味わえるって幸せだなぁ。
イカ(゚д゚)ウマー!
混雑期の年末年始を避け、思い切って12月の上旬に出かけた九州の鉄旅 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。その初日に私が訪れたのは、飛行機が着陸した福岡空港から地下鉄を経てダイレクトにつながっているという筑肥線でした (゚ー゚*)チクヒセソ。
福岡市地下鉄との直通列車が頻繁に運行されている都市路線的な面を持つ区間から (`・ω・´)キリッ、途中の筑前前原を境にしてローカル線のようなのどかな風情が味わえる区間へと (´ー`)マターリ、変化する様子は “乗り鉄” 的に興味深く楽しめ (・∀・)イイネ、またそのローカル区間で最大の絶景スポットといえる玄界灘の海辺でカメラを構えた “撮り鉄” では (゚- ゚)ウミ、穏やかな好天のもとで青く染まる海とともに国電の生き残りである103系1500番台を赤い現行色と青い復刻色の両方が情景的に写せて (^_[◎]oパチリ、その撮影成果に大満足 ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。一本のみの“復刻色”がきょうの運用に就いていたのはホントに嬉しかったなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
とくにこれといったトラブルなく、天候と車両運用に恵まれた一日。本日の打ち上げで飲む酒は格別の美味しさでした(笑)〇○。(~▽~*)ウィッ
福岡市地下鉄との直通列車が頻繁に運行されている都市路線的な面を持つ区間から (`・ω・´)キリッ、途中の筑前前原を境にしてローカル線のようなのどかな風情が味わえる区間へと (´ー`)マターリ、変化する様子は “乗り鉄” 的に興味深く楽しめ (・∀・)イイネ、またそのローカル区間で最大の絶景スポットといえる玄界灘の海辺でカメラを構えた “撮り鉄” では (゚- ゚)ウミ、穏やかな好天のもとで青く染まる海とともに国電の生き残りである103系1500番台を赤い現行色と青い復刻色の両方が情景的に写せて (^_[◎]oパチリ、その撮影成果に大満足 ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。一本のみの“復刻色”がきょうの運用に就いていたのはホントに嬉しかったなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
とくにこれといったトラブルなく、天候と車両運用に恵まれた一日。本日の打ち上げで飲む酒は格別の美味しさでした(笑)〇○。(~▽~*)ウィッ
浜崎(浜玉)の町でじっくりとご当地の名物(イカ料理)を味わい、ほろ酔い気分で食事を終えたころにはすっかり暗くなっていました ( ̄  ̄*)マックラ。
浜崎から唐津までは筑肥線の下り列車に乗っておよそ10分ほど。きょうはその唐津に宿を予約しており、当地で一泊することとします (・∀・)イイネ。
浜崎から唐津までは筑肥線の下り列車に乗っておよそ10分ほど。きょうはその唐津に宿を予約しており、当地で一泊することとします (・∀・)イイネ。
唐津に終着した筑肥線の103系。
人影まばらで静かな夜のホームに
当系のコンプレッサーが発する
独特なアイドル音が響きます。
グルルルルルルルル━━( ̄- ̄ 3)━━━━…
▲23.12.7 唐津線 唐津
唐津線と筑肥線の
二路線が乗り入れる唐津は
佐賀県唐津市の中心駅。
近代的な現駅舎は
1983年の筑肥線電化開業とあわせて
高架化されたものです。
(゚ー゚*)カラツ
駅前はイルミネーションがきらきら~☆
▲23.12.7 唐津線 唐津
人影まばらで静かな夜のホームに
当系のコンプレッサーが発する
独特なアイドル音が響きます。
グルルルルルルルル━━( ̄- ̄ 3)━━━━…
▲23.12.7 唐津線 唐津
唐津線と筑肥線の
二路線が乗り入れる唐津は
佐賀県唐津市の中心駅。
近代的な現駅舎は
1983年の筑肥線電化開業とあわせて
高架化されたものです。
(゚ー゚*)カラツ
駅前はイルミネーションがきらきら~☆
▲23.12.7 唐津線 唐津
浜崎1845-(筑肥369C)-唐津1855
九州を訪れた初冬の鉄旅、次回に続きます・・・くコ:彡。
九州を訪れた初冬の鉄旅、次回に続きます・・・くコ:彡。
2023-12-16 08:08
長野電鉄・・・特急スノーモンキー&ゆけむり 撮影記 [鉄道写真撮影記]
前回からの続きです。
時期は実りの秋 ヤシロ(゚- ゚)アキ。赤く染まるリンゴの実に今の季節らしい風情を求めて、鉄ちゃんの私が“撮り鉄”にやってきたのは、“りんごの里”の信州(長野)(*’∀’*)リンゴ♪。
11月はすでに農園(りんご畑)での収穫と出荷のピークが過ぎつつある頃で、列車と絡めて撮りやすいところにリンゴがまだ残されているのか一抹の不安を抱えながらも σ(・∀・`)ウーン…、まずはしなの鉄道北しなの線の沿線にある長野市郊外の豊野(とよの)へ向かってみると ...(((o*・ω・)o、たしかにもう収穫を終えてしまったりんご畑が多かったものの (´д`;)アウ…、ありがたいことに線路沿いの何か所かではまだリンゴが木に実っている状態の畑を見つけられて (゚∀゚)オッ!、いまや貴重な存在といえる国鉄型車両の115系が使われた北しなの線の普通列車などをリンゴと絡めて撮ることができました (^_[◎]oパチリ。
その成果だけでも個人的にじゅうぶん満足のいくものが得られましたが (+`゚∀´)=b OK牧場!、せっかくリンゴが実る時期の信州に来たのなら、もうひとつ訪れてみたい路線があります σ(゚・゚*)ンー…。そこで、北しなの線の撮影は午前中のみで早々に切り上げて、午後はその別路線のほうへ移動することとしました (・∀・)イイネ。
豊野から長野に戻り、昼食を挟んで次に向かうのは・・・
時期は実りの秋 ヤシロ(゚- ゚)アキ。赤く染まるリンゴの実に今の季節らしい風情を求めて、鉄ちゃんの私が“撮り鉄”にやってきたのは、“りんごの里”の信州(長野)(*’∀’*)リンゴ♪。
11月はすでに農園(りんご畑)での収穫と出荷のピークが過ぎつつある頃で、列車と絡めて撮りやすいところにリンゴがまだ残されているのか一抹の不安を抱えながらも σ(・∀・`)ウーン…、まずはしなの鉄道北しなの線の沿線にある長野市郊外の豊野(とよの)へ向かってみると ...(((o*・ω・)o、たしかにもう収穫を終えてしまったりんご畑が多かったものの (´д`;)アウ…、ありがたいことに線路沿いの何か所かではまだリンゴが木に実っている状態の畑を見つけられて (゚∀゚)オッ!、いまや貴重な存在といえる国鉄型車両の115系が使われた北しなの線の普通列車などをリンゴと絡めて撮ることができました (^_[◎]oパチリ。
その成果だけでも個人的にじゅうぶん満足のいくものが得られましたが (+`゚∀´)=b OK牧場!、せっかくリンゴが実る時期の信州に来たのなら、もうひとつ訪れてみたい路線があります σ(゚・゚*)ンー…。そこで、北しなの線の撮影は午前中のみで早々に切り上げて、午後はその別路線のほうへ移動することとしました (・∀・)イイネ。
豊野から長野に戻り、昼食を挟んで次に向かうのは・・・
北陸新幹線や信越本線、しなの鉄道の各列車が発着する長野駅の構内を出て、駅の西口にあたる善光寺口のほうへ進んでゆくと ...(((o*・ω・)o、その先の地下にあるのが、“長電(ながでん)”の通称で親しまれる長野電鉄の長野駅。そう、私が次に撮影を目的として訪れたかった路線は、この長電です ( ̄∇ ̄)ナガデソ。
そして沿線での“撮り鉄”だけでなく、ここ長野から目的地の駅へ向かうまでに乗る“乗り鉄”としても楽しみにしていた私を、ホームで迎えてくれたのがこちらの“看板列車” (゚∀゚)オッ!。
そして沿線での“撮り鉄”だけでなく、ここ長野から目的地の駅へ向かうまでに乗る“乗り鉄”としても楽しみにしていた私を、ホームで迎えてくれたのがこちらの“看板列車” (゚∀゚)オッ!。
地下ホームに入線して
発車を待っている赤い特急列車(左)。
あれ?これはひょっとして
「成田エクスプレス」!?
(゚.゚*)ネックス?
なお右手に見える普通列車は
元・東京メトロ日比谷線の03系だった
現・長電3000系です。
▲長野電鉄長野線 長野
発車を待っている赤い特急列車(左)。
あれ?これはひょっとして
「成田エクスプレス」!?
(゚.゚*)ネックス?
なお右手に見える普通列車は
元・東京メトロ日比谷線の03系だった
現・長電3000系です。
▲長野電鉄長野線 長野
NEX、イタ━━━━━m9( ゚∀゚)━━━━━ッ!!
鮮やかな赤いお顔が印象的な特急列車 (=゚ω゚)ノ゙ヤア、とくに関東の人には見覚えがある方もいるのではないかと思われますが、これはもともと東京都心と成田空港の間をむすぶJR東日本の特急「成田エクスプレス」(NEX)に使われていた元・253系で (゚ー゚*)ネックス、第一線を退いたあとにJRから一部が譲渡された当系は現在、長野電鉄の特急用車両2100系として活躍を続けているのです (*・`o´・*)ホ─。なお、「成田エクスプレス」を改めて長電が付けた特急列車の愛称(列車名)は、当線の終着駅に近い観光名所の温泉地で冬場に見られるという雪中の露天風呂に浸かるサルにちなんで、特急「スノーモンキー」(笑)@(・ェ・)@ウキ。
そんな長電の特急列車の自由席は乗車券のほかに、距離や区間に関係なく“100円”の追加料金(特急券)で利用することができ Σ(゚∇゚*)100ペソ!?、それだけで元・「NEX」の特急車両に乗れるというハンパないおトク感が嬉しいじゃありませんか (´艸`*)オトク♪。
鮮やかな赤いお顔が印象的な特急列車 (=゚ω゚)ノ゙ヤア、とくに関東の人には見覚えがある方もいるのではないかと思われますが、これはもともと東京都心と成田空港の間をむすぶJR東日本の特急「成田エクスプレス」(NEX)に使われていた元・253系で (゚ー゚*)ネックス、第一線を退いたあとにJRから一部が譲渡された当系は現在、長野電鉄の特急用車両2100系として活躍を続けているのです (*・`o´・*)ホ─。なお、「成田エクスプレス」を改めて長電が付けた特急列車の愛称(列車名)は、当線の終着駅に近い観光名所の温泉地で冬場に見られるという雪中の露天風呂に浸かるサルにちなんで、特急「スノーモンキー」(笑)@(・ェ・)@ウキ。
そんな長電の特急列車の自由席は乗車券のほかに、距離や区間に関係なく“100円”の追加料金(特急券)で利用することができ Σ(゚∇゚*)100ペソ!?、それだけで元・「NEX」の特急車両に乗れるというハンパないおトク感が嬉しいじゃありませんか (´艸`*)オトク♪。
JRから譲渡された長電2100系。
その車内設備は「成田エクスプレス」時代と
ほとんど変わっていない様子で
蓋つきの荷棚(ハットラック)や
リクライニング機能のない固定座席など
元・253系らしい特徴が見られます。
その車内設備は「成田エクスプレス」時代と
ほとんど変わっていない様子で
蓋つきの荷棚(ハットラック)や
リクライニング機能のない固定座席など
元・253系らしい特徴が見られます。
私を乗せて長野を定刻に発車した湯田中(ゆだなか)ゆきの特急「スノーモンキー」は、長野市中心部の街なかを地下線でサクッと通り抜けると、やがて地上へ出て進路を北東方向に取ります ...(((o*・ω・)o。
長野電鉄の長野線は長野市の長野を起点に、権藤(ごんどう)、須坂(すざか)、小布施(おぶせ)、信州中野などの各駅を経て、山ノ内町の湯田中へといたる地方私鉄(中小民鉄)の路線 (・o・*)ホホゥ。ちなみにかつての長電には長野線のほかにも屋代(やしろ)線や木島(きじま)線(河東線)など複数の路線が存在していましたがいずれも近年に廃止となり、現在は長野線(もともとの長野線に河東線の一部や山ノ内線の区間を併せて統合)の一路線のみであることから、“長野線”という線名よりも会社の通称である“長電”の呼び名が一般に定着しているようです (゚ー゚*)ナガデソ。
そんな長電は、長野市近郊の通勤通学などで利用される地域輸送のほか、葛飾北斎ゆかりの地で栗が名物の小布施、湯田中・渋温泉郷や志賀高原の玄関口となる湯田中などへ行楽に訪れる観光客の需要が高く、いま私が乗っている特急「スノーモンキー」の車内も国内外からの観光客と見られる人たちでほぼ満席となっています @(・ェ・)@ウキ。
長野電鉄の長野線は長野市の長野を起点に、権藤(ごんどう)、須坂(すざか)、小布施(おぶせ)、信州中野などの各駅を経て、山ノ内町の湯田中へといたる地方私鉄(中小民鉄)の路線 (・o・*)ホホゥ。ちなみにかつての長電には長野線のほかにも屋代(やしろ)線や木島(きじま)線(河東線)など複数の路線が存在していましたがいずれも近年に廃止となり、現在は長野線(もともとの長野線に河東線の一部や山ノ内線の区間を併せて統合)の一路線のみであることから、“長野線”という線名よりも会社の通称である“長電”の呼び名が一般に定着しているようです (゚ー゚*)ナガデソ。
そんな長電は、長野市近郊の通勤通学などで利用される地域輸送のほか、葛飾北斎ゆかりの地で栗が名物の小布施、湯田中・渋温泉郷や志賀高原の玄関口となる湯田中などへ行楽に訪れる観光客の需要が高く、いま私が乗っている特急「スノーモンキー」の車内も国内外からの観光客と見られる人たちでほぼ満席となっています @(・ェ・)@ウキ。
地上へ出た長電の下り列車が
信濃吉田付近でオーバークロスするのは
先ほど私が乗ってきた北しなの線の線路。
上のほうに見える高架橋は北陸新幹線です。
▲長野電鉄長野線 信濃吉田-朝陽
(車窓から)
私が移動しているルートを
地図で確認するとこんな感じ。
鉄道利用だとなんだか効率が悪そう?
(´〜`*)ウーン
(地図をクリックすると拡大表示します)
信濃吉田付近でオーバークロスするのは
先ほど私が乗ってきた北しなの線の線路。
上のほうに見える高架橋は北陸新幹線です。
▲長野電鉄長野線 信濃吉田-朝陽
(車窓から)
私が移動しているルートを
地図で確認するとこんな感じ。
鉄道利用だとなんだか効率が悪そう?
(´〜`*)ウーン
(地図をクリックすると拡大表示します)
ところで、私が午前中に北しなの線の撮影をしていた豊野から、午後の目的地となる長電の沿線へと列車を使って移動する場合、北しなの線を長野までいったん南下してから長電に乗り換えてふたたび北上するという、地図上で見るとまるで“V字”か“U字”を描くような形となっていて、あまり効率がよくない印象 ( ̄  ̄)ユージコージ。
実は豊野から東へ平行移動したところに長電の小布施が所在し、私はなんとかここをショートカットできないかと考えてみるも σ(゚・゚*)ンー…、その間の直線距離はだいたい5キロ。クルマなら10分くらいで手軽に行けるけれど、路線バスは運行されていないようで、歩くとおよそ一時間かかります ( ̄  ̄;)イチジカン…(かといってタクシーを使うのはもったいないw)。
それでも仮に目的地が小布施ならば、歩いたほうが列車を乗り継ぐ“V字ルート”よりも早く到達できるのですが、小布施からさらに先の湯田中方面へ下り列車で向かおうとする場合、結果的に長野を経由して乗る列車と同じもの(つまり今の私が乗っているスノーモンキー)に小布施から乗ることとなり、それならば無理して一時間(正確にいえば北しなの線を撮っていた撮影ポイントからだと1時間20分)も歩くよりは、ルート的に効率が悪く思えても鉄道を使ったほうが楽だという判断に至りました (-`ω´-*)ウム。
ちなみに北しなの線と長電の交差部分には正式な乗換駅に指定されてないものの、前者に北長野、後者には信濃吉田(しなのよしだ)という両駅が近接していて(300メートル、徒歩5分程度)、そこを活用することも可能なのですが、信濃吉田には普通列車しか停車せず特急列車は通過してしまうため、やはり結果的に途中の須坂で後続の特急「スノーモンキー」へ乗り継ぐこととなります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
でもこの豊野と小布施の位置関係はなんだか、鉄道モノのサスペンスなどでトリックに使えそうですね(笑)( ̄ー ̄)ニヤリ。
実は豊野から東へ平行移動したところに長電の小布施が所在し、私はなんとかここをショートカットできないかと考えてみるも σ(゚・゚*)ンー…、その間の直線距離はだいたい5キロ。クルマなら10分くらいで手軽に行けるけれど、路線バスは運行されていないようで、歩くとおよそ一時間かかります ( ̄  ̄;)イチジカン…(かといってタクシーを使うのはもったいないw)。
それでも仮に目的地が小布施ならば、歩いたほうが列車を乗り継ぐ“V字ルート”よりも早く到達できるのですが、小布施からさらに先の湯田中方面へ下り列車で向かおうとする場合、結果的に長野を経由して乗る列車と同じもの(つまり今の私が乗っているスノーモンキー)に小布施から乗ることとなり、それならば無理して一時間(正確にいえば北しなの線を撮っていた撮影ポイントからだと1時間20分)も歩くよりは、ルート的に効率が悪く思えても鉄道を使ったほうが楽だという判断に至りました (-`ω´-*)ウム。
ちなみに北しなの線と長電の交差部分には正式な乗換駅に指定されてないものの、前者に北長野、後者には信濃吉田(しなのよしだ)という両駅が近接していて(300メートル、徒歩5分程度)、そこを活用することも可能なのですが、信濃吉田には普通列車しか停車せず特急列車は通過してしまうため、やはり結果的に途中の須坂で後続の特急「スノーモンキー」へ乗り継ぐこととなります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
でもこの豊野と小布施の位置関係はなんだか、鉄道モノのサスペンスなどでトリックに使えそうですね(笑)( ̄ー ̄)ニヤリ。
県内を流れる千曲川は
新潟で信濃川と名を変える
総距離日本一(367キロ)の長流。
その悠久なる大河を鉄橋で渡ります。
▲長野電鉄長野線 柳原-村山
(車窓から)
長電の車両基地がある須坂では
今年の1月で退役した3500系
(元・営団地下鉄3000系)が
構内に佇んでいました。
(゚∀゚)オッ!
その姿を車窓越しに一目でも
見られたのは嬉しい。
(´・∀・`)オツカレチャン
▲長野電鉄長野線 須坂(車窓から)
乗客の半数ほどが下車した小布施。
岩松院や北斎館といった観光名所や
今が旬の栗料理なども魅力的ですが
個人的に当地で惹かれるのは
駅構内の一角に保存されている
長電の往年の名車2000系。
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
▲長野電鉄長野線 小布施(車窓から)
新潟で信濃川と名を変える
総距離日本一(367キロ)の長流。
その悠久なる大河を鉄橋で渡ります。
▲長野電鉄長野線 柳原-村山
(車窓から)
長電の車両基地がある須坂では
今年の1月で退役した3500系
(元・営団地下鉄3000系)が
構内に佇んでいました。
(゚∀゚)オッ!
その姿を車窓越しに一目でも
見られたのは嬉しい。
(´・∀・`)オツカレチャン
▲長野電鉄長野線 須坂(車窓から)
乗客の半数ほどが下車した小布施。
岩松院や北斎館といった観光名所や
今が旬の栗料理なども魅力的ですが
個人的に当地で惹かれるのは
駅構内の一角に保存されている
長電の往年の名車2000系。
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
▲長野電鉄長野線 小布施(車窓から)
千曲川を渡って東進を続ける「スノーモンキー」 ...(((@(*・ェ・)@ウキキ。
歩いて到達することも考えた小布施を過ぎたあたりから、車窓にはのどかな田畑の風景が広がるようになり (´ー`)マターリ、そのなかには赤い実をたわわに生らしたものや、もう実はないけどおそらくそうであろうと思われる、リンゴの木が立ち並ぶりんご畑(りんご農園)も多く見られます (「゚ー゚)ドレドレ。
車窓からざっと眺めたリンゴの実の残存具合はやはり豊野と似たような状況で、半分を切った三割程度ってところかなぁ・・・(あくまでも個人的に見た印象)(゚ペ)ウーン…。ここでも線路近くの好位置にウマく、リンゴが残されているといいのだけど 八(゚- ゚)オネガイ。
歩いて到達することも考えた小布施を過ぎたあたりから、車窓にはのどかな田畑の風景が広がるようになり (´ー`)マターリ、そのなかには赤い実をたわわに生らしたものや、もう実はないけどおそらくそうであろうと思われる、リンゴの木が立ち並ぶりんご畑(りんご農園)も多く見られます (「゚ー゚)ドレドレ。
車窓からざっと眺めたリンゴの実の残存具合はやはり豊野と似たような状況で、半分を切った三割程度ってところかなぁ・・・(あくまでも個人的に見た印象)(゚ペ)ウーン…。ここでも線路近くの好位置にウマく、リンゴが残されているといいのだけど 八(゚- ゚)オネガイ。
沿線でもとくに広大なりんご畑がひろがるのは、駅でいうと夜間瀬(よませ)や上条(かみじょう)のあたりなのですが、全24駅中の6駅(起終点を含む)しか停車しない特急「スノーモンキー」(A特急)はその両駅ともさらっと通過し スル━━━( ̄、 ̄*)===3━━━ッ、やがて終点の湯田中へと到着しました (・ω・)トーチャコ。
長野から湯田中までは
特急列車で45分ほど。
「スノーモンキー」の乗り心地は
とても快適でした。
(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
▲長野電鉄長野線 湯田中
駅舎に観光案内所が併設された湯田中は
湯田中・渋温泉郷の最寄駅であるとともに
志賀高原への玄関口でもあり
当地へ向かうバスが駅から接続しています。
昭和30年(1955年)に立てられた駅舎は
“昭和レトロ”っぽさを感じる趣ですが
ただいまバリアフリー工事の最中でした。
(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…
▲長野電鉄長野線 湯田中
特急列車で45分ほど。
「スノーモンキー」の乗り心地は
とても快適でした。
(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
▲長野電鉄長野線 湯田中
駅舎に観光案内所が併設された湯田中は
湯田中・渋温泉郷の最寄駅であるとともに
志賀高原への玄関口でもあり
当地へ向かうバスが駅から接続しています。
昭和30年(1955年)に立てられた駅舎は
“昭和レトロ”っぽさを感じる趣ですが
ただいまバリアフリー工事の最中でした。
(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…
▲長野電鉄長野線 湯田中
長野1133-(長電5A 特急スノーモンキー)-湯田中1218
では、特急列車が停まらずに通過した夜間瀬や上条へ、ここ湯田中から上りの普通列車に乗って戻りたいところですが σ(゚・゚*)ンー…、路線の末端区間に位置するこのあたりの長野線(旧・山ノ内線区間の信州中野〜湯田中)は、普通列車の運行が一時間から一時間半の間隔で、次の湯田中発は今からおよそ一時間後となります(13時11分発の信州中野ゆき)( ̄  ̄;)イチジカン…。
でも実は目的地の上条は湯田中の隣駅で、その駅間距離はわずか1.4キロ。しかも長電の線路は勾配を緩和するために蛇行していますが、ほぼ直線の道路を進めばその距離はもうちょい短くて1.2キロほど。徒歩15分くらいでしょうか (・o・*)ホホゥ。これなら一時間後の列車を待つよりも、歩いちゃったほうがあきらかに早く到達できます ...(((o*・ω・)o。
では、特急列車が停まらずに通過した夜間瀬や上条へ、ここ湯田中から上りの普通列車に乗って戻りたいところですが σ(゚・゚*)ンー…、路線の末端区間に位置するこのあたりの長野線(旧・山ノ内線区間の信州中野〜湯田中)は、普通列車の運行が一時間から一時間半の間隔で、次の湯田中発は今からおよそ一時間後となります(13時11分発の信州中野ゆき)( ̄  ̄;)イチジカン…。
でも実は目的地の上条は湯田中の隣駅で、その駅間距離はわずか1.4キロ。しかも長電の線路は勾配を緩和するために蛇行していますが、ほぼ直線の道路を進めばその距離はもうちょい短くて1.2キロほど。徒歩15分くらいでしょうか (・o・*)ホホゥ。これなら一時間後の列車を待つよりも、歩いちゃったほうがあきらかに早く到達できます ...(((o*・ω・)o。
こんな短い距離の駅間じゃ、徒歩で列車より先回りできてもサスペンスのトリックには使えなさそうだけど (。A。)アヒャ☆、特急が通過する駅に普通列車へ乗り換えるのでなく歩いて戻るというのは、なかなか面白い展開。これはクルマ(マイカーやレンタカー)を使わない“徒歩鉄”だからこそ思いつく妙案(苦肉の策?w)だといえるかもしれません ъ(゚Д゚)ナイス。
ところで、先述のとおり普通列車はしばらくありませんが、私が湯田中まで乗ってきた特急「スノーモンキー」が折り返しの長野ゆきとなり、まもなく発車します (゚ー゚*)スノモン。目的地とする上条のりんご畑にはちょっと間に合わなそうだけど、せっかくならどこか適当な場所でその特急列車を撮りたい σ(゚・゚*)ンー…。
ところで、先述のとおり普通列車はしばらくありませんが、私が湯田中まで乗ってきた特急「スノーモンキー」が折り返しの長野ゆきとなり、まもなく発車します (゚ー゚*)スノモン。目的地とする上条のりんご畑にはちょっと間に合わなそうだけど、せっかくならどこか適当な場所でその特急列車を撮りたい σ(゚・゚*)ンー…。
お!いいじゃん!(゚∀゚*)オオッ!
クネクネと蛇行した線形の一角にあるカーブで、正面気味に捉えた特急「スノーモンキー」。その傍らには程よく色づいていた紅葉も添えてみました (^_[◎]oパチリ。
あらかじめ調べてきた撮影ポイントでなく、適当に見つけたところでためしに撮ると、得てしてそれなりの絵にしかならない場合が多いのですが、ここはアウトカーブから見る列車や紅葉の入り具合、良好な陽あたりの光線状態など、思ったよりも悪くない一枚となりました (・∀・)イイネ。真ん中に立つ架線柱の存在がちょっと強いものの、コンクリ製の柱などでなく昔ながらの鉄骨製というのがまた、地方私鉄のローカル線らしい趣でシブいじゃないですか (´ω`*)シブイ。
この先のりんご畑でリンゴと列車がウマく撮れるかどうかまだわからないけど、とりあえずこの“スノーモンキーと紅葉”という一枚が撮れただけでも、湯田中まで来た価値はあったように思います (-`ω´-*)ウム。
クネクネと蛇行した線形の一角にあるカーブで、正面気味に捉えた特急「スノーモンキー」。その傍らには程よく色づいていた紅葉も添えてみました (^_[◎]oパチリ。
あらかじめ調べてきた撮影ポイントでなく、適当に見つけたところでためしに撮ると、得てしてそれなりの絵にしかならない場合が多いのですが、ここはアウトカーブから見る列車や紅葉の入り具合、良好な陽あたりの光線状態など、思ったよりも悪くない一枚となりました (・∀・)イイネ。真ん中に立つ架線柱の存在がちょっと強いものの、コンクリ製の柱などでなく昔ながらの鉄骨製というのがまた、地方私鉄のローカル線らしい趣でシブいじゃないですか (´ω`*)シブイ。
この先のりんご畑でリンゴと列車がウマく撮れるかどうかまだわからないけど、とりあえずこの“スノーモンキーと紅葉”という一枚が撮れただけでも、湯田中まで来た価値はあったように思います (-`ω´-*)ウム。
湯田中の上り方の隣駅で
ひとつ長野寄りに位置する上条は
交換設備が無い棒線構造(一面一線)の
普通列車しか停まらない無人駅。
( ̄  ̄*)カミジョー
駅のまわりにはりんご畑(りんご農園)が
ひろがります。
でも、もう木にリンゴが無いなぁ・・・。
▲長野電鉄長野線 上条
ひとつ長野寄りに位置する上条は
交換設備が無い棒線構造(一面一線)の
普通列車しか停まらない無人駅。
( ̄  ̄*)カミジョー
駅のまわりにはりんご畑(りんご農園)が
ひろがります。
でも、もう木にリンゴが無いなぁ・・・。
▲長野電鉄長野線 上条
地形的にほぼ下り坂だったこともあり、湯田中から徒歩で難なくたどり着けた上条 (・ω・)トーチャコ。
その素朴な小駅を囲むように広がるりんご畑は、いかにも信州のご当地私鉄である長電らしいのどかな情景ですが (´ー`)マターリ、駅まわりの畑(農園)をざっと見たところ、もうこのあたりにリンゴの実は生ってなく、軒並み収穫を終えてしまった様子 ( ̄  ̄;)ナッシング。いいロケーションだけに惜しいなぁ σ(・∀・`)ウーン…。
そこでさらに隣駅の夜間瀬のほうへ向かって歩き進み、リンゴを探しまわってみると・・・<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ
その素朴な小駅を囲むように広がるりんご畑は、いかにも信州のご当地私鉄である長電らしいのどかな情景ですが (´ー`)マターリ、駅まわりの畑(農園)をざっと見たところ、もうこのあたりにリンゴの実は生ってなく、軒並み収穫を終えてしまった様子 ( ̄  ̄;)ナッシング。いいロケーションだけに惜しいなぁ σ(・∀・`)ウーン…。
そこでさらに隣駅の夜間瀬のほうへ向かって歩き進み、リンゴを探しまわってみると・・・<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ
りんごちゃん、あったー! m9っ`∀´)ミッケ!
そこは線路のすぐそばという“撮り鉄的に好位置”の農園にて、まだ収穫されずに残されているたくさんのリンゴが、日に照らされてキラキラと赤く輝いているじゃありませんか .゚+.(*’∀’*)リンゴ♪.+゚.。しかも、実をたわわに付けた枝が何本も公道から手の届くところにまで垂れ下がっており、この絶妙な条件は列車とリンゴを絡めて撮りやすそう (・∀・)イイネ。
ためしに道路から枝のほうへ腕を伸ばしてカメラを構え、ファインダーを直接覗かずにライブビューモードの背面液晶でアングルを確認しながらシャッターを切ってみます p[◎]qΦωΦ*)パチャ☆
そこは線路のすぐそばという“撮り鉄的に好位置”の農園にて、まだ収穫されずに残されているたくさんのリンゴが、日に照らされてキラキラと赤く輝いているじゃありませんか .゚+.(*’∀’*)リンゴ♪.+゚.。しかも、実をたわわに付けた枝が何本も公道から手の届くところにまで垂れ下がっており、この絶妙な条件は列車とリンゴを絡めて撮りやすそう (・∀・)イイネ。
ためしに道路から枝のほうへ腕を伸ばしてカメラを構え、ファインダーを直接覗かずにライブビューモードの背面液晶でアングルを確認しながらシャッターを切ってみます p[◎]qΦωΦ*)パチャ☆
リンゴが実る木の陰から横顔を覗かせたのは |д゚)チラッ、湯田中ゆきの下り普通列車で、元・東京メトロの03系だった現・3000系 ( ̄ω ̄*)ヒビヤセソ。
もともとこの車両の帯色は前面と側面ともに、前職の東京メトロ時代に日比谷線で使われていたことから当線のラインカラーであるグレー(ねずみ色)だったのですが、譲渡で長電へ編入された際に前面のみを当社のイメージカラーである赤に変更 (゚ー゚*)アカ。長電の赤い色は沿線のリンゴに由来するものだといわれ、このりんご畑の景色に赤帯の3000系がしっくりとマッチしているじゃないですか (・∀・)イイネ。
ちなみにリンゴの品種を私はよくわからないけど、やはりこれも豊野でお話に聞いた“ふじ”なのでしょうか? ( ̄  ̄*)フジ?。その立派に育った赤い実を強調したアングルで切り取ってみました (*’∀’*)リンゴ♪。
もともとこの車両の帯色は前面と側面ともに、前職の東京メトロ時代に日比谷線で使われていたことから当線のラインカラーであるグレー(ねずみ色)だったのですが、譲渡で長電へ編入された際に前面のみを当社のイメージカラーである赤に変更 (゚ー゚*)アカ。長電の赤い色は沿線のリンゴに由来するものだといわれ、このりんご畑の景色に赤帯の3000系がしっくりとマッチしているじゃないですか (・∀・)イイネ。
ちなみにリンゴの品種を私はよくわからないけど、やはりこれも豊野でお話に聞いた“ふじ”なのでしょうか? ( ̄  ̄*)フジ?。その立派に育った赤い実を強調したアングルで切り取ってみました (*’∀’*)リンゴ♪。
収穫期まっただ中のりんご畑をゆく
信州中野ゆき上り普通列車。
赤帯が施されて仲間入りした3000系は
日比谷線時代のグレー帯よりも
あか抜けた印象を受けます。
(・∀・)アカオビ
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
信州中野ゆき上り普通列車。
赤帯が施されて仲間入りした3000系は
日比谷線時代のグレー帯よりも
あか抜けた印象を受けます。
(・∀・)アカオビ
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
さらに農道(公道)を行けるところまで進んで ...(((o*・ω・)o、りんご農園の敷地に突き当たる手前のところでもためしに、湯田中から折り返してきた上りの普通列車(信州中野ゆき)を一枚撮ってみましたが (^_[◎]oパチリ、リンゴの木の広がりかたは嫌いじゃないものの、日の当たり具合が微妙だし、ここはアングルの自由度も低いため、やはり最初に下り列車を撮ったほうのポイントへ戻って撮影を続けることとしました コッチ…((((o* ̄-)o。
そこで次に狙うのは“花形”の特急列車です ハナガタ(゚ー゚*)ミツル。この区間は普通列車の運行が一時間に一本だけど、行楽客の多い土休日の日中は特急列車も約一時間おきに設定されており、およそ30分間隔で普通列車と特急列車が交互にやってくるようなダイヤで、意外と撮影効率は悪くない (*゚ェ゚))フムフム。
そこで次に狙うのは“花形”の特急列車です ハナガタ(゚ー゚*)ミツル。この区間は普通列車の運行が一時間に一本だけど、行楽客の多い土休日の日中は特急列車も約一時間おきに設定されており、およそ30分間隔で普通列車と特急列車が交互にやってくるようなダイヤで、意外と撮影効率は悪くない (*゚ェ゚))フムフム。
そろそろ食べごろ?
大きくて艶やかなリンゴを横目にみる
元・NEXの特急「スノーモンキー」。
@(・ェ・)@ウキ
“空港特急”からコンバートされた“温泉特急”も
今ではすっかり板につきました。
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条
大きくて艶やかなリンゴを横目にみる
元・NEXの特急「スノーモンキー」。
@(・ェ・)@ウキ
“空港特急”からコンバートされた“温泉特急”も
今ではすっかり板につきました。
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条
あ〜かい〜林檎に、ねっく〜す(NEX)寄せて〜♪ ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
先ほど乗ったのとは別の編成の下り列車でふたたび現れた、特急「スノーモンキー」の2100系 @(・ェ・)@ウキ。
JR時代に“ローレル賞”(鉄道車両の優秀賞的なもの)や“ブルネル賞”(鉄道車両の国際的なデザイン賞)などを獲得した、その優れたデザインと端正なスタイルはやはり、無塗装のアルミ合金に帯を配した3000系(普通列車)よりも景色に映えていい絵になります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
ちなみに先述したとおり当系は、前職の「成田エクスプレス」に使われていたときから外装(や内装)を大きく変えておらず、元から赤をアクセントとしたカラーリングなのですが、長電の一員としてみればこの2100系の車体色もまた“りんご色”と捉えてよいでしょう (*’∀’*)リンゴ♪。
そんな特急「スノーモンキー」を、手の届く位置(道路からカメラを構えられる位置)のなかでひときわ赤く染まっていた、艶やかなリンゴの実と合わせてみました パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。
先ほど乗ったのとは別の編成の下り列車でふたたび現れた、特急「スノーモンキー」の2100系 @(・ェ・)@ウキ。
JR時代に“ローレル賞”(鉄道車両の優秀賞的なもの)や“ブルネル賞”(鉄道車両の国際的なデザイン賞)などを獲得した、その優れたデザインと端正なスタイルはやはり、無塗装のアルミ合金に帯を配した3000系(普通列車)よりも景色に映えていい絵になります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
ちなみに先述したとおり当系は、前職の「成田エクスプレス」に使われていたときから外装(や内装)を大きく変えておらず、元から赤をアクセントとしたカラーリングなのですが、長電の一員としてみればこの2100系の車体色もまた“りんご色”と捉えてよいでしょう (*’∀’*)リンゴ♪。
そんな特急「スノーモンキー」を、手の届く位置(道路からカメラを構えられる位置)のなかでひときわ赤く染まっていた、艶やかなリンゴの実と合わせてみました パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。
湯田中からすぐに折り返してきた
上りの長野ゆき「スノーモンキー」は
車両のお顔(前面)が見える角度でパチリ。
リンゴだけでなく紅葉に彩られた背景の山も
秋という季節感を演出しています。
(゚- ゚)アキ
ちなみに長電の2100系は二編成が在籍し、
こちらのE1編成のほうは側面のグレー部分など
より「NEX」時代に近い装い。
( ̄。 ̄)ヘー
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
上りの長野ゆき「スノーモンキー」は
車両のお顔(前面)が見える角度でパチリ。
リンゴだけでなく紅葉に彩られた背景の山も
秋という季節感を演出しています。
(゚- ゚)アキ
ちなみに長電の2100系は二編成が在籍し、
こちらのE1編成のほうは側面のグレー部分など
より「NEX」時代に近い装い。
( ̄。 ̄)ヘー
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
上条のりんご畑で撮影を始めてからここまで、3000系の普通列車と2100系の特急「スノーモンキー」の二形式(二種類)をそれぞれにリンゴと撮りましたが (^_[◎]oパチリ、長電には2100系のほかにもう一種類の特急型車両が運行されており、もちろんそれも抑えたい・・・というか、2100系などは決して“前座”ではないけれど、実は次にやってくる特急列車こそが個人的にいちばんの“本命”といえるものです (-`ω´-*)ウム。
「スノーモンキー」が通過してから、さらに待つこと一時間(その間に3000系の普通列車が往復したけど、同じような絵なので割愛)。やがて私の耳に聞こえてきたのは、空気の澄んだ秋の里山に響きわたる、その“本命”の特急列車ならではの“独特なジョイント音”(走行音) ε-(°ω°*)キタッ!。
「スノーモンキー」が通過してから、さらに待つこと一時間(その間に3000系の普通列車が往復したけど、同じような絵なので割愛)。やがて私の耳に聞こえてきたのは、空気の澄んだ秋の里山に響きわたる、その“本命”の特急列車ならではの“独特なジョイント音”(走行音) ε-(°ω°*)キタッ!。
りんご畑で“HiSE”が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
リンゴ越しに真横から列車を狙うアングルはこれまでと同じような撮り方ではあるものの、シュッとエッジの効いたスタイリッシュなサイドビューが「スノーモンキー」とは違ったインパクトを放ちます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
実はこれもまた他社から長電へ譲渡されてきたものであり、先頭車に備えた展望席が象徴的なこの車両はもともと、都心の新宿と箱根や江ノ島などの観光地を結ぶ小田急電鉄の“特急ロマンスカー”で活躍し、“ブルーリボン賞”(鉄道車両の最優秀賞的なもの)の受賞経歴もある名車の元・小田急10000形 (゚ー゚*)ロマ。現在の長電ではおもに特急「ゆけむり」として使われる1000系です(この日は「ゆけむり〜のんびり号〜」として運行)(o ̄∇ ̄o)ユケムリ。
ちなみにこの構図ではリンゴの木に隠されて確認できませんが、当系の展望席を除く客室は高床構造のいわゆる“ハイデッカー”となっていて、小田急時代には“HiSE”(Highdecker Super Expresの略)の車両愛称が付けられていました (゚ー゚*)ハイエス。また、やはりこの構図ではわからないのですが、当系は車両の連結部分にひとつの台車を備えた構造の“連接車”で、それにより走行時に響かせるジョイント音が長電の他形式(一般的な台車構造の“ボギー車”)とは違う独特なものとなるのです タタン…( ̄- ̄ 3)タタン…。
そんな1000系の外装も2100系と同様、長電へ譲渡された際に塗り替えられたのでなく、この赤と白の塗分けは小田急のころからほぼ変えていない当系オリジナルのカラーリング (゚ー゚*)アカ。これまた“りんご色”をイメージカラーとする長電の特急列車にそのままぴったりとハマり、沿線に実るリンゴといい感じにマッチしてくれました ъ(゚Д゚)ナイス。個人的な好みで撮影の“本命”と位置付けていた元・“HiSE”の「ゆけむり」、それを立派に育ったリンゴといっしょに晴天順光の好条件で撮れたのは満足のいく嬉しい成果です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
リンゴ越しに真横から列車を狙うアングルはこれまでと同じような撮り方ではあるものの、シュッとエッジの効いたスタイリッシュなサイドビューが「スノーモンキー」とは違ったインパクトを放ちます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
実はこれもまた他社から長電へ譲渡されてきたものであり、先頭車に備えた展望席が象徴的なこの車両はもともと、都心の新宿と箱根や江ノ島などの観光地を結ぶ小田急電鉄の“特急ロマンスカー”で活躍し、“ブルーリボン賞”(鉄道車両の最優秀賞的なもの)の受賞経歴もある名車の元・小田急10000形 (゚ー゚*)ロマ。現在の長電ではおもに特急「ゆけむり」として使われる1000系です(この日は「ゆけむり〜のんびり号〜」として運行)(o ̄∇ ̄o)ユケムリ。
ちなみにこの構図ではリンゴの木に隠されて確認できませんが、当系の展望席を除く客室は高床構造のいわゆる“ハイデッカー”となっていて、小田急時代には“HiSE”(Highdecker Super Expresの略)の車両愛称が付けられていました (゚ー゚*)ハイエス。また、やはりこの構図ではわからないのですが、当系は車両の連結部分にひとつの台車を備えた構造の“連接車”で、それにより走行時に響かせるジョイント音が長電の他形式(一般的な台車構造の“ボギー車”)とは違う独特なものとなるのです タタン…( ̄- ̄ 3)タタン…。
そんな1000系の外装も2100系と同様、長電へ譲渡された際に塗り替えられたのでなく、この赤と白の塗分けは小田急のころからほぼ変えていない当系オリジナルのカラーリング (゚ー゚*)アカ。これまた“りんご色”をイメージカラーとする長電の特急列車にそのままぴったりとハマり、沿線に実るリンゴといい感じにマッチしてくれました ъ(゚Д゚)ナイス。個人的な好みで撮影の“本命”と位置付けていた元・“HiSE”の「ゆけむり」、それを立派に育ったリンゴといっしょに晴天順光の好条件で撮れたのは満足のいく嬉しい成果です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
小田急時代の箱根と今の湯田中
目的地がそのどちらでも合いそうな愛称の
特急「ゆけむり」。
(o ̄∇ ̄o)ユケムリ
リンゴの花や実がピークを迎えるころに
当系自慢の展望席から眺めるパノラマビューは
きっと壮観なことでしょう。
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
目的地がそのどちらでも合いそうな愛称の
特急「ゆけむり」。
(o ̄∇ ̄o)ユケムリ
リンゴの花や実がピークを迎えるころに
当系自慢の展望席から眺めるパノラマビューは
きっと壮観なことでしょう。
▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)
先の普通列車や「スノーモンキー」と同じく、湯田中へ到着したあとはすぐに上り方面へと折り返してきた1000系(上りは特急「ゆけむり」でなく、須坂で入庫する回送列車)イッタリo(゚д゚o≡o゚д゚)oキタリ。
それを今度はリンゴの枝に寄らず、これまでより少し引き気味のアングルで撮り(絵的にはたいして変わらんねw (^^;)ゞポリポリ)、これにて長電とリンゴを絡めたコラボ撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
それを今度はリンゴの枝に寄らず、これまでより少し引き気味のアングルで撮り(絵的にはたいして変わらんねw (^^;)ゞポリポリ)、これにて長電とリンゴを絡めたコラボ撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
りんご畑から湯田中の駅へと
歩いて戻る途中
また適当な場所(?)で
紅葉の山を背景に撮ってみた
湯田中ゆきの「スノーモンキー」。
@(・ェ・)@ウキ
こちらの2100系・E2編成は
側面の塗分けにグレーの部分がなく
りんご畑で見かけたE1編成に比べて
“NEXっぽさ”が少し薄い印象です。
( ̄。 ̄)ヘー
▲長野電鉄長野線 湯田中-上条(後追い)
歩いて戻る途中
また適当な場所(?)で
紅葉の山を背景に撮ってみた
湯田中ゆきの「スノーモンキー」。
@(・ェ・)@ウキ
こちらの2100系・E2編成は
側面の塗分けにグレーの部分がなく
りんご畑で見かけたE1編成に比べて
“NEXっぽさ”が少し薄い印象です。
( ̄。 ̄)ヘー
▲長野電鉄長野線 湯田中-上条(後追い)
さて、帰路としてここから長野のほうへ向かうのに、これまでの運行パターンであれば、今しがた撮影した特急「ゆけむり」の次は普通列車が来るものだと思うところですが σ(゚・゚*)ンー…、時刻表を確認すると今の時間帯は普通列車の間隔が一時間半もあいており、今度の上り列車も特急の「スノーモンキー」となっています ( ̄  ̄*)スノモン。
そのため、またしても撮影地(りんご畑)最寄り駅の上条からは乗れず、ふたたび湯田中まで歩いて戻ることとしました ...(((o*・ω・)o。ま、普通列車より特急列車に乗れるほうがいいけどね @(・ェ・)@ウキ。
そのため、またしても撮影地(りんご畑)最寄り駅の上条からは乗れず、ふたたび湯田中まで歩いて戻ることとしました ...(((o*・ω・)o。ま、普通列車より特急列車に乗れるほうがいいけどね @(・ェ・)@ウキ。
湯田中からの帰りも
100円の自由席特急券を加えて
特急「スノーモンキー」に乗車します。
“NEX”ならぬ“NER”のロゴは
“Nagano Electric Railway”の略で
長野電鉄を表すもの。
(´ω`)ナルヘソ
▲長野電鉄長野線 湯田中
「スノーモンキー」の車窓に
りんご畑を眺めながらいただく一杯は
信州産りんごの“シナノリップ”で仕込んだ
地域限定のクラフトチューハイ。
カンパイ♪(〃゚∇゚)ノロ☆
りんごの爽やかな香りを程よく感じつつ
一般的なシードルより
アルコールがちょっと強めで(8%)
コレ、美味しいね。
(゚д゚)ウマー!
西の夕空に浮かぶ北信の山々
(飯縄山や黒姫山などの北信五岳)。
きょうは爽やかな晴天の一日で
絶好の“撮り鉄日和”でした。
(´ー`)シミジミ
▲長野電鉄長野線 桜沢-都住
(車窓から)
100円の自由席特急券を加えて
特急「スノーモンキー」に乗車します。
“NEX”ならぬ“NER”のロゴは
“Nagano Electric Railway”の略で
長野電鉄を表すもの。
(´ω`)ナルヘソ
▲長野電鉄長野線 湯田中
「スノーモンキー」の車窓に
りんご畑を眺めながらいただく一杯は
信州産りんごの“シナノリップ”で仕込んだ
地域限定のクラフトチューハイ。
カンパイ♪(〃゚∇゚)ノロ☆
りんごの爽やかな香りを程よく感じつつ
一般的なシードルより
アルコールがちょっと強めで(8%)
コレ、美味しいね。
(゚д゚)ウマー!
西の夕空に浮かぶ北信の山々
(飯縄山や黒姫山などの北信五岳)。
きょうは爽やかな晴天の一日で
絶好の“撮り鉄日和”でした。
(´ー`)シミジミ
▲長野電鉄長野線 桜沢-都住
(車窓から)
かつての長電は、製造当時に先進的な意匠だった特急型の2000系や、普通列車用で“OSカー”(Officemen & Students Carの略)の愛称が付いた0系、10系など、当社独自の個性的なオリジナル車両が多く存在しましたが、現在はすべての旅客用車両が他社から譲渡されてやってきた“中古車”で賄われています (゚ー゚*)ナガデソ。
それでもその顔ぶれ(車種)はバラエティに富んでおり、元・「NEX」の2100系「スノーモンキー」に、元・「HiSE」の1000系「ゆけむり」、そして元・地下鉄日比谷線だった3000系(と、そのほかに今回の撮影地では運用の範囲外だった元・東急の8500系)などが、本家での第一線を退いたあとに首都圏から離れた信州の地で二幕目となる活躍を続けています (*`・ω・´)-3フンス!。そんな彼らと再会できるのもマニア的に長電の魅力のひとつと言えるでしょう (*´∀`)ノ゙オヒサ。
のどかな“りんごの里”を走る“りんご色の電車”たち、リンゴがたわわに実る時期に当線らしい秋景色を撮ることができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。思い切って豊野から湯田中へ転戦(移動)した判断は、結果として正解だったと思います (-`ω´-*)ウム。
それでもその顔ぶれ(車種)はバラエティに富んでおり、元・「NEX」の2100系「スノーモンキー」に、元・「HiSE」の1000系「ゆけむり」、そして元・地下鉄日比谷線だった3000系(と、そのほかに今回の撮影地では運用の範囲外だった元・東急の8500系)などが、本家での第一線を退いたあとに首都圏から離れた信州の地で二幕目となる活躍を続けています (*`・ω・´)-3フンス!。そんな彼らと再会できるのもマニア的に長電の魅力のひとつと言えるでしょう (*´∀`)ノ゙オヒサ。
のどかな“りんごの里”を走る“りんご色の電車”たち、リンゴがたわわに実る時期に当線らしい秋景色を撮ることができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。思い切って豊野から湯田中へ転戦(移動)した判断は、結果として正解だったと思います (-`ω´-*)ウム。
長野に終着した特急「スノーモンキー」。
(・ω・)トーチャコ
座席の埋まり具合は
湯田中の発車時点で6割程度でしたが
途中の小布施からは満席となり
立ち客も見られる盛況ぶりでした。
▲長野電鉄長野線 長野
長電の長野駅改札前では
沿線で採れたリンゴが販売されていました。
シナノスイートが5玉も入った一袋が300円!
これは買って帰ろ。
(*’∀’*)リンゴ♪
(・ω・)トーチャコ
座席の埋まり具合は
湯田中の発車時点で6割程度でしたが
途中の小布施からは満席となり
立ち客も見られる盛況ぶりでした。
▲長野電鉄長野線 長野
長電の長野駅改札前では
沿線で採れたリンゴが販売されていました。
シナノスイートが5玉も入った一袋が300円!
これは買って帰ろ。
(*’∀’*)リンゴ♪
湯田中1534-(長電12A特急スノーモンキー)-長野1619
信州の山へ日が落ちる頃の夕刻に長野へ戻ってきました (=゚ω゚)ノ タライマ!。
今回の旅で私は、関東甲信越や南東北エリアのJR東日本各線に加え、しなの鉄道や長野電鉄なども全線が乗り放題となる、オトクなきっぷの「週末パス」を使用しており、このきっぷの有効期間は土休日の連続する二日間となっています (*・∀・)つ[パス]。そこで本来であれば長野やその周辺の街で一泊して、旅を翌日につなげたい (・∀・)イイネ・・・ところなのですが、きょうは行楽シーズンの連休初日とあって、ホテルや旅館など宿泊施設はどこも満員御礼 ( ̄△ ̄;)エッ…。ほんの数日前に出かけることを決めた私には、かなり範囲を広げて検索しても適当な空室が見つけられませんでした (´Д⊂ダメポ(むっちゃくちゃ高いリゾートホテルは空いてたけどさw)。それでは仕方なく宿泊を諦めて、もう都内の自宅に帰るしかありません (・ε・`)シャーナイネ。
そんなワケで長電の駅からJRの駅へと移動し、そこから乗るのはもちろん東京ゆきの北陸新幹線・・・ではなく、こちらの列車。
信州の山へ日が落ちる頃の夕刻に長野へ戻ってきました (=゚ω゚)ノ タライマ!。
今回の旅で私は、関東甲信越や南東北エリアのJR東日本各線に加え、しなの鉄道や長野電鉄なども全線が乗り放題となる、オトクなきっぷの「週末パス」を使用しており、このきっぷの有効期間は土休日の連続する二日間となっています (*・∀・)つ[パス]。そこで本来であれば長野やその周辺の街で一泊して、旅を翌日につなげたい (・∀・)イイネ・・・ところなのですが、きょうは行楽シーズンの連休初日とあって、ホテルや旅館など宿泊施設はどこも満員御礼 ( ̄△ ̄;)エッ…。ほんの数日前に出かけることを決めた私には、かなり範囲を広げて検索しても適当な空室が見つけられませんでした (´Д⊂ダメポ(むっちゃくちゃ高いリゾートホテルは空いてたけどさw)。それでは仕方なく宿泊を諦めて、もう都内の自宅に帰るしかありません (・ε・`)シャーナイネ。
そんなワケで長電の駅からJRの駅へと移動し、そこから乗るのはもちろん東京ゆきの北陸新幹線・・・ではなく、こちらの列車。
長野から都内へ向かうには、往路のように北陸新幹線を利用するのがいちばん速くて便利な手段ですが バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、とくに急いで帰ることはなく、せっかくならもう少し“鉄旅”を愉しみたい私はあえて新幹線を使わずに、在来線の普通列車を乗り継ぐという物好きな経路を選択 (゚∀゚)アヒャ☆。また、できれば旅費を少しでも抑えたいボンビー(貧乏)な私には、新幹線の特急券代を浮かすことで節約にもなります (´皿`)セコイ。
ちなみに長野から乗車する当駅始発の上り普通列車は、信越本線、篠ノ井線、中央本線(中央東線)を直通する大月ゆき(446M)で、長野と山梨の両県を跨ぐ210.3キロの距離を4時間14分もかけて走破するロングラン運用(長野17時13分発、大月21時27分着)Σ(゚∇゚*ノ)ノ ナガッ!。そんな当列車に私は過去にも何度かところどころでお世話になっており、最近では今夏に岐阜の明知鉄道へ行った際に塩尻(しおじり)から、新潟のえちごトキめき鉄道へ行った際には上諏訪(かみすわ)から、それぞれ大月まで乗っています (=´▽`=)オセワサマ。しかし始発駅の長野から乗り通したことはなく、今回はそれを体験するいい機会だと考えました (´ω`)ナルヘソ。
普通列車のボックスシートに揺られて、のんびりと帰りましょ ノコノコ...(((o*・ω・)o。
ちなみに長野から乗車する当駅始発の上り普通列車は、信越本線、篠ノ井線、中央本線(中央東線)を直通する大月ゆき(446M)で、長野と山梨の両県を跨ぐ210.3キロの距離を4時間14分もかけて走破するロングラン運用(長野17時13分発、大月21時27分着)Σ(゚∇゚*ノ)ノ ナガッ!。そんな当列車に私は過去にも何度かところどころでお世話になっており、最近では今夏に岐阜の明知鉄道へ行った際に塩尻(しおじり)から、新潟のえちごトキめき鉄道へ行った際には上諏訪(かみすわ)から、それぞれ大月まで乗っています (=´▽`=)オセワサマ。しかし始発駅の長野から乗り通したことはなく、今回はそれを体験するいい機会だと考えました (´ω`)ナルヘソ。
普通列車のボックスシートに揺られて、のんびりと帰りましょ ノコノコ...(((o*・ω・)o。
こまめに各駅へ停車する鈍行列車。
“日本三大車窓”のひとつに挙げられる
姨捨(おばすて)では
特急「しなの」の通過待ちで
3分ほどの停車時間があり、
善光寺平のきれいな夜景を
ホームから眺めることができました。
・:*:・(´▽`*)ステキ・:*:・。
▲篠ノ井線 姨捨
“日本三大車窓”のひとつに挙げられる
姨捨(おばすて)では
特急「しなの」の通過待ちで
3分ほどの停車時間があり、
善光寺平のきれいな夜景を
ホームから眺めることができました。
・:*:・(´▽`*)ステキ・:*:・。
▲篠ノ井線 姨捨
仕事の出張で訪れた青森の津軽地方にて、たわわに実る収穫間近のリンゴを目にしたことがきっかけとなり ( ̄▽ ̄*)リンゴ、あらためてリンゴが実る情景を求めて訪れた信州の長野 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
そこではもうだいぶ収穫が進んでいたものの σ(・∀・`)ウーン…、しなの鉄道北しなの線の豊野でも、そして長野電鉄長野線の上条でも、“撮り鉄的に好位置”な線路際の農園にかろうじてリンゴが残されており (゚∀゚)オッ!、望んでいた“列車とリンゴのコラボ”という秋らしい季節感のある写真をそれぞれの路線で残すことができた撮影成果は、実りのある“大収穫”だったと言えるでしょう (゚∀゚)アヒャ☆。
また、今回の私の撮影では主題とするリンゴを意識した撮影が多かったけど、山々や沿線ではちょうど紅葉の見ごろを迎えていて (*’∀’*)キレイ、その鮮やかな色彩も目を楽しませてくれました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
例年に晴天となることが多くて、“晴れの特異日”なんていわれる“文化の日”の祝日。まさに今年も絶好の秋晴れに恵まれて、撮り鉄をメインとする鉄旅を存分に満喫できました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
そこではもうだいぶ収穫が進んでいたものの σ(・∀・`)ウーン…、しなの鉄道北しなの線の豊野でも、そして長野電鉄長野線の上条でも、“撮り鉄的に好位置”な線路際の農園にかろうじてリンゴが残されており (゚∀゚)オッ!、望んでいた“列車とリンゴのコラボ”という秋らしい季節感のある写真をそれぞれの路線で残すことができた撮影成果は、実りのある“大収穫”だったと言えるでしょう (゚∀゚)アヒャ☆。
また、今回の私の撮影では主題とするリンゴを意識した撮影が多かったけど、山々や沿線ではちょうど紅葉の見ごろを迎えていて (*’∀’*)キレイ、その鮮やかな色彩も目を楽しませてくれました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
例年に晴天となることが多くて、“晴れの特異日”なんていわれる“文化の日”の祝日。まさに今年も絶好の秋晴れに恵まれて、撮り鉄をメインとする鉄旅を存分に満喫できました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪
長野から乗り通して4時間あまり
ようやくたどり着いた大月ですが
ひと息つく間もなくわずか4分の接続で
東京ゆきの快速電車に乗り継ぎます。
ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!
ここからさらに一時間ちょっと乗って
自宅には23時ごろに帰着しました。
▲中央本線 大月
ようやくたどり着いた大月ですが
ひと息つく間もなくわずか4分の接続で
東京ゆきの快速電車に乗り継ぎます。
ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!
ここからさらに一時間ちょっと乗って
自宅には23時ごろに帰着しました。
▲中央本線 大月
長野1713-(篠ノ井446M)-大月2127~2131-(中央2244M 中央特快)-三鷹2243
2023-11-22 22:22
しなの鉄道・・・北しなの線115系 撮影記 [鉄道写真撮影記]
11月3日(金・祝)
おはようございます オハヨン(。・∀・)ノ゙。
気持ちのいい青空が広がる秋晴れに恵まれて、絶好のお出かけ日和となった“文化の日”の祝日。いま私がいるのは信州の長野です (゚ー゚*)ナガノ。
おはようございます オハヨン(。・∀・)ノ゙。
気持ちのいい青空が広がる秋晴れに恵まれて、絶好のお出かけ日和となった“文化の日”の祝日。いま私がいるのは信州の長野です (゚ー゚*)ナガノ。
個人的になんやかんやで(?)公私ともに慌ただしかった印象のここ数週間(10月いっぱい)でしたが、どうにかそれを落ち着かす目途がついたため ε-(´o`A フゥ…、久しぶりにちょっと遠出の鉄道旅を楽しもうと思い、北陸新幹線に乗ってここ長野へと足を延ばしてみました ...(((o*・ω・)o。
北陸新幹線「はくたか」に乗って
秋が深まりつつある長野へ。
(゚ー゚*)ハクタカ
連休で列車が混雑しており
もし自由席しか空きがなかったら
始発駅の東京で並ぶつもりでしたが
事前に指定券が取れたので
少し特急料金が安くなる大宮から
乗車しました。
(´∀`*)セコイ
▲東北新幹線 大宮
秋が深まりつつある長野へ。
(゚ー゚*)ハクタカ
連休で列車が混雑しており
もし自由席しか空きがなかったら
始発駅の東京で並ぶつもりでしたが
事前に指定券が取れたので
少し特急料金が安くなる大宮から
乗車しました。
(´∀`*)セコイ
▲東北新幹線 大宮
なお、本来であればいつもの撮影記や旅行記に倣って、都内を出発する場面から旅の話を始めたかったところですが σ(゚・゚*)ンー…、きょうは行楽シーズンの三連休初日とあって朝6時過ぎに東京を発車する北陸新幹線「はくたか551号」はかなり混んでいて、私が数日前に今旅へ出かけることを決めた時点ですでに指定席の窓側(A、E席)がすべて埋まっており、かろうじて取れたのは三列席の通路側(C席)(・ε・`)シャーナイネ。しかも陽光が差し込むA席のかたはブラインドを下ろされていたし、さらに当列車は指定席車両の通路にも自由席に収まりきらなかった立ち客が流入するほどの混雑状況で (´д`;)人大杉…、これだと私の席から車窓の景色はほとんど見ることができません。列車に乗るのが好きな私でもさすがにこれでは面白くない "o(-ω-;*)ウゥム…。
そんなワケで今回は新幹線の乗車部分を割愛し、長野から話を進めることとします。
そんなワケで今回は新幹線の乗車部分を割愛し、長野から話を進めることとします。
景色が見にくい・・・というか
ほとんど見えない通路側に座り
大宮から一時間ちょっとで長野着。
(・ω・)トーチャコ
混雑した車内からホームへ出たときの
開放感が気持ちいい。
ε-(´∀`*)ホッ
▲北陸新幹線 長野
ほとんど見えない通路側に座り
大宮から一時間ちょっとで長野着。
(・ω・)トーチャコ
混雑した車内からホームへ出たときの
開放感が気持ちいい。
ε-(´∀`*)ホッ
▲北陸新幹線 長野
新宿0535-(山手505G)-池袋0543~0552-(埼京503K)-大宮0628~0652-(北陸新幹線 はくたか551号)-長野0803
長野は私がここまで乗ってきた北陸新幹線のほか、JRの信越本線(篠ノ井線)と飯山線、第三セクター鉄道のしなの鉄道線と北しなの線、さらに地下の駅からは地方私鉄の長野電鉄が発着しており、信州旅の拠点となる主要駅です (・o・*)ホホゥ(列車の乗り入れにより正式な路線区間でないものも含まれます)。
そこから私が乗るのは、北しなの線から飯山線(いいやません)へと直通する戸狩野沢温泉(とがりのざわおんせん)ゆき普通列車 ( ̄  ̄*)イーヤマセソ。
長野は私がここまで乗ってきた北陸新幹線のほか、JRの信越本線(篠ノ井線)と飯山線、第三セクター鉄道のしなの鉄道線と北しなの線、さらに地下の駅からは地方私鉄の長野電鉄が発着しており、信州旅の拠点となる主要駅です (・o・*)ホホゥ(列車の乗り入れにより正式な路線区間でないものも含まれます)。
そこから私が乗るのは、北しなの線から飯山線(いいやません)へと直通する戸狩野沢温泉(とがりのざわおんせん)ゆき普通列車 ( ̄  ̄*)イーヤマセソ。
飯山線は千曲川(信濃川)に沿って長野と新潟の両県にまたがる山あいを進む旅情あふれるローカル線。しかもその列車の行き先が温泉地だというのがまた惹かれるではありませんか (・∀・)イイネ。ローカル線でたどり着いた温泉に浸かれば、これまでの仕事疲れなどが癒されるというもの (´ー`)マターリ・・・ですが、惜しいけれど私の今旅の目的地は温泉でなければ、飯山線の沿線にも行きません (´・ω`・)エッ?。
え?飯山線の列車に乗るのにその沿線へ行かないとは、いったいどういうことかと言うと σ(゚・゚*)ンー…、飯山線の正式な路線起点は長野から北のほうへ三駅ほど進んだ豊野(とよの)で、長野と豊野の間はしなの鉄道の北しなの線(旧・信越本線の長野~妙高高原をむすぶ路線)へ列車が乗り入れる形態(直通運転)となっています。実はその両線の分岐駅である豊野が私の目的地であり、飯山線の区間へ入る前に下車してしまうのです。豊野へは北しなの線の列車(妙高高原ゆき)でも飯山線の列車でも行けるけど、たまたまこの時間の列車が飯山線(への直通列車)だったということでした ( ´_ゝ`)フーン。
え?飯山線の列車に乗るのにその沿線へ行かないとは、いったいどういうことかと言うと σ(゚・゚*)ンー…、飯山線の正式な路線起点は長野から北のほうへ三駅ほど進んだ豊野(とよの)で、長野と豊野の間はしなの鉄道の北しなの線(旧・信越本線の長野~妙高高原をむすぶ路線)へ列車が乗り入れる形態(直通運転)となっています。実はその両線の分岐駅である豊野が私の目的地であり、飯山線の区間へ入る前に下車してしまうのです。豊野へは北しなの線の列車(妙高高原ゆき)でも飯山線の列車でも行けるけど、たまたまこの時間の列車が飯山線(への直通列車)だったということでした ( ´_ゝ`)フーン。
長野を発車した飯山線・・・というか
北しなの線の下り列車。
しばらくすると車窓の右手に見えるのは
JR東日本で最大級の車両整備工場である
長野総合車両センターで
鉄ちゃんには必見の“鉄分スポット”です。
(「゚ー゚)ドレドレ
あ、引退した189系(右)が見える・・・。
▲しなの鉄道北しなの線 長野-北長野。
(車窓から)
北しなの線の下り列車。
しばらくすると車窓の右手に見えるのは
JR東日本で最大級の車両整備工場である
長野総合車両センターで
鉄ちゃんには必見の“鉄分スポット”です。
(「゚ー゚)ドレドレ
あ、引退した189系(右)が見える・・・。
▲しなの鉄道北しなの線 長野-北長野。
(車窓から)
ところで、そもそも私が今回の旅先に長野を選んだのには、ざっくりと二つの理由があります (゚ー゚*)ナガノ。
ひとつは先々月(9月)に群馬県横川(安中市)の「碓氷峠鉄道文化むら」を見学に訪れて、今から26年前に廃止となってしまった旧・信越本線の横川〜軽井沢(通称“ヨコカル”)の在りし日に思いを馳せていたら (´ω`)ヨコカル、碓氷峠を越えた先にある信州の地(長野県)にも行きたいという欲望が高まったこと ((o(・∀・`)o))ウズウズ。
そしてもうひとつは、先月(10月)に仕事の出張で青森県の弘前を訪れた際、青森空港と弘前市内をむすぶバスの車窓から目に留まった“りんご畑”(りんご農園)( ̄  ̄*)リンゴ。この時期の津軽地方はリンゴの収穫の最盛期で、どの木も真っ赤な実をたわわにつけています (゚∀゚)オッ!。ああ、“撮り鉄”の私としてはできることなら、このリンゴをご当地のローカル線である五能線(ごのうせん)や弘南鉄道(こうなんてつどう)などの列車と絡めて撮りたいなぁ・・・σ(・∀・`)ウーン… なんて思うも、仕事で来ている身としてはそんな余裕がいっさいなく、撮影は叶いませんでした (・ε・`)チェ(時間があったら訪れるつもりだった弘南鉄道は線路補修で全線が運休だったしね)。そこで、さすがに津軽へもう一度行くには遠すぎるけど、同じくリンゴの名産地として知られる長野ならばどこかで手軽に、リンゴと列車を組み合わせた鉄道写真が撮れるかもしれないと考えたのです (´ω`)ナルヘソ。
ひとつは先々月(9月)に群馬県横川(安中市)の「碓氷峠鉄道文化むら」を見学に訪れて、今から26年前に廃止となってしまった旧・信越本線の横川〜軽井沢(通称“ヨコカル”)の在りし日に思いを馳せていたら (´ω`)ヨコカル、碓氷峠を越えた先にある信州の地(長野県)にも行きたいという欲望が高まったこと ((o(・∀・`)o))ウズウズ。
そしてもうひとつは、先月(10月)に仕事の出張で青森県の弘前を訪れた際、青森空港と弘前市内をむすぶバスの車窓から目に留まった“りんご畑”(りんご農園)( ̄  ̄*)リンゴ。この時期の津軽地方はリンゴの収穫の最盛期で、どの木も真っ赤な実をたわわにつけています (゚∀゚)オッ!。ああ、“撮り鉄”の私としてはできることなら、このリンゴをご当地のローカル線である五能線(ごのうせん)や弘南鉄道(こうなんてつどう)などの列車と絡めて撮りたいなぁ・・・σ(・∀・`)ウーン… なんて思うも、仕事で来ている身としてはそんな余裕がいっさいなく、撮影は叶いませんでした (・ε・`)チェ(時間があったら訪れるつもりだった弘南鉄道は線路補修で全線が運休だったしね)。そこで、さすがに津軽へもう一度行くには遠すぎるけど、同じくリンゴの名産地として知られる長野ならばどこかで手軽に、リンゴと列車を組み合わせた鉄道写真が撮れるかもしれないと考えたのです (´ω`)ナルヘソ。
ただし、二つの欲求(理由)のうちのひとつは単に信州へ行くことだけですが、ちょっと気がかりなのはリンゴのほう ハイヒール( ̄  ̄*)リンゴ。
品種にもよりますが秋冬が旬のリンゴは9月頃から農園での収穫が始まり、おおむね10月中旬から11月中旬が出荷の最盛期となるそうで、もう都内でも果物屋の店頭にリンゴが並ぶようになりました。ということは、木に実った状態のリンゴを撮るには11月の今だともう遅いのかもしれません (-ω-;*)オセーヨ。たぶん津軽を訪れた10月の三週目あたりがベストだったんだろうなぁ。はたして長野の畑(農園)に少しはまだリンゴが収穫されずに残っているのだろうか (゚ペ)ウーン…。
そんな一抹の不安を抱えつつ、長野市北部に位置する三才(さんさい)を過ぎたあたりで沿線に広がるりんご畑を列車の車窓から眺めてみると・・・(「゚ー゚)ドレドレ、お!リンゴあるじゃん!(゚∀゚)オッ!
たしかにもう収穫を終えてしまった寂しい木が多く目立つけど、まだ実が摘まれずに残された状態の農園もところどころに見られます (*’∀’*)リンゴ♪。あとはその限られたリンゴの木が都合よく、列車と絡めてウマく撮れるといいのですが σ(゚・゚*)ンー…。
長野から走って15分、列車は豊野に到着 (・ω・)トーチャコ。
品種にもよりますが秋冬が旬のリンゴは9月頃から農園での収穫が始まり、おおむね10月中旬から11月中旬が出荷の最盛期となるそうで、もう都内でも果物屋の店頭にリンゴが並ぶようになりました。ということは、木に実った状態のリンゴを撮るには11月の今だともう遅いのかもしれません (-ω-;*)オセーヨ。たぶん津軽を訪れた10月の三週目あたりがベストだったんだろうなぁ。はたして長野の畑(農園)に少しはまだリンゴが収穫されずに残っているのだろうか (゚ペ)ウーン…。
そんな一抹の不安を抱えつつ、長野市北部に位置する三才(さんさい)を過ぎたあたりで沿線に広がるりんご畑を列車の車窓から眺めてみると・・・(「゚ー゚)ドレドレ、お!リンゴあるじゃん!(゚∀゚)オッ!
たしかにもう収穫を終えてしまった寂しい木が多く目立つけど、まだ実が摘まれずに残された状態の農園もところどころに見られます (*’∀’*)リンゴ♪。あとはその限られたリンゴの木が都合よく、列車と絡めてウマく撮れるといいのですが σ(゚・゚*)ンー…。
長野から走って15分、列車は豊野に到着 (・ω・)トーチャコ。
しなの鉄道の北しなの線と
JR飯山線の分岐駅である豊野で下車。
ホームで見送る戸狩野沢温泉ゆきはこの先
飯山線へと進みます。
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
長野市豊野町に所在する豊野駅。
( ̄  ̄*)トヨノ
地域の東西自由通路を兼ねた
近代的な橋上駅舎は
2008年に改築されたもの。
駅前ロータリーには当地らしく
リンゴのモニュメントが見られます。
(*’∀’*)リンゴ
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
JR飯山線の分岐駅である豊野で下車。
ホームで見送る戸狩野沢温泉ゆきはこの先
飯山線へと進みます。
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
長野市豊野町に所在する豊野駅。
( ̄  ̄*)トヨノ
地域の東西自由通路を兼ねた
近代的な橋上駅舎は
2008年に改築されたもの。
駅前ロータリーには当地らしく
リンゴのモニュメントが見られます。
(*’∀’*)リンゴ
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
長野0837-(北しなの線129D)-豊野0852
千曲川の西岸に位置して飯縄山を望む環境にある豊野は、明治期にこの界隈を開墾してリンゴ栽培が始まったという“信州りんご発祥の地”として知られ、県内でもとくにリンゴの生産が盛んなところ ( ̄。 ̄)ヘー。長野市の中心部に近い便利な立地から近年は宅地の整備が進んでいるものの、それでも駅まわりの住宅街を抜けるとその先には広大なりんご畑がひろがります (゚∀゚)オッ!。
千曲川の西岸に位置して飯縄山を望む環境にある豊野は、明治期にこの界隈を開墾してリンゴ栽培が始まったという“信州りんご発祥の地”として知られ、県内でもとくにリンゴの生産が盛んなところ ( ̄。 ̄)ヘー。長野市の中心部に近い便利な立地から近年は宅地の整備が進んでいるものの、それでも駅まわりの住宅街を抜けるとその先には広大なりんご畑がひろがります (゚∀゚)オッ!。
りんご畑に囲まれた線路沿いの道を歩きつつ、目に留まるリンゴの木を意識してみると、まだ収穫されずに実が残っている畑はざっと見て3割ほどって感じでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。つまり7割はもう収穫済みということ(あくまでも私が道すがらに見た個人的な印象ですが)。
そんなビミョーな残存状況でとりあえず私が目指すのは、乗ってきた列車の車窓から見てリンゴがけっこう多く残っているのを確認した一画 ъ(`・ω´・)チェック。ためしにスマホの地図アプリでその場所までのルートを検索すると豊野の駅から歩いて30分近くかかるみたいで、ちょうど30分後にやってくる“とある列車”に間に合うかどうかギリギリのところ ( ̄  ̄;)ギリ。焦って走るほどではないけど、ちょっと急ぎ目に歩みを進めます ε=ε=ε=┌(;・_・)┘。
そんなビミョーな残存状況でとりあえず私が目指すのは、乗ってきた列車の車窓から見てリンゴがけっこう多く残っているのを確認した一画 ъ(`・ω´・)チェック。ためしにスマホの地図アプリでその場所までのルートを検索すると豊野の駅から歩いて30分近くかかるみたいで、ちょうど30分後にやってくる“とある列車”に間に合うかどうかギリギリのところ ( ̄  ̄;)ギリ。焦って走るほどではないけど、ちょっと急ぎ目に歩みを進めます ε=ε=ε=┌(;・_・)┘。
スマホの地図を見ながらも何となく距離感が掴みづらい、牧歌的でのどかなりんご畑の風景(言い方を変えれば景色にあまり変化がないw)。そんななかを早足で歩いて、どうにか次の列車が通過する前に目的の撮影ポイントへとたどり着けました ε-(´o`;)ホッ。
ここは南北にまっすぐと伸びる北しなの線の線路(単線)の両サイドに農園のりんご畑が広がっており、いかにも“りんごの里”のご当地らしい景観です (・∀・)イイネ。ただし、立ち位置に向かって右側(線路の西側)の畑はすでに収穫を終えており、木にリンゴが実っているのは左側の畑のみ。それでも線路の近くにリンゴが残されていたのは嬉しいじゃありませんか ъ(゚Д゚)ナイス。
そこでさっそくカメラを構えてアングル(写真の構図)を考えようとしたところ、すぐに傍らの踏切が鳴りだします Σ(‘=’;)ハッ!。
ここは南北にまっすぐと伸びる北しなの線の線路(単線)の両サイドに農園のりんご畑が広がっており、いかにも“りんごの里”のご当地らしい景観です (・∀・)イイネ。ただし、立ち位置に向かって右側(線路の西側)の畑はすでに収穫を終えており、木にリンゴが実っているのは左側の畑のみ。それでも線路の近くにリンゴが残されていたのは嬉しいじゃありませんか ъ(゚Д゚)ナイス。
そこでさっそくカメラを構えてアングル(写真の構図)を考えようとしたところ、すぐに傍らの踏切が鳴りだします Σ(‘=’;)ハッ!。
おいこっと、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
長野のほうから直線の先に現れたのは、まさにリンゴっぽい臙脂(えんじ)色(と白色)の車体が印象的な、キハ110系の「おいこっと」(o ̄∇ ̄o)オイコット。
先ほど私が長野から豊野まで乗ってきた飯山線の普通列車と同系の車両ですが、この「おいこっと」は外装内装ともにちょっとお洒落にドレスアップした特別仕様となっており (・o・*)ホホゥ、飯山線沿線の田舎暮らしをイメージした古民家風の車内ではご当地米のおにぎりなどがふるまわれて、専属のアテンダントさんが案内を務めるという観光列車(全席指定の臨時快速列車)です (・∀・)イイネ。ちなみに愛称名の「おいこっと」とは地域の方言かと思ったのですが、実はコンセプトとした田舎イメージが東京の真逆にあると言う意味から、“TOKYO”のアルファベット表記を逆さまにしたもの(OYKOT=おいこっと)だそうです(笑)(゚∀゚)アヒャ☆。
そんな楽しい列車の「おいこっと」ですが、私が撮影ポイントに着いてからひと息つく間もなくやってきてしまったため (・Θ・;)アセアセ…、まだアングルが固まっておらず、列車の足回り(台車や床下)を隠す雑草や構図内における架線柱の位置など、ちょっと丁寧さに欠けた一枚となってしまいました (^^;)ゞポリポリ。う〜ん、あとから思えばこれはカメラをタテ位置にしたほうが、画の収まりはよかったかもしれないなぁ・・・σ(・∀・`)タテ…。まあそれでもギリギリで通過に間に合って、リンゴとのコラボショットが撮れただけでもヨシとしますか。個人的にここで撮りたい“本命”(お目当て)は「おいこっと」でなく、“次にくる列車”だし (-`ω´-*)ウム。
その本命に備えてアングルを整えると、やがて踏切がふたたび鳴動しました。今度は落ち着いて列車を迎えます (*`・ω・´)-3フンス!。
長野のほうから直線の先に現れたのは、まさにリンゴっぽい臙脂(えんじ)色(と白色)の車体が印象的な、キハ110系の「おいこっと」(o ̄∇ ̄o)オイコット。
先ほど私が長野から豊野まで乗ってきた飯山線の普通列車と同系の車両ですが、この「おいこっと」は外装内装ともにちょっとお洒落にドレスアップした特別仕様となっており (・o・*)ホホゥ、飯山線沿線の田舎暮らしをイメージした古民家風の車内ではご当地米のおにぎりなどがふるまわれて、専属のアテンダントさんが案内を務めるという観光列車(全席指定の臨時快速列車)です (・∀・)イイネ。ちなみに愛称名の「おいこっと」とは地域の方言かと思ったのですが、実はコンセプトとした田舎イメージが東京の真逆にあると言う意味から、“TOKYO”のアルファベット表記を逆さまにしたもの(OYKOT=おいこっと)だそうです(笑)(゚∀゚)アヒャ☆。
そんな楽しい列車の「おいこっと」ですが、私が撮影ポイントに着いてからひと息つく間もなくやってきてしまったため (・Θ・;)アセアセ…、まだアングルが固まっておらず、列車の足回り(台車や床下)を隠す雑草や構図内における架線柱の位置など、ちょっと丁寧さに欠けた一枚となってしまいました (^^;)ゞポリポリ。う〜ん、あとから思えばこれはカメラをタテ位置にしたほうが、画の収まりはよかったかもしれないなぁ・・・σ(・∀・`)タテ…。まあそれでもギリギリで通過に間に合って、リンゴとのコラボショットが撮れただけでもヨシとしますか。個人的にここで撮りたい“本命”(お目当て)は「おいこっと」でなく、“次にくる列車”だし (-`ω´-*)ウム。
その本命に備えてアングルを整えると、やがて踏切がふたたび鳴動しました。今度は落ち着いて列車を迎えます (*`・ω・´)-3フンス!。
りんご畑で115系が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
私が“本命”と位置づけていたのは北しなの線の妙高高原(みょうこうこうげん)ゆき下り普通列車(325M)で、当線が第三セクター化される以前の旧・信越本線だったころから使われている、国鉄型車両(昭和の国鉄時代に製造された車両)の115系 (゚ー゚*)ゲゲゴ。しなの鉄道では新たに投入しているSR1系への置き換えが進められているなか、いまなお数本の115系が活躍を続けており、東日本地域(関東甲信越)では当鉄道だけに残された貴重な存在です (*・`o´・*)ホ─。そんな当系をたわわに実ったリンゴと組み合わせて撮りたかったのでした (^_[◎]oパチリ。
ちなみにしなの鉄道の115系は基本的な標準色のほかに、昔の塗装を再現した復刻色やご当地の観光ラッピングなど、いろいろなカラーリングが施されているのですが、やってきた編成(S11編成)はなんとも潔さを覚える真っ白(アイボリーホワイト)な車体 ( ̄  ̄)マッチロ。冬の信州の雪景色か、はたまた春に咲くリンゴの花をイメージしたものかと個人的には思うところ σ(゚・゚*)ンー…、よく見ると側面には何かのキャラクターが貼り付けられていて、当鉄道のホームページによるとこれは某アニメとのコラボラッピングなのだそうです ( ̄。 ̄)ヘー。私は最近のアニメに関心や興味は薄いけど、列車を正面気味に見れば側面のラッピング装飾はほとんど目立たなくて気にならないし、初見となる“白一色”の115系というのが個人的に意外と悪くない印象で新鮮に感じます (・Д・*)ヘェー(何となく185系に色を合わせたクロ157-1の顔が思い浮かんだw)。
ホンネを言っちゃうと国鉄時代の“湘南色”を復刻した編成(S3編成)が来てくれたら大喜びで万歳していたところですが (。A。)アヒャ☆、白一色の編成であってもリンゴと組み合わせて115系が撮れたことは嬉しい成果でした (+`゚∀´)=b OK牧場!。アングル的にも先ほどの「おいこっと」より画が安定したかな? (・∀・)イイネ
私が“本命”と位置づけていたのは北しなの線の妙高高原(みょうこうこうげん)ゆき下り普通列車(325M)で、当線が第三セクター化される以前の旧・信越本線だったころから使われている、国鉄型車両(昭和の国鉄時代に製造された車両)の115系 (゚ー゚*)ゲゲゴ。しなの鉄道では新たに投入しているSR1系への置き換えが進められているなか、いまなお数本の115系が活躍を続けており、東日本地域(関東甲信越)では当鉄道だけに残された貴重な存在です (*・`o´・*)ホ─。そんな当系をたわわに実ったリンゴと組み合わせて撮りたかったのでした (^_[◎]oパチリ。
ちなみにしなの鉄道の115系は基本的な標準色のほかに、昔の塗装を再現した復刻色やご当地の観光ラッピングなど、いろいろなカラーリングが施されているのですが、やってきた編成(S11編成)はなんとも潔さを覚える真っ白(アイボリーホワイト)な車体 ( ̄  ̄)マッチロ。冬の信州の雪景色か、はたまた春に咲くリンゴの花をイメージしたものかと個人的には思うところ σ(゚・゚*)ンー…、よく見ると側面には何かのキャラクターが貼り付けられていて、当鉄道のホームページによるとこれは某アニメとのコラボラッピングなのだそうです ( ̄。 ̄)ヘー。私は最近のアニメに関心や興味は薄いけど、列車を正面気味に見れば側面のラッピング装飾はほとんど目立たなくて気にならないし、初見となる“白一色”の115系というのが個人的に意外と悪くない印象で新鮮に感じます (・Д・*)ヘェー(何となく185系に色を合わせたクロ157-1の顔が思い浮かんだw)。
ホンネを言っちゃうと国鉄時代の“湘南色”を復刻した編成(S3編成)が来てくれたら大喜びで万歳していたところですが (。A。)アヒャ☆、白一色の編成であってもリンゴと組み合わせて115系が撮れたことは嬉しい成果でした (+`゚∀´)=b OK牧場!。アングル的にも先ほどの「おいこっと」より画が安定したかな? (・∀・)イイネ
これはのちほど帰り際に
長野駅でふたたび見かけた
115系の“白一色”編成(笑)
( ̄  ̄)マッチロ
その側面に施されているのは
しなの鉄道沿線の千曲市を舞台とした
「Turkey!」というアニメだそうです。
(゚ー゚*)ターキー?
▲信越本線 長野
長野駅でふたたび見かけた
115系の“白一色”編成(笑)
( ̄  ̄)マッチロ
その側面に施されているのは
しなの鉄道沿線の千曲市を舞台とした
「Turkey!」というアニメだそうです。
(゚ー゚*)ターキー?
▲信越本線 長野
続いてもう一本、こんどは20分後に逆方向から長野ゆき上り普通列車(324M)としてやはり、北しなの線の115系がやってきます (゚∀゚)オッ!。
時間的な余裕はあまりないけれど、できれば近場で別のアングルを探して少しでも画に変化をつけたいところです σ(゚・゚*)ンー…。ためしに長野寄りにあるもうひとつの踏切のほうへ向かってみると ...(((o*・ω・)o、そのまわりの農園の畑でもリンゴはまだ収穫されずに残されており、列車と組み合わせて撮ることができそう (・∀・)イイネ。
時間的な余裕はあまりないけれど、できれば近場で別のアングルを探して少しでも画に変化をつけたいところです σ(゚・゚*)ンー…。ためしに長野寄りにあるもうひとつの踏切のほうへ向かってみると ...(((o*・ω・)o、そのまわりの農園の畑でもリンゴはまだ収穫されずに残されており、列車と組み合わせて撮ることができそう (・∀・)イイネ。
次にやってきたのはこんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
手前にあるりんご畑の向こうに
踏切が見えます。
今度はサイド気味(側面気味)に
列車を撮ってみようかな。
σ(゚・゚*)ンー…
▲しなの鉄道北しなの線 三才-豊野
(「゚ー゚)ドレドレ
手前にあるりんご畑の向こうに
踏切が見えます。
今度はサイド気味(側面気味)に
列車を撮ってみようかな。
σ(゚・゚*)ンー…
▲しなの鉄道北しなの線 三才-豊野
りんご畑の傍らの道でカメラを構えて列車の通過を待っていると、散歩で通りかかった地元のオジサマ(りんご農家さんかな?)が気さくに話しかけてくださり (=゚ω゚)ノ゙ヤア、甘味が強くて最近人気の“シナノスイート”というリンゴの品種は艶のよい赤い色がとくに鮮やかで絵になるとのことですが、もうこのあたりではほとんど収穫を終えてしまい、いま木に成っている品種は私もよく耳にする“ふじ”だそうです (* ̄  ̄)フジ。ほかに比べて“ふじ”は少し収穫時期が遅いらしい ( ̄。 ̄)ヘー。
そんなお話を聞いていたところで、まもなく列車の接近を知らせる踏切が鳴りました (゚∀゚)オッ!。
そんなお話を聞いていたところで、まもなく列車の接近を知らせる踏切が鳴りました (゚∀゚)オッ!。
秋晴れの青空に映える
真っ赤なリンゴ。
それに負けないインパクトの
黄色い115系が横切ってゆきます。
(o´∀`o)カコイイ!
ちなみにこの写真のなかに
“ニセモノのリンゴ”がひとつあります。
写真をクリックして拡大したら
わかるかな?
(=゚ω゚=*)ンン!?
▲しなの鉄道北しなの線 豊野-三才
真っ赤なリンゴ。
それに負けないインパクトの
黄色い115系が横切ってゆきます。
(o´∀`o)カコイイ!
ちなみにこの写真のなかに
“ニセモノのリンゴ”がひとつあります。
写真をクリックして拡大したら
わかるかな?
(=゚ω゚=*)ンン!?
▲しなの鉄道北しなの線 豊野-三才
台鉄色、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
国鉄型の古い車両らしい重厚なモーター音をりんご畑に響かせて現れたのは、先ほどの“白一色”とは見た目の印象が大きく異なる、お顔を黄色とオレンジに化粧した派手な115系 ( ̄∇ ̄)ハデ。これはしなの鉄道と友好協定を結んでいる台湾の台湾鉄路管理局(台鉄)の車両をイメージした“台鉄色”と呼ばれるカラーリングです(S9編成)(゚ー゚*)タイテツ。またもちょっぴり期待した“湘南色”ではなかったけど、順光に照らされて鮮やかに発色した“台鉄色”は真っ赤なリンゴとともに明るい絵を演出してくれて、なかなかいい感じじゃないですか (・∀・)イイネ。車両の足回りを隠す枯れ草に煩わしさを覚えるものの、ここはリンゴの木の存在感と良好な光線状態を優先としたアングルに納得し、雑草には目をつむることとしました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
ちなみにこの“台鉄色”ですが、今月中(11月中)に運行を終了してしまう予定だそうで(塗装変更?車両自体の退役?)、まもなく見納めとなる模様 (´・ω・`)ショボン。その引退の花道にリンゴが花を添えて・・・いや、実を添えて(?)くれました (*’∀’*)リンゴ。
国鉄型の古い車両らしい重厚なモーター音をりんご畑に響かせて現れたのは、先ほどの“白一色”とは見た目の印象が大きく異なる、お顔を黄色とオレンジに化粧した派手な115系 ( ̄∇ ̄)ハデ。これはしなの鉄道と友好協定を結んでいる台湾の台湾鉄路管理局(台鉄)の車両をイメージした“台鉄色”と呼ばれるカラーリングです(S9編成)(゚ー゚*)タイテツ。またもちょっぴり期待した“湘南色”ではなかったけど、順光に照らされて鮮やかに発色した“台鉄色”は真っ赤なリンゴとともに明るい絵を演出してくれて、なかなかいい感じじゃないですか (・∀・)イイネ。車両の足回りを隠す枯れ草に煩わしさを覚えるものの、ここはリンゴの木の存在感と良好な光線状態を優先としたアングルに納得し、雑草には目をつむることとしました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
ちなみにこの“台鉄色”ですが、今月中(11月中)に運行を終了してしまう予定だそうで(塗装変更?車両自体の退役?)、まもなく見納めとなる模様 (´・ω・`)ショボン。その引退の花道にリンゴが花を添えて・・・いや、実を添えて(?)くれました (*’∀’*)リンゴ。
さて、ちょっと慌ただしくも、キハ110系の「おいこっと」から始まり、“白一色”と“台鉄色”の二本の115系まで効率よく、念願だったリンゴとの組み合わせが撮れてじゅうぶんに満足 ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。あらためてこの界隈の線路際にリンゴが残されていた状況にありがたみを感じながら、このまま当地でさらに北しなの線の撮影を続けていてもいいのですが、ここのほかに長野でリンゴのイメージを持つ鉄道路線といえば近隣にもうひとつあるんです σ(゚・゚*)ンー…。その沿線に好条件でリンゴが残されている保証はないけれど「“ふじ”の収穫はこれから」と聞いて少し期待が高まり (*゚ェ゚))フムフム、せっかくならばリンゴの収穫時期というこの機会にそちらの別路線のほうへも行ってみたくなりました (・∀・)イイネ。
そこで、北しなの線での撮影はこれにて終了とし、豊野の駅から列車で移動します ...(((o*・ω・)o。
そこで、北しなの線での撮影はこれにて終了とし、豊野の駅から列車で移動します ...(((o*・ω・)o。
豊野のホームに入ってきた
長野ゆき上り列車は
飯山線からの直通列車で
来る時と同じくキハ110系でした。
(゚ー゚*)キハ
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
終点まで乗って
長野に戻ってきました。
(=゚ω゚)ノ゙タライマ
ちなみに長野のホームの
駅名標にデザインされているのは
当地のシンボル的な名刹の善光寺です。
▲信越本線 長野
長野ゆき上り列車は
飯山線からの直通列車で
来る時と同じくキハ110系でした。
(゚ー゚*)キハ
▲しなの鉄道北しなの線 豊野
終点まで乗って
長野に戻ってきました。
(=゚ω゚)ノ゙タライマ
ちなみに長野のホームの
駅名標にデザインされているのは
当地のシンボル的な名刹の善光寺です。
▲信越本線 長野
豊野1033-(北しなの線130D)-長野1048
北しなの線の上り列車(飯山線からの直通列車)に乗って15分、来た道を戻る形で着いたのは多数の路線が集まる長野。ここで次の撮影目的となる路線へと乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
北しなの線と同様、沿線の各所にりんご畑が広がっているその路線とは・・・おっとその前に、ここ長野でちょっと早めの昼食をいただいていくこととしましょうか (›´ω`‹ )ハラヘッタ。
北しなの線の上り列車(飯山線からの直通列車)に乗って15分、来た道を戻る形で着いたのは多数の路線が集まる長野。ここで次の撮影目的となる路線へと乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
北しなの線と同様、沿線の各所にりんご畑が広がっているその路線とは・・・おっとその前に、ここ長野でちょっと早めの昼食をいただいていくこととしましょうか (›´ω`‹ )ハラヘッタ。
りんごの里の撮り鉄、後編に続きます・・・(*’∀’*)リンゴ♪。
2023-11-11 11:11
碓氷峠鉄道文化むら・・・EF63重連運転 撮影記 [鉄道写真撮影記]
“アレ”からもう26年になるのか・・・(´ω`)シミジミ。
そう聞くとおおむね40代以上の鉄ちゃんはピンとくるかな?
1997年10月1日、翌年に長野県での冬季五輪開催を控える状況で新たに誕生したのが、東京都心と長野のあいだをダイレクトに結ぶ新幹線(正式には高崎で上越新幹線から分岐)。それは現在の北陸新幹線の一部に含まれるもので(北陸新幹線の初期開業区間)、当時は“長野新幹線”と呼ばれていました(一時は“長野行き新幹線”とも言われていましたっけ)( ̄ω ̄*)ナガノユキ。
でもその華々しい新幹線開業の裏では、数々の困難を伴う長い歴史に終止符を打った鉄路があります。むしろ当時の鉄ちゃん(鉄道趣味愛好者)は長野新幹線よりも、そちらの動向に関心が高かった人も少なくなかったのではないでしょうか (-`ω´-*)ウム。
そう聞くとおおむね40代以上の鉄ちゃんはピンとくるかな?
1997年10月1日、翌年に長野県での冬季五輪開催を控える状況で新たに誕生したのが、東京都心と長野のあいだをダイレクトに結ぶ新幹線(正式には高崎で上越新幹線から分岐)。それは現在の北陸新幹線の一部に含まれるもので(北陸新幹線の初期開業区間)、当時は“長野新幹線”と呼ばれていました(一時は“長野行き新幹線”とも言われていましたっけ)( ̄ω ̄*)ナガノユキ。
でもその華々しい新幹線開業の裏では、数々の困難を伴う長い歴史に終止符を打った鉄路があります。むしろ当時の鉄ちゃん(鉄道趣味愛好者)は長野新幹線よりも、そちらの動向に関心が高かった人も少なくなかったのではないでしょうか (-`ω´-*)ウム。
長野新幹線が開業する以前に東京〜長野のメインルートとして使われてきた在来線の信越本線は、新幹線と並行した区間となる高崎と長野のあいだのうち、群馬県側の高崎〜横川(よこかわ)と、長野市近郊の篠ノ井(しののい)〜長野をJRが引き続き運営し(路線名もそのまま信越本線)、軽井沢〜篠ノ井は長野県などが出資する第三セクター鉄道のしなの鉄道(しなの鉄道線)に転換されました (・o・*)ホホゥ。
駄菓子菓子(だがしかし)横川と軽井沢のあいだの一駅間(11.2キロ)は、群馬と長野の県境にまたがる碓氷峠(うすいとうげ)を越えるための急勾配が古くから当線の・・・いや、国内の鉄道としてみても屈指の“難所”とされており、ここを通る列車は峠越えを補助する専用の電気機関車(補機)を麓側に必ず連結しなくてはならず、その効率性や採算性、安全面などを協議した結果、当区間は鉄道での存続を断念して路線バスへの転換を決定 (・∀・`)バス…。信越本線の横川〜軽井沢(通称・碓氷線、ファンの間での俗称は“ヨコカル”)は長野新幹線開業の前日となる9月30日をもって廃止となったのです (´・ω・`)ショボン。
その“ヨコカル”の最終日には当区間の乗り納めと、廃止に伴って全機が引退となる補機のEF63形電気機関車(通称・ロクサン)を惜しみ、全国各地からたくさんのファンが集まりました サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~。
ちなみに私もその一人です (゚∀゚)アヒャ☆。
その“ヨコカル”の最終日には当区間の乗り納めと、廃止に伴って全機が引退となる補機のEF63形電気機関車(通称・ロクサン)を惜しみ、全国各地からたくさんのファンが集まりました サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~。
ちなみに私もその一人です (゚∀゚)アヒャ☆。
ヨコカルの廃止が近づく97年9月。
補機を務めるロクサンの各機には
ヘッドマークが付けられて
沿線は多くのファンで賑わいました。
パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝパシャ☆
▲97.9 信越本線 軽井沢-横川
横川の駅構内や近隣の各所にも
このような垂れ幕が掲げられて
惜別と感謝の気持ちを表しています。
(´・∀・)ノ【アリガト サヨナラ】\(・∀・`)
▲97.9 信越本線 横川
なお、ロクサンのみならず、
信越本線を走っていた在来線の特急
「あさま」(上野〜長野・直江津)や
「白山」(上野〜金沢)なども
長野新幹線開業の前日をもって
すべて廃止となりました。
(´ω`)ナツカシス
▲97.9 信越本線 横川-軽井沢
補機を務めるロクサンの各機には
ヘッドマークが付けられて
沿線は多くのファンで賑わいました。
パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝパシャ☆
▲97.9 信越本線 軽井沢-横川
横川の駅構内や近隣の各所にも
このような垂れ幕が掲げられて
惜別と感謝の気持ちを表しています。
(´・∀・)ノ【アリガト サヨナラ】\(・∀・`)
▲97.9 信越本線 横川
なお、ロクサンのみならず、
信越本線を走っていた在来線の特急
「あさま」(上野〜長野・直江津)や
「白山」(上野〜金沢)なども
長野新幹線開業の前日をもって
すべて廃止となりました。
(´ω`)ナツカシス
▲97.9 信越本線 横川-軽井沢
そんなヨコカルの廃止から四半世紀(25年)の節目となった昨年(2022年)には、横川にある碓氷線に関連した保存施設の「碓氷峠鉄道文化むら」でさまざまな記念イベントが催されたそうですが、今年は廃止日の9月30日が週末の土曜日に重なることから(また本年は後述する“碓氷新線開通60周年”の節目でもあります)、やはり同施設にてメモリアルイベントが企画されているとのこと (゚∀゚)オッ!。
そこで今回は26年前の当時を偲びながら、ヨコカルの歴史を今に伝える「碓氷峠鉄道文化むら」を訪れてみようと思います (・∀・)イイネ。
9月30日(土)
あまり天気の記憶はないけど、当時の写真を見ると26年前のヨコカルはどうやら晴れていたっぽい9月30日。でも今年のきょうは秋雨前線の影響で群馬(横川)の予報は“曇り時々雨”。どうもこのところ関東の週末はカラッとした秋晴れになりませんね・・・σ(・ω・`)ウーン…。
そこで今回は26年前の当時を偲びながら、ヨコカルの歴史を今に伝える「碓氷峠鉄道文化むら」を訪れてみようと思います (・∀・)イイネ。
9月30日(土)
あまり天気の記憶はないけど、当時の写真を見ると26年前のヨコカルはどうやら晴れていたっぽい9月30日。でも今年のきょうは秋雨前線の影響で群馬(横川)の予報は“曇り時々雨”。どうもこのところ関東の週末はカラッとした秋晴れになりませんね・・・σ(・ω・`)ウーン…。
いつもの私はおもに気分的な理由で、時間に余裕があれば東京や上野などのターミナル駅から乗ることが多い高崎線や宇都宮線の下り列車ですが、今日は予定していた時間より家を出るのがちょっと遅れたため ε=┌(;゚д゚)┘チコク!、新宿から埼京線で赤羽(あかばね)へショートカットし、そこから高崎線の高崎ゆきに乗り込みました ε-(´o`A フゥ…。赤羽からでも席には座れたけど、ボックス席の窓側は空いてなったな(途中の深谷で空いたボックス席に移動w)。
都内からおよそ二時間で高崎 ( ̄  ̄)タカサキ。
ここで信越本線の横川ゆきに乗り継ぐのですが、その前に私はちょっと立ち寄りたいところがあります。それは当駅構内のホーム上にあるスタンドスタイルの“駅そば屋さん” (゚¬゚*)ジュルリ。
ここで信越本線の横川ゆきに乗り継ぐのですが、その前に私はちょっと立ち寄りたいところがあります。それは当駅構内のホーム上にあるスタンドスタイルの“駅そば屋さん” (゚¬゚*)ジュルリ。
高崎駅の2・4番線ホームにある
駅そば屋さんは
最近はちょっと珍しくなった気がする
昔ながらの“吹きっ晒し”スタイル。
(´w`*)シブイ
ちなみに右奥のほうに見える211系が
これから乗る横川ゆきです。
▲23.9.30 信越本線 高崎
駅そば屋さんは
最近はちょっと珍しくなった気がする
昔ながらの“吹きっ晒し”スタイル。
(´w`*)シブイ
ちなみに右奥のほうに見える211系が
これから乗る横川ゆきです。
▲23.9.30 信越本線 高崎
列車を乗り継ぐ合間に、ちょっと遅めの朝ゴハンとして食べる駅そば (o ̄∇ ̄o)オソバ。今記事の流れでは特筆するものではないように思えるところですが、実はこの当駅名物としても知られる駅そばスタンド(高崎そば5号売店)が、店舗の老朽化を理由に来週の10月8日をもって惜しくも閉店してしまうとのこと (´・ω・`)ショボン。
多くの路線が乗り入れる高崎という場所柄、またホーム上というその立地から、きょうの私のような乗り換えの合間だけでなく、当駅を発着するSL列車や臨時列車などの撮影を待つあいだにサクッと利用していた同好の方々(鉄ちゃん)も多かったのではないでしょうか ( ̄ω ̄*)サクメシ。私もちょくちょく立ち寄らせていただいた馴染みの深いお店です(拙ブログでも過去に何度か、当店で食べたお蕎麦やカレーライスをご紹介しましたっけ)。
知らなかったけど最近では週末の金・土・日のみの営業(7:00~14:00)となっていたらしく、残す営業日は今日を入れてあと5回だけ(9/30現在)。横川へ行くのに高崎で乗り換えるなら、これは寄らないわけにいきません (-`ω´-*)ウム。おそらく私にとってここで食べる最後の一杯に選んだ “コロッケそば” をしみじみと味わわせていただきました ≠( ̄ε ̄*)ズルル。
ごちそうさま、ありがとう、高崎ホームの駅そばスタンド 人´ε`*)ゴッチャンデス。
さ、信越線に乗ろう …((((o* ̄-)o。
ごちそうさま、ありがとう、高崎ホームの駅そばスタンド 人´ε`*)ゴッチャンデス。
さ、信越線に乗ろう …((((o* ̄-)o。
在来線ホームが8番線まであり
列車によって発着番線が変わる高崎で
次の横川ゆきは4番線より発車。
高崎線が反対側の2番線に着いて
当ホームにある駅そばを食べてから
階段を上がらずに効率よく
乗り換えができました。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
(なお3番線は八高線用の切り欠きホーム)
▲23.9.30 信越本線 高崎
列車によって発着番線が変わる高崎で
次の横川ゆきは4番線より発車。
高崎線が反対側の2番線に着いて
当ホームにある駅そばを食べてから
階段を上がらずに効率よく
乗り換えができました。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
(なお3番線は八高線用の切り欠きホーム)
▲23.9.30 信越本線 高崎
高崎を起点とする信越本線はもともとその線名のとおり、信州(長野)を経て越後(新潟)へといたる全長327.1キロもの主要幹線でしたが、今記事の冒頭で述べたように北陸新幹線(旧・長野新幹線)の開業によって、部分的に第三セクター鉄道への転換や廃止となった箇所があり、現在の信越本線は“こま切れ”状態 (´д`)コマギレ…。高崎から私が乗った列車も信越本線と名乗ってはいるものの、もう信州にも越後にも線路はつながっておらず、群馬県内の高崎と横川のあいだ(27.9キロ)を結ぶだけとなった、盲腸線(距離が短くて終端が行き止まりの路線)的な存在です。
そんな寂れてしまった印象のある当区間ですが、高崎近郊という立地から通勤や通学に使う地域利用者は多く、またSL列車(SLぐんまよこかわ号)などイベント性の高い臨時列車も休日を中心にちょくちょく運行されていて、路線や沿線の活性化を図っている様子が伺えます (・o・*)ホホゥ。ちなみに今度の「SLぐんまよこかわ号」の運転日は惜しくも明日の日曜日(10/1)。きょう走ってくれたら「碓氷峠鉄道文化むら」へ行くついでに撮れたのになぁ・・・(・∀・`)ウーン…(いっぽう「文化むら」のイベント開催は本日のみ)。
安中(あんなか)、磯部(いそべ)、松井田(まついだ)と北上を続けて、車窓の左手に上毛三山(群馬の三名山)のひとつに数えられる妙義山(みょうぎさん)の山容が望めると、まもなく列車は終点の横川に到着です (・ω・)トーチャコ。
そんな寂れてしまった印象のある当区間ですが、高崎近郊という立地から通勤や通学に使う地域利用者は多く、またSL列車(SLぐんまよこかわ号)などイベント性の高い臨時列車も休日を中心にちょくちょく運行されていて、路線や沿線の活性化を図っている様子が伺えます (・o・*)ホホゥ。ちなみに今度の「SLぐんまよこかわ号」の運転日は惜しくも明日の日曜日(10/1)。きょう走ってくれたら「碓氷峠鉄道文化むら」へ行くついでに撮れたのになぁ・・・(・∀・`)ウーン…(いっぽう「文化むら」のイベント開催は本日のみ)。
安中(あんなか)、磯部(いそべ)、松井田(まついだ)と北上を続けて、車窓の左手に上毛三山(群馬の三名山)のひとつに数えられる妙義山(みょうぎさん)の山容が望めると、まもなく列車は終点の横川に到着です (・ω・)トーチャコ。
ゴツゴツとした険しい稜線が
特徴的な妙義山ですが、
今日は雲が低くて山頂まで見えませんね。
(≡"≡;*)モヤモヤ
▲23.9.30 信越本線 松井田-西松井田
(車窓から)
横川の広い構内にはかつて
この先の碓氷峠越えに備える
補機のロクサンが集っていましたが
今はもちろんその姿は見られません。
▲23.9.30 信越本線 横川
(車窓から)
高崎から30分ほどで横川に到着。
現在の信越本線はここで線路が途切れて
下り方(軽井沢寄り)には
終端を表す車止めが設けられています。
乂・∀・`)イキドマリ
なお下写真の右手に見えるのは
当駅名物でお馴染み
おぎのやさんの「峠の釜めし」売店。
▲23.9.30 信越本線 横川
群馬県安中市の松井田町に所在する
信越本線の横川。
素朴な趣を感じる木造駅舎です。
ふだんの当駅はさほど利用者は多くなく
落ち着いた雰囲気ですが・・・
(´ー`)マターリ
▲23.9.30 信越本線 横川
ヨコカルの最終日には
たくさんの人が詰めかけて
まるでお祭りのような賑わいでした。
(´∀`;)人大杉…
ちなみに駅舎を現在のものと見比べると
ちょっとリニューアルしていますね。
▲97.9 信越本線 横川
特徴的な妙義山ですが、
今日は雲が低くて山頂まで見えませんね。
(≡"≡;*)モヤモヤ
▲23.9.30 信越本線 松井田-西松井田
(車窓から)
横川の広い構内にはかつて
この先の碓氷峠越えに備える
補機のロクサンが集っていましたが
今はもちろんその姿は見られません。
▲23.9.30 信越本線 横川
(車窓から)
高崎から30分ほどで横川に到着。
現在の信越本線はここで線路が途切れて
下り方(軽井沢寄り)には
終端を表す車止めが設けられています。
乂・∀・`)イキドマリ
なお下写真の右手に見えるのは
当駅名物でお馴染み
おぎのやさんの「峠の釜めし」売店。
▲23.9.30 信越本線 横川
群馬県安中市の松井田町に所在する
信越本線の横川。
素朴な趣を感じる木造駅舎です。
ふだんの当駅はさほど利用者は多くなく
落ち着いた雰囲気ですが・・・
(´ー`)マターリ
▲23.9.30 信越本線 横川
ヨコカルの最終日には
たくさんの人が詰めかけて
まるでお祭りのような賑わいでした。
(´∀`;)人大杉…
ちなみに駅舎を現在のものと見比べると
ちょっとリニューアルしていますね。
▲97.9 信越本線 横川
新宿0625-(埼京653K)-赤羽0641~0650-(高崎827M)-高崎0831~0849-(信越127M)-横川0922
もう26年も経てばさすがに、横川と軽井沢のあいだの線路が繋がっていない事実は受け入れていますが (-`ω´-*)ウム、それでもこの横川という地に立つとまだ、構内の側線に“ロクサン”ことEF63形機関車が待機しているのではないかと錯覚してしまいます。この駅・・・いや、この集落一帯には常にロクサンのブロワー音(電気機関車のモーター音)が響いていたっけなぁ (≡∀≡*)トオイメ。
そんな想い出にふけりながら歩き進むと、駅からすぐのところにあるのが「碓氷峠鉄道文化むら」のメインゲート (゚∀゚)オッ!。ちなみに開園は10時からだと思って9時22分に横川へ着く列車に乗ってきた私でしたが、実際はすでに9時からオープンしていました (; ̄▽ ̄)アリャ。入園券を購入してさっそく中へ入りましょう (*・∀・)つ[チケット]。
もう26年も経てばさすがに、横川と軽井沢のあいだの線路が繋がっていない事実は受け入れていますが (-`ω´-*)ウム、それでもこの横川という地に立つとまだ、構内の側線に“ロクサン”ことEF63形機関車が待機しているのではないかと錯覚してしまいます。この駅・・・いや、この集落一帯には常にロクサンのブロワー音(電気機関車のモーター音)が響いていたっけなぁ (≡∀≡*)トオイメ。
そんな想い出にふけりながら歩き進むと、駅からすぐのところにあるのが「碓氷峠鉄道文化むら」のメインゲート (゚∀゚)オッ!。ちなみに開園は10時からだと思って9時22分に横川へ着く列車に乗ってきた私でしたが、実際はすでに9時からオープンしていました (; ̄▽ ̄)アリャ。入園券を購入してさっそく中へ入りましょう (*・∀・)つ[チケット]。
横川駅から歩いて数分のところにある
「碓氷峠鉄道文化むら」
開園時間は9:00~17:00
(冬期は16:30まで)
入園料は大人700円・小人400円。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
正門を抜けたところに広がる
エントランスエリア(シンボル広場)。
ここにはかつてEF63形の基地だった
横川運転区がありました。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
ヨコカル廃止以前の横川運転区
(旧・横川機関区)。
現在の「文化むら」のエントランス付近に
たくさんのロクサンが集っています。
(´ω`*)ナツカシス
なお三角屋根が印象的な中央の検修庫は
今も鉄道展示館として活用されています。
▲97.6 信越本線 横川運転所
屋外展示場にずらっと並べられているのは
蒸気、電気、ディーゼルの各機関車や
気動車、客車などを中心に
全国から集められた
歴史的に貴重な鉄道車両の数々。
これはなかなか壮観です。
w(゚o゚*)w オオー!
ただし屋外に置かれているのでどうしても
車体の傷みが気になるところか。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
「碓氷峠鉄道文化むら」
開園時間は9:00~17:00
(冬期は16:30まで)
入園料は大人700円・小人400円。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
正門を抜けたところに広がる
エントランスエリア(シンボル広場)。
ここにはかつてEF63形の基地だった
横川運転区がありました。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
ヨコカル廃止以前の横川運転区
(旧・横川機関区)。
現在の「文化むら」のエントランス付近に
たくさんのロクサンが集っています。
(´ω`*)ナツカシス
なお三角屋根が印象的な中央の検修庫は
今も鉄道展示館として活用されています。
▲97.6 信越本線 横川運転所
屋外展示場にずらっと並べられているのは
蒸気、電気、ディーゼルの各機関車や
気動車、客車などを中心に
全国から集められた
歴史的に貴重な鉄道車両の数々。
これはなかなか壮観です。
w(゚o゚*)w オオー!
ただし屋外に置かれているのでどうしても
車体の傷みが気になるところか。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
97年のヨコカル廃止後、横川駅に隣接していた横川運転区(旧・横川機関区)の跡地に建設され、99年に開園した「碓氷峠鉄道文化むら」(゚ー゚*)ムラ。
おもに碓氷峠にまつわる鉄道(碓氷線)の歴史的な資料や、各地から集められた貴重な実物車両の数々を保存し、園内の各エリアにて公開展示されています (*゚ェ゚)フムフム。また、トロッコ列車やミニSLなど乗り物系のアトラクションも充実しており、私のようなコアなマニアのみならず子供連れのファミリーも楽しめる施設となっています (・∀・)イイネ。
そんな園内に保存されている30あまりの車両を、ここでひとつずつひとつずつ丁寧にご説明したいところ (*ФωФ*)フフフ・・・ですが、今記事では当園の紹介でなく、あくまでも“ヨコカルのメモリアル”を主題にして話を進めようと思い、説明はそれに関わるもののみに留めておきましょう ( ´_ゝ`)フーン。
(ここからはかなりマニアックな内容なので、興味の薄いかたはサラッと流してください。(^^;)ゞ)
おもに碓氷峠にまつわる鉄道(碓氷線)の歴史的な資料や、各地から集められた貴重な実物車両の数々を保存し、園内の各エリアにて公開展示されています (*゚ェ゚)フムフム。また、トロッコ列車やミニSLなど乗り物系のアトラクションも充実しており、私のようなコアなマニアのみならず子供連れのファミリーも楽しめる施設となっています (・∀・)イイネ。
そんな園内に保存されている30あまりの車両を、ここでひとつずつひとつずつ丁寧にご説明したいところ (*ФωФ*)フフフ・・・ですが、今記事では当園の紹介でなく、あくまでも“ヨコカルのメモリアル”を主題にして話を進めようと思い、説明はそれに関わるもののみに留めておきましょう ( ´_ゝ`)フーン。
(ここからはかなりマニアックな内容なので、興味の薄いかたはサラッと流してください。(^^;)ゞ)
急勾配が連続する難所の
碓氷峠に鉄道が開通したのは
1892年(明治26年)のこと。
はじめは線路のラックレールに
車両(機関車)の歯車を噛み合わせる
いわゆる「アプト式」と呼ばれる方式を
採用していました。
(゚ー゚*)アプト
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
1912年(明治45年)の電化を経て
ED42形(1号機)は
アプト式の電気機関車として
1934年(昭和9年)に製造。
後述する新線への切り替えによる
アプト式(ラック式の旧線)の廃止まで
ヨコカルを通過する列車の
牽引や補機を務めました。
(´ω`*)シブイ
歴史的にとても価値のある当機は本来
屋内で大切に静態保存されているのですが
きょうは外へ出されていますね。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
時代が昭和の中期になると
単線かつ運行速度の遅いアプト式では
輸送の増加に対応しきれなくなり
1963年(昭和38年)にヨコカルは
複線化に伴って
ラックレールを使用しない方式(粘着式)
の新線へと切り替えられます。
それに対応した出力と重量を備え
峠越え専用の補助機関車として投入したのが
新性能機のEF63形電気機関車。
(o ̄∇ ̄o)ロクサン
「文化むら」の屋外展示場には
先行試作機の1号機が静態保存され
登場時の茶色(ぶどう色2号)を
再現しています。
(゚ー゚*)チャガマ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
峠越えに挑む列車を手助けするEF63形は
基本的に二機一組の“重連”で運用に就き
下り列車(峠を上る)では後押しを
上り列車(峠を下りる)ではストッパー役として
対象列車の麓側となる横川方に連結されました。
信越本線を代表する特急の「あさま」も
ロクサンの力を借りた列車のひとつです。
(=゚ω゚)ノ゙ヨロ
「文化むら」のエントランスエリアでは
国鉄特急色の189系「あさま」が
来園者を迎えます。
▲▲88.4 信越本線 軽井沢-横川
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
この時刻表は横川駅かな?
右上に「61.3.3改正」とあるので
国鉄末期の1986年のものだと思われます。
特急「あさま」や「白山」のほか
特急「そよかぜ」、急行「妙高」など
いま見ると懐かしさを覚える列車たち。
(´ω`*)ナツカシス
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
2次量産形以降(14号機〜)は
青とクリームが標準色となったロクサン
(13号機以前の茶色ものちに同色へ塗替え)。
やはりこの色のほうが見慣れています。
(´ー`)シックリ
元・検修庫だった鉄道展示館では
1次形の10号機を館内で静態保存。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
そしてそのロクサンの前面には
ファンが熱狂した“あの日”と同じ
ヘッドマークが装着されています。
(゚∀゚*)オオッ!
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
前後で異なるロクサンの表情。
補機として多様な車両との連結を想定した
下りの軽井沢方(②エンド側)は
双頭式連結器やジャンパ線などが装備され
ごちゃごちゃした物々しい印象です。
でもそこがロクサンらしくてカッコいい。
(*’ω’*)カッコヨ♪
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
今は「文化むら」の鉄道展示館となった
横川運転区の検修庫で整備を受ける
現役時代のロクサン。
当時はもちろん
庫内への立ち入りは禁止でしたが
これは一般公開のイベントにて
撮影したものです。
(^_[◎]oパチリ
▲97.8 信越本線 横川運転区
展示館でロクサンと縦列に置かれている
“ロクニ”ことEF62形電気機関車(54号機)。
(゚ー゚*)ロクニ
電車や気動車と違って動力を持たない
客車の列車がヨコカルを通過する際に
それを牽引する本務機として活躍。
またヨコカル以外の区間や路線でも
ロクニは幅広く使われました。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
なおヨコカルでは
ロクニが牽引する客車列車の場合でも
補機のロクサンが横川方に必ず連結され
下り列車では前のロクニと後ろのロクサンが
客車をあいだに挟む格好の
いわゆる“プッシュプル”スタイルとなります。
プッシュ( ̄▽ ̄)プル
ちなみにこの列車は廃止間際に運行された
12系客車の臨時快速「さよなら碓氷峠号」。
ファンの顔出しがすげえな・・・。
▲97.9 信越本線 横川-軽井沢
いっぽう上りの客車列車では
本務機となるロクニの前方に
ストッパーとなる重連のロクサンが連結され
なんと電気機関車が三機も連なる
迫力の“三重連”で客車を牽きます。
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
この日は和式客車の「江戸」が
峠を下ってきました。
▲97.9 信越本線 軽井沢-横川
現代の「文化むら」の展示館にて
ロクサンとロクニの連結(開放?)シーンを
イメージしてパチリ。
(^_[◎]oパチリ
きょうは入換灯や補助灯が点いているので
いっそうリアルさを感じます。
(・∀・)イイネ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
全25機が製造されたロクサンは
「文化むら」の屋外でも数機が保存されており
きょうはそちらの機体にもそれぞれに
“例のヘッドマーク”が装着されています。
(゚∀゚)オッ!
まるで最終日間近の横川運転区(下写真)を
覗き見ているみたいだなぁ・・・。
▲▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
▲97.9 信越本線 横川運転区
横川運転区が愛情をこめて製作した
“さよならヘッドマーク”には
ロクサンのみならず
過去にヨコカルの碓氷線で活躍した
機関車などがデザインされています。
( ̄。 ̄)ヘー
ED41形は先出のED42形と同様
アプト式時代の電気機関車。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
エントランスの189系「あさま」は
国鉄特急色でしたが
屋外展示場の一角に置かれたほうの同系は
JR化後にリニューアルされたもので
(通称・あさま色)
ロクサンと並んだ様は
晩年の情景を再現しているかのようです。
(゚ー゚*)アサマ
構内の側線で待機するロクサンを横目に
横川へと到着する特急「あさま」
・・・といった感じの妄想を脳内で展開。
ポヤ〜ン(*≡∀≡)。oO
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
ふだんは非公開ですが
きょうの189系は車内や運転台が
一般開放されていました。
(゚∀゚)オッ!
「あさま」の運転士さんはこんな目線で
側線のロクサンを見ていたのかな。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
碓氷峠に鉄道が開通したのは
1892年(明治26年)のこと。
はじめは線路のラックレールに
車両(機関車)の歯車を噛み合わせる
いわゆる「アプト式」と呼ばれる方式を
採用していました。
(゚ー゚*)アプト
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
1912年(明治45年)の電化を経て
ED42形(1号機)は
アプト式の電気機関車として
1934年(昭和9年)に製造。
後述する新線への切り替えによる
アプト式(ラック式の旧線)の廃止まで
ヨコカルを通過する列車の
牽引や補機を務めました。
(´ω`*)シブイ
歴史的にとても価値のある当機は本来
屋内で大切に静態保存されているのですが
きょうは外へ出されていますね。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
時代が昭和の中期になると
単線かつ運行速度の遅いアプト式では
輸送の増加に対応しきれなくなり
1963年(昭和38年)にヨコカルは
複線化に伴って
ラックレールを使用しない方式(粘着式)
の新線へと切り替えられます。
それに対応した出力と重量を備え
峠越え専用の補助機関車として投入したのが
新性能機のEF63形電気機関車。
(o ̄∇ ̄o)ロクサン
「文化むら」の屋外展示場には
先行試作機の1号機が静態保存され
登場時の茶色(ぶどう色2号)を
再現しています。
(゚ー゚*)チャガマ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
峠越えに挑む列車を手助けするEF63形は
基本的に二機一組の“重連”で運用に就き
下り列車(峠を上る)では後押しを
上り列車(峠を下りる)ではストッパー役として
対象列車の麓側となる横川方に連結されました。
信越本線を代表する特急の「あさま」も
ロクサンの力を借りた列車のひとつです。
(=゚ω゚)ノ゙ヨロ
「文化むら」のエントランスエリアでは
国鉄特急色の189系「あさま」が
来園者を迎えます。
▲▲88.4 信越本線 軽井沢-横川
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
この時刻表は横川駅かな?
右上に「61.3.3改正」とあるので
国鉄末期の1986年のものだと思われます。
特急「あさま」や「白山」のほか
特急「そよかぜ」、急行「妙高」など
いま見ると懐かしさを覚える列車たち。
(´ω`*)ナツカシス
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
2次量産形以降(14号機〜)は
青とクリームが標準色となったロクサン
(13号機以前の茶色ものちに同色へ塗替え)。
やはりこの色のほうが見慣れています。
(´ー`)シックリ
元・検修庫だった鉄道展示館では
1次形の10号機を館内で静態保存。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
そしてそのロクサンの前面には
ファンが熱狂した“あの日”と同じ
ヘッドマークが装着されています。
(゚∀゚*)オオッ!
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
前後で異なるロクサンの表情。
補機として多様な車両との連結を想定した
下りの軽井沢方(②エンド側)は
双頭式連結器やジャンパ線などが装備され
ごちゃごちゃした物々しい印象です。
でもそこがロクサンらしくてカッコいい。
(*’ω’*)カッコヨ♪
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
今は「文化むら」の鉄道展示館となった
横川運転区の検修庫で整備を受ける
現役時代のロクサン。
当時はもちろん
庫内への立ち入りは禁止でしたが
これは一般公開のイベントにて
撮影したものです。
(^_[◎]oパチリ
▲97.8 信越本線 横川運転区
展示館でロクサンと縦列に置かれている
“ロクニ”ことEF62形電気機関車(54号機)。
(゚ー゚*)ロクニ
電車や気動車と違って動力を持たない
客車の列車がヨコカルを通過する際に
それを牽引する本務機として活躍。
またヨコカル以外の区間や路線でも
ロクニは幅広く使われました。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
なおヨコカルでは
ロクニが牽引する客車列車の場合でも
補機のロクサンが横川方に必ず連結され
下り列車では前のロクニと後ろのロクサンが
客車をあいだに挟む格好の
いわゆる“プッシュプル”スタイルとなります。
プッシュ( ̄▽ ̄)プル
ちなみにこの列車は廃止間際に運行された
12系客車の臨時快速「さよなら碓氷峠号」。
ファンの顔出しがすげえな・・・。
▲97.9 信越本線 横川-軽井沢
いっぽう上りの客車列車では
本務機となるロクニの前方に
ストッパーとなる重連のロクサンが連結され
なんと電気機関車が三機も連なる
迫力の“三重連”で客車を牽きます。
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
この日は和式客車の「江戸」が
峠を下ってきました。
▲97.9 信越本線 軽井沢-横川
現代の「文化むら」の展示館にて
ロクサンとロクニの連結(開放?)シーンを
イメージしてパチリ。
(^_[◎]oパチリ
きょうは入換灯や補助灯が点いているので
いっそうリアルさを感じます。
(・∀・)イイネ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
全25機が製造されたロクサンは
「文化むら」の屋外でも数機が保存されており
きょうはそちらの機体にもそれぞれに
“例のヘッドマーク”が装着されています。
(゚∀゚)オッ!
まるで最終日間近の横川運転区(下写真)を
覗き見ているみたいだなぁ・・・。
▲▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
▲97.9 信越本線 横川運転区
横川運転区が愛情をこめて製作した
“さよならヘッドマーク”には
ロクサンのみならず
過去にヨコカルの碓氷線で活躍した
機関車などがデザインされています。
( ̄。 ̄)ヘー
ED41形は先出のED42形と同様
アプト式時代の電気機関車。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
エントランスの189系「あさま」は
国鉄特急色でしたが
屋外展示場の一角に置かれたほうの同系は
JR化後にリニューアルされたもので
(通称・あさま色)
ロクサンと並んだ様は
晩年の情景を再現しているかのようです。
(゚ー゚*)アサマ
構内の側線で待機するロクサンを横目に
横川へと到着する特急「あさま」
・・・といった感じの妄想を脳内で展開。
ポヤ〜ン(*≡∀≡)。oO
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
ふだんは非公開ですが
きょうの189系は車内や運転台が
一般開放されていました。
(゚∀゚)オッ!
「あさま」の運転士さんはこんな目線で
側線のロクサンを見ていたのかな。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
私は過去にも何回か見学や観賞に訪れている「碓氷峠鉄道文化むら」ですが、今回はこれまでといくつか違って、いつもは屋内展示されているアプト式電気機関車のED42形が屋外のエントランスエリアに引き出されていたり (゚∀゚)オッ!、通常は非公開の189系「あさま」の車内や運転台が開放されて見学ができたり (゚∀゚*)オオッ!!、さらには園内に数機が保存されているロクサンことEF63形にヨコカル廃止時のヘッドマークが掲げていたりするなど (*゚∀゚*)オオオッ!!!、ちょっとしたプレミアム感を覚えます (☆∀☆)プレミアム☆。
「聖地で味わう特別な一日」と題した本日のイベント、これを個人的にはヨコカル最終日の9月30日というきょうの日付が印象深くて、それに関連したメモリアル企画だと思い込んでいますが (´ω`)ヨコカル…、「文化むら」的には “アプト式で単線だった碓氷線が複線の新線へ切り替えられて近代化を果たした1963年から今年ででちょうど60年目の節目”となる、「碓氷新線開通60周年記念」のほうが当企画の主旨なのだそうです (*゚▽゚)/゚・:*【祝・60ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。
まあいずれにしても、このイベントの内容がいろいろと貴重な機会であることはたしかで (-`ω´-*)ウム、私にとってはとくにロクサンが掲げたヘッドマークを見るとやはり、ヨコカル最終日が思い出されて感慨深いものがあります +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。良好な保存状態で現役当時と変わらない姿のロクサンを眺めて、「わあ、今にも動き出しそう!」・・・なんてベタなことを言いたくなるところ (´∀`*)ベタ。
すると、妄想にのめり込みすぎたのか ポヤ〜ン(*≡∀≡)。oO、私の耳に「ひゅをぉぉぉ〜〜〜ん」という聞き覚えのある懐かしいブロアー音(機関車のモーター音)が響いてくるような気がするではありませんか (=゚ω゚=*)ンン!?。思わず音の鳴るほうを振り返ってみると、そこには・・・(*゚ロ゚)ハッ!
「聖地で味わう特別な一日」と題した本日のイベント、これを個人的にはヨコカル最終日の9月30日というきょうの日付が印象深くて、それに関連したメモリアル企画だと思い込んでいますが (´ω`)ヨコカル…、「文化むら」的には “アプト式で単線だった碓氷線が複線の新線へ切り替えられて近代化を果たした1963年から今年ででちょうど60年目の節目”となる、「碓氷新線開通60周年記念」のほうが当企画の主旨なのだそうです (*゚▽゚)/゚・:*【祝・60ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。
まあいずれにしても、このイベントの内容がいろいろと貴重な機会であることはたしかで (-`ω´-*)ウム、私にとってはとくにロクサンが掲げたヘッドマークを見るとやはり、ヨコカル最終日が思い出されて感慨深いものがあります +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。良好な保存状態で現役当時と変わらない姿のロクサンを眺めて、「わあ、今にも動き出しそう!」・・・なんてベタなことを言いたくなるところ (´∀`*)ベタ。
すると、妄想にのめり込みすぎたのか ポヤ〜ン(*≡∀≡)。oO、私の耳に「ひゅをぉぉぉ〜〜〜ん」という聞き覚えのある懐かしいブロアー音(機関車のモーター音)が響いてくるような気がするではありませんか (=゚ω゚=*)ンン!?。思わず音の鳴るほうを振り返ってみると、そこには・・・(*゚ロ゚)ハッ!
ロクサン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
曇天のもとでヘッドライトを煌煌と点したロクサンが、軽井沢のほうからゆっくりと慎重に峠道を下りてくる!?…(((=゚ω゚)ノ゙ヤア。 はたしてこれは夢か幻か・・・ ( ゚д゚)・・・(つд⊂)ゴシゴシ・・・(;゚д゚)ロクサン
な~んて、ヘタな大根芝居はこのくらいにして ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ、実は「文化むら」では廃止となったヨコカルの一部に残された線路(約500メートル)を使い、なんと一般の方によるEF63形電気機関車(ロクサン)の運転体験が行なわれているのです (・o・*)ホホゥ。体験といってもイベントやアトラクションではなく、当園にて学科と実技の講習(受講料3万円)を受けて修了試験に合格した者のみが運転できるという本格的なもの(体験料7000円)( ̄。 ̄)ヘー。なお、それに使われるロクサンはいまも現役当時と同様の稼働できる状態にあり、いわゆる“動態保存”の扱いとなっています(11、12、24、25号機の4機)コイツ(`・д・´;)ウゴクゾ。
私には技能的にも料金的にも運転体験への参加は到底ムリな話ですが ヾノ・∀・`)ムリムリ、体験をされている方が操って園内の一角を往復運転する“動くロクサン”は間近に眺めることができます (「゚ー゚)ドレドレ(入園すれば見学は無料w)。ブロア音を響かせていたのは、この運転体験のロクサンだったのですね (´w`)ナルヘソ。
曇天のもとでヘッドライトを煌煌と点したロクサンが、軽井沢のほうからゆっくりと慎重に峠道を下りてくる!?…(((=゚ω゚)ノ゙ヤア。 はたしてこれは夢か幻か・・・ ( ゚д゚)・・・(つд⊂)ゴシゴシ・・・(;゚д゚)ロクサン
な~んて、ヘタな大根芝居はこのくらいにして ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ、実は「文化むら」では廃止となったヨコカルの一部に残された線路(約500メートル)を使い、なんと一般の方によるEF63形電気機関車(ロクサン)の運転体験が行なわれているのです (・o・*)ホホゥ。体験といってもイベントやアトラクションではなく、当園にて学科と実技の講習(受講料3万円)を受けて修了試験に合格した者のみが運転できるという本格的なもの(体験料7000円)( ̄。 ̄)ヘー。なお、それに使われるロクサンはいまも現役当時と同様の稼働できる状態にあり、いわゆる“動態保存”の扱いとなっています(11、12、24、25号機の4機)コイツ(`・д・´;)ウゴクゾ。
私には技能的にも料金的にも運転体験への参加は到底ムリな話ですが ヾノ・∀・`)ムリムリ、体験をされている方が操って園内の一角を往復運転する“動くロクサン”は間近に眺めることができます (「゚ー゚)ドレドレ(入園すれば見学は無料w)。ブロア音を響かせていたのは、この運転体験のロクサンだったのですね (´w`)ナルヘソ。
きょうの運転体験は
25号機と11号機による重連仕業!
ε-(°ω°*)ジューレン!
なお、一般の方が重連を操作するには
運転体験で50回以上の実績が
必要だそうです。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
25号機と11号機による重連仕業!
ε-(°ω°*)ジューレン!
なお、一般の方が重連を操作するには
運転体験で50回以上の実績が
必要だそうです。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
しかも、ふだんの運転体験は一機のロクサンによる“単機”で行なわれることが多いのですが、イベントデーのきょうは二機が連なった“重連”(11+25号機)ε-(°ω°*)ジューレン!。 先述したように補機を務める際のロクサンは二機で一組が基本仕様ですから、単機ではどこか物足りなさが否めず(贅沢を言ってスミマセンw)、重連であってこそまさに“真のロクサン”と言えるでしょう (-`ω´-*)ウム。さらに本日は体験運転に使われる機体(横川方の25号機)もヘッドマーク付き (・∀・)イイネ。
きょうの私が「碓氷峠鉄道文化むら」を訪れたいちばんのお目当ては、この重連となった運転体験のロクサンを撮ることでした。現役当時を思い浮かべながら、いろいろなアングルで狙ってみます (*`・ω・´)-3フンス!。
きょうの私が「碓氷峠鉄道文化むら」を訪れたいちばんのお目当ては、この重連となった運転体験のロクサンを撮ることでした。現役当時を思い浮かべながら、いろいろなアングルで狙ってみます (*`・ω・´)-3フンス!。
二機のロクサンが手を組み
四基のパンタグラフを振りかざした様は
体験運転とは思えない迫力!
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
・・・ですが
運転席に座るのは一般の方なので
制服姿とは限りません。
この回の機関士(体験者)は
黄色いシャツのお兄さん(笑)
(゚∀゚)アヒャ☆
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
赤色の尾灯を点けた後ろ姿を狙うと
下り列車を後押ししているような
シーンに見えます。
ドスコイ (ノ・3・)ノ
ちなみにヘッドマークに記された
“シェルパ(sherpa)”とは
高峰での登山をサポートする
道先案内人を意味するものだそうで
補機として峠越えを手助けするロクサンには
「峠のシェルパ」という
愛称が付けられていました。
( ̄ω ̄*)シェルパ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
ヨコカルの廃止時には
ロクサンの製造初期を復刻したような
茶色の塗装が施されていた25号機
(もともとは青色)。
(゚ー゚*)チャガマ
ラストナンバー(最終製造機)だからか
当機はほかの機体と異なる
固有番号入りの特別なヘッドマークを
実際の最終日にも掲げていました。
( ̄。 ̄)ヘー
▲97.9 信越本線 軽井沢
留置線で待機する24号機(左)と
その脇をかすめて本線で働く25号機
・・・といった感じのイメージ。
(^_[◎]oパチリ
なお24号機のほうも
体験運転に使われる動態保存機です。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
“峠のシェルパ” 今なお健在!
(*`・ω・´)キリッ!
わずかな距離の運転体験であっても
当機の力強い走りが見られるのは
当時を知るファンとして嬉しいかぎりです。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
運転速度は遅いけど
慎重にカメラを振ってみました。
手前に植栽された木の赤い葉を添えて。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
廃止前のヨコカルでも私は
流し撮りにトライしていましたが
このころはまだ列車とのシンクロに
未熟さを感じます。
え?今もたいして変わらないって?w
(´・ω`・)エッ?
▲97.7 信越本線 軽井沢-横川
重連を強調しようと
二機の連結面をローアングルでパチリ。
ロクサンの機重による地響きが
間近に伝わります。
((((;゚∀゚))))ブルルッ!
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
そういえばこれも現役当時に
似たようなアングルで撮っていたなと。
σ(゚・゚*)デジャヴ?
ちなみにこのカット
ロクサンの向こうにちょろっと覗く
煉瓦造りの丸山変電所跡が
撮影者のこだわりポイントですた(笑)
▲95.5 信越本線 軽井沢-横川
運転体験を終えて小休止に入るロクサンを
入換作業員(当園スタッフの方)が誘導。
このようなシーンも動態保存機ならではの
自然な臨場感を覚えます。
(・∀・)イイネ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
はやくも秋色となった木の下で
次の体験者を静かに待つロクサン。
(´ー`)マターリ
過酷な峠越えを控えて
側線に待機していた現役時代よりも
その表情は心なしか
穏やかになった気がしました。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
四基のパンタグラフを振りかざした様は
体験運転とは思えない迫力!
(*゚∀゚)=3ハァハァ!
・・・ですが
運転席に座るのは一般の方なので
制服姿とは限りません。
この回の機関士(体験者)は
黄色いシャツのお兄さん(笑)
(゚∀゚)アヒャ☆
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
赤色の尾灯を点けた後ろ姿を狙うと
下り列車を後押ししているような
シーンに見えます。
ドスコイ (ノ・3・)ノ
ちなみにヘッドマークに記された
“シェルパ(sherpa)”とは
高峰での登山をサポートする
道先案内人を意味するものだそうで
補機として峠越えを手助けするロクサンには
「峠のシェルパ」という
愛称が付けられていました。
( ̄ω ̄*)シェルパ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
ヨコカルの廃止時には
ロクサンの製造初期を復刻したような
茶色の塗装が施されていた25号機
(もともとは青色)。
(゚ー゚*)チャガマ
ラストナンバー(最終製造機)だからか
当機はほかの機体と異なる
固有番号入りの特別なヘッドマークを
実際の最終日にも掲げていました。
( ̄。 ̄)ヘー
▲97.9 信越本線 軽井沢
留置線で待機する24号機(左)と
その脇をかすめて本線で働く25号機
・・・といった感じのイメージ。
(^_[◎]oパチリ
なお24号機のほうも
体験運転に使われる動態保存機です。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
“峠のシェルパ” 今なお健在!
(*`・ω・´)キリッ!
わずかな距離の運転体験であっても
当機の力強い走りが見られるのは
当時を知るファンとして嬉しいかぎりです。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
運転速度は遅いけど
慎重にカメラを振ってみました。
手前に植栽された木の赤い葉を添えて。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
廃止前のヨコカルでも私は
流し撮りにトライしていましたが
このころはまだ列車とのシンクロに
未熟さを感じます。
え?今もたいして変わらないって?w
(´・ω`・)エッ?
▲97.7 信越本線 軽井沢-横川
重連を強調しようと
二機の連結面をローアングルでパチリ。
ロクサンの機重による地響きが
間近に伝わります。
((((;゚∀゚))))ブルルッ!
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
そういえばこれも現役当時に
似たようなアングルで撮っていたなと。
σ(゚・゚*)デジャヴ?
ちなみにこのカット
ロクサンの向こうにちょろっと覗く
煉瓦造りの丸山変電所跡が
撮影者のこだわりポイントですた(笑)
▲95.5 信越本線 軽井沢-横川
運転体験を終えて小休止に入るロクサンを
入換作業員(当園スタッフの方)が誘導。
このようなシーンも動態保存機ならではの
自然な臨場感を覚えます。
(・∀・)イイネ
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
はやくも秋色となった木の下で
次の体験者を静かに待つロクサン。
(´ー`)マターリ
過酷な峠越えを控えて
側線に待機していた現役時代よりも
その表情は心なしか
穏やかになった気がしました。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
(運転体験線)
“ダダダダダダン、ダダダダダダン”と重々しく地を踏む、二機のロクサンによる重連の迫力にもう大興奮 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
これまで私が過去に「文化むら」へ来園した時の運転体験はいつも単機での実施だったため ( ̄  ̄)タンキ、個人的に重連のロクサンを撮るのは、まさにあの“ヨコカル最終日”以来となるのか・・・σ(゚・゚*)ンー…。そう考えるといっそう感慨深いものがあります。実際はわずか数百メートルほどの運転体験線ですが、私のアタマのなかではもうすっかり碓氷の峠越えへ果敢に挑むロクサンを撮っているイメージで 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜、現役のときと変わらない当機の勇姿をカメラのファインダー越しに見ると、26年という時の流れが信じられないような錯覚に陥りました (´ω`)シミジミ。
今さらながらヨコカルが廃止されたのは鉄ちゃんのひとりとして惜しく、とても残念なことだったけど (´・ω・`)ショボン、ゆかりある横川という地にヨコカルの歴史を後世につたえる「碓氷峠鉄道文化むら」が開園し、もともとの検修庫を活かした臨場感ある展示方法の静態保存や、運転体験に使用する動態保存機として“動くロクサン”が見られるとは、ホントにありがたいことだと感じています ☆感謝(*´ー`人)感謝☆。
これまで私が過去に「文化むら」へ来園した時の運転体験はいつも単機での実施だったため ( ̄  ̄)タンキ、個人的に重連のロクサンを撮るのは、まさにあの“ヨコカル最終日”以来となるのか・・・σ(゚・゚*)ンー…。そう考えるといっそう感慨深いものがあります。実際はわずか数百メートルほどの運転体験線ですが、私のアタマのなかではもうすっかり碓氷の峠越えへ果敢に挑むロクサンを撮っているイメージで 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜、現役のときと変わらない当機の勇姿をカメラのファインダー越しに見ると、26年という時の流れが信じられないような錯覚に陥りました (´ω`)シミジミ。
今さらながらヨコカルが廃止されたのは鉄ちゃんのひとりとして惜しく、とても残念なことだったけど (´・ω・`)ショボン、ゆかりある横川という地にヨコカルの歴史を後世につたえる「碓氷峠鉄道文化むら」が開園し、もともとの検修庫を活かした臨場感ある展示方法の静態保存や、運転体験に使用する動態保存機として“動くロクサン”が見られるとは、ホントにありがたいことだと感じています ☆感謝(*´ー`人)感謝☆。
コスモス越しに見るロクサン。
26年前と同じ秋の風を感じました。
(゚- ゚)アキ
ちなみにこの写真は今年のものですが
ススキ越しにロクサンをボカした
今記事トップのタイトル写真は
実は26年前の撮影です。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
26年前と同じ秋の風を感じました。
(゚- ゚)アキ
ちなみにこの写真は今年のものですが
ススキ越しにロクサンをボカした
今記事トップのタイトル写真は
実は26年前の撮影です。
▲23.9.30 碓氷峠鉄道文化むら
あの日からちょうど26年目となる9月30日に訪れた「碓氷峠鉄道文化むら」。
時おり雨がぱらつくぐずついた空模様だったけど、ヨコカルを懐かしむ過去の想い出と現代での妄想にどっぷりと浸れた、充実の一日が楽しめました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
さ、“アレ”を食べて帰ろう (゚¬゚〃)ジュルリ。
時おり雨がぱらつくぐずついた空模様だったけど、ヨコカルを懐かしむ過去の想い出と現代での妄想にどっぷりと浸れた、充実の一日が楽しめました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
さ、“アレ”を食べて帰ろう (゚¬゚〃)ジュルリ。
退園後にいただくお昼ゴハンはもちろん
横川名物「峠の釜めし」(¥1,300)。
駅前にある「おぎのや」さんの
本店でいただきます。
(o ̄∇ ̄o)カマメシ♪
こちらのお味も26年前・・・
いや、それ以前からずっと変わらず
安定した美味しさでした。
(゚д゚)ウマー!
ヨコカルの撮影ポイントで
列車を眺めながら食べた釜めし。
友達とおふざけで撮ったこんな写真も
今となっては貴重な記録・・・かな?(笑)
(。A。)アヒャ☆
97.4 信越本線 軽井沢-横川
横川のホームに入ってきた
信越本線の高崎ゆき普通列車。
現在の当区間(高崎〜横川)は
ロングシートの211系で賄われているので
さすがに車内で釜めしは
ちょっと食べづらいよね・・・。
(^^;)ゞポリポリ
▲23.9.30 信越本線 横川
横川名物「峠の釜めし」(¥1,300)。
駅前にある「おぎのや」さんの
本店でいただきます。
(o ̄∇ ̄o)カマメシ♪
こちらのお味も26年前・・・
いや、それ以前からずっと変わらず
安定した美味しさでした。
(゚д゚)ウマー!
ヨコカルの撮影ポイントで
列車を眺めながら食べた釜めし。
友達とおふざけで撮ったこんな写真も
今となっては貴重な記録・・・かな?(笑)
(。A。)アヒャ☆
97.4 信越本線 軽井沢-横川
横川のホームに入ってきた
信越本線の高崎ゆき普通列車。
現在の当区間(高崎〜横川)は
ロングシートの211系で賄われているので
さすがに車内で釜めしは
ちょっと食べづらいよね・・・。
(^^;)ゞポリポリ
▲23.9.30 信越本線 横川
横川1510-(信越146M)-高崎1541~1611-(高崎2849Y)-新宿1759
2023-10-07 07:07
わたらせ渓谷鐵道・・・国鉄色DE10「トロッコ」撮影記 [鉄道写真撮影記]
私のような鉄道好きの“鉄ちゃん”にとって“駅”といえば当然のごとく、列車が発着する“鉄道の駅”をまっ先に思い浮かべますが σ(゚・゚*)ンー…、クルマやバイク、自転車などでドライブやサイクリングを愉しまれる方々には、道路沿いにある“道の駅”も馴染みがあるでしょう。
今旅の私がふらっと立ち寄ったのは ...(((o*・ω・)o、群馬県の桐生(きりゅう)から栃木県の足尾(あしお)を経て日光(にっこう)へと抜ける、国道122号線(正式には日光が起点で埼玉県の岩槻が終点らしい)の沿道にある、桐生市黒保根町の「道の駅 くろほね・やまびこ」(゚ー゚*)クロホネ。
今旅の私がふらっと立ち寄ったのは ...(((o*・ω・)o、群馬県の桐生(きりゅう)から栃木県の足尾(あしお)を経て日光(にっこう)へと抜ける、国道122号線(正式には日光が起点で埼玉県の岩槻が終点らしい)の沿道にある、桐生市黒保根町の「道の駅 くろほね・やまびこ」(゚ー゚*)クロホネ。
近年の道の駅は、洗練されたデザインの物産館に小粋なレストランやカフェなどを併設したオサレなものも多いなか(例えば以前に私が富山で訪れた「道の駅 あまはらし」など)、この「くろほね・やまびこ」は地元の農産物を扱う昔ながらの産地直売所といった印象の鄙びた雰囲気 (´ω`*)シブイ。でもそれがまた、渓流の渡良瀬川(わたらせがわ)を擁する自然豊かな里山にマッチして、どこか郷愁感が漂う落ち着いた風情を醸し出しています (´ー`)マターリ。ちなみに“くろほね”とはご当地の地域名(旧・黒保根町)を由来とするもの(“やまびこ”はたぶん山彦のことで、もともと道の駅となる前は“やまびこ”っていう名の産直所だったらしい)。
そんな「くろほね・やまびこ」は先述したとおり道の駅であって鉄道の駅ではなく、ここに列車が発着することはありません。
では、いったい私はここへ何をしに来たのかというと σ(゚・゚*)ンー…、農産物直売所の店頭に並べられた大小のカボチャを横目に見ながら向かったのは、敷地内に併設されたお食事処(食堂)(*・ω・)ノ゙チワッス。古民家を改装したものだと思われるその味わい深い趣の店内で、おもむろに自販機へ千円札を投入して950円の食券を購入し、それを調理場直結のカウンターへと差し出します。そしてひとこと・・・
「もつ煮定食、お願いします ( -`д-´)キリッ」(yamatonosukeさん風にw)
では、いったい私はここへ何をしに来たのかというと σ(゚・゚*)ンー…、農産物直売所の店頭に並べられた大小のカボチャを横目に見ながら向かったのは、敷地内に併設されたお食事処(食堂)(*・ω・)ノ゙チワッス。古民家を改装したものだと思われるその味わい深い趣の店内で、おもむろに自販機へ千円札を投入して950円の食券を購入し、それを調理場直結のカウンターへと差し出します。そしてひとこと・・・
「もつ煮定食、お願いします ( -`д-´)キリッ」(yamatonosukeさん風にw)
は?いったい何の話をしているのかって? (´・ω`・)エッ?
9月9日(土)
9月9日(土)
先日に宇都宮へ行ったときと同じように
東京から乗るE231系の普通列車。
でも今日は高崎線の高崎ゆきです。
▲東海道本線 東京
高崎で乗り継いだ211系は
両毛線の小山ゆき下り普通列車。
(゚ー゚*)ニゲゲ
▲信越本線 高崎
東京から乗るE231系の普通列車。
でも今日は高崎線の高崎ゆきです。
▲東海道本線 東京
高崎で乗り継いだ211系は
両毛線の小山ゆき下り普通列車。
(゚ー゚*)ニゲゲ
▲信越本線 高崎
きのうは台風(13号)の影響で雨が激しかった関東地方 ザアアァァ…:il!:il|个c(´д`;))!l|il:|;。明けてきょうの土曜日は台風一過の晴天を期待したものの、台風由来の湿った空気が居残っていまいちスッキリとしない曇天です σ(・∀・`)ウーン…。
そんな空模様の日に私が撮影目的で訪れたのは、群馬県の桐生と栃木県足尾町の間藤(まとう)をむすぶローカル線(第三セクター鉄道)の「わたらせ渓谷鐡道」。通称 “わ鐡” (゚ー゚*)ワ。
そんな空模様の日に私が撮影目的で訪れたのは、群馬県の桐生と栃木県足尾町の間藤(まとう)をむすぶローカル線(第三セクター鉄道)の「わたらせ渓谷鐡道」。通称 “わ鐡” (゚ー゚*)ワ。
桐生で両毛線から乗り換えたのが
今旅の目的路線である
わたらせ渓谷鉄道。
(゚ー゚*)ワテツ
間藤ゆき下り普通列車は
単行のディーゼルカーです。
座席配置がクロスシート仕様の
WKT-520形に当たったのはラッキー。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲わたらせ渓谷鐡道 桐生
今旅の目的路線である
わたらせ渓谷鉄道。
(゚ー゚*)ワテツ
間藤ゆき下り普通列車は
単行のディーゼルカーです。
座席配置がクロスシート仕様の
WKT-520形に当たったのはラッキー。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲わたらせ渓谷鐡道 桐生
わたらせ渓谷鉄道(わたらせ渓谷線)はその線名のとおり、ほぼ全線が渓流の渡良瀬川へ沿うように線路が敷かれていて、列車の車窓からもその風光明媚な自然風景を愉しむことができます (・∀・)イイネ。とくにこれから迎える紅葉シーズンは多くの観光客で賑わうでしょう。
そんな沿線環境を活かして週末や行楽シーズンを中心に当線で運行されているのが、客室の一部が窓ガラスのないオープンデッキ構造となった、いわゆる「トロッコ列車」( ̄▽ ̄)トロッコ。
わ鉄のトロッコ列車には二種類あり、ひとつは気動車(ディーゼルカー)タイプで自走式の「トロッコわっしー号」(WKT-550形)。もうひとつが客車方式でディーゼル機関車(DE10形)の牽引によって運転される「トロッコわたらせ渓谷号」(・o・*)ホホゥ。
後者には茶色いトロッコ客車(わ99形)に色を合わせた専用の機関車(DE10 1537)が用意されていて通常はそれを使うことが多いのですが、当機の検査などによるものなのか私には事情が詳しくわからないけど、今夏の運転では専用機でなく予備的な位置づけとなっているもう一台の同型機(DE10 1678)がトロッコの牽引に連日登板しているとの情報をSNSなどで目にしました (゚∀゚)オッ!。実はこちらの予備的な機関車は製造時からのオリジナルである朱色の“国鉄色”を維持しており、国鉄時代の車両が好きな私にとっては気になる存在なんです σ(゚・゚*)ンー…。
はたして、「トロッコわたらせ渓谷号」の始発駅となっている途中の大間々(おおまま)で、運転準備中の当該列車の様子を乗っていた普通列車の窓から見てみると・・・(「゚ー゚)ドレドレ
わ鉄のトロッコ列車には二種類あり、ひとつは気動車(ディーゼルカー)タイプで自走式の「トロッコわっしー号」(WKT-550形)。もうひとつが客車方式でディーゼル機関車(DE10形)の牽引によって運転される「トロッコわたらせ渓谷号」(・o・*)ホホゥ。
後者には茶色いトロッコ客車(わ99形)に色を合わせた専用の機関車(DE10 1537)が用意されていて通常はそれを使うことが多いのですが、当機の検査などによるものなのか私には事情が詳しくわからないけど、今夏の運転では専用機でなく予備的な位置づけとなっているもう一台の同型機(DE10 1678)がトロッコの牽引に連日登板しているとの情報をSNSなどで目にしました (゚∀゚)オッ!。実はこちらの予備的な機関車は製造時からのオリジナルである朱色の“国鉄色”を維持しており、国鉄時代の車両が好きな私にとっては気になる存在なんです σ(゚・゚*)ンー…。
はたして、「トロッコわたらせ渓谷号」の始発駅となっている途中の大間々(おおまま)で、運転準備中の当該列車の様子を乗っていた普通列車の窓から見てみると・・・(「゚ー゚)ドレドレ
国鉄色のデーテン(DE10)を確認!(*`д´)ゞ ピシッ!
やはりSNSなどで得た情報のとおり、本日の「トロッコわたらせ渓谷号」も専用機ではなく国鉄色のほうが牽引を担当。これには曇天の空模様でも私のテンションは一気に上がります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
その「トロッコわたらせ渓谷号」を沿線の撮影ポイントで撮るべく、先行する普通列車から私が下車したのは本宿(もとじゅく)。
やはりSNSなどで得た情報のとおり、本日の「トロッコわたらせ渓谷号」も専用機ではなく国鉄色のほうが牽引を担当。これには曇天の空模様でも私のテンションは一気に上がります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
その「トロッコわたらせ渓谷号」を沿線の撮影ポイントで撮るべく、先行する普通列車から私が下車したのは本宿(もとじゅく)。
桐生市黒保根町に所在する
無人駅の本宿。
夏場は木々の葉に遮られて
川面がちょっと見にくいけど
そのホームは渡良瀬川に面しています。
▲わたらせ渓谷鐡道 本宿
そして本宿のホームは
道路から一段低いところに位置し
斜面に備えられた階段がアプローチとなるため
駅を表す看板が道沿いに立てられています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲わたらせ渓谷鐡道 本宿
無人駅の本宿。
夏場は木々の葉に遮られて
川面がちょっと見にくいけど
そのホームは渡良瀬川に面しています。
▲わたらせ渓谷鐡道 本宿
そして本宿のホームは
道路から一段低いところに位置し
斜面に備えられた階段がアプローチとなるため
駅を表す看板が道沿いに立てられています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲わたらせ渓谷鐡道 本宿
東京0620-(高崎1822E)-高崎0815~0836-(両毛439M)-桐生0928~1006-(わたらせ渓谷717D)-本宿1037
続行でやってくる「トロッコわたらせ渓谷号」の通過までは、あと30分ほど。
あまり時間に余裕はないけれど、目的地の撮影ポイントは本宿の駅から線路に沿った国道を上り方向へ歩いてわずか5分という、列車利用の“徒歩鉄”に嬉しい近さ ...(((o*・ω・)o。そこなら焦らずともじゅうぶん間に合います ъ(゚Д゚)ナイス。
続行でやってくる「トロッコわたらせ渓谷号」の通過までは、あと30分ほど。
あまり時間に余裕はないけれど、目的地の撮影ポイントは本宿の駅から線路に沿った国道を上り方向へ歩いてわずか5分という、列車利用の“徒歩鉄”に嬉しい近さ ...(((o*・ω・)o。そこなら焦らずともじゅうぶん間に合います ъ(゚Д゚)ナイス。
ここは駅近のお手軽な場所ではあるものの、国道の路肩から少し高い目線でカーブする線路とその向こうに流れる渡良瀬川を望める、なかなかの好撮影地 (・∀・)イイネ。夏場は木々の葉が生い茂って川面がスッキリと見えないのは惜しいところですが、緑が豊かなのも今の時期らしい風情と捉えるべきか (´ω`)ウン。
きょうは台風明けの曇天という出撃を決断しにくい微妙な天候だからか同業者は誰もおらず、ここでは私ひとりで「トロッコわたらせ渓谷号」を迎えます (・ω・)ポツン。
きょうは台風明けの曇天という出撃を決断しにくい微妙な天候だからか同業者は誰もおらず、ここでは私ひとりで「トロッコわたらせ渓谷号」を迎えます (・ω・)ポツン。
国鉄色デーテン(DE10)のトロッコが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
せせらぎをかき消すようにエンジン音を響かせて、朱色のDE10形を先頭にした「トロッコわたらせ渓谷号」が川べりのカーブをゆっくりと進みゆきます ノコノコ...(((o*・ω・)o。ふだんの専用機による色が統一された編成もけっして嫌じゃないけど、個人的にやっぱり国鉄色のディーゼル機関車は落ち着いた印象でいいものだなぁ +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。
4両編成の客車のうち真ん中の二両がオープンデッキ構造のトロッコ車両となっているのですが(前後はふつうの客車)、この角度で見るとそれがあまり目立たず(あえて狙ったアングル?)、国鉄色のDE10形が茶色っぽい客車を従える様はまるで、昭和の国鉄時代に旧型客車で運行されていた地方のローカル列車(客車列車、ローカル客レ)を思わせるような、懐かしい趣が感じられるではありませんか ( ̄  ̄*)キャクレ。う〜んシブい。
ちなみに背景の右側へ写り込んだ国道はけっこう交通量が多いのに、このときはタイミングよくクルマが一台も通らなかったのは、ちょっとしたラッキーでした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
せせらぎをかき消すようにエンジン音を響かせて、朱色のDE10形を先頭にした「トロッコわたらせ渓谷号」が川べりのカーブをゆっくりと進みゆきます ノコノコ...(((o*・ω・)o。ふだんの専用機による色が統一された編成もけっして嫌じゃないけど、個人的にやっぱり国鉄色のディーゼル機関車は落ち着いた印象でいいものだなぁ +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。
4両編成の客車のうち真ん中の二両がオープンデッキ構造のトロッコ車両となっているのですが(前後はふつうの客車)、この角度で見るとそれがあまり目立たず(あえて狙ったアングル?)、国鉄色のDE10形が茶色っぽい客車を従える様はまるで、昭和の国鉄時代に旧型客車で運行されていた地方のローカル列車(客車列車、ローカル客レ)を思わせるような、懐かしい趣が感じられるではありませんか ( ̄  ̄*)キャクレ。う〜んシブい。
ちなみに背景の右側へ写り込んだ国道はけっこう交通量が多いのに、このときはタイミングよくクルマが一台も通らなかったのは、ちょっとしたラッキーでした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
“ピッ!”っと短笛を鳴らして
鉄橋にさしかかるところを
引いたアングルにしてもう一枚。
(^_[◎]oパチリ
このくらいの角度で眺めるDE10形は
長さが違う前後のボンネットによる
アンバランスな凸形スタイルが
際立って見えますね。
( ̄  ̄*)デーテン
▲わたらせ渓谷鐡道 上神梅-本宿
鉄橋にさしかかるところを
引いたアングルにしてもう一枚。
(^_[◎]oパチリ
このくらいの角度で眺めるDE10形は
長さが違う前後のボンネットによる
アンバランスな凸形スタイルが
際立って見えますね。
( ̄  ̄*)デーテン
▲わたらせ渓谷鐡道 上神梅-本宿
日が差さないあいにくの曇天だけど、このシブい印象の編成には案外マッチした空模様のようにも思えるし、もし晴れたとしても今の時間帯のこの場所はおそらく逆光となるハズなので、これはこれでよかったのかもしれません (-`ω´-*)ウム。何よりこの山里風景という穏やかなロケーションで国鉄色のDE10形が牽く列車を撮れたことが、国鉄型好きの私としては満足でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
さて、撮影を終えて時刻は11時過ぎ。ちょっと早いけどお昼時 (›´ω`‹)ハラヘタ・・・ですが、田舎のローカル線では下車した駅や訪れた場所の近くに飲食店や商店などがまったく見あたらず、ときには食事にありつけないなんて場合もよくあること (´д`;)アウ…。そこで今回はいちおう事前に本宿の撮影ポイント付近で何か食べられそうなお店がないか調べてみたところ \_ヘヘ(- ̄*)ドレドレ、実はすぐ近くにラーメン屋さんが一軒と、さらに国道を2キロほど進んだあたりに「道の駅」があることを確認 (・o・*)ホホゥ。これなら“食事難民”にならなくて済みそうです ε-(´∇`*)ホッ。
しかもその「道の駅」のお食事処(食堂)は、豚のモツとコンニャクを自家製の味噌で煮込んだ“もつ煮”が名物らしく、それを食べた人の感想も評価が高い ホシ('ω')ミッツデス。これは魅力的で思わずヨダレが出てしまいます (゚¬゚)ジュルリ。この道の先に美味しいものがあるとわかれば、2キロくらいは大した距離じゃありません。たかだか歩いて20分くらいでしょう ...(((o*・ω・)o。
しかもその「道の駅」のお食事処(食堂)は、豚のモツとコンニャクを自家製の味噌で煮込んだ“もつ煮”が名物らしく、それを食べた人の感想も評価が高い ホシ('ω')ミッツデス。これは魅力的で思わずヨダレが出てしまいます (゚¬゚)ジュルリ。この道の先に美味しいものがあるとわかれば、2キロくらいは大した距離じゃありません。たかだか歩いて20分くらいでしょう ...(((o*・ω・)o。
・・・で、やってきたのが今記事冒頭の「道の駅 くろほね・やまびこ」(゚ー゚*)クロホネ。
んで、オーダーしたのが名物だという“もつ煮定食”です (゚¬゚*)モツニ。
店内の高い天井に張り巡らされた立派な梁などを見上げながら待っていると、それは程なくして私の前に運ばれてきました オマタヘ(((*゚▽゚)つ_▼▽_。御飯とお吸い物(?)や副菜とともにお盆へ並べられた、大きなどんぶりの“もつ煮込み”から漂う味噌の甘い匂いが空腹の胃袋を刺激します (゚A゚;)ゴクリ。
さっそく七味をパッと振ってひと口・・・う、ウマい! (*°▽°*)ウンマ!。
んで、オーダーしたのが名物だという“もつ煮定食”です (゚¬゚*)モツニ。
店内の高い天井に張り巡らされた立派な梁などを見上げながら待っていると、それは程なくして私の前に運ばれてきました オマタヘ(((*゚▽゚)つ_▼▽_。御飯とお吸い物(?)や副菜とともにお盆へ並べられた、大きなどんぶりの“もつ煮込み”から漂う味噌の甘い匂いが空腹の胃袋を刺激します (゚A゚;)ゴクリ。
さっそく七味をパッと振ってひと口・・・う、ウマい! (*°▽°*)ウンマ!。
「道の駅 くろほね・やまびこ」名物の
“もつ煮定食(950円)”
どんぶりいっぱいに盛られたもつ煮は
甘めの味噌が優しいお味で
ご当地産の“くろほね米”を炊いた
つやつやの御飯によく合います。
これは箸が止まりません!
(もちろんビールにも合う合うw)
モツニ(゚д゚)ウマー!
“もつ煮定食(950円)”
どんぶりいっぱいに盛られたもつ煮は
甘めの味噌が優しいお味で
ご当地産の“くろほね米”を炊いた
つやつやの御飯によく合います。
これは箸が止まりません!
(もちろんビールにも合う合うw)
モツニ(゚д゚)ウマー!
牛や豚などの畜産業が盛んな地域で、食肉の加工行程から大量に出るホルモン(内臓)を無駄なく消費しようと、はじめはおもに地元の方を中心に食べられていたという群馬の“もつ煮”ですが、当地を通るトラックドライバーなどの口コミでその美味しさが全国的に広まり、今では県を代表する名物のひとつとなっています (・o・*)ホホゥ。また群馬の“もつ煮”は野菜をほとんど使わずにモツとコンニャクだけで作るのが特徴だそうで、私がいただいたものもそのとおりシンプルな具材でした ≠( ̄〜 ̄*)モグモグ。
副菜はサラダやお新香のほか
白菜のお吸い物だと思っていた椀物は
自家製粉の手打ちそば(十割?)を使った
温かいお蕎麦でした。
(・∀・)オソバ
また煮付けたコンニャクも自家製で
弾力のある食感が美味しい。
( ̄〜 ̄*)コンニャク
隣接する産直所で販売されている
自家製のコンニャクは1kg 570円。
白菜のお吸い物だと思っていた椀物は
自家製粉の手打ちそば(十割?)を使った
温かいお蕎麦でした。
(・∀・)オソバ
また煮付けたコンニャクも自家製で
弾力のある食感が美味しい。
( ̄〜 ̄*)コンニャク
隣接する産直所で販売されている
自家製のコンニャクは1kg 570円。
ちなみに群馬の“もつ煮”といえば、上越線の沿線で同県渋川市の津久田(つくだ)にも美味しいと評判の名店があり、当線でSL列車(SLぐんまみなかみ号)などを撮りに訪れる鉄ちゃんのあいだでもちょくちょく話題に上がるのですが ヽ(゚ω゚)ウマイヨ、そのお店は最寄駅の津久田から5キロ以上もの距離があり(橋が遠い川の対岸)、私のような徒歩鉄だとなかなか気軽には食べに行けません (´Д⊂ ムリポ。
いっぽう今回の「道の駅 くろほね・やまびこ」ならば、本宿から2キロ、下り方隣駅の水沼(みずぬま)からは1キロのところに位置した歩ける距離で、わ鐵の撮影ついでに立ち寄って念願の“もつ煮”を美味しくいただくことができました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。
まあ、慣れないヘタな“食リポもどき”(?)はこのくらいにして・・・(^^;)ゞポリポリ、ごちそうさまでした 人´ε`*)ゴッチャンデス。
いっぽう今回の「道の駅 くろほね・やまびこ」ならば、本宿から2キロ、下り方隣駅の水沼(みずぬま)からは1キロのところに位置した歩ける距離で、わ鐵の撮影ついでに立ち寄って念願の“もつ煮”を美味しくいただくことができました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。
まあ、慣れないヘタな“食リポもどき”(?)はこのくらいにして・・・(^^;)ゞポリポリ、ごちそうさまでした 人´ε`*)ゴッチャンデス。
「道の駅 くろほね・やまびこ」から
1キロほどのところに位置する駅で
本宿と同じく桐生市黒保根町に所在する
わ鐡の水沼。
奥の屋根には“温泉マーク”が見えるけど・・・
(゚∀゚)オッ!
▲わたらせ渓谷鐡道 水沼
あれ?本日休館とな?
(・・?)アリ?
1キロほどのところに位置する駅で
本宿と同じく桐生市黒保根町に所在する
わ鐡の水沼。
奥の屋根には“温泉マーク”が見えるけど・・・
(゚∀゚)オッ!
▲わたらせ渓谷鐡道 水沼
あれ?本日休館とな?
(・・?)アリ?
道の駅での食事を満喫した私が次にやってきたのは、鉄道駅の水沼 ( ̄  ̄)ミズヌマ。
ここからすぐにわ鐵の列車へ乗って移動するのではなく、当駅には日帰り入浴が楽しめる温泉施設(水沼駅温泉センター)が併設されており (゚∀゚)オッ!、少し時間に余裕があることからひとっ風呂浴びていこうかという、撮り鉄のあとに食事から入浴へと流れるナイスなプランを考えていたのですが ъ(゚Д゚)ナイス、駄菓子菓子(だがしかし)土曜日にも関わらずその入口には、「本日休館」と書かれた紙が貼られています (・・?)アリ?。どうやらホントのところは今日だけの休館ではなく、経営的な事情により先月からしばらく休業(閉館?)となっているようで、何にしても残念ながら利用することができませんでした (・ε・`)チェ。
ちなみに思い返せば今夏の7月に訪れた岐阜の明知鉄道でも、駅前温泉として知られる花白温泉がボイラー故障が理由で臨時休館していたっけ。このところの私はどうも温泉との相性が良くないみたいだなぁ "o(-ω-;*)ウゥム。
ここからすぐにわ鐵の列車へ乗って移動するのではなく、当駅には日帰り入浴が楽しめる温泉施設(水沼駅温泉センター)が併設されており (゚∀゚)オッ!、少し時間に余裕があることからひとっ風呂浴びていこうかという、撮り鉄のあとに食事から入浴へと流れるナイスなプランを考えていたのですが ъ(゚Д゚)ナイス、駄菓子菓子(だがしかし)土曜日にも関わらずその入口には、「本日休館」と書かれた紙が貼られています (・・?)アリ?。どうやらホントのところは今日だけの休館ではなく、経営的な事情により先月からしばらく休業(閉館?)となっているようで、何にしても残念ながら利用することができませんでした (・ε・`)チェ。
ちなみに思い返せば今夏の7月に訪れた岐阜の明知鉄道でも、駅前温泉として知られる花白温泉がボイラー故障が理由で臨時休館していたっけ。このところの私はどうも温泉との相性が良くないみたいだなぁ "o(-ω-;*)ウゥム。
温泉へ入れずに“ナイスなプラン”はもろくも崩れちゃったけど気を取り直して、ここ水沼から歩ける範囲でもう一カ所、私には行きたいところがあります・・・というか、本来はそこが今旅いちばんの目的地 (-`ω´-*)ウム。
先ほど食べた“もつ煮定食”をスタミナの源にして快調に歩き進むのは、集落のまわりを囲む里山のひとつに伸びる上り坂 ...(((o*・ω・)o。その登った先にあるのが、わ鐵の線路を高い位置から見下ろすことができる、いわゆる俯瞰ポイントの撮影地です (´ω`)ナルヘソ。
先ほど食べた“もつ煮定食”をスタミナの源にして快調に歩き進むのは、集落のまわりを囲む里山のひとつに伸びる上り坂 ...(((o*・ω・)o。その登った先にあるのが、わ鐵の線路を高い位置から見下ろすことができる、いわゆる俯瞰ポイントの撮影地です (´ω`)ナルヘソ。
さほど高くはない里山の中腹付近でわずかに開けた眺望 (゚∀゚)オッ!。
ひょっとしたら今の時期は鬱蒼と生い茂る草木で視界が遮られて、下界にある線路が望めないかもしれないとの不安はありましたが (゚ペ)ウーン…、たどり着いた現地から目を凝らすと眼下にはかろうじて、壮大な情景のなかだと細々として見える非電化単線の線路が確認できました m9っ`∀´)ミッケ!。これならどうにか列車が撮れそう ε-(´∇`*)ホッ。
そしてこの場所から狙うのはもちろん、例の国鉄色ディーゼル機関車が牽く「トロッコわたらせ渓谷号」にほかなりません ( ̄▽ ̄)トロッコ。昼前に足尾ゆき「トロッコわたらせ渓谷3号」で下っていった当該編成が終点で折り返し、上りの大間々ゆき「トロッコわたらせ渓谷4号」として15時過ぎにこのあたりを通過します (*゚ェ゚)フムフム。
ひょっとしたら今の時期は鬱蒼と生い茂る草木で視界が遮られて、下界にある線路が望めないかもしれないとの不安はありましたが (゚ペ)ウーン…、たどり着いた現地から目を凝らすと眼下にはかろうじて、壮大な情景のなかだと細々として見える非電化単線の線路が確認できました m9っ`∀´)ミッケ!。これならどうにか列車が撮れそう ε-(´∇`*)ホッ。
そしてこの場所から狙うのはもちろん、例の国鉄色ディーゼル機関車が牽く「トロッコわたらせ渓谷号」にほかなりません ( ̄▽ ̄)トロッコ。昼前に足尾ゆき「トロッコわたらせ渓谷3号」で下っていった当該編成が終点で折り返し、上りの大間々ゆき「トロッコわたらせ渓谷4号」として15時過ぎにこのあたりを通過します (*゚ェ゚)フムフム。
きょうはこれまでずっと厚い雲に覆われた曇天の空模様でしたが (-ω-;*)ドングモリ、ここにきて少しずつ上空の雲が薄くなってきたみたいで、時おりほんのわずかながら雲間から太陽が顔を覗かせるようになりました (゚∀゚)オッ!。これは日差しが期待できるというほどではないけれど、タイミングがよければワンチャンあるかも!?(☆∀☆)ワンチャン☆。いまの時間帯のこの場所はおそらく順光となるハズなので、もし晴れてくれたら嬉しいなぁ 八(゚- ゚)ハレテ。
そんな状況のなかで待つことしばし、やがて「トロッコわたらせ渓谷号」が水沼の駅を発車する際に鳴らされる、DE10形機関車の汽笛の音が耳に届きました ピィィィ───( ̄- ̄ 3)───ッ…。ここから列車が見える箇所はわずかなので、通過のタイミングを逸しないよう集中します (*`・ω・´)-3フンス!。
そんな状況のなかで待つことしばし、やがて「トロッコわたらせ渓谷号」が水沼の駅を発車する際に鳴らされる、DE10形機関車の汽笛の音が耳に届きました ピィィィ───( ̄- ̄ 3)───ッ…。ここから列車が見える箇所はわずかなので、通過のタイミングを逸しないよう集中します (*`・ω・´)-3フンス!。
箱庭のような情景のなかで目を引く
朱色のディーゼル機関車に牽かれて
渡良瀬川沿いの深い森を抜ける
「トロッコわたらせ渓谷号」。
地形を活かした山里の棚田は
もうすっかり秋色です。
(゚- ゚)アキ
▲わたらせ渓谷鐵道 水沼-本宿
朱色のディーゼル機関車に牽かれて
渡良瀬川沿いの深い森を抜ける
「トロッコわたらせ渓谷号」。
地形を活かした山里の棚田は
もうすっかり秋色です。
(゚- ゚)アキ
▲わたらせ渓谷鐵道 水沼-本宿
秋の棚田でトロッコが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
まだ夏の名残りを感じる深い緑に包まれた山里の一角で、美しき黄金色の輝きを放つ稲田。その傍らに敷かれた緩いカーブを朱色のDE10形が牽くトロッコ・・・いや、ローカル線の客車列車(という表現でも間違いではない)がコトコトとかすめてゆきます コトコト...(((o*・ω・)o。けっして抜けがよいとはいえない狭い視界のなかで展開される、初秋の田舎風情をぎゅっと凝縮した鉄道情景の素晴らしさに穏やかな感動を覚えます。ああ、いいねぇ・・・ホント、こういうロケーションに国鉄色の車両(DE10形に限らず)はしっくりとマッチするものだよなぁ +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。ちなみにこのあたりの田んぼで作られるお米がおそらく、先ほどの「道の駅」でお昼ゴハンに美味しくいただいた、ご当地米の“くろほね米”と呼ばれるものなのでしょうね (´ω`)ナルヘソ。「水源の郷くろほね。うまい米。」・・・か。
そしてわずかな望みを抱いていた太陽の日差しは、完全に雲が抜けた状態の“バリ晴れ”ではなかったものの、列車が通過するタイミングで陰影が出るくらいの薄日は差して、一帯の景色に明るさを、DE10形の朱色に鮮やかさを与えてくれました (゚∀゚*)オオッ!。ずっと曇り空だったことを考えれば、薄日でも嬉しくてじゅうぶんに満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
山あいにちらりと姿を見せて走り去った「トロッコわたらせ渓谷号」。これにて撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
まだ夏の名残りを感じる深い緑に包まれた山里の一角で、美しき黄金色の輝きを放つ稲田。その傍らに敷かれた緩いカーブを朱色のDE10形が牽くトロッコ・・・いや、ローカル線の客車列車(という表現でも間違いではない)がコトコトとかすめてゆきます コトコト...(((o*・ω・)o。けっして抜けがよいとはいえない狭い視界のなかで展開される、初秋の田舎風情をぎゅっと凝縮した鉄道情景の素晴らしさに穏やかな感動を覚えます。ああ、いいねぇ・・・ホント、こういうロケーションに国鉄色の車両(DE10形に限らず)はしっくりとマッチするものだよなぁ +。:.(´ー`)シミジミ.:。+゚。ちなみにこのあたりの田んぼで作られるお米がおそらく、先ほどの「道の駅」でお昼ゴハンに美味しくいただいた、ご当地米の“くろほね米”と呼ばれるものなのでしょうね (´ω`)ナルヘソ。「水源の郷くろほね。うまい米。」・・・か。
そしてわずかな望みを抱いていた太陽の日差しは、完全に雲が抜けた状態の“バリ晴れ”ではなかったものの、列車が通過するタイミングで陰影が出るくらいの薄日は差して、一帯の景色に明るさを、DE10形の朱色に鮮やかさを与えてくれました (゚∀゚*)オオッ!。ずっと曇り空だったことを考えれば、薄日でも嬉しくてじゅうぶんに満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
山あいにちらりと姿を見せて走り去った「トロッコわたらせ渓谷号」。これにて撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
ディーゼル機関車が牽く観光列車の「トロッコわたらせ渓谷号」を撮りに訪れた、山里のローカル線「わたらせ渓谷鉄道」(゚ー゚*)ワテツ。
国鉄型の古い車両が好きな私にとって、オリジナルの国鉄色を纏うDE10形の貴重な登板にテンションが上がったのもさることながら ε-(°ω°*)デーテン!、事前に食事処を探していて目に留まった「道の駅 くろほね・やまびこ」の“もつ煮”にも惹かれるものがあり ジュルリ、ぶっちゃけ今回は「トロッコ」の撮り鉄よりも“もつ煮”を食べるほうの楽しみが上回ったというのが正直なところかもしれません (。A。)アヒャ☆。そのお味は期待を裏切らないおいしさでした (゚д゚)ウマー!。
もちろん本来の目的である「トロッコわたらせ渓谷号」も晩夏から初秋へとうつろう時期に、その季節感が表れた情景のなかで国鉄色のDE10形を記録することができて (^_[◎]oパチリ、個人的に満足のいく成果が残せたと思っています (-`ω´-*)ウム。とくに復路で高台から眺めた箱庭のような情景が印象的で、そこに薄日でも差してくれたのは曇天ベースの一日で嬉しい誤算でした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。まあ、唯一残念だったのは温泉に入れなかったことでしょうか。タオルも持参してきたのになぁ (^^;)ゞポリポリ。
これから深まりをみせる秋には錦の紅葉が、そして春には桜や花桃が沿線を彩る“わ鐵”。風光明媚な四季折々の情景を楽しみにして、またぜひとも撮影に訪ねたいところです (・∀・)イイネ。
国鉄型の古い車両が好きな私にとって、オリジナルの国鉄色を纏うDE10形の貴重な登板にテンションが上がったのもさることながら ε-(°ω°*)デーテン!、事前に食事処を探していて目に留まった「道の駅 くろほね・やまびこ」の“もつ煮”にも惹かれるものがあり ジュルリ、ぶっちゃけ今回は「トロッコ」の撮り鉄よりも“もつ煮”を食べるほうの楽しみが上回ったというのが正直なところかもしれません (。A。)アヒャ☆。そのお味は期待を裏切らないおいしさでした (゚д゚)ウマー!。
もちろん本来の目的である「トロッコわたらせ渓谷号」も晩夏から初秋へとうつろう時期に、その季節感が表れた情景のなかで国鉄色のDE10形を記録することができて (^_[◎]oパチリ、個人的に満足のいく成果が残せたと思っています (-`ω´-*)ウム。とくに復路で高台から眺めた箱庭のような情景が印象的で、そこに薄日でも差してくれたのは曇天ベースの一日で嬉しい誤算でした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。まあ、唯一残念だったのは温泉に入れなかったことでしょうか。タオルも持参してきたのになぁ (^^;)ゞポリポリ。
これから深まりをみせる秋には錦の紅葉が、そして春には桜や花桃が沿線を彩る“わ鐵”。風光明媚な四季折々の情景を楽しみにして、またぜひとも撮影に訪ねたいところです (・∀・)イイネ。
桐生でわ鐵から乗り継いだ
両毛線の小山ゆき下り普通列車(右)は
わずか4分という好接続。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
往きは高崎経由でしたが
帰りは小山経由で都内へ戻ります。
カエロ…((((o* ̄-)o
▲両毛線 桐生
両毛線の小山ゆき下り普通列車(右)は
わずか4分という好接続。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
往きは高崎経由でしたが
帰りは小山経由で都内へ戻ります。
カエロ…((((o* ̄-)o
▲両毛線 桐生
水沼1557-(わたらせ渓谷724D)-桐生1636~1640-(両毛455M)-小山1738~1742-(東北1627E)-赤羽1848~1850-(湘南新宿ライン2853Y)-新宿1908
☆オマケ☆
今回の私が旅した「わたらせ渓谷鐵道」(゚ー゚*)ワテツ。
その前身はJR東日本の“足尾線”で、旧・国鉄特定地方交通線(いわゆる赤字ローカル線)に選定されて廃止の危機に直面した当線を、県や沿線自治体などが出資する第三セクター鉄道として存続させ、現在のわたらせ渓谷鐵道が1989年(平成元年)に引き継いだものです ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
JR足尾線としての最終日となった89年3月28日に特別運行された「さようなら列車」サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~、その先頭をつとめた牽引機がやはりディーゼル機関車のDE10形で ( ̄  ̄*)デーテン、あれから34年もの月日が経った今日に見た「トロッコわたらせ渓谷号」を牽く国鉄色の同型機(DE10 1678)には、個人的に感慨深いものがありました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
その前身はJR東日本の“足尾線”で、旧・国鉄特定地方交通線(いわゆる赤字ローカル線)に選定されて廃止の危機に直面した当線を、県や沿線自治体などが出資する第三セクター鉄道として存続させ、現在のわたらせ渓谷鐵道が1989年(平成元年)に引き継いだものです ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
JR足尾線としての最終日となった89年3月28日に特別運行された「さようなら列車」サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~、その先頭をつとめた牽引機がやはりディーゼル機関車のDE10形で ( ̄  ̄*)デーテン、あれから34年もの月日が経った今日に見た「トロッコわたらせ渓谷号」を牽く国鉄色の同型機(DE10 1678)には、個人的に感慨深いものがありました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
春雨がそぼ降るなか
国鉄色のDE10形1682号機が先頭に立った
「さようなら足尾線」の特別臨時列車。
後ろに従える客車は
和式客車(お座敷客車)の「くつろぎ」です。
(゚ー゚*)タカビー
▲89.3 足尾線 沢入
こちらはもともとの国鉄色でなく
イベント用の旧型客車(後ろ)に合わせて
茶色(ぶどう色2号)に塗り替えられた
DE10形1705号機が牽引する特別臨時列車。
駅ホームでの手堅い撮影だけど
「さようなら足尾線」のヘッドマークが
いい記録になりました。
パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ
▲89.3 足尾線 足尾
わ鐵への転換を控えた
JR足尾線最終日の足尾駅。
タラコ色の国鉄型気動車が走るのも
この日かぎりです。
多くのファンが集まったけど
どこかまったりとした雰囲気。
(´ー`)マターリ
わ鐵の開業を祝って上げられた
“アドバルーン”が
今ではちょっと懐かしさを感じますね(笑)
(o ̄∇ ̄o)アドバルーン
▲89.3 足尾線 足尾
国鉄色のDE10形1682号機が先頭に立った
「さようなら足尾線」の特別臨時列車。
後ろに従える客車は
和式客車(お座敷客車)の「くつろぎ」です。
(゚ー゚*)タカビー
▲89.3 足尾線 沢入
こちらはもともとの国鉄色でなく
イベント用の旧型客車(後ろ)に合わせて
茶色(ぶどう色2号)に塗り替えられた
DE10形1705号機が牽引する特別臨時列車。
駅ホームでの手堅い撮影だけど
「さようなら足尾線」のヘッドマークが
いい記録になりました。
パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ
▲89.3 足尾線 足尾
わ鐵への転換を控えた
JR足尾線最終日の足尾駅。
タラコ色の国鉄型気動車が走るのも
この日かぎりです。
多くのファンが集まったけど
どこかまったりとした雰囲気。
(´ー`)マターリ
わ鐵の開業を祝って上げられた
“アドバルーン”が
今ではちょっと懐かしさを感じますね(笑)
(o ̄∇ ̄o)アドバルーン
▲89.3 足尾線 足尾
この当時の私はどちらかというと“撮り鉄”よりも“乗り鉄”のほうをメインに行動していたけど、もし今の私だったら駅のホームでなく沿線の撮影ポイントにて「さようなら列車」を狙っただろうな・・・ ( ̄▽ ̄*)トリテツ。
2023-09-16 09:09
えちごトキめき鉄道・・・413系観光急行 撮影記 [鉄道写真撮影記]
先日に私が岐阜県の明知鉄道で乗車した、急行「大正ロマン号」。その記事を見ていただいた何人かの方から「“急行列車”って、なんだか懐かしい」という旨のコメントをいただきました (´ω`*)ナツカシス。そしてとくに意識したわけでないのですが、昭和の国鉄時代の“客車急行”をイメージしたような「上野駅・高崎線開業140周年記念号」、さらには昔の私が撮影した急行「あじがうら」の古い写真と、このところの拙ブログはたまたま“急行列車”に関する話題が続いています ( ̄  ̄*)キューコー。
その名のとおり鈍行(普通列車)よりも“急いで行く”優等列車として、国鉄時代やJRの初期には全国各地で数多く走っていた急行列車ですが、そのほとんどは列車の効率化や速達化、サービス向上(という名目の値上げ?)などを理由に“特急列車”へと格上げ(もしくは料金不要な“快速”に格下げ)され、いちおう臨時列車としての設定は残されているもののJRで定期の急行列車は現在一本も運行されておらず、“急行”という種別の列車は今だと長距離列車でなく、都市圏の私鉄などで運転している“急行電車”をさすイメージが強くなっちゃいましたよね・・・ σ(・∀・`)ウーン。“急行電車”でなく“急行列車”という響きに懐かしさを覚えるのも納得できます (-`ω´-*)ウム。
そんな懐古感のある急行列車を現代に再現し、国鉄時代の急行形車両を“観光列車”として土休日を中心に運行しているのが、新潟県西部の上越地域にある第三セクター鉄道の「えちごトキめき鉄道」、通称“トキ鉄” (゚ー゚*)トキテツ。このところの拙ブログで続いた急行列車の話題に感化された私は、国鉄の面影を色濃く残す“トキ鉄の観光急行”が無性に撮りたくなり ((o(゙ε゙)o))ウズウズ、その撮影を軸とした“乗り鉄”と“撮り鉄”の旅程を計画してみました (・∀・)イイネ。
そして時期的に今回もメインで使用する乗車券は、JR全線の普通列車、快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる、おトクな「青春18きっぷ」です (*・∀・)つ[18] 。
8月4日(金)
その名のとおり鈍行(普通列車)よりも“急いで行く”優等列車として、国鉄時代やJRの初期には全国各地で数多く走っていた急行列車ですが、そのほとんどは列車の効率化や速達化、サービス向上(という名目の値上げ?)などを理由に“特急列車”へと格上げ(もしくは料金不要な“快速”に格下げ)され、いちおう臨時列車としての設定は残されているもののJRで定期の急行列車は現在一本も運行されておらず、“急行”という種別の列車は今だと長距離列車でなく、都市圏の私鉄などで運転している“急行電車”をさすイメージが強くなっちゃいましたよね・・・ σ(・∀・`)ウーン。“急行電車”でなく“急行列車”という響きに懐かしさを覚えるのも納得できます (-`ω´-*)ウム。
そんな懐古感のある急行列車を現代に再現し、国鉄時代の急行形車両を“観光列車”として土休日を中心に運行しているのが、新潟県西部の上越地域にある第三セクター鉄道の「えちごトキめき鉄道」、通称“トキ鉄” (゚ー゚*)トキテツ。このところの拙ブログで続いた急行列車の話題に感化された私は、国鉄の面影を色濃く残す“トキ鉄の観光急行”が無性に撮りたくなり ((o(゙ε゙)o))ウズウズ、その撮影を軸とした“乗り鉄”と“撮り鉄”の旅程を計画してみました (・∀・)イイネ。
そして時期的に今回もメインで使用する乗車券は、JR全線の普通列車、快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる、おトクな「青春18きっぷ」です (*・∀・)つ[18] 。
8月4日(金)
高尾から乗る中央線は
当駅始発の大月ゆき下り列車。
ちなみに「普通」も「各駅停車」も
停車駅は一緒ですが、
高尾始発の列車は「普通」で
中央快速線から直通してくるものは
「各駅停車」と表示されるようです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲中央本線 高尾
当駅始発の大月ゆき下り列車。
ちなみに「普通」も「各駅停車」も
停車駅は一緒ですが、
高尾始発の列車は「普通」で
中央快速線から直通してくるものは
「各駅停車」と表示されるようです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲中央本線 高尾
やはり、“18きっぱー”(青春18きっぷ愛好者)の朝は早い (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…。
一日じゅう乗り放題の「18きっぷ」をフルに活用すべく、私は今回も都内にある地元の駅を朝4時半の初発列車に乗って中央本線を下り、高尾、大月、甲府と普通列車を細かく乗り継いで山梨県を横断するように、ひたすら西進します ...(((o*・ω・)o。
・・・って、この行動パターンは、およそ二週間前(7/22)に明知鉄道へ行ったときとまったく一緒 (゚∀゚)アヒャ☆。できれば今回は路線や経路などを変えたかったところですが、「18きっぷ」を使った“鈍行旅”(在来線の普通列車を利用した行程)を基本とした場合、“トキ鉄の観光急行”という目的の列車を希望の撮影ポイントで効率よく撮るためには、まずはどうしても前回と同じ乗り継ぎで中央本線を下るしかありませんでした (^^;)ゞポリポリ(なお、本文中の往きの道中で“前回”と表しているのは、明知鉄道の旅を指しています)。
一日じゅう乗り放題の「18きっぷ」をフルに活用すべく、私は今回も都内にある地元の駅を朝4時半の初発列車に乗って中央本線を下り、高尾、大月、甲府と普通列車を細かく乗り継いで山梨県を横断するように、ひたすら西進します ...(((o*・ω・)o。
・・・って、この行動パターンは、およそ二週間前(7/22)に明知鉄道へ行ったときとまったく一緒 (゚∀゚)アヒャ☆。できれば今回は路線や経路などを変えたかったところですが、「18きっぷ」を使った“鈍行旅”(在来線の普通列車を利用した行程)を基本とした場合、“トキ鉄の観光急行”という目的の列車を希望の撮影ポイントで効率よく撮るためには、まずはどうしても前回と同じ乗り継ぎで中央本線を下るしかありませんでした (^^;)ゞポリポリ(なお、本文中の往きの道中で“前回”と表しているのは、明知鉄道の旅を指しています)。
大月で乗り継いだ甲府ゆき普通列車は
前回と同様にロングシート仕様の211系。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 大月
きょうの甲府盆地は上空に雲が多く
勝沼ぶどう郷付近の車窓から見る眺めは
ちょっとイマイチです。
(≡"≡*)モヤモヤ
この先の目的地では
晴れてくれるといいけれど・・・。
▲中央本線 勝沼ぶどう郷-塩山
(車窓から)
前回と同様にロングシート仕様の211系。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 大月
きょうの甲府盆地は上空に雲が多く
勝沼ぶどう郷付近の車窓から見る眺めは
ちょっとイマイチです。
(≡"≡*)モヤモヤ
この先の目的地では
晴れてくれるといいけれど・・・。
▲中央本線 勝沼ぶどう郷-塩山
(車窓から)
それでも、たとえ同じ路線を同じ時間に乗って同じ場所の景色を眺めたものであれ、当然ながら天候の違いなどでその見え方や印象は前回と今回で異なるもの (-`ω´-*)ウム。今日の勝沼ぶどう郷付近は雲が多くて高台から望む甲府盆地は前回のほうがよく見えたし (・∀・`)ウーン…、逆に前回は雲に覆われて山容がほとんど見えなかった南アルプスや八ヶ岳の山々は今日のほうがきれいに見えています (゚∀゚)オッ!。
ちなみにもうひとつ違うところといえば、甲府で乗り継いだ松本ゆきの普通列車(423M)が同じ211系でも、前回の座席はセミクロスシート仕様(ボックスシート装備)だったのに、今回はロングシート仕様でした (゚ー゚?)オヨ?。個人的な好みとしては前回のほうが“当たり”だったなぁ (・ε・`)チェ。
ちなみにもうひとつ違うところといえば、甲府で乗り継いだ松本ゆきの普通列車(423M)が同じ211系でも、前回の座席はセミクロスシート仕様(ボックスシート装備)だったのに、今回はロングシート仕様でした (゚ー゚?)オヨ?。個人的な好みとしては前回のほうが“当たり”だったなぁ (・ε・`)チェ。
甲府で松本ゆき普通列車に乗り継ぎ。
あれ?前回はセミクロスだったのに
今回はこの列車もロングシートですた。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 甲府
韮崎を過ぎたあたりから天気は好転し、
南アルプスの甲斐駒ヶ岳(上)も
そして八ヶ岳連山(下)も
今日はその雄大な山容が
車窓からスッキリと拝めました。
(゚∀゚*)オオッ!
下写真は空いていた車内で
窓枠を額縁のようにしてパチリ。
(^_[◎]oパチリ
▲▲中央本線 日野春-長坂
▲中央本線 小淵沢-信濃境
(どちらも車窓から)
あれ?前回はセミクロスだったのに
今回はこの列車もロングシートですた。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 甲府
韮崎を過ぎたあたりから天気は好転し、
南アルプスの甲斐駒ヶ岳(上)も
そして八ヶ岳連山(下)も
今日はその雄大な山容が
車窓からスッキリと拝めました。
(゚∀゚*)オオッ!
下写真は空いていた車内で
窓枠を額縁のようにしてパチリ。
(^_[◎]oパチリ
▲▲中央本線 日野春-長坂
▲中央本線 小淵沢-信濃境
(どちらも車窓から)
やがて県境を越えて山梨から長野へと入った、中央本線(中央東線)の松本ゆき普通列車。前回の私はこの列車を塩尻(しおじり)で降りて、中央西線の中津川方面に乗り換えましたが(ついでに超ボリューミーな“山賊そば”を食べたっけw)、今回は塩尻の少し手前(上り方)に位置する岡谷(おかや)で降りて、篠ノ井線(しののいせん)へと直通する後続の長野ゆき普通列車に乗り継ぎ ノリカエ…((((o* ̄-)o。つまりここから先は前回と違う行程となります。
岡谷で乗り継いだのは
飯田を始発駅として
飯田線、中央本線、篠ノ井線、
信越本線を直通する
長野ゆきの快速「みすず」。
(゚ー゚*)ミスズ
ただし快速運転は飯田線内のみで
私が乗る岡谷から先は普通列車です。
なお、この211系もまたロング仕様ですた。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 岡谷
篠ノ井線の下り列車が松本を過ぎると
左手の車窓に望めるのが
安曇野にそびえる北アルプスの山々。
でも今日は雲が湧いていて
山の稜線がよく見えませんね・・・。
夏の空だなぁ。
▲篠ノ井線 田沢-明科(車窓から)
そして篠ノ井線といえば外せないのが
“日本三大車窓”のひとつに数えられる姨捨。
天気もよくて気持ちのいい眺めです。
(「゚ー゚)ドレドレ
ちなみに当駅は駅名標が表すとおり
スイッチバック構造となっています。
スイッチo(゚д゚o≡o゚д゚)oバック
▲篠ノ井線 姨捨(車窓から)
飯田を始発駅として
飯田線、中央本線、篠ノ井線、
信越本線を直通する
長野ゆきの快速「みすず」。
(゚ー゚*)ミスズ
ただし快速運転は飯田線内のみで
私が乗る岡谷から先は普通列車です。
なお、この211系もまたロング仕様ですた。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 岡谷
篠ノ井線の下り列車が松本を過ぎると
左手の車窓に望めるのが
安曇野にそびえる北アルプスの山々。
でも今日は雲が湧いていて
山の稜線がよく見えませんね・・・。
夏の空だなぁ。
▲篠ノ井線 田沢-明科(車窓から)
そして篠ノ井線といえば外せないのが
“日本三大車窓”のひとつに数えられる姨捨。
天気もよくて気持ちのいい眺めです。
(「゚ー゚)ドレドレ
ちなみに当駅は駅名標が表すとおり
スイッチバック構造となっています。
スイッチo(゚д゚o≡o゚д゚)oバック
▲篠ノ井線 姨捨(車窓から)
篠ノ井線(塩尻〜篠ノ井)は長野と松本という県内の二大都市をむすぶ主要な幹線ですが、信州らしい自然豊かな沿線風景は当線ならではの変化に富んでおり、壮大に連なる北アルプスの高峰や清らかな犀川(さいがわ)の流れ、さらには“日本三大車窓”のひとつに数えられる「姨捨(おばすて)から望む善光寺平の景観」など、車窓に見どころが多くて楽しめます (・∀・)イイネ。
好天で見晴らしのよい姨捨ではつい途中下車をしたくなるところですが、先の行程を考えると寄り道ができるような余裕はなく σ(・∀・`)ウーン、私はそのまま終点まで列車を乗り進み、篠ノ井から信越本線を経て長野までやってきました ( ̄  ̄)ナガノ。
好天で見晴らしのよい姨捨ではつい途中下車をしたくなるところですが、先の行程を考えると寄り道ができるような余裕はなく σ(・∀・`)ウーン、私はそのまま終点まで列車を乗り進み、篠ノ井から信越本線を経て長野までやってきました ( ̄  ̄)ナガノ。
県都の長野は私がここまで乗ってきた篠ノ井線(信越本線)のほか、北陸新幹線、飯山線、しなの鉄道のしなの鉄道線と北しなの線、さらに長野電鉄の長野線が乗り入れる交通の要衝(なお正式な路線区間とは異なるものも含まれます)(・o・*)ホホゥ。
このなかで私が目指すえちごトキめき鉄道方面へ向かうには、在来線だと元・信越本線を部分的に引き継いだ第三セクター鉄道のしなの鉄道・北しなの線(長野〜妙高高原)で新潟との県境に位置する妙高高原(みょうこうこうげん)へと北上すれば、そこでトキ鉄の妙高はねうまライン(妙高高原〜直江津)に乗り継ぐことができます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ・・・が、実はこれだと今旅の目的である“トキ鉄の観光急行(急行1号)”には時間が間に合わず、希望の撮影ポイントで撮ることができません (´・ω`・)エッ?。
んじゃ、どうするのかというと・・・ここは“シンカンセン”(北陸新幹線)のお力を借りましょう (°ω°*)チンカンテン!。長野から乗車するのは北陸新幹線の各駅に停車する「はくたか555号」金沢ゆき。
このなかで私が目指すえちごトキめき鉄道方面へ向かうには、在来線だと元・信越本線を部分的に引き継いだ第三セクター鉄道のしなの鉄道・北しなの線(長野〜妙高高原)で新潟との県境に位置する妙高高原(みょうこうこうげん)へと北上すれば、そこでトキ鉄の妙高はねうまライン(妙高高原〜直江津)に乗り継ぐことができます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ・・・が、実はこれだと今旅の目的である“トキ鉄の観光急行(急行1号)”には時間が間に合わず、希望の撮影ポイントで撮ることができません (´・ω`・)エッ?。
んじゃ、どうするのかというと・・・ここは“シンカンセン”(北陸新幹線)のお力を借りましょう (°ω°*)チンカンテン!。長野から乗車するのは北陸新幹線の各駅に停車する「はくたか555号」金沢ゆき。
「青春18きっぷ」では特例をのぞいて基本的に特急列車や新幹線に乗ることはできませんが(乗車券としての併用も不可)乂・ω・)ダメヨ、先日の明知鉄道の旅でも途中で特急「しなの」を利用したように、今回も乗車券と特急券を別途に買い直してでもここは北陸新幹線に頼る価値が大いにあると判断 (-`ω´-*)ウム。なるべく「18きっぷ」を使った普通列車での移動を基本としながらも、必要とあらば新幹線や特急列車を使うなど臨機応変に対応することで旅の幅はいっそう広がります。そもそも「18きっぷ」だけにこだわって目的の列車が撮れないようでは本末転倒だしね (。A。)アヒャ☆。
なお、仮に北しなの線へ乗り継いだとしても、しなの鉄道はJRではない第三セクター鉄道の路線なので「18きっぷ」の使用範囲外となり、いずれにせよ長野から先は別途に乗車券を買う必要があります。
なお、仮に北しなの線へ乗り継いだとしても、しなの鉄道はJRではない第三セクター鉄道の路線なので「18きっぷ」の使用範囲外となり、いずれにせよ長野から先は別途に乗車券を買う必要があります。
それならばもう今回はいっそのこと「18きっぷ」を使わず、この北陸新幹線の「はくたか555号」に東京から乗れば便利で時間的な効率もいいように思えますが(同列車の東京発は8時44分)σ(゚・゚*)ンー…、私の鉄道旅は決して移動効率や速達性を重視しているのでなく、「18きっぷ」を使った普通列車の乗り継ぎも楽しみのひとつであり、例えば今回の場合は北陸新幹線よりも篠ノ井線へ乗るほうのルートに魅力を感じたといったところ(姨捨を通りたかったの)コッチ…((((o* ̄-)o。そのうえさらに東京から新幹線を使うよりも安く済むのならば、言うことないじゃないですか(あくまでも個人的な感覚(笑))ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
ちなみに各種の割引などを考えずにざっくりとした比較ですが、もし東京から新幹線を使って最終目的地の駅まで行くとしたら片道は10,950円(乗車券5,780円、新幹線自由席特急券5,170円)。いっぽう私が実践したように「18きっぷ」で長野まで行ってから新幹線へ乗り継ぐと「18きっぷ」一回分換算の2,410円と新幹線利用区間の4,510円(乗車券1,970円、新幹線自由席特急券2,540円)を足して6,920円となります (o-∀-)ホゥホゥ。個人的な感覚だけど4,000円の差額はけっこう大きい(往路とする片道だけの比較。復路を含めるとコスパはさらに・・・w)。
ちなみに各種の割引などを考えずにざっくりとした比較ですが、もし東京から新幹線を使って最終目的地の駅まで行くとしたら片道は10,950円(乗車券5,780円、新幹線自由席特急券5,170円)。いっぽう私が実践したように「18きっぷ」で長野まで行ってから新幹線へ乗り継ぐと「18きっぷ」一回分換算の2,410円と新幹線利用区間の4,510円(乗車券1,970円、新幹線自由席特急券2,540円)を足して6,920円となります (o-∀-)ホゥホゥ。個人的な感覚だけど4,000円の差額はけっこう大きい(往路とする片道だけの比較。復路を含めるとコスパはさらに・・・w)。
快適なリクライニングシートにもたれて車窓に映る妙高山の山容などを眺めながら過ごしていると (´ー`)ラクチン、在来線(しなの鉄道の北しなの線とトキ鉄の妙高はねうまライン、さらに同じくトキ鉄の日本海ひすいライン)の普通列車を乗り継いだとしたら二時間半かかるところを、新幹線「はくたか」はわずか36分という驚異的な速さで走り抜け バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、まもなく到着したのは新潟県西部の糸魚川(いといがわ)。
私はここで新幹線を降ります。
私はここで新幹線を降ります。
富山、金沢方面へ向かう「はくたか」を
糸魚川でお見送り。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
なお北陸新幹線は来春(2024年春)に
金沢から福井県の敦賀(つるが)まで
延伸開業が予定されています。
▲北陸新幹線 糸魚川
糸魚川でお見送り。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
なお北陸新幹線は来春(2024年春)に
金沢から福井県の敦賀(つるが)まで
延伸開業が予定されています。
▲北陸新幹線 糸魚川
日本海に面した港町の糸魚川市。その市の中心にある糸魚川の駅には北陸新幹線と大糸線(おおいとせん)、そしてえちごトキめき鉄道の日本海ひすいラインが乗り入れており、ここでようやく私は今旅の目的である“観光急行”が運行されている路線へとたどり着きました (゚ー゚*)トキテツ。
さらにもうちょっとだけ移動して、沿線の撮影ポイントへと向かいます ...(((o*・ω・)o。
さらにもうちょっとだけ移動して、沿線の撮影ポイントへと向かいます ...(((o*・ω・)o。
おまんた祭り・・・
(゚ー゚*)オマンタ…
「おまんた」とは糸魚川の方言で
“あなた方”を意味し、
お囃子の音にあわせてみんなで踊る
ご当地伝統のお祭りだそうです。
糸魚川から乗る
トキ鉄の日本海ひすいライン。
泊ゆき上り普通列車は
単行(一両)のET122形です。
イーティー…((Θ)_(Θ)σ
車内は空いていて
転換クロスシートに座ることが
できました。
▲トキ鉄日本海ひすいライン 糸魚川
(゚ー゚*)オマンタ…
「おまんた」とは糸魚川の方言で
“あなた方”を意味し、
お囃子の音にあわせてみんなで踊る
ご当地伝統のお祭りだそうです。
糸魚川から乗る
トキ鉄の日本海ひすいライン。
泊ゆき上り普通列車は
単行(一両)のET122形です。
イーティー…((Θ)_(Θ)σ
車内は空いていて
転換クロスシートに座ることが
できました。
▲トキ鉄日本海ひすいライン 糸魚川
糸魚川を発車した日本海ひすいラインの泊(とまり)ゆき上り普通列車は、日本海に沿って西のほうへ進路を取ります。いちおう進行方向の右手となる海側の席に座りましたが、私の乗車区間は短いのでそのあいだに車窓から海はたぶん見えない (「゚ー゚)ミエナイ…。
糸魚川を出た上り列車はすぐに
清流として名高い姫川を渡ります。
河口付近に架けられた橋梁ですが
新幹線の高架や国道の橋が並行していて
車窓から海は見えませんでした。
▲日本海ひすいライン 糸魚川-青海
(車窓から)
清流として名高い姫川を渡ります。
河口付近に架けられた橋梁ですが
新幹線の高架や国道の橋が並行していて
車窓から海は見えませんでした。
▲日本海ひすいライン 糸魚川-青海
(車窓から)
日本海ひすいラインは、北陸新幹線の開業(長野〜金沢の延伸開業)に伴ってJRから経営を分離された北陸本線の並行在来線区間(金沢〜直江津)のうち、石川県のIRいしかわ鉄道(金沢〜倶利伽羅)、富山県のあいの風とやま鉄道(倶利伽羅〜市振)とともに、新潟県内の部分である市振(いちぶり)と直江津(なおえつ)のあいだの59.3キロを第三セクター鉄道のえちごトキめき鉄道が引き継いだもので、その線名のとおり新潟県西部の日本海沿岸地域を走る路線です (・o・*)ホホゥ。
JR時代(旧・北陸本線)の電化方式がそのまま継続されている当線ですが、路線の途中に直流と交流電源の境界(いわゆるデッドセクション)が含まれるため、製造費や維持費が高コストな交直両用型の電車ではなく、電源方式にとらわれないで走行できる気動車(ディーゼルカー)のET122形を普通列車に使用 ( ̄  ̄*)ヂーゼル。ただし電気機関車が牽引する貨物列車(JR貨物による運行)と、あとは国鉄急行型電車を使用する“観光急行”の運行には電化設備が必要不可欠です (´ω`)ナルヘソ。
そんな日本海ひすいラインのディーセル列車に揺られて糸魚川からわずか一駅、車窓から海を見ることなく私が下車したのは青海(おうみ)。
JR時代(旧・北陸本線)の電化方式がそのまま継続されている当線ですが、路線の途中に直流と交流電源の境界(いわゆるデッドセクション)が含まれるため、製造費や維持費が高コストな交直両用型の電車ではなく、電源方式にとらわれないで走行できる気動車(ディーゼルカー)のET122形を普通列車に使用 ( ̄  ̄*)ヂーゼル。ただし電気機関車が牽引する貨物列車(JR貨物による運行)と、あとは国鉄急行型電車を使用する“観光急行”の運行には電化設備が必要不可欠です (´ω`)ナルヘソ。
そんな日本海ひすいラインのディーセル列車に揺られて糸魚川からわずか一駅、車窓から海を見ることなく私が下車したのは青海(おうみ)。
せっかく座り心地のよい
転換クロスシートの列車でしたが、
その乗車区間は一駅で6分。
糸魚川の次駅の青海で降ります。
なお運賃は280円也。
(・ω・)トーチャコ
▲日本海ひすいライン 青海
新潟県糸魚川市に所在する青海。
“青梅”でなく“青海”ですが、
某コンサートホール(Z〇pp T〇kyo)の
最寄駅ではありません。
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
下車したのは私一人だけで
今は閑散としている無人駅だけど
構内の広々とした改札口や待合室などには
かつての当駅が多くの海水浴客などで
賑わいを見せていた時代が偲ばれます。
(´ー`)シミジミ
▲日本海ひすいライン 青海
転換クロスシートの列車でしたが、
その乗車区間は一駅で6分。
糸魚川の次駅の青海で降ります。
なお運賃は280円也。
(・ω・)トーチャコ
▲日本海ひすいライン 青海
新潟県糸魚川市に所在する青海。
“青梅”でなく“青海”ですが、
某コンサートホール(Z〇pp T〇kyo)の
最寄駅ではありません。
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
下車したのは私一人だけで
今は閑散としている無人駅だけど
構内の広々とした改札口や待合室などには
かつての当駅が多くの海水浴客などで
賑わいを見せていた時代が偲ばれます。
(´ー`)シミジミ
▲日本海ひすいライン 青海
武蔵小金井0430-(中央415H)-高尾0457~0515-(1335M)-大月0551~0554-(323M)-甲府0641~0646-(423M)-岡谷0802~0808-(篠ノ井3523M みすず)-0958~1019-(北陸新幹線 はくたか555号)-糸魚川1055~1149-(トキ鉄ひすいライン1636D)-青海1155
駅を出たら線路と並行する国道(8号線)を西の市振方向へ、右手に広がる海を眺めながら歩き進みます ...(((o*・ω・)o。
青い海と書いて“青海” ( ̄  ̄*)オウミ。駅名の由来となった地名(旧・西頚城郡青海町)のとおり、快晴の青空を映す真っ青な海景色が気持ちいい (´▽`*)イイテンキ♪。真夏の太陽が照り付ける猛烈な暑さはキビシいものの(この日の糸魚川市の最高気温は38度だったそうな)('A`υ)アツー、上空に日差しを遮るような雲はほとんど見あたらず、もうこの時点で約40分後に通過する“観光急行”の「急行1号」に勝利(好条件での撮影)を確信しちゃいます ( ー`дー´)カッタ。まあ得てしてこういうときに限って、ピントが甘いなどのイージーミスをしがちなのですが(笑)(。A。)アヒャ☆
青い海と書いて“青海” ( ̄  ̄*)オウミ。駅名の由来となった地名(旧・西頚城郡青海町)のとおり、快晴の青空を映す真っ青な海景色が気持ちいい (´▽`*)イイテンキ♪。真夏の太陽が照り付ける猛烈な暑さはキビシいものの(この日の糸魚川市の最高気温は38度だったそうな)('A`υ)アツー、上空に日差しを遮るような雲はほとんど見あたらず、もうこの時点で約40分後に通過する“観光急行”の「急行1号」に勝利(好条件での撮影)を確信しちゃいます ( ー`дー´)カッタ。まあ得てしてこういうときに限って、ピントが甘いなどのイージーミスをしがちなのですが(笑)(。A。)アヒャ☆
まずやってきたのはこんなところ。
(「゚ー゚)ドレドレ
トンネルの上のスペースが
撮影ポイントです。
ちなみにこの場所、
大正11年(1922年)の冬に
北陸本線の列車が雪崩に強襲され
92名もの犠牲者を出す大惨事となった
現場だそうです。
ここで撮影をさせてもらう前に
手を合わせておきましょう。
( ̄人 ̄)ナム
(「゚ー゚)ドレドレ
トンネルの上のスペースが
撮影ポイントです。
ちなみにこの場所、
大正11年(1922年)の冬に
北陸本線の列車が雪崩に強襲され
92名もの犠牲者を出す大惨事となった
現場だそうです。
ここで撮影をさせてもらう前に
手を合わせておきましょう。
( ̄人 ̄)ナム
20分ほどで着いたのは、日本海ひすいラインの線路がくぐるトンネル(勝山隧道)の上に位置したスペースで (「゚ー゚)ドレドレ、ここからは向かって左手に海を入れつつ、おもに市振方面へ向かう上り列車を正面気味(下り列車は後追い)に撮れるという、当線きってのお立ち台的なメジャー撮影ポイントです (・∀・)イイネ。ただし今日の当地は好天にもかかわらず同業者の先客がゼロ。のちほど「急行1号」が通過する直前にクルマで追っかけしてきたと思われる方がお一人いらしたくらいで、まったりとした雰囲気で撮影にのぞめます (´ー`)マターリ。
青ガマ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
当地で撮影を開始して最初にやってきたのは上りの貨物列車 (4060レ)。北陸本線が第三セクター化されてトキ鉄の日本海ひすいラインとなった今も、日本海縦貫線(日本海側の主要幹線を総括した通称)の一角に含まれる当線には日本の物流を担う貨物列車が昼夜問わず頻繁に運行されています ( ̄  ̄)カモレ。
そしてその先頭に立っていたのが、かつては寝台特急「北斗星」の牽引を務めていた電気機関車で、“ブルートレインカラー”の青いEF510形500番台(514号機)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。惜しくも「北斗星」が廃止されてしまったあとの当機はJR東日本からJR貨物へと移籍し、おもに日本海縦貫線などで貨物列車の牽引を任されています (゚ー゚*)アオガマ。今日の私の狙いは“観光急行”だけど、その前にこの“元・北斗星機”が牽く貨物列車が撮れたのも嬉しい収穫でした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
そんな貨物列車を実は青海の構内で待避(通過待ち)していた上りの市振ゆき「急行1号」は(“急行”なのに貨物のほうを先に通すのは、当列車が速達性を求めない“観光列車”だから)、ほどなく続行で直線の先に姿を現します (゚∀゚)オッ!。
当地で撮影を開始して最初にやってきたのは上りの貨物列車 (4060レ)。北陸本線が第三セクター化されてトキ鉄の日本海ひすいラインとなった今も、日本海縦貫線(日本海側の主要幹線を総括した通称)の一角に含まれる当線には日本の物流を担う貨物列車が昼夜問わず頻繁に運行されています ( ̄  ̄)カモレ。
そしてその先頭に立っていたのが、かつては寝台特急「北斗星」の牽引を務めていた電気機関車で、“ブルートレインカラー”の青いEF510形500番台(514号機)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。惜しくも「北斗星」が廃止されてしまったあとの当機はJR東日本からJR貨物へと移籍し、おもに日本海縦貫線などで貨物列車の牽引を任されています (゚ー゚*)アオガマ。今日の私の狙いは“観光急行”だけど、その前にこの“元・北斗星機”が牽く貨物列車が撮れたのも嬉しい収穫でした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
そんな貨物列車を実は青海の構内で待避(通過待ち)していた上りの市振ゆき「急行1号」は(“急行”なのに貨物のほうを先に通すのは、当列車が速達性を求めない“観光列車”だから)、ほどなく続行で直線の先に姿を現します (゚∀゚)オッ!。
きゅーこー、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
陽の高い夏空のもと
青く染まる日本海を横目にみて
浜辺の鉄路を進みゆく
ローズピンクの急行列車。
その情景はまるで
国鉄だった昭和時代の北陸本線へ
タイムスリップしたかのよう。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲日本海ひすいライン 青海-親不知
陽の高い夏空のもと
青く染まる日本海を横目にみて
浜辺の鉄路を進みゆく
ローズピンクの急行列車。
その情景はまるで
国鉄だった昭和時代の北陸本線へ
タイムスリップしたかのよう。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲日本海ひすいライン 青海-親不知
海バックで国鉄急行が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
貴重な国鉄急行型の生き残りであるクハ455形(クハ455‐701)を先頭にして、日本海に沿った北陸路を西進する413系の「急行1号」 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。ローズピンクとクリームの二色に塗り分けられた落ち着いたカラーリングの交直両用急行色、オデコへ誇らしげに表示された【急 行】の赤文字、そして顔(前面)を引き締める大きなヘッドマーク、そのどれもが国鉄時代の急行列車を忠実に再現したマニアにはたまらない演出で、これぞ“昭和レトロ”的な懐古感を醸し出しています (*゚∀゚)=3ハァハァ!。う〜ん、エモいっ (≧∀≦)エモッ!。
なお、トキ鉄の“観光急行”は運転を行う二往復の順に「急行1号」〜「4号」の号数が振り分けられるだけで、愛称(列車名)はとくに付けられていないのですが、車両の前面(おもに下り方のクハ455形)には「立山」や「くずりゅう」などといった往年の国鉄急行をイメージする愛称のヘッドマークがいくつかのパターンで掲げられており(稀にヘッドマークなしというパターンもあり)、今日の運転で見られたのは、妙高高原の赤倉温泉を愛称の由来とする「赤倉」(゚ー゚*)アカクラ。
貴重な国鉄急行型の生き残りであるクハ455形(クハ455‐701)を先頭にして、日本海に沿った北陸路を西進する413系の「急行1号」 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。ローズピンクとクリームの二色に塗り分けられた落ち着いたカラーリングの交直両用急行色、オデコへ誇らしげに表示された【急 行】の赤文字、そして顔(前面)を引き締める大きなヘッドマーク、そのどれもが国鉄時代の急行列車を忠実に再現したマニアにはたまらない演出で、これぞ“昭和レトロ”的な懐古感を醸し出しています (*゚∀゚)=3ハァハァ!。う〜ん、エモいっ (≧∀≦)エモッ!。
なお、トキ鉄の“観光急行”は運転を行う二往復の順に「急行1号」〜「4号」の号数が振り分けられるだけで、愛称(列車名)はとくに付けられていないのですが、車両の前面(おもに下り方のクハ455形)には「立山」や「くずりゅう」などといった往年の国鉄急行をイメージする愛称のヘッドマークがいくつかのパターンで掲げられており(稀にヘッドマークなしというパターンもあり)、今日の運転で見られたのは、妙高高原の赤倉温泉を愛称の由来とする「赤倉」(゚ー゚*)アカクラ。
おもにキハ58系気動車や165系電車などを使用して、名古屋と新潟のあいだを中央西線、篠ノ井線、信越本線経由で結んでいた国鉄時代の急行「赤倉」(1962〜1985・初代)は、現在の日本海ひすいラインとなった旧・北陸本線を本来は走っていなかった列車ですが、日本海沿いというロケーションでみる「赤倉」は信越本線の米山(よねやま)や鯨波(くじらなみ)あたりのイメージといったところでしょうか (´ω`)ナルヘソ。
また、かつての急行「赤倉」の運行経路は、奇遇にも今日の私が往きに通ってきた篠ノ井線など被るところがあり、なんだかちょっとしたシンクロニシティ的なものを感じちゃいます w( ̄▽ ̄;)wワオッ!(ちなみに今日のヘッドマークを私は見てのお楽しみとしていて、いま通過するまで「赤倉」だとは知らなかった)。ひょっとして「18きっぷ」を活用した篠ノ井線経由のルート選択は、この「赤倉」への伏線だったのか?(゚∀゚)アヒャ☆
すでに勝利を確信していたとおり(?)、流れ雲による影落ちなどなく晴天順光の好条件で撮れた「急行1号」(^_[◎]oパチリ。個人的に満足のいく一枚が残せました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。ピントもばっちり(笑)。
また、かつての急行「赤倉」の運行経路は、奇遇にも今日の私が往きに通ってきた篠ノ井線など被るところがあり、なんだかちょっとしたシンクロニシティ的なものを感じちゃいます w( ̄▽ ̄;)wワオッ!(ちなみに今日のヘッドマークを私は見てのお楽しみとしていて、いま通過するまで「赤倉」だとは知らなかった)。ひょっとして「18きっぷ」を活用した篠ノ井線経由のルート選択は、この「赤倉」への伏線だったのか?(゚∀゚)アヒャ☆
すでに勝利を確信していたとおり(?)、流れ雲による影落ちなどなく晴天順光の好条件で撮れた「急行1号」(^_[◎]oパチリ。個人的に満足のいく一枚が残せました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。ピントもばっちり(笑)。
青海から上り方に数えて二駅先の市振を終点とする「急行1号」は、そこで折り返して下り列車の直江津ゆき「急行2号」となるため、およそ40分後にはふたたび私が居るこの付近を通過します (*゚ェ゚)フムフム。
あまり時間に余裕がないなかで次に向かったのは、最初のトンネル上の撮影ポイントからさらに国道を西へ数分ほど進んだ場所で ...(((o*・ω・)o、ここからも日本海ひすいラインの線路とともに海景色が広く望めるという好撮影地 (・∀・)イイネ。
あまり時間に余裕がないなかで次に向かったのは、最初のトンネル上の撮影ポイントからさらに国道を西へ数分ほど進んだ場所で ...(((o*・ω・)o、ここからも日本海ひすいラインの線路とともに海景色が広く望めるという好撮影地 (・∀・)イイネ。
前後をトンネルに挟まれたわずかな隙間で
一瞬だけ海を臨む単行の普通列車。
|∀・)チラッ
乗っている列車がトンネルを出て
パッと車窓に海が見えたら
旅人のテンションは上がるものですよね。
(*’∀’*)ウミ♪
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
一瞬だけ海を臨む単行の普通列車。
|∀・)チラッ
乗っている列車がトンネルを出て
パッと車窓に海が見えたら
旅人のテンションは上がるものですよね。
(*’∀’*)ウミ♪
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
ただし先ほどの撮影ポイントと異なり、ここは上り線と下り線の線路がそれぞれに離れて敷かれている、いわゆる“セパレート区間”の線形で、高台の立ち位置から確認できる海沿いの線路は直江津方面への下り線のみ。上り線のほうはトンネルの中なので見えません (゚ー゚*)セパレート。その下り線をゆく下り列車を後ろから狙う“後追い”の撮影にはなるけれど、まるで単線の路線を走っているかのようなスッキリとした画を撮ることができます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
前後をトンネルに挟まれたわずかな海辺のスキマは、列車がいつ飛び出してくるかわからず、カメラを持つ手に汗がにじむほどの高い緊張感 (`・v・´;)ドキドキ(いや、単に暑いから汗をかいてるだけ?w)。集中力を欠かそうとするように頭上で蝉の聲がやかましく響くなか ミーン<(-‘-;)>ミーン、やがてトンネルのほうから列車が通過する際に鳴らされる警告音が聞こえました (*゚ロ゚)ハッ!。
前後をトンネルに挟まれたわずかな海辺のスキマは、列車がいつ飛び出してくるかわからず、カメラを持つ手に汗がにじむほどの高い緊張感 (`・v・´;)ドキドキ(いや、単に暑いから汗をかいてるだけ?w)。集中力を欠かそうとするように頭上で蝉の聲がやかましく響くなか ミーン<(-‘-;)>ミーン、やがてトンネルのほうから列車が通過する際に鳴らされる警告音が聞こえました (*゚ロ゚)ハッ!。
国鉄急行色という
ノスタルジックな衣装を身にまとい
渚のステージに躍り出た
455形(413系)。
青さが印象的な海景色に
ピンクとクリームのツートンカラーが
しっくりと馴染みます。
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
ノスタルジックな衣装を身にまとい
渚のステージに躍り出た
455形(413系)。
青さが印象的な海景色に
ピンクとクリームのツートンカラーが
しっくりと馴染みます。
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
な〜ぎさのハイカラ急行〜、キュートなヒップ(最後尾)にずっきんどっきん♪ ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
はじめに撮った「急行1号」の撮影ポイントより、いっそう列車と海との距離が近いように感じるこのアングル。そこに収まった413系の「急行2号」は旧・北陸本線の時代を彷彿とさせる懐かしさを覚えつつも、壮観な海景色にはこれぞまさに“日本海ひすいライン”という現行の路線名にも頷けて、旅情あふれるワンシーンが展開されました。
ああ、いいねぇ・・・+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
はじめに撮った「急行1号」の撮影ポイントより、いっそう列車と海との距離が近いように感じるこのアングル。そこに収まった413系の「急行2号」は旧・北陸本線の時代を彷彿とさせる懐かしさを覚えつつも、壮観な海景色にはこれぞまさに“日本海ひすいライン”という現行の路線名にも頷けて、旅情あふれるワンシーンが展開されました。
ああ、いいねぇ・・・+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
さらに追ってもう一枚パチリ。
(^_[◎]oパチリ
夏の眩しい日差しが
車両をきれいに照らしてくれたけど、
この猛暑には列車もトンネルという日陰に
はやく入りたい!?
ε〜ε〜ε〜(((A;´з`)アヂィ
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
(^_[◎]oパチリ
夏の眩しい日差しが
車両をきれいに照らしてくれたけど、
この猛暑には列車もトンネルという日陰に
はやく入りたい!?
ε〜ε〜ε〜(((A;´з`)アヂィ
▲日本海ひすいライン 青海-親不知(後追い)
トンネルに挟まれたわずかなシャッターチャンスに緊張感を高めていたものの (`・v・´;)ドキドキ、車窓から海を眺めたい乗客へのサービス精神が旺盛(?)な“観光急行”はゆ〜っくりとした鈍足で海辺を通過してくれて ノコノコ...(((o*・ω・)o、タイミングを逸することなく余裕で撮影ができました (^_[◎]oパチリ。
そして先ほどの「急行1号」に続いてこちらの「2号」も、雲の阻まれず日差しを浴びた好条件だったのはよかったけど ε-(´∇`*)ホッ、ひとつだけ贅沢を言うならば今日の日本海はあまりにも波が穏やかすぎて、できれば浜辺にもう少し白波が立ってほしかったところかな・・・。
そして先ほどの「急行1号」に続いてこちらの「2号」も、雲の阻まれず日差しを浴びた好条件だったのはよかったけど ε-(´∇`*)ホッ、ひとつだけ贅沢を言うならば今日の日本海はあまりにも波が穏やかすぎて、できれば浜辺にもう少し白波が立ってほしかったところかな・・・。
ちなみに現地で撮っているときには
まったく気が付かなかったのですが、
あとから一つ上の写真をよく見てみたら
(=゚ω゚=*)ンン!?
列車の左上のほうの海上に
なにやら帆船のような形のお船が
写り込んでいました。
(゚ー゚*)フネ
検索してみたところどうやらこれは
糸魚川の姫川港の開港50周年を記念して
翌日から(8/5・6)同港で展示される
国内最大級の帆船「日本丸」だったみたいです。
まったく気が付かなかったのですが、
あとから一つ上の写真をよく見てみたら
(=゚ω゚=*)ンン!?
列車の左上のほうの海上に
なにやら帆船のような形のお船が
写り込んでいました。
(゚ー゚*)フネ
検索してみたところどうやらこれは
糸魚川の姫川港の開港50周年を記念して
翌日から(8/5・6)同港で展示される
国内最大級の帆船「日本丸」だったみたいです。
トンネルに入っていった「急行2号」を見送って、これにてトキ鉄の“観光急行”の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
なお“観光急行”はこのあとさらに「急行3号」〜「4号」の一往復も運行されるのですが、オナカがすいちゃった私はそれを撮らずに引き上げることとしました(笑)(›´ω`‹ )ハラヘタ。糸魚川でお昼ゴハンを食べよう。
なお“観光急行”はこのあとさらに「急行3号」〜「4号」の一往復も運行されるのですが、オナカがすいちゃった私はそれを撮らずに引き上げることとしました(笑)(›´ω`‹ )ハラヘタ。糸魚川でお昼ゴハンを食べよう。
青海から乗る直江津ゆき下り普通列車は
席が埋まっていて座れませんでした。
ま、乗るのは糸魚川までの一駅だけどさ。
▲日本海ひすいライン 青海
新潟県糸魚川市の中心駅、糸魚川。
(゚ー゚*)イトイガワ
格子模様が印象的な橋上駅舎は
北陸新幹線の開業にあわせて近年に改築されたもので
在来線側で北口にあたるこちらは「日本海口」。
ちなみに新幹線側の南口は「アルプス口」です。
▲日本海ひすいライン 糸魚川
席が埋まっていて座れませんでした。
ま、乗るのは糸魚川までの一駅だけどさ。
▲日本海ひすいライン 青海
新潟県糸魚川市の中心駅、糸魚川。
(゚ー゚*)イトイガワ
格子模様が印象的な橋上駅舎は
北陸新幹線の開業にあわせて近年に改築されたもので
在来線側で北口にあたるこちらは「日本海口」。
ちなみに新幹線側の南口は「アルプス口」です。
▲日本海ひすいライン 糸魚川
青海1412-(トキ鉄ひすいライン1639D)-糸魚川1418
糸魚川駅構内のアルプス口にある
「糸魚川ジオステーション ジオパル」には
2010年まで大糸線で使われていた
国鉄型気動車のキハ52形(キハ52 156)が
展示、保存されており、車内に入ることも可能。
(´▽`*)キハ♪
また、右のほうに見えるのは
「トワイライトエクスプレス」のA寝台個室
「スイート」を木材で再現したモックアップです。
港町の糸魚川は
新鮮な魚介類の海鮮丼などが名物ですが、
私がお昼ゴハンに選んだのは
ちょっと変わったB級ご当地グルメの
「糸魚川ブラック焼きそば」。
薄焼き玉子が焼きそばを覆っている
“オムそば”っぽいけれど、
その中身はイカ墨を使った
真っ黒なイカ焼きそばです。
( ̄▼ ̄)マックロケ
具材に惜しげもなくゴロゴロ入った
弾力のあるご当地産のイカがウマいっ。
イカ(゚д゚)ウマー!
「糸魚川ジオステーション ジオパル」には
2010年まで大糸線で使われていた
国鉄型気動車のキハ52形(キハ52 156)が
展示、保存されており、車内に入ることも可能。
(´▽`*)キハ♪
また、右のほうに見えるのは
「トワイライトエクスプレス」のA寝台個室
「スイート」を木材で再現したモックアップです。
港町の糸魚川は
新鮮な魚介類の海鮮丼などが名物ですが、
私がお昼ゴハンに選んだのは
ちょっと変わったB級ご当地グルメの
「糸魚川ブラック焼きそば」。
薄焼き玉子が焼きそばを覆っている
“オムそば”っぽいけれど、
その中身はイカ墨を使った
真っ黒なイカ焼きそばです。
( ̄▼ ̄)マックロケ
具材に惜しげもなくゴロゴロ入った
弾力のあるご当地産のイカがウマいっ。
イカ(゚д゚)ウマー!
さて、糸魚川に来るときの往路はお伝えしたとおり、撮影したい“観光急行”の時間へ間に合わせるために長野から新幹線を利用しましたが バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、帰りの復路ではなるべく追加運賃や料金をかけずに「青春18きっぷ」を活かしたいと思います (*・ω・)つ[18] 。
糸魚川から「18きっぷ」のみで乗れるJRの路線の普通列車は、大糸線の南小谷(みなみおたり)ゆき (゚ー゚*)オーイト。ただし当線の当区間(糸魚川〜南小谷)は運行本数が一日にわずか7本と極端に少なくて(その他、途中の平岩止まりが2本)、日中は二時間〜三時間も運転間隔が開く時間帯もあります ( ̄ヘ ̄)ウーン。
二往復運行されるトキ鉄の“観光急行”を私が一往復のみの撮影で切り上げたのは、もうじゅうぶんに満足のいく撮影成果が得られたからとか、オナカがすいちゃってお昼ゴハンが食べたかったからとか、あまりの暑さにもう耐えられなかったからなどということもあるけれど、ホントのところは大糸線の時刻に行程を合わせたのがいちばんの理由でした (´ω`)ナルヘソ。
糸魚川から「18きっぷ」のみで乗れるJRの路線の普通列車は、大糸線の南小谷(みなみおたり)ゆき (゚ー゚*)オーイト。ただし当線の当区間(糸魚川〜南小谷)は運行本数が一日にわずか7本と極端に少なくて(その他、途中の平岩止まりが2本)、日中は二時間〜三時間も運転間隔が開く時間帯もあります ( ̄ヘ ̄)ウーン。
二往復運行されるトキ鉄の“観光急行”を私が一往復のみの撮影で切り上げたのは、もうじゅうぶんに満足のいく撮影成果が得られたからとか、オナカがすいちゃってお昼ゴハンが食べたかったからとか、あまりの暑さにもう耐えられなかったからなどということもあるけれど、ホントのところは大糸線の時刻に行程を合わせたのがいちばんの理由でした (´ω`)ナルヘソ。
「18きっぱー」の私が
糸魚川からの帰路に選んだのは大糸線。
南小谷ゆき上り普通列車は
キハ120形の単行気動車(ディーゼルカー)で
当駅始発の列車をためしに
入線の15分くらい前から待ってみたら
ボックス席の一角を確保できました。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲大糸線 南小谷
糸魚川からの帰路に選んだのは大糸線。
南小谷ゆき上り普通列車は
キハ120形の単行気動車(ディーゼルカー)で
当駅始発の列車をためしに
入線の15分くらい前から待ってみたら
ボックス席の一角を確保できました。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲大糸線 南小谷
長野県の松本を起点に、信濃大町(しなのおおまち)や南小谷などを経て、新潟県の糸魚川へといたる大糸線は、安曇野(あずみの)と呼ばれる里山地域や北アルプス(飛騨山脈)の東麓を通ることから、自然豊かで風光明媚な沿線風景が車窓に愉しめます (・∀・)イイネ。
路線基準とは逆に終点から起点(糸魚川から松本)のほうへ上り列車で南進する今旅ではまず、当線の北部区間で沿う姫川の渓谷から眺めて、のちほど天候条件が良ければ峻険な北アルプスの山並みが望めるかもしれません (*´v`*)ワクワク♪
路線基準とは逆に終点から起点(糸魚川から松本)のほうへ上り列車で南進する今旅ではまず、当線の北部区間で沿う姫川の渓谷から眺めて、のちほど天候条件が良ければ峻険な北アルプスの山並みが望めるかもしれません (*´v`*)ワクワク♪
白馬を水源に日本海へと流れる姫川。
大糸線の列車はその清流を車窓に映して
ゆっくりと慎重に進みます。
...(((o*・ω・)o
▲大糸線 小滝-平岩(車窓から)
長野県の南小谷で大糸線をさらに南下する
信濃大町ゆき上り普通列車に乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
ここから先の当線は直流電化されていて
車両はE127系(右)です。
▲大糸線 南小谷
白馬付近で望めた北アルプスは
雲間から日光の筋がスッと差し込んで
(薄明光線、もしくは“天使の梯子”)
何とも幻想的な情景でした。
w(*゚o゚*)wオオー!
これが列車の車窓から見られるとは
乗り鉄として贅沢なひと時じゃありませんか。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲大糸線 白馬-飯森(車窓から)
高原の湖畔を走る大糸線。
海ノ口付近で見られるのは
仁科三湖のひとつ木崎湖です。
▲大糸線 海ノ口-稲尾(車窓から)
信濃大町で乗り継いだのは、
当駅始発で篠ノ井線、中央東線へと直通する
富士見ゆき上り普通列車。
この211系(右)はセミクロス仕様で
ボックスシートに座れました。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲大糸線 信濃大町
大糸線の列車はその清流を車窓に映して
ゆっくりと慎重に進みます。
...(((o*・ω・)o
▲大糸線 小滝-平岩(車窓から)
長野県の南小谷で大糸線をさらに南下する
信濃大町ゆき上り普通列車に乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
ここから先の当線は直流電化されていて
車両はE127系(右)です。
▲大糸線 南小谷
白馬付近で望めた北アルプスは
雲間から日光の筋がスッと差し込んで
(薄明光線、もしくは“天使の梯子”)
何とも幻想的な情景でした。
w(*゚o゚*)wオオー!
これが列車の車窓から見られるとは
乗り鉄として贅沢なひと時じゃありませんか。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲大糸線 白馬-飯森(車窓から)
高原の湖畔を走る大糸線。
海ノ口付近で見られるのは
仁科三湖のひとつ木崎湖です。
▲大糸線 海ノ口-稲尾(車窓から)
信濃大町で乗り継いだのは、
当駅始発で篠ノ井線、中央東線へと直通する
富士見ゆき上り普通列車。
この211系(右)はセミクロス仕様で
ボックスシートに座れました。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲大糸線 信濃大町
列車の運行本数が少なくて速達性もなく、けっして効率のいい移動手段ではないけれど、こういう大糸線のようなひなびた風情が味わえるローカル線こそ「18きっぷ」を使った“乗り鉄”の旅にぴったりの路線だと思います (´ー`)マターリ。
途中で新幹線を使った往きと違って帰路の私はとくに急ぐ理由はなく、きょうの最終電車(終電)までに都内の自宅最寄駅へ着ければOK牧場なので(基本的に「18きっぷ」が有効なのは使用当日の24時(午前0時)までですが、大都市圏の路線は24時を過ぎてもその日の終電まで有効)、缶ビールとおつまみを携えて大糸線、篠ノ井線、中央本線を乗り継ぎ、鈍行列車(普通列車)の趣を味わいながらのんびり帰るとしましょう ...(((o*・ω・)o。
途中で新幹線を使った往きと違って帰路の私はとくに急ぐ理由はなく、きょうの最終電車(終電)までに都内の自宅最寄駅へ着ければOK牧場なので(基本的に「18きっぷ」が有効なのは使用当日の24時(午前0時)までですが、大都市圏の路線は24時を過ぎてもその日の終電まで有効)、缶ビールとおつまみを携えて大糸線、篠ノ井線、中央本線を乗り継ぎ、鈍行列車(普通列車)の趣を味わいながらのんびり帰るとしましょう ...(((o*・ω・)o。
乗り継ぎで降りた中央本線の上諏訪は
なんとホーム上に無料の足湯がある駅。
(´ω`)アシユ
次の列車の待ち時間が30分ほどあるので
疲れた足を湯船に浸けていたら
先行する特急「あずさ」が走ってゆきました。
▲中央本線 上諏訪
なんとホーム上に無料の足湯がある駅。
(´ω`)アシユ
次の列車の待ち時間が30分ほどあるので
疲れた足を湯船に浸けていたら
先行する特急「あずさ」が走ってゆきました。
▲中央本線 上諏訪
流行り言葉の“昭和レトロ”を感じさせてくれるような、国鉄時代の急行型車両を懐かしみたくて、455形(413系)の“観光急行”を運転している新潟県の「えちごトキめき鉄道」へ撮影に訪れた今旅。気温38度というキビシい暑さながらも快晴の夏空のもとで海が青く染まる好条件に恵まれ、まさに“日本海ひすいライン”という路線名のイメージに合った素晴らしい情景でお目当ての“急行列車”を撮る事ができました (^_[◎]oパチリ。はるばる足を運んだ甲斐のある成果に撮り鉄として大満足です ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
そして乗り鉄としても、甲斐駒ヶ岳や八ヶ岳、姨捨の景観、妙高山、姫川の渓流に北アルプスの山並み、仁科三湖・・・と、道中の各線で車窓に眺めた甲信越の沿線風景は変化に富んだ見ごたえのあるもので、私の旅情を大いに盛り上げてくれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。新幹線の助けを借りながらも、「18きっぷ」の一回分を活用できたいいルート選択だったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。
ちなみに無粋ながら、文中でざっくりと往路の運賃計算をしていますが(都内から最終目的地の青海まで、長野〜糸魚川は新幹線を利用して実質6,920円)、復路では新幹線や特急列車を利用せずに済み、糸魚川から都内までの経路は「18きっぷ」の使用が可能なJRの在来線のみだったため、往路として計算した分に追加されたのは青海から糸魚川までトキ鉄に乗った280円だけ。結果的に今旅の往復運賃は6,920円+280円で7,200円(18きっぷ一回分を2,410円で換算)となりました。
いくつになっても使える「青春18きっぷ」(年齢制限はありません)、“永遠の青春”に万歳っ(゚∀゚)アヒャ☆
そして乗り鉄としても、甲斐駒ヶ岳や八ヶ岳、姨捨の景観、妙高山、姫川の渓流に北アルプスの山並み、仁科三湖・・・と、道中の各線で車窓に眺めた甲信越の沿線風景は変化に富んだ見ごたえのあるもので、私の旅情を大いに盛り上げてくれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。新幹線の助けを借りながらも、「18きっぷ」の一回分を活用できたいいルート選択だったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。
ちなみに無粋ながら、文中でざっくりと往路の運賃計算をしていますが(都内から最終目的地の青海まで、長野〜糸魚川は新幹線を利用して実質6,920円)、復路では新幹線や特急列車を利用せずに済み、糸魚川から都内までの経路は「18きっぷ」の使用が可能なJRの在来線のみだったため、往路として計算した分に追加されたのは青海から糸魚川までトキ鉄に乗った280円だけ。結果的に今旅の往復運賃は6,920円+280円で7,200円(18きっぷ一回分を2,410円で換算)となりました。
いくつになっても使える「青春18きっぷ」(年齢制限はありません)、“永遠の青春”に万歳っ(゚∀゚)アヒャ☆
上諏訪から乗った中央本線の
大月ゆき上り普通列車は
先日の明知鉄道からの帰りと
同じ時間の列車でした(446M)。
こちらの211系もセミクロス仕様で
ボックスシートに座れたのは嬉しい。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲中央本線 上諏訪
大月ゆき上り普通列車は
先日の明知鉄道からの帰りと
同じ時間の列車でした(446M)。
こちらの211系もセミクロス仕様で
ボックスシートに座れたのは嬉しい。
(o ̄∇ ̄o)ボックス
▲中央本線 上諏訪
糸魚川1513-(大糸432D)-南小谷1615~1618-(5348M)-信濃大町1713~1716-(1542M)-上諏訪1853~1926-(中央446M)- 大月2127~2131-(2244M 中央特快)-三鷹2243
2023-08-15 12:12
明知鉄道・・・田んぼアート 撮影記 [鉄道写真撮影記]
暑中お見舞い申し上げます。
ほぼ全国的に梅雨が明け、いよいよ夏本番 "Q(・∀・`;)アチィィ・・・。
そして学生さんの夏休みとあわせて今シーズンの「青春18きっぷ」(JR全線の普通列車、快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる期間限定のおトクなきっぷ)も有効期間(7/20〜9/10)となりました (゚∀゚)オッ!。
そのきっぷを使ってさっそく、季節感のある“夏らしい情景”を求めて、ちょいとお出かけしてみようと思います ...(((*・∀・)つ[18] 。
7月22日(土)
ほぼ全国的に梅雨が明け、いよいよ夏本番 "Q(・∀・`;)アチィィ・・・。
そして学生さんの夏休みとあわせて今シーズンの「青春18きっぷ」(JR全線の普通列車、快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる期間限定のおトクなきっぷ)も有効期間(7/20〜9/10)となりました (゚∀゚)オッ!。
そのきっぷを使ってさっそく、季節感のある“夏らしい情景”を求めて、ちょいとお出かけしてみようと思います ...(((*・∀・)つ[18] 。
7月22日(土)
とかく、“18きっぱー”(青春18きっぷ愛好者)の朝は早いもの (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…。
一日じゅう乗り放題の「18きっぷ」をフルに活用すべく、私は今回も地元の駅を朝4時半の初発列車に乗って中央本線を下り、高尾、大月、甲府と普通列車を細かく乗り継いで山梨県を横断するように、ひたすら西進します ...(((o*・ω・)o。
一日じゅう乗り放題の「18きっぷ」をフルに活用すべく、私は今回も地元の駅を朝4時半の初発列車に乗って中央本線を下り、高尾、大月、甲府と普通列車を細かく乗り継いで山梨県を横断するように、ひたすら西進します ...(((o*・ω・)o。
大月で乗り継いだ甲府ゆき普通列車は
ロングシート仕様の211系。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 大月
勝沼ぶどう郷付近で望む
高台からの甲府盆地は壮観な眺めで
私の好きな車窓風景です。
(・∀・)イイネ
今日も暑くなりそう。
▲中央本線 勝沼ぶどう郷-塩山
(車窓から)
ロングシート仕様の211系。
( ̄  ̄)ロング
▲中央本線 大月
勝沼ぶどう郷付近で望む
高台からの甲府盆地は壮観な眺めで
私の好きな車窓風景です。
(・∀・)イイネ
今日も暑くなりそう。
▲中央本線 勝沼ぶどう郷-塩山
(車窓から)
ちなみに中央本線の特急「あずさ」や「かいじ」に乗り慣れている方からすれば、普通列車の乗り継ぎなんてまどろっこしいと感じるかもしれませんが (-“-;*)トロイ、実は私のような中央線沿線民のメリットとしてこの時間帯の普通列車を利用すると、朝イチの特急列車(あずさ1号)よりも早い時刻に甲府や塩尻(しおじり)、松本まで到達することができて、篠ノ井線や大糸線などとの接続もいいんです (・o・*)ホホゥ(もちろん列車に乗っている所要時間は、特急より普通列車のほうがずっと長いけど)。
甲府では松本ゆき普通列車に乗り継ぎ。
こちらはセミクロス仕様の211系でした。
ボックスシートに座れるのは嬉しい。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲中央本線 甲府
小淵沢付近では天候条件が良ければ
甲斐駒ヶ岳をはじめとする南アルプスや
八ヶ岳連山などの雄大な山々が
車窓から望めるハズなのですが・・・
きょうはご覧のとおり。
夏の雲だねぇ。
(≡∀≡*)モクモク…
▲▲中央本線 日野春-長坂
▲中央本線 小淵沢-信濃境
(どちらも車窓から)
こちらはセミクロス仕様の211系でした。
ボックスシートに座れるのは嬉しい。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲中央本線 甲府
小淵沢付近では天候条件が良ければ
甲斐駒ヶ岳をはじめとする南アルプスや
八ヶ岳連山などの雄大な山々が
車窓から望めるハズなのですが・・・
きょうはご覧のとおり。
夏の雲だねぇ。
(≡∀≡*)モクモク…
▲▲中央本線 日野春-長坂
▲中央本線 小淵沢-信濃境
(どちらも車窓から)
きょうの甲信地方はおおむね晴れ(晴れ時々曇り)の予報ですが、前夜に雨が降ったらしく湿度はかなり高くて、夏空に湧き上がった豪快な入道雲が列車の車窓から望めるハズの南アルプスや八ヶ岳などの山々をすっぽりと隠しています (≡”≡*)ミエナイ。あいにく山の撮影(というか私の場合は山を背景とした鉄道撮影)には不向きな天候ですね。でも今旅の私の目的地は山バックの撮影ポイントではないので、とりあえずは無問題 (´σ∀`)カンケーナイネ。
県境を越えて山梨から長野へと入り、松本ゆきの普通列車を私が降りたのは塩尻 (゚ー゚*)シオジリ。
県境を越えて山梨から長野へと入り、松本ゆきの普通列車を私が降りたのは塩尻 (゚ー゚*)シオジリ。
塩尻は正式な路線の上だと東京と名古屋を一本でむすぶ中央本線の途中駅ですが、便宜的な事実上はJR東日本が管轄する中央東線(東京〜塩尻)と、JR東海が管轄する中央西線(塩尻〜名古屋)の接続駅(乗換駅)として扱われています トーセソ(゚д゚≡゚д゚)サイセソ(ちなみに松本までが中央本線と思われがちですが、塩尻〜松本は篠ノ井線の一部です)。
その塩尻で私は中央東線から西線の列車へ乗り換えるつもりなのですが、ここでの接続時間はわずか3分しかありません (゚∀゚;)3プン!。そして西線の普通列車は東線に比べて運行本数が極端に少ないうえ(日中は二時間に一本程度)、車両も二両編成で短く(ワンマン仕様の313系)、しかも当駅の塩尻始発ではないため(始発駅は松本)、とくに本日のような「18きっぷ」期間中の週末など車内の混雑は必至でしょう (゚ペ)ウーン…。塩尻から先もまだ目的地までけっこう距離があるので、仮にずっと座れずに“立ちんぼ”だったらツラいよな・・・(・ε・`)タチンボ。
そこで私は、接続待ちをしていた中津川(なかつがわ)ゆき上り普通列車(1824M)を乗らずに見送り、後続の特急列車を利用することとします ( ̄▽ ̄)トッキュー。私が手にしている「18きっぷ」では特急に乗れず、特急券はもちろん乗車券もあらためて購入しなくてはならないのですが、実は混雑回避だけでなく後述するほかの利点においても、ここで特急列車を使う価値はあると判断しました (-`ω´-*)ウム。
とりあえず次の特急列車まで30分以上の待ち時間があるので、遅い朝食?早い昼食?に“幻の塩尻名物”でも食べていきましょうか (・∀・)イイネ。これも特急を使うことのメリットのひとつと言えるかな(笑)
その塩尻で私は中央東線から西線の列車へ乗り換えるつもりなのですが、ここでの接続時間はわずか3分しかありません (゚∀゚;)3プン!。そして西線の普通列車は東線に比べて運行本数が極端に少ないうえ(日中は二時間に一本程度)、車両も二両編成で短く(ワンマン仕様の313系)、しかも当駅の塩尻始発ではないため(始発駅は松本)、とくに本日のような「18きっぷ」期間中の週末など車内の混雑は必至でしょう (゚ペ)ウーン…。塩尻から先もまだ目的地までけっこう距離があるので、仮にずっと座れずに“立ちんぼ”だったらツラいよな・・・(・ε・`)タチンボ。
そこで私は、接続待ちをしていた中津川(なかつがわ)ゆき上り普通列車(1824M)を乗らずに見送り、後続の特急列車を利用することとします ( ̄▽ ̄)トッキュー。私が手にしている「18きっぷ」では特急に乗れず、特急券はもちろん乗車券もあらためて購入しなくてはならないのですが、実は混雑回避だけでなく後述するほかの利点においても、ここで特急列車を使う価値はあると判断しました (-`ω´-*)ウム。
とりあえず次の特急列車まで30分以上の待ち時間があるので、遅い朝食?早い昼食?に“幻の塩尻名物”でも食べていきましょうか (・∀・)イイネ。これも特急を使うことのメリットのひとつと言えるかな(笑)
塩尻駅の珍景?
コンコース(連絡通路)の壁に
駅そば屋さんを表す「そば処」の看板が
立てかけられているけど
そのお店は・・・
(=゚ω゚=*)ンン!?
なんとここが入口!(笑)
Σ(゚∇゚;ノ)ノ エッ!?
ひとつ上の写真でエレベーターと比べると
その細さというか狭さがわかるかと思います。
構内のバリアフリー化で
エレベーターがあとから設置されたことにより
改札内からのお店の入口は
このような形態になっちゃったのだとか。
(´ω`)ナルヘソ
(なお改札外の待合室側からも利用できます)
そんな入口が極狭な駅そば屋さんですが
当店の名物はどんぶりいっぱいの
どデカい唐揚げがどーんとのっかった
豪快な“山賊そば”。
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!!
これはボリューム満点で食べごたえありますし
山賊焼(とり唐)のインパクトのみならず
お蕎麦が美味しいのもさすが信州。
ソバ(゚д゚)ウマー!
ちなみにこの塩尻の山賊そばは数量限定で
早い時間に売り切れてしまうことも多く
駅そば好きには“幻の一品”ともいわれています。
今日はありつけてラッキー。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
塩尻のホームに入ってきた
中央西線の特急「しなの」。
(゚ー゚*)シナノ
つい先日に後継の新型車両投入が発表されて
今後の動向がちょっと気になる383系です。
▲中央本線 塩尻
コンコース(連絡通路)の壁に
駅そば屋さんを表す「そば処」の看板が
立てかけられているけど
そのお店は・・・
(=゚ω゚=*)ンン!?
なんとここが入口!(笑)
Σ(゚∇゚;ノ)ノ エッ!?
ひとつ上の写真でエレベーターと比べると
その細さというか狭さがわかるかと思います。
構内のバリアフリー化で
エレベーターがあとから設置されたことにより
改札内からのお店の入口は
このような形態になっちゃったのだとか。
(´ω`)ナルヘソ
(なお改札外の待合室側からも利用できます)
そんな入口が極狭な駅そば屋さんですが
当店の名物はどんぶりいっぱいの
どデカい唐揚げがどーんとのっかった
豪快な“山賊そば”。
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!!
これはボリューム満点で食べごたえありますし
山賊焼(とり唐)のインパクトのみならず
お蕎麦が美味しいのもさすが信州。
ソバ(゚д゚)ウマー!
ちなみにこの塩尻の山賊そばは数量限定で
早い時間に売り切れてしまうことも多く
駅そば好きには“幻の一品”ともいわれています。
今日はありつけてラッキー。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
塩尻のホームに入ってきた
中央西線の特急「しなの」。
(゚ー゚*)シナノ
つい先日に後継の新型車両投入が発表されて
今後の動向がちょっと気になる383系です。
▲中央本線 塩尻
塩尻から利用する中央西線の名古屋ゆき特急「しなの4号」は8両編成中の前二両が自由席 (゚ー゚*)シナノ。週末の午前中に名古屋方面へ向かう特急列車の乗車率は高く、自由席は座席の大半がすでに埋まっていましたが(当列車は長野始発)、どうにか通路側に空席を見つけることができました ε-(´∇`*)ホッ。深い山あいの自然豊かな木曽路を走りゆく中央西線の列車で、窓側の席でないのはちょっと残念なところですが、座れただけでもありがたいと思いましょう (´ω`)ヨカヨカ。
山あいの木曽川に沿って走る中央西線。
車窓からもその渓谷美が望める
「寝覚の床(ねざめのとこ)」は
国の名勝に指定されている景勝地で、
竜宮城より帰った浦島太郎が
その夢からここで覚めたという伝説に由来して
そう呼ばれているのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
なおこの写真は通路側の座席を離れて
デッキの扉の窓から撮ったもの(笑)
(^_[◎]oパチリ
▲中央本線 上松-倉本
(車窓から)
車窓からもその渓谷美が望める
「寝覚の床(ねざめのとこ)」は
国の名勝に指定されている景勝地で、
竜宮城より帰った浦島太郎が
その夢からここで覚めたという伝説に由来して
そう呼ばれているのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
なおこの写真は通路側の座席を離れて
デッキの扉の窓から撮ったもの(笑)
(^_[◎]oパチリ
▲中央本線 上松-倉本
(車窓から)
塩尻で見送った先行の普通列車を途中の上松(あげまつ)でさらっと追い越し バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、普通列車だとおよそ二時間かかるところを俊足の特急「しなの」はわずか一時間ほどで走り抜けると、長野から岐阜の県境を越えてまもなく中津川に着きます。景色が見づらい通路側だったけど、やっぱり特急列車のリクライニングシートは座り心地が快適でした (´ー`)マターリ。
特急列車の利用区間は塩尻から中津川まで。
乗車券は1,690円、自由席特急券は1,200円、
合計で2,890円の“追い銭”でした
(yamatonosukeさん流の言い回しw)。
あ、いま記事を作成していて気付いたけど
特急券の発券番号が“08888”だったんだ(笑)
▲中央本線 中津川
岐阜の中津川で乗り継いだ
中央西線の名古屋ゆき快速列車は
お!個人的に初乗車となる
新型車両の315系じゃないですか。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
のっぺりしたお顔が何だかかわいい。
▲中央本線 中津川
乗車券は1,690円、自由席特急券は1,200円、
合計で2,890円の“追い銭”でした
(yamatonosukeさん流の言い回しw)。
あ、いま記事を作成していて気付いたけど
特急券の発券番号が“08888”だったんだ(笑)
▲中央本線 中津川
岐阜の中津川で乗り継いだ
中央西線の名古屋ゆき快速列車は
お!個人的に初乗車となる
新型車両の315系じゃないですか。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
のっぺりしたお顔が何だかかわいい。
▲中央本線 中津川
中津川でふたたび「18きっぷ」が使える快速列車の名古屋ゆきに乗り継ぎ ノリカエ…((((o* ̄-)o。
塩尻と中津川の区間は運行本数が少なかった中央西線の普通列車ですが、中津川から先は名古屋への通勤圏となるため列車の本数も編成の両数も一気に増えます (゚∀゚)オッ!。8両編成でガラガラに空いていた中津川始発の列車に乗って二駅ほど進み、私が下車したのは恵那(えな)。
塩尻と中津川の区間は運行本数が少なかった中央西線の普通列車ですが、中津川から先は名古屋への通勤圏となるため列車の本数も編成の両数も一気に増えます (゚∀゚)オッ!。8両編成でガラガラに空いていた中津川始発の列車に乗って二駅ほど進み、私が下車したのは恵那(えな)。
武蔵小金井0430-(中央415H)-高尾0457~0515-(1335M)-大月0551~0554-(323M)-甲府0641~0646-(423M)-塩尻0813~0849-(特急しなの4号)-中津川0951~0956-(中央5718M)-恵那1007
岐阜県南東部の東濃(とうのう)と呼ばれる地域に位置し、かつては中山道の宿場町(大井宿)として栄えた歴史のある恵那市は、里山の自然と街なみがバランスよく共存する印象の郊外都市で、名古屋から中央西線の快速列車で一時間ちょっとの中距離通勤圏にあります (゚ー゚*)エナ。
ちなみに「18きっぷ」を使った今旅の私は都内からここへ向かうのに、“東海道本線まわり(静岡、名古屋経由)”と“中央本線まわり(甲府、塩尻経由)”のどちらが、効率よく行けるのか迷うところでしたが σ(゚・゚*)ンー…(もちろん東京から名古屋まで新幹線を使うのがいちばん早くて便利なんだけどw)、経路や列車の接続などを調べた結果(塩尻から特急「しなの」を使うことも想定)、後者のほうを選択して実践しました チューオー…((((o* ̄-)o。
そんな中央本線経由でやってきた恵那には中央西線のほかに、もうひとつの鉄道路線が存在します。それが今旅の私の目的である「明知(あけち)鉄道・明知線」( ̄∇ ̄*)アケチ。
岐阜県南東部の東濃(とうのう)と呼ばれる地域に位置し、かつては中山道の宿場町(大井宿)として栄えた歴史のある恵那市は、里山の自然と街なみがバランスよく共存する印象の郊外都市で、名古屋から中央西線の快速列車で一時間ちょっとの中距離通勤圏にあります (゚ー゚*)エナ。
ちなみに「18きっぷ」を使った今旅の私は都内からここへ向かうのに、“東海道本線まわり(静岡、名古屋経由)”と“中央本線まわり(甲府、塩尻経由)”のどちらが、効率よく行けるのか迷うところでしたが σ(゚・゚*)ンー…(もちろん東京から名古屋まで新幹線を使うのがいちばん早くて便利なんだけどw)、経路や列車の接続などを調べた結果(塩尻から特急「しなの」を使うことも想定)、後者のほうを選択して実践しました チューオー…((((o* ̄-)o。
そんな中央本線経由でやってきた恵那には中央西線のほかに、もうひとつの鉄道路線が存在します。それが今旅の私の目的である「明知(あけち)鉄道・明知線」( ̄∇ ̄*)アケチ。
JRの駅舎に隣接する
こちらが明知鉄道の恵那駅。
(゚ー゚*)エナ
シンプルな駅舎ですが
有人駅の構内には
明知鉄道のグッズショップなども
設けられています。
▲明知鉄道明知線 恵那
「明知鉄道全線フリーきっぷ」は
ちょっと懐かしさを感じる硬券タイプ。
(*・∀・)つ[キップ]
恵那〜明智の普通乗車券は片道690円なので
往復運賃と1,380円のフリーきっぷは同額。
一駅でも途中下車すればおトクになります。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
こちらは明知鉄道のマスコット
・・・というか案内役の“てつじい”。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
当鉄道で静態保存されている
C12形蒸気機関車(244号機)がモチーフの
シブいキャラクターです。
(o ̄∇ ̄o)テツジイ
恵那の明知鉄道ホームで発車を待つ
明智ゆき普通列車は
クリームをベースに朱色の帯が施された
アケチ101(アケチ100形)。
明知鉄道の車両は“キハ”などでなく
“アケチ”が形式記号です。
( ̄  ̄*)アケチ
▲明知鉄道明知線 恵那
こちらが明知鉄道の恵那駅。
(゚ー゚*)エナ
シンプルな駅舎ですが
有人駅の構内には
明知鉄道のグッズショップなども
設けられています。
▲明知鉄道明知線 恵那
「明知鉄道全線フリーきっぷ」は
ちょっと懐かしさを感じる硬券タイプ。
(*・∀・)つ[キップ]
恵那〜明智の普通乗車券は片道690円なので
往復運賃と1,380円のフリーきっぷは同額。
一駅でも途中下車すればおトクになります。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
こちらは明知鉄道のマスコット
・・・というか案内役の“てつじい”。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
当鉄道で静態保存されている
C12形蒸気機関車(244号機)がモチーフの
シブいキャラクターです。
(o ̄∇ ̄o)テツジイ
恵那の明知鉄道ホームで発車を待つ
明智ゆき普通列車は
クリームをベースに朱色の帯が施された
アケチ101(アケチ100形)。
明知鉄道の車両は“キハ”などでなく
“アケチ”が形式記号です。
( ̄  ̄*)アケチ
▲明知鉄道明知線 恵那
おおむね一時間から一時間半に一本という運行間隔の明知鉄道ですが、次の列車は私が乗ってきた中央線からの接続がよくて、わずか10分後に発車 (゚∀゚)オッ!。明知鉄道のホームにはすでにアケチ100形(アケチ101)ディーゼルカーの単行ワンマン列車が待機しており、恵那の窓口で発券してもらった一日乗車券の「明知鉄道全線フリーきっぷ」を手にしてさっそくそれに乗り込みます (*・∀・)つ[キップ]。
まもなく明智(あけち)ゆきの下り普通列車はエンジンを震わせて、始発駅の恵那をゆっくりとあとにしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
まもなく明智(あけち)ゆきの下り普通列車はエンジンを震わせて、始発駅の恵那をゆっくりとあとにしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
恵那を出ると明知鉄道(右の単線)は
すぐに中央西線(左の複線)と分かれて
進路を東に取ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
ちなみに先日の拙ブログでは
総武本線と成田線の3キロにもおよぶ
“3線区間”をご紹介したけど
ここの並行区間は短い。
▲明知鉄道明知線 恵那-東野
(前方の車窓から)
恵那の街を離れると
車窓に流れるのは目に優しい自然の緑。
“タタン タタン”と車内に響く
ジョイント音(走行音)と相まって
ローカル線らしい旅情を覚えます。
(´ー`)マターリ
▲明知鉄道明知線 恵那-東野
(車窓から)
すぐに中央西線(左の複線)と分かれて
進路を東に取ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
ちなみに先日の拙ブログでは
総武本線と成田線の3キロにもおよぶ
“3線区間”をご紹介したけど
ここの並行区間は短い。
▲明知鉄道明知線 恵那-東野
(前方の車窓から)
恵那の街を離れると
車窓に流れるのは目に優しい自然の緑。
“タタン タタン”と車内に響く
ジョイント音(走行音)と相まって
ローカル線らしい旅情を覚えます。
(´ー`)マターリ
▲明知鉄道明知線 恵那-東野
(車窓から)
恵那を発車してすぐに中央西線と分かれた明知鉄道は、緩やかな上り勾配で街を離れると、やがて里山や田園が広がるのどかな田舎風景のなかを走るようになります (´ー`)マターリ。今の時期は景色の緑が濃いなぁ。
明知鉄道の明知線は、中央西線と接する恵那市の恵那を起点に、阿木(あぎ)、岩村(いわむら)、山岡(やまおか)などを経て、同市明智町(旧・明智町)の明智へといたる、25.1キロの非電化路線。昭和の末期に赤字で廃線危機となった国鉄の明知線を、おもに沿線自治体(岐阜県や恵那市、中津川市)などが出資して運営を引き継いだ、“第三セクター鉄道”のローカル線です (゚ー゚*)サンセク。ちなみに読みは同じ“あけち”でも、地域名(町名)や駅名は“明智”、社名や路線名には“明知”の漢字が用いられており、けっして変換ミス(誤字)などではありません (゚∀゚)アヒャ☆
明知鉄道の明知線は、中央西線と接する恵那市の恵那を起点に、阿木(あぎ)、岩村(いわむら)、山岡(やまおか)などを経て、同市明智町(旧・明智町)の明智へといたる、25.1キロの非電化路線。昭和の末期に赤字で廃線危機となった国鉄の明知線を、おもに沿線自治体(岐阜県や恵那市、中津川市)などが出資して運営を引き継いだ、“第三セクター鉄道”のローカル線です (゚ー゚*)サンセク。ちなみに読みは同じ“あけち”でも、地域名(町名)や駅名は“明智”、社名や路線名には“明知”の漢字が用いられており、けっして変換ミス(誤字)などではありません (゚∀゚)アヒャ☆
恵那から二駅目の飯沼は
急勾配(坂道)の途中に設けられた駅で
ホーム上の高低差(33‰)はなんと日本一!
(゚∀゚*)オオッ!
本来、駅のホームは平坦なところに
設置しなくてはならないのですが、
ここは駅を懇願する地域住民の要請により
安全性を調べたうえで特認されたそうです。
(・o・*)ナルヘソ
▲明知鉄道明知線 飯沼
(車窓から)
なんともおめでたい駅名の極楽。
(≧∀≦)ゴクラク!
金の筋斗雲(?)が乗っかった
赤い待合室のなかにはお釈迦様が、
ホームにはお地蔵さまがいらっしゃいます。
アリガタヤ 人≡∀≡*) アリガタヤ
当駅は商業施設への利便性を目的として
2008年に開業した新しい駅で、
公募によって選ばれたこの駅名は
かつて鎌倉時代の当地に存在した名刹の
“極楽寺”に由来するものだとか。
▲明知鉄道明知線 極楽
(車窓から)
路線のほぼ中間に位置する岩村は
織田信長の叔母にあたる「おつやの方」が
女城主として守っていたことで知られる
岩村城(現在は石垣のみの城址)
の城下町として栄え、
その歴史情緒が漂う古い町なみは
沿線屈指の観光スポットとなっています。
ホームにおられるのは女城主さんかな?
(´∇ノ`*)オホホ♪
▲明知鉄道明知線 岩村
(車窓から)
その岩村は線内の途中駅で唯一
上下列車の行き違いが可能な構造(交換駅)で
恵那ゆき上り列車は鮮やかな朱色がベースの
アケチ102(アケチ100形)。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
ヘッドマークが付けられているけど
とくに何かの記念ではなく
7月の暦と七夕のイラストがデザインされた
季節モノのようです。
▲明知鉄道明知線 岩村
(前方の車窓から)
花白温泉(駅)はホントに
ホームの目の前が温泉施設で
下車して1分もかからない!?
Σ(゚∇゚*ノ)ノ チカッ!
こんなに近いのなら
帰りにひとっぷろ浴びてくか
・・・と思ったのですが、
設備の故障により臨時休館中でした。
あらま残念。
▲明知鉄道明知線 花白温泉
(車窓から)
急勾配(坂道)の途中に設けられた駅で
ホーム上の高低差(33‰)はなんと日本一!
(゚∀゚*)オオッ!
本来、駅のホームは平坦なところに
設置しなくてはならないのですが、
ここは駅を懇願する地域住民の要請により
安全性を調べたうえで特認されたそうです。
(・o・*)ナルヘソ
▲明知鉄道明知線 飯沼
(車窓から)
なんともおめでたい駅名の極楽。
(≧∀≦)ゴクラク!
金の筋斗雲(?)が乗っかった
赤い待合室のなかにはお釈迦様が、
ホームにはお地蔵さまがいらっしゃいます。
アリガタヤ 人≡∀≡*) アリガタヤ
当駅は商業施設への利便性を目的として
2008年に開業した新しい駅で、
公募によって選ばれたこの駅名は
かつて鎌倉時代の当地に存在した名刹の
“極楽寺”に由来するものだとか。
▲明知鉄道明知線 極楽
(車窓から)
路線のほぼ中間に位置する岩村は
織田信長の叔母にあたる「おつやの方」が
女城主として守っていたことで知られる
岩村城(現在は石垣のみの城址)
の城下町として栄え、
その歴史情緒が漂う古い町なみは
沿線屈指の観光スポットとなっています。
ホームにおられるのは女城主さんかな?
(´∇ノ`*)オホホ♪
▲明知鉄道明知線 岩村
(車窓から)
その岩村は線内の途中駅で唯一
上下列車の行き違いが可能な構造(交換駅)で
恵那ゆき上り列車は鮮やかな朱色がベースの
アケチ102(アケチ100形)。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
ヘッドマークが付けられているけど
とくに何かの記念ではなく
7月の暦と七夕のイラストがデザインされた
季節モノのようです。
▲明知鉄道明知線 岩村
(前方の車窓から)
花白温泉(駅)はホントに
ホームの目の前が温泉施設で
下車して1分もかからない!?
Σ(゚∇゚*ノ)ノ チカッ!
こんなに近いのなら
帰りにひとっぷろ浴びてくか
・・・と思ったのですが、
設備の故障により臨時休館中でした。
あらま残念。
▲明知鉄道明知線 花白温泉
(車窓から)
大半が無人(駅員も利用者もいない)の小駅へこまめに停車しつつ、淡々と進みゆく明智ゆきの下り列車 ...(((o*・ω・)o。
“日本一の急勾配駅”(一般鉄道の駅として)がこんなところに存在するのかという意外性が面白い飯沼(いいぬま)や、シンプルな単式ホームでありながらお釈迦様やお地蔵さまが鎮座するめでたい駅名の極楽(ごくらく)、国鉄時代の趣を残す古い駅舎と交換設備に鉄ちゃんとして興味を惹かれる岩村など、短い路線距離ながらもけっこう見どころが多くて楽しめます (・∀・)イイネ。
とはいえ、雄大な高峰の山々や壮大な海景色が車窓に望めるわけでなく(そもそも岐阜に海はないw)、日本三大山城として数えられる岩村城趾の石垣なども列車からは見えません。明知鉄道の沿線に広がるのは素朴な田園風景ばかりなり ( ̄  ̄)タンボバッカ。正直いってそんな地味なローカル線を撮りに訪れた私の目的とはいかに・・・σ(゚・゚*)ンー…。
恵那より列車に揺られて40分、座席から腰を上げたのは明智の二駅手前に位置する山岡(やまおか)。
“日本一の急勾配駅”(一般鉄道の駅として)がこんなところに存在するのかという意外性が面白い飯沼(いいぬま)や、シンプルな単式ホームでありながらお釈迦様やお地蔵さまが鎮座するめでたい駅名の極楽(ごくらく)、国鉄時代の趣を残す古い駅舎と交換設備に鉄ちゃんとして興味を惹かれる岩村など、短い路線距離ながらもけっこう見どころが多くて楽しめます (・∀・)イイネ。
とはいえ、雄大な高峰の山々や壮大な海景色が車窓に望めるわけでなく(そもそも岐阜に海はないw)、日本三大山城として数えられる岩村城趾の石垣なども列車からは見えません。明知鉄道の沿線に広がるのは素朴な田園風景ばかりなり ( ̄  ̄)タンボバッカ。正直いってそんな地味なローカル線を撮りに訪れた私の目的とはいかに・・・σ(゚・゚*)ンー…。
恵那より列車に揺られて40分、座席から腰を上げたのは明智の二駅手前に位置する山岡(やまおか)。
恵那市山岡町に所在する山岡。
ローカル線らしからぬ瀟洒な駅舎(?)は
当地が生産量日本一を誇る
寒天(かんてん)のPRを目的とした
資料館の「かんてんかん」が併設されており
館内では寒天ラーメンや寒天御膳など
さまざまな寒天料理がいただけます。
( ̄。 ̄)ヘー
▲明知鉄道明知線 山岡
そしてその駅舎裏には
「かんてんかん」のカフェスペースとして
三セク転換時の1985年から99年まで使われていた
明知鉄道の初代車両・アケチ1形が
引退後も良好な状態で保存されています。
(゚∀゚)オッ!
ちなみに私が乗り潰しを目的に
初めて当線を訪れたとき(92年)は
この形式の車両に乗りました。
(*´∀`)ノ゙オヒサ
ローカル線らしからぬ瀟洒な駅舎(?)は
当地が生産量日本一を誇る
寒天(かんてん)のPRを目的とした
資料館の「かんてんかん」が併設されており
館内では寒天ラーメンや寒天御膳など
さまざまな寒天料理がいただけます。
( ̄。 ̄)ヘー
▲明知鉄道明知線 山岡
そしてその駅舎裏には
「かんてんかん」のカフェスペースとして
三セク転換時の1985年から99年まで使われていた
明知鉄道の初代車両・アケチ1形が
引退後も良好な状態で保存されています。
(゚∀゚)オッ!
ちなみに私が乗り潰しを目的に
初めて当線を訪れたとき(92年)は
この形式の車両に乗りました。
(*´∀`)ノ゙オヒサ
恵那1018-(明知7D)-山岡1057
地域のPR施設(山岡かんてんかん)が併設された山岡の駅舎(?)は立派な建物だったけど、駅のまわりはやはりのどかな田園風景 ( ̄  ̄)タンボバッカ。そんな牧歌的な環境に敷かれた非電化の線路は撮影の障害物となるようなものがほとんどなく、どこからでも適当に列車が撮れそうなものですが、私はあらかじめ調べてきた撮影ポイントを目指します ...(((o*・ω・)o。炎天下でハンパなくキビしい暑さのなか、幸いなのは目的地までの距離がそう遠くないこと 。゚(A′□`;)qアチィィ・・・。
駅から数分ほど歩いてやってきたのは、里山の起伏を活かしたような自然公園(イワクラ公園)で、さらにその園内の斜面に伸びる細道を上がってゆくと・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
駅から数分ほど歩いてやってきたのは、里山の起伏を活かしたような自然公園(イワクラ公園)で、さらにその園内の斜面に伸びる細道を上がってゆくと・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
園内でバーベキューなども楽しめる
山岡町の「イワクラ公園」。
(゚ー゚*)イワクラ
ちなみに園名の“イワクラ”とは
神が宿ると云われる巨石の
“磐座(いわくら)”のことで、
当地一帯にはそのような巨石や怪石が
多く存在するのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
木陰に幾分の涼しさを感じながら
斜面の細道を進んでゆくと・・・
...(((o*・ω・)o
その先には
高床式の東屋って感じのものが
建てられています。
(=゚ω゚=*)ンン!?
これは景色が望める展望台。
たどり着いたのはこんなところ。
あ!田んぼにお地蔵さまが描かれている!
(゚∀゚*)オオッ!
山岡町の「イワクラ公園」。
(゚ー゚*)イワクラ
ちなみに園名の“イワクラ”とは
神が宿ると云われる巨石の
“磐座(いわくら)”のことで、
当地一帯にはそのような巨石や怪石が
多く存在するのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
木陰に幾分の涼しさを感じながら
斜面の細道を進んでゆくと・・・
...(((o*・ω・)o
その先には
高床式の東屋って感じのものが
建てられています。
(=゚ω゚=*)ンン!?
これは景色が望める展望台。
たどり着いたのはこんなところ。
あ!田んぼにお地蔵さまが描かれている!
(゚∀゚*)オオッ!
園内の高台に備えられた木製の展望台からは眼下の景色が広く見渡せて (「゚ー゚)ドレドレ、そこには田んぼをキャンバスにして描かれた“お地蔵さま”の姿がクッキリと浮かび上がっているではありませんか。これはいわゆる“田んぼアート”ってやつですね w(*゚o゚*)wオオー!。先ほど見た“まだらの田んぼ”はこういうワケ (´ω`)ナルヘソ。そしてその作品の傍らには大きくカーブした明知鉄道の線路も確認できます (゚∀゚)オッ!。そう、私がここへやってきた目的は、田んぼアートと明知鉄道の列車を組み合わせて撮ることでした (・∀・)イイネ。
見事なアート作品を目にしてテンションが上がるなか、さっそくカメラを構えて次の列車を待ちます (*゚v゚*)ワクワク♪。
駄菓子菓子(だがしかし)・・・( ̄△ ̄;)エッ…。
見事なアート作品を目にしてテンションが上がるなか、さっそくカメラを構えて次の列車を待ちます (*゚v゚*)ワクワク♪。
駄菓子菓子(だがしかし)・・・( ̄△ ̄;)エッ…。
あああ、まんだーら・・・(´д`;)アウ…。
田んぼアートをじっくりと鑑賞するかのようにゆっくり進みゆくのは、アケチ10形が二両編成を組んだ急行列車の「大正ロマン2号」(゚ー゚*)ロマン。当列車は下りの明智ゆき(大正ロマン1号)として運行する際に、編成中の一両が車内で食事などを楽しめる事前予約制の“イベント列車”となっており(もう一両は普通車)、いちおう線内の数駅は通過するけれど、速達性よりも観光列車的な要素が強い急行列車です (´ω`)ナルヘソ。
そんな「大正ロマン号」でしたが、日差しが照り付ける晴天ではあるものの、上空には入道雲が崩れたような雲塊がけっこう浮遊していて、その雲影によってタイミング悪く列車が来たときに景色の上半分が翳ってしまいました (-ω-;*)クルクモル。こればかりは不可抗力で運任せのようなものだし、田んぼアートと列車にはギリギリ日が当たっただけでも救われたところですが、せっかくここまで片道7時間もかけてはるばるやってきたのですから、できれば翳られずにスッキリとした画を残したいものです σ(・∀・`)ウーン…。
気を取り直して、今度は雲が悪戯しないよう“目の前のお地蔵さま”に願いながら 八(゚- ゚)オネガイ、次の下り列車を待ちましょう。
田んぼアートをじっくりと鑑賞するかのようにゆっくり進みゆくのは、アケチ10形が二両編成を組んだ急行列車の「大正ロマン2号」(゚ー゚*)ロマン。当列車は下りの明智ゆき(大正ロマン1号)として運行する際に、編成中の一両が車内で食事などを楽しめる事前予約制の“イベント列車”となっており(もう一両は普通車)、いちおう線内の数駅は通過するけれど、速達性よりも観光列車的な要素が強い急行列車です (´ω`)ナルヘソ。
そんな「大正ロマン号」でしたが、日差しが照り付ける晴天ではあるものの、上空には入道雲が崩れたような雲塊がけっこう浮遊していて、その雲影によってタイミング悪く列車が来たときに景色の上半分が翳ってしまいました (-ω-;*)クルクモル。こればかりは不可抗力で運任せのようなものだし、田んぼアートと列車にはギリギリ日が当たっただけでも救われたところですが、せっかくここまで片道7時間もかけてはるばるやってきたのですから、できれば翳られずにスッキリとした画を残したいものです σ(・∀・`)ウーン…。
気を取り直して、今度は雲が悪戯しないよう“目の前のお地蔵さま”に願いながら 八(゚- ゚)オネガイ、次の下り列車を待ちましょう。
気温が高くてめっちゃ暑いけど、
流れ雲の動向にはヒヤヒヤ・・・。
ドキドキ(`・∀・´;)ヒヤヒヤ…
入道雲が湧き上がる夏空のもと
田園のキャンバスに描かれた
お地蔵さまに見送られて
赤い単行列車がのんびりと走りゆく。
美しい弧を描くこの線形もまた
芸術的です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志
流れ雲の動向にはヒヤヒヤ・・・。
ドキドキ(`・∀・´;)ヒヤヒヤ…
入道雲が湧き上がる夏空のもと
田園のキャンバスに描かれた
お地蔵さまに見送られて
赤い単行列車がのんびりと走りゆく。
美しい弧を描くこの線形もまた
芸術的です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志
田んぼアートでアケチが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワ〜イ♪
お地蔵さまへの願いが通じたのか、今度は雲に邪魔されず一帯が太陽の日差しに恵まれた田園風景 (つ▽≦*)マブシッ!。そこへカーブを切ってやってきた下り普通列車(9D)は、先ほど岩村の駅で見かけた(交換した)“7月マーク”付きのアケチ102で、緑の濃い夏景色に映える朱色の単行ディーゼルカーが絵になるじゃないですか 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。遠目に見れば何となく、国鉄時代のタラコ色(首都圏色)に見えなくもないような・・・(゚∀゚)アヒャ☆。いい条件のときに、いい車両が来てくれました ъ(゚Д゚)ナイス。
地元有志の方々が毎年制作されているという山岡の田んぼアート (*’∀’*)ステキ。今年のテーマは「爪切り地蔵尊花火大会」で (゚ー゚*)ツメキリ?、弘法大使が爪を使い一夜で彫ったと云われ、ご当地の山岡町(久保原地域)に祀られている「爪切り地蔵尊」と、それを奉納するとともに郷内の安隠、五穀豊穣を願って執り行われる神事の花火大会がモチーフとなっています。ほっこりとしたお地蔵さまにはそんな由緒があったのね (*・`o´・*)ホ─。
このような田んぼアートは近年に各地で見られ、なかにはスゴく凝った繊細な絵柄や、何枚もの田んぼを使った壮大なものも制作され、それはそれで見ごたえがあると思われますが w(゚o゚)wオオー!、この山岡の作品は絵柄的にもサイズ的にもこの里山ののどかな風景にしっくりとマッチした印象を受け (´ー`)シミジミ、そして何よりもカーブを描く線路を走る列車と組み合わせられるのは、鉄ちゃんにとって嬉しい環境です (・∀・)イイネ。
列車への光線状態(陽あたり具合)も申し分のない順光の好条件で、個人的に満足のいく一枚が撮れました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
お地蔵さまへの願いが通じたのか、今度は雲に邪魔されず一帯が太陽の日差しに恵まれた田園風景 (つ▽≦*)マブシッ!。そこへカーブを切ってやってきた下り普通列車(9D)は、先ほど岩村の駅で見かけた(交換した)“7月マーク”付きのアケチ102で、緑の濃い夏景色に映える朱色の単行ディーゼルカーが絵になるじゃないですか 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。遠目に見れば何となく、国鉄時代のタラコ色(首都圏色)に見えなくもないような・・・(゚∀゚)アヒャ☆。いい条件のときに、いい車両が来てくれました ъ(゚Д゚)ナイス。
地元有志の方々が毎年制作されているという山岡の田んぼアート (*’∀’*)ステキ。今年のテーマは「爪切り地蔵尊花火大会」で (゚ー゚*)ツメキリ?、弘法大使が爪を使い一夜で彫ったと云われ、ご当地の山岡町(久保原地域)に祀られている「爪切り地蔵尊」と、それを奉納するとともに郷内の安隠、五穀豊穣を願って執り行われる神事の花火大会がモチーフとなっています。ほっこりとしたお地蔵さまにはそんな由緒があったのね (*・`o´・*)ホ─。
このような田んぼアートは近年に各地で見られ、なかにはスゴく凝った繊細な絵柄や、何枚もの田んぼを使った壮大なものも制作され、それはそれで見ごたえがあると思われますが w(゚o゚)wオオー!、この山岡の作品は絵柄的にもサイズ的にもこの里山ののどかな風景にしっくりとマッチした印象を受け (´ー`)シミジミ、そして何よりもカーブを描く線路を走る列車と組み合わせられるのは、鉄ちゃんにとって嬉しい環境です (・∀・)イイネ。
列車への光線状態(陽あたり具合)も申し分のない順光の好条件で、個人的に満足のいく一枚が撮れました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
次の上り列車はタテ位置でパチリ。
(^_[◎]oパチリ
青田のなかの花火大会に
朱色のアケチ102が彩りを添えます。
なお、カーブした線路の先に見える
白っぽい建物は
山岡駅の「かんてんかん」です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志(後追い)
(^_[◎]oパチリ
青田のなかの花火大会に
朱色のアケチ102が彩りを添えます。
なお、カーブした線路の先に見える
白っぽい建物は
山岡駅の「かんてんかん」です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志(後追い)
しばらくすると、山岡から二駅先の明智で折り返してきた恵那ゆき上り列車(12D)として、アケチ102がふたたび通過 (=゚ω゚)ノ゙タライマ。このタイミングでも翳られずに日は当たってくれましたが、列車の光線状態をよく見ると先ほどの下り列車(9D)より車両側面の陽あたりがだいぶ弱くなっています σ(゚・゚*)ンー…。午前遅くの昼前くらいが順光となるこの場所、やっぱりさっきのがベストか (-`ω´-*)ウム。
ちなみに、ここへ来るまでの行程で私は中央西線の特急「しなの」を使いましたが、もしも仮に塩尻から特急でなく普通列車のみを利用して(1824M→5722M)明知鉄道に乗り継いでいたとしたら、山岡への到着は一本遅い明智ゆき下り列車、つまり展望台から撮影したアケチ102の列車(9D)となるため、いちばん光線状態のいい時間帯での撮影を逃していたところでした (;`ロ´)ハッ!。そう考えるとこれもまた、特急「しなの」を使ったメリットが活きたといえるでしょう (-`ω´-*)ウム。
上りの急行「大正ロマン2号」と上下一本ずつの普通列車(ともにアケチ102)、マンダーラもあったけど効率よく三本の列車を田んぼアートともにカメラへ収めることができて、いい収穫が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。これにて明知鉄道の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
撮影目的は達成しましたが、やはりここまできたら次の下り列車に乗って、終点の明智へ向かうとしましょうか ...(((o*・ω・)o。
ちなみに、ここへ来るまでの行程で私は中央西線の特急「しなの」を使いましたが、もしも仮に塩尻から特急でなく普通列車のみを利用して(1824M→5722M)明知鉄道に乗り継いでいたとしたら、山岡への到着は一本遅い明智ゆき下り列車、つまり展望台から撮影したアケチ102の列車(9D)となるため、いちばん光線状態のいい時間帯での撮影を逃していたところでした (;`ロ´)ハッ!。そう考えるとこれもまた、特急「しなの」を使ったメリットが活きたといえるでしょう (-`ω´-*)ウム。
上りの急行「大正ロマン2号」と上下一本ずつの普通列車(ともにアケチ102)、マンダーラもあったけど効率よく三本の列車を田んぼアートともにカメラへ収めることができて、いい収穫が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。これにて明知鉄道の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
撮影目的は達成しましたが、やはりここまできたら次の下り列車に乗って、終点の明智へ向かうとしましょうか ...(((o*・ω・)o。
山岡のホームに入ってきた
明智ゆき下り列車は
大きな赤いヘッドマークを掲げた
アケチ10形(アケチ14+10)の
急行「大正ロマン1号」。
( ̄  ̄*)ロマン
急行は次駅の野志を通過するため
明智まで一駅です。
▲明知鉄道明知線 山岡
ためしに列車の窓から眺めてみた
田んぼアートですが
う〜ん、これでは何だかわからないね・・・。
(。A。)アヒャ☆
なお、右上のほうにちょろっと見えている
丘の上の小屋みたいなものが
イワクラ公園の展望台です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志
(車窓から)
山岡から12分で明智に到着。
(・ω・)トーチャコ
「大正ロマン1号」の後方に連結されていた
食事ができるイベント車両(アケチ10)は
その名のとおり当地にゆかりのある
明智光秀公をイメージしたラッピング車。
三日月の兜がカッコいい!
(`・∀・´)キリッ!
▲明知鉄道明知線 明智
明智のホームの壁には
たくさんのヘッドマークが置かれています。
( ̄▽ ̄)マーク
アケチ102に付けられていた
“7月”のヘッドマーク然り、
明知鉄道はヘッドマーク好きなのかな?
▲明知鉄道明知線 明智
恵那市明智町(旧・恵那郡明智町)に所在する
明知鉄道の終点・明智。
(゚ー゚*)アケチ
レトロな趣が漂う白壁の駅舎は
昭和9年(1934年)の開業時に
建造されたものですが
当地の町並みのコンセプトに合わせて
大正ロマン風の暖簾がかけられています。
▲明知鉄道明知線 明智
明智ゆき下り列車は
大きな赤いヘッドマークを掲げた
アケチ10形(アケチ14+10)の
急行「大正ロマン1号」。
( ̄  ̄*)ロマン
急行は次駅の野志を通過するため
明智まで一駅です。
▲明知鉄道明知線 山岡
ためしに列車の窓から眺めてみた
田んぼアートですが
う〜ん、これでは何だかわからないね・・・。
(。A。)アヒャ☆
なお、右上のほうにちょろっと見えている
丘の上の小屋みたいなものが
イワクラ公園の展望台です。
▲明知鉄道明知線 山岡-野志
(車窓から)
山岡から12分で明智に到着。
(・ω・)トーチャコ
「大正ロマン1号」の後方に連結されていた
食事ができるイベント車両(アケチ10)は
その名のとおり当地にゆかりのある
明智光秀公をイメージしたラッピング車。
三日月の兜がカッコいい!
(`・∀・´)キリッ!
▲明知鉄道明知線 明智
明智のホームの壁には
たくさんのヘッドマークが置かれています。
( ̄▽ ̄)マーク
アケチ102に付けられていた
“7月”のヘッドマーク然り、
明知鉄道はヘッドマーク好きなのかな?
▲明知鉄道明知線 明智
恵那市明智町(旧・恵那郡明智町)に所在する
明知鉄道の終点・明智。
(゚ー゚*)アケチ
レトロな趣が漂う白壁の駅舎は
昭和9年(1934年)の開業時に
建造されたものですが
当地の町並みのコンセプトに合わせて
大正ロマン風の暖簾がかけられています。
▲明知鉄道明知線 明智
山岡1307-(明知7009D 急行)-明智1319
明智と聞くとやはり
戦国武将の明智光秀が思い浮かびますが、
その出生地は当地を含めて諸説あるらしく
ここはあくまでも“ゆかりの地”だそうです。
( ̄  ̄*)ユカリ
明智は大正ロマンの雰囲気が漂う町並みを
駅から徒歩圏内で手軽に散策できます。
(・∀・)イイネ
上写真は趣ある細道の“大正路地”、
下写真は旧・町役場(左手)と絵画館(右奥)。
戦国武将の明智光秀が思い浮かびますが、
その出生地は当地を含めて諸説あるらしく
ここはあくまでも“ゆかりの地”だそうです。
( ̄  ̄*)ユカリ
明智は大正ロマンの雰囲気が漂う町並みを
駅から徒歩圏内で手軽に散策できます。
(・∀・)イイネ
上写真は趣ある細道の“大正路地”、
下写真は旧・町役場(左手)と絵画館(右奥)。
明治から大正時代にかけて養蚕や製糸産業で栄えたという明智 (゚ー゚*)アケチ。その町なかには大正期に西洋文化の影響を受けた瀟洒な建造物がいくつも残されており、それらを観光産業に活かすべく中心街を「日本大正村」と称して町ぐるみで大正ロマンのレトロな雰囲気を演出しています ( ̄。 ̄)ヘー。昭和の建築ながら大正風の駅舎もそのひとつ。
そんな当地へ私は30年前(92年)にも一度、明知鉄道の乗り潰しが目的で訪れているけど、明智の町の印象はまったくと言っていいほど記憶に残っておらず (・・?)ハテ?、その時はひょっとしたら駅前に出た程度ですぐに折り返しの列車へ乗ってしまったのかもしれません (^^;)ゞポリポリ(乗り潰しあるあるw)。なので今回は久しぶりで懐かしいというより、あらためて新鮮な気持ちで町を一時間ほどぶらつくことができました (・∀・)イイネ。
ちなみに当地の名物グルメはハイカラな“ハヤシライス(えなハヤシ)”だそうで、それがいただけるようなお店に入ったのですが (*・ω・)ノ゙チワッス、あまりの外の暑さに生ビールがガマンできず (;゚д゚)ゴクリ…、んじゃビールと合わせるならハヤシライスより・・・ってことで、とくに名物と関係ないポークジンジャー(豚の生姜焼きね)をオーダーしちゃいますた ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。食にこだわりの薄い私の旅なんて、そんなもんです(笑)
さ、「18きっぷ」を使った普通列車の乗り継ぎを考えて、そろそろ帰路につくとしますか。ここから東京までまた7時間半もかかるしね カエロ…((((o* ̄-)o。
そんな当地へ私は30年前(92年)にも一度、明知鉄道の乗り潰しが目的で訪れているけど、明智の町の印象はまったくと言っていいほど記憶に残っておらず (・・?)ハテ?、その時はひょっとしたら駅前に出た程度ですぐに折り返しの列車へ乗ってしまったのかもしれません (^^;)ゞポリポリ(乗り潰しあるあるw)。なので今回は久しぶりで懐かしいというより、あらためて新鮮な気持ちで町を一時間ほどぶらつくことができました (・∀・)イイネ。
ちなみに当地の名物グルメはハイカラな“ハヤシライス(えなハヤシ)”だそうで、それがいただけるようなお店に入ったのですが (*・ω・)ノ゙チワッス、あまりの外の暑さに生ビールがガマンできず (;゚д゚)ゴクリ…、んじゃビールと合わせるならハヤシライスより・・・ってことで、とくに名物と関係ないポークジンジャー(豚の生姜焼きね)をオーダーしちゃいますた ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。食にこだわりの薄い私の旅なんて、そんなもんです(笑)
さ、「18きっぷ」を使った普通列車の乗り継ぎを考えて、そろそろ帰路につくとしますか。ここから東京までまた7時間半もかかるしね カエロ…((((o* ̄-)o。
恵那ゆき上り普通列車は
“7月マーク”のアケチ102。
先ほどの田んぼアートでは
当車を絡めたいい画が撮れたことに
感謝しながら乗り込みます。
(*'∀'*)アリガ㌧
▲明知鉄道明知線 明智
交換駅の岩村で
アケチ10形の下り列車と行き違い。
往路では気付きませんでしたが
当駅の構内には
昔の腕木式信号機が保存されていました。
(゚∀゚)オッ!
▲明知鉄道明知線 岩村
(前方の車窓から)
“7月マーク”のアケチ102。
先ほどの田んぼアートでは
当車を絡めたいい画が撮れたことに
感謝しながら乗り込みます。
(*'∀'*)アリガ㌧
▲明知鉄道明知線 明智
交換駅の岩村で
アケチ10形の下り列車と行き違い。
往路では気付きませんでしたが
当駅の構内には
昔の腕木式信号機が保存されていました。
(゚∀゚)オッ!
▲明知鉄道明知線 岩村
(前方の車窓から)
一日じゅう乗り放題の「青春18きっぷ」を使っていくつもの列車を乗り継ぎ ...(((*・∀・)つ[18]、夏らしい情景を求めて訪れた岐阜の明知鉄道 (゚ー゚*)アケチ。
けっして絶景の路線でなく、車窓に広がるのは田園風景ばかりという素朴なローカル線ながらも (´ー`)ノドカ、その環境を活かして沿線に作成されたご当地らしいテーマの“田んぼアート”は気分が和む素敵な作品で (゚∀゚*)オオッ!、弧を描いた線路をのんびりと走りゆく列車とあわせて眺めた情景は、はるばる足を運んで見にきた甲斐のあるものでした +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。。それを入道雲が湧く夏空のもとで撮れたことに大満足です。
そして目的の明知鉄道のみならず、その往復に利用した中央東線や西線の列車にも乗り継ぎの面白さが楽しめて(別途に料金はかかったものの、特急「しなの」を効率よく使えた行程はいい判断だったw)、また塩尻では“幻の名物”(?)が味わえるなどけっこう盛りだくさんな内容で、充実した鉄道旅を存分に満喫しました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
ただ、さすがに日帰りで都内と恵那のあいだを「18きっぷ」主体で往復するのは、体力的にちょっとキツかったけどね・・・(^^;)ゞポリポリ
けっして絶景の路線でなく、車窓に広がるのは田園風景ばかりという素朴なローカル線ながらも (´ー`)ノドカ、その環境を活かして沿線に作成されたご当地らしいテーマの“田んぼアート”は気分が和む素敵な作品で (゚∀゚*)オオッ!、弧を描いた線路をのんびりと走りゆく列車とあわせて眺めた情景は、はるばる足を運んで見にきた甲斐のあるものでした +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。。それを入道雲が湧く夏空のもとで撮れたことに大満足です。
そして目的の明知鉄道のみならず、その往復に利用した中央東線や西線の列車にも乗り継ぎの面白さが楽しめて(別途に料金はかかったものの、特急「しなの」を効率よく使えた行程はいい判断だったw)、また塩尻では“幻の名物”(?)が味わえるなどけっこう盛りだくさんな内容で、充実した鉄道旅を存分に満喫しました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
ただ、さすがに日帰りで都内と恵那のあいだを「18きっぷ」主体で往復するのは、体力的にちょっとキツかったけどね・・・(^^;)ゞポリポリ
恵那で明知鉄道から
中央西線に乗り換えます。
往きは新型の315系だったけど
今度の中津川ゆき快速列車は211系。
( ̄  ̄*)ニゲゲ
▲中央本線 恵那
中津川で乗り継いだ松本ゆき普通列車は
転換クロスシート仕様の313系。
短い二両編成のワンマン列車ですが
当駅始発なので難なく座れました。
ε-(´∇`*)ホッ
▲中央本線 中津川
塩尻で中央東線に乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
上り普通列車の大月ゆきは
セミクロスシート仕様の211系でした。
▲中央本線 塩尻
中央西線に乗り換えます。
往きは新型の315系だったけど
今度の中津川ゆき快速列車は211系。
( ̄  ̄*)ニゲゲ
▲中央本線 恵那
中津川で乗り継いだ松本ゆき普通列車は
転換クロスシート仕様の313系。
短い二両編成のワンマン列車ですが
当駅始発なので難なく座れました。
ε-(´∇`*)ホッ
▲中央本線 中津川
塩尻で中央東線に乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
上り普通列車の大月ゆきは
セミクロスシート仕様の211系でした。
▲中央本線 塩尻
明智1517-(明知16D)-恵那1607~1630-(中央5731M)-中津川1641~1657-(1837M)-塩尻1850~1859-(446M)-大月2127~2131-(2244M 中央特快)-三鷹2243
2023-07-27 17:17
成田線・・・185系「100周年バトンリレー号」 撮影記 [鉄道写真撮影記]
千葉県最東端の銚子市に所在し、銚子と犬吠埼の外川(とかわ)をむすぶ、ローカル私鉄の「銚子電鉄(通称・銚電)」(゚ー゚*)チョーデン。
当鉄道は利用者の減少などで赤字続きの経営難となり、これまでに幾度も廃線の危機に瀕したものの (´・д・`;)ハラハラ…、本業(鉄道事業)ではない“ぬれ煎餅”の売り上げなどにより救われて ヌレセン(*・∀・)つ◯、かろうじて存続したというのは、鉄ちゃんならずとも知る人が多い有名なお話ですね (-`ω´-*)ウム。
そんな苦難を乗り越えてきた銚電は、今年(2023年)の7月5日で1923年(大正12年)の開業からちょうど“100周年” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 100ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。
それを記念して、昨年(2022年)にやはり開業100周年の節目を迎えた、広島の路面電車として知られる「広島電鉄(通称・広電)」から銚電へ向けて、鉄道事業者同士の「100周年のバトン」を繋ぐ“リレーイベント”が実施されます ε=ε=((○`・v・)っ/ ヽ(○`・v・) バトンタッチ。
これは記念のバトンを持った広電の社長さんが使者となって広島空港へ行き、広島〜成田の航空便(LCCのスプリングジャパン)に搭乗。成田からはJR成田線の特別列車(団体臨時列車)に乗って銚子を目指し、銚子で銚電の社長さんにバトンを手渡して、終着駅の外川にゴールするという企画だそうです ( ̄。 ̄)ヘー(ちなみに鉄道路線のみで繋がずに間に飛行機が入るのは、本イベントに航空会社のPRが絡んでいるかららしい)。
私も鉄ちゃんの一人として銚電の100周年をお祝いする気持ちはもちろんのこと (〃'▽'〃)オメデ㌧♪、ここで注目したいのは当該イベントで成田と銚子のあいだを結ぶ成田線の特別列車「100周年バトンリレー号」(゚ー゚*)リレーゴー。その“リレー号”という列車名にかけて、かつて東北・上越新幹線の初期開業時に上野と大宮の間で運行されていた連絡列車の「新幹線リレー号」を再現したような、国鉄特急型車両の185系(リレー号色のC1編成)が使われるというではありませんか (゚∀゚*)オオッ!。これは何とも胸熱で粋な演出です ъ(゚Д゚)ナイス。
銚電のお祝いを主目的としたイベントなのにJRの列車が撮影の狙いとは、なんだか本末転倒のような矛盾を感じる気もするけど (^^;)ゞポリポリ、銚電へ行くならば梅雨時でなく天気のいい日にあらためて訪れたいと思い、今回の私は成田線の「100周年バトンリレー号」を撮りに行くこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
7月8日(土)
当鉄道は利用者の減少などで赤字続きの経営難となり、これまでに幾度も廃線の危機に瀕したものの (´・д・`;)ハラハラ…、本業(鉄道事業)ではない“ぬれ煎餅”の売り上げなどにより救われて ヌレセン(*・∀・)つ◯、かろうじて存続したというのは、鉄ちゃんならずとも知る人が多い有名なお話ですね (-`ω´-*)ウム。
そんな苦難を乗り越えてきた銚電は、今年(2023年)の7月5日で1923年(大正12年)の開業からちょうど“100周年” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 100ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。
それを記念して、昨年(2022年)にやはり開業100周年の節目を迎えた、広島の路面電車として知られる「広島電鉄(通称・広電)」から銚電へ向けて、鉄道事業者同士の「100周年のバトン」を繋ぐ“リレーイベント”が実施されます ε=ε=((○`・v・)っ/ ヽ(○`・v・) バトンタッチ。
これは記念のバトンを持った広電の社長さんが使者となって広島空港へ行き、広島〜成田の航空便(LCCのスプリングジャパン)に搭乗。成田からはJR成田線の特別列車(団体臨時列車)に乗って銚子を目指し、銚子で銚電の社長さんにバトンを手渡して、終着駅の外川にゴールするという企画だそうです ( ̄。 ̄)ヘー(ちなみに鉄道路線のみで繋がずに間に飛行機が入るのは、本イベントに航空会社のPRが絡んでいるかららしい)。
私も鉄ちゃんの一人として銚電の100周年をお祝いする気持ちはもちろんのこと (〃'▽'〃)オメデ㌧♪、ここで注目したいのは当該イベントで成田と銚子のあいだを結ぶ成田線の特別列車「100周年バトンリレー号」(゚ー゚*)リレーゴー。その“リレー号”という列車名にかけて、かつて東北・上越新幹線の初期開業時に上野と大宮の間で運行されていた連絡列車の「新幹線リレー号」を再現したような、国鉄特急型車両の185系(リレー号色のC1編成)が使われるというではありませんか (゚∀゚*)オオッ!。これは何とも胸熱で粋な演出です ъ(゚Д゚)ナイス。
銚電のお祝いを主目的としたイベントなのにJRの列車が撮影の狙いとは、なんだか本末転倒のような矛盾を感じる気もするけど (^^;)ゞポリポリ、銚電へ行くならば梅雨時でなく天気のいい日にあらためて訪れたいと思い、今回の私は成田線の「100周年バトンリレー号」を撮りに行くこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
7月8日(土)
まだ梅雨が明けていない七夕の翌日。
朝の時点で雨は降っていないものの、空はどんよりとした鉛色の雲に覆われており、出がけに見た天気予報によると今日の東京や千葉は“曇り時々雨” (-ω-;*)ドングモリ。たとえ日差しがキビシくとも、できれば晴天の撮影条件を好む私としては、いまいちテンションの上がらない空模様です σ(・∀・`)ウーン…。それでも件の「100周年バトンリレー号」が運転されるのは本日だけなので、それを逃すわけにはいきません (*`・ω・´)-3フンス!。
都内から総武緩行線(各駅停車)の下り列車に乗って東進し、千葉のほうに向かいます ...(((o*・ω・)o。
朝の時点で雨は降っていないものの、空はどんよりとした鉛色の雲に覆われており、出がけに見た天気予報によると今日の東京や千葉は“曇り時々雨” (-ω-;*)ドングモリ。たとえ日差しがキビシくとも、できれば晴天の撮影条件を好む私としては、いまいちテンションの上がらない空模様です σ(・∀・`)ウーン…。それでも件の「100周年バトンリレー号」が運転されるのは本日だけなので、それを逃すわけにはいきません (*`・ω・´)-3フンス!。
都内から総武緩行線(各駅停車)の下り列車に乗って東進し、千葉のほうに向かいます ...(((o*・ω・)o。
先の冒頭でも触れましたが、“広島の広電と銚子の銚電をバトンで繋ぐ”という今回の企画のなかで、私が撮影の目的とする「100周年バトンリレー号」が担うのは成田と銚子のあいだを結ぶ成田線(一部は総武本線)の区間。当列車はバトンの使者を乗せた広島から成田への航空便に合わせる形で設定され、成田の発車時刻が15時00分、銚子の到着時刻は17時03分と公表されています。事前に私が知っていたのもこの程度の情報のみでした φ(。_。*)フムフム。
しかし同好の士(鉄ちゃん)がSNSなどに上げてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、当列車に使われる185系(C1編成)は今日の早朝に大宮の所属基地(大宮総合車両センター)から千葉での拠点となる幕張(まくはり)の車両基地(幕張車両センター)へと送り込まれており、だいたい昼過ぎくらいに成田へ向けて回送されるらしい (・o・*)ホホゥ。
それならば成田の先で銚子ゆきの本運転(団臨としての営業運転)を待つより、成田の手前の区間で回送列車(送り込み回送)を狙うほうがいろいろと効率いいかも・・・σ(゚・゚*)ンー…。
しかし同好の士(鉄ちゃん)がSNSなどに上げてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、当列車に使われる185系(C1編成)は今日の早朝に大宮の所属基地(大宮総合車両センター)から千葉での拠点となる幕張(まくはり)の車両基地(幕張車両センター)へと送り込まれており、だいたい昼過ぎくらいに成田へ向けて回送されるらしい (・o・*)ホホゥ。
それならば成田の先で銚子ゆきの本運転(団臨としての営業運転)を待つより、成田の手前の区間で回送列車(送り込み回送)を狙うほうがいろいろと効率いいかも・・・σ(゚・゚*)ンー…。
すでに185系が送り込まれているという
幕張車両センター。
(゚ー゚*)千マリ
その様子を伺おうと思って
快速でなく各駅停車に乗ってみたのですが
車窓から185系の姿は確認できませんでした。
快速線側に留置されていたのかな?
▲総武本線 幕張本郷(車窓から)
千葉で総武本線の成東ゆきに乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
よく見ると発車案内標には
「八街回り」と表記されていますが
成東ゆきには総武本線経由の“八街回り”と
外房・東金線経由の“大網回り”があり
乗り間違えに要注意です。
▲総武本線 千葉
幕張車両センター。
(゚ー゚*)千マリ
その様子を伺おうと思って
快速でなく各駅停車に乗ってみたのですが
車窓から185系の姿は確認できませんでした。
快速線側に留置されていたのかな?
▲総武本線 幕張本郷(車窓から)
千葉で総武本線の成東ゆきに乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
よく見ると発車案内標には
「八街回り」と表記されていますが
成東ゆきには総武本線経由の“八街回り”と
外房・東金線経由の“大網回り”があり
乗り間違えに要注意です。
▲総武本線 千葉
房総各線(内房、外房、北総方面のJR線)が集まる千葉で乗り継いだのは、八街(やちまた)経由で成東(なるとう)へ向かう総武本線の下り普通列車 ( ̄  ̄*)ソーブ。
成田線ではないこの列車だと成田には行かないのですが、総武本線と成田線は千葉から途中の佐倉(さくら)まで同じ線路を進むため(というか総武本線と分岐する佐倉が成田線の正式な起点)、このあとに幕張から成田へと向かう185系の送り込み回送を佐倉より手前の区間で撮るぶんには、この成東ゆきの列車を利用しても問題はありません (-`ω´-*)ウム。
しかし私は佐倉までの区間で降りず、さらに先へと総武本線を乗り進みます ...(((o*・ω・)o。あれ?成田線から外れちゃうよ?(゚ー゚?)オヨ?
成田線ではないこの列車だと成田には行かないのですが、総武本線と成田線は千葉から途中の佐倉(さくら)まで同じ線路を進むため(というか総武本線と分岐する佐倉が成田線の正式な起点)、このあとに幕張から成田へと向かう185系の送り込み回送を佐倉より手前の区間で撮るぶんには、この成東ゆきの列車を利用しても問題はありません (-`ω´-*)ウム。
しかし私は佐倉までの区間で降りず、さらに先へと総武本線を乗り進みます ...(((o*・ω・)o。あれ?成田線から外れちゃうよ?(゚ー゚?)オヨ?
佐倉は総武本線と成田線の分岐駅
(成田線の起点)。
駅名標に表記された次駅は
酒々井が成田線、
南酒々井が総武本線です。
▲総武本線 佐倉
佐倉を出た総武本線の下り列車は
いくつかの分岐器を経て
左から右の線路へ転線してゆきます。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
向かって左の二線が複線の成田線、
右の一線が単線の総武本線。
ここは三線(三つの線路)が並行する区間です。
(*・`o´・*)ホ─
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
佐倉からおよそ3キロほど進んだところで
成田線は左へ、総武本線は右へ
それぞれカーブして分かれます。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
雑木林に囲まれて伸びる総武本線の単線。
一気にのどかさが増した印象です。
(´ー`)マターリ
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
(成田線の起点)。
駅名標に表記された次駅は
酒々井が成田線、
南酒々井が総武本線です。
▲総武本線 佐倉
佐倉を出た総武本線の下り列車は
いくつかの分岐器を経て
左から右の線路へ転線してゆきます。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
向かって左の二線が複線の成田線、
右の一線が単線の総武本線。
ここは三線(三つの線路)が並行する区間です。
(*・`o´・*)ホ─
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
佐倉からおよそ3キロほど進んだところで
成田線は左へ、総武本線は右へ
それぞれカーブして分かれます。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
雑木林に囲まれて伸びる総武本線の単線。
一気にのどかさが増した印象です。
(´ー`)マターリ
▲総武本線 佐倉-南酒々井
(前方の車窓から)
単線の総武本線と複線の成田線が並行して敷かれているという、ちょっと珍しい形態の“3線区間”を運転室の背後から興味深く眺めて楽しんだのち m(・∀・)m カブリツキ、成田線と分かれた総武本線の列車が佐倉の次に停車した南酒々井(みなみしすい)で私は下車します (・ω・)トーチャコ。
新宿1011-(中央快速918T)-御茶ノ水1020~1026-(総武緩行902B)-千葉1118~1142-(総武1347M)-南酒々井1208
南酒々井は成田線でなく総武本線の駅ですが、私が「100周年バトンリレー号」(の回送)を撮りたい目的地(撮影ポイント)は佐倉から3キロほど東へ進んだところにある総武本線と成田線の分岐点(合流点)付近に位置しており、実はそこへ行くには佐倉から歩くよりも南酒々井のほうが少し近いのです(およそ2キロ) ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
また、もうひとつ南酒々井を下車駅に選んだ理由が、周囲を雑木林に囲まれているという自然豊かな当駅の環境 (´ω`)ノドカ。目的地へと向かう前にせっかくなら、この情景を活かしてちょっと撮っていきたい列車があります σ(゚・゚*)ンー…。構内に架かる跨線橋の上で待ってみると、私が乗ってきた成東ゆき下り列車(1347M)と二駅先の八街で交換(行き違い)したその上り列車は、すぐに南酒々井へやってきました (゚∀゚)オッ!。
南酒々井は成田線でなく総武本線の駅ですが、私が「100周年バトンリレー号」(の回送)を撮りたい目的地(撮影ポイント)は佐倉から3キロほど東へ進んだところにある総武本線と成田線の分岐点(合流点)付近に位置しており、実はそこへ行くには佐倉から歩くよりも南酒々井のほうが少し近いのです(およそ2キロ) ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
また、もうひとつ南酒々井を下車駅に選んだ理由が、周囲を雑木林に囲まれているという自然豊かな当駅の環境 (´ω`)ノドカ。目的地へと向かう前にせっかくなら、この情景を活かしてちょっと撮っていきたい列車があります σ(゚・゚*)ンー…。構内に架かる跨線橋の上で待ってみると、私が乗ってきた成東ゆき下り列車(1347M)と二駅先の八街で交換(行き違い)したその上り列車は、すぐに南酒々井へやってきました (゚∀゚)オッ!。
ビューしおさい(?)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
林のなかのカーブを切って颯爽と姿を現したのは、房総半島の青い海と白い砂浜、太陽と菜の花の黄色をイメージした三色を車体に纏う255系で、銚子から総武本線経由で東京へと向かう特急「しおさい」(8号)(o ̄∇ ̄o)シオサイ。
この255系を私は先々月(5月)のゴールデンウィークにも、同じ県内の内房線を走る特急「新宿さざなみ」として東京湾を背景に撮影をしており (゚ー゚*)ニゴゴ、そのときの記事でもちょろっと触れているのですが、当系は1993年にデビューしてから30年が経過していて、車齢的に今後の動向がちょっと気になる状況 (゚ペ)ウーン…。とくに置き換え計画などが公表されたワケではありませんが、今回のように何かのついででも撮れる機会があればなるべく記録を残しておきたいところです (^_[◎]oパチリ。
嬉しいことに通過するタイミングで雲間から陽が差してくれて、駅の構内とは思えない緑豊かな南酒々井でいい感じに255系の「しおさい」を撮る事ができました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
ではあらためて南酒々井から、「100周年バトンリレー号」の回送が撮れる成田線の撮影ポイントへと向かいましょう ...(((o*・ω・)o。
林のなかのカーブを切って颯爽と姿を現したのは、房総半島の青い海と白い砂浜、太陽と菜の花の黄色をイメージした三色を車体に纏う255系で、銚子から総武本線経由で東京へと向かう特急「しおさい」(8号)(o ̄∇ ̄o)シオサイ。
この255系を私は先々月(5月)のゴールデンウィークにも、同じ県内の内房線を走る特急「新宿さざなみ」として東京湾を背景に撮影をしており (゚ー゚*)ニゴゴ、そのときの記事でもちょろっと触れているのですが、当系は1993年にデビューしてから30年が経過していて、車齢的に今後の動向がちょっと気になる状況 (゚ペ)ウーン…。とくに置き換え計画などが公表されたワケではありませんが、今回のように何かのついででも撮れる機会があればなるべく記録を残しておきたいところです (^_[◎]oパチリ。
嬉しいことに通過するタイミングで雲間から陽が差してくれて、駅の構内とは思えない緑豊かな南酒々井でいい感じに255系の「しおさい」を撮る事ができました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
ではあらためて南酒々井から、「100周年バトンリレー号」の回送が撮れる成田線の撮影ポイントへと向かいましょう ...(((o*・ω・)o。
駅から目的地までは
田園風景が広がるのどかな田舎道。
日差しの弱い曇り空だけど
蒸し暑くて額から汗が滴り落ちます。
(´Д`υ)アツーィ
進む先に見えたのは
成田線の象徴的な存在といえる
成田空港アクセス特急の
E259系「成田エクスプレス」。
( ̄  ̄*)ネックス
▲成田線 佐倉-酒々井
田園風景が広がるのどかな田舎道。
日差しの弱い曇り空だけど
蒸し暑くて額から汗が滴り落ちます。
(´Д`υ)アツーィ
進む先に見えたのは
成田線の象徴的な存在といえる
成田空港アクセス特急の
E259系「成田エクスプレス」。
( ̄  ̄*)ネックス
▲成田線 佐倉-酒々井
総武本線の線路に沿った細道を佐倉のほうへ戻るようにして歩き進むと、雑木林を抜けた先には広大な田園風景が広がっており、その向こうを赤、白、黒の三色に塗り分けられた特急「成田エクスプレス(NEX)」が走ってゆきます (゚∀゚)オッ!。「NEX」が見えたってことはそこが成田線の線路だということ (-`ω´-*)ウム。
総武本線と成田線の合流点付近で線路の上を大きく跨ぐ、国道の立派な陸橋(跨線橋)が目的地の撮影ポイントです (・ω・)トーチャコ。
総武本線と成田線の合流点付近で線路の上を大きく跨ぐ、国道の立派な陸橋(跨線橋)が目的地の撮影ポイントです (・ω・)トーチャコ。
ひとつ上の写真で「NEX」がくぐっている
青い色の陸橋の上へとやってきました。
ここは国道の歩道から安全に
景色が広く望めます。
(「゚ー゚)ドレドレ
その陸橋からパチリ。
(^_[◎]oパチリ
総武快速線から成田線へ直通して
成田空港を目指す快速列車は
徐々に数を減らしているE217系。
詳しい割合はわからないけど
今はE235系と半々くらいでしょうか?
σ(゚・゚*)ンー…
▲成田線 佐倉-酒々井
青い色の陸橋の上へとやってきました。
ここは国道の歩道から安全に
景色が広く望めます。
(「゚ー゚)ドレドレ
その陸橋からパチリ。
(^_[◎]oパチリ
総武快速線から成田線へ直通して
成田空港を目指す快速列車は
徐々に数を減らしているE217系。
詳しい割合はわからないけど
今はE235系と半々くらいでしょうか?
σ(゚・゚*)ンー…
▲成田線 佐倉-酒々井
橋上で車道の西側に備えられた安全な歩道に立つと (「゚ー゚)ドレドレ、そこからは今の時期らしい青々とした田園風景とともに、佐倉方向(上り方)へ大きくカーブする総武本線と成田線の線路が広く一望できて、これはなかなか壮観な眺めじゃないですか (・∀・)イイネ!。
そう、ここは私が先ほど乗っていた電車から前方を眺めていた、ちょっと珍しい“3線区間”(総武本線と成田線の並行区間)の一部にあたります (・o・*)ホホゥ。
そう、ここは私が先ほど乗っていた電車から前方を眺めていた、ちょっと珍しい“3線区間”(総武本線と成田線の並行区間)の一部にあたります (・o・*)ホホゥ。
私の立ち位置から見た3線区間で
いちばん奥の線路は成田線の下り線。
(゚ー゚*)ナリタ
そこを快走する「NEX」は・・・
お!前面(の貫通扉)が銀色になった
リニューアルカラーのE259系じゃん。
(゚∀゚)オッ!
▲成田線 佐倉-酒々井
いっぽう、前面(の貫通扉)が黒くて
「NEX」のロゴマークが目立つこちらは
オリジナルカラー(既存色)のE259系。
リニューアル編成はまだ目新しいけれど
今しっかりと記録すべきはコッチかな。
(^_[◎]oパチリ
▲成田線 佐倉-酒々井
オリジナル編成(右)と
リニューアル編成(左)による
先頭車同士の連結部。
こうやって見比べてみると
切り取った部分のロゴの大きさに違いはあるけど
黒から銀になった前面ほど
イメージの変化は感じられないように
個人的には思います。
σ(゚・゚*)ンー…
▲成田線 佐倉-酒々井
立ち位置から見た3線区間で
いちばん手前は単線(上下線)の総武本線。
(゚ー゚*)ソーブ
緑の絨毯と化した夏の田園を横切るのは
さきほど南酒々井でも出会った
255系の特急「しおさい」。
▲総武本線 佐倉-南酒々井
いちばん奥の線路は成田線の下り線。
(゚ー゚*)ナリタ
そこを快走する「NEX」は・・・
お!前面(の貫通扉)が銀色になった
リニューアルカラーのE259系じゃん。
(゚∀゚)オッ!
▲成田線 佐倉-酒々井
いっぽう、前面(の貫通扉)が黒くて
「NEX」のロゴマークが目立つこちらは
オリジナルカラー(既存色)のE259系。
リニューアル編成はまだ目新しいけれど
今しっかりと記録すべきはコッチかな。
(^_[◎]oパチリ
▲成田線 佐倉-酒々井
オリジナル編成(右)と
リニューアル編成(左)による
先頭車同士の連結部。
こうやって見比べてみると
切り取った部分のロゴの大きさに違いはあるけど
黒から銀になった前面ほど
イメージの変化は感じられないように
個人的には思います。
σ(゚・゚*)ンー…
▲成田線 佐倉-酒々井
立ち位置から見た3線区間で
いちばん手前は単線(上下線)の総武本線。
(゚ー゚*)ソーブ
緑の絨毯と化した夏の田園を横切るのは
さきほど南酒々井でも出会った
255系の特急「しおさい」。
▲総武本線 佐倉-南酒々井
209系の普通列車をはじめ、総武快速線と直通するE217系やE235系の快速列車、E259系の特急「成田エクスプレス」、さらには255系の特急「しおさい」など、総武本線と成田線が並行した3線区間には次々といろいろな種類の列車がやってきて、お目当ての「100周年バトンリレー号」(の回送)を待つあいだも飽きることがありません (*’∀’*)タノシイ。とくにそのなかでも、後継のE235系への置き換えで数を減らしているE217系、塗色変更のリニューアルが進められているE259系、そして先述したように動向がちょっと気になる255系などは、この機会にあわせて記録しておきたいところです (^_[◎]oパチリ。
ちなみに「100周年バトンリレー号」の本運転(団臨の営業運転)が行なわれる成田より先の区間(成田以東)の成田線だと、成田空港方面への空港支線が成田で分岐してしまうため、基本的に日中の定期列車は209系の普通列車(と貨物列車)のみの運行となっています ( ̄  ̄)ローカル。そこで今回はたとえ「100周年バトンリレー号」が本運転でなく回送列車の区間だとしても、成田の手前(成田以西)でいろいろな列車を効率よく撮ることができるこの佐倉の跨線橋を、私は撮影地に選んだのでした (´ω`)ナルヘソ。
ちなみに「100周年バトンリレー号」の本運転(団臨の営業運転)が行なわれる成田より先の区間(成田以東)の成田線だと、成田空港方面への空港支線が成田で分岐してしまうため、基本的に日中の定期列車は209系の普通列車(と貨物列車)のみの運行となっています ( ̄  ̄)ローカル。そこで今回はたとえ「100周年バトンリレー号」が本運転でなく回送列車の区間だとしても、成田の手前(成田以西)でいろいろな列車を効率よく撮ることができるこの佐倉の跨線橋を、私は撮影地に選んだのでした (´ω`)ナルヘソ。
目的の列車は回送列車なので詳しい運転時刻を私は把握していないけど、本運転となる「100周年バトンリレー号」が成田を発車するのは15時ちょうどと公表されているので、たぶん出発前に行なわれるであろうセレモニー(出発式)などを考えると、成田の二駅手前付近に位置するこの撮影ポイントを通過するのは、だいたい30分前の14時半ごろかと思われます σ(゚・゚*)ンー…。それを見計らって同業者(鉄ちゃん)がだんだんと当地にも増えてきました (*・ω・)ノ゙チワッス。
朝に家で見てきた天気予報だと今日の千葉県は“曇り時々雨”でしたが、実際は雲間から青空が覗いて時おり日も差すような空模様 (つ▽≦*)マブシッ!。車体の手前側面が南に面するこの場所は、もし晴れれば今の時間でもかろうじて日が当たるハズなので、太陽の頑張りにちょっと期待しちゃいます p(`・ω・´)q ガンガレ!。
そんな状況のなかで待つことしばし、14時26分というだいたい想定していた時刻のとおりに、カーブの奥からこちらへと近づいてくる185系の姿が確認できました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。
朝に家で見てきた天気予報だと今日の千葉県は“曇り時々雨”でしたが、実際は雲間から青空が覗いて時おり日も差すような空模様 (つ▽≦*)マブシッ!。車体の手前側面が南に面するこの場所は、もし晴れれば今の時間でもかろうじて日が当たるハズなので、太陽の頑張りにちょっと期待しちゃいます p(`・ω・´)q ガンガレ!。
そんな状況のなかで待つことしばし、14時26分というだいたい想定していた時刻のとおりに、カーブの奥からこちらへと近づいてくる185系の姿が確認できました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。
リレー号、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
広島の広電から銚子の銚電へ、
開業100周年のバトンリレーを繋ぐため
出発駅の成田へと足早に向かう185系。
緑のラインが引かれた車体色が
青々とした夏の田園風景にマッチします。
▲成田線 佐倉-酒々井
広島の広電から銚子の銚電へ、
開業100周年のバトンリレーを繋ぐため
出発駅の成田へと足早に向かう185系。
緑のラインが引かれた車体色が
青々とした夏の田園風景にマッチします。
▲成田線 佐倉-酒々井
イッパゴのリレー号が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
国鉄特急型らしい重厚なモータ音を北総の田園に響かせて、ダイナミックなアウトカーブを突き進む185系。出発駅へと送り込むための回送列車でありながら、その顔(前面)にはすでに「100周年バトンリレー号」の記念ヘッドマークが装着されており、本運転さながらの凛々しい姿を披露してくれました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
緑の横帯が引かれた185系(リレー号色・新特急色)にしっくりと収まった見覚えあるデザインのヘッドマークと、さらに当編成は先頭車の側面上部に国鉄を表す「JNR」マークも再現されていて、遠目に見ればこれはまさに往年の「新幹線リレー号」じゃないですか!w(*゚o゚*)wオオー!。ああ、懐かしいなぁ・・・+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
国鉄特急型らしい重厚なモータ音を北総の田園に響かせて、ダイナミックなアウトカーブを突き進む185系。出発駅へと送り込むための回送列車でありながら、その顔(前面)にはすでに「100周年バトンリレー号」の記念ヘッドマークが装着されており、本運転さながらの凛々しい姿を披露してくれました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
緑の横帯が引かれた185系(リレー号色・新特急色)にしっくりと収まった見覚えあるデザインのヘッドマークと、さらに当編成は先頭車の側面上部に国鉄を表す「JNR」マークも再現されていて、遠目に見ればこれはまさに往年の「新幹線リレー号」じゃないですか!w(*゚o゚*)wオオー!。ああ、懐かしいなぁ・・・+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
写真をクローズアップしてみた
「100周年バトンリレー号」のヘッドマーク。
広電と銚電をつなぐ
100周年記念のバトンリレーに
ふさわしいデザインですね。
(・∀・)イイネ
185系C1編成の車体側面に再現された
国鉄の「JNR」マーク
(Japanese National Railways)。
国鉄特急型にこれが記されていると
やっぱり引き締まります。
(`・ω・´)キリッ
▲成田線 佐倉-酒々井
「100周年バトンリレー号」のヘッドマーク。
広電と銚電をつなぐ
100周年記念のバトンリレーに
ふさわしいデザインですね。
(・∀・)イイネ
185系C1編成の車体側面に再現された
国鉄の「JNR」マーク
(Japanese National Railways)。
国鉄特急型にこれが記されていると
やっぱり引き締まります。
(`・ω・´)キリッ
▲成田線 佐倉-酒々井
落ち着いて(?)ヘッドマークをよ〜っく見てみると、かつての「新幹線リレー号」が掲出していた「新幹線連絡専用 上野⇔大宮」ではなく、そこはやはり「100周年バトン連絡専用 広島⇔銚子」となっています (゚∀゚)アヒャ☆。それでも「新幹線リレー号」を彷佛とさせるこのデザインのヘッドマークを採用した粋な遊び心に、ファンとしては楽しさと嬉しさを感じました ъ(゚Д゚)ナイス。
けっきょく通過のタイミングで太陽は雲に隠されて日が当たらなかったけど (・∀・`)ウーン…(通過直後に日が差すのは“撮り鉄あるある”w)、もしも予報どおりなら雨のなかの撮影も覚悟していたことを考えれば、寒々しい絵にならなかっただけでも救われたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。
けっきょく通過のタイミングで太陽は雲に隠されて日が当たらなかったけど (・∀・`)ウーン…(通過直後に日が差すのは“撮り鉄あるある”w)、もしも予報どおりなら雨のなかの撮影も覚悟していたことを考えれば、寒々しい絵にならなかっただけでも救われたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。
成田と銚子をむすぶ「100周年バトンリレー号」の本運転(団臨の営業運転)を控える185系にとってはこれからが本番ですが、私のほうはその大役へ向かう回送列車の後ろ姿にエールを送って本日の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。
撮影地からの帰りはちょっと歩く距離が長いけど、南酒々井よりも列車の発着本数が多い佐倉の駅へ向かうこととしました ...(((o*・ω・)o。
撮影地からの帰りはちょっと歩く距離が長いけど、南酒々井よりも列車の発着本数が多い佐倉の駅へ向かうこととしました ...(((o*・ω・)o。
千葉県佐倉市に所在する佐倉。
特急「しおさい」も停車する
総武本線・成田線の主要駅です。
(゚ー゚*)サクラサク
なお同じく市内にある
京成電鉄の京成佐倉とは
2キロほど離れており、
両駅間には路線バスが運行されています。
ちなみに佐倉といえば野球好きのかたには
長嶋茂雄さんの出身地として
知られているかもしれませんね。
(*’∀’*)ミスター!
▲総武本線 佐倉
特急「しおさい」も停車する
総武本線・成田線の主要駅です。
(゚ー゚*)サクラサク
なお同じく市内にある
京成電鉄の京成佐倉とは
2キロほど離れており、
両駅間には路線バスが運行されています。
ちなみに佐倉といえば野球好きのかたには
長嶋茂雄さんの出身地として
知られているかもしれませんね。
(*’∀’*)ミスター!
▲総武本線 佐倉
銚子電鉄の開業100周年を記念した広電から銚電へのバトンリレーで、そのバトンをつなぐために成田線で運行された「100周年バトンリレー号」ε=ε=((○`・v・)っ/ ヽ(○`・v・) バトンリレー。かつて「新幹線リレー号」に使われた185系はまさに適任で、往年を彷彿とさせる装いには懐かしさを覚えました (ノ∀`)ナツカシス。
ただ今になって見返すと、車両に掲げられた特別なヘッドマークが少しでもわかるようにと意識し、またいっぽうで緑の絨毯のような田園風景で今の時期らしい季節感も表したいとも思って、画的にはちょっと面白味のない無難なまとめ方をしてしまった気がします σ(・∀・`)ウーン…。列車主体か情景主体か、どっちかに割り切ったほうがよかったかな・・・ (^^;)ゞポリポリ 。
「リレー号」はそんな結果でしたが、そのほかにもE259系の「成田エクスプレス」や255系の「しおさい」、E217系の快速列車など、特異な3線区間を行き交ういろいろな列車がみられて、楽しみながらいい記録を残すことができました (^_[◎]oパチリ。
そしてめでたくも100周年を迎えた銚電には、またあらためて訪れる機会を伺おうと思っています。
ただ今になって見返すと、車両に掲げられた特別なヘッドマークが少しでもわかるようにと意識し、またいっぽうで緑の絨毯のような田園風景で今の時期らしい季節感も表したいとも思って、画的にはちょっと面白味のない無難なまとめ方をしてしまった気がします σ(・∀・`)ウーン…。列車主体か情景主体か、どっちかに割り切ったほうがよかったかな・・・ (^^;)ゞポリポリ 。
「リレー号」はそんな結果でしたが、そのほかにもE259系の「成田エクスプレス」や255系の「しおさい」、E217系の快速列車など、特異な3線区間を行き交ういろいろな列車がみられて、楽しみながらいい記録を残すことができました (^_[◎]oパチリ。
そしてめでたくも100周年を迎えた銚電には、またあらためて訪れる機会を伺おうと思っています。
総武本線と成田線をあわせると
南酒々井より列車の本数が多くて
成田空港からの快速も停まる佐倉ですが、
次の千葉ゆき上り普通列車は
総武本線から来たものでした。
これなら南酒々井で乗っても
いっしょだったな・・・。
(。A。)アヒャ☆
▲総武本線 佐倉
南酒々井より列車の本数が多くて
成田空港からの快速も停まる佐倉ですが、
次の千葉ゆき上り普通列車は
総武本線から来たものでした。
これなら南酒々井で乗っても
いっしょだったな・・・。
(。A。)アヒャ☆
▲総武本線 佐倉
佐倉1514-(総武360M)-千葉1531~1540-(総武快速1420F)-東京1622
オマケ
千葉駅の土産物屋さんで見かけた
名菓の「ぴーなっつ最中」。
なんで「SPY×FAMILY」との
コラボなのかと思ったら
アーニャの好物がぴーなっつだからなのね。
(o ̄∇ ̄o)アーニャ
千葉駅の土産物屋さんで見かけた
名菓の「ぴーなっつ最中」。
なんで「SPY×FAMILY」との
コラボなのかと思ったら
アーニャの好物がぴーなっつだからなのね。
(o ̄∇ ̄o)アーニャ
2023-07-13 20:20