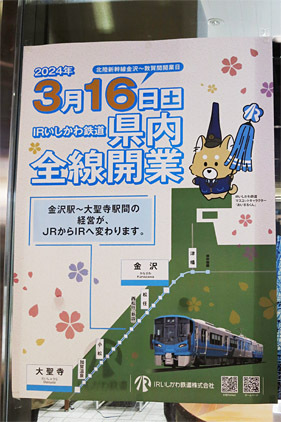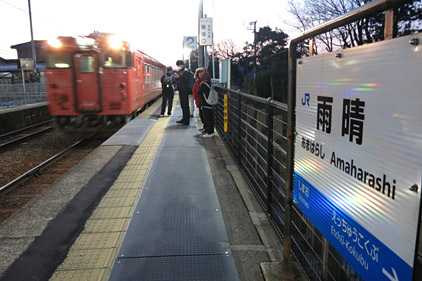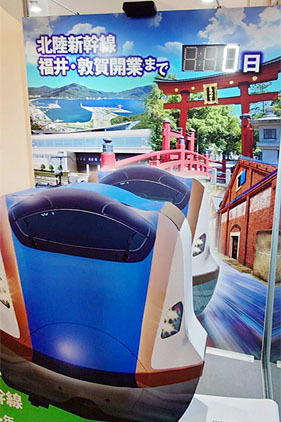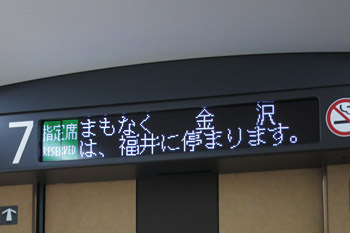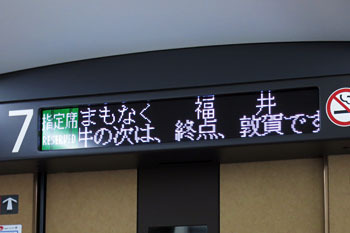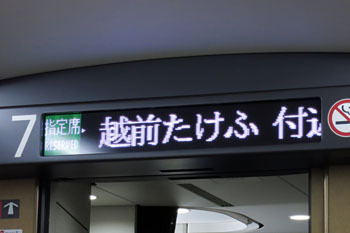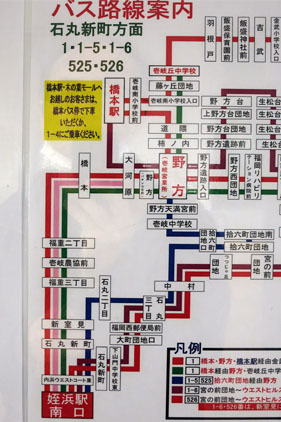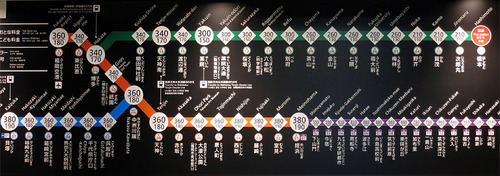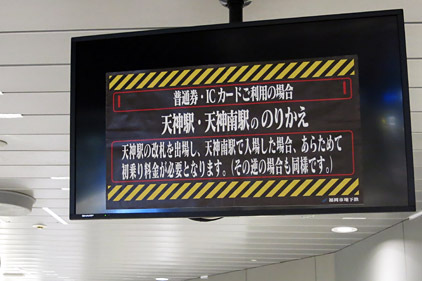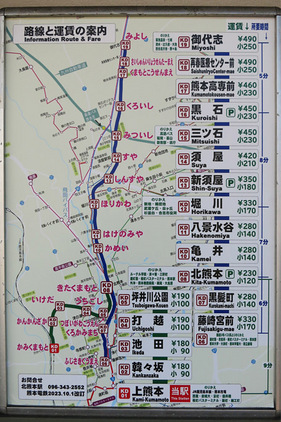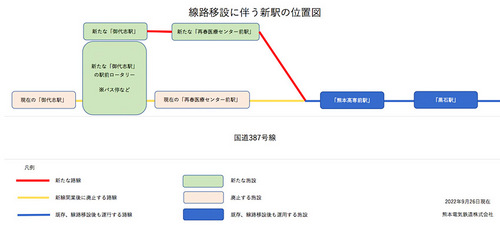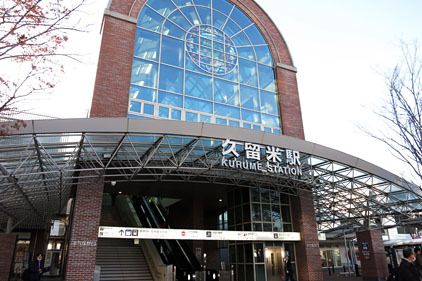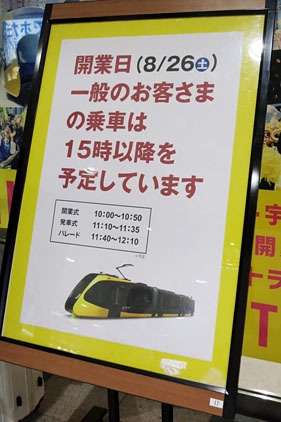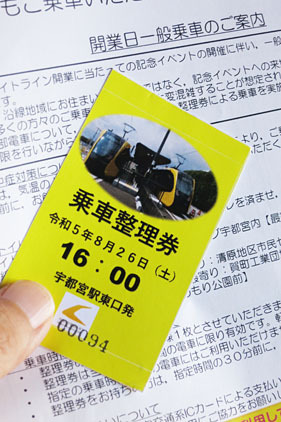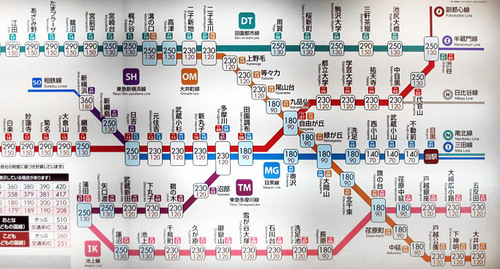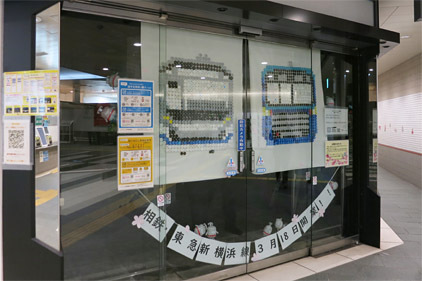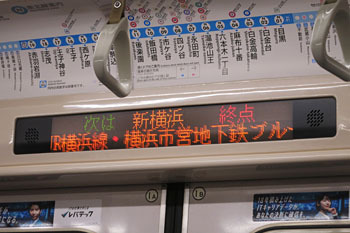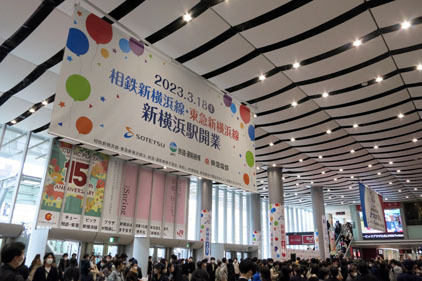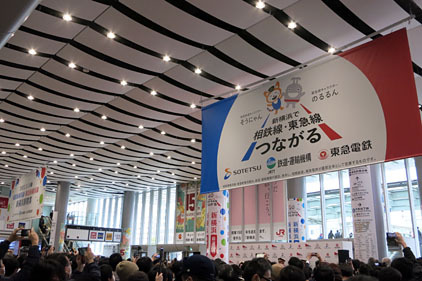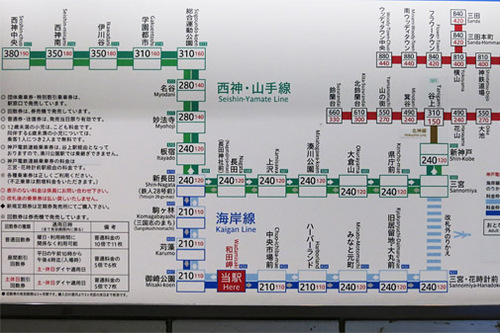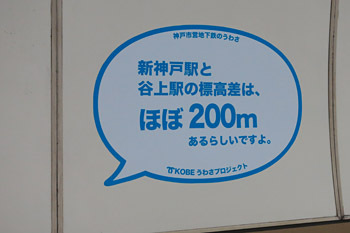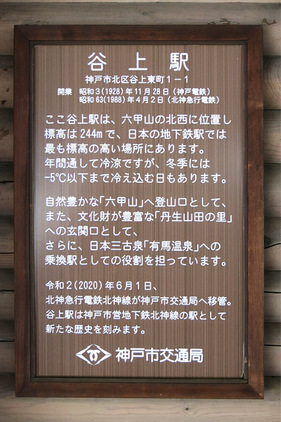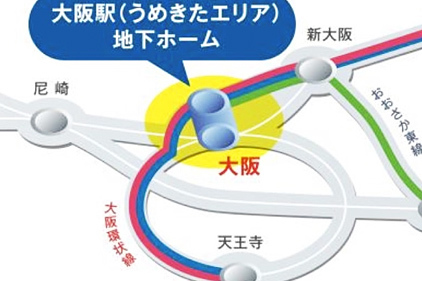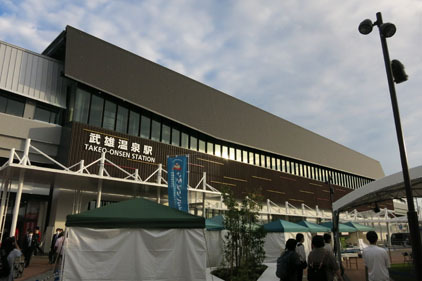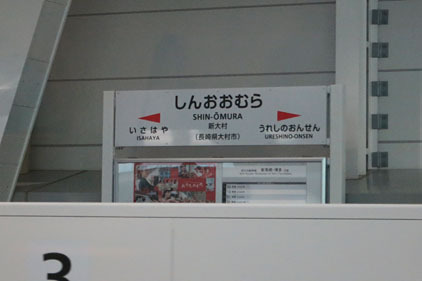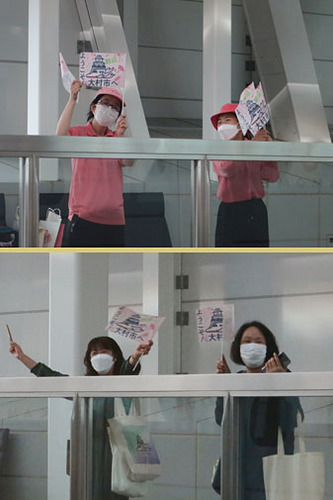IRいしかわ鉄道・・・県内開業初日 乗車記 [鉄道乗車記]
前回からの続きです。
3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)
鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を目指す私はさっそく、その初日に東京から敦賀まで北陸新幹線の「かがやき」に乗車して、金沢〜敦賀の延伸区間を踏破 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。
続いて敦賀からは、新幹線の延伸開業にともなってJR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、福井県の第三セクター鉄道として新たに“再出発”となった「ハピラインふくい(線)」に乗車します (o ̄∇ ̄o)ハピライン。
車内は多くの乗客で混み合っていたけれど、車窓より眺める沿線風景に北陸本線の撮影へ訪れた過去の思い出などを振り返りながら県内を北進し ...(((o*・ω・)o、今庄(いまじょう)、武生(たけふ)、鯖江(さばえ)など個人的に少し馴染みのある各駅を経て、ハピラインの普通列車はやがて県都の福井に着きました (゚ー゚*)フクイ。
3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)
鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を目指す私はさっそく、その初日に東京から敦賀まで北陸新幹線の「かがやき」に乗車して、金沢〜敦賀の延伸区間を踏破 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。
続いて敦賀からは、新幹線の延伸開業にともなってJR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、福井県の第三セクター鉄道として新たに“再出発”となった「ハピラインふくい(線)」に乗車します (o ̄∇ ̄o)ハピライン。
車内は多くの乗客で混み合っていたけれど、車窓より眺める沿線風景に北陸本線の撮影へ訪れた過去の思い出などを振り返りながら県内を北進し ...(((o*・ω・)o、今庄(いまじょう)、武生(たけふ)、鯖江(さばえ)など個人的に少し馴染みのある各駅を経て、ハピラインの普通列車はやがて県都の福井に着きました (゚ー゚*)フクイ。
敦賀と大聖寺(だいしょうじ)の間をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗りかえる必要があります ノリカエ…((((o* ̄-)o 。
そのついでに時間のタイミングがちょうど合った(というか行程を合わせた)新幹線開業祝いの“ブルーインパルス”の演技飛行を福井の駅前広場で観覧したのち (=゚ω゚)ブルー!、慌ただしくも再びハピラインのホームへと戻った私が次に乗るのは金沢ゆきの普通列車。
そのついでに時間のタイミングがちょうど合った(というか行程を合わせた)新幹線開業祝いの“ブルーインパルス”の演技飛行を福井の駅前広場で観覧したのち (=゚ω゚)ブルー!、慌ただしくも再びハピラインのホームへと戻った私が次に乗るのは金沢ゆきの普通列車。
福井から乗るハピラインの下り列車は
まだJR西日本仕様(譲渡前)のままで
青い帯の521系。
( ̄  ̄*)オフル
この編成もいずれはピンク色の
“ハピラインカラー”になるのでしょう。
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
まだJR西日本仕様(譲渡前)のままで
青い帯の521系。
( ̄  ̄*)オフル
この編成もいずれはピンク色の
“ハピラインカラー”になるのでしょう。
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
この列車が走る福井と金沢のあいだも、先ほど(前記事)の敦賀〜福井と同様にこれまではJRの北陸本線だった区間ですが、やはり並行在来線としてJRから第三セクター鉄道へ転換され、県境を越えたところに位置する大聖寺までが福井県の“ハピラインふくい”、そこから先は石川県の“IRいしかわ鉄道”となりますが、列車は両線(両社)を直通して運行されます (*゚ェ゚)フムフム。ただし運賃はハピラインといしかわ鉄道でそれぞれに分けられるため、福井〜金沢はJRのころにくらべて片道の普通運賃が320円も高くなってしまいました(利用区間よっては割引制度があり)。この結果的な値上げが地域の利用者にとって、いちばんツラい“三セク化の弊害”ではないでしょうか ( ̄ヘ ̄)ウーン。
そんなふたつの三セク鉄道を直通する金沢ゆき下り普通列車は、遅れることなく定刻に福井を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。なお、この列車もさっきの列車(敦賀〜福井)ほどではないものの車内は混み気味で (´д`;)人大杉…、席に座れなかった私はやはり立って車窓の景色を眺めます (「゚ー゚)ドレドレ。
そんなふたつの三セク鉄道を直通する金沢ゆき下り普通列車は、遅れることなく定刻に福井を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。なお、この列車もさっきの列車(敦賀〜福井)ほどではないものの車内は混み気味で (´д`;)人大杉…、席に座れなかった私はやはり立って車窓の景色を眺めます (「゚ー゚)ドレドレ。
福井を出て市街地を抜けると
先ほど(前々記事)新幹線からも眺めた
九頭竜川(くずりゅうがわ)を渡ります。
( ̄  ̄*)クズリュー
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井-森田
(車窓から)
その九頭竜川を跨ぐ鉄橋
(九頭竜川橋梁)は
列車の編成がスッキリと撮れる
プレートガーダー橋であることから
福井近郊のお手軽な撮影ポイントとして
私も何度か北陸本線の撮影に
訪れたことがあります。
(^_[◎]oパチリ
このときは泊まりがけの出張ついでに
青森から大阪を目指す夜行列車の
寝台特急「日本海」を撮っていました。
(´ω`)ナツカシス
▲10.3.28 北陸本線 森田-福井
坂井市の丸岡にある丸岡城は
現存するなかで日本最古の
歴史ある天守閣を持つ城であり
また城跡に整備された霞ヶ城公園は
県内屈指の桜の名所でもあります。
(・∀・)イイネ
なお丸岡駅から丸岡城までは約4キロ
バスで15分ほど。
▲24.3.16 ハピラインふくい 丸岡
(車窓から)
丸岡の駅名標の上にも
ちらっと覗いていますが
このあたりの車窓からは
白山(白山連峰)の雄大な山容が
きれいに望めました。
(゚∀゚)オッ!
ちなみに写真の左下のほうに
目を凝らすと小さく見えるのは
北陸新幹線の高架橋です。
▲24.3.16 ハピラインふくい 春江-丸岡
(車窓から)
先ほど(前々記事)新幹線からも眺めた
九頭竜川(くずりゅうがわ)を渡ります。
( ̄  ̄*)クズリュー
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井-森田
(車窓から)
その九頭竜川を跨ぐ鉄橋
(九頭竜川橋梁)は
列車の編成がスッキリと撮れる
プレートガーダー橋であることから
福井近郊のお手軽な撮影ポイントとして
私も何度か北陸本線の撮影に
訪れたことがあります。
(^_[◎]oパチリ
このときは泊まりがけの出張ついでに
青森から大阪を目指す夜行列車の
寝台特急「日本海」を撮っていました。
(´ω`)ナツカシス
▲10.3.28 北陸本線 森田-福井
坂井市の丸岡にある丸岡城は
現存するなかで日本最古の
歴史ある天守閣を持つ城であり
また城跡に整備された霞ヶ城公園は
県内屈指の桜の名所でもあります。
(・∀・)イイネ
なお丸岡駅から丸岡城までは約4キロ
バスで15分ほど。
▲24.3.16 ハピラインふくい 丸岡
(車窓から)
丸岡の駅名標の上にも
ちらっと覗いていますが
このあたりの車窓からは
白山(白山連峰)の雄大な山容が
きれいに望めました。
(゚∀゚)オッ!
ちなみに写真の左下のほうに
目を凝らすと小さく見えるのは
北陸新幹線の高架橋です。
▲24.3.16 ハピラインふくい 春江-丸岡
(車窓から)
福井駅前でブルーインパルスの演技飛行がきれいにみえたとおり、きょうの北陸地方は午後も引き続き青空が広がる好天で (´▽`*)オテンキ♪、福井平野の田園風景をコトコトと走りゆくハピラインの車窓からは、進行方向の右手(東方)に白山(白山連峰)の美しい山なみが望めています (゚∀゚)オッ!。
ちなみに山の手前にはハピラインと並行する北陸新幹線の真新しい高架橋も確認でき、私が来るときに乗った北陸新幹線「かがやき」のA席(下りの進行に向かって右側)ではあまりよく見えませんでしたが、反対側のE席(左側)に座れば白山の眺めをより楽しめることでしょう (´ω`)ナルヘソ(もちろん天候条件が良ければ)。あくまでも個人的な印象だけど、北陸新幹線はやっぱりE席側のほうに見どころが多いかな σ(゚・゚*)ンー…。
そんな北陸新幹線の高架橋がハピラインのほうに近づいてきたところで、列車はまもなく新幹線との接続駅である芦原温泉(あわらおんせん)に停車 ( ̄  ̄*)アワラ。あわら市の中心であり、温泉観光地(芦原温泉)の玄関口でもある当駅では多くの人が下車して、私はここで窓側の席(進行に向かって右側)に座ることができました ε-(´∇`*)ホッ。
んじゃ、車内がすいたことだし、福井で買ってきた駅弁を広げてお昼ゴハンとしますか (・∀・)イイネ。
ちなみに山の手前にはハピラインと並行する北陸新幹線の真新しい高架橋も確認でき、私が来るときに乗った北陸新幹線「かがやき」のA席(下りの進行に向かって右側)ではあまりよく見えませんでしたが、反対側のE席(左側)に座れば白山の眺めをより楽しめることでしょう (´ω`)ナルヘソ(もちろん天候条件が良ければ)。あくまでも個人的な印象だけど、北陸新幹線はやっぱりE席側のほうに見どころが多いかな σ(゚・゚*)ンー…。
そんな北陸新幹線の高架橋がハピラインのほうに近づいてきたところで、列車はまもなく新幹線との接続駅である芦原温泉(あわらおんせん)に停車 ( ̄  ̄*)アワラ。あわら市の中心であり、温泉観光地(芦原温泉)の玄関口でもある当駅では多くの人が下車して、私はここで窓側の席(進行に向かって右側)に座ることができました ε-(´∇`*)ホッ。
んじゃ、車内がすいたことだし、福井で買ってきた駅弁を広げてお昼ゴハンとしますか (・∀・)イイネ。
あわら市に所在する芦原温泉駅は
その駅名のとおり
140年の長い歴史を誇る越前きっての名湯
芦原温泉の最寄駅。
( ̄  ̄*)アワラ
また北陸新幹線の駅が本日開業し
新幹線との接続駅となりました。
▲24.3.16 ハピラインふくい 芦原温泉
(車窓から)
乗車前に福井駅の売店で買ってきたのは
北陸新幹線の延伸開業を記念する
期間限定販売の駅弁で
福井で駅弁を扱う番匠本店さんと
横浜のシウマイ弁当でお馴染みの
崎陽軒さんがコラボした
「北陸シウマイ入り
番匠本店 北陸新幹線弁当」(¥1,500)
(o ̄∇ ̄o)オベント♪
蟹めしや鶏肉の西京焼、若狭牛のしぐれ煮
たくあん煮たの、麩の辛子和えなど
福井の郷土料理をイメージしたものに
富山の白エビ、石川のいしる(魚醤)、
福井県のふくいサーモンを練り込んだ
崎陽軒特製の“北陸シウマイ”を盛り合わせた
内容豊富で豪華なお弁当です。
(゚д゚)ウマー!
駅弁を食べながら
車窓の景色を眺めていると
列車は細呂木(ほそろぎ)に停車。
(゚ー゚*)ホソロギ
このあたりも個人的に何度か
北陸本線の撮影に訪れたことがあります。
▲24.3.16 ハピラインふくい 細呂木
(車窓から)
これは2007年に撮影した
細呂木と芦原温泉の間を力走する
北陸本線の特急「雷鳥」。
イラストマークを掲げた485系は
“これぞ国鉄特急”といった
伝統的な風格が感じられました。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
当時はこの好条件(しかもGW)でも
私のほかに同業者はおらず
一人でまったりと撮れた頃だなぁ笑
(´ー`)マターリ
▲07.4.29 北陸本線 細呂木-芦原温泉
素朴な無人駅の牛ノ谷は
福井県最北端の駅で
列車が当駅を出てすぐのところにある
牛ノ谷峠の熊坂トンネルが
石川との県境です。
▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷
(車窓から)
景色が大きく変わるわけではないけど
トンネルを抜けるとそこは石川県。
(゚ー゚*)イシカワカスミ
▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷-大聖寺
(車窓から)
その駅名のとおり
140年の長い歴史を誇る越前きっての名湯
芦原温泉の最寄駅。
( ̄  ̄*)アワラ
また北陸新幹線の駅が本日開業し
新幹線との接続駅となりました。
▲24.3.16 ハピラインふくい 芦原温泉
(車窓から)
乗車前に福井駅の売店で買ってきたのは
北陸新幹線の延伸開業を記念する
期間限定販売の駅弁で
福井で駅弁を扱う番匠本店さんと
横浜のシウマイ弁当でお馴染みの
崎陽軒さんがコラボした
「北陸シウマイ入り
番匠本店 北陸新幹線弁当」(¥1,500)
(o ̄∇ ̄o)オベント♪
蟹めしや鶏肉の西京焼、若狭牛のしぐれ煮
たくあん煮たの、麩の辛子和えなど
福井の郷土料理をイメージしたものに
富山の白エビ、石川のいしる(魚醤)、
福井県のふくいサーモンを練り込んだ
崎陽軒特製の“北陸シウマイ”を盛り合わせた
内容豊富で豪華なお弁当です。
(゚д゚)ウマー!
駅弁を食べながら
車窓の景色を眺めていると
列車は細呂木(ほそろぎ)に停車。
(゚ー゚*)ホソロギ
このあたりも個人的に何度か
北陸本線の撮影に訪れたことがあります。
▲24.3.16 ハピラインふくい 細呂木
(車窓から)
これは2007年に撮影した
細呂木と芦原温泉の間を力走する
北陸本線の特急「雷鳥」。
イラストマークを掲げた485系は
“これぞ国鉄特急”といった
伝統的な風格が感じられました。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
当時はこの好条件(しかもGW)でも
私のほかに同業者はおらず
一人でまったりと撮れた頃だなぁ笑
(´ー`)マターリ
▲07.4.29 北陸本線 細呂木-芦原温泉
素朴な無人駅の牛ノ谷は
福井県最北端の駅で
列車が当駅を出てすぐのところにある
牛ノ谷峠の熊坂トンネルが
石川との県境です。
▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷
(車窓から)
景色が大きく変わるわけではないけど
トンネルを抜けるとそこは石川県。
(゚ー゚*)イシカワカスミ
▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷-大聖寺
(車窓から)
福井と金沢の二都市を直通でむすぶ列車とはいえ、運行区間のなかでは比較的利用者が少なめとなる県境付近 (´ー`)マターリ。すいている車内で駅弁を味わいながら、のんびりと車窓の景色を眺めていると ≠( ̄〜 ̄*)モグモグ、やがて列車は牛ノ谷峠をトンネルで抜けて福井から石川へと入り、まもなく加賀市の大聖寺に停車します。
石川県加賀市に所在する大聖寺は
IRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅。
なお当駅はいしかわ鉄道の管轄で
駅名標も青いもの(いしかわ鉄道デザイン)に
変わりました。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 大聖寺
(車窓から)
IRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅。
なお当駅はいしかわ鉄道の管轄で
駅名標も青いもの(いしかわ鉄道デザイン)に
変わりました。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 大聖寺
(車窓から)
県境の石川側に位置する大聖寺はIRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅であり、ハピラインにとっては路線の終点となるため、この時点で私はハピラインふくいの全線完乗(敦賀〜大聖寺)を達成 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。ただし先述したとおり、ここから先の大聖寺と金沢の間もJRから三セク鉄道に移管されて本日よりIRいしかわ鉄道(線)となったため、やはりあらためて乗り直す必要がある私はそのまま直通列車の金沢ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。
ちなみに境界駅となって存在感が増した(?)大聖寺は、加賀藩支藩の大聖寺藩の城下町として、また北国街道の宿場町として栄えた歴史があり、かつてはそこに地名の由来となった寺院の大聖寺があったようですが、現在の当地に大聖寺というお寺は存在しないらしい ( ´_ゝ`)フーン。
ちなみに境界駅となって存在感が増した(?)大聖寺は、加賀藩支藩の大聖寺藩の城下町として、また北国街道の宿場町として栄えた歴史があり、かつてはそこに地名の由来となった寺院の大聖寺があったようですが、現在の当地に大聖寺というお寺は存在しないらしい ( ´_ゝ`)フーン。
大聖寺の次の加賀温泉は
加賀市の中心駅で
本日開業した北陸新幹線との接続駅。
( ̄  ̄*)レディカガ
ちなみに加賀温泉の名称は
あわづ、山代、山中、片山津の
4つの温泉からなる総称です
(加賀温泉郷)。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉
(車窓から)
そして加賀温泉といえば
73メートルの高さにインパクトがある
“黄金の巨大な観音さま”こと
加賀大観音。
高速で通過する新幹線では
ちらっと見えた程度でしたが
停車したいしかわ鉄道の車窓からは
赤子を抱いた観音さまのお姿が
じっくりと(?)拝めました。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉
(車窓から)
加賀市の中心駅で
本日開業した北陸新幹線との接続駅。
( ̄  ̄*)レディカガ
ちなみに加賀温泉の名称は
あわづ、山代、山中、片山津の
4つの温泉からなる総称です
(加賀温泉郷)。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉
(車窓から)
そして加賀温泉といえば
73メートルの高さにインパクトがある
“黄金の巨大な観音さま”こと
加賀大観音。
高速で通過する新幹線では
ちらっと見えた程度でしたが
停車したいしかわ鉄道の車窓からは
赤子を抱いた観音さまのお姿が
じっくりと(?)拝めました。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉
(車窓から)
石川県に入ってもきれいに見え続けている白山を右手に臨みながら、いしかわ鉄道を北上する金沢ゆき普通列車 ...(((o*・ω・)o。
大聖寺から乗り入れた「IRいしかわ鉄道」は、2015年に北陸新幹線の長野と金沢のあいだが延伸開業したことにともない、JRから経営が分離された北陸本線(並行在来線)の石川県部分にあたる金沢と倶利伽羅(くりから)の間(17.8キロ)を引き継いで誕生した第三セクター鉄道ですが ( ̄  ̄*)サンセク、このたび新幹線の金沢と敦賀のあいだがさらに延伸されたことで、北陸本線の大聖寺と金沢の間(46.4キロ)もJRからいしかわ鉄道へ移管。これによりあらためてIRいしかわ鉄道線は大聖寺と倶利伽羅のあいだ(64.2キロ)をむすぶ路線となりました (・o・*)ホホゥ。
なお、私はすでに2015年の開業(三セク移管)初日に金沢〜倶利伽羅をいしかわ鉄道として乗っているため(その後も何度か)、今回は新たに編入された大聖寺〜金沢が乗りつぶし(乗り直し)の対象区間です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
大聖寺から乗り入れた「IRいしかわ鉄道」は、2015年に北陸新幹線の長野と金沢のあいだが延伸開業したことにともない、JRから経営が分離された北陸本線(並行在来線)の石川県部分にあたる金沢と倶利伽羅(くりから)の間(17.8キロ)を引き継いで誕生した第三セクター鉄道ですが ( ̄  ̄*)サンセク、このたび新幹線の金沢と敦賀のあいだがさらに延伸されたことで、北陸本線の大聖寺と金沢の間(46.4キロ)もJRからいしかわ鉄道へ移管。これによりあらためてIRいしかわ鉄道線は大聖寺と倶利伽羅のあいだ(64.2キロ)をむすぶ路線となりました (・o・*)ホホゥ。
なお、私はすでに2015年の開業(三セク移管)初日に金沢〜倶利伽羅をいしかわ鉄道として乗っているため(その後も何度か)、今回は新たに編入された大聖寺〜金沢が乗りつぶし(乗り直し)の対象区間です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
空港所在地(小松空港)と
建設機械メーカー(コマツ)の
企業城下町として知られる
小松市の小松も
本日に新幹線の駅が開業した
北陸新幹線との接続駅。
(゚ー゚*)コマツナナ
ちなみに当駅の近くの広場には
かつて北陸本線などで活躍した
国鉄特急型の489系(クハ489形)が
保存されているのですが
以前に私がそこを訪れたときには
車体の塗装を剥離しての大掛かりな
整備作業中だったため
またあらためて再訪したいところです。
(-`ω´-*)ウム
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松
(車窓から)
小松市郊外の
“明峰(めいほう)”付近からも
少し霞み気味ではあるものの
“名峰”の白山がよく見えます。
(゚ー゚*)ハクサン
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松-明峰
(車窓から)
白山市に所在する
西松任(にしまっとう)は
大聖寺〜金沢の三セク移管に合わせて
本日開業した新駅。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
一般公募による駅名は
白山市に由来する“白山(はくさん)”が
有力視されていましたが
選ばれたのは西松任でした。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西松任
(車窓から)
松任(まっとう)は白山市の中心駅。
( ̄  ̄*)マットー
この駅名(地名)を聞くと
鉄ちゃんとしては
国鉄(JR)の車両整備工場として
当地に存在した
松任工場(金沢総合車両所松任本所)が
思い浮かびます。
σ(゚・゚*)ンー…
なお当所(当工場)は
このたびの三セク化に伴う組織変更で
昨年(2023年)の9月に閉鎖。
その後の様子を確認したかったけど
車内が混んでいて反対側(左手)の車窓は
よく見えませんでした。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 松任
(車窓から)
建設機械メーカー(コマツ)の
企業城下町として知られる
小松市の小松も
本日に新幹線の駅が開業した
北陸新幹線との接続駅。
(゚ー゚*)コマツナナ
ちなみに当駅の近くの広場には
かつて北陸本線などで活躍した
国鉄特急型の489系(クハ489形)が
保存されているのですが
以前に私がそこを訪れたときには
車体の塗装を剥離しての大掛かりな
整備作業中だったため
またあらためて再訪したいところです。
(-`ω´-*)ウム
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松
(車窓から)
小松市郊外の
“明峰(めいほう)”付近からも
少し霞み気味ではあるものの
“名峰”の白山がよく見えます。
(゚ー゚*)ハクサン
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松-明峰
(車窓から)
白山市に所在する
西松任(にしまっとう)は
大聖寺〜金沢の三セク移管に合わせて
本日開業した新駅。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
一般公募による駅名は
白山市に由来する“白山(はくさん)”が
有力視されていましたが
選ばれたのは西松任でした。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西松任
(車窓から)
松任(まっとう)は白山市の中心駅。
( ̄  ̄*)マットー
この駅名(地名)を聞くと
鉄ちゃんとしては
国鉄(JR)の車両整備工場として
当地に存在した
松任工場(金沢総合車両所松任本所)が
思い浮かびます。
σ(゚・゚*)ンー…
なお当所(当工場)は
このたびの三セク化に伴う組織変更で
昨年(2023年)の9月に閉鎖。
その後の様子を確認したかったけど
車内が混んでいて反対側(左手)の車窓は
よく見えませんでした。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 松任
(車窓から)
加賀平野の広大な田園風景を淡々と走る列車の車窓風景は、白山の山並み以外にこれといって個人的に目を引くものがとくになく、乗車記録の写真も位置を表すだけのような駅名標の羅列となってしまいます ( ̄  ̄*)エキ。その駅名標はいしかわ鉄道のコーポレートカラーが青のためか、JR西日本のときのものとあまり変わらない印象で(というかぶっちゃけ、JRのものにいしかわ鉄道のマークを上張りしただけ? (。A。)アヒャ☆)、ピンクとなったハピラインのような新鮮さはあまり感じられません。
金沢のひとつ手前(上り方)で
金沢市内に所在する西金沢は
北陸鉄道石川線の新西金沢が隣接する
乗換可能駅。
新幹線の高架下にちらっと
北陸鉄道の架線柱が確認できます。
|∀・)チラッ
当線には鶴来〜加賀一の宮が
部分廃止された2009年以来
しばらくご無沙汰だなぁ・・・。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西金沢
(車窓から)
金沢市内に所在する西金沢は
北陸鉄道石川線の新西金沢が隣接する
乗換可能駅。
新幹線の高架下にちらっと
北陸鉄道の架線柱が確認できます。
|∀・)チラッ
当線には鶴来〜加賀一の宮が
部分廃止された2009年以来
しばらくご無沙汰だなぁ・・・。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西金沢
(車窓から)
県境のあたりでは一時的にすいた車内でしたが、その後は加賀温泉、小松、松任(まっとう)と金沢近郊の市街地へ近づくにつれて徐々に利用者が増えて σ(゚・゚*)ンー…、ふたたび混雑した状態となった列車はそれにより10分程度の遅れで県都の金沢に到着 (・ω・)トーチャコ。大聖寺と倶利伽羅をむすぶいしかわ鉄道で、金沢はきょうから路線の途中にある中間駅となりましたが、私が福井から乗ってきた列車は当駅が終点です。
そしてこの列車から降りた時点で私はIRいしかわ鉄道として未乗だった大聖寺~金沢を乗りつぶしたこととなり、乗車済みの既存区間(金沢~倶利伽羅)とあわせて当線の全線完乗を達成しました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
そしてこの列車から降りた時点で私はIRいしかわ鉄道として未乗だった大聖寺~金沢を乗りつぶしたこととなり、乗車済みの既存区間(金沢~倶利伽羅)とあわせて当線の全線完乗を達成しました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
福井から普通列車に揺られること
およそ一時間半。
多くの乗降客でごったがえす
金沢に到着しました。
(・ω・)トーチャコ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢
これまで北陸本線の主要駅として
長い歴史を刻んできた金沢ですが
きょうから当駅の在来線は
三セクのIRいしかわ鉄道となりました。
改札の表記を見るとその実感がわきます。
( ̄  ̄*)イシテツ
なお津端で分岐するJR七尾線は
いしかわ鉄道へ乗り入れる形で
当駅を起終点に発着しています。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢
今回の開業(三セク移管)により
あらためて大聖寺〜倶利伽羅が
路線区間となったIRいしかわ鉄道線。
おそらくこれ以上は
路線が伸びないと思われることから
“県内全線開業”とうたっています。
(*゚▽゚)/゚・:*【開業 ☆彡】*:・゚\(゚▽゚*)
(ただ富山の城端線や氷見線の例といった
昨今の合理化を進める流れを鑑みると
いずれ七尾線の移管などありえるかも?)
いっぽう駅の構内には
県民に馴染まれて親しみのあった
北陸本線に対する労いのメッセージも
掲げられていました。
とうとう金沢から北陸本線が消えたか・・・。
(´・ω・`)ショボン
夜の金沢で顔をそろえる
北陸本線の寝台特急「北陸」(右)と
夜行急行「能登」(左)。
多くの長距離列車が発着していた
金沢の北陸本線ホームは
高架化されて近代的になっても
旅情が溢れていました。
(´ω`)シミジミ
これは今から15年前の
2009年に撮影したもので
懐かしいという感情はまだ薄いけど
もう“ひと昔前”といえるような
遠い過去に思えちゃう情景ですね。
(´〜`*)ウーン
▲09.12.29 北陸本線 金沢
金沢駅兼六園口(東口)に
どーんとそびえ立つ
鼓門(つづみもん)。
二本の太い柱に支えられた
高さ13メートルの門構えは
圧巻の眺めです。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢
およそ一時間半。
多くの乗降客でごったがえす
金沢に到着しました。
(・ω・)トーチャコ
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢
これまで北陸本線の主要駅として
長い歴史を刻んできた金沢ですが
きょうから当駅の在来線は
三セクのIRいしかわ鉄道となりました。
改札の表記を見るとその実感がわきます。
( ̄  ̄*)イシテツ
なお津端で分岐するJR七尾線は
いしかわ鉄道へ乗り入れる形で
当駅を起終点に発着しています。
▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢
今回の開業(三セク移管)により
あらためて大聖寺〜倶利伽羅が
路線区間となったIRいしかわ鉄道線。
おそらくこれ以上は
路線が伸びないと思われることから
“県内全線開業”とうたっています。
(*゚▽゚)/゚・:*【開業 ☆彡】*:・゚\(゚▽゚*)
(ただ富山の城端線や氷見線の例といった
昨今の合理化を進める流れを鑑みると
いずれ七尾線の移管などありえるかも?)
いっぽう駅の構内には
県民に馴染まれて親しみのあった
北陸本線に対する労いのメッセージも
掲げられていました。
とうとう金沢から北陸本線が消えたか・・・。
(´・ω・`)ショボン
夜の金沢で顔をそろえる
北陸本線の寝台特急「北陸」(右)と
夜行急行「能登」(左)。
多くの長距離列車が発着していた
金沢の北陸本線ホームは
高架化されて近代的になっても
旅情が溢れていました。
(´ω`)シミジミ
これは今から15年前の
2009年に撮影したもので
懐かしいという感情はまだ薄いけど
もう“ひと昔前”といえるような
遠い過去に思えちゃう情景ですね。
(´〜`*)ウーン
▲09.12.29 北陸本線 金沢
金沢駅兼六園口(東口)に
どーんとそびえ立つ
鼓門(つづみもん)。
二本の太い柱に支えられた
高さ13メートルの門構えは
圧巻の眺めです。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢
福井1316-(IRいしかわ鉄道1341M)-金沢1450(混雑によりおよそ10分遅れ)
さて、旅の計画ではこのあとさらに金沢からいしかわ鉄道の下り列車に乗り、あらためて倶利伽藍までの既存区間も乗り通したのち、県境を越えた先につながる富山県の三セク鉄道「あいの風とやま鉄道」を進んで富山のほうに向かうつもり ...(((o*・ω・)o・・・でした。
駄菓子菓子(だがしかし)、金沢のホームに停車していた富山ゆきの普通列車(449M)もまた、これまでの敦賀や福井を発車したときと同様、車内がすでにけっこう混んでいて席はあいておらず (´д`;)人大杉…、おそらく金沢市の近郊を抜ければ座れるようになるかと思われるものの、私はなんだか乗車する気力が萎えてしまいます (・ω・`)ゞウーン。
きょうという日は、ただでさえ晴天のお出かけ日和となった週末の土曜日に加え、新幹線や三セク鉄道の開業日であり、それに伴うイベントもいろいろ催される(ブルーインパルスの観覧をふくむ)とあっては、街や駅の人出はいつも以上に多くなり、列車が混雑するのも当然のこと (-`ω´-*)ウム。それを私はじゅうぶん承知のうえで、むしろ開業日ならではの盛り上がりや賑わいを現地で感じたくてやってきたのですから、人混みに文句を言うような立場でないのですが (^^;)ゞポリポリ、でも、敦賀の乗車券購入列からはじまり(結果的に並ばなかったけど)、福井ゆきの列車、ブルーインパルスを観覧した福井駅周辺、金沢ゆきの列車、そして少しだけ下車した金沢駅の構内は国内外の観光客などで人があふれていた・・・と、混雑した状況が続いたことで、ここへきて心身ともに疲れてしまいました ε-(ーωー;)フゥ…。そして次の列車(富山ゆき)もまた当然のごとく混んでいる (-"-;*)ウググ…。
いくら鉄道好きとはいえ、混んだ列車に乗り続けるのは決して楽しいものじゃないし、先述したように金沢から先(下りの倶利伽藍・富山方面)のいしかわ鉄道やとやま鉄道を私はすでに乗車済みであることから、乗りつぶしや乗り直しといった必須の目的はなく、どうしてもこの富山ゆきに乗らなければならないわけではありません σ(゚・゚*)ンー…。
そんなことから私は行程を少し変更して富山ゆき普通列車は乗らずに見送り、テイクアウトしたカフェラテを片手に駅の待合室で休憩してから (´ー`)マターリ(イートインはどのお店も混んでた)、あらためて次に乗るのはこちらの列車。
さて、旅の計画ではこのあとさらに金沢からいしかわ鉄道の下り列車に乗り、あらためて倶利伽藍までの既存区間も乗り通したのち、県境を越えた先につながる富山県の三セク鉄道「あいの風とやま鉄道」を進んで富山のほうに向かうつもり ...(((o*・ω・)o・・・でした。
駄菓子菓子(だがしかし)、金沢のホームに停車していた富山ゆきの普通列車(449M)もまた、これまでの敦賀や福井を発車したときと同様、車内がすでにけっこう混んでいて席はあいておらず (´д`;)人大杉…、おそらく金沢市の近郊を抜ければ座れるようになるかと思われるものの、私はなんだか乗車する気力が萎えてしまいます (・ω・`)ゞウーン。
きょうという日は、ただでさえ晴天のお出かけ日和となった週末の土曜日に加え、新幹線や三セク鉄道の開業日であり、それに伴うイベントもいろいろ催される(ブルーインパルスの観覧をふくむ)とあっては、街や駅の人出はいつも以上に多くなり、列車が混雑するのも当然のこと (-`ω´-*)ウム。それを私はじゅうぶん承知のうえで、むしろ開業日ならではの盛り上がりや賑わいを現地で感じたくてやってきたのですから、人混みに文句を言うような立場でないのですが (^^;)ゞポリポリ、でも、敦賀の乗車券購入列からはじまり(結果的に並ばなかったけど)、福井ゆきの列車、ブルーインパルスを観覧した福井駅周辺、金沢ゆきの列車、そして少しだけ下車した金沢駅の構内は国内外の観光客などで人があふれていた・・・と、混雑した状況が続いたことで、ここへきて心身ともに疲れてしまいました ε-(ーωー;)フゥ…。そして次の列車(富山ゆき)もまた当然のごとく混んでいる (-"-;*)ウググ…。
いくら鉄道好きとはいえ、混んだ列車に乗り続けるのは決して楽しいものじゃないし、先述したように金沢から先(下りの倶利伽藍・富山方面)のいしかわ鉄道やとやま鉄道を私はすでに乗車済みであることから、乗りつぶしや乗り直しといった必須の目的はなく、どうしてもこの富山ゆきに乗らなければならないわけではありません σ(゚・゚*)ンー…。
そんなことから私は行程を少し変更して富山ゆき普通列車は乗らずに見送り、テイクアウトしたカフェラテを片手に駅の待合室で休憩してから (´ー`)マターリ(イートインはどのお店も混んでた)、あらためて次に乗るのはこちらの列車。
シンカンセン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
在来線(いしかわ鉄道線)のホームから新幹線のホームへ移動すると、まもなく上りの富山ゆき「つるぎ26号」が入線 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。自由席の車内は7割がたの席が埋まっていたものの、私は運よく窓側の良席(進行右側のE席)に座ることができました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
ちなみに、立山連峰の最高峰である剣岳(つるぎだけ)を由来とした「つるぎ」の愛称を持つこの列車は、北陸新幹線のなかでも富山と敦賀の間のみで運行されている各駅停車タイプの種別で、おもに北陸の都市間をつなぐ役割を担っており (・o・*)ホホゥ、関東人であまり縁のない私が「つるぎ」に乗るのはこれが初めてです (゚ー゚*)ツルギ(車両は「かがやき」や「はくたか」と変わらないE7・W7系だけど)。
そんな「つるぎ」に乗って、金沢から一気に富山へ向かうのかというと、実はそうではありません (´・ω`・)エッ?。
在来線(いしかわ鉄道線)のホームから新幹線のホームへ移動すると、まもなく上りの富山ゆき「つるぎ26号」が入線 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。自由席の車内は7割がたの席が埋まっていたものの、私は運よく窓側の良席(進行右側のE席)に座ることができました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
ちなみに、立山連峰の最高峰である剣岳(つるぎだけ)を由来とした「つるぎ」の愛称を持つこの列車は、北陸新幹線のなかでも富山と敦賀の間のみで運行されている各駅停車タイプの種別で、おもに北陸の都市間をつなぐ役割を担っており (・o・*)ホホゥ、関東人であまり縁のない私が「つるぎ」に乗るのはこれが初めてです (゚ー゚*)ツルギ(車両は「かがやき」や「はくたか」と変わらないE7・W7系だけど)。
そんな「つるぎ」に乗って、金沢から一気に富山へ向かうのかというと、実はそうではありません (´・ω`・)エッ?。
待望(?)のE席から
北東方向の車窓を眺めると
そこにう〜〜〜っすらと
かろうじて確認できたのは
霞んで見える立山連峰の稜線。
言われなければ雲にみえるかも?
(≡”≡*)ンン?
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-新高岡
(車窓から)
北東方向の車窓を眺めると
そこにう〜〜〜っすらと
かろうじて確認できたのは
霞んで見える立山連峰の稜線。
言われなければ雲にみえるかも?
(≡”≡*)ンン?
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-新高岡
(車窓から)
これまで綴ってきたように今旅における私のいちばんの目的は、北陸新幹線の延伸開業区間(金沢〜敦賀)の乗りつぶしとJRから三セクへ移管された在来線(ハピラインおよびいしかわ鉄道)の乗り直しで、撮影よりも乗車という“乗り鉄”のほうに比重をおいたものですが ( ̄  ̄*)ノリテツ、晴天のもとにそびえる白山の山並みなどを乗車中の車窓から眺めていると、壮観ないい景色だと感じるいっぽう、この好条件で“撮り鉄”(沿線撮影)をできないことが惜しくも思えて、少しフラストレーションすら覚えます σ(・∀・`)ウーン…。きょうは朝からずっと列車に乗りっぱなしだけど、できればどこかで一枚でも北陸らしい情景で撮り鉄がしたいな・・・((o(゙ε゙)o))ウズウズ。
そこで、福井や石川で白山がきれいに見えたのならば、ひょっとすると富山の立山連峰も望めるのではないかとの期待と希望をもって σ(゚・゚*)タテヤマ…、ためしにそれが撮れそうな“撮り鉄スポット”(撮影地)へ行ってみようと思い立ったのでした ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
立山が見える(かもしれない)、その目的地とは・・・
そこで、福井や石川で白山がきれいに見えたのならば、ひょっとすると富山の立山連峰も望めるのではないかとの期待と希望をもって σ(゚・゚*)タテヤマ…、ためしにそれが撮れそうな“撮り鉄スポット”(撮影地)へ行ってみようと思い立ったのでした ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
立山が見える(かもしれない)、その目的地とは・・・
富山県高岡市に所在する新高岡は
北陸新幹線の金沢延伸時に開業した
新幹線と城端線の接続駅。
ここで「つるぎ」を降りて乗り換えます。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲24.3.16 北陸新幹線 新高岡
非電化ローカル線の城端線では
国鉄型ディーゼルカーのキハ47形が
今なお健在。
(´ω`*)シブイ
多くの利用者で混んでいましたが
終点の高岡までは一駅です。
▲24.3.16 城端線 新高岡
高岡でさらに乗り継いだのは
こちらも非電化ローカル線の氷見線。
なおこのキハ40形の装飾は
作者の藤子不二雄氏が
高岡市出身であることにちなんだ
「忍者ハットリくん」ラッピングです。
ニンニン(@・д・@)/-=≡(((卍 シュッ!!
▲24.3.16 氷見線 高岡
北陸新幹線の金沢延伸時に開業した
新幹線と城端線の接続駅。
ここで「つるぎ」を降りて乗り換えます。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲24.3.16 北陸新幹線 新高岡
非電化ローカル線の城端線では
国鉄型ディーゼルカーのキハ47形が
今なお健在。
(´ω`*)シブイ
多くの利用者で混んでいましたが
終点の高岡までは一駅です。
▲24.3.16 城端線 新高岡
高岡でさらに乗り継いだのは
こちらも非電化ローカル線の氷見線。
なおこのキハ40形の装飾は
作者の藤子不二雄氏が
高岡市出身であることにちなんだ
「忍者ハットリくん」ラッピングです。
ニンニン(@・д・@)/-=≡(((卍 シュッ!!
▲24.3.16 氷見線 高岡
進路を北東へ向けた新幹線「つるぎ」は県境を越えて富山県へと入り バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、金沢からわずか15分ほどで次駅の新高岡に停車 (゚ー゚*)シン・タカオカ。つぎに当駅で接続する城端線(じょうはなせん)の高岡ゆき上り列車に乗り換えて一駅だけ進み、高岡市の中心駅である高岡へ (゚ー゚*)タカオカサキ。さらにここで乗り継いだのは氷見線(ひみせん)の氷見ゆき下り普通列車です ( ̄  ̄*)ヒミセソ。
氷見線の車内はガラガラに空いており、これまで混んでいた列車ばかりに乗っていた私は、ようやく気分がホッと落ち着きました ε-(´∀`*)ホッ(地方のローカル線的にみれば、すいているという状況が決していいことではないけど・・・(^^;ゞ)。もうここまで来たらおそらく、私の目的地がおわかりになった方も多いのではないでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。
氷見線の車内はガラガラに空いており、これまで混んでいた列車ばかりに乗っていた私は、ようやく気分がホッと落ち着きました ε-(´∀`*)ホッ(地方のローカル線的にみれば、すいているという状況が決していいことではないけど・・・(^^;ゞ)。もうここまで来たらおそらく、私の目的地がおわかりになった方も多いのではないでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。
車内が空いていて
ボックスシートに座れた氷見線。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
ハピラインやいしかわ鉄道の
普通列車に使われる
521系の転換クロスシートも
座り心地がいいけれど
個人的にはやっぱり
昔ながらの“直角イス”(ボックスシート)が
落ち着くなぁ。
(´ー`)マターリ
窓の外に見えるのは
西日に照らされてさらに赤みを増す
タラコ(朱色のディーゼル)。
▲24.3.16 氷見線 能町
(車窓から)
ボックスシートに座れた氷見線。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
ハピラインやいしかわ鉄道の
普通列車に使われる
521系の転換クロスシートも
座り心地がいいけれど
個人的にはやっぱり
昔ながらの“直角イス”(ボックスシート)が
落ち着くなぁ。
(´ー`)マターリ
窓の外に見えるのは
西日に照らされてさらに赤みを増す
タラコ(朱色のディーゼル)。
▲24.3.16 氷見線 能町
(車窓から)
だいたい二年に一度くらいの間隔でしょうか、個人的にちょくちょく乗りに訪れている氷見線 (*´∀`)ノ゙オヒサ。拙ブログでも何度か取り上げているので、今回は路線の詳細情報などを省かせていただきますが、当線は能登半島付け根の東側(富山側)を高岡から氷見に向けて北上する非電化路線で (・o・*)ホホゥ、昭和の国鉄時代に製造された古いディーゼルカー(国鉄型ディーゼルカー)が今も使われ続けている普通列車に、ローカル線らしい趣きの旅情を感じながら揺られていると (´ω`*)シミジミ、やがて右手の車窓に富山湾の海景色がぱーっと広がります (゚∀゚)オッ!。これはいつ見ても気持ちのいい壮観な眺め (・∀・)イイネ。
その海岸沿いに設けられた雨晴(あまはらし)という名の小駅で私は下車しました (・ω・)トーチャコ。
その海岸沿いに設けられた雨晴(あまはらし)という名の小駅で私は下車しました (・ω・)トーチャコ。
氷見線に乗るなら、
下り列車(氷見ゆき)の進行に向かって
右側のボックス席に座るのがおススメ。
越中国分(えっちゅうこくぶ)と
雨晴のあいだでは
車窓に富山湾の海景色が広がります。
w(゚o゚*)w オオー!
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
(車窓から)
高岡から普通列車で20分ほど
高岡市内に所在し
雨晴海岸の脇に位置する雨晴で下車。
( ̄∇ ̄)アマハラシ
潮風に晒される立地だからか
造りが素朴感じる木造駅舎です。
▲24.3.16 氷見線 雨晴
下り列車(氷見ゆき)の進行に向かって
右側のボックス席に座るのがおススメ。
越中国分(えっちゅうこくぶ)と
雨晴のあいだでは
車窓に富山湾の海景色が広がります。
w(゚o゚*)w オオー!
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
(車窓から)
高岡から普通列車で20分ほど
高岡市内に所在し
雨晴海岸の脇に位置する雨晴で下車。
( ̄∇ ̄)アマハラシ
潮風に晒される立地だからか
造りが素朴感じる木造駅舎です。
▲24.3.16 氷見線 雨晴
金沢1541-(北陸新幹線 つるぎ26号)-新高岡1555~1611-(城端344D)-高岡1614~1623-(氷見543D)-雨晴1643
駅名にもなっている雨晴という地名は (゚ー゚*)アマハラシ、そのむかし源義経が兄の頼朝に追放されて京都から北陸路を経て奥州へと向かう際、ここを通りかかったときににわか雨にあい、浜辺の岩陰で晴れるのを待ったことに由来するのだそうで、今ではその雨宿りをしたとされる岩は“義経岩”(または雨晴岩)の名で祀られ、当地の観光スポットのひとつとなっています ( ̄。 ̄)ヘー。
駅名にもなっている雨晴という地名は (゚ー゚*)アマハラシ、そのむかし源義経が兄の頼朝に追放されて京都から北陸路を経て奥州へと向かう際、ここを通りかかったときににわか雨にあい、浜辺の岩陰で晴れるのを待ったことに由来するのだそうで、今ではその雨宿りをしたとされる岩は“義経岩”(または雨晴岩)の名で祀られ、当地の観光スポットのひとつとなっています ( ̄。 ̄)ヘー。
義経さんがここで弁慶さんたちとともに
雨宿りをしたと云われている
“義経岩”。
撮り鉄として天候条件に恵まれるよう
私は当地を訪れるたびお参りしています。
(-人-)パンパン☆
雨晴海岸沿いの県道脇に設けられた
船の形を模している白亜の建物は
2018年にオープンした「道の駅・雨晴」。
展望デッキからは富山湾が一望できます。
(・∀・)イイネ
雨宿りをしたと云われている
“義経岩”。
撮り鉄として天候条件に恵まれるよう
私は当地を訪れるたびお参りしています。
(-人-)パンパン☆
雨晴海岸沿いの県道脇に設けられた
船の形を模している白亜の建物は
2018年にオープンした「道の駅・雨晴」。
展望デッキからは富山湾が一望できます。
(・∀・)イイネ
そんな義経岩もある雨晴海岸のすぐ目の前へ近年に建造されたのが、観光情報施設で飲食店や土産物店なども併設された「道の駅・雨晴」(ただし店舗エリアはまもなく17時で閉店)。
ここの二階と三階には展望フロアがあり、そこからは富山湾を広く見渡せるだけでなく海沿いを走る氷見線の列車も望めることから、鉄ちゃんにとってはお手軽かつ絶好の“撮り鉄スポット”(撮影地)として知られています (・∀・)イイネ。しかも良好な天候条件に恵まれると、列車の背景には海越しにそびえる立山連峰の山なみも望めるのですが、はたして晴天の今日はどうでしょう (「゚ー゚)ドレドレ。
日没が近づく17時過ぎ、先ほど私が雨晴まで乗ってきた下り列車(543D)が終点の氷見で折り返し、やがて上りの高岡ゆき(542D)として戻ってきました ε-(=゚ω゚)ノ゙タライマ。
ここの二階と三階には展望フロアがあり、そこからは富山湾を広く見渡せるだけでなく海沿いを走る氷見線の列車も望めることから、鉄ちゃんにとってはお手軽かつ絶好の“撮り鉄スポット”(撮影地)として知られています (・∀・)イイネ。しかも良好な天候条件に恵まれると、列車の背景には海越しにそびえる立山連峰の山なみも望めるのですが、はたして晴天の今日はどうでしょう (「゚ー゚)ドレドレ。
日没が近づく17時過ぎ、先ほど私が雨晴まで乗ってきた下り列車(543D)が終点の氷見で折り返し、やがて上りの高岡ゆき(542D)として戻ってきました ε-(=゚ω゚)ノ゙タライマ。
タラコ色(朱色)に塗られた
ローカル線の鈍行列車が
ディーゼルエンジンをうならせて
夕刻の海岸線を進みゆく。
その奥には立山連峰の峻険な稜線が
西日を受けてぼんやりと
浮かび上がります。
(≡∀≡*)ボンヤリ
ちなみに右のほうの高峰が剣岳。
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
(後追い)
ローカル線の鈍行列車が
ディーゼルエンジンをうならせて
夕刻の海岸線を進みゆく。
その奥には立山連峰の峻険な稜線が
西日を受けてぼんやりと
浮かび上がります。
(≡∀≡*)ボンヤリ
ちなみに右のほうの高峰が剣岳。
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
(後追い)
立山バック(?)で氷見線が撮れました~!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
・・・と言いたいけれど、海越しに見える山脈の存在は霞んでいてハッキリとせず (-"-;*)ンン?、どうにか、なんとか、かろうじて、う~~~っすらと稜線が確認できる程度 (≡∀≡*)ボンヤリ。きっとココロの清らかな優しいお方ならば(?)、この写真でかすかに浮かぶ立山連峰が見えているものだと信じたいところですが ミエル…(*'∀'*)ミエルヨ ララァ (写真をクリックして拡大表示すると分かりやすいかも)、はたしてこれが“立山バック”といえるのかどうかビミョーな感じです (^^;ゞポリポリ。
この状況の結果はすでに、新高岡へ向かっている新幹線の車窓から立山を見た時点で分かりそうなものだけど (・∀・`)ウーン…、夕方になって気温が下がればひょっとしたら霞みが取れて、もうすこし山容がハッキリ見えてくるのではないかという期待を持っていたのですが σ(゚・゚*)ドーダロ、やはりそう都合よくはいきませんでした (。A。)アヒャ☆。
ただ、山がまったく見えないわけではなく(ほとんど見えないケド)、ぼんやりとしながらも西日でほんのりと赤くなった稜線にはそれなりの風情が感じられて (´ω`*)シミジミ、その情景で氷見線のタラコ(ディーゼルカー)が撮れたことは、個人的にここまで来たのが無駄ではなかったと思える納得の成果です (-`ω´-*)ウム。夕暮れ時の雨晴海岸をゆく氷見線の列車、意外と悪くない雰囲気じゃないですか (+`゚∀´)=b OK牧場!。
・・・と言いたいけれど、海越しに見える山脈の存在は霞んでいてハッキリとせず (-"-;*)ンン?、どうにか、なんとか、かろうじて、う~~~っすらと稜線が確認できる程度 (≡∀≡*)ボンヤリ。きっとココロの清らかな優しいお方ならば(?)、この写真でかすかに浮かぶ立山連峰が見えているものだと信じたいところですが ミエル…(*'∀'*)ミエルヨ ララァ (写真をクリックして拡大表示すると分かりやすいかも)、はたしてこれが“立山バック”といえるのかどうかビミョーな感じです (^^;ゞポリポリ。
この状況の結果はすでに、新高岡へ向かっている新幹線の車窓から立山を見た時点で分かりそうなものだけど (・∀・`)ウーン…、夕方になって気温が下がればひょっとしたら霞みが取れて、もうすこし山容がハッキリ見えてくるのではないかという期待を持っていたのですが σ(゚・゚*)ドーダロ、やはりそう都合よくはいきませんでした (。A。)アヒャ☆。
ただ、山がまったく見えないわけではなく(ほとんど見えないケド)、ぼんやりとしながらも西日でほんのりと赤くなった稜線にはそれなりの風情が感じられて (´ω`*)シミジミ、その情景で氷見線のタラコ(ディーゼルカー)が撮れたことは、個人的にここまで来たのが無駄ではなかったと思える納得の成果です (-`ω´-*)ウム。夕暮れ時の雨晴海岸をゆく氷見線の列車、意外と悪くない雰囲気じゃないですか (+`゚∀´)=b OK牧場!。
日没となって
稜線に日が当たらなくなった立山は
完全にその存在が消えますた。
ヤマ?(゚д゚≡゚д゚)ドコ?
さすがにこれでは
ココロがきれいな方でも
写真に山は見えないと思われます(笑)
日が暮れるといっきに冷え込む
春先の雨晴海岸。
ブルートーンに包まれるなか
定時運行で現れた列車が灯す
ヘッドライトの明かりには
どこか安心感を覚えます。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
稜線に日が当たらなくなった立山は
完全にその存在が消えますた。
ヤマ?(゚д゚≡゚д゚)ドコ?
さすがにこれでは
ココロがきれいな方でも
写真に山は見えないと思われます(笑)
日が暮れるといっきに冷え込む
春先の雨晴海岸。
ブルートーンに包まれるなか
定時運行で現れた列車が灯す
ヘッドライトの明かりには
どこか安心感を覚えます。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴
列車の運転間隔がおおむね一時間に一本程度の氷見線。
私は夕方の17時前に雨晴へ着いて、とりあえず上りと下りの列車をそれぞれ一本ずつ狙ってみたものの (^_[◎]oパチリ、ほどなく日没時刻を迎えてあたりはだんだんと暗くなり、撮影の二本目となる下り列車(545D)が通過する頃には立山連峰もまったく見えなくなってしまいました ( ̄  ̄*)マックラ。
そんなわずかな撮影時間だったけど、広大な海や霞む山を眺めながら“撮り鉄”を楽しめたことにより、先ほどまでの人混み疲れによるストレスが少し解消できたように思います ε-(´∀`*)ホッ(道の駅も私が着いた直後は多くの人で賑わっていたけど、店舗の閉店時刻を過ぎてからは利用者が少なくなった)。
私は夕方の17時前に雨晴へ着いて、とりあえず上りと下りの列車をそれぞれ一本ずつ狙ってみたものの (^_[◎]oパチリ、ほどなく日没時刻を迎えてあたりはだんだんと暗くなり、撮影の二本目となる下り列車(545D)が通過する頃には立山連峰もまったく見えなくなってしまいました ( ̄  ̄*)マックラ。
そんなわずかな撮影時間だったけど、広大な海や霞む山を眺めながら“撮り鉄”を楽しめたことにより、先ほどまでの人混み疲れによるストレスが少し解消できたように思います ε-(´∀`*)ホッ(道の駅も私が着いた直後は多くの人で賑わっていたけど、店舗の閉店時刻を過ぎてからは利用者が少なくなった)。
高岡ゆきの上り列車に乗り
雨晴をあとにします。
ホームに吹く海風が冷たい。
{{{(´д`)}}}ブルルッ
▲24.3.16 氷見線 雨晴
高岡に戻って乗り換えたのは
富山の三セク鉄道
あいの風とやま鉄道(線)の
泊(とまり)ゆき下り普通列車。
(゚ー゚*)アイテツ
ハピラインやいしかわ鉄道と同様に
当線の列車に使われる車両も
転換時にJR西日本から譲渡された
521系です。
なおこの列車は車内が空いていました。
(´ー`)マターリ
▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 高岡
高岡から20分ほどで富山に到着。
(・ω・)トーチャコ
当駅にはここまで私が乗ってきた
あいの風とやま鉄道のほか
JRの北陸新幹線と高山本線が、
また同じ構内からは
富山地鉄の路面電車である
市内線や環状線、富山港線が、
近隣に所在する電鉄富山駅からは
富山地方鉄道(富山地鉄)の各列車が
それぞれ発着しています。
▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 富山
雨晴をあとにします。
ホームに吹く海風が冷たい。
{{{(´д`)}}}ブルルッ
▲24.3.16 氷見線 雨晴
高岡に戻って乗り換えたのは
富山の三セク鉄道
あいの風とやま鉄道(線)の
泊(とまり)ゆき下り普通列車。
(゚ー゚*)アイテツ
ハピラインやいしかわ鉄道と同様に
当線の列車に使われる車両も
転換時にJR西日本から譲渡された
521系です。
なおこの列車は車内が空いていました。
(´ー`)マターリ
▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 高岡
高岡から20分ほどで富山に到着。
(・ω・)トーチャコ
当駅にはここまで私が乗ってきた
あいの風とやま鉄道のほか
JRの北陸新幹線と高山本線が、
また同じ構内からは
富山地鉄の路面電車である
市内線や環状線、富山港線が、
近隣に所在する電鉄富山駅からは
富山地方鉄道(富山地鉄)の各列車が
それぞれ発着しています。
▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 富山
日没とともに撮影を終えると、雨晴から氷見線に乗って高岡へ戻り ...(((o*・ω・)o、そこで富山の三セク鉄道であるあいの風とやま鉄道(線)の下り普通列車に乗り換えて、私がやってきたのは県都の富山 (゚ー゚*)トヤマ。
もちろん富山もかつては北陸本線の主要駅でしたが、北陸新幹線が2015年に長野から金沢まで延伸した際に富山県内の北陸本線(倶利伽羅~市振(いちぶり))は第三セクター鉄道のあいの風とやま鉄道へ移管されています (・o・*)ホホゥ。
雨晴1810-(氷見544D)-高岡1832~1904-(あいの風とやま鉄道567M)-富山1922
週末の今夜は富山も多くの人出で賑わっているものの、新幹線の延伸開業による盛り上がりに湧いていた福井や金沢に比べると、駅も街も(居酒屋も?)落ち着いている印象を受けます (´ω`*)マターリ。
そんな富山を今日の宿泊地にえらび、私はあらかじめ駅近くにある手頃なビジネスホテルを予約してきました (*'∀'*)オトマリ。
もちろん富山もかつては北陸本線の主要駅でしたが、北陸新幹線が2015年に長野から金沢まで延伸した際に富山県内の北陸本線(倶利伽羅~市振(いちぶり))は第三セクター鉄道のあいの風とやま鉄道へ移管されています (・o・*)ホホゥ。
雨晴1810-(氷見544D)-高岡1832~1904-(あいの風とやま鉄道567M)-富山1922
週末の今夜は富山も多くの人出で賑わっているものの、新幹線の延伸開業による盛り上がりに湧いていた福井や金沢に比べると、駅も街も(居酒屋も?)落ち着いている印象を受けます (´ω`*)マターリ。
そんな富山を今日の宿泊地にえらび、私はあらかじめ駅近くにある手頃なビジネスホテルを予約してきました (*'∀'*)オトマリ。
富山といえば言わずと知れた
海の幸の宝庫。
ブリや白エビ、ホタルイカなど
ご当地の名物をいただきます。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ。
いろいろ慌ただしかった今日一日
お疲れさまでした。
カンパイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆
海の幸の宝庫。
ブリや白エビ、ホタルイカなど
ご当地の名物をいただきます。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ。
いろいろ慌ただしかった今日一日
お疲れさまでした。
カンパイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆
3月17日(日)
さて、一泊二日の行程とした今旅。
本来ならここで旅行記を“二日目に続く”とするところですが、実は翌朝にホテルの部屋で目覚めるとどうも熱っぽくて頭が重く、クシャミと鼻水が止まらない ( >д<)、;'.・ ィクシッ! ( ̄ii ̄)タラーリ。
考えてみると昨日(初日)は今の時期の北陸地方としては日中の気温が高めだったにもかかわらず、私は東京から厚手のコートを羽織った防寒仕様で来てしまい、そんな恰好で混んだ列車に乗ったり、福井でブルーインパルスを撮ったりしたため、けっこう汗をかいていたハズ (´Д`υ)アツー。いっぽう雨晴の海岸近くで撮影していた夕方には気温が一気に下がって風に冷たさを感じるようになり {{{(>_<+)}}}サブッ、また一日を通して行程的にもちょっとハードだったため アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ、それらが原因でどうやら少し体調を崩してしまったようです。こりゃ風邪をひいたかな・・・il||li(つ∀-;)ウーンil||li。
ちなみに今日(二日目)の北陸地方は天気予報によると、前日の快晴から一転して曇天の雨模様 、ヽ`┐( ̄  ̄;)アメ。もし晴れたら“撮り鉄”(撮影)へ行きたいところがあったのですが σ(゚・゚*)ンー…、天候も体調もイマイチならば無理をせず撮影はやめにして、もう富山から東京へ向けてのんびりと帰ることにしました カエロ…((((o* ̄-)o。
ただ、すごく体調が悪いというほどではなかったため、帰路は北陸新幹線を利用するのでなく、せっかくなのでいくつかの普通列車を乗り継いでゆく“乗り鉄”くらいは楽しんで、今旅をシメようと思います (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。
はじめに富山から乗るのは
あいの風とやま鉄道線の泊(とまり)ゆき
下り普通列車。
(゚ー゚*)アイテツ
朝早い時間なので車内は空いています。
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 富山
車窓に眺める立山連峰。
今朝は予報通りの曇り空ですが
その雄大な山並みは見られました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 東富山-水橋
(車窓から)
あいの風とやま鉄道線の泊(とまり)ゆき
下り普通列車。
(゚ー゚*)アイテツ
朝早い時間なので車内は空いています。
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 富山
車窓に眺める立山連峰。
今朝は予報通りの曇り空ですが
その雄大な山並みは見られました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 東富山-水橋
(車窓から)
お伝えしてきたように、金沢から福井県の敦賀まで延伸した北陸新幹線の開業初日に乗車することをいちばんの目的として、駆け足ながら北陸本線から転換された第三セクター鉄道などもめぐってみた今回の鉄道旅 ...(((o*・ω・)o。
ぶっちゃけ、敦賀という中途ハンパ感が否めない新幹線の開業で、とくに特急列車の廃止(運行区間短縮)により関西方面と北陸地方のアクセスがこれまでよりも不便になったことは確かなように私も感じますが (゚ペ)ウーン…、いっぽうで地元の利用者を対象とした地域輸送の鉄道路線としてみれば普通列車の本数が増えたり、所要時間が短縮された区間があったりと、決してマイナス面だけではないのかなという印象を受けました (*゚ェ゚)フムフム。もちろん三セク化によって運賃が値上がったことは軽視できない問題だと思いますが (-ω-;*)ノミネアガリ…。
このたび新たに開業した“ハピラインふくい”と路線区間が延伸となった“IRいしかわ鉄道”、さらに既存の“あいの風とやま鉄道”や“えちごトキめき鉄道”など、歴史ある北陸本線の鉄路を継承した三セクの各鉄道には地域に根付いて利用者に親しまれる路線となることを、鉄道好きのひとりとしては願っています p(`・ω・´)q ガンガレ!。
ぶっちゃけ、敦賀という中途ハンパ感が否めない新幹線の開業で、とくに特急列車の廃止(運行区間短縮)により関西方面と北陸地方のアクセスがこれまでよりも不便になったことは確かなように私も感じますが (゚ペ)ウーン…、いっぽうで地元の利用者を対象とした地域輸送の鉄道路線としてみれば普通列車の本数が増えたり、所要時間が短縮された区間があったりと、決してマイナス面だけではないのかなという印象を受けました (*゚ェ゚)フムフム。もちろん三セク化によって運賃が値上がったことは軽視できない問題だと思いますが (-ω-;*)ノミネアガリ…。
このたび新たに開業した“ハピラインふくい”と路線区間が延伸となった“IRいしかわ鉄道”、さらに既存の“あいの風とやま鉄道”や“えちごトキめき鉄道”など、歴史ある北陸本線の鉄路を継承した三セクの各鉄道には地域に根付いて利用者に親しまれる路線となることを、鉄道好きのひとりとしては願っています p(`・ω・´)q ガンガレ!。
新潟との県境近くに位置する
富山県朝日町の泊で
えちごトキめき鉄道・日本海ひすいラインの
直江津(なおえつ)ゆき普通列車に
乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
なお当線は電化路線ですが
ディーゼルカーのET122形で
列車を運行しています。
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 泊
県境の新潟側に位置する
新潟県糸魚川市の市振が
あいの風とやま鉄道と
えちごトキめき鉄道の境界駅。
駅名標のデザインもここで変わります。
(゚ー゚*)イチブリ
▲24.3.17 日本海ひすいライン 市振
(車窓から)
日本海ひすいラインの終点である
新潟県上越市の直江津はかつて
米原を起点に353.8キロの長さを誇る
北陸本線の終着駅でもありました。
(´ω`)シミジミ
現在は米原〜敦賀がJR北陸本線
敦賀〜大聖寺がハピラインふくい
大聖寺〜倶利伽藍がIRいしかわ鉄道
倶利伽藍〜市振があいの風とやま鉄道
そして市振〜直江津が
えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインと
並行在来線区間(敦賀〜直江津)は県ごとに
路線が細かく分けられています。
( ̄  ̄*)コマギレ
▲24.3.17 えちごトキめき鉄道 直江津
富山県朝日町の泊で
えちごトキめき鉄道・日本海ひすいラインの
直江津(なおえつ)ゆき普通列車に
乗り継ぎ。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
なお当線は電化路線ですが
ディーゼルカーのET122形で
列車を運行しています。
▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 泊
県境の新潟側に位置する
新潟県糸魚川市の市振が
あいの風とやま鉄道と
えちごトキめき鉄道の境界駅。
駅名標のデザインもここで変わります。
(゚ー゚*)イチブリ
▲24.3.17 日本海ひすいライン 市振
(車窓から)
日本海ひすいラインの終点である
新潟県上越市の直江津はかつて
米原を起点に353.8キロの長さを誇る
北陸本線の終着駅でもありました。
(´ω`)シミジミ
現在は米原〜敦賀がJR北陸本線
敦賀〜大聖寺がハピラインふくい
大聖寺〜倶利伽藍がIRいしかわ鉄道
倶利伽藍〜市振があいの風とやま鉄道
そして市振〜直江津が
えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインと
並行在来線区間(敦賀〜直江津)は県ごとに
路線が細かく分けられています。
( ̄  ̄*)コマギレ
▲24.3.17 えちごトキめき鉄道 直江津
そして個人的な旅のほうを振り返れば、ハピラインの一日乗車券が買えなかったり、想定していたこととはいえ列車の車内や駅の構内が混雑していたことに多少の戸惑いがあったりしたものの (´д`;)アウ…、北陸新幹線の延伸区間の乗りつぶしに続いて、北陸本線から三セク鉄道へ新たに転換された区間をあらためて乗りなおし、その途中ではブルーインパルスの祝賀飛行も見られて、旅の目的はおおむね達成 (+`゚∀´)=b OK牧場!。
また、きまぐれに(?)行程を変更して向かった氷見線での“撮り鉄”も、期待の立山連峰は薄っすらと霞んで見える程度だったけど、海辺を走る国鉄型ディーゼルカーの趣きにローカル線らしい旅情が感じられて気分が癒されました (´ー`)シミジミ。雨晴へはいつかまた再訪し、今度こそ海越しにクッキリとした立山連峰を拝みたいものです。
翌二日目にちょっと体調を崩すという情けない終わりかたとなっちゃいましたが (ノO`)アチャー、初日の一日だけでも北陸の鉄道風景を満喫できた充実の旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
(風邪は一週間ほどこじらせちゃったけど、いまは完治しています)
また、きまぐれに(?)行程を変更して向かった氷見線での“撮り鉄”も、期待の立山連峰は薄っすらと霞んで見える程度だったけど、海辺を走る国鉄型ディーゼルカーの趣きにローカル線らしい旅情が感じられて気分が癒されました (´ー`)シミジミ。雨晴へはいつかまた再訪し、今度こそ海越しにクッキリとした立山連峰を拝みたいものです。
翌二日目にちょっと体調を崩すという情けない終わりかたとなっちゃいましたが (ノO`)アチャー、初日の一日だけでも北陸の鉄道風景を満喫できた充実の旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
(風邪は一週間ほどこじらせちゃったけど、いまは完治しています)
直江津で乗り継いだのは
北越急行ほくほく線の
六日町(むいかまち)ゆき普通列車。
(o ̄∇ ̄o)ホクホク
なお当線も新潟の第三セクター鉄道ですが
並行在来線として転換されたものではなく
国鉄時代に計画された未完成の路線を
三セク鉄道として開通させたものです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.17 信越本線 直江津
上空が雲に覆われた曇天ではあるものの
ほくほく線の車窓からは
上越の名峰・妙高山の雄大な山並みが
きれいに望めました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.17 北越急行ほくほく線
大池いこいの森-くびき(車窓から)
暖冬といわれた今シーズン
北陸地方の平地ではほとんど
積雪が見られなかった今旅でしたが
新潟ではご覧のような雪景色です。
(゚- ゚)ユキ
ちなみに雪原の向こうに見える山は
日本酒の銘柄で知られる八海山。
▲24.3.17 北越急行ほくほく線
魚沼丘陵-六日町(車窓から)
三セク路線の乗り継ぎが続きましたが
(正確にいえばほくほく線の列車で通った
直江津〜犀潟はJR信越本線だけど)
南魚沼市の六日町から乗るのは
JR上越線の水上(みなかみ)ゆき普通列車。
▲24.3.17 上越線 六日町
新潟と群馬の県境にある
清水トンネルを抜けた上越線の列車は
当線名物(?)の湯檜曽ループを通過。
(゚ー゚*)ループ
ループ線とは高低差のある区間を
ぐるりと弧を描くようにして
勾配を緩和する線形で
眼下にはこれから当列車が走る線路を
見下ろすことができます。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.17 上越線 土合-湯檜曽(車窓から)
北越急行ほくほく線の
六日町(むいかまち)ゆき普通列車。
(o ̄∇ ̄o)ホクホク
なお当線も新潟の第三セクター鉄道ですが
並行在来線として転換されたものではなく
国鉄時代に計画された未完成の路線を
三セク鉄道として開通させたものです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.17 信越本線 直江津
上空が雲に覆われた曇天ではあるものの
ほくほく線の車窓からは
上越の名峰・妙高山の雄大な山並みが
きれいに望めました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.17 北越急行ほくほく線
大池いこいの森-くびき(車窓から)
暖冬といわれた今シーズン
北陸地方の平地ではほとんど
積雪が見られなかった今旅でしたが
新潟ではご覧のような雪景色です。
(゚- ゚)ユキ
ちなみに雪原の向こうに見える山は
日本酒の銘柄で知られる八海山。
▲24.3.17 北越急行ほくほく線
魚沼丘陵-六日町(車窓から)
三セク路線の乗り継ぎが続きましたが
(正確にいえばほくほく線の列車で通った
直江津〜犀潟はJR信越本線だけど)
南魚沼市の六日町から乗るのは
JR上越線の水上(みなかみ)ゆき普通列車。
▲24.3.17 上越線 六日町
新潟と群馬の県境にある
清水トンネルを抜けた上越線の列車は
当線名物(?)の湯檜曽ループを通過。
(゚ー゚*)ループ
ループ線とは高低差のある区間を
ぐるりと弧を描くようにして
勾配を緩和する線形で
眼下にはこれから当列車が走る線路を
見下ろすことができます。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.17 上越線 土合-湯檜曽(車窓から)
ところで、今旅の結果により私は北陸新幹線の完乗は無事に果たせましたが、実はこの翌週となる3月23日の土曜日には大阪で、大阪メトロの御堂筋線と直通運転を行っている北大阪急行の南北線が千里中央から箕面萱野(みのおかやの)まで新たに延伸開業(南北延伸線)し、私はまだそちらを乗りに訪れることができていません ( ̄  ̄*)オーサカ。開業日に行けなかったのならばもういつでもよくて焦る必要はないけれど、できれば今年じゅうには乗りつぶしたいところです σ(゚・゚*)ンー…。
目標とする日本の旅客鉄道路線の全線完全乗車、その飽くなき道はまだまだ続く・・・...(((o*・ω・)o。
目標とする日本の旅客鉄道路線の全線完全乗車、その飽くなき道はまだまだ続く・・・...(((o*・ω・)o。
群馬県みなかみ町の水上で乗り継いだ
新前橋ゆき普通列車は
国鉄型車両の生き残りである211系。
( ̄  ̄*)ニゲゲ
なおこの列車は終点の新前橋で
両毛線からの高崎ゆきに接続します。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲24.3.17 上越線 水上
都内までのラストランナーとして
高崎から乗るのは
高崎線と湘南新宿ラインを直通する
特別快速の小田原ゆき。
関東でお馴染みのE231系です。
▲24.3.17 信越本線 高崎
新前橋ゆき普通列車は
国鉄型車両の生き残りである211系。
( ̄  ̄*)ニゲゲ
なおこの列車は終点の新前橋で
両毛線からの高崎ゆきに接続します。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲24.3.17 上越線 水上
都内までのラストランナーとして
高崎から乗るのは
高崎線と湘南新宿ラインを直通する
特別快速の小田原ゆき。
関東でお馴染みのE231系です。
▲24.3.17 信越本線 高崎
富山0514-(あいの風とやま鉄道521M)-泊0601~0623-(トキ鉄日本海ひすいライン1623D)-直江津0739~0812-(北越急行829M)-六日町0919~0932-(上越1728M)-水上1035~1045-(376M)-新前橋1137~1139-(626M)-高崎1149~1214-(高崎4831Y 特別快速)-新宿1358
ハピラインふくい・・・開業初日 乗車記 [鉄道乗車記]
前回からの続きです。
3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)
その初日に私はさっそく、記念すべき“一番列車”の「かがやき501号」・・・は指定券を取ることができずに見送り、“二番目”となる「かがやき503号」の敦賀ゆきに東京から乗車します ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。
既存区間の東京〜金沢を経てから、このたび新たに延伸された金沢より先の区間へ足を踏み入れると、鉄道路線全線完乗(完全乗車)を目指す“乗り鉄”としては興奮で気分が一気に高揚 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。とくに新幹線の窓越しに確認した「福井」の駅名標には、ついに北陸新幹線もここまで来たかと感慨深いものがあります (´ー`)シミジミ。初めて見るその車窓風景を食い入るように眺めて存分に堪能し、およそ3時間かけて終点の敦賀までやってきました (・ω・)トーチャコ。
3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)
その初日に私はさっそく、記念すべき“一番列車”の「かがやき501号」・・・は指定券を取ることができずに見送り、“二番目”となる「かがやき503号」の敦賀ゆきに東京から乗車します ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。
既存区間の東京〜金沢を経てから、このたび新たに延伸された金沢より先の区間へ足を踏み入れると、鉄道路線全線完乗(完全乗車)を目指す“乗り鉄”としては興奮で気分が一気に高揚 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。とくに新幹線の窓越しに確認した「福井」の駅名標には、ついに北陸新幹線もここまで来たかと感慨深いものがあります (´ー`)シミジミ。初めて見るその車窓風景を食い入るように眺めて存分に堪能し、およそ3時間かけて終点の敦賀までやってきました (・ω・)トーチャコ。
福井県のほぼ中央に位置する敦賀市は、日本海の敦賀湾に面した港町で、古くから昆布やかまぼこなどの水産加工業で発展。また日本と大陸をむすぶ貿易港として栄えた歴史を持ち、明治から昭和初期にかけては鉄路と航路をつなぐ国際列車(欧亜国際連絡列車)の中継地としてもにぎわいました (・o・*)ホホゥ。市内にはその面影を色濃く残した名所や旧跡が多く残されており、とくに鉄ちゃんとしては旧・敦賀港駅の駅舎を活用した「敦賀鉄道資料館」などに興味が惹かれるところ (・∀・)イイネ
・・・なのですが (´・ω`・)エッ?、今旅の私は本日に延伸開業した北陸新幹線と、それに伴って大きな変化が生じた在来線の乗車に重点を置いた行程を組んでおり、残念ながら敦賀の街を散策する余裕がありません (´〜`)ウーン。仮に少しばかりの時間が作れても駆け足で巡ることになってしまいそうなので、それならば当地へはまた改めてじっくり訪れることにしようと割り切りました (-`ω´-*)ウム。もし拙ブログに敦賀の観光地めぐりを期待されていた方がおられましたらスミマセン 人( ̄ω ̄;)スマヌ。
・・・なのですが (´・ω`・)エッ?、今旅の私は本日に延伸開業した北陸新幹線と、それに伴って大きな変化が生じた在来線の乗車に重点を置いた行程を組んでおり、残念ながら敦賀の街を散策する余裕がありません (´〜`)ウーン。仮に少しばかりの時間が作れても駆け足で巡ることになってしまいそうなので、それならば当地へはまた改めてじっくり訪れることにしようと割り切りました (-`ω´-*)ウム。もし拙ブログに敦賀の観光地めぐりを期待されていた方がおられましたらスミマセン 人( ̄ω ̄;)スマヌ。
そんなワケで今旅での敦賀は新幹線から在来線への単なる“乗り換え駅”といった扱いなのですが ノリカエ…((((o* ̄-)o、私は乗車券を東京(都区内)からここ敦賀までのものしか持っていないため、次に乗る路線のぶんを当駅で買わなければなりません σ(゚・゚*)ンー…。それならば線内の乗り降りが自由にできて価格的にもおトクな“フリーきっぷ”(一日乗車券)を購入しようと思い、販売している窓口のほうに向かってみたところ・・・(=゚ω゚=*)ンン!?、そこには私と同様に乗車券などを求める多くの人たちで、なんとも長〜い行列ができているではありませんか ( ̄△ ̄;)エッ…。
どうやら一日乗車券のほか、きょうの日付が入った記念の入場券、さらには定期券なども、たった一カ所しかない窓口で対応しているらしく、これは私が買えるまでにどれくらい時間がかかるのか見当がつかないような状況(最低でも一時間はかかりそう・・・)(´д`;)アウ…。できれば今から20分後の列車に乗りたいところなので、もう一日乗車券は諦めてふつうの乗車券(きっぷ)を買おうと自動券売機のほうに移動してみますが コッチ…((((o* ̄-)o、そこもまた窓口ほどではないものの行列ができており、あと20分できっぷが買えるかどうかビミョーなところ (-"-;*)ウググ。時間的に焦りを感じるなかで最後尾に並ぶと (´・д・`;)ハラハラ…、列を整理していた係員の方が「自動改札ではICOCAやSuicaなど(のIC乗車券)が使えますので、チャージ済みの方はそちらもご利用くださーい! >θ( ̄0 ̄*)」と案内の声を張り上げています。あ、なーんだ“Suica”が使えるのね (; ̄▽ ̄)ア…。きょうという記念の日の日付が入ったきっぷを手にできないのはちょっと惜しいけど、時間を考えたらここは致し方あるまい (・ε・`)シャーナイ。私は券売機の行列から外れると、手持ちのICカードを“ピピッ”っと改札機にタッチして入場 ...(((*・ω・)つ[西瓜] ピッ。
なんとか無事に間に合ってホームへ上がると、まもなく列車がやってきました ε-(´∀`;)ホッ。
なんとか無事に間に合ってホームへ上がると、まもなく列車がやってきました ε-(´∀`;)ホッ。
たくさんの人が待つなか
敦賀の在来線ホームに入ってきたのは
車体にピンク色の帯を巻いた電車。
(*’∀’*)ピンク♡
ちなみに当駅のホームは
近江塩津、米原方面の北陸本線や
小浜線が発着する
JR西日本が引き続き管理するため
駅名標のスタイルはそのままです。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
敦賀の在来線ホームに入ってきたのは
車体にピンク色の帯を巻いた電車。
(*’∀’*)ピンク♡
ちなみに当駅のホームは
近江塩津、米原方面の北陸本線や
小浜線が発着する
JR西日本が引き続き管理するため
駅名標のスタイルはそのままです。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
ハピライン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
1882年(明治15年)の開業から140年以上の長い歴史をもち、北陸本線の主要駅としてこれまでに数々の”名列車”と呼ばれる長距離列車や優等列車が行き交ってきた敦賀の構内へ、新風を吹き込むかのように颯爽と現れたのは鮮やかなピンク色の帯が印象的な二両編成の短い電車 (=゚ω゚=*)ンン!?。
これが次に私が乗る「ハピラインふくい(線)」です (o ̄∇ ̄o)ハピライン。
1882年(明治15年)の開業から140年以上の長い歴史をもち、北陸本線の主要駅としてこれまでに数々の”名列車”と呼ばれる長距離列車や優等列車が行き交ってきた敦賀の構内へ、新風を吹き込むかのように颯爽と現れたのは鮮やかなピンク色の帯が印象的な二両編成の短い電車 (=゚ω゚=*)ンン!?。
これが次に私が乗る「ハピラインふくい(線)」です (o ̄∇ ̄o)ハピライン。
ハピラインふくいの車両はもともと
北陸本線の普通列車に使われていて
三セク移管の際にJR西日本から譲渡された
交直両用型の521系。
ワンマン仕様の二両編成です。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
北陸本線の普通列車に使われていて
三セク移管の際にJR西日本から譲渡された
交直両用型の521系。
ワンマン仕様の二両編成です。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
ハピラインふくいは北陸新幹線の金沢〜敦賀の延伸開業にともない、JR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、ここ敦賀を起点に福井を経て、石川県との県境を越えたところに位置する大聖寺(だいしょうじ)までの間(84.3キロ)の運営を受け持つこととなった、福井県の第三セクター鉄道(三セク鉄道)(・o・*)ホホゥ。
一般公募により決定した社名の由来は、「福井県の“福”を表す“ハピネス”(しあわせ)に、鉄道を表す“ライン(線)”を掛け合わせたものであり、“ひと”と“まち”をつなぐことで幸せな福井の未来をつくる鉄道会社」という企業姿勢を表しているのだそうで ( ̄、 ̄*)ナルヘソ、一般鉄道で定番の「〇〇鉄道」や「〇〇電鉄」といったものではない社名には新鮮味と柔らかさを覚えます(なお路線名は「ハピラインふくい線」)(・∀・)イイネ。
そんなハピラインふくい(以降はハピラインと略す)も本日が三セク鉄道に移管されて新たな門出となる“開業日” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 ハピライン】*:・゚\(゚▽゚*)。当線の敦賀〜大聖寺を私は北陸本線で何度も通ったことがある区間だけど(ちなみに北陸本線として当該区間を最後に通ったのは二年前となる2022年の福井出張で、そのときは往路が米原経由、復路を金沢経由としました)、JRから三セク鉄道に運営会社が変わったのならばそれはもう北陸本線と別の路線だと判断し、やはり同様のケースとなった過去の例に倣って、この機会にあらためて乗りつぶし・・・というか乗り直すこととしました (-`ω´-*)ウム。
一般公募により決定した社名の由来は、「福井県の“福”を表す“ハピネス”(しあわせ)に、鉄道を表す“ライン(線)”を掛け合わせたものであり、“ひと”と“まち”をつなぐことで幸せな福井の未来をつくる鉄道会社」という企業姿勢を表しているのだそうで ( ̄、 ̄*)ナルヘソ、一般鉄道で定番の「〇〇鉄道」や「〇〇電鉄」といったものではない社名には新鮮味と柔らかさを覚えます(なお路線名は「ハピラインふくい線」)(・∀・)イイネ。
そんなハピラインふくい(以降はハピラインと略す)も本日が三セク鉄道に移管されて新たな門出となる“開業日” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 ハピライン】*:・゚\(゚▽゚*)。当線の敦賀〜大聖寺を私は北陸本線で何度も通ったことがある区間だけど(ちなみに北陸本線として当該区間を最後に通ったのは二年前となる2022年の福井出張で、そのときは往路が米原経由、復路を金沢経由としました)、JRから三セク鉄道に運営会社が変わったのならばそれはもう北陸本線と別の路線だと判断し、やはり同様のケースとなった過去の例に倣って、この機会にあらためて乗りつぶし・・・というか乗り直すこととしました (-`ω´-*)ウム。
私のような開業に駆けつけた鉄ちゃんのほか、地元の人たちが敦賀へ新幹線を見学に訪れたり、それに合わせていろいろなイベントが催されたりしたのでしょうか、日中はおよそ一時間に一本の間隔で運行される二両編成の普通列車は、まるで首都圏の通勤ラッシュを覚えるような大混雑 w( ̄▽ ̄;)wワオッ!。私は人の動きが少ないと思われる車内の中ほどへと進んで、なるべく車窓の景色が安定して見えるような立ち位置をキープします (*`・ω・)キープ。
なお、路線区間としては敦賀と大聖寺のあいだを結ぶハピラインですが、大半の列車が途中の福井で運行を分けられており、私が乗ったこの下り列車(1243M)も福井ゆき ( ̄  ̄*)フクイ。敦賀から福井までは一時間弱のおよそ50分ほどで、混雑した車内に立っていても通勤ラッシュに普段から慣れていればさほど辛い乗車時間ではありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。
なお、路線区間としては敦賀と大聖寺のあいだを結ぶハピラインですが、大半の列車が途中の福井で運行を分けられており、私が乗ったこの下り列車(1243M)も福井ゆき ( ̄  ̄*)フクイ。敦賀から福井までは一時間弱のおよそ50分ほどで、混雑した車内に立っていても通勤ラッシュに普段から慣れていればさほど辛い乗車時間ではありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。
北陸新幹線の延伸開業により
きょうから敦賀止まり(敦賀発着)となった
北陸本線の特急「サンダーバード」が
福井方面へと向かうハピラインの列車を
敦賀の留置線より見送ります。
イッテラ~(=゚ω゚)ノシ
▲24.3.16 北陸本線 敦賀(車窓から)
きょうから敦賀止まり(敦賀発着)となった
北陸本線の特急「サンダーバード」が
福井方面へと向かうハピラインの列車を
敦賀の留置線より見送ります。
イッテラ~(=゚ω゚)ノシ
▲24.3.16 北陸本線 敦賀(車窓から)
そんな混雑状況により定刻の5分遅れで発車したハピラインは、敦賀を出るとまもなく全長13,870mの「北陸トンネル」へと入ります ( ̄  ̄*)ネルトン。
当トンネルは“狭軌の陸上トンネル”としては日本一の長さを誇るもので(第三軌条の海底トンネルを含めれば、一位の長さはもちろん青函トンネル(53,850m))、それがこのたびの運営移管によりJRでなく三セク鉄道の保有となったことも、ハピラインの初乗車における特筆すべき点でしょうか (*・`o´・*)ホ─(なおこれによりJRの在来線で最長となったのは上越線の新清水トンネル(13,490 m))。
同じ福井県内でも北陸トンネルが貫く木ノ芽峠を隔てた北部(嶺北)と南部(嶺南)の地域では文化圏や経済圏が異なるといい、トンネルの暗闇を12分もかけて抜けた先からは北陸っぽい情緒や風情がいっそう高まるように感じます (´ω`*)ホクリク。
当トンネルは“狭軌の陸上トンネル”としては日本一の長さを誇るもので(第三軌条の海底トンネルを含めれば、一位の長さはもちろん青函トンネル(53,850m))、それがこのたびの運営移管によりJRでなく三セク鉄道の保有となったことも、ハピラインの初乗車における特筆すべき点でしょうか (*・`o´・*)ホ─(なおこれによりJRの在来線で最長となったのは上越線の新清水トンネル(13,490 m))。
同じ福井県内でも北陸トンネルが貫く木ノ芽峠を隔てた北部(嶺北)と南部(嶺南)の地域では文化圏や経済圏が異なるといい、トンネルの暗闇を12分もかけて抜けた先からは北陸っぽい情緒や風情がいっそう高まるように感じます (´ω`*)ホクリク。
長い北陸トンネルを出て
すぐのところにあるのが
南今庄(みなみいまじょう)。
山里集落の素朴な無人駅ですが
個人的に北陸本線の撮影を目的として
何度か当駅で下車したことがあります。
▲24.3.16 ハピラインふくい 南今庄
(車窓から)
この写真は今から20年近く前に
南今庄を訪れたときに撮ったもので
北陸トンネルを抜けてきた
北陸本線の特急「雷鳥」。
貫通型の485系(クハ481-200)というのが
シブいチョイスでしょ(笑)
(´ω`*)シブイ
▲05.8.1 北陸本線 敦賀-南今庄
南越前町に所在する今庄はかつて
北国街道の宿場町として栄えた地。
(゚ー゚*)イマジョー
また北陸トンネルが完成する以前の
北陸本線(旧線)では
線内随一の難所といわれた
山中峠越えの急勾配に挑むため
今庄で上り列車の最後尾に
補助の機関車を連結していました。
当駅の構内には今もその当時に使われていた
蒸気機関車用の給水塔が残されています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄
(車窓から)
冬には豪雪となることもある
このあたりの地域。
大きな三角屋根を設えた立派な家々に
雪国らしい風情を覚えます。
▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄-湯尾
(車窓から)
里山がまわりを囲む田園風景に
のどかさが感じられる
湯尾(ゆのお)と南条のあいだは
北陸本線の列車をスッキリと撮れる
有名な撮影ポイントとして撮り鉄に知られ
私も過去に何度か撮影へ訪れています。
( ̄  ̄*)ユノオ
▲24.3.16 ハピラインふくい 湯尾-南条
(車窓から)
これは2008年に当地(湯尾)で撮影した
北陸本線の「トワイライトエクスプレス」。
大阪と札幌の間のおよそ1500キロを
約22時間もかけて走っていた
豪華な設備が自慢の寝台特急列車です。
(゚ー゚*)トワ
当列車は北陸新幹線や北海道新幹線の
開業にともなって廃止されてしまい
そしてこの区間の路線も
北陸本線からハピラインとなったことで
もうこんな魅力的な長距離の旅客列車が
ここを走ることはないでしょう・・・。
σ(・∀・`)ウーン…
(長距離の貨物列車は通過するけど)
▲08.4.29 北陸本線 南条-湯尾
(車窓から)
越前市に所在する王子保(おうしお)。
個人的に何となく耳障りがいいその駅名は
開業時(1927年)の村名だった
旧・王子保村に由来するもの。
(´ω`)オーシオ
なお当駅と次駅の武生とのあいだには
来年の2025年春ごろに
紫式部の名にちなんだ「しきぶ」という
駅名の新駅が開業する予定となっています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 ハピラインふくい 王子保
(車窓から)
すぐのところにあるのが
南今庄(みなみいまじょう)。
山里集落の素朴な無人駅ですが
個人的に北陸本線の撮影を目的として
何度か当駅で下車したことがあります。
▲24.3.16 ハピラインふくい 南今庄
(車窓から)
この写真は今から20年近く前に
南今庄を訪れたときに撮ったもので
北陸トンネルを抜けてきた
北陸本線の特急「雷鳥」。
貫通型の485系(クハ481-200)というのが
シブいチョイスでしょ(笑)
(´ω`*)シブイ
▲05.8.1 北陸本線 敦賀-南今庄
南越前町に所在する今庄はかつて
北国街道の宿場町として栄えた地。
(゚ー゚*)イマジョー
また北陸トンネルが完成する以前の
北陸本線(旧線)では
線内随一の難所といわれた
山中峠越えの急勾配に挑むため
今庄で上り列車の最後尾に
補助の機関車を連結していました。
当駅の構内には今もその当時に使われていた
蒸気機関車用の給水塔が残されています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄
(車窓から)
冬には豪雪となることもある
このあたりの地域。
大きな三角屋根を設えた立派な家々に
雪国らしい風情を覚えます。
▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄-湯尾
(車窓から)
里山がまわりを囲む田園風景に
のどかさが感じられる
湯尾(ゆのお)と南条のあいだは
北陸本線の列車をスッキリと撮れる
有名な撮影ポイントとして撮り鉄に知られ
私も過去に何度か撮影へ訪れています。
( ̄  ̄*)ユノオ
▲24.3.16 ハピラインふくい 湯尾-南条
(車窓から)
これは2008年に当地(湯尾)で撮影した
北陸本線の「トワイライトエクスプレス」。
大阪と札幌の間のおよそ1500キロを
約22時間もかけて走っていた
豪華な設備が自慢の寝台特急列車です。
(゚ー゚*)トワ
当列車は北陸新幹線や北海道新幹線の
開業にともなって廃止されてしまい
そしてこの区間の路線も
北陸本線からハピラインとなったことで
もうこんな魅力的な長距離の旅客列車が
ここを走ることはないでしょう・・・。
σ(・∀・`)ウーン…
(長距離の貨物列車は通過するけど)
▲08.4.29 北陸本線 南条-湯尾
(車窓から)
越前市に所在する王子保(おうしお)。
個人的に何となく耳障りがいいその駅名は
開業時(1927年)の村名だった
旧・王子保村に由来するもの。
(´ω`)オーシオ
なお当駅と次駅の武生とのあいだには
来年の2025年春ごろに
紫式部の名にちなんだ「しきぶ」という
駅名の新駅が開業する予定となっています。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 ハピラインふくい 王子保
(車窓から)
穏やかな春っぽい陽気のもと、北陸路を軽やかに(編成的に?w)快走するハピラインの普通列車 (o ̄∇ ̄o)ハピライン。車窓から眺める景色は北陸本線のときと変わらないものの、電車の車体色と同様にハピラインのコーポレートカラーとなったピンク色の駅名標が各駅で新鮮に感じます (*’∀’*)ピンク♡。
特急列車が頻繁に往来していたことから“特急街道”と呼ばれた北陸本線のときに比べて、すれ違う列車が一時間に一本ほどの普通列車(と時おり貨物列車)だけとなったのは、やはり鉄ちゃんとして一抹の寂しさがあるけれど σ(・∀・`)ウーン…、特急が廃止(運行区間の短縮)となったことによって普通列車は途中駅での退避(通過待ち)がなくなり、敦賀〜福井では普通列車の所要時間がこれまでより最大で19分も短縮されたのだとか (・o・*)ホホゥ。北陸本線からハピラインに転換されて運賃が値上がりしたのは利用者にとってきびしいところですが、普通列車の時間短縮と運行本数が以前のJRより三割増となったことは地域輸送の利便性としてプラスのメリットといえるのではないでしょうか (*゚ェ゚)フムフム。
そんなハピラインの普通列車はやがて、越前市の中心駅で北陸本線の特急停車駅だった武生(たけふ)に停車 (゚ー゚*)タケフ。敦賀と福井の中間あたりに位置する当駅で車内の乗降客に少しばかり入れ替わりがあり、私はボックスシート(端部の転換しない席)の窓側に座ることができました。進行方向を背にする席だけど、座って車窓風景が見られるのはありがたい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
特急列車が頻繁に往来していたことから“特急街道”と呼ばれた北陸本線のときに比べて、すれ違う列車が一時間に一本ほどの普通列車(と時おり貨物列車)だけとなったのは、やはり鉄ちゃんとして一抹の寂しさがあるけれど σ(・∀・`)ウーン…、特急が廃止(運行区間の短縮)となったことによって普通列車は途中駅での退避(通過待ち)がなくなり、敦賀〜福井では普通列車の所要時間がこれまでより最大で19分も短縮されたのだとか (・o・*)ホホゥ。北陸本線からハピラインに転換されて運賃が値上がりしたのは利用者にとってきびしいところですが、普通列車の時間短縮と運行本数が以前のJRより三割増となったことは地域輸送の利便性としてプラスのメリットといえるのではないでしょうか (*゚ェ゚)フムフム。
そんなハピラインの普通列車はやがて、越前市の中心駅で北陸本線の特急停車駅だった武生(たけふ)に停車 (゚ー゚*)タケフ。敦賀と福井の中間あたりに位置する当駅で車内の乗降客に少しばかり入れ替わりがあり、私はボックスシート(端部の転換しない席)の窓側に座ることができました。進行方向を背にする席だけど、座って車窓風景が見られるのはありがたい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
武生駅が所在する越前市は
和紙や刃物、箪笥造りなどの
伝統工芸で知られ
また越前蕎麦が名物のまち。
(・∀・)イイネ
当駅には三セク方式の地方私鉄
福井鉄道・福武線が接続しており
そちらの駅名は「たけふ新」となっています。
( ̄  ̄*)シン
▲24.3.16 ハピラインふくい 武生
(車窓から)
そして前回の記事でも触れましたが
武生駅の3キロ東方には
今回の北陸新幹線延伸により
「越前たけふ」駅が新規開業。
武生と越前たけふの両駅間は
シャトルバスが結んでいる模様です。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 ハピラインふくい 武生
(車窓から)
鯖江はメガネの生産業が盛んな
“めがねのまち”で
ホームにある待合室も
それをアピールしています。
(σ○-○)メガネ
ちなみに私が愛用しているメガネも
鯖江にあるメーカーなので
メガネの里帰りかな?(笑)
▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江
(車窓から)
鯖江ですれ違った
武生ゆき上り列車の521系は
まだ譲渡前のJRカラー(青帯)のまま。
( ̄  ̄*)アオ
ホームの発車案内標を見ると
日中の運行は
敦賀〜武生が60分間隔でしたが
福井の都市圏にあたる武生〜福井では
30分間隔のパターンダイヤが
組まれているようです。
(*゚ェ゚)フムフム
▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江
(車窓から)
山にも看板が掲げられた
“めがねのまちSABAE”(笑)
(σ○-○)メガネ
▲24.3.16 ハピラインふくい 北鯖江-大土呂
(車窓から)
福井市内に所在する
大土呂(おおどろ)には
味のある木造駅舎が残ります。
(´ω`*)シブイ
三セクとなったことで今後
このような古い駅舎も
リニューアルされるのでしょうか。
▲24.3.16 ハピラインふくい 大土呂
(車窓から)
在来線(ハピライン)と
少し離れた位置に敷かれていた
北陸新幹線の高架橋が
大土呂を過ぎたあたりで
近づいてきます。
(=゚ω゚)チンカンテン
▲24.3.16 ハピラインふくい
大土呂-越前花堂(車窓から)
新幹線の高架下となった
越前花堂(えちぜんはなんどう)は
“九頭竜線”の愛称を持つ
越美北線との接続駅。
なお当線がJRの“飛び地”として
残されていることで
「青春18きっぷ」を使用する場合
敦賀と越前花堂のあいだは
ハピラインの運賃を不要とする
“通過特例”が認められています
(ただし途中下車は不可)。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂
(車窓から)
和紙や刃物、箪笥造りなどの
伝統工芸で知られ
また越前蕎麦が名物のまち。
(・∀・)イイネ
当駅には三セク方式の地方私鉄
福井鉄道・福武線が接続しており
そちらの駅名は「たけふ新」となっています。
( ̄  ̄*)シン
▲24.3.16 ハピラインふくい 武生
(車窓から)
そして前回の記事でも触れましたが
武生駅の3キロ東方には
今回の北陸新幹線延伸により
「越前たけふ」駅が新規開業。
武生と越前たけふの両駅間は
シャトルバスが結んでいる模様です。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 ハピラインふくい 武生
(車窓から)
鯖江はメガネの生産業が盛んな
“めがねのまち”で
ホームにある待合室も
それをアピールしています。
(σ○-○)メガネ
ちなみに私が愛用しているメガネも
鯖江にあるメーカーなので
メガネの里帰りかな?(笑)
▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江
(車窓から)
鯖江ですれ違った
武生ゆき上り列車の521系は
まだ譲渡前のJRカラー(青帯)のまま。
( ̄  ̄*)アオ
ホームの発車案内標を見ると
日中の運行は
敦賀〜武生が60分間隔でしたが
福井の都市圏にあたる武生〜福井では
30分間隔のパターンダイヤが
組まれているようです。
(*゚ェ゚)フムフム
▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江
(車窓から)
山にも看板が掲げられた
“めがねのまちSABAE”(笑)
(σ○-○)メガネ
▲24.3.16 ハピラインふくい 北鯖江-大土呂
(車窓から)
福井市内に所在する
大土呂(おおどろ)には
味のある木造駅舎が残ります。
(´ω`*)シブイ
三セクとなったことで今後
このような古い駅舎も
リニューアルされるのでしょうか。
▲24.3.16 ハピラインふくい 大土呂
(車窓から)
在来線(ハピライン)と
少し離れた位置に敷かれていた
北陸新幹線の高架橋が
大土呂を過ぎたあたりで
近づいてきます。
(=゚ω゚)チンカンテン
▲24.3.16 ハピラインふくい
大土呂-越前花堂(車窓から)
新幹線の高架下となった
越前花堂(えちぜんはなんどう)は
“九頭竜線”の愛称を持つ
越美北線との接続駅。
なお当線がJRの“飛び地”として
残されていることで
「青春18きっぷ」を使用する場合
敦賀と越前花堂のあいだは
ハピラインの運賃を不要とする
“通過特例”が認められています
(ただし途中下車は不可)。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂
(車窓から)
武生から鯖江(さばえ)を経て福井までの区間は福井市近郊の都市圏で、福井へ近づくにつれて車窓はのどかな風景から市街地となり ...(((o*・ω・)o、進行方向の左手に足羽山(あすわやま)を臨み(車内が混んでいたので右側に座った私から左側の景色はあまりよく確認できなかったけど)、そのふもとを流れる足羽川を鉄橋で渡ると、やがて列車は県都の福井に着きます (・ω・)トーチャコ。
併設された新幹線の高架に
視界を遮られつつも
福井の市内を流れる足羽川の
川面をチラ見。
|∀・)チラッ
▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂-福井
(車窓から)
車内が終始混雑した状態だった
ハピラインの普通列車は
構内が広々とした立派な高架駅の
福井に到着。
(゚ー゚*)フクイ
敦賀から乗った当列車は
とりあえずここが終点です。
(´w`*)ドツカレサン
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
福井のホームであらためて
ハピラインの521系を記録撮影。
(^_[◎]oパチリ
JR西日本からハピラインへ
16編成が譲渡された当系ですが
開業日(転換日)を迎えた今日の時点で
新たな“ハピラインカラー”になったのは
この一本(HF15編成)だけらしい
(残りはまだJRの青帯)。
たまたまそれに当たったのは
ラッキーな鉄運でした。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
視界を遮られつつも
福井の市内を流れる足羽川の
川面をチラ見。
|∀・)チラッ
▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂-福井
(車窓から)
車内が終始混雑した状態だった
ハピラインの普通列車は
構内が広々とした立派な高架駅の
福井に到着。
(゚ー゚*)フクイ
敦賀から乗った当列車は
とりあえずここが終点です。
(´w`*)ドツカレサン
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
福井のホームであらためて
ハピラインの521系を記録撮影。
(^_[◎]oパチリ
JR西日本からハピラインへ
16編成が譲渡された当系ですが
開業日(転換日)を迎えた今日の時点で
新たな“ハピラインカラー”になったのは
この一本(HF15編成)だけらしい
(残りはまだJRの青帯)。
たまたまそれに当たったのは
ラッキーな鉄運でした。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
敦賀1112-(ハピラインふくい1243M)-福井1213(混雑によりおよそ10分遅れ)
敦賀と大聖寺をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、先述したように大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗り換える必要があります σ(゚・゚*)ンー…。
せっかく福井で列車を降りるのならば、いまの時間はちょうど正午過ぎなので、当初の計画ではここでお昼ゴハンでも食べて行こうかと考えていました (・∀・)イイネ。福井名物の“ソースカツ丼(ヨーロッパ軒)”なんかいいなぁ・・・とか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。
敦賀と大聖寺をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、先述したように大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗り換える必要があります σ(゚・゚*)ンー…。
せっかく福井で列車を降りるのならば、いまの時間はちょうど正午過ぎなので、当初の計画ではここでお昼ゴハンでも食べて行こうかと考えていました (・∀・)イイネ。福井名物の“ソースカツ丼(ヨーロッパ軒)”なんかいいなぁ・・・とか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。
県内(おもに勝山市)で
恐竜の化石が多く見つかっていることから
“恐竜王国”をアピールしている福井。
福井駅の構内や駅前など
あちこちで恐竜がお出迎えしてくれます。
(=゚ω゚)キョーリュー!
駅前広場でひときわ目立つのは
全長10メートル、高さ6メートルの
“フクイティタン”(のモニュメント)。
(゚∀゚*)オオッ!
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
恐竜の化石が多く見つかっていることから
“恐竜王国”をアピールしている福井。
福井駅の構内や駅前など
あちこちで恐竜がお出迎えしてくれます。
(=゚ω゚)キョーリュー!
駅前広場でひときわ目立つのは
全長10メートル、高さ6メートルの
“フクイティタン”(のモニュメント)。
(゚∀゚*)オオッ!
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
駄菓子菓子(だがしかし)(´・ω`・)エッ?、旅行前の私が“飛行機好きの友人”から聞かされたのが、「北陸新幹線の延伸開業日にそれを記念して、航空自衛隊の“ブルーインパルス”が福井で祝賀飛行をするよ」という情報 ヽ(゚ω゚)ブルー。
私は鉄道好きの“鉄ちゃん”であって、とくに飛行機好きというワケではない(というか飛行機には疎い)けど、過去に何度かブルーインパルスを見る機会があり、とくに北海道新幹線のときの函館や西九州新幹線のときの長崎ではその開業日に現地でその祝賀飛行を観覧しています (o´∀`o)カコイイ!。それならば今回も北陸新幹線の開業祝いとして、旅程の都合をウマく合わせられれば見てみたいもの (・∀・)イイネ。
ちなみに思い返せば一年半前(2022年9月)、西九州新幹線の長崎では有名な歌謡曲のごとく(?)あいにくの雨天にたたられて (* ̄0 ̄)θ<アアアア〜♪ 、ブルーインパルスの演技飛行が予定より大幅にカットされてしまったという残念な経験をしています 、ヽ`个o(・_・。)アメダッタ`ヽ、。もし今日の福井も雨ならばブルーインパルスより“カツ丼”のほうを優先したかもしれませんが、清々しい快晴に恵まれた本日はまさに絶好の“ブルーインパルス日和” (゚∀゚*)オオッ!。この青空で長崎のリベンジを果たしたいじゃありませんか リベンジ!(*`・ω・´)-3。
しかもブルーインパルスが福井駅の上空に飛来するのは13時ごろとのことで、12時過ぎに福井へ到着した列車はちょうどいいタイミング ъ(゚Д゚)ナイス(その列車に乗りたいから敦賀できっぷを買うのに焦ったんだけどw)。そうすると時間的に昼食は削られちゃうけど、私はブルーインパルスを迎えるべく恐竜がいる福井の駅前広場にてカメラを空へ向けることとしました シャキッ!( >_o)r┬=≡[]。
すでに集まっていた大勢の人たちと待つことしばし、飛行機シロートの私にはどの方向から飛んでくるのかさっぱりわからず、空を見上げてキョロキョロしていると <(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ、やがて西のほうから聞こえてきたのは“キーン!”という(アラレちゃんじゃないよw)飛行機のジェット音 (*゚ロ゚)ハッ!。
私は鉄道好きの“鉄ちゃん”であって、とくに飛行機好きというワケではない(というか飛行機には疎い)けど、過去に何度かブルーインパルスを見る機会があり、とくに北海道新幹線のときの函館や西九州新幹線のときの長崎ではその開業日に現地でその祝賀飛行を観覧しています (o´∀`o)カコイイ!。それならば今回も北陸新幹線の開業祝いとして、旅程の都合をウマく合わせられれば見てみたいもの (・∀・)イイネ。
ちなみに思い返せば一年半前(2022年9月)、西九州新幹線の長崎では有名な歌謡曲のごとく(?)あいにくの雨天にたたられて (* ̄0 ̄)θ<アアアア〜♪ 、ブルーインパルスの演技飛行が予定より大幅にカットされてしまったという残念な経験をしています 、ヽ`个o(・_・。)アメダッタ`ヽ、。もし今日の福井も雨ならばブルーインパルスより“カツ丼”のほうを優先したかもしれませんが、清々しい快晴に恵まれた本日はまさに絶好の“ブルーインパルス日和” (゚∀゚*)オオッ!。この青空で長崎のリベンジを果たしたいじゃありませんか リベンジ!(*`・ω・´)-3。
しかもブルーインパルスが福井駅の上空に飛来するのは13時ごろとのことで、12時過ぎに福井へ到着した列車はちょうどいいタイミング ъ(゚Д゚)ナイス(その列車に乗りたいから敦賀できっぷを買うのに焦ったんだけどw)。そうすると時間的に昼食は削られちゃうけど、私はブルーインパルスを迎えるべく恐竜がいる福井の駅前広場にてカメラを空へ向けることとしました シャキッ!( >_o)r┬=≡[]。
すでに集まっていた大勢の人たちと待つことしばし、飛行機シロートの私にはどの方向から飛んでくるのかさっぱりわからず、空を見上げてキョロキョロしていると <(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ、やがて西のほうから聞こえてきたのは“キーン!”という(アラレちゃんじゃないよw)飛行機のジェット音 (*゚ロ゚)ハッ!。
みんなが見上げる視線の先に
ブルーインパルスが
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
壁面に恐竜がデザインされた
福井駅の上空で
5本の白いスモークがなびきます。
バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ
(先日の「ONE-shot」とは別カット)
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
恐竜の背後で
空に描かれたハートマーク。
(*’∀’*)ハート♡
なんとなく個人的にこれは
ハピラインの開業を
お祝いしているような印象です。
これは放射状に広がる
“サンライズ”という演目だそうですが
絶妙な飛行位置で
恐竜のフクイティタンが
キングギドラになっちまった!?(爆)
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
ブルーインパルスが
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
壁面に恐竜がデザインされた
福井駅の上空で
5本の白いスモークがなびきます。
バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ
(先日の「ONE-shot」とは別カット)
▲24.3.16 ハピラインふくい 福井
恐竜の背後で
空に描かれたハートマーク。
(*’∀’*)ハート♡
なんとなく個人的にこれは
ハピラインの開業を
お祝いしているような印象です。
これは放射状に広がる
“サンライズ”という演目だそうですが
絶妙な飛行位置で
恐竜のフクイティタンが
キングギドラになっちまった!?(爆)
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
新幹線が新たに開業した福井駅の上空をパン(通過)したのち、円を描くようにして咲かせた“サクラ”や、ハートに矢を射抜く“バーティカルキューピッド”、放射状に広がる“サンライズ”など、ブルーインパルスが青空を華麗に舞って描いた作品の数々に魅了され w(*゚o゚*)wオオー!、顔を上げて眺める多くの観覧者が歓声と拍手で称えます (*≧▽≦ノノ゙☆パチパチ。長崎のリベンジが果たせた私も感無量の思い (´ω`)シミジミ。鉄ちゃんとして新幹線と絡めて撮ることができなかったのは惜しいけど(ちなみにブルーインパルスと北陸新幹線といえば、東京五輪の時に私は東京駅でそのコラボを撮っています)、それでも福井駅の駅舎や恐竜のモニュメントといっしょに撮れたのは、当地でのいい記録となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。
さて、ブルーインパルスを無事に撮り終えて、駅の近くでサクッと軽くランチを (›´ω`‹ )ハラヘタ…・・・と思ったものの、当然のことながらブルーインパルスというイベントが終了した直後は人が流れてどの店も大混雑 ( ̄△ ̄;)エッ…。駅構内の立ち食いそば屋さんやコンビニのレジにも行列ができるほどです (´д`;)人大杉…。
これでは仕方なく福井で昼食をとるのは諦めて (・ε・`)チェ、空腹に耐えながら私はふたたびハピラインの下り列車に乗車し、福井より先に残された区間の乗りつぶしへ進むこととしました ...(((o*・ω・)o。
ハピラインふくいの乗り鉄旅、次回に続きます (›´ω`‹ )ハラヘタ…。
これでは仕方なく福井で昼食をとるのは諦めて (・ε・`)チェ、空腹に耐えながら私はふたたびハピラインの下り列車に乗車し、福井より先に残された区間の乗りつぶしへ進むこととしました ...(((o*・ω・)o。
ハピラインふくいの乗り鉄旅、次回に続きます (›´ω`‹ )ハラヘタ…。
2024-03-30 10:10
北陸新幹線・・・敦賀延伸 乗車記 [鉄道乗車記]
日ごとに暖かさを増して春めいてきた3月の中旬 (゚- ゚)ハル、JRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では16日に“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)
鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標としている私にとって、新たに開通する路線や区間があればいち早く乗ってみたいもの (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。ちなみに私は新幹線だと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれもその運行開始の当日(初日)に乗車を果たしており ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!、今回延伸する北陸新幹線では第一期(1997年)の東京(高崎)〜長野、第二期(2015年)の長野〜金沢も然り。後者はその様子を拙ブログでお伝えしています。
そして私にとって福井というと、おそらく家系的な縁はまったくないと思われるのですが(ご先祖をうんと遡ったらあるのかもしれないけど)σ(゚・゚*)ンー…、仕事での出張で県内の福井市をはじめ鯖江市や越前市(旧・武生市)などへちょくちょく行くことがあり、ほかの地域に比べたら多少は馴染みのあるところです (-`ω´-*)ウム(その出張ついでに撮る福井鉄道が意外と拙ブログで登場回数が多いw)。
そんなワケで完乗を目指す“乗り鉄”としても、また福井に少しだけ馴染みがある者としても、個人的に今回の“敦賀延伸”を楽しみにしていました (*゚v゚*)ワクワク♪。そこでできれば開業の初日に乗ってご当地を訪れ、その盛り上がりを直に感じたい (・∀・)イイネ。なお、いちおうダメ元でひと月前の指定券発売日に、記念すべき“東京発の一番列車”となる「かがやき501号」の指定席を狙ってみたものの、それはやっぱりダメでしたが(当該列車は数秒で満席になったとか・・・)(´Д⊂ダメポ、東京発の“二番目”となる「かがやき503号」は窓側の席を入手できました ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。それでじゅうぶんです (+`゚∀´)=b OK牧場!。
前置きが長くなりましたが(いつものことw)、それでは延伸開業初日の北陸新幹線に乗って、北陸は福井の敦賀を目指しましょう (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
3月16日(土)
ダイヤ改正が実施されて北陸新幹線が敦賀まで延伸開業する当日の朝 ('-'*)オハヨ♪。
どんな路線でも新たな鉄路が生まれる“開業日”というのは、鉄道趣味人の“鉄ちゃん”にとって気分が高揚するもので (*゚∀゚)=3ハァハァ!、その興奮を抑えつつ私が自宅の最寄駅から向かったのは東京駅。
鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標としている私にとって、新たに開通する路線や区間があればいち早く乗ってみたいもの (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。ちなみに私は新幹線だと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれもその運行開始の当日(初日)に乗車を果たしており ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!、今回延伸する北陸新幹線では第一期(1997年)の東京(高崎)〜長野、第二期(2015年)の長野〜金沢も然り。後者はその様子を拙ブログでお伝えしています。
そして私にとって福井というと、おそらく家系的な縁はまったくないと思われるのですが(ご先祖をうんと遡ったらあるのかもしれないけど)σ(゚・゚*)ンー…、仕事での出張で県内の福井市をはじめ鯖江市や越前市(旧・武生市)などへちょくちょく行くことがあり、ほかの地域に比べたら多少は馴染みのあるところです (-`ω´-*)ウム(その出張ついでに撮る福井鉄道が意外と拙ブログで登場回数が多いw)。
そんなワケで完乗を目指す“乗り鉄”としても、また福井に少しだけ馴染みがある者としても、個人的に今回の“敦賀延伸”を楽しみにしていました (*゚v゚*)ワクワク♪。そこでできれば開業の初日に乗ってご当地を訪れ、その盛り上がりを直に感じたい (・∀・)イイネ。なお、いちおうダメ元でひと月前の指定券発売日に、記念すべき“東京発の一番列車”となる「かがやき501号」の指定席を狙ってみたものの、それはやっぱりダメでしたが(当該列車は数秒で満席になったとか・・・)(´Д⊂ダメポ、東京発の“二番目”となる「かがやき503号」は窓側の席を入手できました ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。それでじゅうぶんです (+`゚∀´)=b OK牧場!。
前置きが長くなりましたが(いつものことw)、それでは延伸開業初日の北陸新幹線に乗って、北陸は福井の敦賀を目指しましょう (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
3月16日(土)
ダイヤ改正が実施されて北陸新幹線が敦賀まで延伸開業する当日の朝 ('-'*)オハヨ♪。
どんな路線でも新たな鉄路が生まれる“開業日”というのは、鉄道趣味人の“鉄ちゃん”にとって気分が高揚するもので (*゚∀゚)=3ハァハァ!、その興奮を抑えつつ私が自宅の最寄駅から向かったのは東京駅。
新幹線のいろいろな列車名が並ぶ
東京駅の発車案内表。
発車順でいちばん上に表示された
北陸新幹線「かがやき501号」の
“敦賀”という行き先が新鮮です。
(=゚ω゚)ツルガ!
▲24.3.16 東北新幹線 東京
東京駅の発車案内表。
発車順でいちばん上に表示された
北陸新幹線「かがやき501号」の
“敦賀”という行き先が新鮮です。
(=゚ω゚)ツルガ!
▲24.3.16 東北新幹線 東京
東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸の各新幹線の各列車がずらっと表示される発車案内標を眺めると、きょうからそこへ新たに加わったのが“敦賀”の行き先 (゚ー゚*)ツルガ。知らないとちょっと読みにくい“つるが”という地名ですが、北陸新幹線の終点となったことで少しは認知度が上がるでしょうか。
東京駅の22番線ホームでは
東京発で敦賀ゆきの一番列車となる
「かがやき501号」の
出発式が行われました。
(*゚▽゚)/゚・:*【祝・オメデ㌧】*:・゚\(゚▽゚*)
なお一般の人は式典を見ることができず
(当該ホームは立ち入りを制限)
これは終了後(501号の発車後)に撮った
記念のボードです。
(^_[◎]oパチリ
当駅で出発の合図を務められたという
浜辺美波ちゃんをひと目みたかったなぁ。
(。A。)アヒャ☆
▲24.3.16 東北新幹線 東京
東京発で敦賀ゆきの一番列車となる
「かがやき501号」の
出発式が行われました。
(*゚▽゚)/゚・:*【祝・オメデ㌧】*:・゚\(゚▽゚*)
なお一般の人は式典を見ることができず
(当該ホームは立ち入りを制限)
これは終了後(501号の発車後)に撮った
記念のボードです。
(^_[◎]oパチリ
当駅で出発の合図を務められたという
浜辺美波ちゃんをひと目みたかったなぁ。
(。A。)アヒャ☆
▲24.3.16 東北新幹線 東京
冒頭で触れたとおり、今回の北陸新幹線で私が入手できた指定券は“一番列車”の「かがやき501号」でなく、そのあとの「かがやき503号」。記念の出発式が行われて華々しく発車する「501号」と、その乗客のみなさんを羨ましく見送ったのち σ(・∀・`)ウラヤマ、次に淡々とホームへ入線してきた「503号」のほうに乗り込みます コッチ…((((o* ̄-)o。
私が乗る「かがやき503号」は
JR東日本のE7系でなく
JR西日本のW7系でした。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
どっちも見た目は一緒だけどね
(乗車後にアナウンスチャイムで気付いた)。
▲24.3.16 東北新幹線 東京
JR東日本のE7系でなく
JR西日本のW7系でした。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
どっちも見た目は一緒だけどね
(乗車後にアナウンスチャイムで気付いた)。
▲24.3.16 東北新幹線 東京
一番列車でない“二番列車”の「かがやき503号」だけど、それでも車両の側面に掲出された“敦賀ゆき”という行き先に多くの人がカメラやスマホを向けています パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝパシャ☆。たしかに行先表示などの記録撮影なら「501号」よりこちらのほうが落ち着いて撮れるかもしれませんね (´ω`)ナルヘソ。
また“二番列車”(クドいw)であっても、全席指定の当列車はグランクラス、グリーン車、普通車ともにすべて満席であることがアナウンスで伝えられます ( ̄  ̄*)マンセキ。ちなみにふだんの私は新幹線に一人で乗るとき、普通車で二列シートの窓側である“E席”を好んで座ることが多いのですが、今回は三列シートの窓側である“A席”しか取れませんでした σ(゚・゚*)ンー…(下りの北陸新幹線でいうと進行方向の右側)。まあ、開業初日に午前の列車で窓側の席が確保できただけでもヨシとしましょうか (´σД`)マ、イッカ。
そんな「かがやき503号」は定刻の7時20分に東京を発車しました ...(((o*・ω・)o。
また“二番列車”(クドいw)であっても、全席指定の当列車はグランクラス、グリーン車、普通車ともにすべて満席であることがアナウンスで伝えられます ( ̄  ̄*)マンセキ。ちなみにふだんの私は新幹線に一人で乗るとき、普通車で二列シートの窓側である“E席”を好んで座ることが多いのですが、今回は三列シートの窓側である“A席”しか取れませんでした σ(゚・゚*)ンー…(下りの北陸新幹線でいうと進行方向の右側)。まあ、開業初日に午前の列車で窓側の席が確保できただけでもヨシとしましょうか (´σД`)マ、イッカ。
そんな「かがやき503号」は定刻の7時20分に東京を発車しました ...(((o*・ω・)o。
【金沢〜敦賀間が開業!】
車内の案内表示器に流れるテロップにも
ついカメラを向けたくなっちゃいます笑
(^_[◎]oパチリ
久しぶりに座ったA席から
東のほうにう~っすらと望めるのは
上州の赤城山。
(≡∀≡*)ウッスラ
晴れているけど空気は霞んでいて
春っぽさを感じます。
▲24.3.16 上越新幹線 本庄早稲田-高崎
(車窓から)
車内の案内表示器に流れるテロップにも
ついカメラを向けたくなっちゃいます笑
(^_[◎]oパチリ
久しぶりに座ったA席から
東のほうにう~っすらと望めるのは
上州の赤城山。
(≡∀≡*)ウッスラ
晴れているけど空気は霞んでいて
春っぽさを感じます。
▲24.3.16 上越新幹線 本庄早稲田-高崎
(車窓から)
きょうの開業に関するようなアナウンスはとくに無かったけど(二番列車だしねw)、通常の自動放送による音声案内でも“かがやき503号 敦賀ゆき”と聞けば、初日の列車に乗れた喜びと嬉しさが込み上げるというもの +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
ところで今回の北陸新幹線の延伸区間は金沢と敦賀のあいだの125キロで、そこが完乗を目指す私の“乗りつぶし”対象となります (*゚ェ゚)フムフム。それならば当該区間(金沢〜敦賀)のみに重点を置いた旅程として、開業の前日となる昨日のうちに前乗りで金沢あたりへ行ってしまい、新幹線の開業にともなって運行区間が短縮される在来線(北陸本線)の特急「サンダーバード」や「しらさぎ」などを記録し、明けて今日の開業日に金沢から敦賀まで北陸新幹線を乗りつぶすか、もしくはきょう出発でも往きの経路を東海道まわり(東海道新幹線と北陸本線を米原で乗り継ぎ)として、敦賀のほうから金沢まで北陸新幹線の延伸区間を乗りつぶすか、などといろいろな案を考えたのですが σ(゚・゚*)ンー…、やはり関東人の私としては金沢〜敦賀の延伸区間だけではなく、東京から長野、富山、金沢を経て福井、敦賀へと、およそ三時間かけて到達する北陸新幹線の全体的な流れを味わいたいと思い、これまでの既存区間(東京〜金沢)を含めた全線をあらためて乗り通すこととしました (-`ω´-*)ウム。
ところで今回の北陸新幹線の延伸区間は金沢と敦賀のあいだの125キロで、そこが完乗を目指す私の“乗りつぶし”対象となります (*゚ェ゚)フムフム。それならば当該区間(金沢〜敦賀)のみに重点を置いた旅程として、開業の前日となる昨日のうちに前乗りで金沢あたりへ行ってしまい、新幹線の開業にともなって運行区間が短縮される在来線(北陸本線)の特急「サンダーバード」や「しらさぎ」などを記録し、明けて今日の開業日に金沢から敦賀まで北陸新幹線を乗りつぶすか、もしくはきょう出発でも往きの経路を東海道まわり(東海道新幹線と北陸本線を米原で乗り継ぎ)として、敦賀のほうから金沢まで北陸新幹線の延伸区間を乗りつぶすか、などといろいろな案を考えたのですが σ(゚・゚*)ンー…、やはり関東人の私としては金沢〜敦賀の延伸区間だけではなく、東京から長野、富山、金沢を経て福井、敦賀へと、およそ三時間かけて到達する北陸新幹線の全体的な流れを味わいたいと思い、これまでの既存区間(東京〜金沢)を含めた全線をあらためて乗り通すこととしました (-`ω´-*)ウム。
上信国境の碓氷峠をトンネルで抜けると
軽井沢付近で車窓に映し出されたのは
青空に雪化粧が映える見事な浅間山。
(゚∀゚*)オオッ!
これはA席側の見どころのひとつですね。
▲24.3.16 北陸新幹線 軽井沢-佐久平
(車窓から)
雪を抱いた浅間山を眺めたら
アイスクリームが食べたくなった!?
(゚∀゚)アヒャ☆
新幹線名物ともいわれる
“シンカンセンスゴイカタイアイス”を
車内販売で買っちゃいました。
この“京都宇治抹茶味”は
本日より発売の新商品だそうです。
アイス(゚д゚)ウマー!
(お行儀が悪いけど
“特徴的な硬さ”をあらわすために
スプーンを立ててみますたw)
軽井沢付近で車窓に映し出されたのは
青空に雪化粧が映える見事な浅間山。
(゚∀゚*)オオッ!
これはA席側の見どころのひとつですね。
▲24.3.16 北陸新幹線 軽井沢-佐久平
(車窓から)
雪を抱いた浅間山を眺めたら
アイスクリームが食べたくなった!?
(゚∀゚)アヒャ☆
新幹線名物ともいわれる
“シンカンセンスゴイカタイアイス”を
車内販売で買っちゃいました。
この“京都宇治抹茶味”は
本日より発売の新商品だそうです。
アイス(゚д゚)ウマー!
(お行儀が悪いけど
“特徴的な硬さ”をあらわすために
スプーンを立ててみますたw)
北陸新幹線の速達列車である「かがやき」(なお停車駅が多い列車は「はくたか」)、そのなかでもこの「503号」は東京から敦賀までの所要時間が3時間8分ともっとも速く、途中の停車駅は大宮、長野、富山、金沢、福井のみなので、満席だけど人の出入りは少なくて車内の空気感は落ち着いた印象 (´ー`)マターリ。車窓に流れる景色を眺めながら(アイスを食べつつw)、新規開通の延伸区間へ入るまでの既存区間をのんびりと過ごします。
東京から1時間20分で長野に停車。
JR東日本とJR西日本の二社にまたがる
北陸新幹線は
新潟県の上越妙高が会社の境界駅ですが
そこを「かがやき」は通過するため
乗務員の交代は長野で行われます。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 北陸新幹線 長野
(車窓から)
糸魚川付近では車窓の右手に
日本海が望めます。
(*’∀’*)ウミ♪
今日は日本海側の各地も晴天で
海が青い。
▲24.3.16 北陸新幹線 糸魚川-黒部宇奈月温泉
(車窓から)
いっぽうこちらは
お手洗いで席を立った際に
車端のデッキから眺めた
進行方向の左手の車窓。
(「゚ー゚)ドレドレ
視界の条件が良ければ
黒部宇奈月温泉駅のあたりから
雄大な立山連峰が望めるハズなのですが
きょうは空気が霞んでいて
山容がよくわかりませんね・・・。
(≡"≡;*)モヤモヤ…。
▲24.3.16 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉-富山
(車窓から)
JR東日本とJR西日本の二社にまたがる
北陸新幹線は
新潟県の上越妙高が会社の境界駅ですが
そこを「かがやき」は通過するため
乗務員の交代は長野で行われます。
(・o・*)ホホゥ
▲24.3.16 北陸新幹線 長野
(車窓から)
糸魚川付近では車窓の右手に
日本海が望めます。
(*’∀’*)ウミ♪
今日は日本海側の各地も晴天で
海が青い。
▲24.3.16 北陸新幹線 糸魚川-黒部宇奈月温泉
(車窓から)
いっぽうこちらは
お手洗いで席を立った際に
車端のデッキから眺めた
進行方向の左手の車窓。
(「゚ー゚)ドレドレ
視界の条件が良ければ
黒部宇奈月温泉駅のあたりから
雄大な立山連峰が望めるハズなのですが
きょうは空気が霞んでいて
山容がよくわかりませんね・・・。
(≡"≡;*)モヤモヤ…。
▲24.3.16 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉-富山
(車窓から)
都心をあとにして、上信越(上州・信州・越後)を縦断するように北上したのち、やがて進路を西にとって北陸地方へと入りゆく北陸新幹線 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。ここまででもその変化に富んだ車窓風景は絵巻を見ているかのように楽しめます (・∀・)イイネ。
私が座った進行方向の右手にあたるA席からは浅間山や日本海が、いっぽう逆の左手にあたるE席だと妙高山や北アルプスの立山連峰が、それぞれに条件が良ければ車窓から見られますが (「゚ー゚)ドレドレ、どちらか選べるとしたら妙高や立山の雄大な山脈がどーんと望めるE席のほうが、あくまでも個人的には好みの眺めでしょうか(ただしきょうの立山は霞んでいた)。
はたしてこの先にひかえる延伸区間ではどうだろう。おそらく金沢を過ぎてから見えると思われる白山(はくさん)も方角的には南なのでE席側(左手)だな・・・σ(゚・゚*)ンー…(んじゃ白山が見えるあたりでもう一度、お手洗いに行こうかしらw)
私が座った進行方向の右手にあたるA席からは浅間山や日本海が、いっぽう逆の左手にあたるE席だと妙高山や北アルプスの立山連峰が、それぞれに条件が良ければ車窓から見られますが (「゚ー゚)ドレドレ、どちらか選べるとしたら妙高や立山の雄大な山脈がどーんと望めるE席のほうが、あくまでも個人的には好みの眺めでしょうか(ただしきょうの立山は霞んでいた)。
はたしてこの先にひかえる延伸区間ではどうだろう。おそらく金沢を過ぎてから見えると思われる白山(はくさん)も方角的には南なのでE席側(左手)だな・・・σ(゚・゚*)ンー…(んじゃ白山が見えるあたりでもう一度、お手洗いに行こうかしらw)
東京から二時間ちょっとで
ここはもう北陸の富山。
新幹線はやっぱり速いなぁ。
(゚ー゚*)トヤマ
ああ、白エビや寒ブリを食べたいw
▲24.3.16 北陸新幹線 富山
(車窓から)
A席側の見どころ探し?
・・・というわけではないけど
富山の港にかかる新湊大橋
(日本海側最大級の斜張橋)が
車窓から遠目に確認できました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.16 北陸新幹線 富山-新高岡
(車窓から)
県境を過ぎて富山から石川に入り
列車はまもなく金沢。
きょうからは次駅案内に
“福井”(もしくは小松)が
スクロールされます。
加賀百万石の城下町で
石川の県都である金沢に停車。
これまでは当駅が北陸新幹線の終点でした。
(゚ー゚*)カナザワ
なお敦賀への延伸後も「はくたか」を中心に
金沢止まり(および金沢始発)とする列車が
設定されています。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢
(車窓から)
ここはもう北陸の富山。
新幹線はやっぱり速いなぁ。
(゚ー゚*)トヤマ
ああ、白エビや寒ブリを食べたいw
▲24.3.16 北陸新幹線 富山
(車窓から)
A席側の見どころ探し?
・・・というわけではないけど
富山の港にかかる新湊大橋
(日本海側最大級の斜張橋)が
車窓から遠目に確認できました。
(゚∀゚)オッ!
▲24.3.16 北陸新幹線 富山-新高岡
(車窓から)
県境を過ぎて富山から石川に入り
列車はまもなく金沢。
きょうからは次駅案内に
“福井”(もしくは小松)が
スクロールされます。
加賀百万石の城下町で
石川の県都である金沢に停車。
これまでは当駅が北陸新幹線の終点でした。
(゚ー゚*)カナザワ
なお敦賀への延伸後も「はくたか」を中心に
金沢止まり(および金沢始発)とする列車が
設定されています。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢
(車窓から)
北陸路を順調に西進する「かがやき」はやがて、昨日まで北陸新幹線の終点だった金沢へ定刻に停車 (゚ー゚*)カナザワ。
首都圏からの“一番列車”となった「かがやき501号」の状況はわからないけど、「503号」ではこの先の延伸区間へ行かずに、北陸地方最大の都市である金沢で下車する人がけっこうみられました。ただし入れ替わるように当駅から乗ってこられる人も多くて、車内はほぼ満席の状態が続きます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
さあ、いよいよここからが本日開業となった延伸区間で、私のテンションはこれまでより一気に爆上がり ε-(°ω°*)ムフーッ!。目を皿のようにして見開き、額を窓に押し当てるくらい(?)の姿勢で、初乗車の車窓風景を眺めます (*゚v゚*)ワクワク♪。
首都圏からの“一番列車”となった「かがやき501号」の状況はわからないけど、「503号」ではこの先の延伸区間へ行かずに、北陸地方最大の都市である金沢で下車する人がけっこうみられました。ただし入れ替わるように当駅から乗ってこられる人も多くて、車内はほぼ満席の状態が続きます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
さあ、いよいよここからが本日開業となった延伸区間で、私のテンションはこれまでより一気に爆上がり ε-(°ω°*)ムフーッ!。目を皿のようにして見開き、額を窓に押し当てるくらい(?)の姿勢で、初乗車の車窓風景を眺めます (*゚v゚*)ワクワク♪。
金沢を発車して
新たな延伸区間へと入った「かがやき」。
...(((o*・ω・)o
なお並走している列車は
JR北陸本線から在来線を引き継いだ
第三セクター鉄道のIRいしかわ鉄道線です。
当線についてはまたあらためて。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
金沢と小松の間で渡るのは
白山を源流として日本海に流れる
手取川。
“石川”の通称で呼ばれた時代もあり
石川県の由来となったそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
いっぽう
左の車窓(デッキの扉窓w)には
立山とともに北陸を代表する名峰であり
山岳信仰の対象とされる霊山の
白山が望めました。
(「゚ー゚)ドレドレ
先ほどの立山より視界が良好。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
新たな延伸区間へと入った「かがやき」。
...(((o*・ω・)o
なお並走している列車は
JR北陸本線から在来線を引き継いだ
第三セクター鉄道のIRいしかわ鉄道線です。
当線についてはまたあらためて。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
金沢と小松の間で渡るのは
白山を源流として日本海に流れる
手取川。
“石川”の通称で呼ばれた時代もあり
石川県の由来となったそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
いっぽう
左の車窓(デッキの扉窓w)には
立山とともに北陸を代表する名峰であり
山岳信仰の対象とされる霊山の
白山が望めました。
(「゚ー゚)ドレドレ
先ほどの立山より視界が良好。
▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松
(車窓から)
きれいに山容が望める白山を横目に見ながら、石川から福井へ向かって加賀平野を突き進む北陸新幹線 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。
今回の延伸開業した区間には金沢の先に、小松、加賀温泉、芦原温泉(あわらおんせん)、福井、越前たけふ、そして敦賀の6駅が新たに新幹線の駅として設けられました (・o・*)ホホゥ。私が乗っている「かがやき503号」は福井と敦賀にしか停まりませんが、通過する各駅もなるべく見逃さないように注意を払います ( ・`ω・´)キリッ。・・・といっても、高速で一瞬のうちに通り過ぎちゃう駅を車窓から目で追うよりも、車内の案内表示器にスクロールされる【ただ今 ◯◯付近を通過】という文字で駅名を確認するほうが、無粋ながら個人的には通過している実感が湧くかもしれない(笑)(^^*)ゞポリポリ
今回の延伸開業した区間には金沢の先に、小松、加賀温泉、芦原温泉(あわらおんせん)、福井、越前たけふ、そして敦賀の6駅が新たに新幹線の駅として設けられました (・o・*)ホホゥ。私が乗っている「かがやき503号」は福井と敦賀にしか停まりませんが、通過する各駅もなるべく見逃さないように注意を払います ( ・`ω・´)キリッ。・・・といっても、高速で一瞬のうちに通り過ぎちゃう駅を車窓から目で追うよりも、車内の案内表示器にスクロールされる【ただ今 ◯◯付近を通過】という文字で駅名を確認するほうが、無粋ながら個人的には通過している実感が湧くかもしれない(笑)(^^*)ゞポリポリ
今回の延伸区間に設けられた
北陸新幹線の各駅はこんな位置。
石川県に小松と加賀温泉の2駅
福井県に芦原温泉、福井、
越前たけふ、敦賀の4駅が
新幹線の駅として加わりました。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
【ただ今 小松 付近を通過】
小松市というと小松空港と
建設機械メーカー(コマツ)の
イメージでしょうか。
( ̄  ̄*)コマツノオヤブン
当駅では北陸新幹線と
IRいしかわ鉄道(旧・北陸本線)が
接続しています。
【ただ今 加賀温泉 付近を通過】
石川県加賀市に所在する加賀温泉は
あわづ、山代、山中、片山津の
4つの温泉からなる温泉郷の総称です
(加賀温泉郷)。
( ̄  ̄*)レディカガ
当駅も北陸新幹線とIRいしかわ鉄道が
接続しています。
これは加賀温泉のシンボル(?)
73メートルの高さにインパクトがある
“黄金の巨大な観音さま”が
新幹線を見守ります。
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!
この加賀大観音
由緒ある観音像かと思いきや
実はバブル期に開園した
仏教をテーマとするレジャー施設に
建造されたものだそうです
( ´_ゝ`)フーン
なおテーマパークは
すでに閉園していますが
観音像の拝観はできるらしい。
▲24.3.16 北陸新幹線 小松-加賀温泉
(車窓から)
石川と福井の県境付近で
国道を跨ぐのに架けられた細坪橋梁は
何本もの白いケーブルが特徴的な
美しい斜張橋。
(車内からだとわかりづらいけど・・・)
ちなみに当橋は橋脚の最大間隔が
155メートルもあり
これは国内の鉄道橋で
最長のスパンだそうです。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.16 北陸新幹線 加賀温泉-芦原温泉
(車窓から)
【ただ今 芦原温泉 付近を通過】
福井県に入って最初の駅は
県内屈指の名湯で知られる芦原温泉。
(゚ー゚*)アワラ
これまでは北陸本線の特急を利用すると
関西圏からのアクセスが良かったことから
“関西の奥座敷”などと言われていましたが
関東と直結する新幹線の開業で
当地の訪客にも変化があるでしょうか。
σ(゚・゚*)ンー…
当駅では北陸新幹線と
福井県の第三セクター鉄道である
ハピラインふくい線(旧・北陸本線)が
接続しています。
福井市内を流れる九頭竜川を渡ると
建物が多く立ち並ぶ市街地となり
まもなく県都の福井に着きます。
(゚ー゚*)フクイ
▲24.3.16 北陸新幹線 芦原温泉-福井
(車窓から)
北陸新幹線の各駅はこんな位置。
石川県に小松と加賀温泉の2駅
福井県に芦原温泉、福井、
越前たけふ、敦賀の4駅が
新幹線の駅として加わりました。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
【ただ今 小松 付近を通過】
小松市というと小松空港と
建設機械メーカー(コマツ)の
イメージでしょうか。
( ̄  ̄*)コマツノオヤブン
当駅では北陸新幹線と
IRいしかわ鉄道(旧・北陸本線)が
接続しています。
【ただ今 加賀温泉 付近を通過】
石川県加賀市に所在する加賀温泉は
あわづ、山代、山中、片山津の
4つの温泉からなる温泉郷の総称です
(加賀温泉郷)。
( ̄  ̄*)レディカガ
当駅も北陸新幹線とIRいしかわ鉄道が
接続しています。
これは加賀温泉のシンボル(?)
73メートルの高さにインパクトがある
“黄金の巨大な観音さま”が
新幹線を見守ります。
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!
この加賀大観音
由緒ある観音像かと思いきや
実はバブル期に開園した
仏教をテーマとするレジャー施設に
建造されたものだそうです
( ´_ゝ`)フーン
なおテーマパークは
すでに閉園していますが
観音像の拝観はできるらしい。
▲24.3.16 北陸新幹線 小松-加賀温泉
(車窓から)
石川と福井の県境付近で
国道を跨ぐのに架けられた細坪橋梁は
何本もの白いケーブルが特徴的な
美しい斜張橋。
(車内からだとわかりづらいけど・・・)
ちなみに当橋は橋脚の最大間隔が
155メートルもあり
これは国内の鉄道橋で
最長のスパンだそうです。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.16 北陸新幹線 加賀温泉-芦原温泉
(車窓から)
【ただ今 芦原温泉 付近を通過】
福井県に入って最初の駅は
県内屈指の名湯で知られる芦原温泉。
(゚ー゚*)アワラ
これまでは北陸本線の特急を利用すると
関西圏からのアクセスが良かったことから
“関西の奥座敷”などと言われていましたが
関東と直結する新幹線の開業で
当地の訪客にも変化があるでしょうか。
σ(゚・゚*)ンー…
当駅では北陸新幹線と
福井県の第三セクター鉄道である
ハピラインふくい線(旧・北陸本線)が
接続しています。
福井市内を流れる九頭竜川を渡ると
建物が多く立ち並ぶ市街地となり
まもなく県都の福井に着きます。
(゚ー゚*)フクイ
▲24.3.16 北陸新幹線 芦原温泉-福井
(車窓から)
小松、加賀温泉、芦原温泉と新幹線の駅としては新設ですが、やはり今日はまだ北陸本線の駅名という印象が強い各駅を次々と通過した「かがやき503号」は、東京から2時間50分で福井に到達 (゚ー゚*)フクイ。
最終的に敦賀へと延伸した今回の開業ですが、福井を目的地として乗られた人も多かったようで、私がいる号車ではだいたい三割くらいの乗客が福井で下車 オリル…((((o* ̄-)o 。敦賀までの残り区間にあえて全席指定の「かがやき」へ福井から乗ってくる人は少なく(各駅に停まる区間列車タイプの「つるぎ」には自由席がある)、ほぼ満席が続いていた車内はここで少し空席ができました (´ー`)マターリ。
最終的に敦賀へと延伸した今回の開業ですが、福井を目的地として乗られた人も多かったようで、私がいる号車ではだいたい三割くらいの乗客が福井で下車 オリル…((((o* ̄-)o 。敦賀までの残り区間にあえて全席指定の「かがやき」へ福井から乗ってくる人は少なく(各駅に停まる区間列車タイプの「つるぎ」には自由席がある)、ほぼ満席が続いていた車内はここで少し空席ができました (´ー`)マターリ。
県内(おもに勝山市)で
恐竜の化石が多く見つかっていることから
“恐竜王国”をアピールしている福井。
車内から窓の外をみると
恐竜たちも新幹線の開業を歓迎!?
(=゚ω゚=*)キョーリュー!
▲24.3.16 北陸新幹線 福井
(車窓から)
恐竜の化石が多く見つかっていることから
“恐竜王国”をアピールしている福井。
車内から窓の外をみると
恐竜たちも新幹線の開業を歓迎!?
(=゚ω゚=*)キョーリュー!
▲24.3.16 北陸新幹線 福井
(車窓から)
ところで本記事の冒頭でもちょろっと触れたように、個人的に福井は仕事関係での馴染みがある土地で、いちばん多かったときは年に二、三度、行くことが減った今も二、三年に一度くらいは訪れており (=゚ω゚)ノ゙ヤア、その福井へ首都圏からダイレクトに新幹線が乗り入れるようになったことは、少なからず感慨深いものがあります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
ちなみにこれまで東京から福井へ行く場合の経路は、東海道新幹線と北陸本線(の特急)を滋賀県の米原で乗り継ぐルートが一般的とされ、私が出張で利用する際もそれが多かったのですが ...(((o*・ω・)o(ためしに北陸新幹線と北陸本線を金沢で乗り継ぐ経路を選んだのは一度だけ。また、出張のついでに“鉄旅”を絡めて、上越新幹線とほくほく線、北陸本線を乗り継ぐルートを選んだこともありましたが)、今回の延伸開業により今後は時間的にも料金的にも北陸新幹線による“ダイレクトルート”を選ぶことになるでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。
なお、東海道ルート(米原経由)と北陸ルート(金沢経由)を比較すると、前者が3時間18分で16,950円、後者が2時間51分で15,810円となっています(時間はいずれも最速、運賃・料金は普通車指定席の場合)(*・`o´・*)ホ─。
ちなみにこれまで東京から福井へ行く場合の経路は、東海道新幹線と北陸本線(の特急)を滋賀県の米原で乗り継ぐルートが一般的とされ、私が出張で利用する際もそれが多かったのですが ...(((o*・ω・)o(ためしに北陸新幹線と北陸本線を金沢で乗り継ぐ経路を選んだのは一度だけ。また、出張のついでに“鉄旅”を絡めて、上越新幹線とほくほく線、北陸本線を乗り継ぐルートを選んだこともありましたが)、今回の延伸開業により今後は時間的にも料金的にも北陸新幹線による“ダイレクトルート”を選ぶことになるでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。
なお、東海道ルート(米原経由)と北陸ルート(金沢経由)を比較すると、前者が3時間18分で16,950円、後者が2時間51分で15,810円となっています(時間はいずれも最速、運賃・料金は普通車指定席の場合)(*・`o´・*)ホ─。
今回の私は下車せずに
車内から駅名標を確認した程度の福井。
当駅にはいずれまた(出張で?)
新幹線から降り立って
新たに完成した駅の構内などを
じっくりと眺めてみたいものです。
なお当駅では北陸新幹線と
越美北線(九頭竜線)
ハピラインふくい線、福井鉄道が
それぞれ接続しています。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井
(車窓から)
車内から駅名標を確認した程度の福井。
当駅にはいずれまた(出張で?)
新幹線から降り立って
新たに完成した駅の構内などを
じっくりと眺めてみたいものです。
なお当駅では北陸新幹線と
越美北線(九頭竜線)
ハピラインふくい線、福井鉄道が
それぞれ接続しています。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井
(車窓から)
さて「かがやき503号」の次の停車駅は終点の敦賀。東京からの旅路もいよいよラストスパートです (*`・ω・)-3フンス! ・・・が、あれ?どうしたことか、福井での停車時間は1分程度のハズですが、発車時刻を過ぎても列車がなかなか動きません (゚ー゚?)オヨ?。新幹線を見学に来た人が安全柵から身を乗り出しでもしたのか「ホーム上の安全確認をしております」とのことで、結果的に8分ほど遅れて福井を発車。ひょっとしてこれは延伸開業後に初めての“遅延列車”かな?(・∀・`)ウーン…。けっして記念にするようないいことではないんだけど。
福井を出るとすぐ見えるのが
足羽山(公園)
標高116メートルほどの低山で
遊園地や動物園などがある
福井市民の憩いの場です。
(・∀・)イイネ
機会があれば山上の展望台から
新幹線を眺めてみたいところ。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
お、“ベル”が見える。
(o ̄∇ ̄o)ベル
これは市内にあるショッピングモールですが
福井鉄道に「ベル前」という
停留場みたいな名の駅があることで
なんとなく私の印象に残っています。
(゚∀゚)アヒャ☆
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
福井の市街地を抜けたこのあたりは
メガネの生産業が盛んなことから
“めがねの街”として知られる
鯖江(さばえ)市。
(゚ー゚*)サバエ
よ~く目を凝らしてみると車窓からは
そのランドマーク的な存在で
ビルにメガネが掲げられている
「めがねミュージアム」が
確認できました。
(゚∀゚)オッ!
以前に地元の人の案内で
見学に訪れたことがありますが
メガネの歴史や製法が学べるだけでなく
著名人がかけていたメガネなども
展示されていて
けっこう楽しめます。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
【ただ今 越前たけふ 付近を通過】
福井県越前市に所在する当駅は
今回開業した延伸区間のなかで唯一
他の路線と接していない
北陸新幹線のみの単独駅で
在来線であるハピラインふくいの武生駅
および福井鉄道のたけふ新駅とは
三キロほど離れた場所に位置しています。
(゚ー゚*)タケフ
のどかな里山風景が広がる
越前市や南越前町。
このあたりでいただける
本場の“越前おろしそば”は
福井市内などで食べるものよりも
ホントに美味しいです。
(゚¬゚〃)ジュルリ
▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀
(車窓から)
足羽山(公園)
標高116メートルほどの低山で
遊園地や動物園などがある
福井市民の憩いの場です。
(・∀・)イイネ
機会があれば山上の展望台から
新幹線を眺めてみたいところ。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
お、“ベル”が見える。
(o ̄∇ ̄o)ベル
これは市内にあるショッピングモールですが
福井鉄道に「ベル前」という
停留場みたいな名の駅があることで
なんとなく私の印象に残っています。
(゚∀゚)アヒャ☆
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
福井の市街地を抜けたこのあたりは
メガネの生産業が盛んなことから
“めがねの街”として知られる
鯖江(さばえ)市。
(゚ー゚*)サバエ
よ~く目を凝らしてみると車窓からは
そのランドマーク的な存在で
ビルにメガネが掲げられている
「めがねミュージアム」が
確認できました。
(゚∀゚)オッ!
以前に地元の人の案内で
見学に訪れたことがありますが
メガネの歴史や製法が学べるだけでなく
著名人がかけていたメガネなども
展示されていて
けっこう楽しめます。
▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ
(車窓から)
【ただ今 越前たけふ 付近を通過】
福井県越前市に所在する当駅は
今回開業した延伸区間のなかで唯一
他の路線と接していない
北陸新幹線のみの単独駅で
在来線であるハピラインふくいの武生駅
および福井鉄道のたけふ新駅とは
三キロほど離れた場所に位置しています。
(゚ー゚*)タケフ
のどかな里山風景が広がる
越前市や南越前町。
このあたりでいただける
本場の“越前おろしそば”は
福井市内などで食べるものよりも
ホントに美味しいです。
(゚¬゚〃)ジュルリ
▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀
(車窓から)
足羽山(あすわやま)は福井名所のひとつだけど、地域のショッピングモール(ベルね)や鯖江(さばえ)の「MEGANE MUSEUM(めがねミュージアム)」など、だいぶ個人的な興味に偏った視点で眺めている車窓風景 ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
延伸開業した区間で風景的にいちばんの見どころはやはり、私が座る“A席”とは逆側の“E席”から望める白山の山なみだと思われるのですが (´ω`*)ハクサン、むしろ今回は“A席”だったことによって白山がよくみられなかったぶん、ほかに車窓から何かを探そうとした意識が働いたせいか (「゚ー゚)ドレドレ、福井の手前の加賀温泉で見えた“黄金の巨大観音像”(加賀大観音)などもそうで、意外と面白いものに目が留まった気がします 。
そんな自己満足な楽しみかたをしていた車窓に暗幕を下ろすかのごとく、やがて列車は長~~いトンネルへと突入 ( ̄  ̄)マックラ。北陸新幹線では「飯山トンネル」(全長22,225 m)に次ぐ二番目の長さを誇る、全長19,760 mの「新北陸トンネル」です (゚ー゚*)ネルトン。
それを抜けるとまもなく終点の敦賀に到着。
延伸開業した区間で風景的にいちばんの見どころはやはり、私が座る“A席”とは逆側の“E席”から望める白山の山なみだと思われるのですが (´ω`*)ハクサン、むしろ今回は“A席”だったことによって白山がよくみられなかったぶん、ほかに車窓から何かを探そうとした意識が働いたせいか (「゚ー゚)ドレドレ、福井の手前の加賀温泉で見えた“黄金の巨大観音像”(加賀大観音)などもそうで、意外と面白いものに目が留まった気がします 。
そんな自己満足な楽しみかたをしていた車窓に暗幕を下ろすかのごとく、やがて列車は長~~いトンネルへと突入 ( ̄  ̄)マックラ。北陸新幹線では「飯山トンネル」(全長22,225 m)に次ぐ二番目の長さを誇る、全長19,760 mの「新北陸トンネル」です (゚ー゚*)ネルトン。
それを抜けるとまもなく終点の敦賀に到着。
在来線(旧・北陸本線)に乗ったときも
「北陸トンネル」(全長13,870 m)は
抜けるまで長く感じたけど
新幹線の「新北陸トンネル」もまた長かった。
( ̄  ̄)マックラ
車窓がふたたび明るくなると
そこは敦賀市です。
▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀
(車窓から)
W7系の「かがやき」が
本日より北陸新幹線と終点となった
敦賀のホームに到着。
(・ω・)トーチャコ
長旅おつかれさまでした!
▲24.3.16 北陸新幹線 敦賀
「北陸トンネル」(全長13,870 m)は
抜けるまで長く感じたけど
新幹線の「新北陸トンネル」もまた長かった。
( ̄  ̄)マックラ
車窓がふたたび明るくなると
そこは敦賀市です。
▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀
(車窓から)
W7系の「かがやき」が
本日より北陸新幹線と終点となった
敦賀のホームに到着。
(・ω・)トーチャコ
長旅おつかれさまでした!
▲24.3.16 北陸新幹線 敦賀
東京0720-(北陸新幹線 かがやき503号)-敦賀1035(定刻の7分遅れ)
東京から本来なら3時間8分のところ、福井での安全確認があったため、定刻より7分ほど遅れて敦賀の新幹線ホームへと滑り込んだ「かがやき503号」(・ω・)トーチャコ。
これにて私は新たに延伸した金沢と福井のあいだを含む、北陸新幹線の全線(高崎~敦賀)を完乗したこととなりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。未乗車だった路線や区間を乗りつぶして、目的駅のホームに降り立つ瞬間に湧きあがる達成感は、何度味わってもいいものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
なお今回の北陸新幹線の金沢~敦賀延伸では、新幹線の開業によって在来線(北陸本線)の特急列車の運行区間が短縮されたことで、おもに関西方面と北陸の各都市あいだのアクセスにこれまでよりも不便が生じる場合もあるようですが(特急と新幹線を敦賀で乗り継がなければならない)(゚ペ)ウーン…、私としてはあえてそのことをここで議論するつもりはなく、「新たに鉄道路線(新幹線)ができたのなら、さっそく開業日に乗りつぶそう」という、あくまでも個人的な興味本位の“趣味目線で見た状況”を淡々とお伝えさせていただきました (-`ω´-*)ウム。そのことをご理解ください。
東京から本来なら3時間8分のところ、福井での安全確認があったため、定刻より7分ほど遅れて敦賀の新幹線ホームへと滑り込んだ「かがやき503号」(・ω・)トーチャコ。
これにて私は新たに延伸した金沢と福井のあいだを含む、北陸新幹線の全線(高崎~敦賀)を完乗したこととなりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。未乗車だった路線や区間を乗りつぶして、目的駅のホームに降り立つ瞬間に湧きあがる達成感は、何度味わってもいいものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
なお今回の北陸新幹線の金沢~敦賀延伸では、新幹線の開業によって在来線(北陸本線)の特急列車の運行区間が短縮されたことで、おもに関西方面と北陸の各都市あいだのアクセスにこれまでよりも不便が生じる場合もあるようですが(特急と新幹線を敦賀で乗り継がなければならない)(゚ペ)ウーン…、私としてはあえてそのことをここで議論するつもりはなく、「新たに鉄道路線(新幹線)ができたのなら、さっそく開業日に乗りつぶそう」という、あくまでも個人的な興味本位の“趣味目線で見た状況”を淡々とお伝えさせていただきました (-`ω´-*)ウム。そのことをご理解ください。
福井県敦賀市の中心にある敦賀駅。
(゚ー゚*)ツルガ
新幹線の開業により新設された
東口(やまなみ口)の立派な駅舎は
港町の敦賀らしい
白と青のカラーリングが印象的です。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
新幹線が発着する高架ホームの
階下に設けられた
北陸本線の特急列車専用ホーム。
北陸新幹線と接続する
京都・大坂方面の「サンダーバード」や
米原・名古屋方面の「しらさぎ」が
当ホームに発着します。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
(゚ー゚*)ツルガ
新幹線の開業により新設された
東口(やまなみ口)の立派な駅舎は
港町の敦賀らしい
白と青のカラーリングが印象的です。
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
新幹線が発着する高架ホームの
階下に設けられた
北陸本線の特急列車専用ホーム。
北陸新幹線と接続する
京都・大坂方面の「サンダーバード」や
米原・名古屋方面の「しらさぎ」が
当ホームに発着します。
(*・`o´・*)ホ─
▲24.3.16 北陸本線 敦賀
さて、北陸新幹線を乗り通して敦賀までやってきた私 (゚ー゚*)ツルガ。
ここ敦賀は北陸新幹線のほか、長浜、米原方面への北陸本線、京阪神方面へ向かう湖西線(正式には北陸本線の近江塩津から分岐)、小浜、東舞鶴方面への小浜線(おばません)、そして当駅から福井方面の北陸本線を引き継いだ第三セクター鉄道のハピラインふくい線、それらの各列車が発着します (*゚ェ゚)フムフム。
そのなかで次に乗るのは・・・σ(゚・゚*)ンー…って、もう答えは速報でご紹介した前記事の「ONE-shot」でお解りですね(笑)(。A。)アヒャ☆
北陸の鉄旅、次回に続きます。
ここ敦賀は北陸新幹線のほか、長浜、米原方面への北陸本線、京阪神方面へ向かう湖西線(正式には北陸本線の近江塩津から分岐)、小浜、東舞鶴方面への小浜線(おばません)、そして当駅から福井方面の北陸本線を引き継いだ第三セクター鉄道のハピラインふくい線、それらの各列車が発着します (*゚ェ゚)フムフム。
そのなかで次に乗るのは・・・σ(゚・゚*)ンー…って、もう答えは速報でご紹介した前記事の「ONE-shot」でお解りですね(笑)(。A。)アヒャ☆
北陸の鉄旅、次回に続きます。
2024-03-23 23:23
福岡市地下鉄七隈線・・・延伸区間 乗車記 [鉄道乗車記]
前回からの続きです (=゚ω゚)ノ゙ヨロシコ。
年末年始の移動で交通機関が混雑する“繁忙期”を避け、比較的旅行者が少ないとされる12月上旬の“閑散期”に、休暇を取った私は成田からLCCの飛行機で九州へと飛びます (o ̄∇ ̄o)キューシュー。
二泊三日とした旅程の初日に福岡空港から向かったのは、福岡市地下鉄との直通運転を行っているJRの路線で、福岡市内から佐賀県の唐津へといたる筑肥線(ちくひせん)(゚ー゚*)チクヒセソ。その沿線に広がる玄界灘(唐津湾)の海景色で列車(国鉄型の103系など)の撮影を存分に楽しみました (^_[◎]oパチリ。
唐津で迎えた二日目は、唐津線、長崎本線、鹿児島本線の列車を乗り継ぎ、佐賀県から福岡県を経て熊本県へと南下 ...(((o*・ω・)o。その道中にて“撮り鉄垂涎”の貴重な電気機関車である“銀ガマ”(EF81 303)が牽く貨物列車の運行情報をキャッチし (゚∀゚)オッ!、急きょ途中の駅(大野下)で下車をして撮影 パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。思わぬラッキーサプライズに大喜びしたのち、この日の本来の目的である熊本電鉄(通称・熊電)へ向かいます (● ̄(エ) ̄●)クマデソ。私は熊電を過去に菊池線と藤崎線の全線を完乗(完全乗車)していますが、昨年(2022年)に沿線の再開発で路線の一部が移設されたため (・o・*)ホホゥ、当該区間(熊本高専前〜御代志)をもう一度あらためて“乗り直し”ました ( ̄  ̄*)ノリナオシ。
目的を果たした私は熊本城などの名所を観光することなく熊本をあとにして、来た道を戻るように鹿児島本線の列車を乗り継いで北上...(((o*・ω・)o。福岡県の久留米を二日目の宿泊地としました (゚ー゚*)クルメ。
12月9日(土)
久留米で朝を迎えた旅の三日目 (*´=ωヾ)オハヨ。
まだ夜明け前の真っ暗な時間帯に唐津を列車で出発した昨日と比べたら、今朝は少し遅めではあるものの、それでも7時前にはホテルをチェックアウトして最寄りの駅へ向かいます。
年末年始の移動で交通機関が混雑する“繁忙期”を避け、比較的旅行者が少ないとされる12月上旬の“閑散期”に、休暇を取った私は成田からLCCの飛行機で九州へと飛びます (o ̄∇ ̄o)キューシュー。
二泊三日とした旅程の初日に福岡空港から向かったのは、福岡市地下鉄との直通運転を行っているJRの路線で、福岡市内から佐賀県の唐津へといたる筑肥線(ちくひせん)(゚ー゚*)チクヒセソ。その沿線に広がる玄界灘(唐津湾)の海景色で列車(国鉄型の103系など)の撮影を存分に楽しみました (^_[◎]oパチリ。
唐津で迎えた二日目は、唐津線、長崎本線、鹿児島本線の列車を乗り継ぎ、佐賀県から福岡県を経て熊本県へと南下 ...(((o*・ω・)o。その道中にて“撮り鉄垂涎”の貴重な電気機関車である“銀ガマ”(EF81 303)が牽く貨物列車の運行情報をキャッチし (゚∀゚)オッ!、急きょ途中の駅(大野下)で下車をして撮影 パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。思わぬラッキーサプライズに大喜びしたのち、この日の本来の目的である熊本電鉄(通称・熊電)へ向かいます (● ̄(エ) ̄●)クマデソ。私は熊電を過去に菊池線と藤崎線の全線を完乗(完全乗車)していますが、昨年(2022年)に沿線の再開発で路線の一部が移設されたため (・o・*)ホホゥ、当該区間(熊本高専前〜御代志)をもう一度あらためて“乗り直し”ました ( ̄  ̄*)ノリナオシ。
目的を果たした私は熊本城などの名所を観光することなく熊本をあとにして、来た道を戻るように鹿児島本線の列車を乗り継いで北上...(((o*・ω・)o。福岡県の久留米を二日目の宿泊地としました (゚ー゚*)クルメ。
12月9日(土)
久留米で朝を迎えた旅の三日目 (*´=ωヾ)オハヨ。
まだ夜明け前の真っ暗な時間帯に唐津を列車で出発した昨日と比べたら、今朝は少し遅めではあるものの、それでも7時前にはホテルをチェックアウトして最寄りの駅へ向かいます。
私が宿泊した久留米市の中心部には、きのう鹿児島本線の列車から降り立ったJRの久留米と、私鉄の“西鉄”こと西日本鉄道の西鉄久留米の二駅があり (・o・*)ホホゥ、どちらかというと繁華街として栄えているのは西鉄久留米のほうで、泊まったホテルもそちらに近い場所でした コッチ…((((o* ̄-)o(なおJRと西鉄の両駅間はおよそ2キロ離れており、歩くにはちょっとしんどい距離だったため、きのうの移動には路線バスを利用しています)。
そしてきょうの行程はとくにJRへこだわる必要はなく、それならば西鉄を利用してみましょう (・∀・)ニシテツ。ちなみに私が西鉄に乗るのはたぶん、福岡出張のついでに当線の沿線に住んでいた友人(現在は関東在住)へ会いに行った、06年以来となる17年ぶりになるのかな (*´∀`)ノ゙オヒサ。
そしてきょうの行程はとくにJRへこだわる必要はなく、それならば西鉄を利用してみましょう (・∀・)ニシテツ。ちなみに私が西鉄に乗るのはたぶん、福岡出張のついでに当線の沿線に住んでいた友人(現在は関東在住)へ会いに行った、06年以来となる17年ぶりになるのかな (*´∀`)ノ゙オヒサ。
西鉄電車(6050形)の色は
爽やかな“アイスグリーン”。
チョコミント好きで
“チョコミン党”の私としては、
この色を見るとチョコミント味の
アイスが食べたくなります(笑)
(o ̄∇ ̄o)ミント
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米
爽やかな“アイスグリーン”。
チョコミント好きで
“チョコミン党”の私としては、
この色を見るとチョコミント味の
アイスが食べたくなります(笑)
(o ̄∇ ̄o)ミント
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米
西鉄久留米から乗った西鉄福岡(天神)ゆきの急行電車は、非対称な前面形状などがいかにも西鉄っぽい車体デザインで、“アイスグリーン”の色に塗られた6050形 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。近年は西鉄でもやはりステンレス製の車両(3000形や9000形など)が増えているようですが、個人的に西鉄の一般車のイメージといえばこのアイスグリーンの電車がパッと思い浮かびます (o ̄∇ ̄o)ミント。
きょうは週末の土曜日だけど、久留米から福岡市内のほうへ向かう朝の上り列車は通勤や通学と思われる人たちで車内がけっこう混んでおり、はじめは座れずに立って車窓の景色を眺めていましたが、途中の小郡(おごおり)で目の前の席が空きました (´∇`*)ラッキー♪。
きょうは週末の土曜日だけど、久留米から福岡市内のほうへ向かう朝の上り列車は通勤や通学と思われる人たちで車内がけっこう混んでおり、はじめは座れずに立って車窓の景色を眺めていましたが、途中の小郡(おごおり)で目の前の席が空きました (´∇`*)ラッキー♪。
車窓より眺める筑後川。
きのうは鹿児島本線の下り列車でしたが
今朝は西鉄の上り列車で渡ります。
窓に反射する車内の様子には
ロングシートで居眠りをしている
通勤客のお姿が映っとる・・・。
(´w`*)オツカレサン
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線
櫛原-宮の陣(車窓から)
きのうは鹿児島本線の下り列車でしたが
今朝は西鉄の上り列車で渡ります。
窓に反射する車内の様子には
ロングシートで居眠りをしている
通勤客のお姿が映っとる・・・。
(´w`*)オツカレサン
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線
櫛原-宮の陣(車窓から)
西日本鉄道(西鉄)の本線である天神大牟田線(てんじんおおむたせん)は、福岡市中心部の繁華街にある西鉄福岡(天神)を起点に、二日市(ふつかいち)、小郡、西鉄久留米、柳川(やながわ)などを経て福岡県西部を縦断し、同県南西部に位置する大牟田市の大牟田(おおむた)へいたる大手私鉄の路線(いまの私は起点のほうへ進む上り列車に乗車しています)(゚ー゚*)ニシテツ。JR鹿児島本線の博多〜大牟田と並行するような形で敷かれているものの、福岡〜久留米は内陸側を、久留米〜大牟田では沿岸側の地域を西鉄がフォローしている格好で、両者は競合路線というより上手く棲み分けている印象です ( ̄。 ̄)ヘー。
ちなみにJRと私鉄で運賃を比べた場合、たいていは私鉄の方が安いイメージがあり、ここでもやはり福岡(博多)〜大牟田がJRだと1,310円(普通乗車券)なのに対し、西鉄は1,050円。福岡(博多)〜久留米でもJRが760円に対し、西鉄は640円で割安となっています (´艸`*)オトク。
そんな西鉄の急行電車に乗って久留米からおよそ45分、私がやってきたのは終点の西鉄福岡(天神)( ̄  ̄*)テンジン。なお、西鉄福岡の駅が天神地区にあることを何度もクドいくらいに私が“カッコ書き”で捕捉しているように思えるかもしれませんが、当駅はカッコの部分まで含めた“西鉄福岡(天神)”が正式な駅名です(2001年に西鉄福岡より改称)(´ω`)ナルヘソ。
ちなみにJRと私鉄で運賃を比べた場合、たいていは私鉄の方が安いイメージがあり、ここでもやはり福岡(博多)〜大牟田がJRだと1,310円(普通乗車券)なのに対し、西鉄は1,050円。福岡(博多)〜久留米でもJRが760円に対し、西鉄は640円で割安となっています (´艸`*)オトク。
そんな西鉄の急行電車に乗って久留米からおよそ45分、私がやってきたのは終点の西鉄福岡(天神)( ̄  ̄*)テンジン。なお、西鉄福岡の駅が天神地区にあることを何度もクドいくらいに私が“カッコ書き”で捕捉しているように思えるかもしれませんが、当駅はカッコの部分まで含めた“西鉄福岡(天神)”が正式な駅名です(2001年に西鉄福岡より改称)(´ω`)ナルヘソ。
福岡市中心部の繁華街である
中央区の天神地区に所在し
立派な駅ビルを構える
西鉄天神大牟田線のターミナル
西鉄福岡(天神)。
( ̄  ̄*)テンジン
ビルの二階に位置するホームは
四面三線の頭端式となっています。
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)
中央区の天神地区に所在し
立派な駅ビルを構える
西鉄天神大牟田線のターミナル
西鉄福岡(天神)。
( ̄  ̄*)テンジン
ビルの二階に位置するホームは
四面三線の頭端式となっています。
▲23.12.9 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)
西鉄久留米0655-(西鉄天神大牟田線急行)-西鉄福岡(天神)0736
福岡市・・・いや、九州で随一の繁華街である天神。車線の広い通り沿いには有名百貨店などの商業施設をはじめとした大きなビルがいくつも立ち並び、まさに“大都会”の様相です (゚ー゚*)クリスタルキング。個人的にこのあたりは旅行よりも仕事の出張(と、その流れでの飲み会w)で訪れるほうが多い印象 ( ̄  ̄*)オシゴト。
ところで、きょうの私のおもな目的地が福岡市内なのに宿泊を当地でなく、あえて久留米としたのは宿泊費の価格差が理由。たとえ閑散期の平日であってもインバウンド需要の高い福岡市内のホテルはどこも設定料金がかなり高かったため (´〜`)ウーン、同程度の部屋(ごくふつうのシングルルーム)がその半額近い値段で泊まれる久留米を選んだのでした (-`ω´-*)ウム。
そんな福岡の天神に私がやってきた目的は・・・拙ブログにお付き合いいただいて鉄道に詳しい方ならばおそらく、もうおわかりになるのではないかと思われますが σ(゚・゚*)ンー…、その前にまずはこちらの電車へ乗ります。
福岡市・・・いや、九州で随一の繁華街である天神。車線の広い通り沿いには有名百貨店などの商業施設をはじめとした大きなビルがいくつも立ち並び、まさに“大都会”の様相です (゚ー゚*)クリスタルキング。個人的にこのあたりは旅行よりも仕事の出張(と、その流れでの飲み会w)で訪れるほうが多い印象 ( ̄  ̄*)オシゴト。
ところで、きょうの私のおもな目的地が福岡市内なのに宿泊を当地でなく、あえて久留米としたのは宿泊費の価格差が理由。たとえ閑散期の平日であってもインバウンド需要の高い福岡市内のホテルはどこも設定料金がかなり高かったため (´〜`)ウーン、同程度の部屋(ごくふつうのシングルルーム)がその半額近い値段で泊まれる久留米を選んだのでした (-`ω´-*)ウム。
そんな福岡の天神に私がやってきた目的は・・・拙ブログにお付き合いいただいて鉄道に詳しい方ならばおそらく、もうおわかりになるのではないかと思われますが σ(゚・゚*)ンー…、その前にまずはこちらの電車へ乗ります。
西鉄の駅ビルからエスカレーターを地下のほうへ下り、いまの時間(7時半過ぎ)はまだ数店ほどしか開いていない地下街のショッピングモールを歩き進むと、その先にあるのが福岡市地下鉄(福岡市交通局)空港線の天神駅 (゚ー゚*)チカテツ。そしてここから私が乗ったのは、博多や福岡空港とは逆のほうへ向かう、下りの姪浜(めいのはま)ゆきです コッチ…((((o* ̄-)o。
この地下鉄空港線といえば、今旅の初日(おととい)にも福岡空港の駅から下り列車に乗って、当線と直通運転を行っているJRの筑肥線へと向かいました (゚ー゚*)チクヒセソ。それをまた繰り返すような今の展開、ひょっとして一昨日の撮影だけでは物足りずにもう一度、筑肥線の103系を撮りに行こうとしているのか? (=゚ω゚=*)モウイッチョ?
しかし今日は筑肥線のほうには進まず、地下鉄空港線の終点である姪浜で下車します。
この地下鉄空港線といえば、今旅の初日(おととい)にも福岡空港の駅から下り列車に乗って、当線と直通運転を行っているJRの筑肥線へと向かいました (゚ー゚*)チクヒセソ。それをまた繰り返すような今の展開、ひょっとして一昨日の撮影だけでは物足りずにもう一度、筑肥線の103系を撮りに行こうとしているのか? (=゚ω゚=*)モウイッチョ?
しかし今日は筑肥線のほうには進まず、地下鉄空港線の終点である姪浜で下車します。
天神から地下鉄で15分
福岡市西区に所在する姪浜。
(゚ー゚*)メーノハマ
駅前で目をひく波と兎のモニュメントは
姪浜の港に伝わる「龍王兎伝説」がモチーフで
大陸の宋を訪れた姪浜の国師がその帰途
狼に襲われそうな兎を助けてやり
いっしょに船へ乗せたところ
嵐の玄界灘で船が沈没しそうになったなか
兎が荒波に飛び込むと嵐がおさまった
・・・という“恩返し伝説”だそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.12.9 福岡市地下鉄空港線 姪浜
福岡市西区に所在する姪浜。
(゚ー゚*)メーノハマ
駅前で目をひく波と兎のモニュメントは
姪浜の港に伝わる「龍王兎伝説」がモチーフで
大陸の宋を訪れた姪浜の国師がその帰途
狼に襲われそうな兎を助けてやり
いっしょに船へ乗せたところ
嵐の玄界灘で船が沈没しそうになったなか
兎が荒波に飛び込むと嵐がおさまった
・・・という“恩返し伝説”だそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.12.9 福岡市地下鉄空港線 姪浜
天神0805-(福岡市空港線)-姪浜0819
姪浜は地下鉄空港線とJR筑肥線の接続駅(直通境界駅)で、発着するのはその二路線のみ。
ちょっとマニアックな趣味的に見ると、初日の記事でも少し触れていますが、もともと地下鉄空港線が開業する1983年より前は博多からこの姪浜までも国鉄の筑肥線として線路が地上でつながっていた過去があり、ひょっとしたら現在でもその痕跡や廃線跡が僅かに残っているかもしれません (「゚ー゚)ドレドレ・・・が、私は鉄道が趣味の“鉄ちゃん”だけど過去の廃線跡には興味が薄くて、それを辿るようなこともあまりしない σ(・∀・`)ウーン…。
んじゃ、なぜ姪浜に来たのかというと、ここから今度は路線バスで移動します ( ̄  ̄*)バス。
姪浜は地下鉄空港線とJR筑肥線の接続駅(直通境界駅)で、発着するのはその二路線のみ。
ちょっとマニアックな趣味的に見ると、初日の記事でも少し触れていますが、もともと地下鉄空港線が開業する1983年より前は博多からこの姪浜までも国鉄の筑肥線として線路が地上でつながっていた過去があり、ひょっとしたら現在でもその痕跡や廃線跡が僅かに残っているかもしれません (「゚ー゚)ドレドレ・・・が、私は鉄道が趣味の“鉄ちゃん”だけど過去の廃線跡には興味が薄くて、それを辿るようなこともあまりしない σ(・∀・`)ウーン…。
んじゃ、なぜ姪浜に来たのかというと、ここから今度は路線バスで移動します ( ̄  ̄*)バス。
姪浜駅南口の停留所から
西鉄バスに乗ります。
これでどこへ行くのか?
σ(゚・゚*)ンー…
▲23.12.9 西鉄バス 姪浜駅南口
利用したバスの路線図はこんな感じ。
(*゚ェ゚)フムフム
私が乗車したのは
姪浜駅から左端の赤い線で示された
野方、橋本駅経由の金武車庫ゆきです。
西鉄バスに乗ります。
これでどこへ行くのか?
σ(゚・゚*)ンー…
▲23.12.9 西鉄バス 姪浜駅南口
利用したバスの路線図はこんな感じ。
(*゚ェ゚)フムフム
私が乗車したのは
姪浜駅から左端の赤い線で示された
野方、橋本駅経由の金武車庫ゆきです。
きょうは“鉄旅”でなく“ローカル路線バスの旅”か?(゚∀゚)アヒャ☆
姪浜駅前を発車したバスは線路沿いには進まず、東西にのびる地下鉄空港線や筑肥線から離れて街なかを南下します。その区名のとおり福岡市の西部に位置する西区、バスの車窓からは近年に建ったと思われる高層マンションや新しさを感じるきれいな一戸建て住宅が多く目に留まり、天神や博多、さらには福岡空港まで姪浜から地下鉄で一本の好立地による、人気の高いエリアだということが伺えます (・∀・)イイネ。
そんな閑静な住宅街を進むこと25分、大きなショッピングモールをかすめたのちにバスが停まったのは、橋本駅前のロータリーにある停留所 (・ω・)トーチャコ。
姪浜駅前を発車したバスは線路沿いには進まず、東西にのびる地下鉄空港線や筑肥線から離れて街なかを南下します。その区名のとおり福岡市の西部に位置する西区、バスの車窓からは近年に建ったと思われる高層マンションや新しさを感じるきれいな一戸建て住宅が多く目に留まり、天神や博多、さらには福岡空港まで姪浜から地下鉄で一本の好立地による、人気の高いエリアだということが伺えます (・∀・)イイネ。
そんな閑静な住宅街を進むこと25分、大きなショッピングモールをかすめたのちにバスが停まったのは、橋本駅前のロータリーにある停留所 (・ω・)トーチャコ。
バスを降りたのは
姪浜と同じ福岡市西区内に所在する
福岡市地下鉄七隈線の橋本。
当駅は日本最西端に位置する地下鉄駅です。
(*・`o´・*)ホ─
ちなみに最南端は同線の梅林。
(最北端は栄町、最東端は新さっぽろ
いずれも札幌市営地下鉄の駅。)
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 橋本
姪浜と同じ福岡市西区内に所在する
福岡市地下鉄七隈線の橋本。
当駅は日本最西端に位置する地下鉄駅です。
(*・`o´・*)ホ─
ちなみに最南端は同線の梅林。
(最北端は栄町、最東端は新さっぽろ
いずれも札幌市営地下鉄の駅。)
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 橋本
姪浜駅南口0845-(西鉄バス)-橋本駅0908
“橋本(はしもと)”という駅名を聞くと (゚ー゚*)ハシモトカンナ、関東の人ならJR横浜線と相模線、京王相模原線が発着する神奈川県相模原市の駅を、関西の人ならJR和歌山線と南海高野線が発着する和歌山県橋本市にある駅(もしくは京都府八幡市にある京阪本線の駅)を、それぞれイメージするのではないかと思いますが σ(゚・゚*)ンー…、ここ福岡にある橋本は福岡市地下鉄七隈線(ななくません)の駅で当線の西端に位置する起点駅 (・o・*)ホホゥ。
そう、本日の私の目的とする路線はこの地下鉄七隈線です ( ̄▽ ̄)ナナクマ。
先ほど下車した空港線の姪浜は地下鉄でも高架駅でしたが、七隈線は全線の全駅が地下にあり、地上からエスカレーターを下ってホームへおりると、そこにはちょっと小柄なかわいい電車が発車を待っていました (゚∀゚)オッ!。
“橋本(はしもと)”という駅名を聞くと (゚ー゚*)ハシモトカンナ、関東の人ならJR横浜線と相模線、京王相模原線が発着する神奈川県相模原市の駅を、関西の人ならJR和歌山線と南海高野線が発着する和歌山県橋本市にある駅(もしくは京都府八幡市にある京阪本線の駅)を、それぞれイメージするのではないかと思いますが σ(゚・゚*)ンー…、ここ福岡にある橋本は福岡市地下鉄七隈線(ななくません)の駅で当線の西端に位置する起点駅 (・o・*)ホホゥ。
そう、本日の私の目的とする路線はこの地下鉄七隈線です ( ̄▽ ̄)ナナクマ。
先ほど下車した空港線の姪浜は地下鉄でも高架駅でしたが、七隈線は全線の全駅が地下にあり、地上からエスカレーターを下ってホームへおりると、そこにはちょっと小柄なかわいい電車が発車を待っていました (゚∀゚)オッ!。
路線のトンネル断面が狭小な七隈線で使用される3000系(および3000A系)は、空港線やJR、西鉄などで使われる一般的な鉄道車両よりも車体規格がひとまわり小さい、いわゆる“ミニ地下鉄”と呼ばれる車両で(鉄輪式リニアモーターの地下鉄車両)、東京の都営大江戸線や大阪の長堀鶴見緑地線などと同様の方式です (o ̄∇ ̄o)ミニ。
実はその小さな車体寸法がゆえ、ラッシュ時における七隈線の激しい混雑が少し前のニュースで話題に取り上げられていたのを目にしたけれど、始発駅となる橋本では車内がすいていました。そのロングシートの一角に私が腰を下ろすと列車はまもなく発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
実はその小さな車体寸法がゆえ、ラッシュ時における七隈線の激しい混雑が少し前のニュースで話題に取り上げられていたのを目にしたけれど、始発駅となる橋本では車内がすいていました。そのロングシートの一角に私が腰を下ろすと列車はまもなく発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
橋本駅に掲げられていた運賃表で見る
福岡市地下鉄の路線図。
(*゚ェ゚)フムフム
真ん中に表記されたオレンジのラインが
先ほど乗った空港線(福岡空港〜姪浜)
右上に伸びるグリーンのラインが
七隈線(橋本〜博多)
そして今旅では訪れなかったけど
左下に伸びるブルーのラインが
箱崎線(中洲川端〜貝塚)です。
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
福岡市地下鉄の路線図。
(*゚ェ゚)フムフム
真ん中に表記されたオレンジのラインが
先ほど乗った空港線(福岡空港〜姪浜)
右上に伸びるグリーンのラインが
七隈線(橋本〜博多)
そして今旅では訪れなかったけど
左下に伸びるブルーのラインが
箱崎線(中洲川端〜貝塚)です。
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
福岡市地下鉄(福岡市交通局)の七隈線は橋本を起点に、梅林(うめばやし)、七隈、別府(べふ)、六本松、薬院(やくいん)、そして天神にほど近い天神南などの各駅を経て、空港線やJRの各線と接する博多区の博多へといたる全長13.6キロ、交通渋滞が慢性化していた同市西南部の西区や早良区、城南区エリアと福岡の中心市街地を結ぶ目的で敷設された地下鉄路線です (・o・*)ホホゥ(上記路線図も参照)。
そんな七隈線は今から18年前の2005年(平成17年)に橋本〜天神南のあいだ(12.0キロ)で初開業し、国内の“旅客鉄道全線完乗”を目標とする私は、その年にさっそく乗りつぶしに訪れて全区間の完乗を果たしましたが ( ̄▽ ̄)ノリテツ、さらなる利便性の向上を目的として当線は天神南から博多への延伸計画が進められ、当該区間は今年(2023年)の3月27日に開通 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 延伸】*:・゚\(゚▽゚*)。できれば私もその延伸開業日に駆けつけたいところでしたが ((o(゙ε゙)o))ウズウズ、さすがに福岡の地は遠くて気軽には行けなかった ヾノ・∀・`)ムリムリ。それでもどうにか年内には乗りつぶしを済ませたいと思い、開業から9ヶ月が経った本日(12/9)にようやくその機会を得ることができました ヽ(゚ω゚*)オマタヘ。3000系の前面で目にした【博多】の行き先表示には感慨深さを覚えます (´ω`)シミジミ。
とはいえ、先述したように七隈線は全線(全区間)が地下トンネルを走る地下鉄なので、車窓の景色(?)に面白さはありません (≡ω≡*)マックラ。都心(福岡中心部)方向へ進むにつれてやはり車内が混んできたこともあり、停車する駅を車内放送で確認しながら淡々と乗り進むだけ ...(((o*・ω・)o。
橋本から25分で開業時の終着駅だった天神南に停車し、とりあえずここでいったん降りてみます。
そんな七隈線は今から18年前の2005年(平成17年)に橋本〜天神南のあいだ(12.0キロ)で初開業し、国内の“旅客鉄道全線完乗”を目標とする私は、その年にさっそく乗りつぶしに訪れて全区間の完乗を果たしましたが ( ̄▽ ̄)ノリテツ、さらなる利便性の向上を目的として当線は天神南から博多への延伸計画が進められ、当該区間は今年(2023年)の3月27日に開通 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 延伸】*:・゚\(゚▽゚*)。できれば私もその延伸開業日に駆けつけたいところでしたが ((o(゙ε゙)o))ウズウズ、さすがに福岡の地は遠くて気軽には行けなかった ヾノ・∀・`)ムリムリ。それでもどうにか年内には乗りつぶしを済ませたいと思い、開業から9ヶ月が経った本日(12/9)にようやくその機会を得ることができました ヽ(゚ω゚*)オマタヘ。3000系の前面で目にした【博多】の行き先表示には感慨深さを覚えます (´ω`)シミジミ。
とはいえ、先述したように七隈線は全線(全区間)が地下トンネルを走る地下鉄なので、車窓の景色(?)に面白さはありません (≡ω≡*)マックラ。都心(福岡中心部)方向へ進むにつれてやはり車内が混んできたこともあり、停車する駅を車内放送で確認しながら淡々と乗り進むだけ ...(((o*・ω・)o。
橋本から25分で開業時の終着駅だった天神南に停車し、とりあえずここでいったん降りてみます。
福岡市中央区の繁華街
天神地区の一角に所在する天神南。
(*’∀’*)ミナミチャソ
以前は当駅が七隈線の終点でした。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 天神南
駅の構内図を見ると
七隈線の天神南と空港線の天神は
天神地下街でつながっています。
また図の左下のほうには
西鉄天神大牟田線の表記も。
(*゚ェ゚)フムフム
ただし天神南と天神は
同一駅としては扱われず
両駅を使って乗り換えをすると
入場時にあらためて
初乗り料金がかかります
(博多延伸以前は乗継可能駅だった)。
その注意喚起の案内は何となく
某アニメっぽい表記?
(o ̄∇ ̄o)ネルフ?
天神地区の一角に所在する天神南。
(*’∀’*)ミナミチャソ
以前は当駅が七隈線の終点でした。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 天神南
駅の構内図を見ると
七隈線の天神南と空港線の天神は
天神地下街でつながっています。
また図の左下のほうには
西鉄天神大牟田線の表記も。
(*゚ェ゚)フムフム
ただし天神南と天神は
同一駅としては扱われず
両駅を使って乗り換えをすると
入場時にあらためて
初乗り料金がかかります
(博多延伸以前は乗継可能駅だった)。
その注意喚起の案内は何となく
某アニメっぽい表記?
(o ̄∇ ̄o)ネルフ?
天神南は七隈線のみの単独駅ですが、地下街(天神地下街)などを介して同じ福岡市地下鉄の路線である空港線の天神駅とつながっており(改札外)、また西鉄の西鉄福岡(天神)駅もすぐ近くにあります (*゚ェ゚)フムフム。
・・・ということは、今朝の久留米から西鉄で天神に着いたところで七隈線へ乗り換えることも簡単にできたのですが(もしくは薬院で乗り換えることも可能)(´・ω`・)エッ?、私にとって18年前の初開業のとき以来となる七隈線は、せっかくならこの機会に延伸区間(天神南〜博多)だけでなく久しぶりに当線の全線を乗り通そうと思い、そしてそのルートもちょっと工夫してみようと考えて σ(゚・゚*)ンー…、わざわざ(?)姪浜から橋本まで路線バスを使ったものとしてみました (´ω`)ナルヘソ。
ではあらためて、天神南から先の延伸区間へ進みましょう ...(((o*・ω・)o。
・・・ということは、今朝の久留米から西鉄で天神に着いたところで七隈線へ乗り換えることも簡単にできたのですが(もしくは薬院で乗り換えることも可能)(´・ω`・)エッ?、私にとって18年前の初開業のとき以来となる七隈線は、せっかくならこの機会に延伸区間(天神南〜博多)だけでなく久しぶりに当線の全線を乗り通そうと思い、そしてそのルートもちょっと工夫してみようと考えて σ(゚・゚*)ンー…、わざわざ(?)姪浜から橋本まで路線バスを使ったものとしてみました (´ω`)ナルヘソ。
ではあらためて、天神南から先の延伸区間へ進みましょう ...(((o*・ω・)o。
新たに延伸されたのは
天神南〜博多の1.6キロ
二駅間です。
( ̄  ̄)サンプン
天神南から乗る博多ゆきは
お!3000A系だ!
(゚∀゚)オッ!
“A系”は3000系のマイナーチェンジ仕様で
件の博多延伸に合わせて4本が増備された
2021年製の新しい編成です。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 天神南
3000A系のきれいな液晶モニターに
案内された次駅は「櫛田神社前」。
延伸区間に設けられた中間駅の
櫛田神社前。
その駅名となっている櫛田神社は
博多の総鎮守で
夏まつりとして行なわれる
博多祇園山笠の奉納神事が有名です。
( ̄▽ ̄)ヤマガサ
また当駅はキャナルシティ(複合商業施設)の
最寄駅でもあります。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 櫛田神社前
つぎは終点「博多」。
乗り換えの各線が案内されます。
運転席の後ろから前方を眺めてみると
列車は方向別にそれぞれ掘られた
単線シールドトンネルを進むのがわかります。
(*・`o´・*)ホ─
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線
櫛田神社前-博多(前方の車窓から)
天神南〜博多の1.6キロ
二駅間です。
( ̄  ̄)サンプン
天神南から乗る博多ゆきは
お!3000A系だ!
(゚∀゚)オッ!
“A系”は3000系のマイナーチェンジ仕様で
件の博多延伸に合わせて4本が増備された
2021年製の新しい編成です。
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 天神南
3000A系のきれいな液晶モニターに
案内された次駅は「櫛田神社前」。
延伸区間に設けられた中間駅の
櫛田神社前。
その駅名となっている櫛田神社は
博多の総鎮守で
夏まつりとして行なわれる
博多祇園山笠の奉納神事が有名です。
( ̄▽ ̄)ヤマガサ
また当駅はキャナルシティ(複合商業施設)の
最寄駅でもあります。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 櫛田神社前
つぎは終点「博多」。
乗り換えの各線が案内されます。
運転席の後ろから前方を眺めてみると
列車は方向別にそれぞれ掘られた
単線シールドトンネルを進むのがわかります。
(*・`o´・*)ホ─
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線
櫛田神社前-博多(前方の車窓から)
初めて足を踏み入れる新たな区間(延伸区間)だけど (*゚v゚*)ワクワク♪、やはり地下鉄である以上は当然ながら真っ暗な地下トンネルのなかを走ることにこれまでと変わりはありません (≡ω≡*)マックラ。そこで少しでも初乗車の気分を盛り上げようと思い、私は席に座らず立って運転室の後方にかぶりついてみます m(・∀・)m カブリツキ。七隈線の3000系(3000A系)は運転室の背面がほかの一般的な地下鉄車両と比べて開放的な造りとなっており、運転室越しに前方の景色(トンネル内部)が眺めやすい (・∀・)イイネ。
途中に当該区間で唯一の中間駅として設けられた櫛田神社前(くしだじんじゃまえ)に停車し、天神南からの1.6キロを3分ほどで走り抜けた列車はやがて終点となる博多に到着しました (・ω・)トーチャコ。
途中に当該区間で唯一の中間駅として設けられた櫛田神社前(くしだじんじゃまえ)に停車し、天神南からの1.6キロを3分ほどで走り抜けた列車はやがて終点となる博多に到着しました (・ω・)トーチャコ。
ダブルクロスポイント(分岐器)を
慎重に渡って
島式ホームの一面二線である
博多の構内へ進入。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線
櫛田神社前-博多(前方の車窓から)
博多に終着した七隈線。
(・ω・)トーチャコ
空港線のホームと通し番号で振られた
七隈線ホームの3、4番線は
地下5階に位置します。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 博多
慎重に渡って
島式ホームの一面二線である
博多の構内へ進入。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線
櫛田神社前-博多(前方の車窓から)
博多に終着した七隈線。
(・ω・)トーチャコ
空港線のホームと通し番号で振られた
七隈線ホームの3、4番線は
地下5階に位置します。
▲23.12.9 福岡市地下鉄七隈線 博多
これにて私は福岡市地下鉄の七隈線を全線完乗 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
車窓に映っていたのはずっとトンネルの壁でしたが、真新しいホームに掲げられた「博多」の駅名標は眩しく輝いて見えて、完乗したことへの達成感と満足感がふつふつと湧き上がります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
これまで天神南を都心側の発着駅としていた七隈線は、個人的にどうしても中途ハンパ感が否めない印象でしたが、博多へ直結したことによりとくに沿線利用者の利便性は格段に向上したことでしょう (・∀・)イイネ。そして当線はさらに博多から福岡空港(国際線ターミナル)への再延伸も構想されているそうで、もしそれが実現したら私はまた乗りに訪れなくてはなりませんね (゚∀゚)アヒャ☆。
車窓に映っていたのはずっとトンネルの壁でしたが、真新しいホームに掲げられた「博多」の駅名標は眩しく輝いて見えて、完乗したことへの達成感と満足感がふつふつと湧き上がります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
これまで天神南を都心側の発着駅としていた七隈線は、個人的にどうしても中途ハンパ感が否めない印象でしたが、博多へ直結したことによりとくに沿線利用者の利便性は格段に向上したことでしょう (・∀・)イイネ。そして当線はさらに博多から福岡空港(国際線ターミナル)への再延伸も構想されているそうで、もしそれが実現したら私はまた乗りに訪れなくてはなりませんね (゚∀゚)アヒャ☆。
地下鉄空港線と七隈線をむすぶ
博多駅構内の連絡通路(地下4階)
その壁面に施されたピクトグラムが
ちょっとSFちっくでカッコいい!
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
案内に従って歩き進むと
七隈線ホームから150メートルほどで
空港線のホーム(地下3階の1、2番線)へ
行くことができました。
(゚∀゚)オッ!
▲23.12.9 福岡市地下鉄空港線 博多
そして改札を抜けて地上へ出れば
そこはJRの博多駅前(博多口)。
新幹線やJR各線との乗り換えも
スムーズです。
(・∀・)イイネ
▲23.12.9 福岡市地下鉄 博多
博多駅構内の連絡通路(地下4階)
その壁面に施されたピクトグラムが
ちょっとSFちっくでカッコいい!
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
案内に従って歩き進むと
七隈線ホームから150メートルほどで
空港線のホーム(地下3階の1、2番線)へ
行くことができました。
(゚∀゚)オッ!
▲23.12.9 福岡市地下鉄空港線 博多
そして改札を抜けて地上へ出れば
そこはJRの博多駅前(博多口)。
新幹線やJR各線との乗り換えも
スムーズです。
(・∀・)イイネ
▲23.12.9 福岡市地下鉄 博多
橋本0929-(福岡市七隈線)-天神南0954
天神南1024-(七隈線)-博多1028
さて、七隈線を博多まで無事に乗り終えたことで、九州を訪れた今旅の私の目的はおおむね果たせました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
今の時刻はまだ午前の11時前ですが、福岡へ来た時の往路と同様に帰りの復路もLCC(格安航空会社)でなるべく運賃が安めに設定された時間帯の便を選択しており ( ̄∀ ̄;)セコイ、それが福岡空港を出発するのは昼過ぎの13時05分 σ(゚・゚*)ンー…。できればもう少し福岡で遊びたかったところだけど、週末の土曜日に“5,580円という破格値”で成田まで飛べるのであれば、この時間でも文句はいえません (-`ω´-*)ウム(週末の夕方便や夜便は運賃が高めの設定)。まあ、きょうはその飛行機の時間を踏まえて、空港にも近い福岡市内での“七隈線乗車”に充てたため、効率はよかったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。
んじゃ、ちょっと早めのお昼ゴハンを街なかで食べてから、地下鉄で空港へ向かうとしますか カエロ…((((o* ̄-)o。
天神南1024-(七隈線)-博多1028
さて、七隈線を博多まで無事に乗り終えたことで、九州を訪れた今旅の私の目的はおおむね果たせました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
今の時刻はまだ午前の11時前ですが、福岡へ来た時の往路と同様に帰りの復路もLCC(格安航空会社)でなるべく運賃が安めに設定された時間帯の便を選択しており ( ̄∀ ̄;)セコイ、それが福岡空港を出発するのは昼過ぎの13時05分 σ(゚・゚*)ンー…。できればもう少し福岡で遊びたかったところだけど、週末の土曜日に“5,580円という破格値”で成田まで飛べるのであれば、この時間でも文句はいえません (-`ω´-*)ウム(週末の夕方便や夜便は運賃が高めの設定)。まあ、きょうはその飛行機の時間を踏まえて、空港にも近い福岡市内での“七隈線乗車”に充てたため、効率はよかったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。
んじゃ、ちょっと早めのお昼ゴハンを街なかで食べてから、地下鉄で空港へ向かうとしますか カエロ…((((o* ̄-)o。
博多といえば博多ラーメン
・・・といきたいところですが
きのう久留米ラーメンを食べたので
きょうはこれもご当地名物のひとつである
“博多うどん”と“かしわめし”にしてみました。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ
コシの弱いやわらかなうどんは
讃岐うどんなどとはまた違った味わいで
優しさを感じる美味しさです。
ウロン(゚д゚)ウマー!
ちなみに関東人の私はつい何となく
かき揚げをのせた天ぷらうどんにしちゃったけど
博多うどんの鉄板トッピングといえば
“ゴボウ天”を選ぶのがツウなのだとか。
(あとから知ったw)
博多から乗る福岡空港ゆきの
地下鉄空港線は
JR筑肥線から直通してきた
305系でした。
(゚∀゚)オッ!
今旅で何度か乗車した空港線だけど
JR車に当たったのはこの一回だけだったな。
▲23.12.9 福岡市地下鉄 博多
・・・といきたいところですが
きのう久留米ラーメンを食べたので
きょうはこれもご当地名物のひとつである
“博多うどん”と“かしわめし”にしてみました。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ
コシの弱いやわらかなうどんは
讃岐うどんなどとはまた違った味わいで
優しさを感じる美味しさです。
ウロン(゚д゚)ウマー!
ちなみに関東人の私はつい何となく
かき揚げをのせた天ぷらうどんにしちゃったけど
博多うどんの鉄板トッピングといえば
“ゴボウ天”を選ぶのがツウなのだとか。
(あとから知ったw)
博多から乗る福岡空港ゆきの
地下鉄空港線は
JR筑肥線から直通してきた
305系でした。
(゚∀゚)オッ!
今旅で何度か乗車した空港線だけど
JR車に当たったのはこの一回だけだったな。
▲23.12.9 福岡市地下鉄 博多
師走の冬旅・・・というにはあまり寒さを感じずに穏やかな小春日和の晴天のもとで、九州のおもに筑肥地区を巡った三日間 (゚ー゚*)テツタビ。
今や貴重な国鉄型車両の103系(1500番台)を撮影することが目的だった筑肥線では、運用がウマく合えばいいなぁと思っていた“国鉄復刻色の青い編成(E12編成)”と運よく巡り会えて、それを沿線に広がる壮大な海景色で撮れたことは満足度の高いものとなり (^_[◎]oパチリ、また、どちらかというと乗り鉄(乗りつぶし)を主軸とした今旅で、撮り鉄の収穫は筑肥線の103系くらいだろうと思っていたところ、二日目にたまたま鹿児島本線で“銀ガマ”(EF81 303)の牽く貨物列車の情報をキャッチし、好条件で捉えられたのはとてもラッキーなサプライズでした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ひょっとするとこの“銀ガマ”との遭遇が、旅のなかでいちばん嬉しかったことかもしれません (´艸`*)ウレシス。
そして全線完乗を目指す“乗り鉄”としては、二日目に熊本電鉄の菊池線で0.7キロの移設区間、本記事でお伝えした三日目の地下鉄七隈線では1.6キロの延伸区間と、わずかな距離を乗りつぶすために遠方へ再訪しなくてはならないのは、全線完乗をキープする者にとって宿命といえるけど (-`ω´-*)シュクメイ、それはたとえ短い距離でも私には決して小さなものではなく、この旅で熊電の菊池線と七隈線を訪れたことにより、とりあえず(?)現時点で私の国内における未乗の旅客営業路線は無くなりました (+`゚∀´)=b OK牧場!(なお鋼索線は除く・・・^^;)。ちなみに次に目指すのは来春(明けて今春)に控えている北陸新幹線の金沢〜敦賀延伸(と、それに伴って移管される三セク路線)かな σ(゚・゚*)ンー…。
このように私の旅は鉄道趣味ばかりに偏っていて、観光名所や景勝地などはほとんど訪れませんが (。A。)アヒャ☆、そんななかでも唐津のイカ料理や久留米ラーメン、博多うどんなど(そのほか記事に載せなかったモノも)、美味しいご当地の名物料理がいろいろと楽しめて、私なりに九州の魅力を存分に満喫した旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
今や貴重な国鉄型車両の103系(1500番台)を撮影することが目的だった筑肥線では、運用がウマく合えばいいなぁと思っていた“国鉄復刻色の青い編成(E12編成)”と運よく巡り会えて、それを沿線に広がる壮大な海景色で撮れたことは満足度の高いものとなり (^_[◎]oパチリ、また、どちらかというと乗り鉄(乗りつぶし)を主軸とした今旅で、撮り鉄の収穫は筑肥線の103系くらいだろうと思っていたところ、二日目にたまたま鹿児島本線で“銀ガマ”(EF81 303)の牽く貨物列車の情報をキャッチし、好条件で捉えられたのはとてもラッキーなサプライズでした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ひょっとするとこの“銀ガマ”との遭遇が、旅のなかでいちばん嬉しかったことかもしれません (´艸`*)ウレシス。
そして全線完乗を目指す“乗り鉄”としては、二日目に熊本電鉄の菊池線で0.7キロの移設区間、本記事でお伝えした三日目の地下鉄七隈線では1.6キロの延伸区間と、わずかな距離を乗りつぶすために遠方へ再訪しなくてはならないのは、全線完乗をキープする者にとって宿命といえるけど (-`ω´-*)シュクメイ、それはたとえ短い距離でも私には決して小さなものではなく、この旅で熊電の菊池線と七隈線を訪れたことにより、とりあえず(?)現時点で私の国内における未乗の旅客営業路線は無くなりました (+`゚∀´)=b OK牧場!(なお鋼索線は除く・・・^^;)。ちなみに次に目指すのは来春(明けて今春)に控えている北陸新幹線の金沢〜敦賀延伸(と、それに伴って移管される三セク路線)かな σ(゚・゚*)ンー…。
このように私の旅は鉄道趣味ばかりに偏っていて、観光名所や景勝地などはほとんど訪れませんが (。A。)アヒャ☆、そんななかでも唐津のイカ料理や久留米ラーメン、博多うどんなど(そのほか記事に載せなかったモノも)、美味しいご当地の名物料理がいろいろと楽しめて、私なりに九州の魅力を存分に満喫した旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
福岡1305-(ジェットスターGK508)-成田1455
空港第2ビル1532-(京成本線快速1564K)-京成船橋1627…船橋1633-(総武快速1666F)-錦糸町1649~1652-(総武緩行1699B)-御茶ノ水1701~1704-(中央1705H)-三鷹1732
空港第2ビル1532-(京成本線快速1564K)-京成船橋1627…船橋1633-(総武快速1666F)-錦糸町1649~1652-(総武緩行1699B)-御茶ノ水1701~1704-(中央1705H)-三鷹1732
2024-01-11 11:11
熊本電鉄・・・菊池線移設区間 乗車記 [鉄道乗車記]
年をまたいでちょっと間が空きましたが、前回からの続きです (=゚ω゚)ノ゙ヨロシコ。
年末年始の移動で交通機関が混雑する“繁忙期”を避け、比較的旅行者が少ないとされる12月上旬の“閑散期”に、私が休暇を取って“鉄旅”(鉄道旅行)へお出かけしたのは九州の福岡 (o ̄∇ ̄o)キューシュー。
その玄関口となる福岡空港に飛行機で着くとさっそく、空港の地下駅から福岡市地下鉄の空港線に乗ってそのまま西進し、地下鉄と直通運転を行なっているJRの筑肥線(ちくひせん)に向かいます...(((o*・ω・)o。私のお目当ては当線の一部区間(筑前前原以西)で使われている国鉄型車両の103系1500番台 (ー`дー´)ヒャクサン。それを快晴に恵まれた好条件のもと、沿線に広がる玄界灘の海景色にて撮ることができ (^_[◎]oパチリ、また“赤い現行色”(通常仕様)とともに国鉄時代をイメージした“青い復刻色”の編成にも出会えて (゚∀゚)オッ!、とても満足のいく撮影成果が得られました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
撮影後は筑肥線の終点である佐賀県の唐津(からつ)まで乗り通し、旅の初日はそこで宿泊 (゚ー゚*)カラツ。
12月8日(金)
鉄ちゃんの朝は早いもの (*´=ωヾ)オハヨ。
唐津で迎えた旅の二日目、まだ夜明け前で真っ暗な早朝の5時にホテルをチェックアウトして駅へ向かいます。
年末年始の移動で交通機関が混雑する“繁忙期”を避け、比較的旅行者が少ないとされる12月上旬の“閑散期”に、私が休暇を取って“鉄旅”(鉄道旅行)へお出かけしたのは九州の福岡 (o ̄∇ ̄o)キューシュー。
その玄関口となる福岡空港に飛行機で着くとさっそく、空港の地下駅から福岡市地下鉄の空港線に乗ってそのまま西進し、地下鉄と直通運転を行なっているJRの筑肥線(ちくひせん)に向かいます...(((o*・ω・)o。私のお目当ては当線の一部区間(筑前前原以西)で使われている国鉄型車両の103系1500番台 (ー`дー´)ヒャクサン。それを快晴に恵まれた好条件のもと、沿線に広がる玄界灘の海景色にて撮ることができ (^_[◎]oパチリ、また“赤い現行色”(通常仕様)とともに国鉄時代をイメージした“青い復刻色”の編成にも出会えて (゚∀゚)オッ!、とても満足のいく撮影成果が得られました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
撮影後は筑肥線の終点である佐賀県の唐津(からつ)まで乗り通し、旅の初日はそこで宿泊 (゚ー゚*)カラツ。
12月8日(金)
鉄ちゃんの朝は早いもの (*´=ωヾ)オハヨ。
唐津で迎えた旅の二日目、まだ夜明け前で真っ暗な早朝の5時にホテルをチェックアウトして駅へ向かいます。
唐津駅の構内で見かけた
「いい日旅立ちの碑」
と彫られた立派な石碑。
“いい日旅立ち”といえば
国鉄時代の旅行キャンペーンと
そのキャンペーンソングだった
百恵ちゃんの歌が思い浮かぶけど
それとこの碑は何か関係があるのかな?
σ(゚・゚*)ンー…
(ちなみに山口百恵さんの出身地は
唐津ではないようです)
「いい日旅立ちの碑」
と彫られた立派な石碑。
“いい日旅立ち”といえば
国鉄時代の旅行キャンペーンと
そのキャンペーンソングだった
百恵ちゃんの歌が思い浮かぶけど
それとこの碑は何か関係があるのかな?
σ(゚・゚*)ンー…
(ちなみに山口百恵さんの出身地は
唐津ではないようです)
乗務員さんと私のほかは誰もいない閑散とした高架駅のホームにて、カラカラカラ・・・とアイドル音を響かせて佇んでいたのは、どこか哀愁が漂っているように見える古い国鉄型気動車(ディーゼルカー)のキハ47形 ( ̄  ̄*)キハ。
ここ唐津には唐津線と筑肥線の二路線が乗り入れており、これから私が乗るのは唐津線のほう コッチ…((((o* ̄-)o。昨日に乗った筑肥線(の姪浜〜唐津)は直流電化されていて103系や303系などの電車を使用していましたが、大半が非電化の唐津線(筑肥線の列車が直通する西唐津〜唐津のみ電化区間)は、ディーゼルカーで運行されています (・o・*)ホホゥ。
ここ唐津には唐津線と筑肥線の二路線が乗り入れており、これから私が乗るのは唐津線のほう コッチ…((((o* ̄-)o。昨日に乗った筑肥線(の姪浜〜唐津)は直流電化されていて103系や303系などの電車を使用していましたが、大半が非電化の唐津線(筑肥線の列車が直通する西唐津〜唐津のみ電化区間)は、ディーゼルカーで運行されています (・o・*)ホホゥ。
夜明け前の唐津で発車を待つ
唐津線の佐賀ゆき初発列車は
キハ47形の二両編成。
( ̄  ̄*)キハ
ちなみに前面に見える
ヘッドマークのようなものは
何かの記念ではなく
佐賀県の観光をPRする
ラッピングデザインの一環です。
▲23.12.8 唐津線 唐津
唐津線の佐賀ゆき初発列車は
キハ47形の二両編成。
( ̄  ̄*)キハ
ちなみに前面に見える
ヘッドマークのようなものは
何かの記念ではなく
佐賀県の観光をPRする
ラッピングデザインの一環です。
▲23.12.8 唐津線 唐津
本日の初発となる唐津線の上り普通列車(5820D)は定刻の5時15分に唐津を発車。すぐに筑肥線と分かれて進路を南のほうへと取ります ...(((o*・ω・)o。
唐津線は長崎本線と接する佐賀市の久保田から、小城(おぎ)、多久(たく)、厳木(きゅうらぎ)、山本、唐津などを経て、唐津市の西唐津へといたる42.5キロのローカル線(なお今回の私は、唐津から久保田のほうへ向かう上り列車に乗っています)。当線の正式な路線起点は久保田ですが、列車は当駅より長崎本線の上り方面に乗り入れて県都の佐賀を起終点としています (´ω`)ナルヘソ。私が乗ったこの列車も佐賀ゆき ( ̄  ̄*)サガ。
唐津線は長崎本線と接する佐賀市の久保田から、小城(おぎ)、多久(たく)、厳木(きゅうらぎ)、山本、唐津などを経て、唐津市の西唐津へといたる42.5キロのローカル線(なお今回の私は、唐津から久保田のほうへ向かう上り列車に乗っています)。当線の正式な路線起点は久保田ですが、列車は当駅より長崎本線の上り方面に乗り入れて県都の佐賀を起終点としています (´ω`)ナルヘソ。私が乗ったこの列車も佐賀ゆき ( ̄  ̄*)サガ。
外がまだ真っ暗で鏡と化した車窓。
そこに映り込むのは車内の様子で
昔ながらのボックスシートが並びます。
(´ω`)シブイ
唐津を発車した時点での乗客は
私のみの一人でしたが
山本や多久など途中の駅から
学生さんがいっぱい乗ってきました。
個人的に唐津線の沿線で
パッと思い浮かぶ一駅といえば
“小城羊羹”が名物で知られる小城。
σ(゚・゚*)ヨーカン…
▲23.12.8 唐津線 小城
(車窓から)
そこに映り込むのは車内の様子で
昔ながらのボックスシートが並びます。
(´ω`)シブイ
唐津を発車した時点での乗客は
私のみの一人でしたが
山本や多久など途中の駅から
学生さんがいっぱい乗ってきました。
個人的に唐津線の沿線で
パッと思い浮かぶ一駅といえば
“小城羊羹”が名物で知られる小城。
σ(゚・゚*)ヨーカン…
▲23.12.8 唐津線 小城
(車窓から)
佐賀と唐津という県内の二都市をむすぶ唐津線ですが、正直いうと個人的には影の薄い地味な印象の路線でして ( ̄  ̄)ジミコ、私が当線の列車を利用するのは“乗りつぶし”を目的とした初乗車のとき以来これが二度目。およそ30年ぶりのことです (*´∀`)ノ゙オヒサ。そんなめったに乗る機会がない唐津線なのに、いまの車窓は夜明け前で真っ暗け (≡ω≡*)マックラ。景色がほとんど見えないのは、なんだかもったいない気がします σ(・∀・`)ウーン…。
ただ今回の唐津線はあくまでも移動経路のひとつであって(本来、鉄道路線とはそういうものだけどねw)、当線に乗ることがきょうの主目的ではありません (-`ω´-*)ウム。
暗闇に包まれた唐津線を南下したのち、久保田で長崎本線に乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
ただ今回の唐津線はあくまでも移動経路のひとつであって(本来、鉄道路線とはそういうものだけどねw)、当線に乗ることがきょうの主目的ではありません (-`ω´-*)ウム。
暗闇に包まれた唐津線を南下したのち、久保田で長崎本線に乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
久保田からの普通列車は、長崎本線と鹿児島本線を直通する上りの博多ゆき (゚ー゚*)ハカタ。
ちなみに唐津線で終点の佐賀まで行っても、同じ列車(博多ゆき1820M)へと乗り換えることはできますが、平日朝の通勤時間帯に博多方面へ向かう列車は佐賀からの利用者で混むかと思い σ(゚・゚*)ンー…、それより二駅手前に位置する久保田で私は乗り換えました ( ̄∇ ̄)クボタ。たとえ佐賀から乗ったとしても席には余裕で座れるような状況だったけど、久保田でクロスシートの窓側席がキープできたのは乗り鉄にとって大きなアドバンテージです ъ(゚Д゚)ナイス。
この列車で博多へ・・・は行かず、途中の鳥栖(とす)でまた乗り換え ノリカエ…((((o* ̄-)o。そもそも仮に唐津から博多へ向かうのならば、唐津線経由でなく筑肥線の地下鉄直通列車(福岡空港ゆき)に乗ったほうが楽で速くて安い (。A。)アヒャ☆。
ちなみに唐津線で終点の佐賀まで行っても、同じ列車(博多ゆき1820M)へと乗り換えることはできますが、平日朝の通勤時間帯に博多方面へ向かう列車は佐賀からの利用者で混むかと思い σ(゚・゚*)ンー…、それより二駅手前に位置する久保田で私は乗り換えました ( ̄∇ ̄)クボタ。たとえ佐賀から乗ったとしても席には余裕で座れるような状況だったけど、久保田でクロスシートの窓側席がキープできたのは乗り鉄にとって大きなアドバンテージです ъ(゚Д゚)ナイス。
この列車で博多へ・・・は行かず、途中の鳥栖(とす)でまた乗り換え ノリカエ…((((o* ̄-)o。そもそも仮に唐津から博多へ向かうのならば、唐津線経由でなく筑肥線の地下鉄直通列車(福岡空港ゆき)に乗ったほうが楽で速くて安い (。A。)アヒャ☆。
鳥栖で乗り換えた
鹿児島本線の普通列車も
811系でした。
だいぶ明るくなりましたね。
▲23.12.8 鹿児島本線 鳥栖
筑後川を渡りながら
車窓越しに見上げる旅の空は
ほんのりと朝焼け。
(´ω`)シミジミ
▲23.12.8 鹿児島本線 肥前旭-久留米
(車窓から)
鹿児島本線の普通列車も
811系でした。
だいぶ明るくなりましたね。
▲23.12.8 鹿児島本線 鳥栖
筑後川を渡りながら
車窓越しに見上げる旅の空は
ほんのりと朝焼け。
(´ω`)シミジミ
▲23.12.8 鹿児島本線 肥前旭-久留米
(車窓から)
鳥栖から今度は鹿児島本線の荒尾(あらお)ゆき下り普通列車に乗って南下します...(((o*・ω・)o。
九州の日の出は東京より40分くらい遅く、とくに冬場はなかなか明るくならないものですが、7時過ぎに発車した久留米のあたりでようやく東の空に太陽が顔を出しました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。昨日に続き今日の天気も快晴のようで嬉しい (´▽`*)イイテンキ♪。
九州の日の出は東京より40分くらい遅く、とくに冬場はなかなか明るくならないものですが、7時過ぎに発車した久留米のあたりでようやく東の空に太陽が顔を出しました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。昨日に続き今日の天気も快晴のようで嬉しい (´▽`*)イイテンキ♪。
福岡県の南西端に位置する大牟田市の大牟田(おおむた)で、鹿児島本線をさらに下る八代(やつしろ)ゆき普通列車へ乗り継ぐと、次駅(荒尾)とのあいだで県境を越えて熊本県に入ります |フクオカ|…((((o* ̄-)o|クマモト|。そうすると今日の目的地はその県都の熊本でしょうか? σ(゚ー゚*)クマモン?
しかし、私が車窓へと入り込む日差しの状況(光線状態)を確認しつつ、おもむろに列車を降りたのは大野下(おおのしも)という小駅。
しかし、私が車窓へと入り込む日差しの状況(光線状態)を確認しつつ、おもむろに列車を降りたのは大野下(おおのしも)という小駅。
唐津0515-(唐津5820D)-久保田0612~0622-(長崎1820M)-鳥栖0654~0701-(鹿児島1321M)-大牟田0738~0754-(5327M)-大野下0809
駅のまわりに田畑が広がり、のどかな雰囲気が漂う大野下 (´ー`)マターリ。
実は当初の旅程だと、ここで下車する予定はなかった駅なのですが (´・ω`・)エッ?、移動中にスマホで“趣味的な運行情報”を同好者のSNSなどでチェックしていたところ []o(・_・*)ドレドレ、“ちょっと気になる列車”の目撃情報が目に留まりました (゚∀゚)オッ!。しかも当該の列車は現在、鹿児島本線を博多のほうから熊本方面へと下ってきており、奇遇にも(?)私が乗っていた普通列車(5327M)の30分後くらいを追いかける形で続行している模様 (*・`o´・*)ホ─。これはまるで図ったかのように絶妙なタイミングじゃないですか (☆∀☆)キラーン☆。
そこで、朝方の今の時間帯に鹿児島本線の下り列車が良好な光線状態で狙える、大野下駅近くの撮影ポイントに立ち寄ってみようと思い、急きょ当駅で途中下車をしたのでした (´ω`)ナルヘソ。
駅のまわりに田畑が広がり、のどかな雰囲気が漂う大野下 (´ー`)マターリ。
実は当初の旅程だと、ここで下車する予定はなかった駅なのですが (´・ω`・)エッ?、移動中にスマホで“趣味的な運行情報”を同好者のSNSなどでチェックしていたところ []o(・_・*)ドレドレ、“ちょっと気になる列車”の目撃情報が目に留まりました (゚∀゚)オッ!。しかも当該の列車は現在、鹿児島本線を博多のほうから熊本方面へと下ってきており、奇遇にも(?)私が乗っていた普通列車(5327M)の30分後くらいを追いかける形で続行している模様 (*・`o´・*)ホ─。これはまるで図ったかのように絶妙なタイミングじゃないですか (☆∀☆)キラーン☆。
そこで、朝方の今の時間帯に鹿児島本線の下り列車が良好な光線状態で狙える、大野下駅近くの撮影ポイントに立ち寄ってみようと思い、急きょ当駅で途中下車をしたのでした (´ω`)ナルヘソ。
線路に沿った道路から鹿児島本線の下り列車をスッキリと撮ることができるこの場所は、むかしから多くの撮り鉄に知られるメジャーな撮影ポイントで、私も過去に何度か撮影へ訪れています (・∀・)イイネ。といっても、以前に来たときは寝台特急「はやぶさ」の廃止が迫っていたころ(2009年)なので、もう10年以上も前のことなのか Oo。(´-`)ハヤブサ…。
そのときと当地の環境はほぼ変わっていない印象で、だいたいこのあたり・・・という好みの立ち位置を思い出しながら望遠レンズを装着したカメラを構えると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、やがて直線の先に“お目当ての列車”が見えてきました。
そのときと当地の環境はほぼ変わっていない印象で、だいたいこのあたり・・・という好みの立ち位置を思い出しながら望遠レンズを装着したカメラを構えると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、やがて直線の先に“お目当ての列車”が見えてきました。
銀ガマ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
冬の朝の澄んだ空気に轟音を響かせて通過する、コンテナを積載した貨物列車(4093レ)(゚ー゚*)カモレ。
それを威風堂々と牽いていたのは、銀色・・・というか、色が塗られていないステンレス無塗装のメタリックな電気機関車で *.+(0゚・∀・)メタリック+.*、この出で立ちであるEF81形の303号機は全国でわずか一機だけが九州に存在するという、とてもとても貴重なものです w(*゚o゚*)wオオー!(もともと関門トンネルの通過用として全4機が製造されたEF81形300番台のなかで最後に残った現役の一機)。当機は鉄ちゃんからの人気も高く、ファンが親しみを込めて呼ぶ愛称は“銀ガマ” (o ̄∇ ̄o)ギンガマ。
その一機しかない“銀ガマ”はおもに鹿児島本線や日豊本線などで貨物列車の牽引を担っており(JR貨物の所属機)、鉄ちゃんとして九州を訪れたならその動きが気になるところですが σ(゚・゚*)ンー…、私が唐津から次の目的地へと移動しているそのすぐあとをたまたま、当機の牽引する貨物列車が続行で追いかけてきているとは、なんとラッキーなサプライズ w( ̄▽ ̄*)wワオッ!。しかも晴天順光という好条件の舞台も整って、列車を主体とする“編成写真”を撮るのがあまり得意ではない私は、カメラのシャッターを押す指が震えるほどの高い緊張を感じましたが ((((;゚∀゚))))ブルルッ!。どうにか無難に仕留めることができたでしょうか【◎】]ω・´)パチッ!。
機関車のすぐ後ろ(次位)の貨車にコンテナの積載が無いのはやや惜しいものの σ(・∀・`)ウーン、本線で運用に就く“銀様”のお姿を拝めただけでも東京から遠路やってきた私にはありがたいこと 人≡∀≡*)アリガタヤ アリガタヤ。日に照らされて輝く前面に対し、車体側面の反射がほんのりと空色なのもまた粋じゃないですか 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。旅程の途中で立ち寄った“行きがけの駄賃”にしては、もらいすぎるくらいの嬉しい“お小遣い”となりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
それにしても、きのうの筑肥線の“青い復刻色”(103系1500番台・E12編成)といい、きょうの“銀ガマ”といい、事前には運用が掴みづらい“レアな車両”とウマく出会えるなんて、今旅の私はなんだか“鉄運”がツイている気がします (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
冬の朝の澄んだ空気に轟音を響かせて通過する、コンテナを積載した貨物列車(4093レ)(゚ー゚*)カモレ。
それを威風堂々と牽いていたのは、銀色・・・というか、色が塗られていないステンレス無塗装のメタリックな電気機関車で *.+(0゚・∀・)メタリック+.*、この出で立ちであるEF81形の303号機は全国でわずか一機だけが九州に存在するという、とてもとても貴重なものです w(*゚o゚*)wオオー!(もともと関門トンネルの通過用として全4機が製造されたEF81形300番台のなかで最後に残った現役の一機)。当機は鉄ちゃんからの人気も高く、ファンが親しみを込めて呼ぶ愛称は“銀ガマ” (o ̄∇ ̄o)ギンガマ。
その一機しかない“銀ガマ”はおもに鹿児島本線や日豊本線などで貨物列車の牽引を担っており(JR貨物の所属機)、鉄ちゃんとして九州を訪れたならその動きが気になるところですが σ(゚・゚*)ンー…、私が唐津から次の目的地へと移動しているそのすぐあとをたまたま、当機の牽引する貨物列車が続行で追いかけてきているとは、なんとラッキーなサプライズ w( ̄▽ ̄*)wワオッ!。しかも晴天順光という好条件の舞台も整って、列車を主体とする“編成写真”を撮るのがあまり得意ではない私は、カメラのシャッターを押す指が震えるほどの高い緊張を感じましたが ((((;゚∀゚))))ブルルッ!。どうにか無難に仕留めることができたでしょうか【◎】]ω・´)パチッ!。
機関車のすぐ後ろ(次位)の貨車にコンテナの積載が無いのはやや惜しいものの σ(・∀・`)ウーン、本線で運用に就く“銀様”のお姿を拝めただけでも東京から遠路やってきた私にはありがたいこと 人≡∀≡*)アリガタヤ アリガタヤ。日に照らされて輝く前面に対し、車体側面の反射がほんのりと空色なのもまた粋じゃないですか 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。旅程の途中で立ち寄った“行きがけの駄賃”にしては、もらいすぎるくらいの嬉しい“お小遣い”となりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
それにしても、きのうの筑肥線の“青い復刻色”(103系1500番台・E12編成)といい、きょうの“銀ガマ”といい、事前には運用が掴みづらい“レアな車両”とウマく出会えるなんて、今旅の私はなんだか“鉄運”がツイている気がします (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
大野下から乗る下りの熊本ゆきは
黒い顔がクールな印象の817系。
当系のオリジナルは
転換クロスシートだったけど
この編成はロングシート仕様へ
リニューアルされたものでした。
( ̄  ̄)ロング…
▲23.12.8 鹿児島本線 大野下
黒い顔がクールな印象の817系。
当系のオリジナルは
転換クロスシートだったけど
この編成はロングシート仕様へ
リニューアルされたものでした。
( ̄  ̄)ロング…
▲23.12.8 鹿児島本線 大野下
大野下に滞在したのはわずか50分間。そのあいだにお目当ての“銀ガマ貨物”を効率よく捕獲して(4093レの大野下通過は8時半過ぎ)、ふたたび大野下から熊本方面へ向かう鹿児島本線の下り普通列車(5329M)に乗り込みます ...(((o*・ω・)o。なお、寄り道をしたけど、このあとの行程に大きな影響はありません (+`゚∀´)=b OK牧場。
明治時代の西南戦争で激戦地だったとして知られる田原坂(たばるざか)などを経て熊本県内を南下し、私が次に下車したのは熊本・・・のひとつ手前に位置する上熊本(かみくまもと)(゚ー゚*)カミクマ。
明治時代の西南戦争で激戦地だったとして知られる田原坂(たばるざか)などを経て熊本県内を南下し、私が次に下車したのは熊本・・・のひとつ手前に位置する上熊本(かみくまもと)(゚ー゚*)カミクマ。
熊本の隣駅(上り方)で
熊本市西区に所在する上熊本。
(゚ー゚*)カミクマ
格子のようなデザインの駅舎は
九州新幹線の開業と合わせて
当駅付近の鹿児島本線が高架化された際に
大きくリニューアルされたものです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.12.8 鹿児島本線 上熊本
熊本市西区に所在する上熊本。
(゚ー゚*)カミクマ
格子のようなデザインの駅舎は
九州新幹線の開業と合わせて
当駅付近の鹿児島本線が高架化された際に
大きくリニューアルされたものです。
( ̄。 ̄)ヘー
▲23.12.8 鹿児島本線 上熊本
大野下0859-(鹿児島5329M)-上熊本0929
上熊本はここまで私が乗ってきた鹿児島本線のほかに、地方私鉄の熊本電鉄と路面電車の熊本市電(熊本市交通局)がそれぞれ駅や停留場を構えており、そこへ各線の列車や電車が発着します (・o・*)ホホゥ。
上熊本はここまで私が乗ってきた鹿児島本線のほかに、地方私鉄の熊本電鉄と路面電車の熊本市電(熊本市交通局)がそれぞれ駅や停留場を構えており、そこへ各線の列車や電車が発着します (・o・*)ホホゥ。
上熊本駅前停留場で眺める
熊本市電(B系統・上熊本線)の路面電車。
( ̄∇ ̄)チンチンデンシャ
当線は市内中心部の辛島町や熊本城、
さらには水前寺公園などを経て
市内東部(東区)の健軍町へと至ります。
▲23.12.8 熊本市交通局 上熊本停留場
熊本市電(B系統・上熊本線)の路面電車。
( ̄∇ ̄)チンチンデンシャ
当線は市内中心部の辛島町や熊本城、
さらには水前寺公園などを経て
市内東部(東区)の健軍町へと至ります。
▲23.12.8 熊本市交通局 上熊本停留場
それにしても高架化されたJRの駅は立派になったなぁ・・・w(゚o゚*)w オオー!。
私が当駅を利用するのは、九州新幹線の博多と新八代のあいだが開業したときに立ち寄った2011年以来となる12年ぶり。以前はまだ高架化工事の真っ最中で、JRの上熊本駅はプレハブのような仮駅舎でしたっけ ( ̄  ̄)プレハブ。そしてそのときに上熊本へ寄った目的は、当時の熊本電鉄で使われていた元・東急5000系(熊電5000形)を撮影することでした (゚ー゚*)アオガエル。
そして実は今旅でもやはり私がここへ来た目的は熊本電鉄、通称 “熊電” であり、そのユニークな外観の見た目から“青ガエル”の愛称が付けられていた5000形はもうすでに退役していますが(2016年に営業運行を終了)、それとは別の理由があってこの度の再訪となりました (-`ω´-*)ウム。
私が当駅を利用するのは、九州新幹線の博多と新八代のあいだが開業したときに立ち寄った2011年以来となる12年ぶり。以前はまだ高架化工事の真っ最中で、JRの上熊本駅はプレハブのような仮駅舎でしたっけ ( ̄  ̄)プレハブ。そしてそのときに上熊本へ寄った目的は、当時の熊本電鉄で使われていた元・東急5000系(熊電5000形)を撮影することでした (゚ー゚*)アオガエル。
そして実は今旅でもやはり私がここへ来た目的は熊本電鉄、通称 “熊電” であり、そのユニークな外観の見た目から“青ガエル”の愛称が付けられていた5000形はもうすでに退役していますが(2016年に営業運行を終了)、それとは別の理由があってこの度の再訪となりました (-`ω´-*)ウム。
JRの駅とは
ロータリーを挟んだ位置にあり
入口が幹線道路に面した
熊本電鉄の上熊本駅。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
そこに停まっていた電車は・・・
前面に“くまモン”がどーん!
ド━━━━(● ̄(エ) ̄●)━━━━ン!
ちなみに当車はかつて
東京の地下鉄銀座線で使われていた
元・東京メトロ01系です。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
ロータリーを挟んだ位置にあり
入口が幹線道路に面した
熊本電鉄の上熊本駅。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
そこに停まっていた電車は・・・
前面に“くまモン”がどーん!
ド━━━━(● ̄(エ) ̄●)━━━━ン!
ちなみに当車はかつて
東京の地下鉄銀座線で使われていた
元・東京メトロ01系です。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
12年前の訪問時から大きく様変わりしたJRの駅に対して、熊電の駅はほとんど変わっていない印象 σ(゚・゚*)ンー…。しかしホームに停車していたのはかつての“青ガエル”でなく、その引退した5000形のあとを引き継いだ電車で、私が初対面(?)となる銀色車体(アルミ合金製)の01形です (=゚ω゚)ノ゙ヤア。
熊本県の有名なキャラクターである「くまモン」が車両の内外に装飾(ラッピング)されていて、当地にすっかり馴染んでいるように見えるこの電車ですが (● ̄(エ) ̄●)モン、もともと当形は東京で地下鉄の銀座線に使われていた東京メトロの01系で、その“お古”を熊電が譲り受けた、いわゆる“譲渡車両”(中古車両)( ̄▽ ̄)ギンザセソ。銀座線での第一線を退いたあとに、ここ熊本の地でさらなる活躍を続けています (*・`o´・*)ホ─。
熊本県の有名なキャラクターである「くまモン」が車両の内外に装飾(ラッピング)されていて、当地にすっかり馴染んでいるように見えるこの電車ですが (● ̄(エ) ̄●)モン、もともと当形は東京で地下鉄の銀座線に使われていた東京メトロの01系で、その“お古”を熊電が譲り受けた、いわゆる“譲渡車両”(中古車両)( ̄▽ ̄)ギンザセソ。銀座線での第一線を退いたあとに、ここ熊本の地でさらなる活躍を続けています (*・`o´・*)ホ─。
なので、私にとって“熊電の01形”としては初対面だけど、“元・銀座線の01系”としてはお久しぶりの再会 (*´∀`)ノ゙オヒサ。
そういえば銀座線から01系が引退する際(2017年)には譲渡先の熊電をイメージした“くまモンラッピング”が施されて、それを拙ブログの記事にしたときに私は「いつの日か機会を見つけて、熊本に渡った同系を訪ねに行けたらと思っています」と記述しており、それが6年の時を経て実現したことになります (´ω`)シミジミ。ただし、今旅の私が熊電を訪れたいちばんの目的は、01系(形)との再会ではないんです。
とりあえずこの01形の“上熊本線”(菊池線)に上熊本から乗り、私が向かったのは熊電の運行の要衝である北熊本(きたくまもと)(゚ー゚*)キタクマ。そこでさらに“本線”(藤崎線)の藤崎宮前(ふじさきぐうまえ)ゆきに乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
そういえば銀座線から01系が引退する際(2017年)には譲渡先の熊電をイメージした“くまモンラッピング”が施されて、それを拙ブログの記事にしたときに私は「いつの日か機会を見つけて、熊本に渡った同系を訪ねに行けたらと思っています」と記述しており、それが6年の時を経て実現したことになります (´ω`)シミジミ。ただし、今旅の私が熊電を訪れたいちばんの目的は、01系(形)との再会ではないんです。
とりあえずこの01形の“上熊本線”(菊池線)に上熊本から乗り、私が向かったのは熊電の運行の要衝である北熊本(きたくまもと)(゚ー゚*)キタクマ。そこでさらに“本線”(藤崎線)の藤崎宮前(ふじさきぐうまえ)ゆきに乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。
上熊本のホームに掲示されていた
熊本電鉄の路線図。
タテにいくつもの駅名が並ぶ路線のうち
右側の藤崎宮前~御代志が“本線”で
それと北熊本で分岐する形となっている
左側の北熊本〜上熊本が“上熊本線”です。
なおいずれも正式な路線名でなく
便宜的な通称によるもの。
(*゚ェ゚))フムフム
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
熊本電鉄の路線図。
タテにいくつもの駅名が並ぶ路線のうち
右側の藤崎宮前~御代志が“本線”で
それと北熊本で分岐する形となっている
左側の北熊本〜上熊本が“上熊本線”です。
なおいずれも正式な路線名でなく
便宜的な通称によるもの。
(*゚ェ゚))フムフム
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
熊本市の近郊に線路を張る熊本電鉄は、熊本市西区の上熊本を起点に、打越(うちこし)、北熊本、須屋(すや)、黒石(くろいし)などを経て、同県合志市(こうしし)の御代志(みよし)へいたる10.6キロの菊池線と、北熊本を起点に熊本市中央区の藤崎宮前へいたる2.3キロの藤崎線、その二路線を持つ地方私鉄(中小民鉄)(・o・*)ホホゥ。
ただし本来の路線分けと実際の運行形態は異なっており、便宜上は藤崎線の藤崎宮前と菊池線の御代志のあいだを直通でむすぶものを“本線”、上記の路線図だと北熊本で“本線”から分岐するような形となっている菊池線の北熊本と上熊本のあいだを“上熊本線”と称して、それぞれ運行されています ( ̄。 ̄)ヘー。
ちなみに菊池線という線名は、かつて御代志からさらに先の同県菊池市の菊池(きくち)まで当線が伸びていたことを表す名残りで、御代志〜菊池は1986年(昭和61年)に部分廃止となりました (゚ー゚*)ラ・ムー。
ただし本来の路線分けと実際の運行形態は異なっており、便宜上は藤崎線の藤崎宮前と菊池線の御代志のあいだを直通でむすぶものを“本線”、上記の路線図だと北熊本で“本線”から分岐するような形となっている菊池線の北熊本と上熊本のあいだを“上熊本線”と称して、それぞれ運行されています ( ̄。 ̄)ヘー。
ちなみに菊池線という線名は、かつて御代志からさらに先の同県菊池市の菊池(きくち)まで当線が伸びていたことを表す名残りで、御代志〜菊池は1986年(昭和61年)に部分廃止となりました (゚ー゚*)ラ・ムー。
正式には菊池線と藤崎線、
運行上では本線と上熊本線の分岐駅で
熊電の要所である北熊本。
右奥のホームに停まる01形が上熊本線
手前の03形は本線の藤崎宮前ゆきです。
わ、今度はピンクの“くまモン電車”だ。
w( ̄▽ ̄*)w ピンク!
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
北熊本には鉄道事業の本部や
車両基地などが併設されており
構内の留置車両を眺めることができます。
東京メトロから譲渡された3本の編成
元・銀座線の01形(両側)と
元・日比谷線の03形(中央)が
いい感じに並んでいます。
( ̄  ̄*)メトロ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
そして車庫のなかには
退役した5000形の“青ガエルさん”も
その姿を見ることができました。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
保存状態にある当車は
時おりイベントなどで公開されている模様。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
運行上では本線と上熊本線の分岐駅で
熊電の要所である北熊本。
右奥のホームに停まる01形が上熊本線
手前の03形は本線の藤崎宮前ゆきです。
わ、今度はピンクの“くまモン電車”だ。
w( ̄▽ ̄*)w ピンク!
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
北熊本には鉄道事業の本部や
車両基地などが併設されており
構内の留置車両を眺めることができます。
東京メトロから譲渡された3本の編成
元・銀座線の01形(両側)と
元・日比谷線の03形(中央)が
いい感じに並んでいます。
( ̄  ̄*)メトロ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
そして車庫のなかには
退役した5000形の“青ガエルさん”も
その姿を見ることができました。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
保存状態にある当車は
時おりイベントなどで公開されている模様。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
国内の“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私 (-`ω´-*)ウム(今のところ鋼索線は除外してるけど・・・)。
この熊電は廃止となった御代志〜菊池には乗ることができなかったものの、現在の列車が営業運行している区間は菊池線も藤崎線も30年くらい前に全線の完乗を済ませており、さらに完乗したあとも何度か撮影などへ訪れています ...(((o*・ω・)o。
先出の上熊本線ではおもに“青ガエル”がお目当てだったけど、本線のほうも道路上に線路が敷かれた“併用軌道っぽい”ところ(黒髪町〜藤崎宮前の一部)などは、撮影をしていて面白いんですよね (・∀・)イイネ。
この熊電は廃止となった御代志〜菊池には乗ることができなかったものの、現在の列車が営業運行している区間は菊池線も藤崎線も30年くらい前に全線の完乗を済ませており、さらに完乗したあとも何度か撮影などへ訪れています ...(((o*・ω・)o。
先出の上熊本線ではおもに“青ガエル”がお目当てだったけど、本線のほうも道路上に線路が敷かれた“併用軌道っぽい”ところ(黒髪町〜藤崎宮前の一部)などは、撮影をしていて面白いんですよね (・∀・)イイネ。
藤崎線(本線)の
黒髪町〜藤崎宮前のあいだの一部は
わずか200メートル弱の距離ながら
道路にレールが敷かれた
併用軌道っぽい趣きが楽しめます。
(*・`o´・*)ホ─
“ピンクのくまモン電車”となった
元・日比谷線03系の現・03形をパチリ。
何だかいろいろと情報量がカオスな
一枚だなぁ(笑)
(。A。)アヒャ☆
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
黒髪町-藤崎宮前(後追い)
同じく本線で使われている
元・都営三田線の6000系だった
現・6000形。
(゚ー゚*)ミタセソ
95年から01年にかけて譲渡され
熊電での活躍も20年以上になります。
東京では地下を走っていたけど
熊本では道路を(も)走る
(ちょっとの区間だけどね)。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
藤崎宮前-黒髪町
黒髪町〜藤崎宮前のあいだの一部は
わずか200メートル弱の距離ながら
道路にレールが敷かれた
併用軌道っぽい趣きが楽しめます。
(*・`o´・*)ホ─
“ピンクのくまモン電車”となった
元・日比谷線03系の現・03形をパチリ。
何だかいろいろと情報量がカオスな
一枚だなぁ(笑)
(。A。)アヒャ☆
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
黒髪町-藤崎宮前(後追い)
同じく本線で使われている
元・都営三田線の6000系だった
現・6000形。
(゚ー゚*)ミタセソ
95年から01年にかけて譲渡され
熊電での活躍も20年以上になります。
東京では地下を走っていたけど
熊本では道路を(も)走る
(ちょっとの区間だけどね)。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
藤崎宮前-黒髪町
駄菓子菓子(だがしかし)、すでに“完乗済み”だった熊電の各線ですが (´・ω`・)エッ?、昨年(2022年)10月に合志市の御代志地区における土地区画整理事業(いわゆる再開発)に伴い、菊池線(本線)の北端部にあたる熊本高専前(くまもとこうせんまえ)から御代志にかけての二駅間(先の路線図も参照)で、線路や駅を既存の東寄りに数百メートルほど移設するという大掛かりな工事が行なわれました (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…。
線路移設に伴う配置図。
熊本高専前から御代志にかけて
黄色で表した既存線(2022年10月まで)から
赤で表した新線へと切り替えられ、
再春医療センター前と御代志は
駅も移設されています。
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
熊本高専前から御代志にかけて
黄色で表した既存線(2022年10月まで)から
赤で表した新線へと切り替えられ、
再春医療センター前と御代志は
駅も移設されています。
(画像をクリックすると
別ウインドウで拡大表示されます)
その移設幅の大小は個人によって印象が異なると思われますが σ(゚・゚*)ンー…、既存の線路をちょっとずらす程度や地平に敷かれていたものを同地で高架に上げるといったものではなく、今件の場合は新たに線路を別の位置に敷き直して駅は建て替えられ、さらに路線の営業距離にも変更が生じると聞いたら エッ!(゚Д゚≡゚Д゚)マジ!?、これは私のなかでもう一度乗り直すべきものと判断 ( ̄ヘ ̄)ウーン。
そう、ここまでいろいろと引っ張ってきたけど、今旅の二日目に私が唐津から熊本まで移動して熊電を訪れた理由は、この“線路移設区間の再乗車”がいちばんの目的でした (´ω`)ナルヘソ。
そう、ここまでいろいろと引っ張ってきたけど、今旅の二日目に私が唐津から熊本まで移動して熊電を訪れた理由は、この“線路移設区間の再乗車”がいちばんの目的でした (´ω`)ナルヘソ。
こちらの電車は昨年の2022年に
熊電の仲間へ新たに加わった
元・静岡鉄道1000系の現・1000形。
(゚ー゚*)シズテツ
路面電車でなくふつうの電車が
酒屋さんの軒先をかすめてゆきます。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
黒髪町-藤崎宮前
熊電の仲間へ新たに加わった
元・静岡鉄道1000系の現・1000形。
(゚ー゚*)シズテツ
路面電車でなくふつうの電車が
酒屋さんの軒先をかすめてゆきます。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)
黒髪町-藤崎宮前
ただ、せっかく久しぶりに熊電へやってきたのに、目的がそれだけではちょっともったいないので、藤崎線(本線)の名所(?)である準併用軌道区間に立ち寄って列車を何本か撮影 (^_[◎]oパチリ。“くまモンラッピング”がにぎやかな元・日比谷線の03形や、シブさを覚える元・都営地下鉄(東京都交通局)三田線の6000形、そして昨年に静岡鉄道(静鉄)から譲渡された1000形などを一時間程度で効率よく収めたのちに、あらためて本線での起点あつかいとなっている(藤崎線としては終点)藤崎宮前から御代志ゆきの下り列車に乗ります ...(((o*・ω・)o。
駅ビル(?)の奥に存在していて
ちょっと場所がわかりにくい
熊電の藤崎宮前。
<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ
近くにある藤崎八幡宮を
駅名の由来としています。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)藤崎宮前
おや?ここは新静岡?
(゚.゚*)シゾーカ?
・・・ではなく
次の御代志ゆき下り列車は
元・静鉄の1000形。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)藤崎宮前
昨年に“熊電デビュー”となった1000形。
車内の中吊りスペースには
そのデビュー記念のポスターとともに
静鉄時代の写真などが飾られていました。
(゚ー゚*)シズテツ
ちょっと場所がわかりにくい
熊電の藤崎宮前。
<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ
近くにある藤崎八幡宮を
駅名の由来としています。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)藤崎宮前
おや?ここは新静岡?
(゚.゚*)シゾーカ?
・・・ではなく
次の御代志ゆき下り列車は
元・静鉄の1000形。
▲23.12.8 熊本電鉄藤崎線(本線)藤崎宮前
昨年に“熊電デビュー”となった1000形。
車内の中吊りスペースには
そのデビュー記念のポスターとともに
静鉄時代の写真などが飾られていました。
(゚ー゚*)シズテツ
構内の造りはこぢんまりとしているものの、二面一線の頭端式ホームに私鉄のターミナル駅らしい趣きを感じる藤崎宮前 (・∀・)イイネ。
そのホームに当駅始発の御代志ゆき下り列車として停まっていたのは、先ほど沿線で撮影をした元・静鉄1000系の現・1000形で、駅の構造が同じく頭端式ホームのターミナルである静鉄の新静岡や新清水と似たような雰囲気に当形がしっくりとマッチしています (゚ー゚*)シズテツ。
ちなみに静鉄から熊電へ譲渡されたこの1009編成(1009+1509)は、一昨年(2021年)に私が訪れた静鉄の車両基地公開イベントにて展示をされており、これもまたここ熊本の地で再会を果たすこととなりました (*´∀`)ノ゙オヒサ。
そんな1000形の御代志ゆきに乗り込むと、列車はまもなく藤崎宮前を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。件の線路が移設された区間は終点のほうなので、それまではのんびりと車窓風景を眺めながら過ごします。平日11時過ぎの下り列車、二両編成の車内に乗客はまばら (´ー`)マターリ。
そのホームに当駅始発の御代志ゆき下り列車として停まっていたのは、先ほど沿線で撮影をした元・静鉄1000系の現・1000形で、駅の構造が同じく頭端式ホームのターミナルである静鉄の新静岡や新清水と似たような雰囲気に当形がしっくりとマッチしています (゚ー゚*)シズテツ。
ちなみに静鉄から熊電へ譲渡されたこの1009編成(1009+1509)は、一昨年(2021年)に私が訪れた静鉄の車両基地公開イベントにて展示をされており、これもまたここ熊本の地で再会を果たすこととなりました (*´∀`)ノ゙オヒサ。
そんな1000形の御代志ゆきに乗り込むと、列車はまもなく藤崎宮前を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。件の線路が移設された区間は終点のほうなので、それまではのんびりと車窓風景を眺めながら過ごします。平日11時過ぎの下り列車、二両編成の車内に乗客はまばら (´ー`)マターリ。
菊池線、藤崎線とも全区間が単線の熊電。
熊本の市街地に近いあたりでは
住宅のあいだを縫うように進みます。
▲23.12.8 熊電藤崎線 藤崎宮前-黒髪町
(前方の車窓から)
そして例の準併用軌道区間は
ゆっくりと慎重に走ります。
...(((o*・ω・)o
路面電車とはまた違った高さの目線から
車窓に道路を見るのが新鮮で
何となく江ノ電の七里ヶ浜あたりに近い印象。
σ(゚・゚*)エノデソ…
▲23.12.8 熊電藤崎線 藤崎宮前-黒髪町
(車窓から)
熊本の市街地に近いあたりでは
住宅のあいだを縫うように進みます。
▲23.12.8 熊電藤崎線 藤崎宮前-黒髪町
(前方の車窓から)
そして例の準併用軌道区間は
ゆっくりと慎重に走ります。
...(((o*・ω・)o
路面電車とはまた違った高さの目線から
車窓に道路を見るのが新鮮で
何となく江ノ電の七里ヶ浜あたりに近い印象。
σ(゚・゚*)エノデソ…
▲23.12.8 熊電藤崎線 藤崎宮前-黒髪町
(車窓から)
大都市圏の大手私鉄に対して、地方に存在する中小私鉄は“地方私鉄”や“ローカル私鉄” などと呼ばれることもあり、拙ブログでちょくちょくご紹介する千葉県の小湊鐵道のように、車窓から田畑や山々が望めるのどかな雰囲気を思い浮かべてしまうところですが (´ω`)ローカル、中小私鉄でも熊電は熊本市近郊の住宅地を幹線道路と並行するような形で敷かれていて、沿線風景にあまり牧歌的なのどかさは感じられず、ローカル線というよりは都市郊外の私鉄路線って感じ σ(゚・゚*)ンー…。そのような沿線環境なので、今の私が乗っている時間帯の車内はすいているけれど、朝夕の通勤通学には地域のかたが多く利用されることでしょう。
そんな熊電の菊池線に揺られること藤崎宮前からおよそ20分、やがて列車は熊本高専前に停車 ( ̄  ̄*)コーセン。
一面一線の棒線構造という何の変哲もない途中駅ですが、ここより先が“線路移設区間”となるため、おのずと私のテンションは上がります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。マニア丸出しの行動で少々恥ずかしいけど、前方の様子がよく見えるように運転室背後の窓にかぶりついちゃおうっと m(・∀・)m カブリツキ♪。
一面一線の棒線構造という何の変哲もない途中駅ですが、ここより先が“線路移設区間”となるため、おのずと私のテンションは上がります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。マニア丸出しの行動で少々恥ずかしいけど、前方の様子がよく見えるように運転室背後の窓にかぶりついちゃおうっと m(・∀・)m カブリツキ♪。
熊本高専前を出るとすぐ
見るからに新しい線路となり
進行に向かって右のほうへカーブ。
いっぽう旧線は左の道路に並行して
まっすぐ伸びていました。
このあたりがその分岐点。
(*・`o´・*)ホ─
▲23.12.8 熊電菊池線
熊本高専前-再春医療センター前
(車窓から)
線路とともに駅も移設された
再春医療センター前。
なおこの移設によって当駅は
駅名が表す施設に
より近づいた形となりました。
▲23.12.8 熊電菊池線 再春医療センター前
(車窓から)
右手に医療施設の敷地、
左手には広大な更地をみて
列車は単線の線路を進みます。
側窓から(下写真)見ると
以前に旧線が沿っていた道路とは
けっこう離れたなぁ。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲23.12.8 熊電菊池線
再春医療センター前-御代志
(車窓から)
見るからに新しい線路となり
進行に向かって右のほうへカーブ。
いっぽう旧線は左の道路に並行して
まっすぐ伸びていました。
このあたりがその分岐点。
(*・`o´・*)ホ─
▲23.12.8 熊電菊池線
熊本高専前-再春医療センター前
(車窓から)
線路とともに駅も移設された
再春医療センター前。
なおこの移設によって当駅は
駅名が表す施設に
より近づいた形となりました。
▲23.12.8 熊電菊池線 再春医療センター前
(車窓から)
右手に医療施設の敷地、
左手には広大な更地をみて
列車は単線の線路を進みます。
側窓から(下写真)見ると
以前に旧線が沿っていた道路とは
けっこう離れたなぁ。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲23.12.8 熊電菊池線
再春医療センター前-御代志
(車窓から)
御代志ゆき下り列車は熊本高専前を発車するとすぐ、進行に向かって右のほう(東のほう)へとカーブする真新しい線路を進みます ...(((o*・ω・)o。ここで車窓の左側を注視すると、線路や架線柱などはすでに撤去されているものの、移設前の旧線だった跡がわずかに確認できました (*・`o´・*)ホ─。
その線路移設によって旧線と新線のあいだに設けられた、市が進める土地区画整理事業における“更地”の広大さが印象的で、ここは将来的にいくつのも家やマンションが並ぶ住宅地が形成されるのか、それとも大学などの教育施設、もしくは企業の工場などが誘致されるのか、もしくは最近流行り(?)の大型商業施設が建てられるのか、その使い道は知らないけれど (´σд`)シランケド、何にしても次にまた私が何年後かに熊電へ乗ってこの場所を通る機会があるとすれば、その景色は大きく変わっているのでしょうね。
ただ、あくまでも今の段階では何にもない更地を車窓に映しながら、新たに敷き直された移設区間の線路を列車は淡々と進み、熊本高専前から二駅、わずか3分ほどで終点の御代志に到着しました (・ω・)トーチャコ。
その線路移設によって旧線と新線のあいだに設けられた、市が進める土地区画整理事業における“更地”の広大さが印象的で、ここは将来的にいくつのも家やマンションが並ぶ住宅地が形成されるのか、それとも大学などの教育施設、もしくは企業の工場などが誘致されるのか、もしくは最近流行り(?)の大型商業施設が建てられるのか、その使い道は知らないけれど (´σд`)シランケド、何にしても次にまた私が何年後かに熊電へ乗ってこの場所を通る機会があるとすれば、その景色は大きく変わっているのでしょうね。
ただ、あくまでも今の段階では何にもない更地を車窓に映しながら、新たに敷き直された移設区間の線路を列車は淡々と進み、熊本高専前から二駅、わずか3分ほどで終点の御代志に到着しました (・ω・)トーチャコ。
まもなく前方に見えてきたのは
こちらも駅の移設が行われた御代志。
構内は一面一線にとどめた配線ですが
島式ホームとした二線化も
可能そうな印象です。
(・o・*)ホホゥ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 御代志
(前方の車窓から)
1000形の下り列車に
藤崎宮前から乗り通して
菊池線(本線)の終点である
御代志に到着。
(・ω・)トーチャコ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
こちらも駅の移設が行われた御代志。
構内は一面一線にとどめた配線ですが
島式ホームとした二線化も
可能そうな印象です。
(・o・*)ホホゥ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 御代志
(前方の車窓から)
1000形の下り列車に
藤崎宮前から乗り通して
菊池線(本線)の終点である
御代志に到着。
(・ω・)トーチャコ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
上熊本0950-(熊電菊池線)-北熊本0959~1001-(熊電藤崎線)-藤崎宮前1007
藤崎宮前1125-(熊電藤崎・菊池線)-御代志1151
これで私は菊池線の移設区間を乗り直したこととなり、熊本電鉄を(ふたたび)全線完乗です ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
なおこの移設により、これまで道路に沿ってまっすぐの直線だった旧線(既存線)に対して、敷き直された新線は曲線の箇所が多くなっており、そうすると当該区間の距離は伸びたような印象を受けますが σ(゚・゚*)ンー…、実際は終着駅の御代志がこれまでの旧駅よりも少し起点側(南方)に設置されたため、その距離を比べてみると・・・以前は熊本高専前~御代志の二駅間が0.9キロ(上熊本~御代志の総距離では10.8キロ)で、移設後は同駅間が0.7キロ(同総距離10.6キロ) (゚ー゚?)オヨ?。
ありゃま、たいていの場合は乗りつぶしをすると踏破距離は訪れる前より増えるものですが、今回の場合は0.2キロ(200メートル)ほど減っちゃいますた(笑)(。A。)アヒャ☆
藤崎宮前1125-(熊電藤崎・菊池線)-御代志1151
これで私は菊池線の移設区間を乗り直したこととなり、熊本電鉄を(ふたたび)全線完乗です ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
なおこの移設により、これまで道路に沿ってまっすぐの直線だった旧線(既存線)に対して、敷き直された新線は曲線の箇所が多くなっており、そうすると当該区間の距離は伸びたような印象を受けますが σ(゚・゚*)ンー…、実際は終着駅の御代志がこれまでの旧駅よりも少し起点側(南方)に設置されたため、その距離を比べてみると・・・以前は熊本高専前~御代志の二駅間が0.9キロ(上熊本~御代志の総距離では10.8キロ)で、移設後は同駅間が0.7キロ(同総距離10.6キロ) (゚ー゚?)オヨ?。
ありゃま、たいていの場合は乗りつぶしをすると踏破距離は訪れる前より増えるものですが、今回の場合は0.2キロ(200メートル)ほど減っちゃいますた(笑)(。A。)アヒャ☆
合志市に所在する御代志。
(゚ー゚*)ミヨシ
移設によって新たに建てられた駅舎は
シンプルなデザインながら
緑色の三角屋根がいいアクセントです。
(・∀・)イイネ
また、広く取られた駅前ロータリーからは
かつて菊池線が伸びていた
菊池方面などへ路線バスが接続しています。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
ちなみにこちらの写真は
私が以前に訪れたときに撮った
移設前の旧・御代志駅。
(´ω`)ナツカシス
駅舎はなくホームがそのまま
バスロータリーにむき出しのような
ちょっと特徴的な駅でした。
▲02.7 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
(゚ー゚*)ミヨシ
移設によって新たに建てられた駅舎は
シンプルなデザインながら
緑色の三角屋根がいいアクセントです。
(・∀・)イイネ
また、広く取られた駅前ロータリーからは
かつて菊池線が伸びていた
菊池方面などへ路線バスが接続しています。
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
ちなみにこちらの写真は
私が以前に訪れたときに撮った
移設前の旧・御代志駅。
(´ω`)ナツカシス
駅舎はなくホームがそのまま
バスロータリーにむき出しのような
ちょっと特徴的な駅でした。
▲02.7 熊本電鉄菊池線(本線)御代志
200メートル短縮されて0.7キロ、乗車時間はわずか3分 ( ̄  ̄)ミジカイ。それでも“全線完乗”にこだわる私にとってこの距離はとても重要なもので、移設から一年が経過した今もまだ新しさを感じる御代志のホームに降り立つと、乗車距離以上の大きな達成感を覚えました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。たかが0.7キロ、されど0.7キロです (-`ω´-*)ウム。
そして完乗の証(?)として、もちろん駅の外へも出てみたけれど、まだ再開発途中(区画整理中)の当駅周辺でこれといった見どころはとくに無さそうだし σ(゚・゚*)ンー…、そもそも元からこのあたりは住宅や医療施設が建つような地域なので私に用事はなく、きれいに整備されたロータリーから建て替わった新しい駅舎を眺めた程度で適当に時間をつぶしたのち、次の藤崎宮前ゆき上り列車に乗って御代志をあとにしました モドロ…((((o* ̄-)o。
そして完乗の証(?)として、もちろん駅の外へも出てみたけれど、まだ再開発途中(区画整理中)の当駅周辺でこれといった見どころはとくに無さそうだし σ(゚・゚*)ンー…、そもそも元からこのあたりは住宅や医療施設が建つような地域なので私に用事はなく、きれいに整備されたロータリーから建て替わった新しい駅舎を眺めた程度で適当に時間をつぶしたのち、次の藤崎宮前ゆき上り列車に乗って御代志をあとにしました モドロ…((((o* ̄-)o。
御代志から上り列車で北熊本へ。
元・静鉄と元・日比谷線が並ぶシーンは
当線ならではの面白さです。
(゚∀゚)オッ!
なお熊電では03形が先輩だけど
製造初年では1000形のほうが年上
(1000系1973年、03系1988年)。
( ̄∀ ̄)パイセン
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
北熊本で乗り換えた上熊本線の01形で
上熊本に戻ってきました。
(=゚ω゚)ノ゙タライマ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
元・静鉄と元・日比谷線が並ぶシーンは
当線ならではの面白さです。
(゚∀゚)オッ!
なお熊電では03形が先輩だけど
製造初年では1000形のほうが年上
(1000系1973年、03系1988年)。
( ̄∀ ̄)パイセン
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 北熊本
北熊本で乗り換えた上熊本線の01形で
上熊本に戻ってきました。
(=゚ω゚)ノ゙タライマ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)上熊本
御代志1241-(熊電菊池線)-北熊本1301~1332-(菊池線)-上熊本1341
熊本市の郊外にある中小私鉄、熊本電鉄を訪れた九州旅の二日目(● ̄(エ) ̄●)クマデソ。
その目的は整備事業によって線路が移設された区間の“乗り直し”で、それは一キロに満たないわずかな距離 ( ̄、 ̄*)チョッピリ。路線の新規開業でも延伸開業でもなく“移設”という理由で九州の熊本に残された未乗区間は、全線完乗を目指す私にとってモヤモヤを感じるものでしたが (≡"≡;*)モヤモヤ…、それが晴れて今はとても爽快な気分です (*´v`*)スッキリ。
また、“青ガエル”の5000形が現役だったとき以来となる、12年ぶりの熊電は車両の顔ぶれが変わり(元・三田線の6000形は以前もいたけど)、元・銀座線の01形や元・日比谷線の03形、元・静鉄の1000形など、ちょっと言いかたは悪いけど “各地から寄せ集められた中古電車たち” との再会も楽しめました (*´∀`)ノ゙オヒサ。
でも実は今日いちばん嬉しかったのは、行きしなにたまたまキャッチすることができた、“銀ガマ”(EF81 303)の貨物列車を好条件で撮れたことだったかな ε-(°ω°*)ギンガマッ!。鉄運降臨(笑)。
せっかく魅力的な名所や名物が満載の熊本県までやってきたのに、阿蘇はおろか熊本の街なか(繁華街)すら行かず、シンボルの熊本城を観光するようなこともなかったけど σ(・∀・`)ウーン…、私としては熊電の“乗り直し”ができただけで満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
熊本市の郊外にある中小私鉄、熊本電鉄を訪れた九州旅の二日目(● ̄(エ) ̄●)クマデソ。
その目的は整備事業によって線路が移設された区間の“乗り直し”で、それは一キロに満たないわずかな距離 ( ̄、 ̄*)チョッピリ。路線の新規開業でも延伸開業でもなく“移設”という理由で九州の熊本に残された未乗区間は、全線完乗を目指す私にとってモヤモヤを感じるものでしたが (≡"≡;*)モヤモヤ…、それが晴れて今はとても爽快な気分です (*´v`*)スッキリ。
また、“青ガエル”の5000形が現役だったとき以来となる、12年ぶりの熊電は車両の顔ぶれが変わり(元・三田線の6000形は以前もいたけど)、元・銀座線の01形や元・日比谷線の03形、元・静鉄の1000形など、ちょっと言いかたは悪いけど “各地から寄せ集められた中古電車たち” との再会も楽しめました (*´∀`)ノ゙オヒサ。
でも実は今日いちばん嬉しかったのは、行きしなにたまたまキャッチすることができた、“銀ガマ”(EF81 303)の貨物列車を好条件で撮れたことだったかな ε-(°ω°*)ギンガマッ!。鉄運降臨(笑)。
せっかく魅力的な名所や名物が満載の熊本県までやってきたのに、阿蘇はおろか熊本の街なか(繁華街)すら行かず、シンボルの熊本城を観光するようなこともなかったけど σ(・∀・`)ウーン…、私としては熊電の“乗り直し”ができただけで満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。
そういえば上熊本線の車窓から
遠くにちょろっとだけ熊本城が望めました。
(゚∀゚)オッ!
熊電の乗り鉄が目的の私には
観光をせずともこれでじゅうぶん?
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)
坪井川公園-打越(車窓から)
上熊本から乗る鹿児島本線は
815系のワンマン列車。
車内は学生さんでけっこう混んでいたけど
次駅の崇城大学前で座席が空きました。
▲23.12.8 鹿児島本線 上熊本
遠くにちょろっとだけ熊本城が望めました。
(゚∀゚)オッ!
熊電の乗り鉄が目的の私には
観光をせずともこれでじゅうぶん?
ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ
▲23.12.8 熊本電鉄菊池線 (上熊本線)
坪井川公園-打越(車窓から)
上熊本から乗る鹿児島本線は
815系のワンマン列車。
車内は学生さんでけっこう混んでいたけど
次駅の崇城大学前で座席が空きました。
▲23.12.8 鹿児島本線 上熊本
さて、熊電の本線と上熊本線を北熊本で乗り継いで(正式には菊池線を二本の列車で乗り通して)上熊本へ戻り、そこから鹿児島本線の上り普通列車で北上します ...(((o*・ω・)o。熊本と福岡の県境付近に位置する荒尾でさらに列車を乗り継ぎ、私がやってきたのは久留米 ( ̄  ̄*)クルメ。
“久留米ラーメン”で知られるこの街を本日の宿泊地としました。
“久留米ラーメン”で知られるこの街を本日の宿泊地としました。
福岡県久留米市の中心駅で
九州新幹線、鹿児島本線、久大本線の
各線が発着する久留米。
( ̄  ̄*)クルメ
新幹線の開業にともなって
2010年に改築された橋上駅舎は
聖堂を思わせるようなデザインに施された
ステンドグラスが印象的です。
(・∀・)イイネ
なお、同市内に所在する
西日本鉄道(西鉄)の西鉄久留米駅は
東方へ2キロほど離れた距離にあります。
▲23.12.8 鹿児島本線 久留米
九州新幹線、鹿児島本線、久大本線の
各線が発着する久留米。
( ̄  ̄*)クルメ
新幹線の開業にともなって
2010年に改築された橋上駅舎は
聖堂を思わせるようなデザインに施された
ステンドグラスが印象的です。
(・∀・)イイネ
なお、同市内に所在する
西日本鉄道(西鉄)の西鉄久留米駅は
東方へ2キロほど離れた距離にあります。
▲23.12.8 鹿児島本線 久留米
上熊本1450-(鹿児島5356M)-大牟田1536~1537-(350M)-久留米1613
久留米の名物といえば
クセが強いくらいにこってりとした
濃厚な豚骨スープの“久留米ラーメン”。
(゚¬゚〃)ジュルリ
とんこつラーメンは関東人の私だと
博多ラーメンのイメージですが
豚骨ラーメンの元祖(発祥)は
久留米ラーメンなのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
一杯飲んだあとのシメに
本場の味をおいしくいただきました。
塩分を控えなきゃならない体質だけど
このこってりスープはやみつきになりそう♪
メンラー(゚д゚)ウマー!
クセが強いくらいにこってりとした
濃厚な豚骨スープの“久留米ラーメン”。
(゚¬゚〃)ジュルリ
とんこつラーメンは関東人の私だと
博多ラーメンのイメージですが
豚骨ラーメンの元祖(発祥)は
久留米ラーメンなのだそうです。
( ̄。 ̄)ヘー
一杯飲んだあとのシメに
本場の味をおいしくいただきました。
塩分を控えなきゃならない体質だけど
このこってりスープはやみつきになりそう♪
メンラー(゚д゚)ウマー!
九州の鉄旅、次回に続きます・・・(● ̄(エ) ̄●)モン
2024-01-04 07:07
宇都宮ライトレール・・・開業初日 乗車記 [鉄道乗車記]
北関東は栃木県の県都、宇都宮市 ウツ(゚ー゚*)ノミヤ。
その市内中心部と郊外の芳賀町(はがまち)にある工業団地をむすび、慢性的な交通渋滞の緩和などが期待される新たな公共交通システムとして、LRT(Light Rail Transit)と呼ばれる“次世代型路面電車方式”の鉄道、「宇都宮ライトレール(宇都宮芳賀ライトレール線)」が今夏に誕生 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 開業】*:・゚\(゚▽゚*)。部分的な延伸などでなく全線を新設した路面電車は、1948年(昭和23年)の富山地鉄伏木線(現在の万葉線高岡軌道線)以来となる、実に75年ぶりだそうです (*・`o´・*)ホ─。
構想から完成まで30年をかけた「宇都宮ライトレール」。私も鉄ちゃんとしてそのような計画があることは知っていたものの、ぶっちゃけ宇都宮にさほど馴染みのない私が当地の“LRT”を何となく意識し始めたのは、まだ着工前にあたる今から10年くらい前のことで ( ̄▽ ̄)エルアールテー?、当時の宇都宮にお住まいだった(単身赴任していた)ブログ仲間さんと会って市内をクルマで案内していただいた際(駅東公園のゴナナを見に行ったのよね)にLRTの話題となり、多くのクルマが行き交う駅前通りを眺めながら「ホントに出来るんすかね〜。ここを路面電車が走るなんて、なんだか夢物語だなぁ」などと半信半疑だったものです ( ´_ゝ`)フーン(hanamura師匠、お元気かしら)。
そんな宇都宮のLRTはホントに2018年から建設が着手され (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…、およそ5年かけて14.6キロの全線を敷設 ε-(´o`A フゥ…。まさに夢が現実となり、正式な路線名を「宇都宮芳賀ライトレール線」として今年(2023年)8月26日に開業のときを迎えました w(*゚o゚*)wオオーッ!。もうね、10年前に疑ったことを謝りたい気分ですよ ゴメンネ(人∀`o)ゴメンネ〜。
JRや私鉄など国内における“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私にとって、路面電車ももちろん例外でなく(今のところ鋼索線は除外してるけど・・・)、新たな路線ができたのならば、それをいち早く乗りつぶしたいところ (-`ω´-*)ウム。そこでさっそく「ライトレール」が開業する初日に宇都宮へと向かうこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
8月26日(土)
記録的な真夏日続きの関東地方 。゚(A′□`;)qアチィィ・・・。きょうも東京は朝からギラギラと太陽が照り付ける晴天で、これから向かう宇都宮も“晴れ時々曇り”の予報 ( ̄  ̄*)ハレ。とはいえ今の時期、とくに北関東では天気の急変による豪雨や雷雨は珍しくなく、たとえ晴天予報でも折り畳み傘の携帯は必須でしょう 个o(・ω・*)カサ。
その市内中心部と郊外の芳賀町(はがまち)にある工業団地をむすび、慢性的な交通渋滞の緩和などが期待される新たな公共交通システムとして、LRT(Light Rail Transit)と呼ばれる“次世代型路面電車方式”の鉄道、「宇都宮ライトレール(宇都宮芳賀ライトレール線)」が今夏に誕生 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 開業】*:・゚\(゚▽゚*)。部分的な延伸などでなく全線を新設した路面電車は、1948年(昭和23年)の富山地鉄伏木線(現在の万葉線高岡軌道線)以来となる、実に75年ぶりだそうです (*・`o´・*)ホ─。
構想から完成まで30年をかけた「宇都宮ライトレール」。私も鉄ちゃんとしてそのような計画があることは知っていたものの、ぶっちゃけ宇都宮にさほど馴染みのない私が当地の“LRT”を何となく意識し始めたのは、まだ着工前にあたる今から10年くらい前のことで ( ̄▽ ̄)エルアールテー?、当時の宇都宮にお住まいだった(単身赴任していた)ブログ仲間さんと会って市内をクルマで案内していただいた際(駅東公園のゴナナを見に行ったのよね)にLRTの話題となり、多くのクルマが行き交う駅前通りを眺めながら「ホントに出来るんすかね〜。ここを路面電車が走るなんて、なんだか夢物語だなぁ」などと半信半疑だったものです ( ´_ゝ`)フーン(hanamura師匠、お元気かしら)。
そんな宇都宮のLRTはホントに2018年から建設が着手され (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…、およそ5年かけて14.6キロの全線を敷設 ε-(´o`A フゥ…。まさに夢が現実となり、正式な路線名を「宇都宮芳賀ライトレール線」として今年(2023年)8月26日に開業のときを迎えました w(*゚o゚*)wオオーッ!。もうね、10年前に疑ったことを謝りたい気分ですよ ゴメンネ(人∀`o)ゴメンネ〜。
JRや私鉄など国内における“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私にとって、路面電車ももちろん例外でなく(今のところ鋼索線は除外してるけど・・・)、新たな路線ができたのならば、それをいち早く乗りつぶしたいところ (-`ω´-*)ウム。そこでさっそく「ライトレール」が開業する初日に宇都宮へと向かうこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
8月26日(土)
記録的な真夏日続きの関東地方 。゚(A′□`;)qアチィィ・・・。きょうも東京は朝からギラギラと太陽が照り付ける晴天で、これから向かう宇都宮も“晴れ時々曇り”の予報 ( ̄  ̄*)ハレ。とはいえ今の時期、とくに北関東では天気の急変による豪雨や雷雨は珍しくなく、たとえ晴天予報でも折り畳み傘の携帯は必須でしょう 个o(・ω・*)カサ。
東京から宇都宮へは東北新幹線なら一時間足らずで行けますが、私が乗るのはいつものごとく在来線の宇都宮線。快速「ラビット」でおよそ二時間弱の鉄旅です ...(((o*・ω・)o。
ちなみに今回も使用する乗車券は、JR全線の普通・快速列車が一日じゅう乗り放題の「青春18きっぷ」(の一回分)。今夏の私が岐阜の恵那(えな)や新潟の糸魚川(いといがわ)を東京から往復するのに活用したことを考えたら、宇都宮までに使うのはちょっともったいない気もするけれど σ(゚・゚*)ンー…、都内にあるウチの最寄駅から宇都宮への普通乗車券(通常運賃)は片道2,310円(往復4,620円)。これは「18きっぷ」一回分換算の2,410円とほぼ同額で、往復すればじゅうぶんにモトがとれます (´艸`*)オトク♪。
6時半に東京を出た快速「ラビット」は宇都宮線を順調に北上し、遅れることなく8時半に宇都宮へ到着 (・ω・)トーチャコ。
東京0641-(東北3620E)-宇都宮0821
ちなみに今回も使用する乗車券は、JR全線の普通・快速列車が一日じゅう乗り放題の「青春18きっぷ」(の一回分)。今夏の私が岐阜の恵那(えな)や新潟の糸魚川(いといがわ)を東京から往復するのに活用したことを考えたら、宇都宮までに使うのはちょっともったいない気もするけれど σ(゚・゚*)ンー…、都内にあるウチの最寄駅から宇都宮への普通乗車券(通常運賃)は片道2,310円(往復4,620円)。これは「18きっぷ」一回分換算の2,410円とほぼ同額で、往復すればじゅうぶんにモトがとれます (´艸`*)オトク♪。
6時半に東京を出た快速「ラビット」は宇都宮線を順調に北上し、遅れることなく8時半に宇都宮へ到着 (・ω・)トーチャコ。
東京0641-(東北3620E)-宇都宮0821
栃木県宇都宮市の中心駅で
当市の玄関といえるJR宇都宮駅には
東北新幹線、宇都宮線(東北本線)、日光線、
さらには烏山線の直通列車が発着。
また当駅から1.5キロほど西方には
東武宇都宮線の東武宇都宮駅も所在します。
▲東北本線 宇都宮
宇都宮に着いたら
まずは餃子像にご挨拶。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
なお繁華街があるこちら側は
駅の西口です。
いっぽう、
近年に駅前の再開発が行なわれた東口。
きょうはコッチのほうが賑わっている?
σ(゚・゚*)ンー…
その理由はもちろん“LRT”。
▲東北本線 宇都宮
当市の玄関といえるJR宇都宮駅には
東北新幹線、宇都宮線(東北本線)、日光線、
さらには烏山線の直通列車が発着。
また当駅から1.5キロほど西方には
東武宇都宮線の東武宇都宮駅も所在します。
▲東北本線 宇都宮
宇都宮に着いたら
まずは餃子像にご挨拶。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
なお繁華街があるこちら側は
駅の西口です。
いっぽう、
近年に駅前の再開発が行なわれた東口。
きょうはコッチのほうが賑わっている?
σ(゚・゚*)ンー…
その理由はもちろん“LRT”。
▲東北本線 宇都宮
個人的に遊びでも仕事でも、これまでに何度か訪れている宇都宮 ( ̄  ̄*)ウツノミヤ。
駅同士が少し離れたJRと東武線を乗り換えるついでに街なかをぶらついたり、冒頭で触れたようにブログ仲間や友人と会ったり、名物の餃子などを食べにきたり、そういえば当地を早朝に通過する寝台特急「カシオペア」が撮りたくて宿泊したこともあったっけ。そのほとんどの場合で私は繁華街側である西口から駅を出ていましたが、きょうの舞台となるのは東口エリアのほう コッチ…((((o* ̄-)o。
そう、件の「ライトレール」はJR宇都宮駅の東側に隣接する形で停留場(路面電車の駅)が設けられているのです (・o・*)ホホゥ。停留場名はそのまま「宇都宮駅東口(停留場)」。
駅同士が少し離れたJRと東武線を乗り換えるついでに街なかをぶらついたり、冒頭で触れたようにブログ仲間や友人と会ったり、名物の餃子などを食べにきたり、そういえば当地を早朝に通過する寝台特急「カシオペア」が撮りたくて宿泊したこともあったっけ。そのほとんどの場合で私は繁華街側である西口から駅を出ていましたが、きょうの舞台となるのは東口エリアのほう コッチ…((((o* ̄-)o。
そう、件の「ライトレール」はJR宇都宮駅の東側に隣接する形で停留場(路面電車の駅)が設けられているのです (・o・*)ホホゥ。停留場名はそのまま「宇都宮駅東口(停留場)」。
ちなみに駅の構内へ掲げられた案内標に沿って停留場のほうへ歩き進むと、目に留まるのは「ライトレール」でなく「ライトライン」の表記 (゚ー゚*)ライトライン。
当線は「宇都宮ライトレール」という鉄道会社(上下分離方式の運送事業者)が運営する、LRT(次世代型路面電車)を使った、「宇都宮芳賀ライトレール線」が正式なものだけど ライトレール?(゚д゚≡゚д゚)ライトライン?、親しみを持って呼びやすい「ライトライン(LIGHT LINE)」の愛称も付けられており、一般的にはこちらの呼称を定着させたい印象が伺えます。
んじゃ、ここからは私(拙ブログ)も「ライトライン」と呼びますか。
当線は「宇都宮ライトレール」という鉄道会社(上下分離方式の運送事業者)が運営する、LRT(次世代型路面電車)を使った、「宇都宮芳賀ライトレール線」が正式なものだけど ライトレール?(゚д゚≡゚д゚)ライトライン?、親しみを持って呼びやすい「ライトライン(LIGHT LINE)」の愛称も付けられており、一般的にはこちらの呼称を定着させたい印象が伺えます。
んじゃ、ここからは私(拙ブログ)も「ライトライン」と呼びますか。
では、その「ライトライン」へさっそく乗ってみましょう!(*゚v゚*)ワクワク♪
・・・と、いいたいところですが (´・ω`・)エッ?、実は開業初日である本日(8/26)は開業式や発車式などの記念式典が午前から昼にかけて行なわれ、また多くの乗車希望者による混乱を避けるため、通常の営業運転を朝の初発電車から開始するのではなく、まずは式典出席者や招待客を乗せた試乗形式のものから走りはじめて、ふつうの一般客が利用できるのは15時以降を予定しているとのこと ヾノ・∀・`)マダマダ。つまり一般運行の“一番列車”は宇都宮駅東口を15時00分発になります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
・・・と、いいたいところですが (´・ω`・)エッ?、実は開業初日である本日(8/26)は開業式や発車式などの記念式典が午前から昼にかけて行なわれ、また多くの乗車希望者による混乱を避けるため、通常の営業運転を朝の初発電車から開始するのではなく、まずは式典出席者や招待客を乗せた試乗形式のものから走りはじめて、ふつうの一般客が利用できるのは15時以降を予定しているとのこと ヾノ・∀・`)マダマダ。つまり一般運行の“一番列車”は宇都宮駅東口を15時00分発になります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
一般運行が15時からだということを私はあらかじめ公式のホームページなどで見て承知しており、それならば何も朝の8時半に宇都宮へ来る必要はなかったように思うかもしれませんが、15時に開始されてそれにすんなりと乗れるわけではなく、乗車するためには事前に朝8時から配布される“乗車整理券”なるものが必要らしい ( ̄  ̄)セーリケン。
徹夜組も出たという15時発の一番列車は到底ムリだけど、16時台か17時台くらいに宇都宮駅東口を発車する列車に乗れたら、日が明るいうちに終点までの車窓風景が楽しめるかな・・・σ(゚・゚*)ンー…。もしも整理券の配布がすでに終了していたり、乗れるのが日暮れ後の列車になったりするようなら、きょうは宇都宮駅周辺で開業日の雰囲気だけを味わって、乗車するのはまた後日でもいいやくらいの心づもりでいましたが、ためしに整理券の配布列へ並んでみたところ、一番列車から一時間後となる16時00分発の整理券を私は難なく手にすることができました (*・∀・)つ[16:00]
(なお整理券が事前配布されたのは15時台と16時台の列車のみで、17時以降は直接列へ並んで定員を区切っての乗車制となった模様)。
徹夜組も出たという15時発の一番列車は到底ムリだけど、16時台か17時台くらいに宇都宮駅東口を発車する列車に乗れたら、日が明るいうちに終点までの車窓風景が楽しめるかな・・・σ(゚・゚*)ンー…。もしも整理券の配布がすでに終了していたり、乗れるのが日暮れ後の列車になったりするようなら、きょうは宇都宮駅周辺で開業日の雰囲気だけを味わって、乗車するのはまた後日でもいいやくらいの心づもりでいましたが、ためしに整理券の配布列へ並んでみたところ、一番列車から一時間後となる16時00分発の整理券を私は難なく手にすることができました (*・∀・)つ[16:00]
(なお整理券が事前配布されたのは15時台と16時台の列車のみで、17時以降は直接列へ並んで定員を区切っての乗車制となった模様)。
無事にゲットできた
運行初日の乗車整理券。
(σ゚∀゚)σゲッツ!
私が乗れるのは宇都宮駅東口を
16時ちょうど発です。
ちなみに“配布終了”の札を見て
いっしゅん焦ったけど
こちらは“発車式”の整理券でした。
ホームで行なわれる発車式は
見られなさそうだな・・・。
(・∀・`)ウーン…
運行初日の乗車整理券。
(σ゚∀゚)σゲッツ!
私が乗れるのは宇都宮駅東口を
16時ちょうど発です。
ちなみに“配布終了”の札を見て
いっしゅん焦ったけど
こちらは“発車式”の整理券でした。
ホームで行なわれる発車式は
見られなさそうだな・・・。
(・∀・`)ウーン…
一番列車ではないものの、開業日に乗車が確約されただけでも嬉しくて安堵の気分 ε-(´∀`*)ホッ。鉄道全線完乗を目指す者として、やはり乗れるものなら初日に乗りつぶしたいよね (-`ω´-*)ウム。
とはいえ、今はまだ9時で、16時まではあと7時間もあります ( ̄  ̄;)ナナジカン…。さてどうしましょうか・・・。
整理券とともに配布されたイベントスケジュールによると今日は一般運行に先がけて、10時から「開業式」、11時10分から「出発式」、そして11時40分から「パレード」が行われる予定となっています (*゚ェ゚)フムフム。このうち開業式は屋内のホールのようなところへ関係者のみが参列して一般の入場はできず、停留場のホームでテープカットなどを行なうであろう出発式は先着300人程度の観覧エリアが設けられているものの整理券の配布はすでに終了 (´д`)アウ…。いっぽうパレードは「ライトライン」が実際に走行する街なかの併用軌道区間(線路が敷かれた道路)の一部である宇都宮駅東口から隣駅の東宿郷(ひがししゅくごう)にかけて催され、これは沿道にいれば誰でも自由に観覧できるようです (゚∀゚)オッ!。
ならば、開業日の記録のひとつとしてこのパレードを撮影しようと思い、駅ナカのカフェで少しばかり時間をつぶしてから、パレードが始まる一時間前の10時過ぎくらいに会場となる駅前通り(鬼怒通り)へ向かってみました ...(((o*・ω・)o。
とはいえ、今はまだ9時で、16時まではあと7時間もあります ( ̄  ̄;)ナナジカン…。さてどうしましょうか・・・。
整理券とともに配布されたイベントスケジュールによると今日は一般運行に先がけて、10時から「開業式」、11時10分から「出発式」、そして11時40分から「パレード」が行われる予定となっています (*゚ェ゚)フムフム。このうち開業式は屋内のホールのようなところへ関係者のみが参列して一般の入場はできず、停留場のホームでテープカットなどを行なうであろう出発式は先着300人程度の観覧エリアが設けられているものの整理券の配布はすでに終了 (´д`)アウ…。いっぽうパレードは「ライトライン」が実際に走行する街なかの併用軌道区間(線路が敷かれた道路)の一部である宇都宮駅東口から隣駅の東宿郷(ひがししゅくごう)にかけて催され、これは沿道にいれば誰でも自由に観覧できるようです (゚∀゚)オッ!。
ならば、開業日の記録のひとつとしてこのパレードを撮影しようと思い、駅ナカのカフェで少しばかり時間をつぶしてから、パレードが始まる一時間前の10時過ぎくらいに会場となる駅前通り(鬼怒通り)へ向かってみました ...(((o*・ω・)o。
照りつける日差しで暑さがキビシいなか (´Д`υ)アツー、沿道にはすでに多くの人が観覧に集まっていましたが、どうにか私もパレードが見やすい前列を確保できて、開始時間までしばらく待機します。
すると、程なくしてそこへ颯爽と現れたのは・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
すると、程なくしてそこへ颯爽と現れたのは・・・(=゚ω゚=*)ンン!?
パレードを待つ観覧者の前に
ひと足早く姿を見せた「ライトライン」。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
鮮やかな黄色い車体もさることながら
キリッとしたツリ目(?)の
ヘッドライト(前部標識灯)も印象的です。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
ひと足早く姿を見せた「ライトライン」。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
鮮やかな黄色い車体もさることながら
キリッとしたツリ目(?)の
ヘッドライト(前部標識灯)も印象的です。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
ライトライン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
パレードの起点となる宇都宮駅東口とは反対のほう(下り方)から、上り線を【回送】の表示でやってきた「ライトライン」こと宇都宮ライトレールのHU300形 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。そのスタイリッシュな黄色いトラムの姿に観覧者から歓声が起こり w(*゚o゚*)wオオー!、実車を見るのはこれが初めての私も思わず興奮しちゃいます (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
いま宇都宮駅東口のほうへ向かったこの電車が発車式やパレードに使われるもので、これは事前の“送り込み回送”といったところ。記念行事に抜擢されたHU300形がトップナンバーのHU301号車なのは納得だけど (・∀・)イイネ、個人的にちょっと期待していた開業記念の装飾など(ヘッドマーク的なステッカーとか)が施されなかったのは少し残念かな σ(・∀・`)ウーン…。
ちなみに車両形式の“HU”は「宇都宮芳賀ライトレール線」がむすぶ芳賀の“H”と宇都宮の“U”を、“300”は3車体連接構造(3両編成)を表しています (´ω`)ナルヘソ。
パレードの起点となる宇都宮駅東口とは反対のほう(下り方)から、上り線を【回送】の表示でやってきた「ライトライン」こと宇都宮ライトレールのHU300形 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。そのスタイリッシュな黄色いトラムの姿に観覧者から歓声が起こり w(*゚o゚*)wオオー!、実車を見るのはこれが初めての私も思わず興奮しちゃいます (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
いま宇都宮駅東口のほうへ向かったこの電車が発車式やパレードに使われるもので、これは事前の“送り込み回送”といったところ。記念行事に抜擢されたHU300形がトップナンバーのHU301号車なのは納得だけど (・∀・)イイネ、個人的にちょっと期待していた開業記念の装飾など(ヘッドマーク的なステッカーとか)が施されなかったのは少し残念かな σ(・∀・`)ウーン…。
ちなみに車両形式の“HU”は「宇都宮芳賀ライトレール線」がむすぶ芳賀の“H”と宇都宮の“U”を、“300”は3車体連接構造(3両編成)を表しています (´ω`)ナルヘソ。
パレードが行なわれる前に
沿道の観覧者へ向けて
パフォーマーの方による
合いの手のレクチャーが行なわれました。
指でライトラインの“L”を表してから
拳を天に突き上げて
「ライトライン・・・ゴー!!」
(/*´∀`)o ゴー♪
沿道の観覧者へ向けて
パフォーマーの方による
合いの手のレクチャーが行なわれました。
指でライトラインの“L”を表してから
拳を天に突き上げて
「ライトライン・・・ゴー!!」
(/*´∀`)o ゴー♪
待ち時間のあいだに、車両の送り込み回送やダンスパフォーマンスのリハーサル、また、合いの手のレクチャー(?)などもあって、意外と退屈せずに過ごすことができました (/*´∀`)o ゴー♪。
そして予定時間どおりに開始された開業記念パレード (*゚v゚*)ワクワク♪。“ジャズのまち”としても知られる宇都宮にちなんで会場に流れた「Sing,Sing,Sing」の音楽にのせて、黄色いフラッグを掲げる旗手や小刻みなダンスをするパフォーマーたちに伴われた「ライトライン」が、真新しい線路の敷かれた大通りを威風堂々と進みゆきます ...(((o*・ω・)o。それを迎える観客のボルテージも最高潮!ヾ((*≧∀≦))ノ゙イェ──イ♪。
(ここでは先日にご紹介した「PICK UP ONE-shot」とは別の写真をお見せしましょう)
そして予定時間どおりに開始された開業記念パレード (*゚v゚*)ワクワク♪。“ジャズのまち”としても知られる宇都宮にちなんで会場に流れた「Sing,Sing,Sing」の音楽にのせて、黄色いフラッグを掲げる旗手や小刻みなダンスをするパフォーマーたちに伴われた「ライトライン」が、真新しい線路の敷かれた大通りを威風堂々と進みゆきます ...(((o*・ω・)o。それを迎える観客のボルテージも最高潮!ヾ((*≧∀≦))ノ゙イェ──イ♪。
(ここでは先日にご紹介した「PICK UP ONE-shot」とは別の写真をお見せしましょう)
パレード、キタ────∵・(゚∀゚)・∵────ッ!!
宇都宮の地に今日から刻まれるLRTの歴史。
その記念すべき一歩を噛み締めるかのように
ゆっくりと行進する記念列車のライトラインが
沿道へ集まった観覧者の声援に応えます。
ライトライン(/*´∀`)o ゴー♪
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
トラムとともにパレードを盛り上げるのは
ライトラインをイメージした
イエロー&ブラックの衣装を纏う
ダンスパフォーマーの方たち。
暑さを感じさせない素敵な笑顔です。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
パレードの行進に続いて
広い交差点(東宿郷交差点)を舞台とした
華麗なダンスパフォーマンスを披露。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
フィニッシュのポーズが決まると
観覧者からは割れんばかりの拍手が
送られました。
パチパチ☆(*゚▽゚ノノ゙パチパチ☆
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
宇都宮の地に今日から刻まれるLRTの歴史。
その記念すべき一歩を噛み締めるかのように
ゆっくりと行進する記念列車のライトラインが
沿道へ集まった観覧者の声援に応えます。
ライトライン(/*´∀`)o ゴー♪
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
トラムとともにパレードを盛り上げるのは
ライトラインをイメージした
イエロー&ブラックの衣装を纏う
ダンスパフォーマーの方たち。
暑さを感じさせない素敵な笑顔です。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
パレードの行進に続いて
広い交差点(東宿郷交差点)を舞台とした
華麗なダンスパフォーマンスを披露。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
フィニッシュのポーズが決まると
観覧者からは割れんばかりの拍手が
送られました。
パチパチ☆(*゚▽゚ノノ゙パチパチ☆
▲宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
「ライトライン」の開業を祝う華やかなムードに包まれた宇都宮の街 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 開業】*:・゚\(゚▽゚*)。私は各地のいろいろな路線で何度か経験があるけれど、新路線の開業初日というのはやっぱりいいものだなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。この日をいちばん待ち望んでいたのはもちろん普段使いされる地元の方だと思いますが、私のような鉄道趣味人にとっても新たな鉄路の誕生は喜ばしくて、開業日は鉄ちゃんにとってお祭りのようなものです ワッショイ♪ヘ(゚ω゚ヘ)(ノ ゚ω゚)ノワッショイ♪。
しかもふつうの路線(一般鉄道)ならば駅のホームで出発式のテープカットが行われるくらいですが、今回はLRTという路面電車であることから道路上の併用軌道をウマく活かして、ストリートパレードやストリートパフォーマンス(ダンスなど)が催されたのもまた楽しいじゃありませんか (・∀・)イイネ!。
私の本来の目的である「ライトライン」への初乗車はこれからだけど、まずはこのパレードが見られただけでも、開業日に宇都宮まで来た価値はあったと思います。今日ならではのいい記録が残せました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
しかもふつうの路線(一般鉄道)ならば駅のホームで出発式のテープカットが行われるくらいですが、今回はLRTという路面電車であることから道路上の併用軌道をウマく活かして、ストリートパレードやストリートパフォーマンス(ダンスなど)が催されたのもまた楽しいじゃありませんか (・∀・)イイネ!。
私の本来の目的である「ライトライン」への初乗車はこれからだけど、まずはこのパレードが見られただけでも、開業日に宇都宮まで来た価値はあったと思います。今日ならではのいい記録が残せました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
パレードのほかにも
宇都宮駅東口の駅前エリアでは
広場やステージなどで
さまざまなイベントが行われています。
(゚∀゚)オッ!
お、ミヤリー。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
宇都宮市の公式ゆるキャラで
サツキ(市の花)の冠をかぶった
妖精だそうです。
お、どーもくん(NHKのキャラ)。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
きょうは栃木のいちごバージョン?
お相撲好きの私が気になったのは
ライトラインの電停前に建立された
こちらの力士像。
江戸時代に人気を博したとされる
下野国・宇都宮出身の力士で
“初代横綱”の明石志賀之助です。
( ̄。 ̄)ヘー
一連の記念式典が終了したあと
宇都宮駅東口電停を発着するようになった
ライトライン。
でもまだ一般客は利用できず、
乗車されるのは招待客のようです。
( ̄- ̄ )マダヨ
ちなみに写真の右奥に見えるのが
JR宇都宮駅のホーム。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
宇都宮駅東口の駅前エリアでは
広場やステージなどで
さまざまなイベントが行われています。
(゚∀゚)オッ!
お、ミヤリー。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
宇都宮市の公式ゆるキャラで
サツキ(市の花)の冠をかぶった
妖精だそうです。
お、どーもくん(NHKのキャラ)。
(=゚ω゚)ノ゙ヤア
きょうは栃木のいちごバージョン?
お相撲好きの私が気になったのは
ライトラインの電停前に建立された
こちらの力士像。
江戸時代に人気を博したとされる
下野国・宇都宮出身の力士で
“初代横綱”の明石志賀之助です。
( ̄。 ̄)ヘー
一連の記念式典が終了したあと
宇都宮駅東口電停を発着するようになった
ライトライン。
でもまだ一般客は利用できず、
乗車されるのは招待客のようです。
( ̄- ̄ )マダヨ
ちなみに写真の右奥に見えるのが
JR宇都宮駅のホーム。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
さて、開業式や発車式、そしてパレードといった一連の記念式典が終わったところで、時刻はまだお昼の12時。「ライトライン」の一般運行が開始されるまであと三時間、私が乗れる16時の列車まではあと四時間もあります ( ̄  ̄;)ヨジカン…。う~ん、どうしよ。
せっかくJRの普通列車が乗り放題の「18きっぷ」を持っているのなら、宇都宮から日光線か烏山線(からすやません)でも往復してくるかな σ(゚・゚*)ンー…・・・なんて考えながら、東口駅前の広場で催されていたLRT開業イベントの出店などを物色していると、不意に背後から肩をたたかれて呼び止められます ビクッ!Σ(゚◇゚;ノ)ノ。驚いて振り返るとそこにいたのは、会うのが数年ぶりという鉄道趣味仲間の友人じゃありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。どうやら彼も「ライトライン」の開業日に朝から一人で駆けつけて、一般運行の開始を待っている身らしい ナカーマ(*・ω・)人(・ω・*)ユキエ(朝7時ごろから並んで15時15分の整理券を確保したそうな。私より気合いが入っているw)。
ごった返すくらいに多くの人出があるなか、たまたまここで会えたのも何かの縁 (-`ω´-*)ウム。しかもお互いに時間を持て余しているとあらば・・・昼飲みできる居酒屋へ向かうのは自然な流れ(?)でしょう(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。。酒と飲み相手がいれば、三時間くらいは簡単に時間が潰せます。こりゃ好都合 ъ(゚Д゚)ナイス。
せっかくJRの普通列車が乗り放題の「18きっぷ」を持っているのなら、宇都宮から日光線か烏山線(からすやません)でも往復してくるかな σ(゚・゚*)ンー…・・・なんて考えながら、東口駅前の広場で催されていたLRT開業イベントの出店などを物色していると、不意に背後から肩をたたかれて呼び止められます ビクッ!Σ(゚◇゚;ノ)ノ。驚いて振り返るとそこにいたのは、会うのが数年ぶりという鉄道趣味仲間の友人じゃありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。どうやら彼も「ライトライン」の開業日に朝から一人で駆けつけて、一般運行の開始を待っている身らしい ナカーマ(*・ω・)人(・ω・*)ユキエ(朝7時ごろから並んで15時15分の整理券を確保したそうな。私より気合いが入っているw)。
ごった返すくらいに多くの人出があるなか、たまたまここで会えたのも何かの縁 (-`ω´-*)ウム。しかもお互いに時間を持て余しているとあらば・・・昼飲みできる居酒屋へ向かうのは自然な流れ(?)でしょう(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。。酒と飲み相手がいれば、三時間くらいは簡単に時間が潰せます。こりゃ好都合 ъ(゚Д゚)ナイス。
LRTの開業と偶然の再会を祝い
“ライトライン色”の麦酒で乾杯っ!
イエーイ♪(〃゚∇゚)ノ凵☆凵ヽ( ̄∇ ̄*)カンパーイ♪
宇都宮餃子をうたう有名店でなく
居酒屋の一品メニューだけど
それでも当地で餃子が食べられるのは
やっぱり嬉しい
(意外と言っちゃなんだけど、
こういうところのがまたウマいのよね)。
ギョーザ(゚д゚)ウマー!
“ライトライン色”の麦酒で乾杯っ!
イエーイ♪(〃゚∇゚)ノ凵☆凵ヽ( ̄∇ ̄*)カンパーイ♪
宇都宮餃子をうたう有名店でなく
居酒屋の一品メニューだけど
それでも当地で餃子が食べられるのは
やっぱり嬉しい
(意外と言っちゃなんだけど、
こういうところのがまたウマいのよね)。
ギョーザ(゚д゚)ウマー!
時間を持て余すどころか話が盛り上がって15時近くまで飲み (~▽~*)ウィッ、先行する友人が乗る15時15分発の列車を駅東口近くの沿道から見送ったのち イッテラ~(=゚∇゚)ノシ、いよいよ私も宇都宮駅東口停留場のホームへ向かいます ...(((o*・ω・)o。
ライトラインこと
宇都宮芳賀ライトレール線の起点である
宇都宮駅東口停留場は
島式ホームの一面二線構造。
ホームの両側を使って列車が発着します。
(・o・*)ホホゥ
なお向かって右の1番線に停車しているのが
友人の乗る15時15分発のライトレール。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
宇都宮芳賀ライトレール線の起点である
宇都宮駅東口停留場は
島式ホームの一面二線構造。
ホームの両側を使って列車が発着します。
(・o・*)ホホゥ
なお向かって右の1番線に停車しているのが
友人の乗る15時15分発のライトレール。
▲宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
ちなみに国内の一般的な路面電車と同様、「ライトライン」の停留場に改札はなく普段はフリーでホームまで立ち入れますが、きょうの今の時間に限っては事前に配布された例の“乗車整理券”の提示が求められました セーリケン(*・∀・)つ[16:00] 。
そしてホーム上で待つことしばし、まもなく私が乗る「ライトライン」が停留場の先で大きくカーブを切って入線してきます (゚∀゚)オッ!。
そしてホーム上で待つことしばし、まもなく私が乗る「ライトライン」が停留場の先で大きくカーブを切って入線してきます (゚∀゚)オッ!。
私の(?)ライトライン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
起点から終点まで全線の所要時間がおよそ48分の「ライトライン」。きょうは宇都宮駅東口発の下り列車と同じく、芳賀・高根沢工業団地(はが・たかねざわこうぎょうだんち)発の上り列車も一般運行は15時からとされているため、時間的におそらくこの到着列車が上りの“一番列車”だったものと思われます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。下車される方々の顔には初乗車を満喫したあとの充実感のようなものが表れていました (´ー`)エガッタ。
その折り返しとなる列車へ私が乗り込むと、鼻で感じたのは車内に漂う独特な新車の匂い ( ̄・・ ̄)クンクン。
起点から終点まで全線の所要時間がおよそ48分の「ライトライン」。きょうは宇都宮駅東口発の下り列車と同じく、芳賀・高根沢工業団地(はが・たかねざわこうぎょうだんち)発の上り列車も一般運行は15時からとされているため、時間的におそらくこの到着列車が上りの“一番列車”だったものと思われます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。下車される方々の顔には初乗車を満喫したあとの充実感のようなものが表れていました (´ー`)エガッタ。
その折り返しとなる列車へ私が乗り込むと、鼻で感じたのは車内に漂う独特な新車の匂い ( ̄・・ ̄)クンクン。
乗る際に車内の扉脇に備えられた
ICカードリーダーの乗車側(下)に
手持ちのICカード(電子乗車券)をタッチ。
(*・∀・)つ[西瓜] ピッ☆
降りるときは降車側(上)にタッチします。
(*゚ェ゚))フムフム
なお、ICカードを使用せず
現金で運賃を支払う場合には
あらかじめ乗車駅ホームの発券機にて
整理券を取る必要があります。
ICカードリーダーの乗車側(下)に
手持ちのICカード(電子乗車券)をタッチ。
(*・∀・)つ[西瓜] ピッ☆
降りるときは降車側(上)にタッチします。
(*゚ェ゚))フムフム
なお、ICカードを使用せず
現金で運賃を支払う場合には
あらかじめ乗車駅ホームの発券機にて
整理券を取る必要があります。
3車体連接構造(3両編成)のHU300形は、一編成の定員が160人で座席の数は50 (・o・*)ホホゥ。配布された乗車整理券は一列車につき120名分だったそうで、定員より少し余裕を持った案内人数ですが、ホームへ入線した「ライトライン」の流麗な外観についうっとりと見惚れてしまった私は ポー…(*゚o゚*)~゚、席の争奪戦に出遅れて座ることができず (; ̄▽ ̄)ア…。まあ、大きな側窓の前に立って初乗車の車窓を眺めるとしますか。
定刻の16時ちょうど、芳賀・高根沢工業団地ゆき下り列車の「ライトライン」は、すーっと滑らかな走り出しで宇都宮駅東口を発車しました ライトライン(/*´∀`)o ゴー♪。
定刻の16時ちょうど、芳賀・高根沢工業団地ゆき下り列車の「ライトライン」は、すーっと滑らかな走り出しで宇都宮駅東口を発車しました ライトライン(/*´∀`)o ゴー♪。
開業イベントで賑わう
駅前広場をかすめて走り出した
ライトライン。
電車に向かって手を振る方も見られます。
ヾ(*´▽`*)ノ゙ワーイ♪
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
あ!ミヤリーもお見送りしてくれてる!
(≧∇≦)ミヤリー!
木の影でまんだーらだけど・・・w
駅東口のロータリー的なところを抜けると
駅前通り(鬼怒通り)の併用軌道を走ります。
...(((o*・ω・)o
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
先ほどダンスパフォーマンスが披露された
東宿郷の交差点を通過。
通常は交通量の多い交差点です。
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
かつて東北本線で使われていた名機の
EF57形電気機関車が静態保存されていて
鉄道好きにはちょっと知られた存在の駅東公園。
( ̄  ̄*)ゴナナ
車窓から公園はほとんど見えないけど
すぐ近くに停留場が設けられました。
陸橋へアプローチする登坂もなんのその。
交差する国道の上を大きく跨ぎます。
w(゚o゚)w オオー!
▲宇都宮芳賀LRT 駅東公園-峰
(車窓から)
駅前広場をかすめて走り出した
ライトライン。
電車に向かって手を振る方も見られます。
ヾ(*´▽`*)ノ゙ワーイ♪
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
あ!ミヤリーもお見送りしてくれてる!
(≧∇≦)ミヤリー!
木の影でまんだーらだけど・・・w
駅東口のロータリー的なところを抜けると
駅前通り(鬼怒通り)の併用軌道を走ります。
...(((o*・ω・)o
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
先ほどダンスパフォーマンスが披露された
東宿郷の交差点を通過。
通常は交通量の多い交差点です。
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮駅東口-東宿郷
(車窓から)
かつて東北本線で使われていた名機の
EF57形電気機関車が静態保存されていて
鉄道好きにはちょっと知られた存在の駅東公園。
( ̄  ̄*)ゴナナ
車窓から公園はほとんど見えないけど
すぐ近くに停留場が設けられました。
陸橋へアプローチする登坂もなんのその。
交差する国道の上を大きく跨ぎます。
w(゚o゚)w オオー!
▲宇都宮芳賀LRT 駅東公園-峰
(車窓から)
めでたくも本日に開業となった宇都宮ライトレールの宇都宮芳賀ライトレール線(ライトライン)は、JR線と接する宇都宮駅東口を起点に、宇都宮市内の陽東3丁目(ようとうさんちょうめ)や平石(ひらいし)、清原地区市民センター前(きよはらちくしみんせんたーまえ)、ゆいの杜中央(ゆいのもりちゅうおう)、芳賀郡芳賀町内の芳賀台(はがだい)、芳賀町工業団地管理センター前(はがまちこうぎょうだんちかんりせんたーまえ)など各地域に細かく設置された停留場を経て、芳賀・高根沢工業団地へといたる、14.5キロ(停留場数19)の軌道路線(路面電車)(・o・*)ホホゥ。
市内中心部から東方の郊外へと伸びるその沿線は、環境のよさそうな住宅地が形成されているほか、学生が通う小中学校や高校、大学などの教育施設、勤め人を多く抱える工業団地(工場や倉庫群)がいくつもあり、新たに敷設された当線は地域住民の移動手段はもとより、通勤通学の足としての活用が大きく期待されています ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。とくに工業団地への通勤客が「ライトライン」を利用することで、慢性的となっている交通渋滞の解消につながるらしい (・д・*)ヘェー。
また当地は古来より鬼怒川の水資源を生かした稲作が盛んな地域でもあり、路線の途中で跨ぐ鬼怒川のあたりでは広大でのどかな田園風景なども車窓から望めるようです (・∀・)イイネ。
市内中心部から東方の郊外へと伸びるその沿線は、環境のよさそうな住宅地が形成されているほか、学生が通う小中学校や高校、大学などの教育施設、勤め人を多く抱える工業団地(工場や倉庫群)がいくつもあり、新たに敷設された当線は地域住民の移動手段はもとより、通勤通学の足としての活用が大きく期待されています ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。とくに工業団地への通勤客が「ライトライン」を利用することで、慢性的となっている交通渋滞の解消につながるらしい (・д・*)ヘェー。
また当地は古来より鬼怒川の水資源を生かした稲作が盛んな地域でもあり、路線の途中で跨ぐ鬼怒川のあたりでは広大でのどかな田園風景なども車窓から望めるようです (・∀・)イイネ。
車窓を眺めていると沿線の各所で
「ライトライン」を歓迎する装飾や
お見送りされる方たちに目が留まります。
こういうのは嬉しいですね。
ヾ(*´▽`*)ノ゙ワーイ♪
自動車販売店の店頭に置かれていたのは、
ライトラインカラーのクルマ!?
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!
「ライトライン」を歓迎する装飾や
お見送りされる方たちに目が留まります。
こういうのは嬉しいですね。
ヾ(*´▽`*)ノ゙ワーイ♪
自動車販売店の店頭に置かれていたのは、
ライトラインカラーのクルマ!?
w( ̄▽ ̄*)wワオッ!
私が乗る「ライトライン」は宇都宮駅東口から続く道路上の併用軌道を走って15分 ...(((o*・ω・)o、やがて大きなショッピングモールのすぐ前に位置する宇都宮大学陽東キャンパス(停留場)に停車し、ここで私の前に座っていた親子(母娘)の二人が席を立ちます (゚ー゚?)オヨ?。
開業の初日、しかも事前に配布された乗車整理券が必要な時間帯の列車なので、私はてっきり乗客のほとんど・・・いや、全員といってもいいくらい、みんながみんな興味本位で終点まで乗り通すものだと勝手に推測していたのですが σ(゚・゚*)ンー…、その親子はまるで「買い物へ行くのにちょっと乗っただけよ (ΦωΦ)フフフ」といったような自然体で利用していたことに、なんだか意表を突かれた感じ (。A。)アヒャ☆。開業日だからといって浮き足たてずに考えればあたりまえのことだけど、この電車に乗っているのは私のようなマニアだけじゃないんだなぁ (^^;)ゞポリポリ。
なんにしてもこれにより、私は都合よく窓側の席に座ることができました。終点まであと30分くらいは乗るハズなので、これはラッキー (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。なお、これまでは進行方向の左側の車窓を見ていましたが、ここからは右側となります (「゚ー゚)ドレドレ。
開業の初日、しかも事前に配布された乗車整理券が必要な時間帯の列車なので、私はてっきり乗客のほとんど・・・いや、全員といってもいいくらい、みんながみんな興味本位で終点まで乗り通すものだと勝手に推測していたのですが σ(゚・゚*)ンー…、その親子はまるで「買い物へ行くのにちょっと乗っただけよ (ΦωΦ)フフフ」といったような自然体で利用していたことに、なんだか意表を突かれた感じ (。A。)アヒャ☆。開業日だからといって浮き足たてずに考えればあたりまえのことだけど、この電車に乗っているのは私のようなマニアだけじゃないんだなぁ (^^;)ゞポリポリ。
なんにしてもこれにより、私は都合よく窓側の席に座ることができました。終点まであと30分くらいは乗るハズなので、これはラッキー (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。なお、これまでは進行方向の左側の車窓を見ていましたが、ここからは右側となります (「゚ー゚)ドレドレ。
郊外の大型商業施設「ベルモール」。
ライトラインの開業により
ここへのお買い物も便利になりそうですね。
オカイモノ♪(*'∀'*)オカイモノ♪
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮大学陽東キャンパス
(車窓から)
宇都宮大学陽東キャンパスで空き、
座ることができたライトラインの座席。
車体の外装にあわせたような配色の
かわいいシートです。
景色が見やすいクロスシート配置なのも嬉しい。
(・∀・)イイネ
(これは終着時に撮影したもの)
道路上の併用軌道でなく
専用軌道上に停留場が設けられた平石は
島式ホーム2面の4線構造で
当駅での折り返しや
将来的な優等列車の運行を想定して
緩急接続が可能なものとしています。
(*・`o´・*)ホ─
(現在の当線は各駅停車の運行のみ)
▲宇都宮芳賀LRT 平石
(車窓から)
また平石停留場の南方には
ライトラインの車両基地や検修・整備施設、
宇都宮ライトレールの本社(右の建物)が所在し
当線の主要な機能が集約されています。
(*゚ェ゚)フムフム
▲宇都宮芳賀LRT 平石-平石中央小学校前
(車窓から)
前半の市街地とは変わり
やがてのどかな田園風景のなかを
専用軌道(ふつうの線路)で走る
ライトライン。
(´ー`)ノドカ
緩やかにカーブしている
上り勾配(坂道)の先は・・・
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
鉄橋でなく近代的なコンクリート橋で
ライトラインは鬼怒川を渡ります。
(゚ー゚*)キヌガワ
大きくて開放的な側窓から望む
晴天の川景色が気持ちいい。
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
橋を渡ったあたりから見えたのは
見覚えのある特徴的な山容。
これって筑波山じゃないですか。
(゚∀゚*)オオッ!
宇都宮からでもこんなにスッキリと
望めるものなんだなぁ。
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
清陵高校前という停留場名のとおり
このあたりには高校や大学、短大などが建ち
(関連校が集約)
さながら“学園都市”といった雰囲気です。
( ̄  ̄*)トアル?
今まではバスを使っていた学生さんも
道路事情に左右されないライトラインは
利用しやすい通学手段になるでしょう。
スイスイ━━━( ̄、 ̄*)=3=3=3━━━ッ。
▲宇都宮芳賀LRT 清陵高校前
(車窓から)
当線でいちばん長い停留所名の
芳賀町工業団地管理センター前。
“はがまちこうぎょうだんちかんりせんたーまえ”
という読み仮名21文字は
駅名(停留場名)の長さランキングでも
けっこう上位にくるのではないでしょうか。
( ゚д゚)ハガマチコウギョウダンチカンリセンターマエ
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀町工業団地管理センター前
(車窓から)
そしてやはりその停留場名が表すとおり、
付近には大きな工場や倉庫などが建ち並びます。
これもまた当線らしい沿線風景のひとつ。
(-`ω´-*)ウム
▲芳賀町工業団地管理センター前-かしの森公園前
(車窓から)
そんな工業団地を貫く産業道路
(併用軌道)の途中には
地形が谷状となっていることから
アップダウンの激しい箇所があり、
およそ60パーミルという急勾配は
数字の上だと旧・信越本線の“碓氷峠”に相当。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
望遠レンズを駆使して圧縮した撮影をすると
面白い画になる撮り鉄スポットで
機会があれば私も撮影に訪れてみたいところです。
▲芳賀町工業団地管理センター前-かしの森公園前
(車窓から)
ライトラインの開業により
ここへのお買い物も便利になりそうですね。
オカイモノ♪(*'∀'*)オカイモノ♪
▲宇都宮芳賀LRT 宇都宮大学陽東キャンパス
(車窓から)
宇都宮大学陽東キャンパスで空き、
座ることができたライトラインの座席。
車体の外装にあわせたような配色の
かわいいシートです。
景色が見やすいクロスシート配置なのも嬉しい。
(・∀・)イイネ
(これは終着時に撮影したもの)
道路上の併用軌道でなく
専用軌道上に停留場が設けられた平石は
島式ホーム2面の4線構造で
当駅での折り返しや
将来的な優等列車の運行を想定して
緩急接続が可能なものとしています。
(*・`o´・*)ホ─
(現在の当線は各駅停車の運行のみ)
▲宇都宮芳賀LRT 平石
(車窓から)
また平石停留場の南方には
ライトラインの車両基地や検修・整備施設、
宇都宮ライトレールの本社(右の建物)が所在し
当線の主要な機能が集約されています。
(*゚ェ゚)フムフム
▲宇都宮芳賀LRT 平石-平石中央小学校前
(車窓から)
前半の市街地とは変わり
やがてのどかな田園風景のなかを
専用軌道(ふつうの線路)で走る
ライトライン。
(´ー`)ノドカ
緩やかにカーブしている
上り勾配(坂道)の先は・・・
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
鉄橋でなく近代的なコンクリート橋で
ライトラインは鬼怒川を渡ります。
(゚ー゚*)キヌガワ
大きくて開放的な側窓から望む
晴天の川景色が気持ちいい。
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
橋を渡ったあたりから見えたのは
見覚えのある特徴的な山容。
これって筑波山じゃないですか。
(゚∀゚*)オオッ!
宇都宮からでもこんなにスッキリと
望めるものなんだなぁ。
▲宇都宮芳賀LRT 平石中央小学校前-飛山城跡
(車窓から)
清陵高校前という停留場名のとおり
このあたりには高校や大学、短大などが建ち
(関連校が集約)
さながら“学園都市”といった雰囲気です。
( ̄  ̄*)トアル?
今まではバスを使っていた学生さんも
道路事情に左右されないライトラインは
利用しやすい通学手段になるでしょう。
スイスイ━━━( ̄、 ̄*)=3=3=3━━━ッ。
▲宇都宮芳賀LRT 清陵高校前
(車窓から)
当線でいちばん長い停留所名の
芳賀町工業団地管理センター前。
“はがまちこうぎょうだんちかんりせんたーまえ”
という読み仮名21文字は
駅名(停留場名)の長さランキングでも
けっこう上位にくるのではないでしょうか。
( ゚д゚)ハガマチコウギョウダンチカンリセンターマエ
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀町工業団地管理センター前
(車窓から)
そしてやはりその停留場名が表すとおり、
付近には大きな工場や倉庫などが建ち並びます。
これもまた当線らしい沿線風景のひとつ。
(-`ω´-*)ウム
▲芳賀町工業団地管理センター前-かしの森公園前
(車窓から)
そんな工業団地を貫く産業道路
(併用軌道)の途中には
地形が谷状となっていることから
アップダウンの激しい箇所があり、
およそ60パーミルという急勾配は
数字の上だと旧・信越本線の“碓氷峠”に相当。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
望遠レンズを駆使して圧縮した撮影をすると
面白い画になる撮り鉄スポットで
機会があれば私も撮影に訪れてみたいところです。
▲芳賀町工業団地管理センター前-かしの森公園前
(車窓から)
宇都宮駅前の賑やかな繁華街から始まり、道沿いに軒を連ねる家々や商店などに生活感が漂う郊外の住宅地を通り抜け、広大な田園風景と鬼怒川の流れにのどかさを感じた先には、自然豊かな環境を活かした学園や球場、公園があり、さらに走りを進めて後半に展開するのは大規模な工業地帯・・・“ネットワーク型コンパクトシティ”なるものを掲げる宇都宮市の街づくりコンセプトをとくに理解しなくとも(あえて触れないw)、さまざまな変化に富んだ沿線風景とその立地に合わせて併用と専用を巧みに振り分けたような「ライトライン」の軌道形態は、車窓から様子を眺めていて飽きることがなく (*・`o´・*)ホ─、全線で48分の乗車時間はあっという間でした (*゚v゚*)タノシイ♪。
最後の見どころ(あくまでも鉄ちゃん的な)として、高低差60パーミルという国内の路面電車で屈指の急勾配となったアップダウンを「ライトライン」の安定した走りでさらっと体感したら (゚∀゚*)オオッ!、下り列車はまもなく終点の芳賀・高根沢工業団地に着きます。
最後の見どころ(あくまでも鉄ちゃん的な)として、高低差60パーミルという国内の路面電車で屈指の急勾配となったアップダウンを「ライトライン」の安定した走りでさらっと体感したら (゚∀゚*)オオッ!、下り列車はまもなく終点の芳賀・高根沢工業団地に着きます。
私が乗った「ライトライン」は
とくに大きな遅れなく
芳賀・高根沢工業団地へ終着。
(・ω・)トーチャコ
運賃は乗車距離によって変動する対距離制で
宇都宮駅東口から当停留場までは
当線の最高額となる400円でした。
乗車の際に使用したICカードを
降車側のリーダーにタッチして下車します。
(*・∀・)つ[西瓜] ピッ☆
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
芳賀郡芳賀町に所在する
芳賀・高根沢工業団地(停留場)。
当停留場も宇都宮駅東口と同様に
島式ホームの一面二線構造で
列車の発着に対応します。
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
とくに大きな遅れなく
芳賀・高根沢工業団地へ終着。
(・ω・)トーチャコ
運賃は乗車距離によって変動する対距離制で
宇都宮駅東口から当停留場までは
当線の最高額となる400円でした。
乗車の際に使用したICカードを
降車側のリーダーにタッチして下車します。
(*・∀・)つ[西瓜] ピッ☆
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
芳賀郡芳賀町に所在する
芳賀・高根沢工業団地(停留場)。
当停留場も宇都宮駅東口と同様に
島式ホームの一面二線構造で
列車の発着に対応します。
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
宇都宮駅東口1600-(宇都宮芳賀LRT)-芳賀・高根沢工業団地1648
これにて私は宇都宮・芳賀ライトレール線の全線を完乗 ヽ(´▽`)ノワーイ♪。その達成感を開業の初日に味わえたことで、いっそうの喜びを覚えます +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
それはさておき、終点である芳賀・高根沢工業団地もまたその停留場名が表すとおり、あまり面白みのない工場地帯(工業団地)の一角にぽつんと設けられた停留場で、周囲をざっと見わたした限りだと工場の施設以外のものは何もないような環境 σ(゚・゚*)ンー…。コンビニすらありません。
私にとって「ライトライン」を乗りつぶせたのなら、もうここにいる理由はとくにないので、乗車整理券を持たずとも列に並べば乗れるという30分後の上り列車(17時30分発)で早々に宇都宮へ戻ることとしました カエロ…((((o* ̄-)o。
これにて私は宇都宮・芳賀ライトレール線の全線を完乗 ヽ(´▽`)ノワーイ♪。その達成感を開業の初日に味わえたことで、いっそうの喜びを覚えます +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
それはさておき、終点である芳賀・高根沢工業団地もまたその停留場名が表すとおり、あまり面白みのない工場地帯(工業団地)の一角にぽつんと設けられた停留場で、周囲をざっと見わたした限りだと工場の施設以外のものは何もないような環境 σ(゚・゚*)ンー…。コンビニすらありません。
私にとって「ライトライン」を乗りつぶせたのなら、もうここにいる理由はとくにないので、乗車整理券を持たずとも列に並べば乗れるという30分後の上り列車(17時30分発)で早々に宇都宮へ戻ることとしました カエロ…((((o* ̄-)o。
今の時間のライトラインは
15分間隔で運行(開業日の特別ダイヤ)。
満員により一本見送るかたちで
30分後の上り列車に振り分けられた私は
ここでも運よく席に座ることができました。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
15分間隔で運行(開業日の特別ダイヤ)。
満員により一本見送るかたちで
30分後の上り列車に振り分けられた私は
ここでも運よく席に座ることができました。
(o ̄∇ ̄o)ラキー♪
▲宇都宮芳賀LRT 芳賀・高根沢工業団地
「LRTなんてホントに出来るの? (¬、¬)アヤシイ…」などと言っていた10年前の半信半疑からするとなんとも調子のいいことですが、私も鉄ちゃんのひとりとして完成と開通を心待ちにしていた宇都宮ライトレールの「宇都宮芳賀ライトレール線」 ((o(´∀`)o))ワクワク。
その開業日に宇都宮を訪れて、大勢集まった市民の方々とともに観覧できた華やかなパレードなど、当日ならではの祝賀ムードによる街の盛り上がりを直に味わい ヾ(*´▽`*)ノ゙バンザーイ♪、きょうから歴史を刻むひとつの鉄道路線(軌道線)の誕生に立ち会えたのは鉄ちゃん冥利に尽きるというものです (´ω`*)シミジミ。
そして初日早々に乗車することも叶い、次世代型といわれるスタイリッシュなトラムの大きなスクリーンみたいな窓から眺めた沿線風景は、街あり、川あり、工場あり(?)と、想像していた以上の変化に富んだ楽しいもので (゚∀゚*)オオッ!、乗車中は常に新鮮さを感じながら終点まで完乗を果たすことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
また、友人と出くわしたのも面白い奇遇で、乗車時間になるまで居酒屋で昼飲みをしていたことは、私がきょうのことを語るうえでのエピソードに欠かせないものとなるでしょう ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
その開業日に宇都宮を訪れて、大勢集まった市民の方々とともに観覧できた華やかなパレードなど、当日ならではの祝賀ムードによる街の盛り上がりを直に味わい ヾ(*´▽`*)ノ゙バンザーイ♪、きょうから歴史を刻むひとつの鉄道路線(軌道線)の誕生に立ち会えたのは鉄ちゃん冥利に尽きるというものです (´ω`*)シミジミ。
そして初日早々に乗車することも叶い、次世代型といわれるスタイリッシュなトラムの大きなスクリーンみたいな窓から眺めた沿線風景は、街あり、川あり、工場あり(?)と、想像していた以上の変化に富んだ楽しいもので (゚∀゚*)オオッ!、乗車中は常に新鮮さを感じながら終点まで完乗を果たすことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
また、友人と出くわしたのも面白い奇遇で、乗車時間になるまで居酒屋で昼飲みをしていたことは、私がきょうのことを語るうえでのエピソードに欠かせないものとなるでしょう ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
なお、今回開業した宇都宮芳賀ライトレール線はお伝えしてきたとおり、宇都宮駅東口を起点として東方へ伸びるものでしたが、将来的には当市の中心街となる宇都宮駅から西側エリアの敷設も計画されているそうです(完成した暁には東西路線が駅を跨いで直結する構想)(*・`o´・*)ホ─。その開業予定は2030年代前半を目指すとのことだけど、今度はいっさい疑うことなく(笑)、そちらの開通も心待ちにしたいと思います ((o(´∀`)o))ワクワク。およそ10年(足らず)なんて、あっという間よね・・・(゚- ゚)10ネソ…。
芳賀・高根沢工業団地1730-(宇都宮芳賀LRT)-宇都宮駅東口1825
宇都宮1900-(東北1641E)-赤羽2034~2038-(埼京2042K)-新宿2052
宇都宮1900-(東北1641E)-赤羽2034~2038-(埼京2042K)-新宿2052
イベント会場などで手に入れた
配布品の数々
(左下の瓶入り水だけ販売品を購入)。
マニアにとってはこういうものも
開業日ならではのいい記念になります。
(・∀・)イイネ
ちなみに地元紙の号外も
駅前などで配られたそうなのですが
私はちょうどその時間帯に飲んでいて
気付かなかったのは失敗でした。
(ノ∀`)アチャー
配布品の数々
(左下の瓶入り水だけ販売品を購入)。
マニアにとってはこういうものも
開業日ならではのいい記念になります。
(・∀・)イイネ
ちなみに地元紙の号外も
駅前などで配られたそうなのですが
私はちょうどその時間帯に飲んでいて
気付かなかったのは失敗でした。
(ノ∀`)アチャー
2023-09-03 16:16
相鉄・東急・・・相鉄・東急新横浜線 乗車記 [鉄道乗車記]
いささか鮮度落ちの話題で恐縮ですが 人( ̄ω ̄;)スマヌ、先月(3月)中旬の18日にはJRの各社をはじめとした多くの鉄道会社にて、この時期恒例の“ダイヤ改正”(ダイヤの見直し)を実施 (゚ー゚*)ダイカイ。
これを機に新路線や新駅の開業、新たな列車や車両の運行開始、またいっぽうで廃止されてしまった駅や役目を終えて退役した車両など、さまざまな出来事がありました (・o・*)ホホゥ。ちなみに先日の拙ブログで取り上げた梅田貨物線の「大阪駅うめきた地下ホーム」も当日より使用が開始されています ( ̄∇ ̄)ウメキタ。
そしてこの日、関東の首都圏近郊で大きな話題を集めていたのが、シン・ヨコハマ・・・もとい、“新横浜” (゚ー゚*)シン・ヨコハマ。
横浜の中心地(繁華街)から少し離れた北東の場所に位置する港北区の新横浜。鉄道における当駅といえば「のぞみ」も停まる東海道新幹線の駅として知られ、ほかにJR横浜線と横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れていますが、そこへ新たに相模鉄道(相鉄)と東急電鉄(東急)の駅も開業し、アクセス路線となる「相鉄新横浜線」と「東急新横浜線」がそれぞれ開通(相鉄は延伸、東急は新規)。また、両線(両社)による相互乗り入れや東急線を介した複数路線の直通運転も開始されました (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。
最近の拙ブログで多用するフレーズで少々クドいのですが、“国内における旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を生涯の目標(?)としている私にとって”(コピペw)、新たに開業した路線はいち早く乗り潰したいところです (-`ω´-*)ウム。そこでさっそく相鉄新横浜線と東急新横浜線の開業初日に乗車目的で訪れてみることとしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
3月18日(土)
これを機に新路線や新駅の開業、新たな列車や車両の運行開始、またいっぽうで廃止されてしまった駅や役目を終えて退役した車両など、さまざまな出来事がありました (・o・*)ホホゥ。ちなみに先日の拙ブログで取り上げた梅田貨物線の「大阪駅うめきた地下ホーム」も当日より使用が開始されています ( ̄∇ ̄)ウメキタ。
そしてこの日、関東の首都圏近郊で大きな話題を集めていたのが、シン・ヨコハマ・・・もとい、“新横浜” (゚ー゚*)シン・ヨコハマ。
横浜の中心地(繁華街)から少し離れた北東の場所に位置する港北区の新横浜。鉄道における当駅といえば「のぞみ」も停まる東海道新幹線の駅として知られ、ほかにJR横浜線と横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れていますが、そこへ新たに相模鉄道(相鉄)と東急電鉄(東急)の駅も開業し、アクセス路線となる「相鉄新横浜線」と「東急新横浜線」がそれぞれ開通(相鉄は延伸、東急は新規)。また、両線(両社)による相互乗り入れや東急線を介した複数路線の直通運転も開始されました (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。
最近の拙ブログで多用するフレーズで少々クドいのですが、“国内における旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を生涯の目標(?)としている私にとって”(コピペw)、新たに開業した路線はいち早く乗り潰したいところです (-`ω´-*)ウム。そこでさっそく相鉄新横浜線と東急新横浜線の開業初日に乗車目的で訪れてみることとしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
3月18日(土)
記念すべき相鉄新横浜線と東急新横浜線の開業日 (*’∀’*)オメ。
この佳き日を晴天で祝いたいところでしたが、今ごろの時期は菜種梅雨というのか、朝からあいにくの雨模様となったなか 、ヽ`┐( ̄  ̄ )アメ、私が山手線に乗ってまずやってきたのは都内の目黒(めぐろ)。
当駅は地上にJR山手線、地下に東急目黒線と東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線の発着ホームが設けられており、東急目黒線と南北線、三田線は相互乗り入れの直通運転を行っています。そしてさらに、その目黒線へ本日より新たに東急新横浜線を介して相鉄線からの直通運転も開始されました (*・`o´・*)ホ─。
この佳き日を晴天で祝いたいところでしたが、今ごろの時期は菜種梅雨というのか、朝からあいにくの雨模様となったなか 、ヽ`┐( ̄  ̄ )アメ、私が山手線に乗ってまずやってきたのは都内の目黒(めぐろ)。
当駅は地上にJR山手線、地下に東急目黒線と東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線の発着ホームが設けられており、東急目黒線と南北線、三田線は相互乗り入れの直通運転を行っています。そしてさらに、その目黒線へ本日より新たに東急新横浜線を介して相鉄線からの直通運転も開始されました (*・`o´・*)ホ─。
目黒駅の運賃表でざっくりと見る
東急電鉄の路線図。
(「゚ー゚)ドレドレ
ちょっと分かりにくいかも知れませんが
(写真をクリックすると拡大表示されます)、
真ん中のあたりを横切る
青いラインが目黒線(目黒〜日吉)、
右上から真ん中のほうへ引かれている
赤いラインが東横線(渋谷〜横浜)
そして両線の日吉で接続する
紫色のラインが東急新横浜線です。
東急電鉄の路線図。
(「゚ー゚)ドレドレ
ちょっと分かりにくいかも知れませんが
(写真をクリックすると拡大表示されます)、
真ん中のあたりを横切る
青いラインが目黒線(目黒〜日吉)、
右上から真ん中のほうへ引かれている
赤いラインが東横線(渋谷〜横浜)
そして両線の日吉で接続する
紫色のラインが東急新横浜線です。
このほど横浜市港北区の日吉(ひよし)と新横浜のあいだに新設された東急新横浜線は、東急沿線から東海道新幹線が発着する新横浜への新たなアクセスルートとして、また新横浜から先の相鉄線へ乗り入れるための連絡線としての役割が大きく、東急では東横線と目黒線の一部に日吉から東急新横浜線(を介して相鉄線方面)へ直通する列車が設定されています ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
すなわち都内のほうから東急新横浜線への直通列車に乗る場合、東横線と目黒線の二つのルートがあり、それならば私は渋谷から東横線を使うほうがホントは便利なのですが σ(゚・゚*)ンー…、個人的に東横線はちょくちょく乗ることが多いのに対し、目黒線は利用機会が少ないため、今回はあえて後者のほうを選んで目黒を出発地としてみました コッチ…((((o* ̄-)o。
すなわち都内のほうから東急新横浜線への直通列車に乗る場合、東横線と目黒線の二つのルートがあり、それならば私は渋谷から東横線を使うほうがホントは便利なのですが σ(゚・゚*)ンー…、個人的に東横線はちょくちょく乗ることが多いのに対し、目黒線は利用機会が少ないため、今回はあえて後者のほうを選んで目黒を出発地としてみました コッチ…((((o* ̄-)o。
そんな目黒線には自社(東急)の車両(3000系、5080系、3020系)のほか、相互乗り入れ(直通運転)を行っている、東京メトロ南北線(9000系)と南北線の先で繋がっている埼玉高速鉄道線(2000系)、都営三田線(6300形、6500形)、そして相鉄線(21000系)という5社の車両が混在して使われており、その形式は実に8車種にも及びます (´∀`)カオス。今ふうに言えば、これぞ直通車両による“電車ガチャ”状態 (o ̄∇ ̄o)ガチャ。
はたして私が目黒から乗る電車はどこの会社の何系が来るのか σ(゚・゚*)ンー…、本日より直通を開始した相鉄の21000系を見てみたいし、最近投入された都営三田線の新型である6500形にも乗ってみたい。東急の車両だとちょっとつまんないかな・・・などと、何が出てくるかわからないガチャガチャを興じるかのごとくホームで待っていると (*゚v゚*)ワクワク♪、まもなく日吉方面へ向かう下り列車がやってきます。
はたして私が目黒から乗る電車はどこの会社の何系が来るのか σ(゚・゚*)ンー…、本日より直通を開始した相鉄の21000系を見てみたいし、最近投入された都営三田線の新型である6500形にも乗ってみたい。東急の車両だとちょっとつまんないかな・・・などと、何が出てくるかわからないガチャガチャを興じるかのごとくホームで待っていると (*゚v゚*)ワクワク♪、まもなく日吉方面へ向かう下り列車がやってきます。
南北線から直通してきた各駅停車の新横浜ゆきは、アルミ製の車体に青緑色の帯が巻かれた東京メトロの9000系(第3次車の9815F)( ̄∀ ̄*)ナソボクセソ。
1991年の南北線初開業(第一期開業)に合わせて90年に第一編成(9801F)が製造された当系は、先に挙げた8種(8形式)のなかだと古いほうの車両で今さら新鮮味はなく、製造時期(増備時期)やリニューアルによる編成別の個体差はあるものの同一形式としての本数も多くて“レア度”は低いため、ガチャの結果で“当たり”を引いたとは言えないところか ( ̄  ̄*)スカ?。もしこの列車へ乗らずにガチャを引き直したら(一本見送ったら)、ひょっとすると次は相鉄の新しい電車が来るかな?・・・なんて、つい考えちゃいます σ(・∀・`)ウーン…。
でも、個人的に東京メトロの車両は嫌いじゃないし、営団地下鉄時代だった南北線の第一期開業(駒込〜赤羽岩淵)からの歴史を知っている私には、【新横浜】の行き先を輝かせた9000系の姿にどこか成長を覚えるような感慨深いものがあります (´ω`)シミジミ。とくに運用などを意識せず、ガチャでたまたま当系を引いたのも何かの縁でしょう (-`ω´-*)ウム。私は次の列車を待たないでこの9000系の新横浜ゆきに乗り、初乗車となる東急新横浜線へのエスコートを任せました。
1991年の南北線初開業(第一期開業)に合わせて90年に第一編成(9801F)が製造された当系は、先に挙げた8種(8形式)のなかだと古いほうの車両で今さら新鮮味はなく、製造時期(増備時期)やリニューアルによる編成別の個体差はあるものの同一形式としての本数も多くて“レア度”は低いため、ガチャの結果で“当たり”を引いたとは言えないところか ( ̄  ̄*)スカ?。もしこの列車へ乗らずにガチャを引き直したら(一本見送ったら)、ひょっとすると次は相鉄の新しい電車が来るかな?・・・なんて、つい考えちゃいます σ(・∀・`)ウーン…。
でも、個人的に東京メトロの車両は嫌いじゃないし、営団地下鉄時代だった南北線の第一期開業(駒込〜赤羽岩淵)からの歴史を知っている私には、【新横浜】の行き先を輝かせた9000系の姿にどこか成長を覚えるような感慨深いものがあります (´ω`)シミジミ。とくに運用などを意識せず、ガチャでたまたま当系を引いたのも何かの縁でしょう (-`ω´-*)ウム。私は次の列車を待たないでこの9000系の新横浜ゆきに乗り、初乗車となる東急新横浜線へのエスコートを任せました。
土曜日の朝7時半の下り列車は適度に空いていて、立ち客はなくロングシートに数人が座っている程度の状況 ( ̄  ̄)ガラガラ。新線の開業日ですが今のところ同業者らしき人(鉄ちゃん)の姿もとくに見あたりません σ(゚・゚*)ンー…。
もっとも、私より気合いの入ったお仲間はもっと早い時間から活動をして、開業の一番列車(初発列車)に乗ったり、記念きっぷや記念グッズなどを求めて列に並んだりしているのではないでしょうか (´ω`)ナルヘソ。
もっとも、私より気合いの入ったお仲間はもっと早い時間から活動をして、開業の一番列車(初発列車)に乗ったり、記念きっぷや記念グッズなどを求めて列に並んだりしているのではないでしょうか (´ω`)ナルヘソ。
「田園調布に家が建つっ!」
(゚∀゚)アヒャ☆
高級住宅街として知られる
大田区の田園調布。
ここから日吉までの区間は
東横線と目黒線の複々線区間となります。
▲東急東横線 田園調布(車窓から)
私が乗っている目黒線の電車と
複々線で並走する東横線の5050系。
▲東急東横線 田園調布-多摩川
(車窓から)
(゚∀゚)アヒャ☆
高級住宅街として知られる
大田区の田園調布。
ここから日吉までの区間は
東横線と目黒線の複々線区間となります。
▲東急東横線 田園調布(車窓から)
私が乗っている目黒線の電車と
複々線で並走する東横線の5050系。
▲東急東横線 田園調布-多摩川
(車窓から)
目黒から乗車した東急電鉄の目黒線は、武蔵小山(むさしこやま)、大岡山(おおおかやま)、田園調布(でんえんちょうふ)、多摩川、武蔵小杉(むさしこすぎ)などを経て、日吉にいたる11.9キロの通勤路線(都市近郊の大手私鉄路線)。なお、先出の路線図を見ると分かりますが、田園調布と日吉のあいだは東横線と並行した複々線区間で、正式な目黒線の路線区間は目黒〜田園調布(6.5キロ)となっています (・o・*)ホホゥ。
ちなみに当線はもともと、目黒と東京都大田区の蒲田(かまた)をむすぶ「目蒲線(めかません)」として1923年に開業したものでしたが (゚ー゚*)メカマセソ、東横線の混雑緩和をおもな目的とした田園調布〜日吉の複々線化、および目黒を介して地下鉄南北線、三田線との直通運転を実施するにあたり、2000年に目蒲線を途中の多摩川園(現在の多摩川)で分割 (* ̄ー)つ8× チョッキン。目黒〜多摩川(~日吉)が「目黒線」、多摩川〜蒲田が「東急多摩川線」という現在の形になりました ( ̄。 ̄)ヘー。世代によっては“目蒲線”の線名に懐かしさを覚えるかたがいらっしゃるかもしれませんね (´ω`*)ナツカシス。
ちなみに当線はもともと、目黒と東京都大田区の蒲田(かまた)をむすぶ「目蒲線(めかません)」として1923年に開業したものでしたが (゚ー゚*)メカマセソ、東横線の混雑緩和をおもな目的とした田園調布〜日吉の複々線化、および目黒を介して地下鉄南北線、三田線との直通運転を実施するにあたり、2000年に目蒲線を途中の多摩川園(現在の多摩川)で分割 (* ̄ー)つ8× チョッキン。目黒〜多摩川(~日吉)が「目黒線」、多摩川〜蒲田が「東急多摩川線」という現在の形になりました ( ̄。 ̄)ヘー。世代によっては“目蒲線”の線名に懐かしさを覚えるかたがいらっしゃるかもしれませんね (´ω`*)ナツカシス。
都県境の多摩川を渡ると神奈川県。
並行して架かるアーチ橋は
中原街道の丸子橋で
さらにその向こう(下流側)のほうに
東海道新幹線の橋があります。
▲東急東横線 多摩川-新丸子
(車窓から)
川崎市中原区の武蔵小杉は
東急東横線、目黒線のほか
JRの南武線、横須賀線、湘南新宿ライン、
埼京線(JRと相鉄の直通線)の各方面へ
多くの列車が発着する一大ジャンクション。
( ̄  ̄*)ムサコ
▲東急東横線 武蔵小杉(車窓から)
並行して架かるアーチ橋は
中原街道の丸子橋で
さらにその向こう(下流側)のほうに
東海道新幹線の橋があります。
▲東急東横線 多摩川-新丸子
(車窓から)
川崎市中原区の武蔵小杉は
東急東横線、目黒線のほか
JRの南武線、横須賀線、湘南新宿ライン、
埼京線(JRと相鉄の直通線)の各方面へ
多くの列車が発着する一大ジャンクション。
( ̄  ̄*)ムサコ
▲東急東横線 武蔵小杉(車窓から)
目黒から田園調布までの目黒線は一部の区間や駅が地下化されたものの、住宅街をすり抜けるように敷かれたせせこましい線形や、速度を上げ切らない駅間距離の短さに、今も思わず目蒲線と呼びたくなるような本来の当線らしい印象を受けますが (´ー`)マターリ、田園調布を出ると高架線へ上がって東横線と並行する複々線となり、それまでとはスピード感ががらっと変わったように感じます (`・ω・´)キリッ!。
雨に煙る多摩川を鉄橋で渡って東京都から神奈川県へ入り、発展が著しく無数のタワマンが駅前ににょきにょきと建ちならぶ武蔵小杉を過ぎたら、列車はまもなく東急新横浜線との接続駅である日吉に停車 ( ̄  ̄*)ヒヨシ。
雨に煙る多摩川を鉄橋で渡って東京都から神奈川県へ入り、発展が著しく無数のタワマンが駅前ににょきにょきと建ちならぶ武蔵小杉を過ぎたら、列車はまもなく東急新横浜線との接続駅である日吉に停車 ( ̄  ̄*)ヒヨシ。
さあ、ここからいよいよ本日開業したばかりの新路線、東急新横浜線へと足を踏み入れます ドキドキ♪(*゚v゚*)ワクワク♪。
ちなみに東横線や目黒線は“東急”を付けずに呼んでいましたが(東急東横線と呼ぶ場合は“東急電鉄の東横線”を略したもの)、東急新横浜線は相鉄新横浜線と区別するため、“東急”も含めたものが正式な路線名です ( ̄。 ̄)ヘー(もし東横線の例に倣うと“東急電鉄の東急新横浜線”で“東急東急新横浜線”となるw)。
ちなみに東横線や目黒線は“東急”を付けずに呼んでいましたが(東急東横線と呼ぶ場合は“東急電鉄の東横線”を略したもの)、東急新横浜線は相鉄新横浜線と区別するため、“東急”も含めたものが正式な路線名です ( ̄。 ̄)ヘー(もし東横線の例に倣うと“東急電鉄の東急新横浜線”で“東急東急新横浜線”となるw)。
ホームの部分が駅ビルに覆われた
半地下構造の日吉。
前方に見える線路は向かって左から順に
東横線の下り線(横浜方面)、
東急新横浜線の下り線(新横浜方面)、
日吉で折り返す列車の引き上げ線
(影になっている都営6300形が停車中)、
東急新横浜線の上り線(目黒線方面)
(都営6500形がこちらに向かっている)、
東横線の上り線(渋谷方面)となっています。
▲東急東横線 日吉(前方の車窓から)
半地下構造の日吉。
前方に見える線路は向かって左から順に
東横線の下り線(横浜方面)、
東急新横浜線の下り線(新横浜方面)、
日吉で折り返す列車の引き上げ線
(影になっている都営6300形が停車中)、
東急新横浜線の上り線(目黒線方面)
(都営6500形がこちらに向かっている)、
東横線の上り線(渋谷方面)となっています。
▲東急東横線 日吉(前方の車窓から)
出発信号の開通待ちによる数分ほどの停車時間で私を焦らしたのち、目黒線からの直通列車は定刻より若干遅れて日吉を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。構内に設けられたいくつかの分岐器(ポイント)を慎重に通過して、その先に伸びる真新しい線路の上を進んでゆきます ...(((o*・ω・)o。
これが初乗車となる東急新横浜線、その列車から望む車窓の風景とはいかなるものか・・・(「゚ー゚)ドレドレ
これが初乗車となる東急新横浜線、その列車から望む車窓の風景とはいかなるものか・・・(「゚ー゚)ドレドレ
スピードを上げた列車はすぐに地下のトンネルへ突入 (´・ω`・)エッ?。
そう、東急新横浜線は起点となる日吉こそ地上駅(半地下構造)ですが、その付近以外はほぼ全区間が地下に敷かれた路線。当然ながら車窓には暗い壁しか映りません ( ̄  ̄)マックラケ。まあ近年に都市近郊で開通する新路線などそんなものでしょう。
もちろんその事はあらかじめ承知していたけど、たまたま最近の私は梅田貨物線の“うめきたルート”といい、神戸市営地下鉄の北神線といい、なんだか地下線ばっかり乗っているイメージだなぁ・・・ (^^;)ゞポリポリ。新線の乗り潰しという趣味的な面白さはあっても、旅情はカケラも感じられませんね ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
そう、東急新横浜線は起点となる日吉こそ地上駅(半地下構造)ですが、その付近以外はほぼ全区間が地下に敷かれた路線。当然ながら車窓には暗い壁しか映りません ( ̄  ̄)マックラケ。まあ近年に都市近郊で開通する新路線などそんなものでしょう。
もちろんその事はあらかじめ承知していたけど、たまたま最近の私は梅田貨物線の“うめきたルート”といい、神戸市営地下鉄の北神線といい、なんだか地下線ばっかり乗っているイメージだなぁ・・・ (^^;)ゞポリポリ。新線の乗り潰しという趣味的な面白さはあっても、旅情はカケラも感じられませんね ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
轟々と地下を驀進する東急新横浜線。
日吉と新綱島の区間は
上下線のトンネルがそれぞれに分かれた
単線シールドトンネル構造。
▲東急新横浜線 日吉-新綱島
(前方の車窓から)
日吉と新横浜のあいだに設けられた
途中駅の新綱島に停車。
もちろん当駅も本日開業の新駅です。
(゚ー゚*)シン・ツナシマ
ちなみに新綱島と東横線の綱島は
別駅ながら徒歩で数分の位置に近接しています。
▲東急新横浜線 新綱島(車窓から)
次は 新横浜 終点
新綱島と新横浜の区間は
上下線がひとつのトンネルに収まる
複線シールドトンネル構造。
ふつうに乗車していたら
地下なのであまり意識しませんが
前方を眺めると意外に
線路のアップダウンを感じます。
(*・`o´・*)ホ─
▲東急新横浜線 新綱島-新横浜
(前方の車窓から)
新横浜は中線のある二面三線構造。
ここからさらに先、
相鉄線へ直通する列車は
向かって左の1番線を着発しますが、
私が乗ってきた新横浜止まりの列車は
まん中の2・3番線に入線して
折り返し運転となります。
右の4番線は相鉄線のほうから来て
東急線へ直通する列車が着発
(ただし発着番線に例外の列車もあり)。
▲東急新横浜線 新横浜(前方の車窓から)
東京メトロ南北線から
目黒線、東急新横浜線を経て
新横浜のホームに終着した9000系。
開業したての新しいホームがきれい!
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
▲東急新横浜線 新横浜
日吉と新綱島の区間は
上下線のトンネルがそれぞれに分かれた
単線シールドトンネル構造。
▲東急新横浜線 日吉-新綱島
(前方の車窓から)
日吉と新横浜のあいだに設けられた
途中駅の新綱島に停車。
もちろん当駅も本日開業の新駅です。
(゚ー゚*)シン・ツナシマ
ちなみに新綱島と東横線の綱島は
別駅ながら徒歩で数分の位置に近接しています。
▲東急新横浜線 新綱島(車窓から)
次は 新横浜 終点
新綱島と新横浜の区間は
上下線がひとつのトンネルに収まる
複線シールドトンネル構造。
ふつうに乗車していたら
地下なのであまり意識しませんが
前方を眺めると意外に
線路のアップダウンを感じます。
(*・`o´・*)ホ─
▲東急新横浜線 新綱島-新横浜
(前方の車窓から)
新横浜は中線のある二面三線構造。
ここからさらに先、
相鉄線へ直通する列車は
向かって左の1番線を着発しますが、
私が乗ってきた新横浜止まりの列車は
まん中の2・3番線に入線して
折り返し運転となります。
右の4番線は相鉄線のほうから来て
東急線へ直通する列車が着発
(ただし発着番線に例外の列車もあり)。
▲東急新横浜線 新横浜(前方の車窓から)
東京メトロ南北線から
目黒線、東急新横浜線を経て
新横浜のホームに終着した9000系。
開業したての新しいホームがきれい!
*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*
▲東急新横浜線 新横浜
途中に当線で唯一の中間駅として設けられた新綱島(しんつなしま)に停車して、日吉からの5.8キロをおよそ7分ほどで走り抜けた東急新横浜線の列車はやがて、終点となる新横浜の地下ホームに到着 (・ω・)トーチャコ。ちなみに目黒からの乗車時間は直通の各駅停車でちょうど30分でした。
これにて私は東急新横浜線を完乗 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。車窓がずっと真っ暗な地下の路線ではあるけれど、「新横浜」の駅名標が掲げられたホームに列車から降り立つと、えも言えぬじわじわとした達成感が湧き上がります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
これにて私は東急新横浜線を完乗 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。車窓がずっと真っ暗な地下の路線ではあるけれど、「新横浜」の駅名標が掲げられたホームに列車から降り立つと、えも言えぬじわじわとした達成感が湧き上がります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
東京メトロおよび都営地下鉄の車両は
相鉄線への直通列車には使われず、
当駅で折り返すことになります
(東急と相鉄を直通運行できるのは
基本的に東急と相鉄の車両のみ)。
9000系が表示した折り返しの行先は
以前から見慣れている赤羽岩淵ゆき。
▲東急新横浜線 新横浜
相鉄線への直通列車には使われず、
当駅で折り返すことになります
(東急と相鉄を直通運行できるのは
基本的に東急と相鉄の車両のみ)。
9000系が表示した折り返しの行先は
以前から見慣れている赤羽岩淵ゆき。
▲東急新横浜線 新横浜
さて先述したように、新横浜は東急電鉄の東急新横浜線と、やはり本日に同時開業した相模鉄道の相鉄新横浜線が接続する共同使用駅で トーキュー(゚ー゚≡゚ー゚)ソーテツ、新横浜止まりの列車から降りた私は同じホームの反対側(2番から1番ホームへの対面接続)で少し待てば、次に相鉄新横浜線へ向かう直通列車がやってくるのですが σ(゚・゚*)ンー…、せっかくなら開業ムードで盛り上がっているであろう新横浜駅の様子も見てみたいと思い、先を急がずにいったん当駅の改札を出てみることとしました ...(((o*・ω・)o。
なにか開業日ならではのイベントが催されていたり、記念グッズの販売などが行われたりしていないかな?
なにか開業日ならではのイベントが催されていたり、記念グッズの販売などが行われたりしていないかな?
相鉄新横浜線、東急新横浜線のほか
東海道新幹線、JR横浜線、
横浜市営地下鉄ブルーラインが集まる新横浜。
なお相鉄と東急以外の各線はいずれも
改札外での乗換えとなります。
▲東急新横浜線 新横浜
(当駅は相鉄と東急の共同使用駅ですが
写真の北改札は東急の管轄)
東海道新幹線、JR横浜線、
横浜市営地下鉄ブルーラインが集まる新横浜。
なお相鉄と東急以外の各線はいずれも
改札外での乗換えとなります。
▲東急新横浜線 新横浜
(当駅は相鉄と東急の共同使用駅ですが
写真の北改札は東急の管轄)
目黒0736-(東急目黒線・東急新横浜線)-新横浜0810(定刻より4分遅れ)
地下からの長いエスカレータを上がると
新幹線や横浜線のJR新横浜駅へアプローチする
ペデストリアンデッキに出ました。
新横浜の駅ビル(キュービックプラザ新横浜)も
壁面に垂れ幕を掲げて
相鉄・東急新横浜線の開業をお祝いしています。
(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)
▲東海道新幹線 新横浜
新幹線や横浜線のJR新横浜駅へアプローチする
ペデストリアンデッキに出ました。
新横浜の駅ビル(キュービックプラザ新横浜)も
壁面に垂れ幕を掲げて
相鉄・東急新横浜線の開業をお祝いしています。
(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)
▲東海道新幹線 新横浜
地下4階の発着ホームから地下1階の改札を経て長いエスカレータを上りきると、そこは新幹線や横浜線が発着するJRの駅・・・の前に設けられたペデストリアンデッキ(歩道橋)。JRの駅構内(駅ビル)へダイレクトには直結していないようで、ちょっと位置が離れている印象は否めないところですが σ(゚・゚*)ンー… (相鉄・東急の地下ホームと新幹線が発着するホームの乗換時間はおおむね10分とされています)、それでも相鉄と東急の両線が新横浜への乗り入れを果たしたことで、とくに両線の沿線のかたは新幹線への乗り換えがとても便利になったのでしょう (・∀・)イイネ。
そして新横浜といえば横浜アリーナ(多目的イベントホール)や日産スタジアム(横浜国際総合競技場)の最寄駅でもあり、都心方面からそれらへのアクセスもかなり向上しました。都内に住む私が東京や品川でなく、わざわざ新横浜から東海道新幹線を利用することはあまりないと思いますが、スタジアムへサッカーの試合を見に行くときなどに、この東急新横浜線ルートが活用できそうです ъ(゚Д゚)ナイス(応援しているチームが今はJ2なので、日産スタジアムで試合をすることはほとんどないんだけどさ・・・^^;)
そして新横浜といえば横浜アリーナ(多目的イベントホール)や日産スタジアム(横浜国際総合競技場)の最寄駅でもあり、都心方面からそれらへのアクセスもかなり向上しました。都内に住む私が東京や品川でなく、わざわざ新横浜から東海道新幹線を利用することはあまりないと思いますが、スタジアムへサッカーの試合を見に行くときなどに、この東急新横浜線ルートが活用できそうです ъ(゚Д゚)ナイス(応援しているチームが今はJ2なので、日産スタジアムで試合をすることはほとんどないんだけどさ・・・^^;)
駅ビルのイベントスペースでは
大きな垂れ幕の下にステージが設けられ、
たくさんの人たちで賑わっています。
ちょいと壇上を覗いてみると・・・
(=゚ω゚=*)ンン!?
そこにいたのは
相鉄のキャラ「そうにゃん」(左)と
東急のキャラ「のるるん」じゃありませんか。
人気のゆるキャラが二人そろって
今日の開業ムードを盛り上げています。
ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪
そしてさらに
新横浜駅に乗り入れる鉄道5社の駅長さんも
ずらっと勢ぞろい!
(向かって左から横浜市営、相鉄、東急、
JR東海、JR東日本)
これはなんとも豪華な式典です。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
両脇で花を添えるように立つお着物の方は
京都祇園の舞妓さんで、
相鉄と東急が新横浜へ直結したことにより
京都へも行きやすくなったことを
アピールしています。
(*´v`*)オイデヤス
お目目が光るという
のるるんさんの特技(?)に
ステージ上の一同が拍手(笑)
(*゚∀゚ノノ゙パチパチパチパチ
大きな垂れ幕の下にステージが設けられ、
たくさんの人たちで賑わっています。
ちょいと壇上を覗いてみると・・・
(=゚ω゚=*)ンン!?
そこにいたのは
相鉄のキャラ「そうにゃん」(左)と
東急のキャラ「のるるん」じゃありませんか。
人気のゆるキャラが二人そろって
今日の開業ムードを盛り上げています。
ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪
そしてさらに
新横浜駅に乗り入れる鉄道5社の駅長さんも
ずらっと勢ぞろい!
(向かって左から横浜市営、相鉄、東急、
JR東海、JR東日本)
これはなんとも豪華な式典です。
w(*゚o゚*)wオオーッ!
両脇で花を添えるように立つお着物の方は
京都祇園の舞妓さんで、
相鉄と東急が新横浜へ直結したことにより
京都へも行きやすくなったことを
アピールしています。
(*´v`*)オイデヤス
お目目が光るという
のるるんさんの特技(?)に
ステージ上の一同が拍手(笑)
(*゚∀゚ノノ゙パチパチパチパチ
そんな新横浜ではやはり、相鉄・東急新横浜線の開業にあわせて様々な記念商品や鉄道グッズなどの販売が行なわれていましたが (゚∀゚)オッ!、雨が降る屋外のブースにできた長蛇の列に私はとても並ぶ気がおきず (´д`;)人大杉…、駅構内のコンビニで“記念パッケージの総菜パン”をひとつ買っただけ ( ̄ω ̄*)ランチパック。
でもその流れでちょいと覗いてみた構内の特設のステージでは、開業に関連したイベントが賑やかに催されており (゚∀゚)オッ!、相鉄の「そうにゃん」と東急の「のるるん」という二体のキャラクター ソーニャソ!(=゚ω゚)ノルルソ!、さらには新横浜駅に乗り入れる鉄道5社(相鉄、東急、JR東海、JR東日本、横浜市交通局)の駅長さんたちによる記念式典の様子を写真に撮ることができました (^_[◎]oパチリ。とくに「そうにゃん」と「のるるん」の共演は“ゆるキャラ”が好きな私にとって嬉しい収穫ですし ヽ(´▽`*)ノワーイ♪、壇上で主賓のみなさんが勢ぞろいした記念撮影も開業日ならではの貴重な記録となりました (o ̄∇ ̄o)ラキー。
でもその流れでちょいと覗いてみた構内の特設のステージでは、開業に関連したイベントが賑やかに催されており (゚∀゚)オッ!、相鉄の「そうにゃん」と東急の「のるるん」という二体のキャラクター ソーニャソ!(=゚ω゚)ノルルソ!、さらには新横浜駅に乗り入れる鉄道5社(相鉄、東急、JR東海、JR東日本、横浜市交通局)の駅長さんたちによる記念式典の様子を写真に撮ることができました (^_[◎]oパチリ。とくに「そうにゃん」と「のるるん」の共演は“ゆるキャラ”が好きな私にとって嬉しい収穫ですし ヽ(´▽`*)ノワーイ♪、壇上で主賓のみなさんが勢ぞろいした記念撮影も開業日ならではの貴重な記録となりました (o ̄∇ ̄o)ラキー。
駅のコンビニで買ったのは
相鉄・東急新横浜線の開業記念デザインが
パッケージに施された
ヤマザキさんの「ランチパック」。
横浜らしい「しゅうまい風味」です。
“シウマイ”と言えないのは大人の事情?w
( ̄▽ ̄)シュ-マイ
そういえば相鉄とJRの直通開始のときは
崎陽軒さんの記念弁当が発売されましたが
今回の開業では見かけなかったな・・・
(とくに発売はなかったみたい)。
相鉄・東急新横浜線の開業記念デザインが
パッケージに施された
ヤマザキさんの「ランチパック」。
横浜らしい「しゅうまい風味」です。
“シウマイ”と言えないのは大人の事情?w
( ̄▽ ̄)シュ-マイ
そういえば相鉄とJRの直通開始のときは
崎陽軒さんの記念弁当が発売されましたが
今回の開業では見かけなかったな・・・
(とくに発売はなかったみたい)。
では、ふたたび地下にある相鉄と東急のホームへ戻って、今度は相鉄新横浜線のほうに乗ってみましょう (゚ー゚*)ソーテツ。
当線はSuicaやPASMOなどのICカード(IC乗車券)ももちろん使えるけれど、せっかくなので開業初日となった今日の日付が入ったきっぷ(乗車券)を券売機で買って改札を入ります (*・∀・)つ[キップ]。
当線はSuicaやPASMOなどのICカード(IC乗車券)ももちろん使えるけれど、せっかくなので開業初日となった今日の日付が入ったきっぷ(乗車券)を券売機で買って改札を入ります (*・∀・)つ[キップ]。
開業日である「2023.-3.18」の
日付が刻印された相鉄線のきっぷ。
(*・∀・)つ[キップ]
ふつうの乗車券ですが
記念に求める方も多くて
券売機で購入するのに30分くらい
並ぶことになりました。
(当駅の改札を出た時点ですぐに並んだ)
日付が刻印された相鉄線のきっぷ。
(*・∀・)つ[キップ]
ふつうの乗車券ですが
記念に求める方も多くて
券売機で購入するのに30分くらい
並ぶことになりました。
(当駅の改札を出た時点ですぐに並んだ)
相鉄こと相模鉄道は、横浜と海老名(えびな)の間をむすぶ本線(24.6キロ)と、その途中の二俣川(ふたまたがわ)で分岐して湘南台(しょうなんだい)へいたるいずみ野線(11.3キロ)、および西谷(にしや)で分岐して新横浜にいたる相鉄新横浜線(6.3キロ)の三路線(と貨物線(回送線)の厚木線)から成る関東の大手私鉄。なお、先述した東急新横浜線と同様の理由で、相鉄新横浜線も“相鉄”を含めたものが正式な路線名です (・o・*)ホホゥ。
新横浜の構内に掲示されていた
相鉄線の路線図。
(写真をクリックすると拡大表示されます)。
横浜〜海老名が本線、
途中で上のほうに分岐するのが
二俣川〜湘南台のいずみ野線、
そして下のほうへ分岐するのが
西谷〜新横浜の相鉄新横浜線です。
(*゚ェ゚)フムフム
相鉄線の路線図。
(写真をクリックすると拡大表示されます)。
横浜〜海老名が本線、
途中で上のほうに分岐するのが
二俣川〜湘南台のいずみ野線、
そして下のほうへ分岐するのが
西谷〜新横浜の相鉄新横浜線です。
(*゚ェ゚)フムフム
神奈川の旧国名である“相模(さがみ)”が社名に付けられているとおり、相鉄の路線はすべてが神奈川県内の横浜近郊に収まっており、1921年(大正10年)に相模線(現在のJR相模線)を開業して以来、長らく他線との直通運転も行わない“鎖国状態”が続いていましたが ( ̄▽ ̄;)サコク…、今から三年半前の2019年11月に相鉄新横浜線の西谷と羽沢横浜国大(はざわよこはまこくだい)を部分的に先行開業させ、羽沢横浜国大にて接続するJR埼京線(JR・相鉄連絡線)と相互乗り入れ形式の直通運転を開始 ソーテツ(=´∀`)人(´∀`=)尺。これにより相鉄本線から埼京線沿線の渋谷や新宿、池袋までダイレクトにアクセスできるようになり(最長で海老名から埼玉県の川越まで直通)、悲願の都心乗り入れが実現しています ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。
そしてさらに本日、相鉄新横浜線は羽沢横浜国大と新横浜の区間を延伸させ、晴れて全線が開通 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。新横浜にて接続する東急新横浜線を介して東急東横線と目黒線、その先に繋がる地下鉄線などとの直通運転も開始されました ソーテツ(=´∀`)人(´∀`=)トーキュー。
ここ数年内にJRと東急という二経路の都心アクセスルートを確立した様はまさに、このプロジェクトのキャッチフレーズとなっている「相鉄の大進撃」ですね …((((`・∀・)ノ Go!Go!。
そしてさらに本日、相鉄新横浜線は羽沢横浜国大と新横浜の区間を延伸させ、晴れて全線が開通 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。新横浜にて接続する東急新横浜線を介して東急東横線と目黒線、その先に繋がる地下鉄線などとの直通運転も開始されました ソーテツ(=´∀`)人(´∀`=)トーキュー。
ここ数年内にJRと東急という二経路の都心アクセスルートを確立した様はまさに、このプロジェクトのキャッチフレーズとなっている「相鉄の大進撃」ですね …((((`・∀・)ノ Go!Go!。
そんな二段階に分けて開業した相鉄新横浜線。JRとの直通線として先に開通していた西谷と羽沢横浜国大のあいだを私はすでに乗車を済ませているので、今回の乗りつぶし対象は羽沢横浜国大と新横浜の一駅間(4.2キロ)となります (´ω`)ナルヘソ。
先ほど新横浜止まりの列車で降り立ったのと同じホームの1番線側で待つのは、東急目黒線から直通してきて相鉄本線のほうへ向かう海老名ゆき (゚ー゚*)エビナミドリ。
ちなみに、東急は東横線と目黒線の二路線の列車が東急新横浜線へ乗り入れているように、相鉄のほうも本線といずみ野線の二路線の列車が相鉄新横浜線に乗り入れており、東急と相鉄の両社による直通運転のパターンは基本的に、“東横線はいずみ野線”と“目黒線は本線”というカップリングになることが多いようです ( ̄。 ̄)ヘー。
そして多様な直通運転における鉄ちゃんの楽しみといえば、目黒での出発時にも触れた各社の車両による“電車ガチャ”ですが (o ̄∇ ̄o)ガチャ、東横線は横浜高速鉄道みなとみらい線や東京メトロ副都心線、東武東上線、西武池袋線との相互乗り入れによる直通運転を行なっているものの、相鉄・東急新横浜線へ直通する列車の運用に使われるのは今のところ東急の5050系(4000番台)と相鉄の20000系のみ。また目黒線のほうも三田線、南北線、埼玉高速鉄道線の車両はいずれも東急新横浜線の新横浜までの運用となっていて、相鉄線方面へ直通できるのは東急の3000系と5080系(3020系は今のところ対応外の模様)、相鉄の21000系のみ。しかも東急の5050系と5080系、相鉄の20000系と21000系はそれぞれがほぼ同形式と言っていい仕様なので、実質的に新横浜から乗る相鉄新横浜線で引けるガチャの内容は二社の三車種(東急3000系と5000系列、相鉄20000系列)に限られます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
それならあくまでも個人的な趣味で、どちらかといえば東急より相鉄の電車に乗りたいなぁ σ(゚・゚*)ソーテツ…。
ちなみに、東急は東横線と目黒線の二路線の列車が東急新横浜線へ乗り入れているように、相鉄のほうも本線といずみ野線の二路線の列車が相鉄新横浜線に乗り入れており、東急と相鉄の両社による直通運転のパターンは基本的に、“東横線はいずみ野線”と“目黒線は本線”というカップリングになることが多いようです ( ̄。 ̄)ヘー。
そして多様な直通運転における鉄ちゃんの楽しみといえば、目黒での出発時にも触れた各社の車両による“電車ガチャ”ですが (o ̄∇ ̄o)ガチャ、東横線は横浜高速鉄道みなとみらい線や東京メトロ副都心線、東武東上線、西武池袋線との相互乗り入れによる直通運転を行なっているものの、相鉄・東急新横浜線へ直通する列車の運用に使われるのは今のところ東急の5050系(4000番台)と相鉄の20000系のみ。また目黒線のほうも三田線、南北線、埼玉高速鉄道線の車両はいずれも東急新横浜線の新横浜までの運用となっていて、相鉄線方面へ直通できるのは東急の3000系と5080系(3020系は今のところ対応外の模様)、相鉄の21000系のみ。しかも東急の5050系と5080系、相鉄の20000系と21000系はそれぞれがほぼ同形式と言っていい仕様なので、実質的に新横浜から乗る相鉄新横浜線で引けるガチャの内容は二社の三車種(東急3000系と5000系列、相鉄20000系列)に限られます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
それならあくまでも個人的な趣味で、どちらかといえば東急より相鉄の電車に乗りたいなぁ σ(゚・゚*)ソーテツ…。
相鉄・東急新横浜線を介して
東急目黒線と相鉄本線を直通する
各駅停車の海老名ゆき。
車体色がシックなネイビーブルーの
相鉄21000系がやってきました。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
▲相鉄新横浜線 新横浜
東急目黒線と相鉄本線を直通する
各駅停車の海老名ゆき。
車体色がシックなネイビーブルーの
相鉄21000系がやってきました。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
▲相鉄新横浜線 新横浜
そーてつ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
ホームに入ってきた海老名ゆきは希望の(?)相鉄21000系(21804F)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。
東急も、東京メトロも、都営も、埼玉高速も、ここ新横浜に顔を出す各社の車両はどれもステンレスかアルミの無塗装車体に路線イメージの色帯が巻かれたものばかりのなか、車体全体がネイビーブルー(YOKOHAMA NAVYBLUE)と呼ばれる上品な藍色に包まれた21000系(20000系も同様)は他社の車両に比べてインパクトがあります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。また当系は車内の内装もモノトーンにまとめた落ち着く雰囲気で好印象 (・∀・)イイネ。ガチャの確率的には“レア”ってほどのものではないけど、たまたまこの車両に当たったのは嬉しい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
といっても、乗車する区間はわずか一駅だけなんですが・・・ (^^;)ゞポリポリ。
ホームに入ってきた海老名ゆきは希望の(?)相鉄21000系(21804F)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。
東急も、東京メトロも、都営も、埼玉高速も、ここ新横浜に顔を出す各社の車両はどれもステンレスかアルミの無塗装車体に路線イメージの色帯が巻かれたものばかりのなか、車体全体がネイビーブルー(YOKOHAMA NAVYBLUE)と呼ばれる上品な藍色に包まれた21000系(20000系も同様)は他社の車両に比べてインパクトがあります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。また当系は車内の内装もモノトーンにまとめた落ち着く雰囲気で好印象 (・∀・)イイネ。ガチャの確率的には“レア”ってほどのものではないけど、たまたまこの車両に当たったのは嬉しい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。
といっても、乗車する区間はわずか一駅だけなんですが・・・ (^^;)ゞポリポリ。
つぎは 羽沢横浜国大
東急新横浜線の新綱島〜新横浜と同様、
相鉄新横浜線は西谷〜新横浜のほぼ全区間が
上下線がひとつのトンネルに収まる
複線シールドトンネル構造。
(*・`o´・*)ホ─
▲相鉄新横浜線 新横浜-羽沢横浜国大
(前方の車窓から)
東急新横浜線の新綱島〜新横浜と同様、
相鉄新横浜線は西谷〜新横浜のほぼ全区間が
上下線がひとつのトンネルに収まる
複線シールドトンネル構造。
(*・`o´・*)ホ─
▲相鉄新横浜線 新横浜-羽沢横浜国大
(前方の車窓から)
東急新横浜線に引き続き、相鉄新横浜線もまた全線が“ほぼ”地下に敷かれており、海老名ゆきの列車は無機質なトンネルのなかを淡々と進みゆきます ...(((o*・ω・)o。まあ近年に都市近郊で開通する新路線などそんなものでしょう(笑)(。A。)アヒャ☆。
そのようななか、JR線方面(相鉄・JR直通線)の線路と合流(分岐)するあたりでわずかながらトンネルが切れ、一瞬だけ窓から車内に外光が差し込んだかと思ったら (つ▽≦*)マブシ!、まもなく列車は新規に延伸した区間を走り終えて羽沢横浜国大に停車します (・ω・)トーチャコ。
そのようななか、JR線方面(相鉄・JR直通線)の線路と合流(分岐)するあたりでわずかながらトンネルが切れ、一瞬だけ窓から車内に外光が差し込んだかと思ったら (つ▽≦*)マブシ!、まもなく列車は新規に延伸した区間を走り終えて羽沢横浜国大に停車します (・ω・)トーチャコ。
羽沢横浜国大の手前(上り方)に位置する
JR直通線との合流(分岐)地点で
相鉄新横浜線は少しだけトンネルを出ます。
(゚∀゚)オッ!
▲相鉄新横浜線 新横浜-羽沢横浜国大
(車窓から)
その相鉄新横浜線とJR直通線の合流地点を
羽沢横浜国大のホームの新横浜方より眺めると
こんな感じ。
(「゚ー゚)ドレドレ
真ん中の二線が相鉄新横浜線で
左右に分かれるのがJR直通線です。
ちょうどタイミングよく
相鉄新横浜線に東急5080系が、
JR直通線のほうにはJRのE233系が
同時に写り込みました。
(^_[◎]oパチリ
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
相鉄・JR直通線との接続駅である
羽沢横浜国大に到着。
(・ω・)トーチャコ
ここから先の西谷までは
2019年に開通した区間となります。
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
JR直通線との合流(分岐)地点で
相鉄新横浜線は少しだけトンネルを出ます。
(゚∀゚)オッ!
▲相鉄新横浜線 新横浜-羽沢横浜国大
(車窓から)
その相鉄新横浜線とJR直通線の合流地点を
羽沢横浜国大のホームの新横浜方より眺めると
こんな感じ。
(「゚ー゚)ドレドレ
真ん中の二線が相鉄新横浜線で
左右に分かれるのがJR直通線です。
ちょうどタイミングよく
相鉄新横浜線に東急5080系が、
JR直通線のほうにはJRのE233系が
同時に写り込みました。
(^_[◎]oパチリ
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
相鉄・JR直通線との接続駅である
羽沢横浜国大に到着。
(・ω・)トーチャコ
ここから先の西谷までは
2019年に開通した区間となります。
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
このまま相鉄新横浜線の終点(路線上の起点)となる西谷まで全線を乗り通してもよかったのですが、いちおう未乗区間の踏破という区切りを付けたくて、私は羽沢横浜国大で下車 (゚ー゚*)ハザコク。すでに乗車済みとなっている当駅と西谷のあいだと合わせて、相鉄新横浜線はこれにて完乗となりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
わずか一駅だけの4分間、車窓から眺めた景色の感想はとくにないけど(地下だからねw)、やはりここでも未乗区間を乗りつぶして降り立った羽沢横浜国大のホームでは、達成感がわいて感慨深いものがあります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
わずか一駅だけの4分間、車窓から眺めた景色の感想はとくにないけど(地下だからねw)、やはりここでも未乗区間を乗りつぶして降り立った羽沢横浜国大のホームでは、達成感がわいて感慨深いものがあります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
新横浜1026-(相鉄新横浜線)-羽沢横浜国大1030
ちなみに私がこの羽沢横浜国大の駅を利用するのは、相鉄とJRが直通運行を開始したとき(2019年11月)の初日以来となる三年半ぶり (*´∀`)ノ゙オヒサ。その間に当駅での下車はおろか、列車で通ることもありませんでした。ぶっちゃけ、個人的に相鉄沿線って、仕事でもプライベートでもあんまし縁がないもんなぁ・・・(^^;)ゞポリポリ(先日に仕事で大和へ行く用事があったけど、運賃が安い小田急線を利用した)。
そこで、ここから都内のほうへ戻る経路は久しぶりに、相鉄・JR直通線の列車(埼京線に直通)に乗ってみようと思います ( ̄  ̄*)尺。このようにJR経由や東急経由など、路線のルートにいくつかの幅ができたのは、私のような鉄ちゃんにとっては楽しい選択 (*´v`*)ワクワク♪。ただ一般的に見ると、経路や行先の異なる列車がけっこう複雑に入り混じっているので、鉄ちゃんじゃないふつうの人は慣れるまでにちょっと戸惑うかもしれませんね σ(゚・゚*)ンー…。
ちなみに私がこの羽沢横浜国大の駅を利用するのは、相鉄とJRが直通運行を開始したとき(2019年11月)の初日以来となる三年半ぶり (*´∀`)ノ゙オヒサ。その間に当駅での下車はおろか、列車で通ることもありませんでした。ぶっちゃけ、個人的に相鉄沿線って、仕事でもプライベートでもあんまし縁がないもんなぁ・・・(^^;)ゞポリポリ(先日に仕事で大和へ行く用事があったけど、運賃が安い小田急線を利用した)。
そこで、ここから都内のほうへ戻る経路は久しぶりに、相鉄・JR直通線の列車(埼京線に直通)に乗ってみようと思います ( ̄  ̄*)尺。このようにJR経由や東急経由など、路線のルートにいくつかの幅ができたのは、私のような鉄ちゃんにとっては楽しい選択 (*´v`*)ワクワク♪。ただ一般的に見ると、経路や行先の異なる列車がけっこう複雑に入り混じっているので、鉄ちゃんじゃないふつうの人は慣れるまでにちょっと戸惑うかもしれませんね σ(゚・゚*)ンー…。
羽沢横浜国大の発車案内標。
先発はJR線直通の新宿ゆき。
次発は東急東横線と東京メトロ副都心線、
東武東上線へ直通する川越市ゆき。
次々発は東急目黒線と都営三田線に直通の
西高島平ゆき
・・・となっています。
(´∀`;)カオス…
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
羽沢横浜国大から
相鉄・JR直通線の列車に乗って
都内のほうへ戻ります。
ホームに入ってきた新宿ゆきは
埼京線用のE233系。
( ̄  ̄*)サイキョーセソ
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
今度はJR直通線のほうから見る
相鉄新横浜線との分岐点。
トンネルの先が新横浜方面です。
▲東海道本線(相鉄・JR直通線)
羽沢横浜国大-武蔵小杉(車窓から)
羽沢横浜国大は
東海道貨物線の貨物駅である
横浜羽沢と隣接しており、
相鉄・JR直通線の車窓からは
構内の様子が少しだけ覗けます。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲東海道本線(相鉄・JR直通線)
羽沢横浜国大-武蔵小杉(車窓から)
本来の貨物線を通る相鉄・JR直通線は
大きく迂回するようなルートとなっており
一駅間で15分も要しますが、
羽沢横浜国大の次駅は武蔵小杉。
ちなみに今朝の私が新横浜へ向かう際には
当駅を東急目黒線の列車で通っています。
( ̄  ̄*)ムサコ
▲東海道本線(品鶴線)武蔵小杉
(車窓から)
先発はJR線直通の新宿ゆき。
次発は東急東横線と東京メトロ副都心線、
東武東上線へ直通する川越市ゆき。
次々発は東急目黒線と都営三田線に直通の
西高島平ゆき
・・・となっています。
(´∀`;)カオス…
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
羽沢横浜国大から
相鉄・JR直通線の列車に乗って
都内のほうへ戻ります。
ホームに入ってきた新宿ゆきは
埼京線用のE233系。
( ̄  ̄*)サイキョーセソ
▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
今度はJR直通線のほうから見る
相鉄新横浜線との分岐点。
トンネルの先が新横浜方面です。
▲東海道本線(相鉄・JR直通線)
羽沢横浜国大-武蔵小杉(車窓から)
羽沢横浜国大は
東海道貨物線の貨物駅である
横浜羽沢と隣接しており、
相鉄・JR直通線の車窓からは
構内の様子が少しだけ覗けます。
(「゚ー゚)ドレドレ
▲東海道本線(相鉄・JR直通線)
羽沢横浜国大-武蔵小杉(車窓から)
本来の貨物線を通る相鉄・JR直通線は
大きく迂回するようなルートとなっており
一駅間で15分も要しますが、
羽沢横浜国大の次駅は武蔵小杉。
ちなみに今朝の私が新横浜へ向かう際には
当駅を東急目黒線の列車で通っています。
( ̄  ̄*)ムサコ
▲東海道本線(品鶴線)武蔵小杉
(車窓から)
羽沢横浜国大1056-(相鉄・JR直通線242M)-新宿1131
開業の初日に乗車目的で訪れた東急新横浜線と相鉄新横浜線 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
鉄道路線の完乗を目指す者の一人として新たな路線をさっそく踏破できた喜びもさることながら ヽ(´▽`*)ノワーイ♪、直通運転の拡大による各社の車両バラエティー(電車ガチャねw)に興味深い面白さを感じ (*゚v゚*)ワクワク♪、また新横浜で見物できた記念式典など開業日ならではの賑やかさも味わえて ソーニャソ(*’∀’*)ノルルソ、趣味的に充実した両線初乗車の日となりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
そして今回の私は新規に開業した区間(日吉〜新横浜〜羽沢横浜国大)に重点を置いた形での乗車としましたが、いずれ機会があれば各社の各線をまたいで直通する列車を、端から端まで(始発駅から終点まで)一気に乗り通してみたいものですね (・∀・)イイネ(ちなみに直通列車のなかには一本で、相鉄本線の海老名から東武東上線の小川町(埼玉県)まで、116.4キロもの長距離を二時間半かけて走る列車もあるのだそうな w( ̄▽ ̄;)wワオッ!)。そんな楽しみも増えた、相鉄・東急新横浜線の直通運転開始でした。
開業の初日に乗車目的で訪れた東急新横浜線と相鉄新横浜線 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。
鉄道路線の完乗を目指す者の一人として新たな路線をさっそく踏破できた喜びもさることながら ヽ(´▽`*)ノワーイ♪、直通運転の拡大による各社の車両バラエティー(電車ガチャねw)に興味深い面白さを感じ (*゚v゚*)ワクワク♪、また新横浜で見物できた記念式典など開業日ならではの賑やかさも味わえて ソーニャソ(*’∀’*)ノルルソ、趣味的に充実した両線初乗車の日となりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
そして今回の私は新規に開業した区間(日吉〜新横浜〜羽沢横浜国大)に重点を置いた形での乗車としましたが、いずれ機会があれば各社の各線をまたいで直通する列車を、端から端まで(始発駅から終点まで)一気に乗り通してみたいものですね (・∀・)イイネ(ちなみに直通列車のなかには一本で、相鉄本線の海老名から東武東上線の小川町(埼玉県)まで、116.4キロもの長距離を二時間半かけて走る列車もあるのだそうな w( ̄▽ ̄;)wワオッ!)。そんな楽しみも増えた、相鉄・東急新横浜線の直通運転開始でした。
相鉄・東急新横浜線の開業を祝って
ヘッドマークなどの記念装飾が施された
東急5080系(5186F)と
相鉄21000系(21102F)。
開業日に記念編成とは遭遇できなかったため
あらためて後日に新横浜で撮影しました。
(^_[◎]oパチリ
▲相鉄・東急新横浜線 新横浜
ヘッドマークなどの記念装飾が施された
東急5080系(5186F)と
相鉄21000系(21102F)。
開業日に記念編成とは遭遇できなかったため
あらためて後日に新横浜で撮影しました。
(^_[◎]oパチリ
▲相鉄・東急新横浜線 新横浜
ところで、今回の乗りつぶしにより私は東急新横浜線と相鉄新横浜線を完乗したものの、全国的に見ると3月27日には九州の福岡で福岡市営地下鉄・七隈線(ななくません)の天神南と博多の間が延伸開業しており(これも地下鉄・・・^^;)、さすがにそれはまだ乗りに行けていません (´〜`*)ウーン。
私の生涯の目標である国内の旅客鉄道路線の全線完乗、その飽くなき道はまだまだ続く・・・(*`・ω・´)-3フンス!。
私の生涯の目標である国内の旅客鉄道路線の全線完乗、その飽くなき道はまだまだ続く・・・(*`・ω・´)-3フンス!。
2023-04-13 04:04
神戸市営地下鉄・・・北神線 乗車記 [鉄道乗車記]
3月の第一週目に仕事の出張で関西のほうへ赴いた私 シュッチョ…((((o* ̄-)o。
そのついでに(?)、先月(2/13)より線路が地上線(旧・梅田信号場経由)から地下線(大阪うめきた地下ホーム経由)へ切り替えられたばかりの「梅田貨物線」(新大阪〜西九条の区間)を通ってみたくて、京都から大阪までの移動に特急「はるか」を利用(特急券は自費購入)(´∇ノ`*)オホホホホ。旅客線と貨物線の転線を繰り返す複雑な経路を走るという、当列車ならではのマニアックな車窓風景を存分に楽しみました (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
そして実はこれのみならず、“出張ついでの鉄旅”(?)にはもうちょっとだけ続きがあります。
出張業務の最終日は金曜日(3/3)、それならば関西にもう一日ほど延泊して(この宿泊費ももちろん自腹で)、週末の土曜日を鉄道趣味(撮り鉄や乗り鉄)にウマく活かしたいところ (・∀・)イイネ。たまたまながら数日前(2/27)には兵庫県の和田岬線で使われている103系の引退が公表されたため、できればそれを記録したいなと思いますし、そのほかにも効率よく絡められそうな “とある目的” がアタマの中に浮かびます σ(゚・゚*)ンー…。
そこで私は大阪での仕事を終えてからJR神戸線(東海道本線)の下り列車に乗り、神戸市の兵庫(兵庫区)へ向かいました ...(((o*・ω・)o。
3月4日(土)
そのついでに(?)、先月(2/13)より線路が地上線(旧・梅田信号場経由)から地下線(大阪うめきた地下ホーム経由)へ切り替えられたばかりの「梅田貨物線」(新大阪〜西九条の区間)を通ってみたくて、京都から大阪までの移動に特急「はるか」を利用(特急券は自費購入)(´∇ノ`*)オホホホホ。旅客線と貨物線の転線を繰り返す複雑な経路を走るという、当列車ならではのマニアックな車窓風景を存分に楽しみました (*゚∀゚)=3ハァハァ!。
そして実はこれのみならず、“出張ついでの鉄旅”(?)にはもうちょっとだけ続きがあります。
出張業務の最終日は金曜日(3/3)、それならば関西にもう一日ほど延泊して(この宿泊費ももちろん自腹で)、週末の土曜日を鉄道趣味(撮り鉄や乗り鉄)にウマく活かしたいところ (・∀・)イイネ。たまたまながら数日前(2/27)には兵庫県の和田岬線で使われている103系の引退が公表されたため、できればそれを記録したいなと思いますし、そのほかにも効率よく絡められそうな “とある目的” がアタマの中に浮かびます σ(゚・゚*)ンー…。
そこで私は大阪での仕事を終えてからJR神戸線(東海道本線)の下り列車に乗り、神戸市の兵庫(兵庫区)へ向かいました ...(((o*・ω・)o。
3月4日(土)
神戸市兵庫区に所在する
山陽本線の兵庫。
( ̄  ̄*)ヒョーゴ
当駅は1888年(明治21年)に開業し、
現駅舎は高架化の際に改築された二代目ですが、
それでも1930年(昭和5年)に建造の
歴史あるものです。
▲山陽本線 兵庫
山陽本線の兵庫。
( ̄  ̄*)ヒョーゴ
当駅は1888年(明治21年)に開業し、
現駅舎は高架化の際に改築された二代目ですが、
それでも1930年(昭和5年)に建造の
歴史あるものです。
▲山陽本線 兵庫
兵庫で迎えた土曜日の朝 (‘-‘*)オハヨン。前日に続いて今日も朝から晴天のいいお天気です。
兵庫駅のある神戸市兵庫区は、県名にもなっている“兵庫”が堂々と付いた街ですが ( ̄  ̄*)ヒョーゴ、このあたりはおもに住宅地が形成されており、また工場や倉庫なども多く、賑やかな繁華街の元町や三宮に比べると落ち着いた雰囲気・・・というか、何となくあか抜けない印象 σ(゚・゚*)ンー…。そんな当地は繁華街よりも宿泊施設の料金がリーズナブルに抑えられているようで、神戸観光などにおける穴場の宿泊地といえるかもしれません (*-∀-)ホホゥ(なお、兵庫はJR神戸線の上り普通列車で神戸まで一駅、三ノ宮まで3駅のところに位置していて意外と便利なんです)。
ちなみに今回の私がネットで選んだビジネスホテルのプランは、シングルルーム(ダブルベッド仕様で部屋の広さもとくに狭く感じない程度)の素泊まりで平日価格が一泊4,800円 (゚∀゚)オッ!。それだけでもじゅうぶんお安いと感じるのに、“全国旅行支援割引”が適用されて20%引きの3,840円となり (゚∀゚*)オオッ!!、さらに2,000円分のクーポン券まで貰えたので、実質は1,840円!? エッ!(゚Д゚≡゚∀゚)マジ!?。ビックリするほどおトクに泊まることができました。これは嬉しい (´艸`*)オトク♪。
兵庫駅のある神戸市兵庫区は、県名にもなっている“兵庫”が堂々と付いた街ですが ( ̄  ̄*)ヒョーゴ、このあたりはおもに住宅地が形成されており、また工場や倉庫なども多く、賑やかな繁華街の元町や三宮に比べると落ち着いた雰囲気・・・というか、何となくあか抜けない印象 σ(゚・゚*)ンー…。そんな当地は繁華街よりも宿泊施設の料金がリーズナブルに抑えられているようで、神戸観光などにおける穴場の宿泊地といえるかもしれません (*-∀-)ホホゥ(なお、兵庫はJR神戸線の上り普通列車で神戸まで一駅、三ノ宮まで3駅のところに位置していて意外と便利なんです)。
ちなみに今回の私がネットで選んだビジネスホテルのプランは、シングルルーム(ダブルベッド仕様で部屋の広さもとくに狭く感じない程度)の素泊まりで平日価格が一泊4,800円 (゚∀゚)オッ!。それだけでもじゅうぶんお安いと感じるのに、“全国旅行支援割引”が適用されて20%引きの3,840円となり (゚∀゚*)オオッ!!、さらに2,000円分のクーポン券まで貰えたので、実質は1,840円!? エッ!(゚Д゚≡゚∀゚)マジ!?。ビックリするほどおトクに泊まることができました。これは嬉しい (´艸`*)オトク♪。
山陽本線(JR神戸線)と
その支線の和田岬線が発着する兵庫。
両線の乗換口(連絡通路)には
和田岬線の専用改札が設けられていて、
無人駅である和田岬までの運賃は
ここで清算される仕組みとなっています。
(関東でいうところの“東武大師線システム”ね)
( ̄。 ̄)ヘー
▲山陽本線 兵庫
その支線の和田岬線が発着する兵庫。
両線の乗換口(連絡通路)には
和田岬線の専用改札が設けられていて、
無人駅である和田岬までの運賃は
ここで清算される仕組みとなっています。
(関東でいうところの“東武大師線システム”ね)
( ̄。 ̄)ヘー
▲山陽本線 兵庫
そんな兵庫の同じホテルに私は昨年(2022年)の8月にも宿泊をしており、その時の目的も和田岬線の103系を撮ることでした ( ̄  ̄)ワダミサキ。
和田岬線はここ兵庫で山陽本線(JR神戸線)と分岐し、港湾地区の和田岬にいたるわずか2.7キロの支線で、そこに今も使われているのが国鉄時代の通勤型電車、いわゆる“国電”の生き残りである103系です (゚ー゚*)コクデソ。当系は1970年代の製造からすでに半世紀(50年)が経っていて、たぶん先はそう長くないだろうな・・・σ(・∀・`)ウーン…と、うすうす引退が近いことを察して私は昨夏に撮影へ訪れたのですが (^_[◎]oパチリ、それから半年後となる先日(2/27)にやはり、3月18日に実施されるダイヤ改正をもって定期運用を終了(引退)する旨がJR西日本より発表されてしまいました (´・ω・`)ショボン。
和田岬線はここ兵庫で山陽本線(JR神戸線)と分岐し、港湾地区の和田岬にいたるわずか2.7キロの支線で、そこに今も使われているのが国鉄時代の通勤型電車、いわゆる“国電”の生き残りである103系です (゚ー゚*)コクデソ。当系は1970年代の製造からすでに半世紀(50年)が経っていて、たぶん先はそう長くないだろうな・・・σ(・∀・`)ウーン…と、うすうす引退が近いことを察して私は昨夏に撮影へ訪れたのですが (^_[◎]oパチリ、それから半年後となる先日(2/27)にやはり、3月18日に実施されるダイヤ改正をもって定期運用を終了(引退)する旨がJR西日本より発表されてしまいました (´・ω・`)ショボン。
その103系の引退発表とタイミングを合わせるかのように、たまたま私のもとへ舞い込んできたのが今回の関西出張 (゚∀゚)アヒャ☆。和田岬線は昨夏にも撮影しているとはいえ、引退記念の特別な“ヘッドマーク”を掲げた103系の姿を見ることができるのならば、それもまた記録に残したいと思うのが鉄ちゃんの性というものです (-`ω´-*)ウム。
そこで私は大阪での出張業務を終えた昨日(金曜日)の夕方にまず一度、当線の沿線を何か所か訪れて日が暮れるころまで撮影に没頭(先日に拙ブログの“ONE-shot”でご紹介したぶん)【◎】]ω・´)パチッ!。そして引退発表直後で最初の週末となる今日の土曜日は、おそらくたくさんの同業者(鉄ちゃん)が詰めかけることが予想されるため σ(゚・゚*)ンー…、沿線での撮影よりも103系に乗ることを優先して、混雑する時間帯の前に兵庫から和田岬まで片道だけの“惜別乗車”を味わうこととしました (・∀・)イイネ。つまり昨日は“撮り鉄”で、今日は“乗り鉄”といったところです ъ(゚Д゚)ナイス。
兵庫の主改札と連絡改札(中間改札)の二カ所でそれぞれにIC乗車券をタッチして (*・∀・)つ[西瓜]ピッ!(これで兵庫から和田岬までの運賃が精算されたことになります)、本線のJR神戸線とは別に設けられた和田岬線の専用ホームへ入ります。
そこで私は大阪での出張業務を終えた昨日(金曜日)の夕方にまず一度、当線の沿線を何か所か訪れて日が暮れるころまで撮影に没頭(先日に拙ブログの“ONE-shot”でご紹介したぶん)【◎】]ω・´)パチッ!。そして引退発表直後で最初の週末となる今日の土曜日は、おそらくたくさんの同業者(鉄ちゃん)が詰めかけることが予想されるため σ(゚・゚*)ンー…、沿線での撮影よりも103系に乗ることを優先して、混雑する時間帯の前に兵庫から和田岬まで片道だけの“惜別乗車”を味わうこととしました (・∀・)イイネ。つまり昨日は“撮り鉄”で、今日は“乗り鉄”といったところです ъ(゚Д゚)ナイス。
兵庫の主改札と連絡改札(中間改札)の二カ所でそれぞれにIC乗車券をタッチして (*・∀・)つ[西瓜]ピッ!(これで兵庫から和田岬までの運賃が精算されたことになります)、本線のJR神戸線とは別に設けられた和田岬線の専用ホームへ入ります。
イチマールサン、イタ━━━━m9( ゚∀゚)━━━━ッ!
和田岬線ホームで静かに発車を待っている、スカイブルー(青22号)の103系(R1編成)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。私にとって半年ぶりの再会ですが(昨日にも会っているけど)、既報のとおり今回はその車体の前後に引退を労う“ヘッドマーク”が取り付けられていて、前回とはちょっと異なる感傷的な気持ちになります (゚ーÅ)ホロリ。
和田岬線ホームで静かに発車を待っている、スカイブルー(青22号)の103系(R1編成)(=゚ω゚)ノ゙ヤア。私にとって半年ぶりの再会ですが(昨日にも会っているけど)、既報のとおり今回はその車体の前後に引退を労う“ヘッドマーク”が取り付けられていて、前回とはちょっと異なる感傷的な気持ちになります (゚ーÅ)ホロリ。
車内の中吊りスペースには
「どうも、スカイブルーでお馴染みの103系です」
というメッセージ風の文章で書かれた
103系から引退のご挨拶が掲出されていて
全文を読むとグッとくるものがあります・・・。
(´;ω;`)ウッ
「どうも、スカイブルーでお馴染みの103系です」
というメッセージ風の文章で書かれた
103系から引退のご挨拶が掲出されていて
全文を読むとグッとくるものがあります・・・。
(´;ω;`)ウッ
乗車するのは兵庫を7時48分に発車する和田岬ゆき下り列車(525M)で、平日ならば多くの通勤客で和田岬線が混雑する時間帯ですが土曜日の今日は少なめ。そのかわりホームや車内には一般の通勤利用者よりも、私と同様に103系の乗車や撮影に訪れた“鉄ちゃん”のほうが明らかに多く見られます (o ̄∇ ̄o)テツ。それでも写真で様子を見てお分かりのとおり、ファンがホームを埋め尽くすような“激パ”というほどの激しい混雑や混乱はなくて落ち着いている感じ ε-(´∀`*)ホッ。ヘッドマークを付けた先頭車の写真はふつうに難なく撮れたし (^_[◎]oパチリ、車内も運転室背後のいわゆる“かぶりつき”の立ち位置はファンでひしめき合っていたものの、それ以外の車両は座席に余裕があるくらい空いています (´ー`)マターリ。モーター(主電動機)の音を聴きたかった私はむしろ先頭車の“クハ”(制御車)を避けて、中間車の“モハ”(電動車)の座席に腰掛けました (゚ー゚*)モハ。
そしてまもなく“ぷしゅっ”と空気を抜いたような音とともにドアが“ガラガラ”閉まり、“ガクン”と動き出した103系は甲高い独特のモーター音を“ぐぅぅぅぅん…”って感じに響かせて、工場地帯の片隅に敷かれた単線を南に向かって突き進みます。ああ、その一挙一動一音のどれもが103系らしさなんだよなぁ・・・(*゚∀゚)=3ハァハァ!(マニアックだけど、わかる人にはわかるハズw)。
そしてまもなく“ぷしゅっ”と空気を抜いたような音とともにドアが“ガラガラ”閉まり、“ガクン”と動き出した103系は甲高い独特のモーター音を“ぐぅぅぅぅん…”って感じに響かせて、工場地帯の片隅に敷かれた単線を南に向かって突き進みます。ああ、その一挙一動一音のどれもが103系らしさなんだよなぁ・・・(*゚∀゚)=3ハァハァ!(マニアックだけど、わかる人にはわかるハズw)。
おもに工場地帯の殺風景なところを走る
和田岬線の車窓風景ですが、
沿線の公園にはピンク色の花が見られて
退役する103系の花道を
慎ましやかに彩っていました。
▲山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
(車窓から)
沿線でいちばんの見どころ(?)である
兵庫運河を鉄橋で渡ります。
(゚ー゚*)テッキョー
ちなみに前回の訪問時(半年前)に
拙ブログで少しご紹介していますが、
この鉄橋は橋脚を軸に橋桁が旋回する
旋回橋と呼ばれる珍しい構造です
(ただし現在は可動せずに固定状態)。
( ̄。 ̄)ヘー
▲山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
(車窓から)
その兵庫運河にか架かる
和田旋回橋を渡りゆく和田岬線の103系。
水辺の風景に青い国電がマッチします。
(・∀・)イイネ
▲23.3.3 山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
和田岬線の車窓風景ですが、
沿線の公園にはピンク色の花が見られて
退役する103系の花道を
慎ましやかに彩っていました。
▲山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
(車窓から)
沿線でいちばんの見どころ(?)である
兵庫運河を鉄橋で渡ります。
(゚ー゚*)テッキョー
ちなみに前回の訪問時(半年前)に
拙ブログで少しご紹介していますが、
この鉄橋は橋脚を軸に橋桁が旋回する
旋回橋と呼ばれる珍しい構造です
(ただし現在は可動せずに固定状態)。
( ̄。 ̄)ヘー
▲山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
(車窓から)
その兵庫運河にか架かる
和田旋回橋を渡りゆく和田岬線の103系。
水辺の風景に青い国電がマッチします。
(・∀・)イイネ
▲23.3.3 山陽本線(和田岬線)兵庫-和田岬
兵庫から和田岬まで一駅、2.7キロ、わずか4分という短い乗車時間。車窓からの眺めもさほどいい景色ではなく(ほとんど住宅地や工場地帯だからね・・・(^^;)ゞポリポリ)、しかも今回に限ってはぶっちゃけ、沿線で撮影をされている同業者の方たち(撮り鉄さん)ばかりが目に留まる印象だったけど (。A。)アヒャ☆、いい具合に弾む適度な揺れ加減(?)や耳に残るモーターとかブレーキなどの音といった体感で、昔から変わらない103系の走りをじっくりと噛みしめるように堪能。和田岬線から去りゆく当系の“惜別乗車”は、私の記憶に深く刻まれるものとなりました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
ひと駅だけ“国電”に揺られて
終点の和田岬に到着。
(・ω・)トーチャコ
ホームでは多くのファンが
思い思いに撮影されていました。
手前でスマホを構える少年鉄ちゃんも
ウマく撮れたかな?
(^_[◎]oパチリ
▲山陽本線(和田岬線)和田岬
終点の和田岬に到着。
(・ω・)トーチャコ
ホームでは多くのファンが
思い思いに撮影されていました。
手前でスマホを構える少年鉄ちゃんも
ウマく撮れたかな?
(^_[◎]oパチリ
▲山陽本線(和田岬線)和田岬
昭和時代の国電を代表する103系通勤型電車。それが令和のこの時代まで生き延びていたのは、あらためて考えるとスゴいことですよね w(*゚o゚*)wオオー!。都市圏を中心に走り続けて多くの人たちを運んだ半世紀、長年にわたる活躍おつかれさまでした (´w`*)ドツカレサン。
なお、103系はこの和田岬線からの引退で完全に形式消滅したわけではなく、同じく兵庫県の加古川線(3550番台)や播但線(3500番台)、九州の筑肥線(1500番台)などにまだ残されていますが、いずれも短編成化されたローカル線仕様となっており、“国電”と呼ばれた通勤型電車としての103系らしい使われかたは、この和田岬線からオリジナル車(0番台)が退役したことで一区切り付いたのかな・・・と個人的に思います (-`ω´-*)ウム(などと言いつつ、播但線などでまた103系を見たら、「国電の生き残り!」と言っちゃいそうだけど w)。
なお、103系はこの和田岬線からの引退で完全に形式消滅したわけではなく、同じく兵庫県の加古川線(3550番台)や播但線(3500番台)、九州の筑肥線(1500番台)などにまだ残されていますが、いずれも短編成化されたローカル線仕様となっており、“国電”と呼ばれた通勤型電車としての103系らしい使われかたは、この和田岬線からオリジナル車(0番台)が退役したことで一区切り付いたのかな・・・と個人的に思います (-`ω´-*)ウム(などと言いつつ、播但線などでまた103系を見たら、「国電の生き残り!」と言っちゃいそうだけど w)。
兵庫と同じく神戸市兵庫区内に所在する
和田岬線の終点・和田岬。
(゚ー゚*)ワダミサキ
基本的に朝夕しか列車が発着しない当駅は
ホームが一面のみの簡素な造りで、
2009年までは終端部に駅舎がありましたが
現在は撤去されています。
▲山陽本線(和田岬線)和田岬
和田岬線の終点・和田岬。
(゚ー゚*)ワダミサキ
基本的に朝夕しか列車が発着しない当駅は
ホームが一面のみの簡素な造りで、
2009年までは終端部に駅舎がありましたが
現在は撤去されています。
▲山陽本線(和田岬線)和田岬
兵庫0729-(和田岬線525M)-和田岬0733
さて、ここ和田岬は路線名(支線の通称名)にもなっている和田岬線の印象が強いですが、実はもうひとつ別の路線の駅も存在します。和田岬線の線路が途切れた終端の先を横切る幹線道路(国道?県道?)、その地下にあるのが神戸市営地下鉄・海岸線の和田岬駅 ( ̄  ̄*)チカテツ。
和田岬線で103系の惜別乗車を終えた私が次に乗るのは、この地下鉄です。
さて、ここ和田岬は路線名(支線の通称名)にもなっている和田岬線の印象が強いですが、実はもうひとつ別の路線の駅も存在します。和田岬線の線路が途切れた終端の先を横切る幹線道路(国道?県道?)、その地下にあるのが神戸市営地下鉄・海岸線の和田岬駅 ( ̄  ̄*)チカテツ。
和田岬線で103系の惜別乗車を終えた私が次に乗るのは、この地下鉄です。
地上の入口から地下の改札口へ進んでみると、103系を記録する多くのファンで賑わっていた和田岬線のホームに対し、こちらの駅は土曜日の朝ということもあって通勤客の姿も少なく、人影まばらで閑散とした雰囲気 シーー( ̄、 ̄*)ーーン。
ホームで待っているとまもなく、一般的なふつうの鉄道車両よりやや小ぶりなサイズの白い電車(5000形)が入ってきました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。海岸線は地下トンネルの断面が狭い構造のため、それに合わせた車両の規格も小さい、いわゆる“ミニ地下鉄”と呼ばれるもので(鉄輪式リニアモーターのミニ地下鉄)、東京の都営大江戸線や、大阪の長堀鶴見緑地線などと同様の方式です (o ̄∇ ̄o)ミニ。
ホームで待っているとまもなく、一般的なふつうの鉄道車両よりやや小ぶりなサイズの白い電車(5000形)が入ってきました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。海岸線は地下トンネルの断面が狭い構造のため、それに合わせた車両の規格も小さい、いわゆる“ミニ地下鉄”と呼ばれるもので(鉄輪式リニアモーターのミニ地下鉄)、東京の都営大江戸線や、大阪の長堀鶴見緑地線などと同様の方式です (o ̄∇ ̄o)ミニ。
神戸市営地下鉄は、新神戸と西神中央(せいしんちゅうおう)の間をむすぶ西神・山手線(西神延伸線・西神線・山手線の総称)をメイン路線として、新神戸と谷上(たにがみ)の間をむすぶ北神線、そして新長田(しんながた)と三宮・花時計前の間をむすぶ海岸線の三路線(正式には5路線)から成り、三宮(三宮・花時計前)を軸に神戸市の中心地から郊外のほうへ伸びる神戸市交通局の地下鉄路線 (・o・*)ホホゥ。なお、先述した“ミニ地下鉄”方式なのは海岸線のみで、その他の路線は一般鉄道と同じ規格(線路幅は標準軌)となっています。
和田岬の運賃表で見る
神戸市営地下鉄の路線図。
緑のラインが西神・山手線、
茶色いラインが北神線、
青いラインが海岸線です。
なお、右上の赤いラインは
当駅から連絡乗車券が購入できる
私鉄の神戸電鉄で、
神戸市営地下鉄の路線ではありません。
神戸市営地下鉄の路線図。
緑のラインが西神・山手線、
茶色いラインが北神線、
青いラインが海岸線です。
なお、右上の赤いラインは
当駅から連絡乗車券が購入できる
私鉄の神戸電鉄で、
神戸市営地下鉄の路線ではありません。
国内における“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私にとって地下鉄の路線ももちろん例外でなく、神戸市営地下鉄は西神・山手線(せいしん・やまてせん)も海岸線も過去に全区間を乗り潰して(完乗して)います (-`ω´-*)ウム。
ところがちょっと引っかかる存在なのが、上記の路線図(運賃表)で一区間だけ茶色いラインで表された“北神線”(ほくしんせん)(´・ω`・)エッ?。
ところがちょっと引っかかる存在なのが、上記の路線図(運賃表)で一区間だけ茶色いラインで表された“北神線”(ほくしんせん)(´・ω`・)エッ?。
実はこの北神線はもともと神戸市営地下鉄でなく、少し前までは“北神急行電鉄”という別会社の路線で、私はその北神急行として過去に北神線を踏破 ホクシソ(゚ー゚*)キューコー。
(ちなみに私はこの北神急行電鉄を兵庫県や神戸市などが出資する“第三セクター鉄道”なのだと思っていましたが、この記事を書くにあたって調べてみたところ、当鉄道は阪急電鉄や神戸電鉄などの出資によって設立された“民間の鉄道会社”で、中小私鉄(地方私鉄)に属していたのだそうです。)
(ちなみに私はこの北神急行電鉄を兵庫県や神戸市などが出資する“第三セクター鉄道”なのだと思っていましたが、この記事を書くにあたって調べてみたところ、当鉄道は阪急電鉄や神戸電鉄などの出資によって設立された“民間の鉄道会社”で、中小私鉄(地方私鉄)に属していたのだそうです。)
これは今から21年前の2002年、
私が北神急行の北神線を完乗した時に
終点の谷上で撮影した北神急行の7000系。
薄茶色の帯色が印象的でした。
なお当系は現在、
神戸市営地下鉄に編入されて、
西神・山手線を中心に使われているそうです
(ただし6000形への置き換え対象らしい)。
▲02.3 北神急行北神線 谷上
私が北神急行の北神線を完乗した時に
終点の谷上で撮影した北神急行の7000系。
薄茶色の帯色が印象的でした。
なお当系は現在、
神戸市営地下鉄に編入されて、
西神・山手線を中心に使われているそうです
(ただし6000形への置き換え対象らしい)。
▲02.3 北神急行北神線 谷上
駄菓子菓子(だがしかし)、神戸の中心地(中央区など)と北部地域(北区など)をむすぶ目的で1988年に開通した北神急行電鉄の北神線は、六甲山地を長大なトンネル(7,276mの北神トンネル)で貫く建設費用が高額に嵩んだため、乗車運賃の設定が高くなり(最高額のときは新神戸〜谷上の一駅間7.5キロで430円。参考までにJRならば同距離で180円)Σ(゚∇゚;)タカッ!、そのことなどを理由に利用者数が伸び悩んで苦しい経営状況に陥ります (´д`;)アウ…。そんななか神戸市は、北部地域の郊外開発や活性化、住民人口の増加を図ることを目的に、北神急行の事業を市が譲り受けて交通局による運営(市営化)とし、運賃の引き下げを提言。それを受けて北神線は2020年6月に北神急行から神戸市営地下鉄の路線となったのです ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。なお、市営化に伴って新神戸〜谷上の運賃は路線譲渡前の370円から280円に、新神戸を境に別会社扱いで運賃が加算されていた三宮〜谷上などは550円から280円にまで引き下げられました(2020年当時)(´艸`*)ヤスイ。
そんな北神線を私は北神急行の時代に一度乗っているので、まったくの未乗路線ではないけれど、このように譲渡などで運営が変わった路線はできるだけもう一度乗り直して整理し、気持ち的にスッキリしたいところ (-c_-´。)ウミュ。
そこで今回は和田岬線で103系の惜別乗車を終えたあと、和田岬から海岸線の三宮・花時計前ゆきに乗り、同じく神戸市営地下鉄の西神・山手線を経て、北神線を訪れることにしたのでした ...(((o*・ω・)o。
そこで今回は和田岬線で103系の惜別乗車を終えたあと、和田岬から海岸線の三宮・花時計前ゆきに乗り、同じく神戸市営地下鉄の西神・山手線を経て、北神線を訪れることにしたのでした ...(((o*・ω・)o。
海岸線で終点の三宮・花時計前に到着。
ランドマークとなるような花時計が
駅の近くにあるのかと思っちゃいますが、
(*’∀’*)ハナドケイ?
実際はかつて神戸市役所にあったものだそうで
現在の花時計は別の場所(遊園地)に
移設されたらしい。
▲神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計前
海岸線の三宮・花時計前と
西神・山手線の三宮は少し離れており、
両線の乗換えにはいったん改札を出て
地下街を通り抜けます。
移動に要する時間は5分程度。
...(((o*・ω・)o
▲神戸市営地下鉄山手線 三宮
ランドマークとなるような花時計が
駅の近くにあるのかと思っちゃいますが、
(*’∀’*)ハナドケイ?
実際はかつて神戸市役所にあったものだそうで
現在の花時計は別の場所(遊園地)に
移設されたらしい。
▲神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計前
海岸線の三宮・花時計前と
西神・山手線の三宮は少し離れており、
両線の乗換えにはいったん改札を出て
地下街を通り抜けます。
移動に要する時間は5分程度。
...(((o*・ω・)o
▲神戸市営地下鉄山手線 三宮
神戸市でいちばんの賑わいをみせる繁華街の三宮は、神戸市営地下鉄のほか、JR神戸線(三ノ宮駅)、阪神本線、阪急神戸線、神戸高速鉄道(神戸三宮駅)、神戸新交通ポートライナーなどの各線が発着する交通の要衝 (゚ー゚*)サンノミヤ。
ここで私は海岸線から西神・山手線と北神線を直通する谷上ゆきに乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。なお、上写真の発車標に表示されているように、三宮から谷上方面へ向かう列車の半分以上は新神戸止まりで、谷上まで行くのは三本に一本程度といった感じです ( ̄  ̄*)ジジハツ。
ここで私は海岸線から西神・山手線と北神線を直通する谷上ゆきに乗り換えます ノリカエ…((((o* ̄-)o。なお、上写真の発車標に表示されているように、三宮から谷上方面へ向かう列車の半分以上は新神戸止まりで、谷上まで行くのは三本に一本程度といった感じです ( ̄  ̄*)ジジハツ。
先行する新神戸ゆきを見送り、
少し待ってやってきた谷上ゆきは
西神・山手線のラインカラーである
緑色の前面デザインが印象的な6000形。
(゚ー゚*)ミドリ
▲神戸市営地下鉄山手線 三宮
山陽新幹線への乗換駅でもある新神戸が
西神・山手線と北神線の接続駅。
谷上ゆきの直通列車に乗っているので
下車することなく車窓から
ホーム上の駅名標を記録します。
(^_[◎]oパチリ
▲神戸市営地下鉄山手線 新神戸(車窓から)
少し待ってやってきた谷上ゆきは
西神・山手線のラインカラーである
緑色の前面デザインが印象的な6000形。
(゚ー゚*)ミドリ
▲神戸市営地下鉄山手線 三宮
山陽新幹線への乗換駅でもある新神戸が
西神・山手線と北神線の接続駅。
谷上ゆきの直通列車に乗っているので
下車することなく車窓から
ホーム上の駅名標を記録します。
(^_[◎]oパチリ
▲神戸市営地下鉄山手線 新神戸(車窓から)
三宮から谷上ゆきに乗って一駅目の新神戸までが西神・山手線で、これより先・・・といっても一駅だけなのですが、新神戸から谷上までが北神線となり、いちおう私にとっては乗り潰し(乗り直し)の対象となる区間へ足を踏み入れます (゚∀゚)オッ!。
ただし、三宮など都市部の地下を走ってきた西神・山手線も、六甲山地を北神トンネルで貫く北神線も、地下トンネルと山岳トンネルという違いはあれど、列車は引き続き暗闇のなか(トンネルのなか)を進むことに変わりはありません ( ̄  ̄)マックラケ。
ただし、三宮など都市部の地下を走ってきた西神・山手線も、六甲山地を北神トンネルで貫く北神線も、地下トンネルと山岳トンネルという違いはあれど、列車は引き続き暗闇のなか(トンネルのなか)を進むことに変わりはありません ( ̄  ̄)マックラケ。
これは三宮駅の壁に貼ってあった
神戸市営地下鉄の蘊蓄のひとつ。
ずっとトンネルのなかを走っているので
あまり実感はわきませんが、
新神戸と谷上の標高差は
ほぼ200メートルもあるらしい
(谷上のほうが高い)。
( ̄。 ̄)ヘー
神戸市営地下鉄の蘊蓄のひとつ。
ずっとトンネルのなかを走っているので
あまり実感はわきませんが、
新神戸と谷上の標高差は
ほぼ200メートルもあるらしい
(谷上のほうが高い)。
( ̄。 ̄)ヘー
余談ながら、私は乗った列車の車窓に流れる景色を眺めることが好きで、その面白さからJRや私鉄などの全線を完乗するにいたったのですが、車窓の大半がトンネル(地下区間)という地下鉄路線の乗り潰しはさすがに楽しさよりも苦労した印象のほうが強く残っています σ(・∀・`)ウーン…。ふだんの私の生活圏である東京の地下鉄は機を見て各線をこまめに片付けられたけど、大阪や名古屋などの地下鉄はそこを訪れた際に複数の路線を一気に乗り潰したため、車窓が真っ暗な地下鉄に一日中ずっと乗っているのはかなりキツいものがありました クライヨ(´д`;)セマイヨ。さしずめそれは全線完乗を達成するために課せられた、“苦行”といったところか (-"-;*)ウググ…(地下鉄で使われている車両は趣味的に好きなんだけどね)。ちなみに神戸の地下鉄は距離がけっこう長いものの、直通運転している西神延伸線・西神線・山手線・北神線を一本と考えれば路線数は少ないので、乗り潰しは楽なほうです。郊外では地下から外にも出るし。
六甲山に掘られた北神トンネルを抜けると
北神線は外へ出ます。
(つ▽≦*)マブシッ!
車窓の左手(北側)に並行する線路は
神戸電鉄有馬線のもの。
▲神戸市営地下鉄北神線 新神戸-谷上
(車窓から)
谷上のホームの先端より望んでみた
北神トンネルから出てきた6000形。
なお、線路が三線ありますが
向かって左から上り線、下り線で
いちばん右は車庫へ通じる回送線です。
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
北神線は外へ出ます。
(つ▽≦*)マブシッ!
車窓の左手(北側)に並行する線路は
神戸電鉄有馬線のもの。
▲神戸市営地下鉄北神線 新神戸-谷上
(車窓から)
谷上のホームの先端より望んでみた
北神トンネルから出てきた6000形。
なお、線路が三線ありますが
向かって左から上り線、下り線で
いちばん右は車庫へ通じる回送線です。
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
新神戸から7.5キロ、標高差200メートルの登坂を、都市路線(地下鉄路線)の一駅間としては長く感じる8分の所要時間をかけて、北神線はまもなく終点の谷上に着きます (゚∀゚)オッ!。その直前に列車がトンネルから外へ出ると、車窓に見える景色は北神地域(神戸北部)の山々が近くて、自然豊かな郊外らしい街なみの雰囲気が印象的に感じられました (´ω`)シミジミ。
終点の谷上に到着。
当駅の標高は244メートルで、
地上駅ではあるものの
日本の地下鉄路線に属する駅としては
最高地点になります。
( ̄。 ̄)ヘー
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
谷上は北神線と神戸電鉄有馬線の接続駅。
(゚ー゚*)シンテツ
両線は一部の列車において
(おもに日中の時間帯)
同一ホームによる対面での乗り換えが
可能となっています。
到着した北神線の接続を待っていた有馬線は
2000系の三田ゆき準急列車。
▲神戸電鉄有馬線 谷上
そんな北神線と有馬線が接続する
ホーム上の西端に建てられているのが
「山の家 ロッジ谷上」。
( ̄  ̄*)ロッジ
これは当駅を利用するハイカーの
交流の場として設けられたスペースで、
室内には沿線の登山コースや
ハイキングコースのマップなどが
常備されています。
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
そのロッジの壁面に掲げられた
谷上駅の案内には
北神線が北神急行から神戸市交通局へ
移管されたことも記されていました。
(・o・*)ホホゥ
当駅の標高は244メートルで、
地上駅ではあるものの
日本の地下鉄路線に属する駅としては
最高地点になります。
( ̄。 ̄)ヘー
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
谷上は北神線と神戸電鉄有馬線の接続駅。
(゚ー゚*)シンテツ
両線は一部の列車において
(おもに日中の時間帯)
同一ホームによる対面での乗り換えが
可能となっています。
到着した北神線の接続を待っていた有馬線は
2000系の三田ゆき準急列車。
▲神戸電鉄有馬線 谷上
そんな北神線と有馬線が接続する
ホーム上の西端に建てられているのが
「山の家 ロッジ谷上」。
( ̄  ̄*)ロッジ
これは当駅を利用するハイカーの
交流の場として設けられたスペースで、
室内には沿線の登山コースや
ハイキングコースのマップなどが
常備されています。
▲神戸市営地下鉄北神線 谷上
そのロッジの壁面に掲げられた
谷上駅の案内には
北神線が北神急行から神戸市交通局へ
移管されたことも記されていました。
(・o・*)ホホゥ
これにて北神急行あらため、神戸市営地下鉄の北神線を完乗 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
新規に開業した新路線の“乗り潰し”でなく、運営が変わった既存路線の“乗り直し”、しかも昨日にやはり乗り直しをした梅田貨物線のように移設などでルートが変更されたワケでもないので、新鮮味が薄くて達成感はあまり湧かないけれど σ(゚・゚*)ンー…、それでも全線完乗にこだわる者としてはスッキリとした気分です (*´v`*)スッキリ。
ちなみに私が谷上の駅で下車する(改札を出る)のは、北神急行を乗り潰した前回のとき以来となる21年ぶりのことでした (*´∀`)ノ゙オヒサ(そのブランクの間にも神戸電鉄の列車で当駅を通ってはいるけど)。
新規に開業した新路線の“乗り潰し”でなく、運営が変わった既存路線の“乗り直し”、しかも昨日にやはり乗り直しをした梅田貨物線のように移設などでルートが変更されたワケでもないので、新鮮味が薄くて達成感はあまり湧かないけれど σ(゚・゚*)ンー…、それでも全線完乗にこだわる者としてはスッキリとした気分です (*´v`*)スッキリ。
ちなみに私が谷上の駅で下車する(改札を出る)のは、北神急行を乗り潰した前回のとき以来となる21年ぶりのことでした (*´∀`)ノ゙オヒサ(そのブランクの間にも神戸電鉄の列車で当駅を通ってはいるけど)。
和田岬0816-(神戸市営海岸線)-三宮・花時計前0824…三宮0842-(神戸市営西神・山手線 北神線)-谷上0852
さてさてせっかくここまで来たのなら、神戸電鉄の有馬線に乗り換えて有馬温泉にでも行きたくなるところですが (・∀・)イイネ、本日の目的だった和田岬線や北神線をなるべく身軽な格好で効率よく巡ろうと思って、数日分の着替えや仕事道具などが入った重いキャリーバックを宿泊したホテルの部屋に置いてきた私は、チェックアウトの時刻までに兵庫へ戻らねばなりません。なので、神戸電鉄に乗ることや有馬温泉のお湯に浸かることはまたの機会として、谷上からは三宮方面へ折り返しとなる北神線の西神中央ゆきに乗りこみます モドル…((((o* ̄-)o。
それでも今旅(?)は、地上から地下へ移設された梅田貨物線を特急「はるか」で通過し、引退が間近に迫った和田岬線の103系を撮影し、さらには近年に運営が変わった神戸市営地下鉄の北神線を乗り直すこともできて、ついつい “仕事の出張のついで” であることを忘れてしまうくらい充実した鉄道趣味の時間を存分に楽しむことができました ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
谷上0910-(神戸市営北神線 西神・山手線)-三宮0919…三ノ宮0932-(東海道143C)-兵庫0939
さてさてせっかくここまで来たのなら、神戸電鉄の有馬線に乗り換えて有馬温泉にでも行きたくなるところですが (・∀・)イイネ、本日の目的だった和田岬線や北神線をなるべく身軽な格好で効率よく巡ろうと思って、数日分の着替えや仕事道具などが入った重いキャリーバックを宿泊したホテルの部屋に置いてきた私は、チェックアウトの時刻までに兵庫へ戻らねばなりません。なので、神戸電鉄に乗ることや有馬温泉のお湯に浸かることはまたの機会として、谷上からは三宮方面へ折り返しとなる北神線の西神中央ゆきに乗りこみます モドル…((((o* ̄-)o。
それでも今旅(?)は、地上から地下へ移設された梅田貨物線を特急「はるか」で通過し、引退が間近に迫った和田岬線の103系を撮影し、さらには近年に運営が変わった神戸市営地下鉄の北神線を乗り直すこともできて、ついつい “仕事の出張のついで” であることを忘れてしまうくらい充実した鉄道趣味の時間を存分に楽しむことができました ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
谷上0910-(神戸市営北神線 西神・山手線)-三宮0919…三ノ宮0932-(東海道143C)-兵庫0939
そしてもうひとつオマケに“嬉しいご褒美”だったのが、ホテルでチェックインした際に貰えた旅行支援による2,000円分もの“地域クーポン券” (゚∀゚*)オオッ!。宿泊地となる兵庫県内のお店でのみ有効なこのクーポン券をありがたく使わせていただき、三宮あたりのお店で昼食に美味しいものでも食べてから新幹線で東京へ帰ることとしましょうか (σ´∀`)σイイネ。
今回は金曜日にチェックインした
平日の宿泊だったので、
2,000円分もクーポン券がもらえました。
ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪
(ちなみに土休日だと1,000円分)
そのクーポン券+αで
お昼はちょっとリッチにレストランで
神戸ビーフのランチメニューを
いただいちゃいました。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ
お飲物は赤のグラスワインで
梅田貨物線と北神線の完乗を祝し・・・
いや、出張業務の打ち上げに乾杯っ!
ルネッサーンス♪(〃゚∇゚)_Y
平日の宿泊だったので、
2,000円分もクーポン券がもらえました。
ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪
(ちなみに土休日だと1,000円分)
そのクーポン券+αで
お昼はちょっとリッチにレストランで
神戸ビーフのランチメニューを
いただいちゃいました。
(〃゚¬゚〃)ジュルリ
お飲物は赤のグラスワインで
梅田貨物線と北神線の完乗を祝し・・・
いや、出張業務の打ち上げに乾杯っ!
ルネッサーンス♪(〃゚∇゚)_Y
2023-03-27 15:15
梅田貨物線・・・うめきた新線 乗車記 [鉄道乗車記]
拙ブログの前記事(短編のONE-shot)で少し触れたように、3月の第一週目に仕事の出張で関西のほうへ赴いた私 シュッチョ…((((o* ̄-)o。もちろん仕事の業務が最優先なのは言うまでもないけれど、せっかくならそのついでに(?)鉄道趣味のほうもちょろっと(??)愉しみたいところです ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。
いまの関西で“撮り鉄”としての私が注目したのは、先日に退役が発表された和田岬線の103系(R1編成)でしたが (゚ー゚*)コクデン、実は“乗り鉄”的にも関心を惹かれる路線・・・というか“区間”があります σ(゚・゚*)ンー…。しかもそれは“少しだけ乗車経路を工夫すれば”、訪問先(仕事先)への移動に組み込むことができそう ( -∀-)ホホウ。
そこでこの機会をウマく活かして(公私混同?w)、その気になる区間を通る列車に乗ってみることとしました (・∀・)イイネ。
(*今回の記事は列車から眺めた車窓の景色ばかりという、いつもに増してマニアックな内容となっていますので、興味の無い方はスルーしてください。(^^;)ゞ)
3月3日(金)
前日から京都に滞在していた出張の二日目。きょうは午前中のみ京都で仕事をして、午後には大阪へ移動するという日程です ( ̄  ̄*)オーサカ。
京都と大阪のあいだを鉄道路線で移動するには、東海道新幹線をはじめ、JR京都線(東海道本線)、京阪本線、阪急京都線など、路線別にいくつかの経路がありますが、今回の私が選んだのはJR京都線 (゚ー゚*)尺。ただし快速や新快速でなく、乗るのはこちらの列車 (=゚ω゚=*)ンン!?。
いまの関西で“撮り鉄”としての私が注目したのは、先日に退役が発表された和田岬線の103系(R1編成)でしたが (゚ー゚*)コクデン、実は“乗り鉄”的にも関心を惹かれる路線・・・というか“区間”があります σ(゚・゚*)ンー…。しかもそれは“少しだけ乗車経路を工夫すれば”、訪問先(仕事先)への移動に組み込むことができそう ( -∀-)ホホウ。
そこでこの機会をウマく活かして(公私混同?w)、その気になる区間を通る列車に乗ってみることとしました (・∀・)イイネ。
(*今回の記事は列車から眺めた車窓の景色ばかりという、いつもに増してマニアックな内容となっていますので、興味の無い方はスルーしてください。(^^;)ゞ)
3月3日(金)
前日から京都に滞在していた出張の二日目。きょうは午前中のみ京都で仕事をして、午後には大阪へ移動するという日程です ( ̄  ̄*)オーサカ。
京都と大阪のあいだを鉄道路線で移動するには、東海道新幹線をはじめ、JR京都線(東海道本線)、京阪本線、阪急京都線など、路線別にいくつかの経路がありますが、今回の私が選んだのはJR京都線 (゚ー゚*)尺。ただし快速や新快速でなく、乗るのはこちらの列車 (=゚ω゚=*)ンン!?。
京都駅の“30番線”という
大きな数字のプラットホームには
車体に“キティちゃん”がデザインされた
特急列車が停車しています。
ハロー(*’∀’*)キティ♡
▲東海道本線 京都
281系の特急「はるか29号」
関西空港ゆき。
え?大阪までこれに乗ってくの?
エッ!(゚Д゚≡゚∀゚)マジ!?
▲東海道本線 京都
大きな数字のプラットホームには
車体に“キティちゃん”がデザインされた
特急列車が停車しています。
ハロー(*’∀’*)キティ♡
▲東海道本線 京都
281系の特急「はるか29号」
関西空港ゆき。
え?大阪までこれに乗ってくの?
エッ!(゚Д゚≡゚∀゚)マジ!?
▲東海道本線 京都
キティはるか、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!
昼下がりの京都で発車を待っていたのは、車体に“キティちゃん”(Hello Kitty)のデザインが賑々しく施された281系で、大阪湾にある関西空港へのアクセスを担うことから“関空特急”とも呼ばれる、関西空港ゆきの特急「はるか」(゚ー゚*)ハルカクリスティーン。
ちなみにキティちゃんがデザインされているのは、「関空を利用する海外からの観光客に人気の高いキティちゃんで“おもてなし”をする」というコンセプトのコラボ企画(JR西日本×サンリオ)だそうで、2019年より運行されているもの ( ̄。 ̄)ヘー。そんな特別仕様の“キティはるか”にどうしても乗りたかったのよ (*´v`*)ワクワク♪・・・というほど、私はキティちゃん好きではありません ヾノ・∀・`)イヤイヤ。キティ仕様の281系に当たったのは単なる偶然です(今は全編成がこの仕様なんだっけ?)。
昼下がりの京都で発車を待っていたのは、車体に“キティちゃん”(Hello Kitty)のデザインが賑々しく施された281系で、大阪湾にある関西空港へのアクセスを担うことから“関空特急”とも呼ばれる、関西空港ゆきの特急「はるか」(゚ー゚*)ハルカクリスティーン。
ちなみにキティちゃんがデザインされているのは、「関空を利用する海外からの観光客に人気の高いキティちゃんで“おもてなし”をする」というコンセプトのコラボ企画(JR西日本×サンリオ)だそうで、2019年より運行されているもの ( ̄。 ̄)ヘー。そんな特別仕様の“キティはるか”にどうしても乗りたかったのよ (*´v`*)ワクワク♪・・・というほど、私はキティちゃん好きではありません ヾノ・∀・`)イヤイヤ。キティ仕様の281系に当たったのは単なる偶然です(今は全編成がこの仕様なんだっけ?)。
んじゃ「はるか」を選んだのは、次に向かう訪問先が大阪のなかでもちょっと郊外のほうにある泉佐野市(大阪府南部)のあたりで、阪和線へ直通する「はるか」を使えば移動が便利だから?σ(゚・゚*)ンー…・・・という、もっともそうな理由でもなく、大阪での目的地(訪問先の最寄駅)は中心部に位置する地下鉄の心斎橋(しんさいばし)で、発券した「はるか」のきっぷ(乗車券と特急券)は大阪市内の天王寺(てんのうじ)まで (*・ω・)つ[キップ] 。
ちなみに京都から天王寺までの乗車券は940円で、特急券(B自由席特急券)は990円。
倍以上のお金をかけてこの区間を特急列車で移動するとは、何ともリッチなことじゃありませんか (´∇ノ`*)オホホホホ。不必要に特急へ乗って無駄に出張経費を使おうなんて企んでいる? (´・ω`・)エッ?。重役ならまだしもヒラ社員の私がこんな精算書を提出したら経理課に怒られるぞ (゚Д゚#)ゴルァ!!。いえいえ経費の無駄遣いだなんて滅相もない、移動に必要な乗車券はたしかに経費での購入ですが、特急券のほうは別に“自腹”で買っています (-`ω´-*)ウム。
そうまでして私が「はるか」に乗りたかったのは、“今はまだ”この特急列車じゃないと通らない区間があるからなんです。それは先日に地下化されたばかりの、“うめきた新線”こと「梅田貨物線」 (o ̄∇ ̄o)ウメキタ。
倍以上のお金をかけてこの区間を特急列車で移動するとは、何ともリッチなことじゃありませんか (´∇ノ`*)オホホホホ。不必要に特急へ乗って無駄に出張経費を使おうなんて企んでいる? (´・ω`・)エッ?。重役ならまだしもヒラ社員の私がこんな精算書を提出したら経理課に怒られるぞ (゚Д゚#)ゴルァ!!。いえいえ経費の無駄遣いだなんて滅相もない、移動に必要な乗車券はたしかに経費での購入ですが、特急券のほうは別に“自腹”で買っています (-`ω´-*)ウム。
そうまでして私が「はるか」に乗りたかったのは、“今はまだ”この特急列車じゃないと通らない区間があるからなんです。それは先日に地下化されたばかりの、“うめきた新線”こと「梅田貨物線」 (o ̄∇ ̄o)ウメキタ。
路線図上の赤いラインで示した
特急「はるか」の運行経路
(クリックで拡大します)。
関西空港ゆきの下り列車は
京都から新大阪、天王寺、日根野を経て
関西空港へと至ります。
なお後述しますが、
現在はまだ大阪には停車しません。
特急「はるか」の運行経路
(クリックで拡大します)。
関西空港ゆきの下り列車は
京都から新大阪、天王寺、日根野を経て
関西空港へと至ります。
なお後述しますが、
現在はまだ大阪には停車しません。
東海道本線の支線扱いである梅田貨物線は、本線(JR京都線)の茨木(いばらき)付近で分岐し(正式な起点は吹田貨物ターミナル)、最近まで大阪駅の北側に位置していた梅田信号場(旧・梅田貨物駅)を経て、“大阪駅を通らずに”大阪環状線の西九条(にしくじょう)へといたる電化路線 (・o・*)ホホゥ。
“貨物線”と呼ばれるとおり当線はもともと、旅客列車の発着が多い大阪駅を通さずに、迂回して貨物列車を運行させるためのバイパス的な役割を持つ(おもに東海道方面と桜島線の安治川口をむすぶ)、いわゆる“短絡線”として設けられたもの。しかし現在は本来の用途である貨物列車だけでなく、京都や新大阪を発着駅として関西空港とのあいだを結ぶ特急「はるか」、または和歌山・南紀方面とのあいだを結ぶ特急「くろしお」などといった、定期旅客列車の運行ルートとしても活用されています ( ̄。 ̄)ヘー。
そして最近、広大な敷地を持っていた梅田貨物駅の廃止による大阪駅北側エリア(梅田北・うめきたエリア)の大規模な再開発事業の一環として、当線はそれまでの地上線から地下線へ線路の切り替え工事(移設)を実施 (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…。そこには大阪駅と連絡通路で直結した新たな旅客用の地下ホームが設けられ (゚∀゚*)オオッ!、まもなく今月(3月)の18日に行われるダイヤ改正に合わせて開業することとなりました (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。
ちなみに建設当初はこの新たな地下ホームを「北梅田」とか「うめきた」などという駅名の新駅になるのではないかとされていましたが σ(゚・゚*)ンー…、大阪駅と繋がっていることから当駅に属する地下ホームとして取り扱うこととし、「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」の呼称が用いられるそうです ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
“貨物線”と呼ばれるとおり当線はもともと、旅客列車の発着が多い大阪駅を通さずに、迂回して貨物列車を運行させるためのバイパス的な役割を持つ(おもに東海道方面と桜島線の安治川口をむすぶ)、いわゆる“短絡線”として設けられたもの。しかし現在は本来の用途である貨物列車だけでなく、京都や新大阪を発着駅として関西空港とのあいだを結ぶ特急「はるか」、または和歌山・南紀方面とのあいだを結ぶ特急「くろしお」などといった、定期旅客列車の運行ルートとしても活用されています ( ̄。 ̄)ヘー。
そして最近、広大な敷地を持っていた梅田貨物駅の廃止による大阪駅北側エリア(梅田北・うめきたエリア)の大規模な再開発事業の一環として、当線はそれまでの地上線から地下線へ線路の切り替え工事(移設)を実施 (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…。そこには大阪駅と連絡通路で直結した新たな旅客用の地下ホームが設けられ (゚∀゚*)オオッ!、まもなく今月(3月)の18日に行われるダイヤ改正に合わせて開業することとなりました (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。
ちなみに建設当初はこの新たな地下ホームを「北梅田」とか「うめきた」などという駅名の新駅になるのではないかとされていましたが σ(゚・゚*)ンー…、大阪駅と繋がっていることから当駅に属する地下ホームとして取り扱うこととし、「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」の呼称が用いられるそうです ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
そんな梅田貨物線、大阪駅うめきたエリア地下ホームの使用開始日(開業日)は半月後の18日でもうちょい先のことですが (´ω`)マダヨ、地上線から地下線へ線路を切り替える移設工事はいち早く2月13日に完了しており、すでに特急「はるか」や「くろしお」などは新ホームにまだ停車こそしないものの、新たな地下線のほうを使用して運行されています (・o・*)ホホゥ。
JRや私鉄など国内における“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私にとって、たとえ名称(通称)は“貨物線”であっても定期の旅客列車が一本でも運行されている路線や区間に関しては“乗り潰し”の踏破対象としており、当然この梅田貨物線もそれに含まれます (-`ω´-*)ウム。
そこで今回は当線を経由する特急「はるか」に乗車して、地下に移設となった区間をあらためて乗り潰そうと考えたのでした (゚ー゚*)ノリテツ。ちなみに私は地下化される以前の梅田貨物駅を経由する同線はすでに乗車済みで、そのときもわざわざ京都から「はるか」に乗ったっけ。
前置きが長くなりましたが、そのような目的の私を乗せた特急「はるか29号」は、定刻の13時ちょうどに京都を発車しました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
JRや私鉄など国内における“旅客鉄道路線の全線完乗(完全乗車)”を生涯の目標(?)としている私にとって、たとえ名称(通称)は“貨物線”であっても定期の旅客列車が一本でも運行されている路線や区間に関しては“乗り潰し”の踏破対象としており、当然この梅田貨物線もそれに含まれます (-`ω´-*)ウム。
そこで今回は当線を経由する特急「はるか」に乗車して、地下に移設となった区間をあらためて乗り潰そうと考えたのでした (゚ー゚*)ノリテツ。ちなみに私は地下化される以前の梅田貨物駅を経由する同線はすでに乗車済みで、そのときもわざわざ京都から「はるか」に乗ったっけ。
前置きが長くなりましたが、そのような目的の私を乗せた特急「はるか29号」は、定刻の13時ちょうどに京都を発車しました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
嵯峨野線(山陰本線)のホームに隣接した
30番線を発車した「はるか」。
京都を出るとすぐ
右のほうに嵯峨野線が分かれてゆきます。
その向こうにちらっと見える梅小路公園では
梅の花が見ごろを迎えている様子。
( ̄∇ ̄)ウメ
▲東海道本線 京都-西大路
(進行方向で右の車窓)
先日には高崎線の窓から
大宮の鉄道博物館をチラ見しましたが
こちらは「はるか」の車窓から見た
「京都鉄道博物館」の建物。
キョート(゚ー゚*)テッパク
▲東海道本線 京都-西大路
(進行方向で右の車窓)
京都を発車後は配線の関係でしばらく
本線と並行する貨物線のほうを走行します。
(*・`o´・*)ホ─
左手の南側に見えるのが本線(JR京都線)で
通過している駅は西大路。
( ̄  ̄*)ニシオージ
▲東海道本線 西大路
(進行方向で左の車窓)
桂川の手前で「はるか」が走る貨物線は
複々線の本線を一気に跨ぎます。
▲東海道本線 西大路-桂川
(進行方向で右の車窓)
今度は右のほう(北側)に本線の複々線を見て
向日町の手前付近で外側の下り列車線に合流。
新快速などと同様に向日町のホームを通過します。
バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ
▲東海道本線 向日町
(進行方向で右の車窓)
ちなみに向日町といえば
鉄ちゃんとして車窓からチェックしたいのが
車両基地の「吹田総合車両所 京都支所」
(旧・京都総合運転所)。
(「゚ー゚)ドレドレ
特急「くろしお」用の289系や
「WEST EXPRESS 銀河」用の117系などが
構内に確認できました。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 向日町-長岡京
(進行方向で左の車窓)
30番線を発車した「はるか」。
京都を出るとすぐ
右のほうに嵯峨野線が分かれてゆきます。
その向こうにちらっと見える梅小路公園では
梅の花が見ごろを迎えている様子。
( ̄∇ ̄)ウメ
▲東海道本線 京都-西大路
(進行方向で右の車窓)
先日には高崎線の窓から
大宮の鉄道博物館をチラ見しましたが
こちらは「はるか」の車窓から見た
「京都鉄道博物館」の建物。
キョート(゚ー゚*)テッパク
▲東海道本線 京都-西大路
(進行方向で右の車窓)
京都を発車後は配線の関係でしばらく
本線と並行する貨物線のほうを走行します。
(*・`o´・*)ホ─
左手の南側に見えるのが本線(JR京都線)で
通過している駅は西大路。
( ̄  ̄*)ニシオージ
▲東海道本線 西大路
(進行方向で左の車窓)
桂川の手前で「はるか」が走る貨物線は
複々線の本線を一気に跨ぎます。
▲東海道本線 西大路-桂川
(進行方向で右の車窓)
今度は右のほう(北側)に本線の複々線を見て
向日町の手前付近で外側の下り列車線に合流。
新快速などと同様に向日町のホームを通過します。
バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ
▲東海道本線 向日町
(進行方向で右の車窓)
ちなみに向日町といえば
鉄ちゃんとして車窓からチェックしたいのが
車両基地の「吹田総合車両所 京都支所」
(旧・京都総合運転所)。
(「゚ー゚)ドレドレ
特急「くろしお」用の289系や
「WEST EXPRESS 銀河」用の117系などが
構内に確認できました。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 向日町-長岡京
(進行方向で左の車窓)
京都で「はるか」が発着に使用する専用ホーム(30番線)は、構内の配線等による都合でJR京都線の下り本線(大阪方面)へ簡単に入ることができず σ(゚・゚*)ンー…、当列車はまず嵯峨野線(山陰本線)の線路を通って京都を出発し、京都貨物駅(旧・梅小路貨物駅)の構内からは本線(JR京都線)と並行する貨物線のほうを走行。桂川(かつらがわ)付近で本線をオーバークロスしたのち、向日町(むこうまち)の手前で本線(外側の列車線)の下り線へ合流するという複雑な経路を走ります (*・`o´・*)ホ─。
今回の目的はこの先の茨木付近で分岐する梅田貨物線だけど、京都から向日町までの経路も「はるか」の下り列車でなければ乗ることができないマニアックな区間で、乗り鉄としては車窓から目が離せません (*゚∀゚)=3ハァハァ!。右の車窓を見たり、左の車窓を見たり、列車が転線するたびにちょろちょろと座席を移動して落ち着きありませんが アッチo(゚д゚o≡o゚д゚)oコッチ、平日の昼過ぎに京都から関西空港へと向かう「はるか29号」は利用者が少ないようで、なんと先頭車の自由席(6号車)は私のほかに乗客が一人もいない“貸し切り”状態 (・ω・)ポツン。これは左右両側の車窓を眺めたい私にとって好都合な状況です (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみにもしも乗客が多かったとしたら、席に座らず車端部のデッキ(出入口部分)に立って左右の車窓を見ていたかもしれません。
今回の目的はこの先の茨木付近で分岐する梅田貨物線だけど、京都から向日町までの経路も「はるか」の下り列車でなければ乗ることができないマニアックな区間で、乗り鉄としては車窓から目が離せません (*゚∀゚)=3ハァハァ!。右の車窓を見たり、左の車窓を見たり、列車が転線するたびにちょろちょろと座席を移動して落ち着きありませんが アッチo(゚д゚o≡o゚д゚)oコッチ、平日の昼過ぎに京都から関西空港へと向かう「はるか29号」は利用者が少ないようで、なんと先頭車の自由席(6号車)は私のほかに乗客が一人もいない“貸し切り”状態 (・ω・)ポツン。これは左右両側の車窓を眺めたい私にとって好都合な状況です (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみにもしも乗客が多かったとしたら、席に座らず車端部のデッキ(出入口部分)に立って左右の車窓を見ていたかもしれません。
山崎付近で車窓に見えるのは
サントリーウイスキーの山崎蒸留所。
( ̄  ̄*)ザキヤマ
これも沿線名所のひとつですね。
▲東海道本線 山崎-高槻
(進行方向で右の車窓)
新快速が停車する高槻を通過すると
特急列車に乗っているという
優越感(?)を覚えます(笑)
(´ー`)フッ
▲東海道本線 高槻
(進行方向で右の車窓)
線路脇に立つ巨大な板チョコは
明治製菓の大阪工場に建つ看板の
“ビッグミルチ”
(ビッグなミルクチョコレート)。
やっぱし板チョコと言えば明治よね(笑)
(o ̄∇ ̄o)チョコ
▲東海道本線 高槻-摂津富田
(進行方向で右の車窓)
茨木を過ぎたあたりで
「はるか」はふたたび本線から転線して
貨物線のほうに入ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
なお上を跨いでいるのは
吹田貨物ターミナルと大阪貨物ターミナルの
あいだを結ぶ大阪ターミナル貨物線。
▲東海道本線 茨木-千里丘
(進行方向で右の車窓)
も一度オーバークロスして本線を越え、
今度は本線の南側から北側へ。
▲東海道本線 茨木-千里丘
(進行方向で左の車窓)
本線と並行する貨物線を走る「はるか」。
左手(南側)に見える通過駅は千里丘です。
( ̄  ̄*)センリオカ
▲東海道本線 千里丘
(進行方向で左の車窓)
そして右手(北側)に見えるヤードは
吹田貨物ターミナル(駅)。
正式には当駅が梅田貨物線の起点となります。
(・o・*)ホホゥ
お!手前にいるのは
EF210とEF510(青)の重単じゃん。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 千里丘-吹田(吹田貨物ターミナル)
(進行方向で右の車窓)
吹田を過ぎると左のほうへ分岐するのは
おおさか東線を経て関西本線方面へと向かう
城東貨物線。
▲東海道本線 吹田-東淀川
(進行方向で左の車窓)
いっぽう左から近づいてくる高架線は
4年前の2019年に開業したおおさか東線。
「はるか」が走っている貨物線はこの先で
おおさか東線の線路と合流します。
▲東海道本線 吹田-東淀川
(進行方向で左の車窓)
京都から30分、
特急「はるか」はまもなく
新大阪の3番線ホームに停車。
お、「スーパーはくと」だ。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 新大阪
(進行方向で左の車窓)
サントリーウイスキーの山崎蒸留所。
( ̄  ̄*)ザキヤマ
これも沿線名所のひとつですね。
▲東海道本線 山崎-高槻
(進行方向で右の車窓)
新快速が停車する高槻を通過すると
特急列車に乗っているという
優越感(?)を覚えます(笑)
(´ー`)フッ
▲東海道本線 高槻
(進行方向で右の車窓)
線路脇に立つ巨大な板チョコは
明治製菓の大阪工場に建つ看板の
“ビッグミルチ”
(ビッグなミルクチョコレート)。
やっぱし板チョコと言えば明治よね(笑)
(o ̄∇ ̄o)チョコ
▲東海道本線 高槻-摂津富田
(進行方向で右の車窓)
茨木を過ぎたあたりで
「はるか」はふたたび本線から転線して
貨物線のほうに入ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
なお上を跨いでいるのは
吹田貨物ターミナルと大阪貨物ターミナルの
あいだを結ぶ大阪ターミナル貨物線。
▲東海道本線 茨木-千里丘
(進行方向で右の車窓)
も一度オーバークロスして本線を越え、
今度は本線の南側から北側へ。
▲東海道本線 茨木-千里丘
(進行方向で左の車窓)
本線と並行する貨物線を走る「はるか」。
左手(南側)に見える通過駅は千里丘です。
( ̄  ̄*)センリオカ
▲東海道本線 千里丘
(進行方向で左の車窓)
そして右手(北側)に見えるヤードは
吹田貨物ターミナル(駅)。
正式には当駅が梅田貨物線の起点となります。
(・o・*)ホホゥ
お!手前にいるのは
EF210とEF510(青)の重単じゃん。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 千里丘-吹田(吹田貨物ターミナル)
(進行方向で右の車窓)
吹田を過ぎると左のほうへ分岐するのは
おおさか東線を経て関西本線方面へと向かう
城東貨物線。
▲東海道本線 吹田-東淀川
(進行方向で左の車窓)
いっぽう左から近づいてくる高架線は
4年前の2019年に開業したおおさか東線。
「はるか」が走っている貨物線はこの先で
おおさか東線の線路と合流します。
▲東海道本線 吹田-東淀川
(進行方向で左の車窓)
京都から30分、
特急「はるか」はまもなく
新大阪の3番線ホームに停車。
お、「スーパーはくと」だ。
(゚∀゚)オッ!
▲東海道本線 新大阪
(進行方向で左の車窓)
JR京都線を順調に西進する特急「はるか」は、茨木の先でふたたび本線から貨物線へと転線し、梅田貨物線の起点となる吹田貨物ターミナル(駅)の構内をかすめるようにして通過 ...(((o*・ω・)o。そしてまもなく東海道・山陽新幹線と接続する新大阪に停車します (゚ー゚*)シン・オーサカ。
当駅からは5、6人ほどが乗ってこられ、さすがに今までのような頻繁な席の移動は少し控えますが、私の座っている席の左右横一列(A〜D席)は空席のままで、引き続き両側の車窓を見ることができそう (o ̄∇ ̄o)ラキー。
今回の目的である梅田貨物線の乗り潰しは、新大阪発車後のここからが本番です (*゚v゚*)ワクワク♪。
当駅からは5、6人ほどが乗ってこられ、さすがに今までのような頻繁な席の移動は少し控えますが、私の座っている席の左右横一列(A〜D席)は空席のままで、引き続き両側の車窓を見ることができそう (o ̄∇ ̄o)ラキー。
今回の目的である梅田貨物線の乗り潰しは、新大阪発車後のここからが本番です (*゚v゚*)ワクワク♪。
「はるか」が停車する新大阪のホームは
駅名標の次駅表記が3月3日現在
“にしくじょう”(西九条)となっていますが、
これが今月の18日以降はおそらく
“おおさか”(大阪)となるハズです。
▲東海道本線 新大阪
(進行方向で左の車窓)
新大阪を出た「はるか」は
引き続き本線を左手(南側)に見て、
並行する梅田貨物線の線路を走行します。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
淀川の鉄橋(上淀川橋梁)を渡ると
本線のほうはまっすぐ大阪駅に向かいますが・・・
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線は右(北)のほうにカーブして
本線と分かれます。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
私は大阪の道路をあまり知らないけど
このあたりの梅田貨物線は
城北公園通りに沿って敷かれています。
上を跨ぐ高架橋は新御堂筋。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
旧線(地上線)と新線(地下線)の
上り方(新大阪方)の切り替え地点を通過。
(゚∀゚)オッ!
役目を終えて撤去される
地上線の線路が確認できました。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線を走る「はるか」は
新たに敷き直された線路を通って
徐々に地下トンネルへと潜ってゆきます。
...(((o*・ω・)o
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
駅名標の次駅表記が3月3日現在
“にしくじょう”(西九条)となっていますが、
これが今月の18日以降はおそらく
“おおさか”(大阪)となるハズです。
▲東海道本線 新大阪
(進行方向で左の車窓)
新大阪を出た「はるか」は
引き続き本線を左手(南側)に見て、
並行する梅田貨物線の線路を走行します。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
淀川の鉄橋(上淀川橋梁)を渡ると
本線のほうはまっすぐ大阪駅に向かいますが・・・
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線は右(北)のほうにカーブして
本線と分かれます。
バイチャ!( ゚д゚)ノシ
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
私は大阪の道路をあまり知らないけど
このあたりの梅田貨物線は
城北公園通りに沿って敷かれています。
上を跨ぐ高架橋は新御堂筋。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
旧線(地上線)と新線(地下線)の
上り方(新大阪方)の切り替え地点を通過。
(゚∀゚)オッ!
役目を終えて撤去される
地上線の線路が確認できました。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線を走る「はるか」は
新たに敷き直された線路を通って
徐々に地下トンネルへと潜ってゆきます。
...(((o*・ω・)o
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
新大阪を出たのち淀川を梅田貨物線の鉄橋で渡った「はるか」は、やがて右のほう(北のほう)に大きくカーブすると、まもなく旧線(地上線)との上り方の切り替え地点を通過して、真新しい線路が敷かれたばかりの地下トンネルへと突入してゆきます ...(((o*・ω・)o。当然ながら地下区間の車窓は真っ暗でほとんど何も見えませんが、一瞬たりとも見逃さないようにまばたき厳禁で刮目していると・・・(ФωФ*)ジーーーッ
うめきた、ミエタ────(n‘∀‘)η────ッ!
分岐器(線路のポイント)を通過する走行音が足元に響いた直後、暗かった車窓がパッと明るくなり (*゚ロ゚)ハッ!、そこにまばゆく見えたのは広い2面4線構造を備える「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」の新しいプラットホーム w(゚0゚*)w オォー!。
当ホームは乗降ホームと線路のあいだが大きなガラス扉で仕切られた“フルスクリーンホームドア”(しかも、あらゆる車種や編成に対応して開口できる世界初の方式なのだとか)を採用していて ( ̄。 ̄)ヘー、それ越しにホームの様子を車窓から撮るのはちょっと難しい状況でしたが、適当にカメラのシャッターを切った一枚にはかろうじて「大阪」の駅名標が写っていました (^_[◎]oパチリ。
そんな大阪駅うめきたエリア地下ホームを一瞬で通過した「はるか」は バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、また車窓に暗い壁を映したのち、まもなくトンネルを抜けてふたたび地上へと出ます (つ▽≦*)マブシッ!。そこは大阪環状線の福島(ふくしま)駅付近に位置し、地下からの新線はここで既存の線路と合流(下り方の旧線との切り替え地点を通過)( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ガッタイ。また先述したとおり“梅田貨物線”という線名は通称であって、正式には東海道本線の支線(吹田貨物ターミナル〜福島)と大阪環状線(福島〜西九条)の二路線で形成されており、その路線境界(福島の浄正橋踏切付近)を跨いだ「はるか」はこの先、大阪環状線(と並行する貨物線)を走ることとなります カンジョーセソ…((((o* ̄-)o。
分岐器(線路のポイント)を通過する走行音が足元に響いた直後、暗かった車窓がパッと明るくなり (*゚ロ゚)ハッ!、そこにまばゆく見えたのは広い2面4線構造を備える「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」の新しいプラットホーム w(゚0゚*)w オォー!。
当ホームは乗降ホームと線路のあいだが大きなガラス扉で仕切られた“フルスクリーンホームドア”(しかも、あらゆる車種や編成に対応して開口できる世界初の方式なのだとか)を採用していて ( ̄。 ̄)ヘー、それ越しにホームの様子を車窓から撮るのはちょっと難しい状況でしたが、適当にカメラのシャッターを切った一枚にはかろうじて「大阪」の駅名標が写っていました (^_[◎]oパチリ。
そんな大阪駅うめきたエリア地下ホームを一瞬で通過した「はるか」は バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、また車窓に暗い壁を映したのち、まもなくトンネルを抜けてふたたび地上へと出ます (つ▽≦*)マブシッ!。そこは大阪環状線の福島(ふくしま)駅付近に位置し、地下からの新線はここで既存の線路と合流(下り方の旧線との切り替え地点を通過)( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ガッタイ。また先述したとおり“梅田貨物線”という線名は通称であって、正式には東海道本線の支線(吹田貨物ターミナル〜福島)と大阪環状線(福島〜西九条)の二路線で形成されており、その路線境界(福島の浄正橋踏切付近)を跨いだ「はるか」はこの先、大阪環状線(と並行する貨物線)を走ることとなります カンジョーセソ…((((o* ̄-)o。
地下を抜けて車窓に外光が入ります。
(つ▽≦*)マブシッ!
なおこの地下から地上への登坂は
最大で22.6パーミルもの急勾配となっており、
ここを通過する貨物列車の一部にはなんと
編成の後方に補機(EF210-300)が
連結されるのだそうです。
(*・`o´・*)ホ─
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
大阪環状線の福島駅前にある
なにわ筋の踏切(浄正橋踏切)を通過。
この手前が旧線(地上線)と新線(地下線)の
下り方(西九条方)の切り替え地点にあたり、
ここで既存の線路に合流します。
( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ガッタイ
また、この踏切付近が
梅田貨物線における
東海道本線と大阪環状線の境界らしい。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
地下から地上、
そして一気に大阪環状線の高架へと上ります。
...(((o*・ω・)o
すれ違う221系は
環状線の外回りに直通してきた
大和路線の大和路快速。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
左手(東側)に見える複線が大阪環状線で
並行する貨物線は野田を通過します。
( ̄  ̄*)ノダ
ちなみに先ほどまで通っていたJR京都線は
駅名標のカラーが青でしたが
環状線は赤です。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
そして野田の先で
桜島線方面(安治川口方面)へ向かう
貨物線から離れ、
大阪環状線の外回り線を渡って
内回り線のほうに合流。
「はるか」は環状線の内回りを南下します。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線としての終点である
大阪環状線の西九条を通過。
(゚∀゚)オッ!
当駅はかつて
梅田貨物線経由の「はるか」が
大阪駅を通らないため
その代替的な停車駅でしたが
現在は通過駅となっています。
(特急「くろしお」の一部は停車。
ただしそれも今度のダイヤ改正前日まで。)
▲大阪環状線 西九条
(進行方向で右の車窓)
(つ▽≦*)マブシッ!
なおこの地下から地上への登坂は
最大で22.6パーミルもの急勾配となっており、
ここを通過する貨物列車の一部にはなんと
編成の後方に補機(EF210-300)が
連結されるのだそうです。
(*・`o´・*)ホ─
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
大阪環状線の福島駅前にある
なにわ筋の踏切(浄正橋踏切)を通過。
この手前が旧線(地上線)と新線(地下線)の
下り方(西九条方)の切り替え地点にあたり、
ここで既存の線路に合流します。
( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ガッタイ
また、この踏切付近が
梅田貨物線における
東海道本線と大阪環状線の境界らしい。
▲梅田貨物線(東海道本線) 新大阪-西九条
(進行方向で右の車窓)
地下から地上、
そして一気に大阪環状線の高架へと上ります。
...(((o*・ω・)o
すれ違う221系は
環状線の外回りに直通してきた
大和路線の大和路快速。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
左手(東側)に見える複線が大阪環状線で
並行する貨物線は野田を通過します。
( ̄  ̄*)ノダ
ちなみに先ほどまで通っていたJR京都線は
駅名標のカラーが青でしたが
環状線は赤です。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
そして野田の先で
桜島線方面(安治川口方面)へ向かう
貨物線から離れ、
大阪環状線の外回り線を渡って
内回り線のほうに合流。
「はるか」は環状線の内回りを南下します。
▲梅田貨物線(大阪環状線) 新大阪-西九条
(進行方向で左の車窓)
梅田貨物線としての終点である
大阪環状線の西九条を通過。
(゚∀゚)オッ!
当駅はかつて
梅田貨物線経由の「はるか」が
大阪駅を通らないため
その代替的な停車駅でしたが
現在は通過駅となっています。
(特急「くろしお」の一部は停車。
ただしそれも今度のダイヤ改正前日まで。)
▲大阪環状線 西九条
(進行方向で右の車窓)
野田(のだ)を過ぎたところで大阪環状線の内回り線へと乗り入れた「はるか」は、やがて西九条のホームを右にかすめてゆっくりと通過 ...(((o*・ω・)o。停車はしないけれど当駅が梅田貨物線の終点とされており、これにて地下に切り替えられた新ルート(移設部分)を含む梅田貨物線の全区間を完乗となりました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。
もっとも今回の場合は、私が過去に地上の旧線(梅田貨物駅経由)をすでに踏破しているため、“乗り潰した”というよりは“乗り直した”といったほうが正しいのですが、それでもやはり新たな地下ルートとしては初乗車なので個人的に達成感と満足感を覚えます +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
ちなみに梅田貨物線の総距離は12.6キロ(吹田貨物ターミナル〜西九条)、そのうち地下への移設にともなって線路が敷き直された区間は2.2キロでした ( ̄  ̄)ニキロ。
もっとも今回の場合は、私が過去に地上の旧線(梅田貨物駅経由)をすでに踏破しているため、“乗り潰した”というよりは“乗り直した”といったほうが正しいのですが、それでもやはり新たな地下ルートとしては初乗車なので個人的に達成感と満足感を覚えます +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
ちなみに梅田貨物線の総距離は12.6キロ(吹田貨物ターミナル〜西九条)、そのうち地下への移設にともなって線路が敷き直された区間は2.2キロでした ( ̄  ̄)ニキロ。
西九条を過ぎて
右のほうに分岐するのは
USJのあるユニバーサルシティや
桜島方面へと伸びる
JRゆめ咲線(桜島線)。
なお当線の安治川口は貨物取扱駅であり
もともと梅田貨物線は
おもにそこを発着する貨物列車のための
貨物線でした。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
▲大阪環状線 西九条-弁天町
(進行方向で右の車窓)
左の車窓に見える
ドーム球場の「京セラドーム大阪」。
まるでフリーザの宇宙船(?)のような
インパクトあるデザインですね。
( ̄∇ ̄;)フリーザ…
▲大阪環状線 弁天町-大正
(進行方向で左の車窓)
新今宮の手前で今度は
大阪環状線から大和路線(関西本線)へ転線。
新今宮の2番線を通過します。
...(((o*・ω・)o
▲関西本線 新今宮
(進行方向で左の車窓)
左の車窓に
新世界のシンボル「通天閣」が見えてくると
まもなく天王寺。
( ̄▽ ̄)ツーテンカク
▲関西本線 新今宮-天王寺
(進行方向で左の車窓)
右のほうに分岐するのは
USJのあるユニバーサルシティや
桜島方面へと伸びる
JRゆめ咲線(桜島線)。
なお当線の安治川口は貨物取扱駅であり
もともと梅田貨物線は
おもにそこを発着する貨物列車のための
貨物線でした。
( ̄、 ̄*)ナルヘソ
▲大阪環状線 西九条-弁天町
(進行方向で右の車窓)
左の車窓に見える
ドーム球場の「京セラドーム大阪」。
まるでフリーザの宇宙船(?)のような
インパクトあるデザインですね。
( ̄∇ ̄;)フリーザ…
▲大阪環状線 弁天町-大正
(進行方向で左の車窓)
新今宮の手前で今度は
大阪環状線から大和路線(関西本線)へ転線。
新今宮の2番線を通過します。
...(((o*・ω・)o
▲関西本線 新今宮
(進行方向で左の車窓)
左の車窓に
新世界のシンボル「通天閣」が見えてくると
まもなく天王寺。
( ̄▽ ̄)ツーテンカク
▲関西本線 新今宮-天王寺
(進行方向で左の車窓)
JR京都線(東海道線)、梅田貨物線、大阪環状線、そして環状線との重複区間ではありますが大和路線(関西本線)を経由して京都から45分、特急「はるか29号」は定刻の13時45分に大阪市内の天王寺へ到着しました (・ω・)トーチャコ。当列車は関西空港ゆきですが私はここで下車します。
京都1300-(特急はるか29号)-天王寺1345
大阪駅北側(うめきたエリア)の再開発にともなって地上から地下へ移設された、梅田貨物線の“乗り直し”を目的に乗車した特急「はるか」の“乗り鉄旅” (゚ー゚*)ハルカ。
梅田貨物線のみならず旅客線と貨物線の転線を繰り返す複雑な経路を進む当列車は、京都〜天王寺の乗車区間全体を通して鉄ちゃん的にとても興味深いものがあり、そのマニアックな車窓風景を存分に満喫 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そして主目的の梅田貨物線は、かつて梅田貨物駅の構内をかすめていた地上線時代のほうが車窓からの景色に面白さはあったものの、このたび新たに設置された「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」をいち早く眺められたところや (゚∀゚)オッ!、地下トンネルをくぐり抜けて大阪環状線の福島付近に出てくる展開などは (゚∀゚*)オオッ!、個人的に新鮮な印象で車窓を見ることができました (=´▽`=)ワーイ♪。これは特急料金(特急券)を払って乗ったぶんの価値はあったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。ただ、大阪駅うめきたエリア地下ホームに関してはやはり一瞬で通過しちゃうのでなく、あの新しいホームに降り立ってみたいもの σ(・∀・`)ウーン…。“フルスクリーンホームドア”ってヤツが可動するところも見てみたいですしね (・∀・)ミタイ。
まもなく3月18日に開業(使用開始)する「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」。そのホームから私が列車に乗ることは、次にまた大阪を訪れるときの楽しみにしたいと思います (*´v`*)ワクワク♪。
大阪駅北側(うめきたエリア)の再開発にともなって地上から地下へ移設された、梅田貨物線の“乗り直し”を目的に乗車した特急「はるか」の“乗り鉄旅” (゚ー゚*)ハルカ。
梅田貨物線のみならず旅客線と貨物線の転線を繰り返す複雑な経路を進む当列車は、京都〜天王寺の乗車区間全体を通して鉄ちゃん的にとても興味深いものがあり、そのマニアックな車窓風景を存分に満喫 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そして主目的の梅田貨物線は、かつて梅田貨物駅の構内をかすめていた地上線時代のほうが車窓からの景色に面白さはあったものの、このたび新たに設置された「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」をいち早く眺められたところや (゚∀゚)オッ!、地下トンネルをくぐり抜けて大阪環状線の福島付近に出てくる展開などは (゚∀゚*)オオッ!、個人的に新鮮な印象で車窓を見ることができました (=´▽`=)ワーイ♪。これは特急料金(特急券)を払って乗ったぶんの価値はあったと思います ъ(゚Д゚)ナイス。ただ、大阪駅うめきたエリア地下ホームに関してはやはり一瞬で通過しちゃうのでなく、あの新しいホームに降り立ってみたいもの σ(・∀・`)ウーン…。“フルスクリーンホームドア”ってヤツが可動するところも見てみたいですしね (・∀・)ミタイ。
まもなく3月18日に開業(使用開始)する「大阪駅(うめきたエリア)地下ホーム」。そのホームから私が列車に乗ることは、次にまた大阪を訪れるときの楽しみにしたいと思います (*´v`*)ワクワク♪。
JRの改札を出て、
天王寺の地下から乗るのは
大阪メトロ御堂筋線の中津ゆき。
以前にもご紹介しましたが
当駅のホームの照明は
特徴的なデザインをしています。
( ̄∇ ̄)シャンデリア
▲大阪メトロ御堂筋線 天王寺
天王寺の地下から乗るのは
大阪メトロ御堂筋線の中津ゆき。
以前にもご紹介しましたが
当駅のホームの照明は
特徴的なデザインをしています。
( ̄∇ ̄)シャンデリア
▲大阪メトロ御堂筋線 天王寺
さてと、本来なら新世界あたりの居酒屋で梅田貨物線の完乗を祝って打ち上げでもしたいところだけど (σ´∀`)σイイネ♪、今回の私は仕事の出張で来ていることを忘れてはいけません (; ̄▽ ̄)ア…。“鉄ちゃんモード”から“仕事モード”に気持ちを切り替えて、地下鉄の御堂筋線で心斎橋へ向かうとしますか オシゴト…((((o* ̄-)o 。
そしてこの写真は
仕事の要件を済ませたあとに立ち寄ってみた
3月3日時点の大阪駅の様子。
(「゚ー゚)ドレドレ
東海道本線(JR京都、神戸線)の塚本方
大阪環状線の福島方など
各ホーム(11番線ホームを除く)の西側に
“うめきたエリア”の地下ホームへとつながる
連絡通路が設けられました。
(*・`o´・*)ホ─
なお、既存の地上駅と
うめきたエリア地下ホームの乗換時間は
歩く速度や混雑具合により
おおむね6分〜10分程度とされています。
東京駅の京葉線地下ホームよりは近いのかな?
σ(゚・゚*)ンー…
▲東海道本線 大阪
「うめきた開業まで 15日」っ!
(3/3現在)
(*゚v゚*)ワクワク♪
仕事の要件を済ませたあとに立ち寄ってみた
3月3日時点の大阪駅の様子。
(「゚ー゚)ドレドレ
東海道本線(JR京都、神戸線)の塚本方
大阪環状線の福島方など
各ホーム(11番線ホームを除く)の西側に
“うめきたエリア”の地下ホームへとつながる
連絡通路が設けられました。
(*・`o´・*)ホ─
なお、既存の地上駅と
うめきたエリア地下ホームの乗換時間は
歩く速度や混雑具合により
おおむね6分〜10分程度とされています。
東京駅の京葉線地下ホームよりは近いのかな?
σ(゚・゚*)ンー…
▲東海道本線 大阪
「うめきた開業まで 15日」っ!
(3/3現在)
(*゚v゚*)ワクワク♪
2023-03-14 20:20
西九州新幹線・・・「かもめ」乗車記 [鉄道乗車記]
おはようございます ('-'*)オハヨ。
9月なかば過ぎの“秋分の日”ともなれば、だいぶ日の出の時刻が遅くなった印象で、まだ夜が明けやらぬ早朝の5時半。私が今いるのは福岡県の博多駅です ( ̄▽ ̄)ハカタ。
9月なかば過ぎの“秋分の日”ともなれば、だいぶ日の出の時刻が遅くなった印象で、まだ夜が明けやらぬ早朝の5時半。私が今いるのは福岡県の博多駅です ( ̄▽ ̄)ハカタ。
巨大な駅ビルがそびえたつ
博多駅(博多口)。
九州最大のターミナルである当駅は
鹿児島本線を軸に各方面の列車が発着し、
また、山陽新幹線と九州新幹線の接続駅
(九州新幹線の起点)でもあります。
▲22.9.23 鹿児島本線 博多
博多駅(博多口)。
九州最大のターミナルである当駅は
鹿児島本線を軸に各方面の列車が発着し、
また、山陽新幹線と九州新幹線の接続駅
(九州新幹線の起点)でもあります。
▲22.9.23 鹿児島本線 博多
私が九州へとやってきた理由、それはもう拙ブログにお付き合いいただいている方ならば、すぐにお分かりのことでしょう σ(゚・゚*)ンー…。きょう2022年9月23日は、九州西部の長崎を終着地とする「西九州新幹線」の開業日です (゚∀゚*)オオッ!。
鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標に掲げている私にとって、新たに開通する路線があれば、いち早く乗りたいところ (*`・ω・´)-3フンス!。ちなみに私は新幹線でいうと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれも初日に乗車を果たしています。
そんなワケで私は西九州新幹線の開業に合わせるべく、前夜の退勤後に羽田空港から飛行機で飛び、福岡へと前乗り(前泊)しました ⊂ニニニ(^ω^)ニニ⊃ブーン。
(あまり思い出したくないけど、今回と同様に新幹線の開業前日に福岡へ飛行機で前乗りするパターンは個人的に、九州新幹線全通(博多〜新八代 開業)のときに羽田空港で経験した、東日本大震災の記憶が蘇ってしまいます・・・。)
きょうの出発前に、まずは昨日(22日)の博多駅の様子を、ちょろっとご覧いただきましょう。
鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標に掲げている私にとって、新たに開通する路線があれば、いち早く乗りたいところ (*`・ω・´)-3フンス!。ちなみに私は新幹線でいうと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれも初日に乗車を果たしています。
そんなワケで私は西九州新幹線の開業に合わせるべく、前夜の退勤後に羽田空港から飛行機で飛び、福岡へと前乗り(前泊)しました ⊂ニニニ(^ω^)ニニ⊃ブーン。
(あまり思い出したくないけど、今回と同様に新幹線の開業前日に福岡へ飛行機で前乗りするパターンは個人的に、九州新幹線全通(博多〜新八代 開業)のときに羽田空港で経験した、東日本大震災の記憶が蘇ってしまいます・・・。)
きょうの出発前に、まずは昨日(22日)の博多駅の様子を、ちょろっとご覧いただきましょう。
博多駅構内のコンコースに掲げられた
カウントダウンボード。
西九州新幹線開業まで “あと1日”。
m9・∀・´)カウントダウン!
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
在来線の特急「かもめ」は
この日(22日)が最終運行です。
シックな787系で運転されていたのは、
通称「黒いかもめ」(41号)。
( ̄  ̄*)クロ
なお、ホームに見られる乗車列は、
最終列車となる「かもめ45号」を待つ方たち。
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
こちらはまさにカモメのような
白い車体の885系で運転されていた、
通称「白いかもめ」(43号)。
( ̄  ̄*)シロ
個人的に先の787系は「つばめ」の印象が強く、
「かもめ」といえばこの885系のイメージだなぁ。
σ(゚・゚*)ンー…
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
カウントダウンボード。
西九州新幹線開業まで “あと1日”。
m9・∀・´)カウントダウン!
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
在来線の特急「かもめ」は
この日(22日)が最終運行です。
シックな787系で運転されていたのは、
通称「黒いかもめ」(41号)。
( ̄  ̄*)クロ
なお、ホームに見られる乗車列は、
最終列車となる「かもめ45号」を待つ方たち。
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
こちらはまさにカモメのような
白い車体の885系で運転されていた、
通称「白いかもめ」(43号)。
( ̄  ̄*)シロ
個人的に先の787系は「つばめ」の印象が強く、
「かもめ」といえばこの885系のイメージだなぁ。
σ(゚・゚*)ンー…
▲22.9.22 鹿児島本線 博多
西九州新幹線の開業にともない、いままで博多と長崎のあいだを鹿児島本線、長崎本線経由で結んでいた在来線の特急「かもめ」は、開業前日の22日を持って廃止となり、その愛称は新幹線へと引き継がれます (゚ー゚*)カモメ。せっかく福岡へ前乗りしたので、見納めとなる特急「かもめ」を博多のホームで少しだけ記録しておきました (^_[◎]oパチリ。885系の「かもめ」に博多から長崎まで私が最後に乗ったのは、もう10年以上も前(2007年)のことだなぁ・・・。
1976年に現行の電車特急となってから、昭和、平成、令和の時代を駆け抜けてきた特急「かもめ」。46年間の活躍おつかれさまでした (´w`*)ドツカレサン。
そして明けた23日。西九州新幹線はきょう開業を迎えます。
9月23日(金・祝)
1976年に現行の電車特急となってから、昭和、平成、令和の時代を駆け抜けてきた特急「かもめ」。46年間の活躍おつかれさまでした (´w`*)ドツカレサン。
そして明けた23日。西九州新幹線はきょう開業を迎えます。
9月23日(金・祝)
まだ薄暗い早朝なので空模様はよくわからないけど、きょうの九州北部・西部の天気はおおむね曇りの予報。本州に接近している台風15号の影響はあまり受けないものの、スッキリとした秋晴れにはならなそうな感じです ( ̄  ̄)クモリ…。長崎では新幹線の開業を記念して、航空自衛隊の「ブルーインパルス」による祝賀飛行が行なわれる予定なので、できれば晴れて欲しいなぁ・・・σ(・∀・`)ウーン… などと思いながら、私は博多駅の在来線改札を入り、昨夜に特急「かもめ」を見送った鹿児島本線のホームに向かいます ...(((o*・ω・)o。
え?新幹線のホームじゃないのかって? (゚ー゚?)オヨ?。そう、ここ博多からまず乗るのは、新幹線でなくこちらの列車。
え?新幹線のホームじゃないのかって? (゚ー゚?)オヨ?。そう、ここ博多からまず乗るのは、新幹線でなくこちらの列車。
あれ?「黒いかもめ」・・・ (=゚ω゚=*)カモメ!?
いえいえ、たしかに同じ787系を使用する特急列車なのですが、昨日までの特急「かもめ」をあらため、今日からは特急「リレーかもめ」(黒いリレーかもめ?)となりました (=゚ω゚)ノ゙ヨロ。
「リレー」とはいったいどういうことなのかというと・・・σ(゚・゚*)リレー…、もう大半の方はご存じかと思われますが、今回開業する西九州新幹線は、博多と長崎を一本の新幹線でダイレクトに結ぶものではなく、佐賀県西部の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎の間のみで運行される、いわば“部分開業(もしくは区間開業)”のようなもの (・o・*)ホホゥ。そこで、新幹線が未開業となっている博多と武雄温泉の間をつなぐのが、今までの特急「かもめ」と同様に在来線の鹿児島本線と長崎本線(と佐世保線)を経由する、特急「リレーかもめ」です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
いえいえ、たしかに同じ787系を使用する特急列車なのですが、昨日までの特急「かもめ」をあらため、今日からは特急「リレーかもめ」(黒いリレーかもめ?)となりました (=゚ω゚)ノ゙ヨロ。
「リレー」とはいったいどういうことなのかというと・・・σ(゚・゚*)リレー…、もう大半の方はご存じかと思われますが、今回開業する西九州新幹線は、博多と長崎を一本の新幹線でダイレクトに結ぶものではなく、佐賀県西部の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎の間のみで運行される、いわば“部分開業(もしくは区間開業)”のようなもの (・o・*)ホホゥ。そこで、新幹線が未開業となっている博多と武雄温泉の間をつなぐのが、今までの特急「かもめ」と同様に在来線の鹿児島本線と長崎本線(と佐世保線)を経由する、特急「リレーかもめ」です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。
今回開業する西九州新幹線は
武雄温泉と長崎のあいだの区間(水色)で、
博多と武雄温泉のあいだ(オレンジ)は
在来線の特急「リレーかもめ」がつなぎます。
ε=(ヘ^^)ノ”ヘ(*・▽・)ノ バトンタッチ
「リレーかもめ」の行先標は
接続も含めた最終目的地として
「長崎」を掲出しており、
「武雄温泉駅で新幹線かもめに接続しています」
との注釈が併記されています。
( ̄。 ̄)ヘー
武雄温泉と長崎のあいだの区間(水色)で、
博多と武雄温泉のあいだ(オレンジ)は
在来線の特急「リレーかもめ」がつなぎます。
ε=(ヘ^^)ノ”ヘ(*・▽・)ノ バトンタッチ
「リレーかもめ」の行先標は
接続も含めた最終目的地として
「長崎」を掲出しており、
「武雄温泉駅で新幹線かもめに接続しています」
との注釈が併記されています。
( ̄。 ̄)ヘー
東海道・山陽新幹線が乗り入れる博多や、九州新幹線(鹿児島ルート)の新鳥栖(しんとす)とつながっておらず、端部の武雄温泉と長崎の間だけを先行(?)開業させる西九州新幹線 ( ̄△ ̄;)エッ…。これは誰がどう見ても中途ハンパ感が否めず、このような不自然な形での開業にこぎつけた経緯には、未開業区間(新鳥栖〜武雄温泉)を通ることになる佐賀県の同意が得られていないといった事情などがあるのですが・・・(´〜`*)ウーン…、拙ブログとしてはあえてそのことを深く議論するつもりはなく(のちほど路線概要の説明でちょろっと触れるけど)、「新たに鉄道路線(新幹線)ができたのなら、それを乗り潰そう」、「特急列車と新幹線を途中で乗り継ぐなんて、鉄ちゃん的に面白いじゃない」という、あくまでも個人的な興味本位の“趣味目線で見た状況”を淡々とお伝えしようと思っています (-`ω´-*)ウム。
先頭車付近に人だかりができていたので
ちょいと覗いてみたら・・・
へー、このあと出発式なんて行なわれるのね。
(゚∀゚)オッ!
ちなみにこの787系は
九州新幹線が部分開業したときも
特急「つばめ」あらため「リレーつばめ」として
新幹線連絡を担った過去があり、
当系にとっては二度目の「リレー特急」就任です。
▲22.9.23 鹿児島本線 博多
ちょいと覗いてみたら・・・
へー、このあと出発式なんて行なわれるのね。
(゚∀゚)オッ!
ちなみにこの787系は
九州新幹線が部分開業したときも
特急「つばめ」あらため「リレーつばめ」として
新幹線連絡を担った過去があり、
当系にとっては二度目の「リレー特急」就任です。
▲22.9.23 鹿児島本線 博多
武雄温泉で新幹線「かもめ1号」に接続する、特急「リレーかもめ1号」。開業初日の今日は一番列車となる「かもめ1号」の指定席が早々に満席となり、自由席への乗車も人数制限がかけられるようですが σ(゚・゚*)ンー…、「リレーかもめ1号」のほうはざっと見たところ6〜7割程度の乗車率で、私も余裕で窓側の席に座ることができました ε-(´∇`*)ホッ。
先頭車付近で行なわれていた出発式に応えるために鳴らされた警笛が聞こえると、列車はゆっくりと動き出して博多をあとにします (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
先頭車付近で行なわれていた出発式に応えるために鳴らされた警笛が聞こえると、列車はゆっくりと動き出して博多をあとにします (/*´∀`)o レッツラゴー♪。
福岡と佐賀の県境付近で日の出時刻を迎え、
「リレーかもめ」の車窓越しに仰ぐ空模様。
雲は多めながら晴れ間も覗きます。
好天にならないかな・・・。
八(゚- ゚)ハレテ
▲22.9.23 鹿児島本線 天拝山-原田
(車窓から)
佐賀県の鳥栖(とす)は
鹿児島本線と長崎本線の分岐駅
(長崎本線の起点)。
「リレーかもめ」はここから長崎本線へ入ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
ちなみに駅名標の背後に見えている青い鉄骨は
Jリーグ「サガン鳥栖」のホームスタジアム。
▲22.9.23 鹿児島本線 鳥栖(車窓から)
鳥栖の次駅の新鳥栖は
鹿児島方面へ伸びる九州新幹線との接続駅。
もしも西九州新幹線がフル規格で全通したら
当駅で分岐することになるハズですが・・・
はたしてそれはいつのことになるのやら。
σ(・∀・`)ウーン…
▲22.9.23 長崎本線 新鳥栖(車窓から)
佐賀を通る長崎本線といえば
個人的に車窓でちょっと気になるのが、
弥生時代の環濠集落跡で知られる
吉野ケ里遺跡(公園)。
遺跡は長崎本線の線路沿いにあるため
車窓からも土塁などがちらっと見えます。
(゚∀゚)オッ!
いつか入園して遺跡と列車を絡めた写真を
撮ってみたいなぁ(笑)
▲22.9.23 長崎本線 吉野ケ里公園-神崎
(車窓から)
長崎本線と佐世保線が分岐する江北。
(゚ー゚*)コーホク
当駅は西九州新幹線の開業にあわせて
本日より駅名が肥前山口から
町名由来(佐賀県江北町)の江北へ
改称されました。
▲22.9.23 長崎本線 江北(車窓から)
江北を出ると、
車窓の左のほうに分かれる長崎本線。
今までの特急「かもめ」は
むこう(長崎本線)を進んでいましたが、
「リレーかもめ」は佐世保線に入り、
武雄温泉方面へ向かいます
コッチ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 佐世保線 江北-大町
(車窓から)
「リレーかもめ」の車窓越しに仰ぐ空模様。
雲は多めながら晴れ間も覗きます。
好天にならないかな・・・。
八(゚- ゚)ハレテ
▲22.9.23 鹿児島本線 天拝山-原田
(車窓から)
佐賀県の鳥栖(とす)は
鹿児島本線と長崎本線の分岐駅
(長崎本線の起点)。
「リレーかもめ」はここから長崎本線へ入ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
ちなみに駅名標の背後に見えている青い鉄骨は
Jリーグ「サガン鳥栖」のホームスタジアム。
▲22.9.23 鹿児島本線 鳥栖(車窓から)
鳥栖の次駅の新鳥栖は
鹿児島方面へ伸びる九州新幹線との接続駅。
もしも西九州新幹線がフル規格で全通したら
当駅で分岐することになるハズですが・・・
はたしてそれはいつのことになるのやら。
σ(・∀・`)ウーン…
▲22.9.23 長崎本線 新鳥栖(車窓から)
佐賀を通る長崎本線といえば
個人的に車窓でちょっと気になるのが、
弥生時代の環濠集落跡で知られる
吉野ケ里遺跡(公園)。
遺跡は長崎本線の線路沿いにあるため
車窓からも土塁などがちらっと見えます。
(゚∀゚)オッ!
いつか入園して遺跡と列車を絡めた写真を
撮ってみたいなぁ(笑)
▲22.9.23 長崎本線 吉野ケ里公園-神崎
(車窓から)
長崎本線と佐世保線が分岐する江北。
(゚ー゚*)コーホク
当駅は西九州新幹線の開業にあわせて
本日より駅名が肥前山口から
町名由来(佐賀県江北町)の江北へ
改称されました。
▲22.9.23 長崎本線 江北(車窓から)
江北を出ると、
車窓の左のほうに分かれる長崎本線。
今までの特急「かもめ」は
むこう(長崎本線)を進んでいましたが、
「リレーかもめ」は佐世保線に入り、
武雄温泉方面へ向かいます
コッチ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 佐世保線 江北-大町
(車窓から)
従来の特急「かもめ」と同じ787系が、鹿児島本線と長崎本線を経て西のほうへ走る。ここまではまだ新鮮味がなく、この先で新幹線に接続するという実感もあまり湧きませんでしたが σ(゚・゚*)ンー…、本日より駅名を肥前山口(ひぜんやまぐち)から改称した江北(こうほく)を出て、長崎本線から佐世保線のほうに進路を取ると、やがて列車は武雄温泉の手前で高架線へと上がります。するとその左隣には並行して、新幹線用の真新しい高架線が現れました (゚∀゚)オッ!。
博多からちょうど一時間、「リレーかもめ」はまもなく、西九州新幹線の「かもめ」が待つ武雄温泉に着きます。
博多からちょうど一時間、「リレーかもめ」はまもなく、西九州新幹線の「かもめ」が待つ武雄温泉に着きます。
武雄温泉付近の高架線を走る
「リレーかもめ」。
左には新幹線用の高架が寄り添います。
(゚∀゚)オッ!
なお、新幹線の開業を見据えて
このあたりの佐世保線が高架化されたのは、
2008年のこと。
▲22.9.23 佐世保線 高橋-武雄温泉
(車窓から)
「かもめ」、イタ━━━━m9( ゚∀゚)━━━━ッ!!
武雄温泉のホームに入る「リレーかもめ」を
新幹線「かもめ」が迎えます。
▲22.9.23 佐世保線 武雄温泉(車窓から)
「リレーかもめ」。
左には新幹線用の高架が寄り添います。
(゚∀゚)オッ!
なお、新幹線の開業を見据えて
このあたりの佐世保線が高架化されたのは、
2008年のこと。
▲22.9.23 佐世保線 高橋-武雄温泉
(車窓から)
「かもめ」、イタ━━━━m9( ゚∀゚)━━━━ッ!!
武雄温泉のホームに入る「リレーかもめ」を
新幹線「かもめ」が迎えます。
▲22.9.23 佐世保線 武雄温泉(車窓から)
先述したとおり、事実上は「リレーかもめ」の終点となる武雄温泉は、在来線の佐世保線と西九州新幹線の接続駅で、長崎方面へ向かう新幹線の利用者はここで乗り換えなくてはなりません ラジャ!(* ̄- ̄)ゞ。
ちなみに新幹線が発着する駅では一般的に、在来線と新幹線のホームは改札を隔てて分けられているものですが、「リレーかもめ」が到着した武雄温泉のホーム(10番線)は、島式のホームを挟んだ反対側(11番線)に新幹線の「かもめ」が待機しており、スムーズな“対面乗換”が可能な構造となっています ノリカエ…((((o* ̄-)o(なお、この対面ホームの10番線に入線する在来線の列車は基本的に「リレーかもめ」のみで、佐世保線の普通列車や特急列車が発着するホームは別にあり(1・2番線)、そちらから新幹線へ乗り換える場合には新幹線改札を通る必要があります)。
ちなみに新幹線が発着する駅では一般的に、在来線と新幹線のホームは改札を隔てて分けられているものですが、「リレーかもめ」が到着した武雄温泉のホーム(10番線)は、島式のホームを挟んだ反対側(11番線)に新幹線の「かもめ」が待機しており、スムーズな“対面乗換”が可能な構造となっています ノリカエ…((((o* ̄-)o(なお、この対面ホームの10番線に入線する在来線の列車は基本的に「リレーかもめ」のみで、佐世保線の普通列車や特急列車が発着するホームは別にあり(1・2番線)、そちらから新幹線へ乗り換える場合には新幹線改札を通る必要があります)。
武雄温泉の島式ホームを挟み、
左に到着した「リレーかもめ」と、
右で待機する長崎ゆきの新幹線「かもめ」。
同一ホームによる対面乗換ができます。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
左に到着した「リレーかもめ」と、
右で待機する長崎ゆきの新幹線「かもめ」。
同一ホームによる対面乗換ができます。
ノリカエ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
そんな武雄温泉のホームで対面に待機していた新幹線は「かもめ1号」。そう、わずか10秒で指定券が売り切れて満席になったという、当駅始発の下り“一番列車”です (゚∀゚*)オオッ!。
しかし、博多からの「リレーかもめ1号」は7時ちょうどに当駅へ到着し、接続する長崎ゆきの新幹線「かもめ1号」の発車時刻は7時03分 ( ̄  ̄;)サンプン…。同一ホームの対面乗換とはいえ、時間が短くてけっこうタイトです。せっかくの一番列車だけど、「リレーかもめ1号」から「かもめ1号」へ乗り継ぐ乗客の方たちは、記念撮影などをしているような余裕はほとんどなく、ちょっと慌て気味にホームを右から左へと移動しているご様子 アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ。
え?アンタは急いで乗らないのかって? (´・ω`・)エッ?。いや、実は私もひと月前の発売開始日に「かもめ1号」の指定券をチャレンジしてみたのですが、窓側の席に限定して申し込んだこともあってか結果は敗北 (´д`;)アウ…。入手できた指定券は次発となる「かもめ3号」ですた (・ε・`)シャーナイネ。・・・というワケで私は「かもめ1号」には乗らず(乗れず)に、ホームから指をくわえてお見送りです σ(・∀・`)イイナァ…。
その発車前にとりあえず、新幹線のお顔(正面)を拝見しようと思って先頭車のほう(ホームの先端)に行ってみると・・・お!なんだか“賑やかなこと”をやっているぞ!(゚∀゚)オッ!
しかし、博多からの「リレーかもめ1号」は7時ちょうどに当駅へ到着し、接続する長崎ゆきの新幹線「かもめ1号」の発車時刻は7時03分 ( ̄  ̄;)サンプン…。同一ホームの対面乗換とはいえ、時間が短くてけっこうタイトです。せっかくの一番列車だけど、「リレーかもめ1号」から「かもめ1号」へ乗り継ぐ乗客の方たちは、記念撮影などをしているような余裕はほとんどなく、ちょっと慌て気味にホームを右から左へと移動しているご様子 アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ。
え?アンタは急いで乗らないのかって? (´・ω`・)エッ?。いや、実は私もひと月前の発売開始日に「かもめ1号」の指定券をチャレンジしてみたのですが、窓側の席に限定して申し込んだこともあってか結果は敗北 (´д`;)アウ…。入手できた指定券は次発となる「かもめ3号」ですた (・ε・`)シャーナイネ。・・・というワケで私は「かもめ1号」には乗らず(乗れず)に、ホームから指をくわえてお見送りです σ(・∀・`)イイナァ…。
その発車前にとりあえず、新幹線のお顔(正面)を拝見しようと思って先頭車のほう(ホームの先端)に行ってみると・・・お!なんだか“賑やかなこと”をやっているぞ!(゚∀゚)オッ!
長崎方の先頭車(1号車)の横では
「かもめ1号」の出発式が催されています。
私も一枚撮らせてっ!
p[◎]q▽≦*)パチャ!
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
発車に合わせて右手をスッと挙げ、
「出発進行!」
(/`・ω・)ピシッ!
日本の鉄道路線網へ新たに
今日から西九州新幹線が加わりました。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
「かもめ1号」の出発式が催されています。
私も一枚撮らせてっ!
p[◎]q▽≦*)パチャ!
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
発車に合わせて右手をスッと挙げ、
「出発進行!」
(/`・ω・)ピシッ!
日本の鉄道路線網へ新たに
今日から西九州新幹線が加わりました。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
西九州新幹線、開業おめでとう!ヽ(´▽`*)ノオメデ㌧♪
人垣のスキマからちゃっかりと、ウマい具合に覗けた(撮影できた)「かもめ1号」の出発式 (「゚ー゚)ドレドレ。これはいいものが見られて、開業日ならではの貴重なシーンを写真に残すことができました (^_[◎]oパチリ。
もしも「かもめ1号」の指定券を私が希望どおりに取れていたとしたら、「リレーかもめ」から慌ただしく乗り換えていて、おそらくこの出発式を撮ることなどできなかったと思われるので(乗ってたら出発の合図は絶対に撮れないw)、乗車を「3号」のほうにしたのは結果オーライだったかもしれません ъ(゚Д゚)ナイス。まあ、「1号」に乗れなかった者の負け惜しみですけどね・・・ (。A。)アヒャ☆。
ちなみに、武雄温泉の駅長さんとともに出発の合図を務められたのは、“ちびっこ一日駅長”に任命された地元在住で4歳の“鉄道大好き少年くん” (゚ー゚*)コテツ。どういう経緯で彼が大役に抜擢されたのか私にはわからないけど、壇上に立ったのが芸能人やスポーツ選手などの有名人じゃなかったぶん取り囲む人垣がユルくて、スキマからの撮影もしやすかったように思います(笑)(長崎駅のほうの上り出発式は、長濱ねるさんだったのよね)。
人垣のスキマからちゃっかりと、ウマい具合に覗けた(撮影できた)「かもめ1号」の出発式 (「゚ー゚)ドレドレ。これはいいものが見られて、開業日ならではの貴重なシーンを写真に残すことができました (^_[◎]oパチリ。
もしも「かもめ1号」の指定券を私が希望どおりに取れていたとしたら、「リレーかもめ」から慌ただしく乗り換えていて、おそらくこの出発式を撮ることなどできなかったと思われるので(乗ってたら出発の合図は絶対に撮れないw)、乗車を「3号」のほうにしたのは結果オーライだったかもしれません ъ(゚Д゚)ナイス。まあ、「1号」に乗れなかった者の負け惜しみですけどね・・・ (。A。)アヒャ☆。
ちなみに、武雄温泉の駅長さんとともに出発の合図を務められたのは、“ちびっこ一日駅長”に任命された地元在住で4歳の“鉄道大好き少年くん” (゚ー゚*)コテツ。どういう経緯で彼が大役に抜擢されたのか私にはわからないけど、壇上に立ったのが芸能人やスポーツ選手などの有名人じゃなかったぶん取り囲む人垣がユルくて、スキマからの撮影もしやすかったように思います(笑)(長崎駅のほうの上り出発式は、長濱ねるさんだったのよね)。
佐賀県武雄市に所在する武雄温泉。
当駅は武雄市の中心駅であり、
開湯から1300年の歴史を誇る武雄温泉郷の
観光拠点となっています。
タケオ(゚ー゚*)キクチ
優等列車は先出の新幹線「かもめ」と
連絡特急「リレーかもめ」のほか、
佐世保線の特急「みどり」、「ハウステンボス」、
観光特急「ふたつ星4047」などが停車。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
「かもめ1号」が発車したあと、
次に武雄温泉の新幹線ホームに入ってきたのは、
「かもめ3号」長崎ゆき。
いよいよ私も西九州新幹線に乗車です。
(*゚v゚*)ワクワク♪
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
西九州新幹線の愛称は「かもめ」のみで、
それに使われるのは
モノクラス6両編成のN700S8000番台。
東海道・山陽新幹線で使われている
N700S(系)をベースにした番台区分ですが、
裾部に施された赤い帯色が新鮮な印象で、
先頭車の先端には「かもめ」のエンブレムが
掲げられています。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
車内はホテルのような心地よさをテーマに、
自然素材を多用した和洋折衷の空間を表現。
(´ー`)マターリ
座席は自由席が2+3配列で、指定席が2+2配列。
また指定席は座席のモケット(布地の柄)を
それぞれの号車ごとに変えており、
私が乗る2号車はモスグリーンの“獅子柄”です
(なお、普通車のみでグリーン車はありません)。
当駅は武雄市の中心駅であり、
開湯から1300年の歴史を誇る武雄温泉郷の
観光拠点となっています。
タケオ(゚ー゚*)キクチ
優等列車は先出の新幹線「かもめ」と
連絡特急「リレーかもめ」のほか、
佐世保線の特急「みどり」、「ハウステンボス」、
観光特急「ふたつ星4047」などが停車。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
「かもめ1号」が発車したあと、
次に武雄温泉の新幹線ホームに入ってきたのは、
「かもめ3号」長崎ゆき。
いよいよ私も西九州新幹線に乗車です。
(*゚v゚*)ワクワク♪
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
西九州新幹線の愛称は「かもめ」のみで、
それに使われるのは
モノクラス6両編成のN700S8000番台。
東海道・山陽新幹線で使われている
N700S(系)をベースにした番台区分ですが、
裾部に施された赤い帯色が新鮮な印象で、
先頭車の先端には「かもめ」のエンブレムが
掲げられています。
。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
車内はホテルのような心地よさをテーマに、
自然素材を多用した和洋折衷の空間を表現。
(´ー`)マターリ
座席は自由席が2+3配列で、指定席が2+2配列。
また指定席は座席のモケット(布地の柄)を
それぞれの号車ごとに変えており、
私が乗る2号車はモスグリーンの“獅子柄”です
(なお、普通車のみでグリーン車はありません)。
出発式を行った「かもめ1号」を送り出して、構内の賑わいが少し落ち着いたころ、私が乗る「かもめ3号」がホームに入線してきました (゚∀゚)オッ!。
手元の指定券に従って2号車へと乗り込むと、ほのかに漂うのはデビューしたての新車が放つ特有の匂い ( ̄・・ ̄)クンクン。西九州新幹線の開通とともに、「かもめ」で使われるN700S8000番台も今日が営業運転開始のデビューです *.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*。背面や袖仕切りに木材を、モケットには和装布を用いた指定席車両の座席は、先輩である九州新幹線の800系を踏襲した印象で、東海道・山陽新幹線や東日本の各新幹線とは違う、個性的な“九州(の新幹線)らしさ”を覚えます (・∀・)イイネ。幅が広くて座り心地のよいシートだなぁ (´ー`)マターリ。ちなみに、満席が伝えられた「1号」に対して「3号」のほうは、左右両端の窓側の席こそほぼ埋まっているものの、通路側は半分以上が空いており、私の隣も空席でした。
そして先ほどの「1号」と同様にやはり、「リレーかもめ3号」からの接続を取った「かもめ3号」は、定刻の7時43分に武雄温泉を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。私がまだ未踏の鉄路を、新幹線は滑るように走り出します (*゚v゚*)ワクワク♪。
手元の指定券に従って2号車へと乗り込むと、ほのかに漂うのはデビューしたての新車が放つ特有の匂い ( ̄・・ ̄)クンクン。西九州新幹線の開通とともに、「かもめ」で使われるN700S8000番台も今日が営業運転開始のデビューです *.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*。背面や袖仕切りに木材を、モケットには和装布を用いた指定席車両の座席は、先輩である九州新幹線の800系を踏襲した印象で、東海道・山陽新幹線や東日本の各新幹線とは違う、個性的な“九州(の新幹線)らしさ”を覚えます (・∀・)イイネ。幅が広くて座り心地のよいシートだなぁ (´ー`)マターリ。ちなみに、満席が伝えられた「1号」に対して「3号」のほうは、左右両端の窓側の席こそほぼ埋まっているものの、通路側は半分以上が空いており、私の隣も空席でした。
そして先ほどの「1号」と同様にやはり、「リレーかもめ3号」からの接続を取った「かもめ3号」は、定刻の7時43分に武雄温泉を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。私がまだ未踏の鉄路を、新幹線は滑るように走り出します (*゚v゚*)ワクワク♪。
「リレーかもめ」からバトンを受け継ぎ、
新幹線「かもめ」が長崎へ向けて出発!
(/*´∀`)o レッツラゴー♪
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
(車窓から)
武雄温泉を出るとすぐに佐世保線と分かれて、
西九州新幹線は南に進路を取ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉-嬉野温泉
(車窓から)
次の停車駅は嬉野温泉。
(゚ー゚*)ウレシノ
新幹線「かもめ」が長崎へ向けて出発!
(/*´∀`)o レッツラゴー♪
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉
(車窓から)
武雄温泉を出るとすぐに佐世保線と分かれて、
西九州新幹線は南に進路を取ります。
コッチ…((((o* ̄-)o
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉-嬉野温泉
(車窓から)
次の停車駅は嬉野温泉。
(゚ー゚*)ウレシノ
西九州新幹線は、佐賀県武雄市の武雄温泉から、同県嬉野市の嬉野温泉(うれしのおんせん)、長崎県大村市の新大村(しんおおむら)、同県諫早市の諫早(いさはや)の各駅を経て、長崎市の長崎にいたる、全長66.0キロ(実距離、営業キロは69.6キロ)の新幹線 (・o・*)ホホゥ。
当新幹線は本来、九州新幹線の新鳥栖を介して福岡県の博多と長崎を結ぶ計画(整備新幹線計画)となっており、武雄温泉〜長崎はそのうちの暫定開業区間という位置付けなのですが、武雄温泉以東への延伸(新鳥栖〜武雄温泉)は佐賀県との議論が進まずに、現時点(2022年9月)で全通は未定となっています ( ̄。 ̄)ヘー。
当新幹線は本来、九州新幹線の新鳥栖を介して福岡県の博多と長崎を結ぶ計画(整備新幹線計画)となっており、武雄温泉〜長崎はそのうちの暫定開業区間という位置付けなのですが、武雄温泉以東への延伸(新鳥栖〜武雄温泉)は佐賀県との議論が進まずに、現時点(2022年9月)で全通は未定となっています ( ̄。 ̄)ヘー。
新幹線の車窓から望む、
佐賀と長崎の県境に連なる山々。
あくまでも個人的な印象ですが、
西九州新幹線の防音壁は全体を通して
少し高く感じる気がします。
気のせいかな?
σ(゚・゚*)ンー…
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉-嬉野温泉
(車窓から)
武雄温泉から10.9キロ、
わずか6分ほどで嬉野温泉に停車。
当駅はほかに接続する路線がなく、
今回開業したなかでは唯一、
西九州新幹線のみの単独駅です。
(・o・*)ホホゥ
駅名にもなっている嬉野温泉は
大小50軒近くの旅館やホテルがならぶ
西九州屈指の温泉街で、
日本三大美肌の湯に数えられる
名湯だそうです。
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉
(車窓から)
次の停車駅は新大村。
(゚ー゚*)シンオームラ
佐賀と長崎の県境にある
俵坂トンネルを抜けると、
下り列車の進行方向の右手には
大村湾の海景色が望めます。
(´▽`*)ウミ♪
あいにく今日は曇っているけれど、
トンネルが多い西九州新幹線の車窓では
このあたりの眺めがいちばんよさそう。
(・∀・)イイネ
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉-新大村
(車窓から)
そして新大村の手前で見られるのは、
西九州新幹線の車両基地である大村車両基地
(熊本総合車両所大村車両管理室)。
ちなみに当車両基地のすぐ横を走る
在来線の大村線には、
本日の西九州新幹線の開業に合わせて
新駅が設置されたのですが、
駅名はそのまんま「大村車両基地」(笑)
( ̄∀ ̄*)マジカ
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉-新大村
(車窓から)
新大村は大村線(諫早〜早岐)との接続駅で、
こちらも新幹線の開業に合わせて設置された
新駅です。
なお、大村市の中心街は
当駅から大村線で上り方向へ二駅目の大村。
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村(車窓から)
新大村のホームでは地元の方(?)が、
歓迎の旗をふって新幹線を見送ってくださいました。
ありがとうございます。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村(車窓から)
次の停車駅は諫早。
(゚ー゚*)イサハヤ
佐賀と長崎の県境に連なる山々。
あくまでも個人的な印象ですが、
西九州新幹線の防音壁は全体を通して
少し高く感じる気がします。
気のせいかな?
σ(゚・゚*)ンー…
▲22.9.23 西九州新幹線 武雄温泉-嬉野温泉
(車窓から)
武雄温泉から10.9キロ、
わずか6分ほどで嬉野温泉に停車。
当駅はほかに接続する路線がなく、
今回開業したなかでは唯一、
西九州新幹線のみの単独駅です。
(・o・*)ホホゥ
駅名にもなっている嬉野温泉は
大小50軒近くの旅館やホテルがならぶ
西九州屈指の温泉街で、
日本三大美肌の湯に数えられる
名湯だそうです。
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉
(車窓から)
次の停車駅は新大村。
(゚ー゚*)シンオームラ
佐賀と長崎の県境にある
俵坂トンネルを抜けると、
下り列車の進行方向の右手には
大村湾の海景色が望めます。
(´▽`*)ウミ♪
あいにく今日は曇っているけれど、
トンネルが多い西九州新幹線の車窓では
このあたりの眺めがいちばんよさそう。
(・∀・)イイネ
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉-新大村
(車窓から)
そして新大村の手前で見られるのは、
西九州新幹線の車両基地である大村車両基地
(熊本総合車両所大村車両管理室)。
ちなみに当車両基地のすぐ横を走る
在来線の大村線には、
本日の西九州新幹線の開業に合わせて
新駅が設置されたのですが、
駅名はそのまんま「大村車両基地」(笑)
( ̄∀ ̄*)マジカ
▲22.9.23 西九州新幹線 嬉野温泉-新大村
(車窓から)
新大村は大村線(諫早〜早岐)との接続駅で、
こちらも新幹線の開業に合わせて設置された
新駅です。
なお、大村市の中心街は
当駅から大村線で上り方向へ二駅目の大村。
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村(車窓から)
新大村のホームでは地元の方(?)が、
歓迎の旗をふって新幹線を見送ってくださいました。
ありがとうございます。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村(車窓から)
次の停車駅は諫早。
(゚ー゚*)イサハヤ
新幹線開業以前に特急「かもめ」が走っていた長崎本線は、肥前半島(広義的に見る佐賀県西部および長崎県の本土部一帯)南部の有明海側に線路が敷かれていて、車窓からもその海景色がよく望めたのですが ( ̄▽ ̄*)ウミ、西九州新幹線のほうはいくつものトンネルを抜けて同半島の真ん中を突っ切り、いかにも景色より速達性を重視したようなルートとなっています(新幹線ってそういうものだけど)バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。
そんななかでも、今まで鉄道が通っていなかった嬉野温泉の駅名を目にすると新鮮さを感じ (゚∀゚)オッ!、また、佐賀と長崎の県境付近では断続するトンネルの合間に緑深い山景色が、新大村付近では半島西部の大村湾がわずかに望めるなど (゚∀゚*)オオッ!、全体を通してトンネルの多さは仕方なく感じるものの、意外と変化のある車窓風景が楽しめます (・∀・)イイネ。ちなみに大村湾の海が見えるのは、長崎ゆきの下り列車で右側(上り列車で左側)の車窓。4列の指定席なら“D席”、5列の自由席なら“E席”で \_( ゚ロ゚)ココ重要、私もこのことを踏まえて、D席の指定券を発券していただきました (*・∀・)つ[キップ]。
そんななかでも、今まで鉄道が通っていなかった嬉野温泉の駅名を目にすると新鮮さを感じ (゚∀゚)オッ!、また、佐賀と長崎の県境付近では断続するトンネルの合間に緑深い山景色が、新大村付近では半島西部の大村湾がわずかに望めるなど (゚∀゚*)オオッ!、全体を通してトンネルの多さは仕方なく感じるものの、意外と変化のある車窓風景が楽しめます (・∀・)イイネ。ちなみに大村湾の海が見えるのは、長崎ゆきの下り列車で右側(上り列車で左側)の車窓。4列の指定席なら“D席”、5列の自由席なら“E席”で \_( ゚ロ゚)ココ重要、私もこのことを踏まえて、D席の指定券を発券していただきました (*・∀・)つ[キップ]。
沿線の会社の屋上にも
開業を祝うお手製の横断幕が掲げられており、
何人かの方が新幹線に向かって
手をふられています。
このような光景は開業日ならではですね。
ありがとうございます。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村-諫早
(車窓から)
既存の駅に新幹線が併設された諫早は
長崎本線と大村線、
ローカル私鉄の島原鉄道(諫早~島原港)が接続。
先ほど武雄温泉の手前の
江北で別れた長崎本線とは、
ここで合流することになります。
(*´∀`)ノ゙オヒサ
▲22.9.23 西九州新幹線 諫早(車窓から)
次の停車駅は終点の長崎。
(゚ー゚*)ナガサキ
開業を祝うお手製の横断幕が掲げられており、
何人かの方が新幹線に向かって
手をふられています。
このような光景は開業日ならではですね。
ありがとうございます。
ヽ(´▽`*)ノワーイ♪
▲22.9.23 西九州新幹線 新大村-諫早
(車窓から)
既存の駅に新幹線が併設された諫早は
長崎本線と大村線、
ローカル私鉄の島原鉄道(諫早~島原港)が接続。
先ほど武雄温泉の手前の
江北で別れた長崎本線とは、
ここで合流することになります。
(*´∀`)ノ゙オヒサ
▲22.9.23 西九州新幹線 諫早(車窓から)
次の停車駅は終点の長崎。
(゚ー゚*)ナガサキ
嬉野温泉、新大村と、今回の新幹線開業に合わせて設置された新駅が続きましたが、既存の在来線駅に併設されて過去に私も訪れたことがある諫早に着くと、あらためて新幹線が長崎の地を走っていることを実感します (´ω`)シミジミ。
そして路線で最長となる7,460mの新長崎トンネルを通り抜けると、もうそこは長崎の市街地です (゚∀゚)オッ!。右手に稲佐山を眺めながら減速した新幹線「かもめ」は、ゆっくりと長崎に終着しました (・ω・)トーチャコ。武雄温泉からの乗車時間はわずか29分(同区間の最速列車は23分)と実際に短かったけど、ホントにあっという間の感覚だったなぁ。もう降りちゃうのがもったいないくらい(笑)
そして路線で最長となる7,460mの新長崎トンネルを通り抜けると、もうそこは長崎の市街地です (゚∀゚)オッ!。右手に稲佐山を眺めながら減速した新幹線「かもめ」は、ゆっくりと長崎に終着しました (・ω・)トーチャコ。武雄温泉からの乗車時間はわずか29分(同区間の最速列車は23分)と実際に短かったけど、ホントにあっという間の感覚だったなぁ。もう降りちゃうのがもったいないくらい(笑)
最後に長〜いトンネルを抜けると
車窓の右手に見えたのは
長崎の観光名所で知られる稲佐山。
(゚∀゚*)オオッ!
おお!ここに出るのか!
・・・って感じです(笑)
▲22.9.23 西九州新幹線 諫早-長崎
(車窓から)
ドーム型の白い屋根が印象的な
長崎のホームに到着する「かもめ」。
ああ、ホントに長崎に新幹線が
できたんだなぁ。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲22.9.23 西九州新幹線 長崎
車窓の右手に見えたのは
長崎の観光名所で知られる稲佐山。
(゚∀゚*)オオッ!
おお!ここに出るのか!
・・・って感じです(笑)
▲22.9.23 西九州新幹線 諫早-長崎
(車窓から)
ドーム型の白い屋根が印象的な
長崎のホームに到着する「かもめ」。
ああ、ホントに長崎に新幹線が
できたんだなぁ。
+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。
▲22.9.23 西九州新幹線 長崎
これにて西九州新幹線の武雄温泉〜長崎を完乗 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。中途ハンパな開業区間で、全長66キロほどの“日本一短い新幹線”ですが、私にとっては大きな達成感が得られました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。
博多0600-(特急リレーかもめ1号)-武雄温泉0700~0743-(新幹線かもめ3号)-長崎0814
博多0600-(特急リレーかもめ1号)-武雄温泉0700~0743-(新幹線かもめ3号)-長崎0814
さて、念願の西九州新幹線に乗って、長崎へとやってきた私。
“開業初日の新幹線に乗る”という目的は早々に果たせたけど、このあとはどうしましょうか・・・σ(゚・゚*)ンー…。ちゃんぽん?トルコライス?五島うどん? (゚¬゚*)ジュル。おっとその前にまずは、新幹線開業の“記念きっぷ”を買わなきゃ ε=┌(*゚д゚)┘キップ!。
“開業初日の新幹線に乗る”という目的は早々に果たせたけど、このあとはどうしましょうか・・・σ(゚・゚*)ンー…。ちゃんぽん?トルコライス?五島うどん? (゚¬゚*)ジュル。おっとその前にまずは、新幹線開業の“記念きっぷ”を買わなきゃ ε=┌(*゚д゚)┘キップ!。
・・・九州の鉄旅、次回に続きます。
2022-10-01 07:07